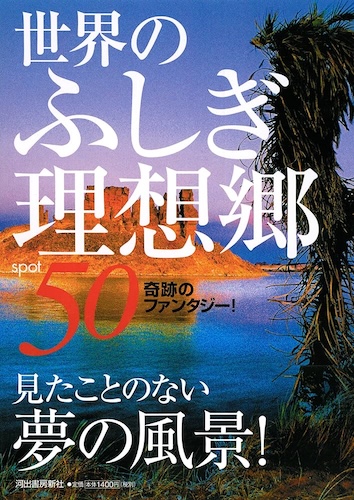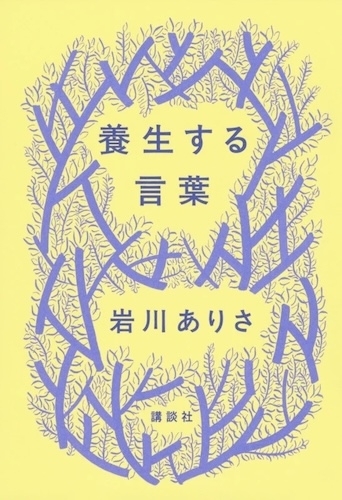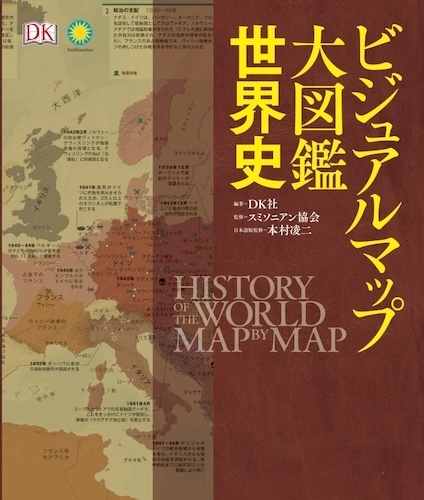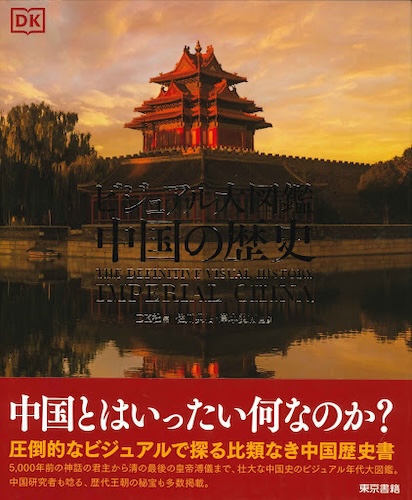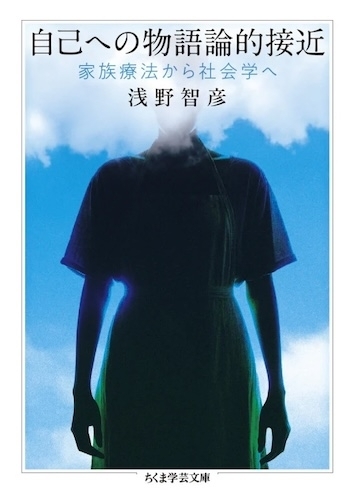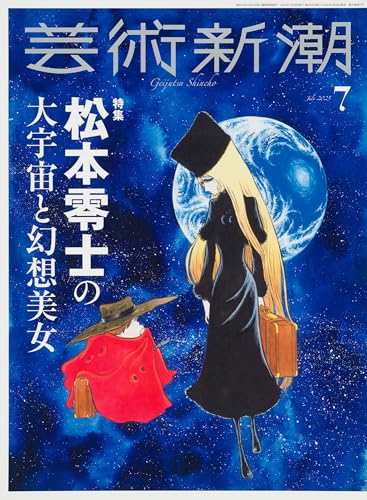20年以上ブログを書き続けているけど、固定読者はほとんどいない。
これはむしろ稀有なことではないか。
もともと自分のために書きはじめたもの。宣伝もしないし、あえて読者を増やそうという小細工もしない。
本についても同じ。価格を上げたせいで、少なかった注文はますます減った。先月はKindle Unlimitedで数ページ読まれただけ。紙の本はまったく売れていない。
もう宣伝もしないし、読んでほしいと誰かに献本することもしない。
言葉を換えれば、もう他人に理解してもらうことはあきらめる、ということ。孤独であることを恐れないということ。
緑深い山奥にひっそりと咲く、まだ名前のつけられていない花のようでありたい。
さくいん:理解、孤独
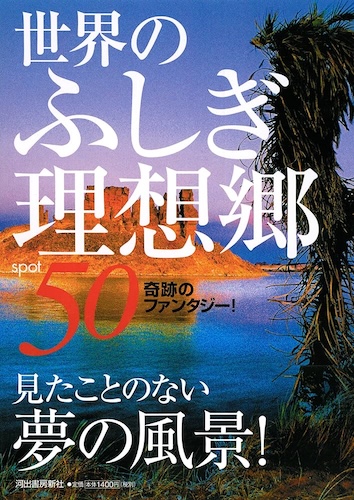
世界の絶景を集めた写真集を眺めるのが好きで図書館でよく借りてくる。本書もその一冊。
どちらかというと自然が作った絶景よりも、歴史的建造物や古代遺跡を見るほうが好き。
毎週、世界遺産を紹介するテレビ番組も、自然系のときには見ないことが多い。そもそも自然科学一般に興味がない。動物を特集したテレビ番組は見ないし、公園や植物園など人工的な緑は好きでも、むき出しの大自然には怖くて近づけない。
そうは言いながら、実際に目にすると圧倒され、感激することもある。大学時代に旅したグランドキャニオンがまさにそれ。運よく頂上のロッジに泊まれたので、夕陽、星空、朝陽の脅威的な光景を目にすることができた。言葉では表現できない景色はいまも忘れない。
さくいん:アメリカ
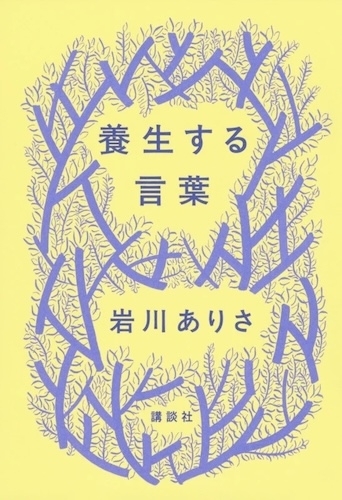




土曜日は月例の診察日だった。待たされたときのために、書店で文庫本と新書を一冊ずつ買っていた。すると、そんな日に限って待合室には一人しかいない。
本を準備していると空いていて準備してないと混んでいる
この法則はまた正しかった。診察では母の介護で精神的な行き詰まりを感じていることを話した。解決法は明示してくれなかったけど、ケアマネージャーに心情を伝えておいてもいいだろうという助言をS先生から授かった。
薬局で4週間分の薬をもらってから少し歩いて久しぶりにVVDへ。開店したばかりで最初の客だった。
この日は、期間限定のラム&チーズバーガーを食べた。てっきり羊肉をパティにしたのかと思ったらそうではない。牛肉のパティの上に焼いた薄切り肉がのっている。羊肉独特の風味がいい。とろとろのチーズもおいしい。付け合わせはポテトでなく、オニオンリング。大容量で満足した。
ヒューガルデンのビールがいつもの半額だったので2杯呑んでしまった。半額なら2倍呑むのは酒呑みの愚かな性と言えよう。
酷暑のなか外にいても消耗するだけなので、駅ビルを一回りしてすぐに家に帰った。
さくいん:S先生




一面に咲くひまわりを見たくて立川にある昭和記念公園まで行ってきた。昭和記念公園は子どもが小さい頃へプールへ来て以来か。
青梅線の西立川駅で下車すると公園の入口はすぐ。でも、昭和記念公園はとても大きい。ひまわり畑のある原っぱまでは15分くらい歩いた。
ひまわり畑は思った以上に広かった。快晴だったのでいい写真も撮れた。
公園を散策しようかとも思ったものの、歩いているだけで頭がふらふらしてくるので、熱中症を恐れてすぐに帰ってきた。
日傘と妻に借りた日焼け止めのおかげでやけどはせずに済んだ。
東京に住んで30年も経つのに、私の行動範囲は非常に狭い。高尾山に登ったことがないし八王子にも縁がない。立川が西端。東側は日本橋よりも先はほとんど知らない。一度、清澄白河へ行ったことがあるくらい。
我が家からは、立川へ行くのも新宿へ行くのもかかる時間は同じくらい。あまり馴染みがないので、立川へは滅多に来ない。公園も百貨店もあるし、もっと西方面に出かけてもいいだろう。
さくいん:東京
娘が結婚する前に、家族4人で旅行しようということになった。日程は娘の希望で披露宴の準備も落ち着いた来年1月初旬の3連休。
我が家の旅行は毎度「やる気のない」非活動的な旅行なので、シュノーケリングやスキーなどは考えられない。
のんびりできて、食事がおいしくて、費用はほどほどで、思い出になる場所。なかなか、そういう場所が見つからない。
遠いところは予算オーバーになるし、移動だけで時間を取られてしまう。近くではまた行く機会があるかもしれないから、特別な思い出にならないかもしれない。
沖縄、石垣、宮古、湯布院、伊豆、日光、能登、金沢。
いろいろ案はあるけどまだ決まらない。最後は娘の希望次第か。
8月19日追記。
行き先は石垣島に決まった。
さくいん:HOME(家族)、石垣島
ブクログで本の表示順を変えられなくなった。有料会員になればできるという。
せっかくお気に入りの本が上段に表示されるよう工夫しておいたのに、いまでは登録した順に本が表示されるので、まったく整理されていないカオスになっている。
向こうも慈善事業でやっているわけではないから、無料会員と有料会員で使える機能が違うのは仕方ない。かといって、有料会員になるかというとそのつもりも今はない。
毎月、いろいろなサービスにお金を払っている。日経新聞電子版、Amazonプライム、iCloud追加ストレージ、楽天マガジン。スマホの故障保険、インターネットプロバイダー。
これだけあると月々の固定費はけっこうな額になる。もうこれ以上は増やせない。
Twitter(現X)とブクログは多用しているので有料会員にしたら便利になることはわかっている。利用しているので恩返しをしたい気もする。でも費用対効果を考えると二の足を踏む。
さくいん:日経新聞
ひとりごと
最近、気後れすることが何度かあった。
立派な仕事をしているとか、超高学歴とか超高収入とか。そういう人と面すると非正規で収入も少ない自分が恥ずかしくなる。
そんな卑下することはない。自分は自分でいい。そう言い聞かせても、どうしても気後れしてしまう。相手がそれを自慢しているわけではないのに、圧力にさえ感じてしまう。
そこで気づいた。いままで自分がそんな風に相手に思わせてはいなかったか。
学歴、職業、収入、住所、子どもの学歴や職業。こちらには自慢するつもりはなくても、相手には「圧」と感じられたり、もっと言えば、「マウンティング」と受け止められたこともあったのではないか。
私に友人が極端に少ないのは、そういう、相手よりも優位に立とうとする無意識の態度が嫌われているからではないか。
格差社会に対して批判的な姿勢でいるように見せかけて、本心では、できるだけ上の方にいたいという下卑た野心を隠し持っている。
人付き合いが下手な原因は、このあたりにもあるような気がする。
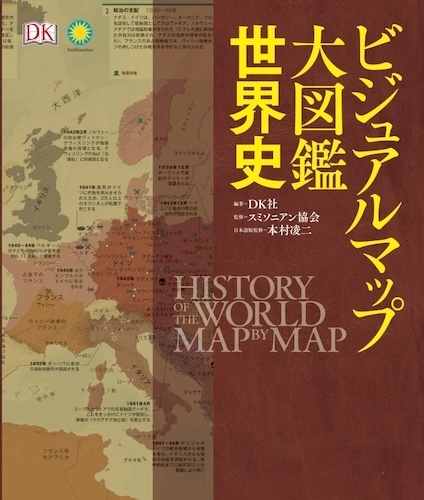
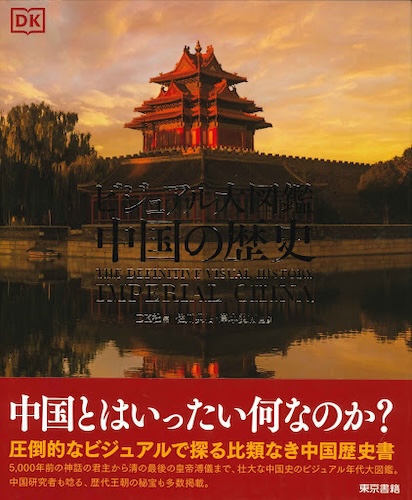
図書館で借りてきた大判図鑑、2冊。高校生向け教科書と資料集をさらに詳しくした感じ。一言で言えば、眺める博物館。
とくに『中国の歴史』は文化史に多くのページを割いていて、中国史を飾る宝物をたくさん写真で紹介しているので、見ていて楽しい。
本書は西洋史と東洋史に加えて、アフリカ史、コロンブス以前の北米史、太平洋史など、教科書にない記述もあり興味深い。西欧諸国が南米やアフリカを植民地化する非道な歴史は読んでいて気分が悪くなる。
南北アメリカ大陸で原住民が激減した原因は、欧米人による武力ではなく、欧州から持ち込まれた伝染病だったという説明に驚いた。
眺めていると代ゼミで受けた山村先生の講義を思い出す。「勉強はご飯と一緒、満腹になったら一休み。おなかが空いたらまた食べればいい」と仰っていた。
こうして受験勉強としての世界史に没頭していた時期から40年が経ち、あらためて図鑑を読んで学んでみると、高校生のときに学んだ基礎知識が役に立っていることがわかる。
忘れたと思っていた人名や地名も図鑑を眺めていると思い出されてくる。世界史を勉強しておいてよかったと思う。
同時に、高校で日本史を履修しなかったことが悔やまれる。日本史の知識はいまだに中学レベル。とりわけ幕末維新以降の近現代史。
せっかく世界史の基礎知識があるのだから、世界史のなかで日本の近現代史を理解できるようにしないといけない。
さくいん:山村良橘、中国、アメリカ、アフリカ、理解
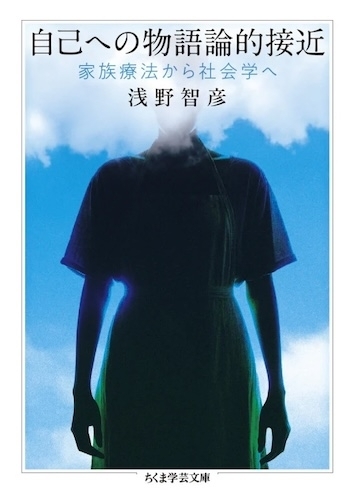
Twitter(現X)への投稿で知った本。最近、文庫本になったようだけど、図書館に初版の単行本があったのでそちらを読んだ。
以前、杉田峰康『人生ドラマの自己分析―交流分析の実際』という本を読んだ。
少し古い本だったけど、自分の人生の脚本は自分で書くという視点は、人生はままならぬものと思っていたので新鮮だった。
本書の要旨は、私が読んだかぎり、自己とは、自分が創る物語と他人が受け止める物語によって規定されるもの。だから何度でも、いかようにも語りなおすことができて、創りなおすことができる。
第一に、自己は、自分自身について物語ることを通して産み出されるということ。そして第二に、自己物語はいつでも「語り得ないもの」を前提にし、かつそれを隠蔽しているということである。(第一章 「自己」への物語論的接近)
書く、という行為は、物語を創る非常に能動的な行為。23年、書き続けてきてそう思う。
書くことを通じて、私の「自己」に対する考え方は何度も変わってきた。つまり、私は書くことを通して、自分を発見し、同時に自分を創造してきた。
本書は、語ることは同時に「語らないもの」を生み出すこと、と指摘している。隠蔽とも書いている。確かに私も語りたいのに語れないものがあり、また意図的に「語らないでいる」こともあった。言うまでもなく、姉の自死のこと。
『庭』をはじめる前の2002年6月には、「書きたいことはあるのだが、書けることではないのだ」と書いていた。
「語りえないもの」は読書と思索と執筆を重ねていくうちに、やがて「書かずにはいられないもの」に変わっていた。そして、『親と死別した子どもたちへ』を読んだことと、2回のカウンセリングを通じて、「書かずにいられないもの」は、ようやく一つのまとまりのある「語り」に結実した。
いま、その「語り」は一冊の本にまとめたことで「あえて語る必要もないこと」に徐々に変わりつつある。
これから私の物語がどうなるか、自分でもわからない。わかっていることは、これからも書きつづけるということ。書くことで、新たな自分を見出し、新たな自分を生み出していく。そして、苦しみながら「新生」を繰り返していく。
さくいん:自死遺族
Twitter(現X)上で「いまの若者には物欲がない」という説と「金がないから欲しくても買えないだけ」という説が激論となっていた。圧倒的に優勢なのは後者の説。確かにそういう一面はあるだろう。
ここで、あえて「若者に物欲がない」という説に加勢してみようと思う。思うに、生まれたときから豊かな時代に育った現代の若者には、「どうしても欲しい」という物欲は薄いのではないか。つまり、「物欲がない」説にも一理あるのではないか。
娘も息子もクルマも持っていないし、腕時計も「高見え」するデザインの安い製品を選んでつけている。出かけるときにはカーシェアリングで借りているし、服は古着屋で買ったりもしている。もちろん、奮発するときがないわけではない。
思い出すと、娘も息子も幼いころでも、おもちゃ屋で買ってもらうまで駄々をこねるということがなかった。欲しいものは祖父母や親戚が先んじて買ってくれていた。いわゆる"6 pockets"。
買おうと思えばいつでも買える。そういう感覚は私の世代ではまだなかったし、私の親の世代ではさらになかった。ステレオ、テレビ、クルマ、パソコン。モノがなかったからモノに飢えていた。新しいモノは何でも魅力的に見えた。
一方、若者たちは広告やマーケティングに簡単に踊らされない。娘と息子を見ていると、何というか、ガツガツしたところがない。モノに飢えていた昭和ヒトケタとは物欲の強さは明かに違う。
もちろん、格差社会の現代において、食べるものにも困っている人が少なくないことを知らないわけではない。ただ、その場合でも、格差から生じているのは「いいものが持てない」相対的貧困であり、私の親世代が戦後に味わった絶対的貧困とは異なる。
たぶん、私の主張は多くの共感は得られないだろう。「お前の家族が恵まれているのだ」と言われれば、「ありがたいことでした」と返すしかない。


ソロ活を中断しての社交の時間。第3弾。土曜日に、みなとみらいで高校時代からの旧友とランチを楽しんだ。
まず渋谷から東横線で新高島まで。駅前にある京急本社の1階でミュージアムをのぞいた。品川、蒲田、上大岡など主要駅が緻密に再現されたジオラマは、子どもでなくても見ていて楽しい。しばし童心に帰った。
会食の場所は26階にある和食レストラン、高ようじ。酒をあまり呑まない相手なので夜に会うよりいいかと思い、ランチに誘った。私は生ビールを一杯呑んだ。ランドマークタワーもよく見えて展望が素晴らしい。
刺身、天ぷら、焼き魚、だし巻き卵と色とりどりの松花堂弁当もとてもおいしかった。
話題は、互いの家族の近況や健康診断の数値、親の介護、などまさに中年の会話。でも、気兼ねなく話せる相手がいることはそれだけでありがたい。
夜に呑み歩くよりもずっと健康的で和やかな時間を過ごすことができた。
また会う約束などすることもなくそれじゃまたなと別れるときのお前がいい
——中村雅俊「たゞお前がいい」(小椋佳作詞作曲)
そんな風に次回も決めずに別れた。彼とは横浜の高校で出会ったので、帰り道、小田和正「My Hometown」を口ずさんだ。
さくいん:横浜、京浜急行、中村雅俊、小椋佳、小田和正

日曜日は母と甥姪家族と横浜そごうでランチをした。
ランチのあと2階にある資生堂パーラーへ行った。この店は今週で閉店する。母と家族との食事のあと、何度も来ている思い出の多い店。5月にも来た。閉店は本当に残念でならない。
最後にチーズケーキを頼んだ。甥と姪はそれぞれいちごとメロンのパフェを食べていた。
チーズケーキは売り切れのことも多かったので最後に食べられてラッキーだった。
会計をするとき、お店の人にお礼とお別れの言葉を伝えた。
この店ばかりではない。家族の誕生日会や忘年会でよく使っていた吉祥寺の聘珍楼も、つい最近、突然に閉店した。
新しい店を開拓するよりは、行き慣れた店に通い倒す性分なので、お気に入りの店がなくなるのは本当にさびしい。飲食業の難しさを思う。
さくいん:横浜、HOME(家族)
ブクログのブックリスト作成機能でリストを作ってみた。選んだのは次の3冊。
年間3万人近くが自ら命を断つ現代日本社会。
一件の自死により6人が強い衝撃や深い悲しみを感じると言われている。
自死遺族、とりわけ悲しみを封印して長い時間を過ごし、悲しみをこじらせてしまった人には特別な心理ケア(グリーフケア)が必要。
自死遺族の悲しみを知ると同時にグリーケアのヒントになる3冊を選んだ。
さくいん:自死遺族
ブクログのブックリスト作成機能でもう一つ、リストを作ってみた。選んだのは次の3冊。
比較的読みやすい本を選んだ。もう一つポイントがある。どの本も戦争の後について書いている。戦争へ行った人たちは戦後、どうなったか。どう考え、どう行動したか。「戦争はよくない」と唱えるために、戦争の「あと」について知ることも大切。
とはいえ、内容は鋭く、深く、戦争とは何かを教えてくれる。
ベトナム戦争で民間人と対峙した米兵、南方で玉砕を命じられた日本兵、シベリアに抑留された詩人。
それぞれが人間を極限状態に追い込む戦争の本質を伝える。
今年は敗戦から80年、昭和100年。先週『クローズアップ現代』の特集番組を見た。この番組を見たときも、また、10年前に『私の「戦後70年談話」』を読んだときも思った。
戦後復興とは、要するに「よその戦争」で儲けたということではないか。
80年間、戦争をしてこなかったと誇らしくいう人もいるけど、実態は、間接的には何度も戦争に関わってきたのではないか?
関わっただけではない。そこで金を儲けて復興してきた。よその戦争で亡くなった人たちを踏み台にして復興し、経済成長を遂げた。
その真実を直視する言葉は、「平和」だった80年間を寿ぐ言葉に比べて、見聞きする機会はほとんどない。
声を大にして言いたい。日本国には、侵略戦争を起こした責任だけでなく、戦後によその国の戦争から利益を得た戦争の受益者という責任がある。
いつでも、どこにいても、暴力の受益者という視点を忘れてはならない。「思想は加害者の立場からしか生まれない」という石原吉郎の言葉は、そういう姿勢を示唆していると思う。
さくいん:水木しげる、石原吉郎


先週土曜日から日曜日まで9連休。家にいるとふだんと同じになってしまうので、なるべく出かけている。13日の水曜日には行きつけの美術館へ出かけた。お目当ては、子ども向けの企画展ではなく、収蔵作品を展示するコレクション展。牛島憲之を見たかった。
行ってみると、牛島憲之が10点も、難波田龍起は3点、正宗得三郎も4点、とお気に入りの画家の作品をたくさん見ることができた。とくに印象に残った作品をメモしておく。
- 牛島憲之:灯台のある島、ある日、白南風、残夏、灯台、昼の水門
- 難波田龍起:青い風景、発生B、コンポジション
- 正宗得三郎:欅並木マーケット、府中並木街、府中並木通
牛島には、柔らかな線と穏やかな色の樹木をモチーフにした作品と、直線を基調とした港やタンクをモチーフにした作品と2種類ある。さらに「残夏」のように、糸瓜も葉も枝も暑さに溶けてしまったような緩やかな線の絵もある。それらが一部屋に並べられていても不思議なことに違和感はない。まだ上手く言葉にできないけど、何か彼のスタイルに一貫したものがあるのだろう。
難波田の「青い風景」は1960年の作品。16年後に描く「昇天」の伏線にも思えるような青・白・紫の混じる背景に、描いたというより無造作に切りつけたような荒々しい線。エナメルを垂らしているらしい。やはり彼の青に惹かれる。
正宗得三郎はこの美術館に通うようになったきっかけをくれた画家。いずれも府中のシンボルであるけやき並木を住民の一人として温もりのある視点で描いている。
2002年に初めて来てから何度も何度も足を運んでいる。どの作品も何度も見ている。この日も一人だったけど、旧い友人に再会したような気がした。
美術館のあとは駅に戻り、定番の「らいおん・らーめん」。ビールを呑みたいところを我慢して、辛味ねぎと味玉、ノリを追加した。おなかがいっぱいになった。
満腹なのに、帰路、明大前駅のホームでおからが材料の「はらどーなつ」を買って帰った。
家に着くと、盆休みの娘が帰省していた。
さくいん:府中市美術館、牛島憲之、難波田龍起、正宗得三郎、ひとり
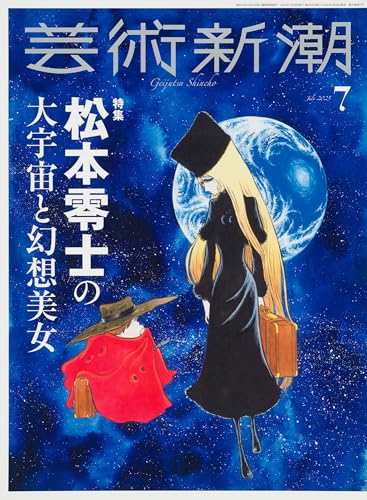
松本零士についてはテレビと映画のアニメ『銀河鉄道999』しか知らない。ほかには『宇宙戦艦ヤマト』のキャラクターやメカ設定。『宇宙海賊キャプテン・ハーロック』は、主題歌は覚えているけど内容は覚えていない。マンガは全然知らない。
小学生の頃に熱心に見ていたから、未来の宇宙船の操縦席はあんな感じになるだろうなと想像していた。それくらい松本零士のメーターデザインは影響力があった。
同じように「絶世の美女」と言葉で書かれていたら、つい、メーテルやスターシアを思い浮かべてしまう。『神曲』を読んだときは、ベアトリーチェにメーテルを思い浮かべていた。美女像でも松本零士が私に与えた影響は大きい。
現在、朝ドラのモデルになっているやなせたかしにしても、トキワ荘のメンバーにしても、皆、たいへんな苦労をして漫画家になっている。情熱とハングリーさが尋常でない。驚くべきことは、豊かな現代にあっても、漫画家になることを夢見る情熱とハングリーさで負けないくらいの若者が少なからずいること。漫画という文化がその情熱とともに受け継がれていることを強く感じる。
さくいん:松本零士、『銀河鉄道999』、『宇宙戦艦ヤマト』、『神曲』(ダンテ)


盆休みで帰省している娘と吉祥寺でランチを楽しんだ。
手元を見るとキラリと光る指輪。婚約指輪は10月に予定している家族顔合わせで披露するのかと思ったら、「もう出来上がったから」と涼しい顔。「顔合わせはカジュアルな食事会で結納ではないし」とも言う。でも、来年4月に披露宴はきっちりする。イマドキの若者のこだわりのなさ、あるいはこだわるところへのこだわりはよくわからない。
ざっくばらんにいろいろ話していて気づいたこと。子どもは親が思っている以上に客観的に親を見ている。独立してさらによく見えるようになっている。両親への冷静な分析に驚いた。でも、見えていない部分ももちろんある。社会人生活にも慣れてきたので、私の職歴について話した。
大学院終了後の第二新卒での就職、ヘッドハンティング、元上司の誘い、倒産とリストラ、スタートアップでの経験を話すと、今度は向こうが驚いていた。
二人暮らしは順調で、披露宴の準備も楽しそうで安心した。
夕方、美容院から帰宅した娘が夕飯の支度を手伝ってくれた。作ったのは餃子。キクラゲとモロヘイヤの卵とじスープ。
台所仕事の手際もいい。家事もこなしていることがわかった。娘と餃子を作るのはかなり久しぶりのこと。でも、教えたたたみ方は忘れていない。我が家の文化として引き継いでくれそう。娘と料理、しかも餃子。この上なく幸せなひとときを過ごした。
私がどんな思いで餃子を作っているか、なぜ、背景でビリー・ジョエルが流れているのか、彼女は知らない。私から話すつもりもない。いつか私がこの世界から立ち去るときにこれを読んで知るだろう。それまでは秘密のまま。それでいい。
さくいん:餃子、ビリー・ジョエル、秘密


先週金曜日の夜。帰省していた娘に息子も加わり、4人で食事をした。場所は吉祥寺のタイ料理、アムリタ食堂。トムヤムクンやバッタイなど定番のタイ料理を楽しんだ。
思えば、去年の今ごろ、娘に彼氏を紹介された。それから同棲が始まり、プロポーズされて婚約まで進んだ。合間に、息子も彼女と同棲を始めた。
それぞれ、多忙ながらも楽しく暮らしている様子。私たちも二人暮らしを楽しんでいる。
一年で家族の形は大きく変わった。それぞれに幸せな方向に進んでいるのはうれしい。
来年1月に予定している、4人では最後になる旅行は討論の末、石垣島に決まった。
さくいん:HOME(家族)、石垣島
夏休みの最後に






先週の土曜日と日曜日のこと。妻はジムと美容院だったので一人だった。土曜日はMLBのパドレス対ドジャースをテレビ観戦してから昼寝と読書で過ごした。夕方、「挽歌」と名前をつけたプレイリストを聴いていたら、悲しい気持ちになった。
夏休み最終日となった日曜日には「心のオアシス」、神代植物公園へ行った。今回の目的は百日紅(サルスベリ)。
まずは、ハスの花がどれくらい残っているか、見に行くと咲いているのは数輪だけだった。
百日紅の花はちょうど見頃だった。青空に白い雲。緑の葉に赤い花。心地よい、鮮やかな夏の景色が広がっていた。
森林浴のあとはご馳走。定番の深大寺そばの店、多聞。まずはキンキンに冷えた生ビール、中ジョッキで渇いたのどを潤した。それから長年通っていて初めて冷やし山菜そばを頼んだ。量は中盛(二人前)。
先日出かけた昭和記念公園ではひまわり畑まで、木陰のない芝生の広場を歩いてちょっと気分が悪くなった。植物公園は木陰が多く、林を抜けてくる風のおかげで猛暑は感じない。
帰り道。吉祥寺駅の手前で降りて井の頭公園を少し歩いた。これがいけなかった。歩いているうちに、だんだん頭がぼーっとしてきた。手作りソーセージの店「ケーニッヒ」で夕飯の買い物をして急いで帰宅した。暑さを甘くみてはいけないと痛感した。
こうして9連休の夏休みは終わった。
追記。この日、新しい日傘をソーセージ店に忘れて帰ってしまった。火曜日の朝に気づき、夕方に引き取り行った。お礼も込めて白ビールにチョリソーフランクを食べた。

さくいん:ひとり、悲しみ、神代植物公園

先週、夏休みのあいだに一人で家にいるときに、Amazonプライムで見た。
重く、辛い話だった。母の認知症のことと、自分のうつ病のことを考えた。映画で扱った認知症とは違うけれど、私も働き盛りの最中に病気で職業人から、社会人から落ちこぼれてしまったから。
46歳のとき、数年前からうつ病で通院していることを社長に伝えた。「心配だから」という言葉とともに追われるように会社を辞めた。辞めさせられたも同然だった。だから、病気で会社を辞めたときの辛さや、病気が好転しないで不安になる気持ちはよくわかった。
家族には、とくに妻には、たいへんな苦労をかけた。うまくコミュニケーションができず、互いに気持ちが離れた時期もあった。でも、苦境にあった私を救ってくれたのも妻だった。
子どもたちには上手に説明して秘密にしてくれた。激務をこなしたおかげで蓄えはあった。それを教育費や住宅ローンで賢く差配してくれたのも妻だった。
結婚相手には「この人と幸せになりたい」と思う相手ではなく、「この人となら苦労に耐えられる」と思える相手を選ぶといい。最近、どこかで聞いた言葉を思い出した。
夫婦関係の本当のところは他人にはわからない。結婚してからずっと仕事一途な夫に苦しめられていた妻が、夫が難病になったとき、よく見捨てなかった。辛いことがあっても、愛情が残っていたのだろう。渡辺謙と樋口可南子は病苦と戦う夫婦を見事に演じていた。
幸い、私はうつ病に関してはだいぶ回復している。非正規雇用の障害者ではあるものの、何とか暮らすことができている。妻との関係も修復できた。子どもたちとも円満な関係を維持できている。
でもこの先、私たちのどちらかが認知症になったり、がんや難病になったりしたら、どうなるだろう。本作のように、支え合える夫婦になりたい。
妄想なのか現実なのかわからない謎の老人を演じた大滝秀治がとてもよかった。
夏休みのあいだにもう一本、『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』を見た。相変わらず登場人物が多く、にぎやかで楽しい作品だった。
さくいん:うつ病、秘密、HOME(家族)、『忍たま乱太郎』
今週月曜日。夏休みを一日延ばした。目的はケアマネージャーとの面談。
しばらく前に母が玄関で転倒したことがあった。幸いそのときは骨折はしなかったけど、この先また転倒すると困るので玄関から門扉まで手すりをつけてもらうことにした。
次の話題は食事。冷蔵庫を見るかぎりでは、ほとんど料理はしていない。デイサービスで週に2回きちんとした食事をしているけど、それだけではもちろん足りない。配食サービスをいくつか紹介してもらった。
母は、家政科を卒業した専業主婦というプライドがあるらしく、「毎日、料理している」と口では言う。なのでケータリングを納得させるには苦労しそう。もう理詰めは通用しない。上手に情緒に訴えないと納得しない。
母は会うたびに認知症が進んでいるように見える。同じ話しかしないし、同じことを何度も尋ねる。料理の件のように、言っていることとしていることに大きな差がある。それについて自分でさえわからなくなっている感じがする。要するに、一瞬一瞬を生きているだけで、持続した記憶や注意力がない。息子の顔はわかっていても、孫の年齢はあやふやになっている。
今週はデイサービスから電話がかかってきた。月曜日に連絡帳を入れる袋に2週間分の昼の薬を入れておいたのに、デイサービスでは見つけられなかったという。薬は施設で管理するので家族がまとめて持参して欲しいと言われた。
これまでは身の回りのことは自分でできていた。最近はそれもあやしい。
この調子では、一人暮らしも長くは続けられないのではないか。施設への入居についても考えはじめた方がいいかもしれない。
月曜日の帰り。久しぶりにラッシュで混雑する電車に乗った。皆、毎日この電車に乗っている。しかも仕事のストレスを抱えて。私もかつてはそういう暮らしを送っていたけど、今はとてもできそうにない。
仕事のストレスはないのに、介護と満員電車でとても疲れた。
9時半過ぎに帰宅してすぐに寝た。


大学では政治学科にいた。政治学専攻といってもいい。三年生から所属するゼミでは政治思想史を専門とする教授についた。大学院でも政治思想史を研究した。いままでずっと、そういうつもりでいた。
今回、読みたいと思って図書館で借りた本を開いて、それは単なる思い込みだったと気づかされた。2冊とも、まるで歯が立たなかった。「はじめに」の一行目から、すでに何が書いてあるのか、わからなかった。
6年間、勉強したつもりでいたのに、どうしたことだろう。何も身についてなかったのか。それとも長い間、専門的な文章を読んでいないから読解力が落ちているのだろうか。
きっと、そのどちらでもない。政治思想の本を読んでも頭に入ってこないのは、いま、私が政治や政治学に強い関心を持っていないから。そんな気がする。興味がないから、能動的に読むことができない。
政治思想史の研究者になれなかったのは当然のことだった。
確かに、3年前に自分の興味の範囲をまとめたとき、政治学も政治思想も入ってなかった。
大学を卒業して30年以上経つ。そのあいだに関心事が変わるのは不思議なことではない。いまはいまの関心事がある。それはそれで幸福なことだろう。
2冊の専門書は「はしがき」と「あとがき」だけを読んで返却した。
さくいん:千葉眞

娘の結婚相手は大学院で物理を専攻し、宇宙にも興味があると聞いたので、今後、雑談ができるように宇宙についての新しい新書を買って読んでみた。
丁寧にわかりやすく書こうと努めていることはよくわかった。それでも、高校で数学物理が落第ギリギリだった私にはほとんど理解できなかった。
わかったことは、宇宙は、そして物質は、途方もなく複雑であるということ。一番驚いたのは、マルチバースという考え方。私たちが住む銀河のほかに銀河があるという事実だけでも十分な驚きなのに、何百億光年という広大な宇宙そのものが、私たちが暮らす宇宙とは別にあるというのだから驚愕しない方がおかしい。
そこで本書には書かれていない「謎」が私のなかで頭をもたげる。
この複雑で途方もない世界を創ったのは、ほんとうに「神」なのか?
神話や伝説は主に地球(大地と海)の創造を説明する。それは、神話を語り継いだ大昔の人間たちには、そこまでしか想像できなかったからではないか。つまり、創世神話はどれも人間の想像の産物に過ぎないのではないか。宇宙創世の謎はまだ明かされていない。
言葉を換えれば、「神」という設定こそ、人間の想像の産物ではないか。
最先端の宇宙理論と結びつける神学はあるのだろうか。浅学にしては私は知らない。少なくとも聖書はマルチバースについては書いていない。
どこまでも疑い深い私は、この先もずっと神の存在を信じることはできないかもしれない。
追記。「神という設定は人間の想像の産物ではないか?」と考えてみたけど、「それを含めて創造した存在がある」と反論することもできる。信じる、信じないはまた別の問題としても。

先週末、実家に帰ってみたものの、猛暑で出かけることができず、映画を見ることにした。この作品は朱川湊人が原作と聞いて映画館で見るつもりだったのに見逃していた。Amazonで見られるようになったので見てみた。
期待どおりの作品だった。「いっぺんさん」を読んだときと同じくらい泣いた。
その死生観は彼の死別体験に裏づけられている。「あのカバンの意味を探して」というエッセイを読んでそう思った。
子役の二人がよかった。彼らがしっかりしていないと台無しになる作品だった。それほど重要で、実際、とてもいい演技だった。
出演者の多くが関西出身者で、関西弁の丁々発止のやりとりも楽しかった。
朱川湊人の死生観に共感する。死者とのコミュニケーションは不可能ではない。だから、死者とともに生きることができる。本作でも「いっぺんさん」でもそう訴えている。
もっとも、私自身は死者の影を追いかけているだけで、死者とともに生きることができていない。
ほかにも彼の死生観が反映している作品があるなら読んでみたい。
さくいん:朱川湊人、死生観


日曜日。実家から帰京する途中で寄り道をして横須賀美術館へ行った。大きな企画展ではなかったけど、いい作品を見ることができて満足した。
モネ「モンソー公園」、ルオー「曲馬団の娘たち」、ルノワール「花」、香月泰男「ドリルを持つ人」、正宗得三郎「海景」、岡鹿之助「三色スミレ」。
ルノワール「花」は、手足が不自由になった晩年に描いた作品で、絵筆を手に縛りつけて描いたという。それでも、色合いも画調もルノワールのスタイルを失ってはいない。
優れた芸術家とは、ほんとうに自分のスタイルをとことんまで突き詰めるということを、あらためて思い知らされた。
同時開催されていた建築家、山本理顕展。建築の知識はないけれど、たくさん模型があって面白かった。横須賀美術館そのものが山本の設計による。広い芝の前庭から海が見渡せる、直線を基調としたこの建築はとてもいい。
暑かった。この美術館はバス停から歩く。たいした距離ではないのに、かなり消耗した。
帰りはバスでJR横須賀駅へ出た。駅から護衛艦かがの巨大な艦橋が見えた。
さくいん:横須賀美術館、ルノワール、ルオー、正宗得三郎、香月泰男、スタイル
今年は長年隠蔽されてきた高校野球の欺瞞が露呈した。
「教育の一環」を隠れ蓑に高校スポーツが新聞社の商売道具になっている。
野球部員が高校のなかで一番高校生らしくないと感じていた、そして今も感じているのは私だけではあるまい。
スポーツ庁はオリンピックのメダル数に目標値をつけている。
それ自体、馬鹿げたことと私は思っているけど、もしも、多くの種目でメダルを取りたいのならば、さまざまな種目の裾野を広げることが大切だろう。
そのためには、高校野球だけを全試合放送するのではなく、インターハイ全種目の決勝を放送したほうが多様なスポーツの普及に効果大ではないだろうか。
野球だけを特別扱いする時代はもう終わっていい。この主張は前にも書いた。
今回は沖縄勢が優勝したことで爽やかな幕切れとなり、高野連はほっとしているだろう。
ここで批判の手をゆるめてはいけない。高野連と新聞社がむさぼる商業主義と悪習の隠蔽構造は徹底的に破壊されなければならない。
さくいん:野球

盆休みに娘が帰省して自分の部屋を片付けていった。勉強机に付属していたデスクワゴンの中身も全部出していったので、そのまま借りることにした。
デスクワゴンとは机の引き出し部分に車輪が付いていて移動可能な家具。これを私が使っているパソコンデスクの下に置いてみた。ちょうどいい。
これまで机の上は文房具が散乱していた。万年筆のインク、メガネ拭き、爪切り、ギターのピック、イヤホン、など。そういうものを引き出しにしまったので机の上がスッキリした。
三段ある引き出しの一番下にはA4サイズも入る。ここにこれまで頭上に置いて危険だったクリアファイルにしまった多種多様な書類をしまった。
できるなら、iMacのキーボードもしまって、空いたスペースで手書きで文章を書いたり、仏像の塗り絵をしたり、そういう使い方をしたい。
とりあえず準備はできた。あとは心がけ次第。
三段目の引き出しがきちんと閉まっていないのは、奥に何かが落ちているため。手持ちの道具では取り出せないのでこのままにしておく。
これは似たような家具を買おうとしていた。おかげで大きな節約になった。一歩、理想の部屋に近づいた。

一昨日のこと。日中、とても暑くてふだんならエアコンを止めている午後3時以降も部屋を涼しくしていた。夕方、窓を開けると少し涼しい風が吹いてたので、久しぶりに外へ出た。
以前は早朝や夕方に遠い公園まで散歩することもあったのに、猛暑の今夏は、ずっと部屋に閉じこもっている。
まず、最近たくさんの家が建築されている所へ行ってみた。以前は畑だったところ。ここへ人が越してくるとバスが混むようになるかもしれない。
次に我が家に一番近い公園まで歩いた。子どもたちの声が聴こえる。何時から遊んでいるのだろう。熱中症警戒アラートが出ているから昼間は家にいて夕方出てきたのかもしれない。外で思い切り遊べない夏はかわいそうに思う。
それからクルマは一方通行の道を逆方向にどんどん歩いた。着いたのは、家から一番近いファミリーマート。15分以上はかかる。
最近、外へ出ていないからファミリーマートにも来てない。だから、しばらく好物のたっぷりクリームデニッシュも食べていない。一つ、翌日のおやつ用に買った。
帰りは、違う道を歩いた。家に一番近いコンビニのセブンイレブンが見えてきた。迷った。呑むか、呑まないか。前日の火曜日にすでにビールとジンを呑んでいた。
結局、欲望に負けて缶ビールとソーセージを一本、駐車場で遅いおやつにした。
消化と摂取では完全にプラスが過剰な散歩になった。日中より気温は下がったとはいえ、汗をかいたので帰宅してすぐ風呂に入った。
昨日は一転して涼しいとは言わないまでも暑さは和らいだ。一日中、エアコンはつけずに扇風機だけで過ごせた。ビールも我慢できた。ようやく猛暑も終わりに近づいているか。
さくいん:ジン

NHKのテレビ番組『100分de名著』。8月の課題図書はサン=テグジュペリ『人間の大地』だった。指南役の野崎歓は前に『英語のたくらみ、フランス語のたわむれ』で読んだことがある。
有名な『星の王子さま』は読んだことがあるけれど、それほど感銘は受けなかった。感動したのはふと図書館で手に取って読んだ『人生に意味を』だった。子ども向けの文体より、「硬質な輝きを放つ」(解説)大人向けの文体は私の好みだった。
1920年代、発明されたばかりの飛行機はまだ危険な乗り物だった。安全な飛行は操縦士の技量に委ねられていた。その人馬一体が求められた時代の操縦士の勇敢さを、著者は丁寧に描き出している。当時の飛行機は高度も低かった。だから、操縦士は地表の様子をよく観察することができた。著者の観察眼は、地上にいてはわからなかった山や畑、道路や家と庭、そうしたものをよく見ている。
飛行機は一個の機械であるにせよ、分析の道具としてなんと役に立つことか! おかげでわれわれは大地の本当の顔を発見することができた。
そうやってわれわれは、人間を宇宙的尺度で判断し、実験器具をのぞくようにして舷窓越しに人間を観察する。自分たちの歴史を読み直すのだ。
第一次大戦で飛行機はすでに武器になっていた。戦争は、戦士の勇気や騎士道精神を競うものではもはやなく、機械と機械が、また国民と国民が戦う総力戦の時代になっていた。
サン=テグジュペリは、飛行機が日進月歩で進化していることも、戦争の様相がそれまでとはまったく異なるものに変化していることも見抜いている。
航空機と有毒ガスが登場して以来、戦争は血まみれの外科手術以外の何ものでもなくなった。(中略)だが敵対する双方はともに朽ち果てるのだ。
本書には黎明期の飛行機乗りたちを賞賛するエピソードに加えて、こうした鋭い文明批評も書き込まれている。
番組も面白かった。『侍タイムトリッパー』で主役を演じた山口馬木也による朗読も、引用部分が的確で本書のエッセンスを感じとることができ、指南役の解説も理解を深める助けになった。
さくいん:サン=テグジュペリ、NHK(テレビ)、野崎歓