森有正エッセー集成3「遥かなノートル・ダム」他(原著1967 - 1974)、二宮正之編、安藤宏解説、ちくま学芸文庫、1999
思索と経験をめぐって、森有正、講談社学術文庫、1976
遠ざかるノートル・ダム、森有正、辻邦生(著者あとがきにかえて)、筑摩書房、1976
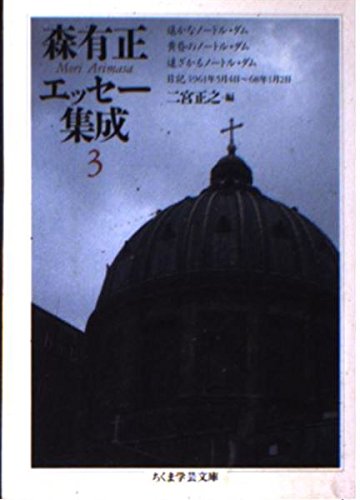
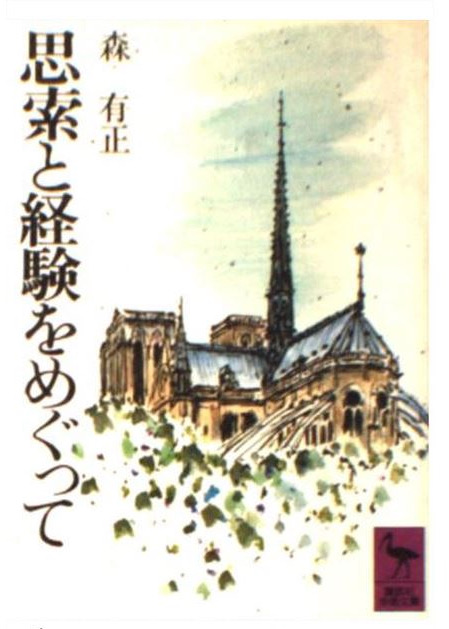
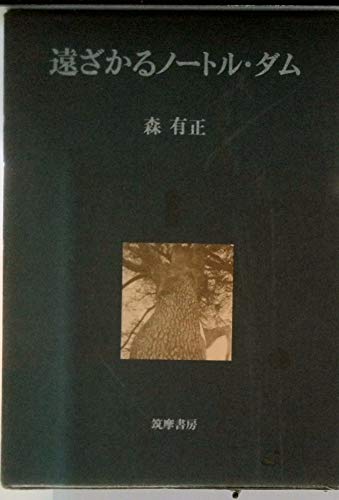
全5巻からなる『森有正エッセー集成』もいよいよ佳境。ところが三冊目を読んでいてどうにもとまどいを感じる。理由は、文庫が作品を時系列に沿って掲載していない点にある。以前『小林秀雄全集』を読んだときには、全作品が発表順に並べられていて、読みながら小林の思索と表現の変遷をたどることができた。
小林秀雄と同じように、森有正においても思索と表現の変遷は重要。最重要概念である「経験」という語が見出され、磨かれていく過程は、書かれた順を追って読まなければ混乱する。とくに各巻後半に収められたエッセーと日記の執筆時期が一致していないのは、思索の熟成をわかりづらくしている。
森有正を研究しようとするならば、どれから読んでもかまわない。どこから読むにしてもすべてを読まなければ、森の思想の全体を分析し、論じることはできないだろう。
思想を体感することを目指して読む場合はそうはいかない。読んでしまってからは感じられないこともあるから。その作家を読む前にどう思っていたか、読みはじめてどう思ったか、そういう印象の移り変わりを感じることが、私の読書にとっては大切。批評は読む前から、その本と出会ったときにはじまっている。
もっとも小林秀雄の時と違い、すでに晩年の新書や講演を読んでいるので、森の晩年の思想がどんなものか、大まかには知っている。いまさら順序を気にすることもないだろう。そこで、古本屋で見つけた晩年に出版された文庫と、絶筆となった単行本も併せて読むことにした。
「霧の朝」「遥かなノートル・ダム」「変貌」そして「遠ざかるノートル・ダム」。これらの文章は山あり谷あり、川あり砂漠ありの道のりを経てたどりついた思想の水源。言葉に無駄がない。論旨に揺るぎがない。すべての定義がそこから生まれ行動への促しが流れ出す。パリの情景から自己の内奥へ視点を移していく、森の得意とする文体が完成されている。
こういう文章について後から何か書くことはほとんどできない。つるつるに磨かれた石のようにひっかかるものが何もなく手をかけても滑り落ちていく。文章が流れるように読めてしまう。
こういう文章は自分の思索を進めるためには、かえってよくない。わかった気になりやすいから。
畏れ多いことだけど、知識や思索の深さでは遠く及ばないとしても、何冊か読んできて、気質の面で森有正に自分が似ているように思うことがある。もう少し具体的に言えば、思索の波長が合うと言うべきか。波長が合うとは、同じ問題を抱えているということではない。
むしろ私は、森とはまったく違う問題を思索の中心にすえている。しかし、その問題のとらえ方が似ている。だから、彼が思索をすすめる過程を読み込むことが、自分の思索の案内になるように感じられる。
森を思索の先行者、ときには伴走者のように感じながら、これまで読みすすめてきた。少なくとも気持ちのうえでは、ともに思索を進めていた。ところが「遠ざかるノートル・ダム」を読み終えたとき、彼だけが一気に遠くに行ってしまったように感じた。
別々の問題ではあったとはいえ、同じように真剣に取り組んでいたのに、彼だけが答えを見つけている。ごつごつした硬い岩を苦しみながら転がしてきたのに、いつの間にか、滑らかで光り輝く球体に磨きあげ、そのうえ軽々と乗りこなしている。
これはある意味で、仕方がない。エッセー集成は二十年分にわたる作品群。それを一度に読んでいるのだから、私の数ヶ月の思索を引き離していくことは当然のこと。むしろ、森が思想を獲得するまで歩んだ道程を案内にして今後も思索を進めることができるのだから、幸福といわなければなるまい。
森有正は幼いときからフランス語を学び、家庭も当時としては相当に西洋風、さらに言えば貴族風だった。だから、フランス語ができると自信を持っていたし、西欧的な感覚を身につけているという自負さえ持っていた。
ところが39歳でパリへ到着したとき、パリに息づく言葉と精神とが、自分が身につけていると信じていたフランス語やヨーロッパ精神とまったく本質的に異なるものであることを知り、絶望した。
フランス語を使い教えていても、精神の基底では日本的なものからまったく抜け出ていなかったことに彼は気づく。そこから彼の思索は始まった。
注目したいのは森のなかでは、日本的なものと同時にフランス的なものも、漠然としながらも、ある独立性をもって存在していたということ。フランスは彼にとって遠い憧れの地ではなかった。だから森はほんとうの「フランス」を見なかったことにして「日本」に戻ることも、「日本」を捨て「フランス」に溶け込むことも、あるいは自分の中に別々に存在する「日本」と「フランス」を使い分けることもできたはず。
しかし彼は、在外研究期間の終了とともに帰国をする途を選ばなかったし、フランスに帰化することも拒み、両者を和魂洋才のように使い分けることもしなかった。彼は、一人の人間として「日本」と「フランス」を内的に統一する道を選んだ。それは孤独で、苦悩(アンゴワッス)に彩られた道だった。
私が抱える問題はどうか。私は大衆文化のなかでずっと過ごしてきた。幼いときから漫画を読み、アニメを見て、バラエティ番組で笑い転げた。歌謡曲に踊り、ニューミュージックに酔い、洋楽に憧れた。
その一方で、教養文化の一端に触れてもいた。入江泰吉の写真で知った仏教美術、『破戒』を起点に少しずつ読みはじめた文学作品は、私の中でアニメやコミックとは違うもう一つの世界になっていた。幼い頃に読み聞かされた絵本にも、啓蒙的、教養主義的な匂いがあった。
それでも思春期を通じて、思索の源泉は、常にコミックやアニメの台詞や、ロックやポップスの歌詞だった。文学作品や思想書は、むしろ敬遠していた。思想の材料も指南も体系も、身近でわかりやすい言葉の中にあると信じていたから。実際、そうして思いついたことを、後で難しい本で知ったこともある。受験勉強を通じて興味を持ちはじめた歴史や美術も高尚な知識と気取った趣味でしかなかった。
それではコミックは正しいのか、思想書は気取っているだけなのか。大学にいる間、そうした思いは次第に打ち砕かれていった。何人かの誠実な研究者に出会い、学問の広さと深さを思い知らされた。そして今度は、コミックや歌詞には、思想のきっかけこそあっても、その本質はないように感じられてきた。そこで一度は企業へ就職したものの、学問の世界に深く分け入っていきたいと思いつき、実際、学校へ戻ったのだが、結局、その計画は実現しなかった。
その理由は、才能と資金が不足している分、情熱で埋め合わせなければいけないのに、その情熱が実はもっとも希薄だったから。自分の非学問的、非教養主義的側面を抜きにして、自分の研究、ましてや思想を確立することなどできないように私は感じた。
自分の境遇と日常生活に密着した学問、思想が、研究生活を通じて見つかるだろうか、そうした疑念がぬぐえなかった。もっとも、実際はもっと現実的な理由による。自分から潔く別の道を選んだわけではない。
この点は、森の場合と違う。森は外的な力でフランスへ押し出され、そこで腹を決めて残ることにした。私の場合、象牙の塔に片足を入れたところで押し戻され、仕方なく還俗した。こうして学問の代わりに企業労働が生活の大きな部分を占めるようになった。
奇妙なことに、ここで再び森の境遇と私の境遇は似通ってくる。森は外国人としてパリに住み、東京とは異なる職業で生計をたてざるをえなかった。とはいえ、それは渡航以前にしていた教員だった。私もまた、それまでの経験とはほとんど関わりがなく学問ともかけ離れた世界で、自分のもっているわずかな能力を頼りに食い扶持を見つけた。同じ国内にいても、ある意味、私は外人でありつづけている。元いた大衆文化の世界に戻ったとも言える。
自分の思想を確立した森は生活に対しても迷いがない。パリ在住を決心した頃の日記では生活のために通訳を請け負うことを屈辱に感じているが、やがてフランスで日本語を、東京で西欧哲学を教えることを「職業」として、また、自分の思索を書くことを「仕事」として、明確に、しかも積極的に受け止めるようになる。この点でも、森はずっと遠くへ行ってしまった。
ところで、私のなかでは、日本文化と外国文化の相違は、森のように深刻な問題ではない。その理由はいくつか考えられる。「大衆文化と教養文化」というより深刻な対立構図の中に埋もれている。この場合、常に西欧が上位というわけではない。懐石料理とファスト・フードの例もある。
また、高度成長期に育ち、国民意識としての劣等感がない、若い頃に外国を見聞してカルチャー・ショックという通過儀礼が済んでいる、日本企業の海外部門ではなく、多国籍企業の日本支社という労働体験を通じて、日本対外国ではなく、事業組織のなかの一部門という実感をもっていることも挙げられる。対立は、国境ではなく本社と支社、営業と製造、売る側と買う側の間にある。
このため、森の日本対西欧という自己認識よりも、辻邦生のような楽観的な多文化理解の方が、どちらかといえば私にはなじむ。
そのため、ランス文化や日本文化があたかも固定した存在のように書かれた文章を読むたびに、日本文化の多様性に気づかず、日本対西欧という固定的な構図にとらわれた戦後知識人の一人に、森有正も数えられてしまうのかという危惧を何度も感じた。晩年は東京の大学で教えたことを知ったときも、多くの海外体験者に見られる「日本回帰」を森も最後はたどったのかもしれない、と半ば諦めながらエッセー集成を読んできた。
だから「遠ざかるノートル・ダム」の最後の部分をを読み終えたとき、強い驚きとともに、森有正の思索をたどってきて本当 によかったという深い感動を覚えた。
こうしてノートル・ダムは私から、あるいは私はノートル・ダムから遠ざかりはじめる。或る時、或る場所で邂逅し、接近し、抱擁し、交接を遂げた男女が離れて行くように。私は今後も永くパリあるいはフランスにいるかも知れない。あるいは東京へ戻るかも知れない。しかし、私の今後の仕事は、日本の中に決定的に定位されることになるであろう。ただそれは世上言われる「日本への回帰」という種類のものではないであろう。それはむしろ出発の機に臨むと言う方が適切であるかも知れないのである。とにかく一つのサイクルが終結しようとしているのである。しかし私自身に即して言えば、私は出発なぞ少しもしていなかったのかも知れないのである。ただ出発の準備は、今度こそ終わったのである。 どこへ向かってであろうか。それはもうノートル・ダムもない国へ、法隆寺もない国へ向かってである。私の内面は今激しくそこへと私を促しているのである。もうこれからは、パリについて直接更めて書くことはあるまいと思う。
法隆寺もノートル・ダムもない国へ、森は旅立った。
まだ私は旅立てない。しかし旅立つ先は見えてきた。クラリスもヘーゲルもいない場所へ。いない、というのは、忘れるということではない。こだわりがなくなること、憑き物が剥がれること、対象がモノに還ること。
その日が訪れるまで、私の思索と労働は続く。いや違う。そのとき初めて、ほんとうの思索と労働がはじまる。
uto_midoriXyahoo.co.jp