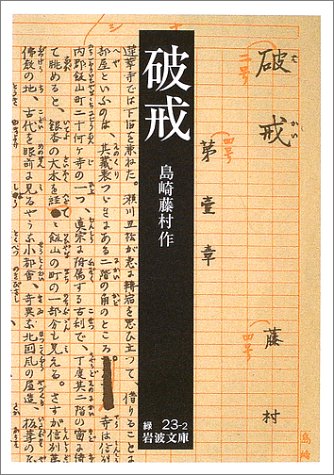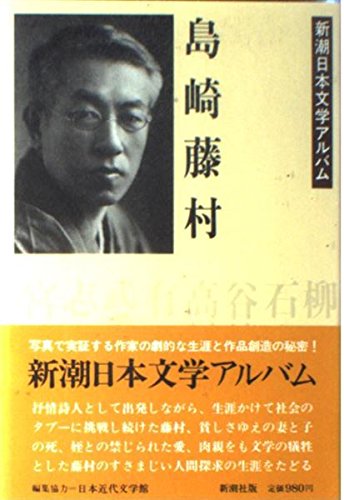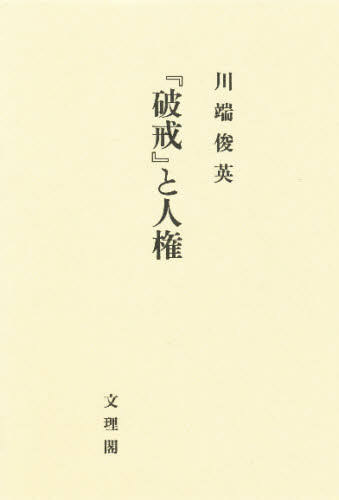『破戒』は、はじめて読んだ文学作品。中学二年の冬、ちょうど今ごろ。熱を出して一週間近く学校を休んだ。ラジオにもマンガにも飽きてきた頃、何気なくすすめられた本を読みはじめて没頭した。
なぜ心を動かされたのか。思い出してみるために、再び読んでみることにした。読み終えてみると、感動した理由を探る以前に物語の展開や結末が記憶と違っていることに気づいた。また、巻末にある野間宏の解説も、自分の読後感とは何か違っているように感じて、島崎藤村の手軽な評伝と、図書館の新刊棚で偶然見つけた、『破戒』について何冊も本を出している研究者の最新刊を借りてきた。
私がかつて読んだ本は、赤いカバーの新潮文庫版。解説は内容も筆者の名前も覚えていない。藤村の作品は『破戒』以外、読んだことがない。藤村についても、『破戒』についても、知らないことばかりだった。
記憶違いしていたのは主人公、瀬川丑松が父の戒めで秘密にしていた穢多の身分を告白するくだり。それを隠しとおすことに悩み疲れて告白したと私は思い込んでいた。実際には、秘密を知る代議士候補の不可解な策略から、学校ではその噂で持ちきりになる。もともと丑松を排除することを狙っていた校長らはこれ幸いと丑松が告白を決意する前から彼の放逐を企んでいる。つまり、丑松はすでに告白するかしないか、追放されるかどうかという窮地に追い込まれている。私が覚え違えていたような単純な自発的告白ではなかった。
丑松を追い詰める謀略は、代議士候補高柳が蓮花寺に丑松を訪ねる第十三章にはじまる。今回読みなおしてみて、この第十三章を境に前半と後半とでは小説の雰囲気がだいぶ違うことに気づいた。
前半は、秘密を隠しとおす丑松の内面的な苦悩が中心になっている。同じ穢多の出自である猪子蓮太郎の作品を愛読していることを周囲に知られたことから、秘密が露見するのではないかと悩んだり、その尊敬する猪子にだけは秘密を打ち明けたいが、父の戒めを思い出してあきらめたりしている。
これに対して、後半は内面的な葛藤より、周囲との軋轢が問題になる。秘密は高柳の密告により露見する。丑松は否応なく対応を迫られる。そして告白の決意、教室での土下座、テキサスへの旅立ちと話は進んでいく。
ところで、『破戒』は部落差別の問題を文学作品としてはじめて正面から扱いながら、それを糾弾しきれず、かえって助長する作品に終わってしまったという見方が、従来多勢であったと、川端は書いている。その発信源は昭和29年に部落解放全国委員会が発表した「『破戒』初版本復元に関する声明」にあったという。岩波文庫版に添えられた野間の解説もその意図を踏襲しているらしい。
野間は、「いくらわれわれが無知で、卑しい者だからといって」と蓮太郎に言わせていること、丑松に土下座させていることから、藤村は結局、ルソーなどのフランスの自然主義文学と違い、人間平等の思想的根拠を打ち立てられなかったとみている。また、開拓地への旅立ちという結末は、差別的な制度や因習と対決せずに「逃げて行くことを示すものにほかならない」と手厳しい。
川端は、野間の解説を含めて、作品が書かれた時代や作者の真意を無視して、読み手がいる現時点の事情や視点から、過去の作品や作家を断罪するような読み方を批判する。彼が心がけるのは、「本来あるべき読み方、つまり作品を作品として丸ごと読み取る読み(「九 『破戒』と人権を考える」)。『破戒』を部落問題を扱った特殊な作品としてではなく、人権全体を見すえた普遍的な作品であるという見方には共感もするし、また多くを教えられる。
もともと丑松は被差別者ではない。幼いときには出自の秘密を知らず、秘密を知ってからは隠し続け一平民として暮らしたから、彼自身は差別を受けたことがない。だから、「丑松が部落民としての肉体を持っていないし、心理も持っていない」と野間がいうのも、もっともな気がする。この点、はじめから差別される地域で生まれ、育ち、暮らしていく人々を描いた住井すゑ『橋のない川』(新潮文庫)とは、はっきりと性格が違う。
『破戒』は秘密という人間に普遍的な問題を扱った作品。そう私は思う。今回読みなおして強く感じた。とりわけ前半では、秘密を抱える人間の苦悩が詳しく描写されている。それでは、なぜ普遍的な秘密の問題が後半では社会的な問題にすりかわったのか。その原因が、部落問題というきわめて社会的な問題を題材にしたことにあることは明らか。
社会的な問題を扱う以上、心理的な解決だけでは物語は決着しないし、まして小説として、つまり思想の探求としては問題の提起にもならない。だから川端も指摘するように、周囲の疑念、告白、別天地への旅立ち、お志保との幸福な結末など、後半を構成する諸要素は、みな藤村が社会を通じて小説を描くリアリストであったことを示していると見るべきだろう。
それではなぜ藤村は、普遍的で心理的な水準にある秘密の問題を描こうとしながら、制度的で、社会的な部落問題を題材にしたのだろうか。その理由は、穢多であることは外見ではわからないという点にあると思う。この違いは、部落差別と人種差別を明確に分ける点。
人種差別も慣習や制度によって増幅される。しかし表面的には生理的な嫌悪感として即座に現れる。肌の色や容姿に対する気持ちは、見た途端に顔に出るもの。一方、丑松の例がそうであるように、穢多であることは言わなければわからない。もし、父親に告げられず、周囲も気づかないままでいたら、丑松は一生、自分が穢多であるとは気づかなかったかもしれない。言葉を換えれば、部落差別は自分が穢多であるという自覚に基づく。さらに言葉を換えて、秘密は、きわめて実存的な問題と言うこともできるだろう。
秘密とは何か。自分しか知らないことは秘密ではない。それは自意識の一部分。誰でも知っていることも秘密ではない。知っている人と知らない人がいて、その色分けが自分でできないことが秘密。秘密は自分を自分にしている個性の重要な部分。本人が気にしなければ、どんなに客観的には深刻な問題でも秘密ではない。
藤村は、秘密の例として部落差別を小説の題材にした。現代社会ではこれ以外にも、外見からは見えないが、露見したとき差別の徴になる個性は少なくない。出身地や国籍、学歴、性的志向、信仰、家庭環境、さまざまな経歴や趣味。こうした例はむしろ一般的に深刻な秘密と思われているけれど、誰にとっても秘密になるわけではないし、こればかりが秘密ではない。秘密は、自分が決めるもの。些細なことでも秘密になる。他人の秘密を決めつけるのは、多数派や社会階層にあって上位にいる者が相手を見下している思い込み。
重要なことは、『破戒』は後半部では社会問題として部落差別をとらえて物語が展開、収束していくために、普遍的な水準にある秘密の問題が解決されずに放置されてしまうということ。もし、『破戒』の後半部分が現代に書き直されるとしたら、おそらく違う展開になるだろう。
憲法や国際条約で人権は保障され、今や制度的な差別は法律で禁じられている。観念としての人権は、人々のあいだに広く啓蒙されている。それでも丑松は悩むだろう。自分が自分であることは、穢多であることと切り離すことができない。自分を自分として受け入れてもらうためには、告白しなければならない。それを隠して暮らすことは、差別の有無に関わらず、自分と周囲を偽ることになるから。今の言葉でいえば、カミングアウトとなるだろう。
本人にとっては、身を削るような思いで告白する秘密。周囲の反応は『破戒』の学校とは違うだろう。「気にすることはない」、「もうそういう時代ではないではないのだから」、「こちらも気にしないから」。温かいとも冷ややかともとれる中立的な対応。しかし告白のあと、周囲は前と同じようにはいられない。人間は何も変わっていないのに、告白された秘密を通じてしか、その人をみなくなる。
穢多の、あの人。国籍を変えた、あの人、あの経歴の、あの人、あんな境遇の、あの人。感想は時と場合により、「にもかかわらず」か、「だから、やっぱり」に色づけされる。その人をその人にしている他の要素はもう顧みられない。そうなると秘密を打ち明けたことで、秘密がその人の個性にされてしまう。さらには、秘密がその人のすべてになる。丑松は告白することで、解放された。しかし、もう告白は解放にならない。さらなる孤独とさらなる秘密をもたらす。
残された選択肢は多くない。誰も秘密を知らない場所へと逃げるか、同じ秘密を共有できる仲間を探すか、それとも、固定したキャラを受け入れて暮らしていくか。いずれの場合も、秘密は内面的な葛藤として残る。
実は、『破戒』の後半にも、告白のあとにも続く葛藤は暗示的に描かれている。鍵になるのは、無二の親友、銀之助と、恋愛の対象、お志保の存在。
銀之助は、丑松の苦悩をはじめは性格的なもの、後には恋わずらいとみている。そのうえ彼は、優秀な教員である丑松が卑しい身分であるはずはないと信じて、それを丑松や他の教員の前でも公言してしまう。
だから、銀之助は丑松の告白に誰よりも驚いた。にもかかわらず、彼は「わかった、わかった、君の心持はよくわかった。」「むヽ――進退伺いも用意してきたね。とにかく、あとの事は僕に任せるとして、君はすぐにこれから帰りたまえ――ね、君はそうしたまえ。」と告白を正面から受け止めることをせず聞き流し、教員を辞することに反対もしないで、問題を処置することに急ぐ。
銀之助の内面は書かれていないからわからない。しかし、これでは終わらない。銀之助は校長に談判するのではなく、蓮花寺を訪ね、お志保を訪ねる。第二十二章は、銀之助とお志保との会話が続く。印象的なやりとりを抜書きしておく。
「いろいろ伺ってみたいと思っておりますうちに、瀬川さんはもう帽子をかぶって、さっさと出て行っておしまいなさるーーあとで私はさんざん泣きました。」
「そうですかあ。」と銀之助も嘆息して、「あヽ、僕の想像したとおりだった。さだめしあなたも驚いたでしょう、瀬川君の素性を始めてお聞きになった時は。」
「いいえ。」お志保は力を入れて言うのであった。
「ホウ。」と銀之助は目を丸くする。
「してみると、あなたも瀬川君を気の毒だと思ってくださるんですかなあ。」
「でも、そうじゃございませんかーー新平民だってなんだってしっかりしたかたの方が、あんな口先ばかりのかたよりはよっぽどいいじゃございませんか。」
「しかし、」とお志保は清しいひとみを輝かした。「おとっさんやおっかさんの血統がどんなでございましょうと、それは瀬川さんの知ったことじゃございますまい。」
「そうです――たしかにそうです。あの男の知ったことではないんです。そうあなたが言ってくだされば、どんなに僕も心強いか知れません。実は僕はこう思いましたーーあの男の素性をお聞きになったら、さだめしあなたも今までの瀬川君とは考えてくださるまいかと。」
「なぜでしょう。」
「だって、それが普通ですもの。」
「あれ、ひとはそうかもしれませんが、私はそうは思いませんわ。」
「(前略)そこですーーもしあなたにあの男の真情がわかりましたら、一つ助けてやろうという思想を持ってくださることはできますかいな。」
「まあ、なんと申し上げていいかわかりませんけれどーー」とお志保は耳の根もとまであかくなって、「私はもうそのつもりでおりますんですよ。」
「一生?」と銀之助はお志保の顔を熟視りながら尋ねた。
「はあ。」
このお志保の答えは銀之助の心を動かしたのである。愛も、涙も、決心も、すべてこの一息のうちに含まれていた。
二人のやりとりからわかること。銀之助は丑松を優れた人物と思っているが、秘密を知り、とまどいを隠せないでいる。それでも銀之助は、彼を救えるのはお志保だけであることを見抜き、丑松への尊敬と友情から彼女を説得しようとする。対するお志保は、銀之助の動揺が理解できない。彼女ははじめから身分や能力によって丑松を判断していないから、まして社会的な関係のなかで見ていないから。
丑松へのお志保の思いは、銀之助の迷いを消し去る。「いろいろ君にはお世話になった。」という丑松に対して、彼は素直に、「それはお互いサ。」と返す。そして、生徒たちと丑松を見送るため授業を休講にしようとして、校長の使いである準教員に激しく抵抗する。
友情は社会的な関係に依存し、恋愛は本人どおしの直接的な交流であると結論してしまうのは、早計だろうか。しかし、結婚が本人の自由意思よりも家と家の結合にすぎず、まして自由恋愛など許されなかった時代に、ここまで思い切って社会的な差別を越えた恋愛を女性の側から描いた意味は小さくないだろう。
川端の研究や三好の評伝によれば、藤村は北村透谷の「恋愛ありて後人世あり、恋愛を抽き去りたらむには人生何の色味かあらむ」という恋愛至上主義に感動し、その真髄を作品に込めようとしていたという。
そうだとすれば、社会的な排除に抗して新天地へ脱出するという後半の大きな流れの底で、恋愛が友情と対比されながら、女性からの愛の表明によって前者の優位性が宣言されていることは、今も続く普遍的な問題として秘密を考えるとき、示唆深いように感じる。
ここまで書いてきたようなことが書けるようになったのは、二十年以上ぶりで読みなおし、作品が成立した経緯や、作者の生涯についてさまざまなことを知り、加えて、すぐれた研究を読んだおかげ。当時は、読み終えてもほとんど何も考えなかった。それでも、この一冊をきっかけにある時期まで次々と本を読むようになったことは事実。
それは、社会的な問題と個人の思想的な問題という、当時、私が関心をもっていた主題が提示されていて、にもかかわらず明快に解決されていないように感じられたからだろうか。不満と期待が次の読書へ導いたのだろうか。
今から思い返せば、そういう一面があったにしても、それがすべてではない。だいたいその頃は自分が向かうべき主題にまったく気づいていなかった。それどころか、そこから逃げようとさえしていた。
それよりも、この作品に引き込まれたのは、その文章のせいに違いない。ほぼ百年前に書かれたこの作品を、いま読み返してみると、斬新な表現に驚く。引用した男性、女性、友人、恋人の心の機微を書き分けた会話文。「地は日の光のためにかわき、人は運動の熱のために燃えた。」のような、詩的で刺激的な表現。この一文に続く、活動的で情熱的な緊張感にあふれたテニスの場面。丑松が帰省先で志保を思い出すほんのりと官能的な場面。いずれも簡潔でいて、映像が目の前に浮かび上がるように鮮やかな描写。
書き出しの「蓮花寺では下宿を兼ねた。」も印象的。川端によれば、昭和14年の改訂版では「蓮花寺では広い庫裏の一部を仕切って、下宿するものを置いていた。」になっている。全国水平社からの圧力だけでなく、戦時体制下における自主規制からなされたこの改変について、川端は、「筆致の弛緩は、思想性の減退を象徴するもの」とみなしている。
『破戒』は、文学を読むこと、読書の楽しみを教えてくれた。そしていまでも、文学は不正の告発や思想の表現というより何より、文章による芸術、文芸であることを教えてくれる。
『破戒』の物語はわずか39日間の出来事という。秘密が露見して大日向が宿を追い出され、恐れをなした丑松が転宿を思いつくところから、旅立ちへ続く物語ははじまる。しかし、物語の前に伏線は引かれている。丑松が猪子蓮太郎の作品に出会ったとき、彼の人生は変わりはじめていた。
一冊の本が人生を変えることはない。しかし、一冊の本によって変りはじめるとは言えるだろう。『破戒』は、間違いなく扉を開けた一冊だった。
とはいえ、続いて読んだ本はテニスン『イノック・アーデン』と井上ひさし『ブンとフン』。長編でもなければ、いわゆる純文学でもなかった。引き込まれるように読んでしまい、あとで何か考えたくなる、そんな本を探すようになった。
もっとも、あるいは、もちろん、探すようになったのは、本だけではなかった。
uto_midoriXyahoo.co.jp