在日外国人と帰化制度、浅川晃広、新幹社、2003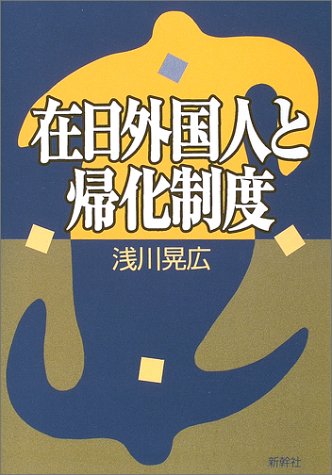
これまで光が当たらなかった分野の意欲的な研究。図書館の新刊棚で見つけた。 年間一万六千人近い人が、外国籍から日本国籍へと変更、すなわち「帰化」しているという。この数字は、日本国の人口や諸外国が受け入れている移民数と比較しても、けっして多い数字ではないらしい。それでも実数としてこれだけいるということは、年々、「日本人」の多様化は進んでいるといえる。 ふだん、何の気なしに使っている「日本人」という言葉。「日本人にしかわからない」「日本人には理解しにくい」など、用例はいくらでもある。しかしその一言だけで、ある人々を傷つけていることに、当の「日本人」はほとんど気づかない。にもかかわらず、「日本人」という言葉は、日常会話から政治論争、文化批評にまであまりにも安易に使われている。 日本で生まれ育っても「日本人」とは呼ばれない人がいる。日本国籍を持っていても肌の色が多数派と違うばかりに「外人」扱いされる人もいる。反対に、いわゆる日本文化とは異なる文化を両親から受け継いでいても、帰化した途端に、「日本人」と言われてしまうことに戸惑う人もいる。 彼らはただ「日本人」と呼ばれたいだけではない。かといって「日本人」ではないと決めつけられたくもない。国籍変更者の気持ちは単純ではない。 著者は帰化制度の実状、手続きの実際、経験者の実感をまとめながら、国籍を「観念としての国籍」と「現実としての国籍」の二つの概念に分ける。そこから日系米国人のように、韓系日本人のような考え方ができないかと提案する。 従来の使い方では、「観念としての国籍」を「現実としての国籍」に重ね合わせる傾向が強かった。「日本人」とは、日本文化を身につけた日本国籍保持者、いわば日系日本人、という考え方。この傾向からは、前者を後者の必要条件とする考えが生まれやすい。「これを知らなければ日本人でない」「日本人ならこうすべき」となり、個人の思想、良心の自由を侵す恐れがでてくる。 浅川の提案する考え方は、国籍変更者がもつ複合的なアイデンティティに内面的な整合性をもたせることができるだけでなく、この国で、同じ国籍をもつ両親から生まれた、いわゆる生粋の「日本人」を無意識に抑圧する単一的なアイデンティティを解放する可能性をもっているし、また、そう機能しなければならない。 もし、日本が政策として移民を受け入れるとすれば、それは単なる労働力であることは到底許されない。社会のフルメンバーとして受け入れる前提がなければ、単なる「二級市民」を生産するのみである。そうした意味で、受け入れる側の自己規定の変革が視野に入らなければ、それは単なる労働力移入に終始するであろう。そうした意味で、日本人概念の再構成は、日本の「あるべき姿」という視点を確立する作業の中で、長期的な視野をもって行われなければならない。(終章 提言:今後の日本国籍に向けて) 浅川が分析し、また多くの体験者が語るとおり、日本国の国籍変更は、人数、手続き、精神的な配慮のいずれの点から見ても、まだまだ充分とはいえない。今はまず、政策上の改善と国籍概念の明確な区分が必要なのだろう。要するに、「韓系日本人」という言葉が違和感なく使われるようになること。 それには同意したうえで、やはり問いたい。「観念としての国籍」は必要なのだろうか。国家という行政機構が厳然とある現代社会にあって「現実としての国籍」なくして生きることはほとんどできない。だから多くの場合、人は「現実としての国籍」を一つだけ持つ。 対して「観念としての国籍」はあくまでも観念であり、誰もが一つだけ持つとは限らない。むしろ一つと限定することは、「現実としての国籍」との齟齬を生んだり、過剰な密着感を生みかねない。日系といっても、キムチも食べれば、パスタも食べる。韓系といっても、味噌汁も飲めば、餃子も食べるはず。食べ物だけが文化ではないとしても、その他の分野でも状況は同じであるに違いない。その意味では、いまや誰もがクレオール系。 それに気づかなければ、「現実としての国籍」によって再生産される「観念としての国籍」が、これまでどおり差別や抑圧を繰り返してしまうだろう。例えば、太平洋戦争中の日系やアフリカ系の人々が「アメリカ人」であることを証明するために見せた、過剰なほどの忠誠を思い出すと、「観念」と「現実」を区別することさえ、そう簡単ではないことがわかる。だから「日本人」概念の再構成は、「現実としての国籍」に多様性を認めていくことだけでなく、「観念としての国籍」を分解していくことでもなければならない。 「日本人」とは日本国籍を持っている人のこと。それで充分ではないか。もちろん、それは在日外国人を差別するということではない。住民には住民の権利と義務があり、国民には国民の権利と義務がある。それ以上の観念性を「何々人」という言い方に託す必要はないように思う。 本書は、帰化制度についての実証研究。アンケートの分析は、帰化という言葉から想像してしまいがちな思い込みを覆す実証をいくつも提示する。国籍変更は最近では旧植民地出身者およびその家族、すなわち特別永住者の割合が減少していること、手続きが異常なほど煩雑であるにも関わらず、場合によって拍子抜けするほど迅速に許可されることがあること、法務省の対応は必ずしもお役所的ではなく、担当者によっては親身な対応であること、従って問題は官僚的な対応というより、対応が職員の資質に依存するほど事務がマニュアル化されていない点にあること、などなど。 こうした実証的な分析は、行政に対して有益な提言になるだろう。一般の読者にとっても、帰化制度を知る概説書になる。とはいえ、実証研究である以上に、本書の読みどころとなるのは、浅川による国籍概念の再構成とともに、実証研究のより所となったアンケート調査の自由記入欄への書き込み。 経験者による国籍変更についての感想を聞く機会はめったにない。そして、アンケートの分析による実証研究が帰化制度の現状からある傾向を抽出する一方で、自由記入欄からの引用は、帰化申請を行った人々の思いは、文字通り十人十色であることを明らかにしている。国籍の実態は実証できても、国籍の実感は、引照するしかない。 苦々しい思いで国籍を変えた人もいれば、「日本人」として憲法に明記された権利を手に入れ、晴れがましく思う人もいる。日の丸を見て感激する元植民地出身者さえいる。あるいは、結婚相手に合わせて変える人もいれば、生活に不便という実際的な理由だけで国籍を変えた人もいる。もちろん祖国に残した家族や、先祖とのつながりが消えてしまったように感じる人もいる。 こうした感想を読んでみると、国籍についての考え方も個人によってさまざまであり、そうしたさまざまなあり方を保障することが何より大切なのではないかと思われてくる。そこから、かまびすしい国籍やナショナリズムの議論について、同じ抵抗感でも違った議論が可能になる。 例えば、国旗や国歌についての論争。確かに国旗国歌の法制化は、市民生活への強制、極端にいえば良心の自由への侵害にも感じられる。しかし、強制に反対する論拠が「アジア人はみんな日の丸が嫌いだ」という画一的な思い込みにあるとすれば、それは行政による強制と同様、個人個人の思いを無視した集団主義の短絡的な考えと言わざるをえない。 国民は、国家という組織の構成員であり、それ以上に憲法上の主権者でもある。自分たちが主権をもつ国家に敬意と忠誠心をもつのは、当然のこと。ただし、それは現在の政権を支持することとは限らない。国のためを思えばこそ、政権に異を唱えるべき時もある。 そのように考えると、問題の焦点は、どのようにして敬意と忠誠を表す態度や方法を個人に強制させないか、どのようにして他の組織に属する人を差別したり、排除したりしないようにするか、という点に当たらなければならない。けっして敬意と忠誠を持つべきかどうかという点ではない。 神社仏閣、教会のように誰かが神聖と思っている場所では、仮に自分は何とも思っていなくても、土足で騒ぐことは許されない。その場所を自分では神聖には思わなくても、最低限の敬意を払うことはできるはず。そうして他人の観念を尊重しながらも、自分が大切だと思うことを他人に押しつけずに、共に暮らすことはできないものだろうか。 国家は、なぜ人殺しまで平気で人にさせることができるのか。国籍という考え方の「観念」に問題があるのか、「現実」の方に問題があるのか。それともその相乗効果が生命を賭すほどの忠誠心を生み出すのか。国籍概念を分解することで、国家の暴力性は、どこまで緩和されるだろうか。 もちろん暴力的なのは国家ではなく、国家に依存する人間のほう。その意味で、浅川が提起する国籍の再構成は、人間にとって国家とは何か、暴力とは何か、という政治思想の基本問題にまで水脈が続いている。 浅川は、添付されているアンケートの依頼文の中で、自らも国籍変更者であることを告げている。アンケートは官報に掲載されているもとの外国人名によって送付された。そのことで辛い思いをした人もいたらしい。そうした人々から寄せられた苦情も浅川は紹介している。 自分の体験を赤裸々に語るのではなく、アンケート調査そのものを通じて国籍問題の複雑な現状を明らかにする。こうした配慮に実証研究になくてはならない冷静な情熱を感じる。 凝り固まった古い積み木細工を打ち砕き、組立て直すのはいつもクールな熱血漢。 |
碧岡烏兎 |