「聴く」ことの力、鷲田清一、TBSブリタニカ、1999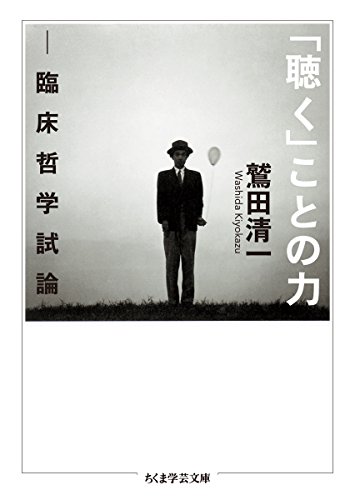
鷲田清一は、自覚的に読み、書くことを始めるきっかけになった作家の一人。日経新聞夕刊一面のコラム「あすへの話題」で彼の文章に出会い、ほかの文章を読んでみようと図書館にでかけた。 『だれのための仕事ー労働 vs 余暇を超えて』(岩波書店、1996)、『普通をだれも教えてくれない』(潮出版、1998)、『時代のきしみー<わたし>と国家のあいだ』(TBSブリタニカ、2002)を読んだ。それから、講座本の論文や目についた新聞の書評なども読むようになった。 身近な話題から、歴史や文明、人間のあり方にまで無理なく伸びやかに広がる構想、社会や自分のなかに根付く思い込みを覆す発想、読みやすく、それでいてぐさりと心に残る表現、そして、議論や表現を支える該博な知識。そんな文章をまねしたいと思った。鷲田の作品を読むことは、いつも原点回帰の意味がある。 鷲田の文章に出会ってから、約二年。文章をまねすることはおろか、著書を読んで理解することもまだできないでいる。いくつか著書は読んだ。読後感も文章にしてみた。けれども、読み返してみると、いずれも短く、貧相きわまりない。要約にも、反論にもなっていないし、彼の文章を受けて自分なりに議論を展開することもまったくできていない。 これは、読んでいるときには感心するばかりで、何一つ自分の言葉で置き換えることができないから。その一方で、鷲田が投げかけた話題は、他の書評や雑記のなかに頻繁に表れている。読んだときには、感想はすぐに言葉にならなくても、あとで何かを考えさせられる。こうした傾向は、私の受け止め方の問題であるだけでなく、鷲田の文体、スタイルに由来するように思われる。 以前、『エッセイとは何か』(法政大学出版、2003)について書いた鷲田の書評を読み、促されるように「エッセイについて」という随想を書き、そのあとで、対象となった本も読んで書評を書いた。 エッセイという文章のありかたが、鷲田にとってどれほど重要なことか、彼の書評を読んでわかったつもりでいた。彼の考えが本書第一章「試みとしての哲学」で詳しく書かれていることは、そのときはまだ知らなかった。 鷲田のエッセイに対する考えは、『エッセイとは何か』の書評で彼がまとめたものとほぼ同じ。一貫した論行ではなく、寄り道、脱線を好む、まったく無関係な事柄や考えを結んで、従来の思い込みを打破する新鮮な見方を提示する、内容だけでなく一見奇抜な、あるいは非学問的な表現方法が硬直した考えを転覆する。要するに「エッセイの行き方は方法的に非方法的である」。 ところで、上記の引用文を含めて、鷲田は、アドルノの文章を軸にエッセイについての考えを進めている。アドルノは、一時期、ナチスから逃れ、アメリカに亡命し、南カリフォルニアに住んだ。『エッセイとは何か』でも取り上げられている亡命生活、アメリカ文化に対する否定的な感覚から思索を深めるアドルノの姿勢は、同じように一種の亡命生活者でありながら、ヨーロッパへ肯定的に身を投げ込んでいくことで思索を深めた森有正と著しい対照をなしている。 こうしたエッセイの特徴は、言うまでもなく、鷲田の文章に反映されている。確かにこれまで読んだ彼の著書はいずれも、何か一貫した問題意識を軸に書かれていた。けれども鷲田の文章を読む楽しみは、そうした一貫性や統一性を追うことではない。彼の寄り道、逸脱、転覆、表現、すなわち彼の助手席に座り、試みのドライブに同行すること。 ただし、もともと哲学者である鷲田は、「聴く」ことの力とエッセイ的な方法を二本柱としながらも、あくまで哲学の再構築を目指している。 いまわたしたちが、(中略)哲学にこそ求めたいのも、そういうしなやかな批判力、濃やかな批判力なのだ。絶対的な知識や普遍的な妥当性が可能かどうかとか、「体系的な基礎付け連関の統一」が可能か不可能かといった二者択一ではなく、その中間領域で、世界を構成するさまざまな象面のそのテクスチュアに濃やかに感応しながら、事象の襞のなかに深く分け入って思考する、そのような哲学の方法なのである。スタイルはすでに思想である。ある思想を学(まね)ぶというのは、まずはある思想が世界を見る、世界に触れるそのスタイルに感応するということである。もうそういう見方しかできなくなるということである。その意味で、哲学はその語り口、その文体をないがしろにしてはいけないと、つよくおもう。(第一章 <試み>としての哲学 8 非方法の方法) 鷲田のエッセイ的な思索のドライブにつきあおうすると、読後の感想も、作品全体から受ける印象や問題意識への応答ではなく、印象に残った挿話や表現について短い感想を付箋のように添えておく程度のことしかできない。しかも、読後すぐには、文章は乾いた土に透明な水を撒いたようにしみこんでしまい、ほとんど何の感想も書けなくなる。 それでいて、しばらく経って別の本を読んだり、別のことを考えたりした時、ふと鷲田の書いていたことが小石に躓くように思い出されるから不思議。鷲田のスタイルは、読後感にまでエッセイ性を残すところに最大の特徴があると言えるのではないだろうか。 鷲田の文章を読んで、いつも感想が書けないでいたことは、こうして一応は説明がつけられる。あとは、読後すぐに躓いた小さな小石、なぜかしら心に残る挿話を二つ書き残しておくことにする。 一つめは、「聴く」こととジェンダーの問題。「聴く」こととは、相手と議論することでもなければ、相手を諭すことでもない。相手に寄り添い、相手とともに「ただ、いること」。 「ただ、いること」は、私も好んで使うプレゼンスという語の訳語。鷲田は「(じっとその場に)いてくれること」と訳す精神科医、中井久夫の語法を援用しながら、「聴く」ことを「無条件のプレゼンス」と言い換えている(第七章 享けるということ 2 「時間をあげる」、あるいは無条件のプレゼンス)。 重要なことは、「無条件のプレゼンス」は、実は新しい考え方でも、これまで難しくて実践されてこなかった方法でもないということ。学生たちとの議論のひとコマ。 C ホテル、病院、ホスピス、クラブのホステス、ホストさん、これらをまとめて「ホスト業」っていうんだと、本で読んだことがあります。苦しんでいるひと、疲れているひと、落ち込んでいるひとを慰め、励まし、送り出す」。でも、これって主婦が長らくやってきたこと、やらされてきたことなんですよね。臨床哲学というのは、それを哲学にまで高めてやろうというわけですか? 著作のなかで著者自身が沈黙する瞬間はめずらしい。よほど衝撃を受けたからにちがいない。だからこそこの一言は「聴く」ことの核心といえるのではないか。この核心を突いていかなければ、いくら周囲を叩いても、何一つ理解はできないように思われてならない。 もう一つは、家族のあり方について。言うまでもなく、家族の問題は、ジェンダーの問題と密接に関連している。鷲田は、ルネ・シェレールという人の文章を引きながら硬直した近代的な家庭にとって<客>を迎え入れる歓待は不法侵入であると言う(第四章 迎え入れるということ 4 ホスピタリティについて)。 確かに、現代の核家族は非常に閉鎖的。近所づきあいも少ない。親戚づきあいも兄弟姉妹が減ったせいもあり、よくも悪くも家父長を中心とする全員集合型ではなく、個別会合型になりつつある。面ではない点のつながりは、かえって点にかかる重心を強くしてもいる。また、不妊治療技術の進歩は、子どもを授からなかった人たちには光明となると同時に、まるで血がつながっていないと家族でないかのような血縁関係に過度に依存する考え方を助長してもいる。そもそも家族とは、血のつながらない人びとが出会い、つくりだすものなのに。 それに対して、昔話や過去のいわゆる偉人の伝記を読んでみても、かつての家庭は客だけではなく、構成員の出入りも激しい。子どもの生存率が低いために、たくさん生まれたくさん亡くなる。産後に亡くなる母親も少なくなかった。その結果、死別、再婚、継母、養子という家庭のあり方も、ごく一般的に行われていたようにみえる。 居候、書生、住み込みという言葉も、今ではほとんど聞かれない。いま、家庭のなかには他人がいない、他者がいない。それが寛ぎと取り違えた甘えの温床となり、かえって家庭を窮屈なものにしている。そのように考えると、古い家族のあり方は、ピラミッド型の抑圧装置であった一面と、柔軟で敷居が低く、他の家族や人間との接点をもつ一面の両方をもっていたのかもしれない。 とはいえ、時代がかわり環境が変わっても、家族は、結婚や誕生によって、新しく構成員が入ったり、また独立や死別によって構成員が離れていくところであることは変わらない。要するに、いま家族は、閉鎖的で原理主義的な溝に落ち込んでいるように見えても、人が生まれ、また人が別れる、人間関係の原初的な現場であることに変りはない。 家族というコインを裏返して考えることもできる。人間であれ、動物であれ、たとえ機械であれ、人が取替えのきかない存在という意味での生命と出会い、別れる場所であれば、夫婦、父母、兄弟、親子など決まりきった存在がいようといまいと、そこは家庭であり、その関係は家族といえるのではないだろうか。 硬直した原理主義に閉塞することなく、そうかといって前近代的な抑圧装置に戻ることもなく、緩やかな結びつきをもった家族のあり方は構想できるだろうか。一つめの、ジェンダーの問題との兼ね合いを考えてみると、新しい家族のあり方を考えることは、それが日々の実践を伴わざるをえないだけに、非常に困難に感じる。 それでも「他のひとに触れたい、なにかを伝えあいたいという、静かではあるがやみがたい思い」(あとがき)が湧きあがるもっとも身近な場所は、いまの私にとっては家族。希望を捨てないかぎり、試行錯誤が続いていくだろう。 鷲田清一の文章はあまり気安く励ましてくれない。むしろ、彼の文章を読むと、考えながら生きていくことの困難さをいつも突きつけられているように感じる。ただし、それはあくまで文章の内容においてのこと。表現においては、彼の物腰はいつも柔らか。 「聴く」こととしての文章という試みは、元気をくれたりはしないが、小さな飴のかけらをくれる。じっくりなめているうちに、いろんな味がしてくる。しかもこの飴は、たんたが探検にいくときになめた飴のように、驚くほど長持ちする。だから、長い冒険にでる勇気がでてくる。 |
碧岡烏兎 |