浦上の旅人たち、今西祐行、太田大八挿絵、実業之日本社、1985年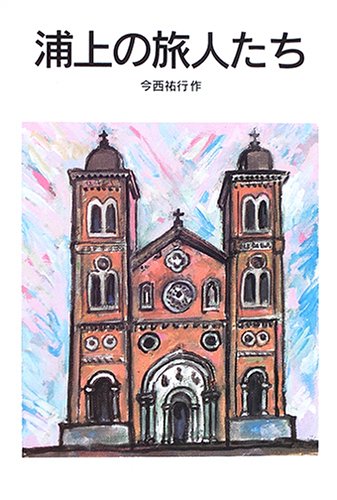
昨年の暮れに、図書館のリサイクル文庫で見つけた。読みはじめるきっかけがないまま数ヶ月が経ち、ようやく手にとると物語に引き込まれ、あっという間に読みおえた。 明治維新で政治体制は変ったものの、キリスト教が禁教であることは変らなかった。すでに農民一揆などに手を焼いていた明治政府は、隠れキリシタンたちが立ち上がることを防ぐために、外国政府の目を盗んで長崎に残るキリスト教徒たちを流刑同然にして西日本各地へ分散させた。物語が描くのは、信者たちが、「旅」と名づけたこの試練の始まりから終わり、すなわち旅立ちから帰還まで。 人生は旅ということがある。人生には始まりと終わりがある。旅にも終わりがある。行き先を決めない旅もある。けれども旅には終わりがある以上、旅は必ず終わりに向かっていくものであり、その意味で、すべての旅には帰る場所があるということができるかもしれない。 旅は帰るためにでかける。どこへ帰るのか。旅立った場所へ帰るのか。旅立った場所とは、どこか。人生が旅とすれば、生れた場所が旅立った場所か。生れたときには自分という意識もなく、ましてや旅立つという意識もなったのだから、生れた場所を旅立った場所とは言えない。だからそこが帰る場所とも言えない。 では、旅立ったと自覚するときはいつか。自分という意識をもつときはいつか。そう考えると、もうこれまでに何度も旅立っているような気もするし、まだほんとうには出発していないようにも感じる。出発したかどうかもわからないから、帰る場所も、もちろんわからない。人生は旅であるにしても、その旅は、旅立つときも、帰る場所もわからない旅。 浦上の隠れキリシタンや、彼らに同行するキリシタンではない千吉にとっても、同じことがいえる。確かに、長崎に生まれて、そこから流刑となった彼らには、長崎は「旅」から帰る場所には違いない。しかし、それは彼らの人生という旅にとって帰る場所であるとは限らない。 千吉にとって帰る場所は、長崎ではなかった。しかし別の意味で、やはり帰る場所は長崎でなければならなかった。彼の出発はいつだったか、どこだったか、それを考えてみると、帰る場所、帰る意味もさまざまに受けとれる。 どこかにたどり着いたとき、自分はあのとき出発していた、だから、この場所に帰ってきた、と後から出発を自覚する。そういう旅もある。その自覚を表現することが、証言ということかもしれない。千吉ならば、どう証言しただろう。いや、千吉を長崎に帰さずにはいられなかった作者今西は、どのように証言するだろう、と問うべきかもしれない。 旅立つ、帰る。そして遠ざかる、近づく。そんなことをこの小説は考えさせる。史実を基にしているけれども、登場人物を含め大部分が創作という。史実を基にした小説というと、同じようにキリスト教徒の受難を描いたシェンケヴィッチ『クオ・ヴァディス』(吉上昭三訳、福音館書店、2000)を思い出す。 もう一つ、春江一也『プラハの春』『ベルリンの秋』(集英社文庫、2000、2001)も、忘れられない。時代や背景は異なるけれども、時代に翻弄されながら出発したり帰還したりするという点では共通している。 ちょうどこの本を読みおえたとき、戦国時代にはるばるローマへ旅して教皇に謁見した天正少年使節団のことをテレビで見た。使節団が日本に戻ってからは、徳川幕府の鎖国、キリスト教弾圧の時代となった。ある者はマカオに追放され、ある者は棄教したという。信仰を捨てたと言われている千々石ミゲルの墓石が、最近見つかったと番組で知った。 本書や『クオ・ヴァディス』をはじめとして、キリスト教の中でもとくにカトリックに関わりのある本に時おり出会う。思い出してみると、小学校に入学したばかりの頃には教会の日曜学校へ通っていた。 援助を行う有名人ではなく、貧民街に生きる人々のうちの一人として生き、周囲の人々を変えていった北原怜子を描いた『アリの街のマリア』(酒井友美、女子パウロ会、1988)も、本書と同じように図書館の除籍資料の棚で見つけた。身近にはカトリックの信者や神父に知合いもいる。 私が思想史を学んだ恩師の一人はカトリックだった。もっとも、彼が信徒であることは彼が亡くなるまで知らなかった。だから、彼に信仰について訊くことはできなかった。 長崎へは一度だけ行ったことがある。ボランティアの通訳としてインドからの来訪者と平和祈念公園、グラバー邸、稲佐山、それから大浦天主堂と、名所といわれるところはほとんどまわった。連れてまわり、説明することが仕事だったので、自分自身で何かについて感心したり考えたりする余裕はなかった。覚えているのは、刺身でもステーキでもちゃんぽんでも、何を食べても美味しかったこと。また訪ねてみたいと、ずっと思ってはいる。 とはいえ、長崎が私が最後に帰る場所であると、いま思っているわけではない。仮にそう思ったとしても、そう思うだけでは帰る場所と言えないだろう。帰る場所は、向かっていくものではなく、帰りついたときにそうわかるものとすれば。 千吉は確かに何かに導かれるようにして帰っていった。でも、それがどこだったのか読むたびに、また読む人によっても違うだろう。 私が帰るところと思う場所は、まだ、朝目ざめるたびに違う。 さくいん:長崎 |
碧岡烏兎 |