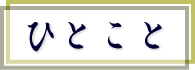
寺報第59号より
合掌。令和三年辛丑 六白金星 あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。恒例になりました立春を迎えての新年です。ここから今年の「気」が始まります。地球上で生きとし生けるもの何もかもが、この「気」に少なからず影響を受けながら日々を過ごします。皆さまにとって今年が良い年でありますようにお祈り申し上げます。
日々の勤行の中で世界の平和と皆さまの家内安全 身体健全等を祈念させていただいております。特に冬の「寒」の時期は毎朝水行をしてありがたい気持ちで御宝前にお経をあげさせて頂いてます。毎年節分まで水行してご祈祷していますから「節分会」の厄除け祈祷は、かなり気合いが入ります。と言うことで私の場合ホントに祈ってますので皆さま・・・お願いだから幸せでいて下さい。
とは言え、問題はコロナウィルスです。どうにかならないですかね。お寺も閑散としたまま、しばらく人と話をしていません。経済も大変なことになっていることでしょう。特にサービス業界飲食店は大変だと思います。協力しようと思っても非常事態宣言下では外食にも行けません。皆さまはご無事ですか? なんとか乗り越えて、また笑顔でお会いしたいと思っています。
こんな中、日経株価は値上がりしているそうです。私は経済には疎いほうですが、コロナ禍の中で景気好調! とはとても思えません。きっと少数一部の強力な人たちだけが株価を支えているのだろうな~と思っています。ニュースを見ながら楽観はできないなあと感じています。そしてこのコロナウィルス・・・これも楽観してはいけません。厄介ですね・・・感染してもいけないし、経済を止めるわけにもいかないのです。とにかく手洗い、うがいは徹底的に、用心用心。そして良く食べて、良く寝て、大いに笑う! 冗談を言っているわけではありません。自分の免疫力を高めることも大事なんです。菌はどこから入ってくるか分りません。そんなとき私たちの体の中でNK細胞(ナチュラルキラー細胞)が頼りになるのです。楽しく予防しましょう。お題目もきっと免疫力をあげてくれますね。南無妙法蓮華経
さて日蓮聖人ならこのコロナ禍をどのように見るのでしょうか? きっと経典に照らして私たちを正しい生き方、正しい信仰に導いてくれることでしょう。前回は日蓮聖人が比叡山から千葉に戻って立教開宗をしたところまでお話ししましたが、その後に聖人は、当時幕府が置かれていた鎌倉に移り、松葉ヶ谷に草庵を構えて弘教活動を開始しました。そしてすぐに後の六老僧の一人である日昭上人が弟子となります。ここから聖人は五年間、辻々に立ち毎日毎日説法を続けました。この頃は幕府政治家を始め庶民に至るまで念仏信仰が広まっていたので、聖人の説法は中々聞いてもらえませんでした。それどころか念仏信仰を否定する聖人に石を投げつける者までいたようです。そんな中でも日朗上人が二人目の弟子となり、在家信徒としては富木常忍・四条頼基(金吾)・池上宗仲・工藤吉隆らが信徒になったと伝えられています。
正嘉元年(1257)八月、鎌倉に大地震があり、大きな被害が出ました。聖人は、多くの死者を出したこの自然災害の原因を仏法に照らして究明しようと、翌年には一切経が所蔵されていた駿河国岩本実相寺へ行き、経典を紐解きました。(この頃に日興上人が弟子となりました)そしてその結果、大規模な災害や飢饉が生じている原因は為政者を含めた多くの人々が正しい教えに違背して間違った信仰をしているために、国土を守る諸天善神が国を去ってその代わりに悪鬼が国に入って災難が生ずる(神天上の法門)という結論に至ったのです。そこで聖人は「立正安国論」を述作し、時の最高権力者にして鎌倉幕府第五代執権の北条時頼に提出して国家諫暁を行ったのです。聖人三十九歳の時です。「立正安国論」によれば災難を止めるには国主が正しい信仰をしなければならず、このまま間違った信仰をしていれば、自界叛逆難(内乱)と他国侵逼難(他国からの侵略)が生ずると予言し、警告したのです。しかし「立正安国論」による国家諫暁は幕府から完全に無視され、逆に念仏批判は念仏者の激しい反発を招き、文応元年(1260)八月二十七日の夜、松葉ヶ谷の草庵が多数の念仏者によって襲撃されてしまいました(松葉ヶ谷の法難)。この時の伝承では裏山に逃げた聖人の前に猿が現れ、その先導によって草庵襲撃の危難を免れたとされています。聖人は一時、下総国若宮(現在の千葉県市川市)の富木常忍の館に移り、有力な信徒を増やしていきました。(大田乗明・曾谷教信・秋元太郎など)。
やがて鎌倉に戻って活動を再開しようとされた聖人でしたが幕府の近臣の者たち(念仏信仰者)の怒りは凄まじく、弘長元年(1261)五月十二日に拘束され、伊豆の伊東に流罪となってしまいました。この流罪は名ばかりで実際は死罪として、俎岩(まないたいわ)という岩礁に置き去りにされてしまうのです。潮が満ちれば岩は海中に没し聖人の命は絶たれるところでした。しかしそこに川奈の漁師・船守弥三郎という者が船で通りかかり助けられたとされています。なんとか一命を取り留めた聖人ですが流罪の身、不便で肩身の狭い苦しい生活を余儀なくされました。しかしこれがまた聖人の不思議力・・・伊豆流罪中、監視に当たったのは伊東の地頭・念仏者伊東八郎左衛門祐光でありましたが、この者が病を得た折、聖人の祈念によって平癒したので、すっかり帰依してしまったのです。また、伊豆流罪中、二年間で聖人は今でも残されている様々な書を著わしています。次回は伊豆流罪赦免からお話し致します。
ご報告
- 12月19日 (土)
- 大黒祭 守護神幣束取り替え繁栄祈願 星祭り 令和三年度年間祈祷会 各種お札開眼
- 令和3年1月元旦 (金)
- 初参り 元旦祝祷会 皆さま、このコロナ禍の中、よくぞご参拝下さいました。心配しながらも嬉しかったです。こんなに人が少ないお正月も初めてでしたが来て下さった皆さまには感謝申し上げます。いずれも茶話会はできませんでしたが行事は無事にできました。お年玉くじも皆さん当たりでしたね! 世界全体が平和で、そしてコロナが早く収束→終息しますように。
お知らせ
- 2月16日(火)11時~ 日蓮聖人御降誕八〇〇年慶讃法要
- コロナ禍の中でどうしようかかなり迷いましたが法要を行うことに致しました。住職と副住職が内陣でお経をあげ、皆さまは外陣で自由参拝の形をとります。日蓮聖人の八百回目の記念の日です。
コロナへの対策をし、用心しながらできる範囲でご参拝下さい。
報恩のお塔婆をあげる方は所定の用紙にて申し込みをして下さい。 - 法事について
- 場合によってリモートの法事を受付けます。
(四十九日やその他 不可能な場合もありますのでご相談下さい)
但し、PC・タブレットなど使用可能な方に限らせて頂きます。 - 令和六年 信隆寺開創四〇〇年 記念式典 記念事業 開催
- 現在計画中です。随時、お知らせ致します。
南無妙法蓮華経
