1/29/2016/SUN
行人(1913)、夏目漱石、大野淳一注、解説、新潮文庫、1952
漱石全集 第八巻、岩波書店、1994

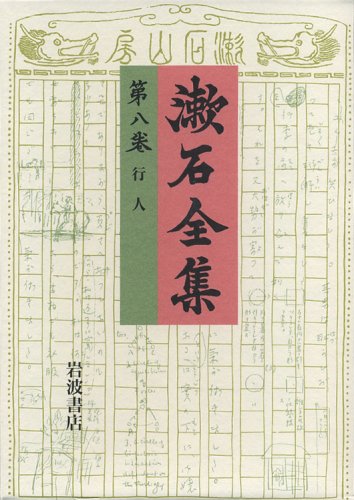
正月に実家で、夏目漱石を特集した古い雑誌、『KOTOBA』(集英社)2013年夏号を読んだ。そのなかで『行人』がうつ病患者の心理をよく表現していると加賀乙彦が話していたので興味を持ち、文庫本を買った。
漱石の作品は、中高生の頃に『こころ』『坊ちゃん』『三四郎』『それから』『門』『虞美人草』などは読んだ。どれも私が読む前から家にあった。『行人』も背表紙を見た記憶はあるが、読んだことはなかった。『明暗』は途中で挫折した。
『庭』をはじめてから、「文芸の哲学的基礎」を読むために『漱石文芸論集』を読んでいる。
つい最近では、『夢十夜』を美しい漫画で読んだばかり。
『行人』は、ほかの漱石作品と同様、新聞小説だったので、区切りが短く読みやすい。物語は、それまで登場していなかった人物の手紙で唐突に終わる。連載途中で病気をして中断したため構想が変わったとも言われているらしい。
新潮文庫版にある大野淳の解説によると、後半部分は唐突なものではなく、計算された構成とも考えられる。前半では、いくつかの夫婦や男女の関係が描かれる。読者は自然と男女関係について思いを巡らす。その中で、一郎と妻との関係がかなり異常なものであることもわかってくる。そのうえでHさんの手紙を読むと、一郎が病的な状態にある事実がさらに際立つ。
この手紙のなかには、Hさんが観察した「兄」の様子として、うつ病的な心理や行動が詳しく描写されている。
兄さんは碁を打つのは固より、何をするのも厭だったのだそうです。同時に、何かしなくってはいられなかったそうです。この矛盾が既に兄さんには苦痛なのでした。(31)
「自分の苦しさは他人に理解してもらえない」と思うことの多い「うつ」と診断された人には、「よくぞ書いてくれた」と感激する表現が数え切れないほどある。
うつ病の人は「誰にもわかってもらえない」という不安と同時に猜疑心も強い。「あの人は自分を嫌っているのではないか」という身近なものから「この世界のどこへ行っても私は必要とされていないのではないか」という途方もないものまで、そうした不安と猜疑心で心のなかは常にざわついてる。
弟に妻の貞操を試させるのは異常にも見えるけれど、心理としてはわからないものではない。猜疑心が向けられることが最も多い人は、皮肉なことに一緒に過ごす時間が長く、一番心配している家族であることは、体験上、よくわかる。
心配してかけてもらったひとことが、自分を侮辱しているように感じたり、病気であることを責められているように思うことも少なくない。
兄さんは親しい私に対して疑念を持っている以上に、その家庭の誰彼を疑っている様でした。兄さんの眼には御父さんと御母さんも偽りの器なのです。細君は殊にそう見えるらしいのです。(塵労 37)
一番近くにいて一番わかってほしい人が、自分の苦しみをわかってくれていないように見える。それでいて、弟とは問題もなく、それどころか仲睦まじく話をしている。まさかとは思うが、自分より弟のことを気にかけていないか。不安は疑念になり、妄想はやがて断定になる。典型的な認知の歪み。
わかってくれないという気持ちと迷惑をかけているという気持ちが相半ばしていると、家族には悩みを打ち明けることも、泣き言を言うこともできなくなる。
そういう意味では、家族以外の人に兄の様子を観察してもらうという策は、現代の精神医学の観点から見ても正しいのではないか。
うつの人には几帳面で真面目な人が多いとよく言われる。漱石はそれについても書いている。
兄さんは鋭敏な人です。美的にも倫理的にも、智的にも鋭敏過ぎて、つまり自分を苦しめに生まれて来たような結果に陥っています。兄さんには甲でも乙でも構わないという鈍な所がありません。必ず甲か乙かの何方でなくては承知出来ないのです。
心が落ち着いていないから、自分の意思で選択することができずに、両極端のあいだを振り子のように往復する。その究極が、「生きるか死ぬか」の二者択一。
一郎のように一日中、気難しい顔でいたら、近くにいる家族は彼の神経を逆なでしないように用心深くなり、さらに彼を遠ざける。
あなた方は兄さんが傍のものを不愉快にすると云って、気の毒な兄さんに多少非難の意味をもたせている様ですが、自分が幸福でないものに、他を幸福にする力がある筈がありません。
誰からも理解されず、自分自身も理解できないうつ病患者は、細い縄のような死の淵を歩いている。一歩でも踏み間違えれば深淵に落ちてしまう。その時になってもなお家族は神経をすり減らして付き合ってきた人がいなくなったことで、緊張した雰囲気が消えて、団欒が戻ったと思うかもしれない。
「傍のものを不愉快にする」兄さんは身を削るようにして毎日を送っていた。その人を気遣うどころか不愉快に思い、いなくなったことで安堵までしたことを家族が後悔するのは、ずっと時を経てから。どれだけ自責の念が深くなっても、兄さんは戻ってこない。これではどちらにとっても幸福であるはずがない。
「兄さん」、長野一郎のうつは「漠然とした不安」で、何か具体的な出来事に由来するものではない。だから、加賀乙彦が指摘するように、もし、現代の薬物療法と精神療法を適用することができたら、症状はかなり改善するのではないか。
加賀乙彦によれば、漱石が生きていた時代にはまだ「うつ病」という概念はなかった。精神病という言葉は作品にも出てくるが大雑把な意味しかなく、その中身も、狂気か神経衰弱の二種類程度の分類しかない。
そんな時代に医学を学んだわけでもない一人の文学者が自らを含めた人間の観察から、現代では一種の病気と認められている状態を克明に表現したことは十分に驚きに値する。荒川洋治が言う「文学は実学」とは、こういうことを指していると思う。
一郎の心理状態は漱石自身の体験を反映しているものらしい。病名もなければ薬もない時代に苦悩を抱えた漱石は、それでも病気と苦悩と戦いながら「自己本位」という思想にたどり着く。
私はただ寝ているのではない、えらい事を考えようと思って寝ているのである。不幸にしてまだ考えつかないだけである。なかなかもって閑人ではない。
(「文芸の哲学的基礎」『漱石全集 第十六巻』)
この講演は明治40年(1907)に行われた。『行人』を書く4年前、『こころ』を書く7年前にあたる。
漱石は自らの苦悩を小説という作品に昇華させることで、「えらい事」を成し遂げた。私にはそう思われてならない。彼の実生活を知ると、苦しみながらも自分自身を傷つけることはなく、人生を生ききった勇敢な人と見ることもできる。
そう考えるならば、「文芸の哲学的基礎」は「実学としての文学」を宣言するマニフェストだったと言える。
ところで、『行人』の次に書かれた作品である『こころ』も、物語は同じように手紙で終わる。あらすじは覚えていたので、図書館で全集を借りてきて最後の手紙を読み返してみた。
『行人』では『こころ』と違い、「結末のその後」は読者の想像に委ねられる。二つの手紙は、また二つの作品全体でも、それぞれ「死」が主題の一つとなっている。『行人』では死は暗示されるだけで、「兄」、一郎が自死するかどうかは読者の解釈に委ねられている。一方、『こころ』では死では作品の中で現実となり、物語は先生の死で終わる。
一郎の気分障害は「漠然とした不安」である一方、先生のそれは具合的な出来事に由来する点で異なる。しかも、その出来事によって先生は幸福を得てしまい、同時に友人を裏切る加害者ともなる。この両義的な心理が先生の苦悩を複雑にしている。
さらに言えば、一郎の不安は彼一人のもので、先生の不安は明治の精神とともにある。先生は自分の心情を過度に明治の終焉に重ねている。
そういう死は確かにある。乃木希典もそうだし、それで責任を取ったことになるのかは別として、敗戦と同時に自決した阿南惟幾の例もある。
そういう考え方自体、視野狭窄と見ることができる。先生が先にいて時代が後なのではなく、時代が先にあって人間である先生が後にある。要するに、漱石はあえて明治という時代精神(Zeitgeist)を擬人化して、先生という人格に投影したのではないか。
妻との関係、そしてKとの関係が、明治史の中の出来事と呼応しているのではないか。『こころ』を再読する機会を得たら考えてみたい。
森有正は先生の死で終わる『こころ』を「作品の文学的芸術的構成への関心によって、その内容を犠牲にしたのだと思う」と批判している。「罪人は自ら手を下して死ぬことはできないはずである」とさらに手厳しいことも書いている。
森ならば、最期が不明なまま終わる『行人』の方を評価するだろう。私も未来が読者の想像に委ねられている『行人』を好む。
ただ、その続きが幸福へ転換していくとは容易には思えない。きちんとした治療を受けなければ、彼は早晩「ひとり、ただくずれさる」状態になり、「この世界」から立ち去るだろう。
この感想は今の私の心理状態を反映している。気分が変われば、感想も変わるかもしれない。楽観的過ぎるだろうか。
先生を明治時代の擬人化と見て、その死を時代の終わりと見ると、森の批判は作品の中核を突いてはいないともとれる。
そして、苦悩する一郎を漱石が自身を投影した人物とするならば、静かに寝息を立てて眠っていたうつ病患者は、上に書いたように、生きていく拠り所を自力で見出していく。
『こころ』に対する森有正の指摘は、一理あるものの、森の見方には二点の誤謬があるように思う。
一つは、表現は賛同とは限らないということ。自死を描いたとしても、自死を積極的に肯定しているとは限らない。文学作品の表現は「こういう選択をする人もいる。あなたはどう思うか」という問いかけかもしれない。
さらに言えば、小説は虚構であり、実世界の出来事としてとらえて批判を加えることに限界もある。「画家は自分の死んだ姿を描くことで何度も生まれ変わることができる」といったことを小林秀雄が『近代の超克』で発言している。
森有正の「読み」にある二つ目の誤りは、自死を「冷静に熟慮した結果の自発的行為」と考えていること。多くの場合、自死は「死ななければならない」という強迫観念や、「自分は生きるに値しない人間」という視野狭窄を原因にしている。
先生の手紙も、思い詰めた心理状態にいることが推察できる。淀みない文章とはいえ、冷静な思考とは思えない。
西田幾多郎が夏目漱石と同じ時代の人であることを知ってから、片方を読むとき、もう片方を考える癖がついた。夏目漱石は1867年の生まれで、西田幾多郎は1870年生まれで3年しか違わない。大きな違いは活動した期間と亡くなった年齢。漱石は1916年に早逝したので、作家活動は1905年から1916年までの10年程度しかない。
一方で、西田は、『行人』が出版された年にようやく京都大学教授になったところで、本格的な研究活動はここに始まり、天皇に御進講もし、終戦直前まで生きた。
『行人』のなかで、「然し宗教にはどうも這入れそうもない」と一郎は述べて、宗教は現代にあって心の支えにはならない非力なものとみなされている。現代人は合理的になりすぎて宗教に身を投げ出すことが出来ない。こうした宗教観は『門』にも書かれている。全否定ではないにしても、宗教に対する懐疑が漱石にあったことは間違いないだろう。
まず絶対を意識して、それからその絶対が相対に変る刹那を捕らえて、そこに二つの統一を見出すなんて、随分骨が折れるだろう。第一、人間に出来る事か何だかそれさえ判然しない。(塵労 48)
兄さんが試みて出来ずにいるとHさんが見ていること。それこそ、西田幾多郎が生涯をかけて試みたものではないか。
西田は漱石が消極的にとらえた宗教に深く沈潜し、なおかつ自身の宗教体験を神学ではなく、哲学という普遍的な学問の言葉で表現した。
「うつ」という心理状態を自力で言語化した漱石は凄い。現代社会において廃れようとしていた宗教を徹底的に極めて現代の哲学に蘇らせた西田幾多郎もまた凄い。
近代日本における個人の在り方について、まったく異なる方向から思索し、表現をした二人の対談を聞いてみたかった。
2017年2月22日。「一郎の眠り」を箱庭に掲載。
写真は、図書館で借りた岩波書店版『漱石全集』の表紙。
現在、刊行中の「最終決定版!」「定本」とは別の「1994年」(平成6年)版。
2017年4月6日、追記。
信か、狂か、それとも、死か。漱石と西田はそれ以外の道を選んだ。
漱石が文学を通じた自己本位を、西田はどこまでも続く思索の先に哲学を見出した。
森有正と遠藤周作には信仰があった。小林秀雄の場合、彼自身ははっきりした言葉にはしなかったものの、遠藤周作が「人間のなかのX」と呼ぶ、生きる支えになる「何か」があった。「美」もその一部分をなしていただろう。それは、川端康成についても言える。
私には、まだ信仰への道は見えていない。すでに狂の状態にある。とすれば、この先で待つのは死のみか。
このところ、いつ、どこで、何をしていても、考えは同じところへ向く。
2017年7月1日推敲。
講演「文芸の哲学的基礎」は『行人』の執筆以前だったことがわかったので、論点はそのまま表現を変えた。以下は差替えた部分。
甲か乙かで悩む神経衰弱は消えて、自分の仕事を、自分の速度で、自分の好きなところまで広げる自由と余裕が感じられる。漱石は言うまでもなく優れた文学作品を書き残した文豪として知られている。彼の実生活を知ると、苦しみながらも自分を傷つけることなく、人生を生ききった勇敢な人と見ることもできる。
2017年11月3日追記。
「行人」とは旅人のこと、と川合康三『生と死のことば - 中国の名言を読む』(岩波新書、2017)に教えられた。思えば現代では使われていない言葉であるのに「行人」の意味には注意していなかった。
書名に込められた含意は、一郎が目的地の定まらない旅を続けて彷徨っている、ということだろう。
さくいん:夏目漱石、森有正、荒川洋治、遠藤周作、小林秀雄、川端康成、西田幾多郎

このブックカバーに書名を書いたのは高校三年生。すでにほとんどの漱石作品を読んでいる。そして、その人も神経衰弱だった。
