森有正エッセー集成2「城門のかたわらにて」他(原著1962-1969)、二宮正之編、イレーヌ・丹波・メックス(解説)、ちくま学芸文庫、1999
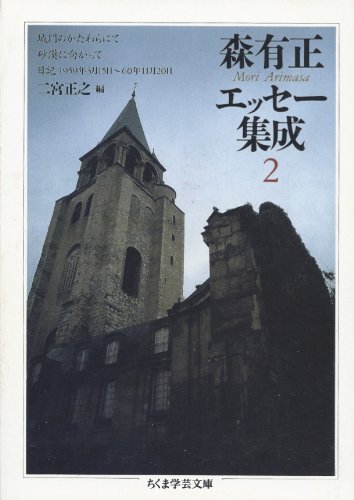
森有正のエッセー集は長い。堅苦しい文体で延々と独白が続く。それでいてけっして一本調子ではない。「城門のかたわらにて」は前の二作で提示された森思想の根幹をなす感覚、経験、定義という公式が敷衍されている。
どこを読んでも同じ雰囲気でありながらどこも少しずつ違っていて、論述の進行とともに思想が深化する。同じ概念が言葉や表現を変え何度も登場する。思想の深まりとともに表現も芳醇になる。
ところが、続いて収録された「砂漠にむかって」はどうにもわかりにくい。毅然とした態度で思索をつづける、それまでの三作品から文体こそ踏襲してはいるものの、話題や主張、さらに底流となる思考においてだいぶ違っている。一言で言って、不安定でとりとめのない作品。おそらくは著者もそれを知っていて、むしろそれを意図して過去に書いた文章を集めているようにもみえる。題名が、歩き疲れて、呆然としている思索者の心境を物語る。
「砂漠」がとりとめのない作品に感じられる理由は、構成全体の不安定さにある。まず、収録された手記が書かれた期間が長期にわたっている。そして、個人的な些事が中途半端に、また文脈に直接必要がないように思われる場面で断片的に挿入されている。こうした構成は読者を混乱させると同時に、作品に砂漠のような茫漠とした雰囲気を帯びさせる効果をあげてもいる。
こうした作品の構成がもつ不安定さだけではなく、この作品には、本質的な不安定さ、すなわち、思想に関わる問題も、「砂漠」には垣間見られる。
まず、政治的事象を宗教や文明の問題に還元してしまう傾向が見られる。
60年代は、ベトナム戦争、第三次中東戦争、文化大革命などが起きた、正に政治の時代だった。東西冷戦が強固な舞台装置となっていたことは言うまでもない。これらの事象のなかで、中東紛争は頻繁に「砂漠」に登場するが、森の中東問題に対する理解は宗教対立という見方に終始している。しかもイスラム教に対しては、不寛容ともいえそうなくらい、理解を示そうとしない。いずれ西欧キリスト教文明に屈服するだろうという見方は、あまりに一方的。
一言で言えば、西欧中心主義。とりわけフランスについては、文化だけではなく、当時のド・ゴール政権についてもほとんど無批判に賞賛している。いわゆる植民地主義への視点も、残念ながらほとんど見られない。
遅れた日本と進んだヨーロッパと、いう図式からも逃れられていない。西欧文明の批判なき礼賛、西欧文明以外の文明、宗教世界への無理解、植民地主義への無知、遅れた日本という自覚。この思考枠組みは左右を問わず、いわゆる戦後知識人の多くと共通している。
こうしてみると、森有正もいわゆる戦後知識人の思考方法にとらわれていた部分が少なくなかったと言わざるをえない。あるいは、森有正ほど自分自身の内側に巣食う偏見や思い込みと対峙しつづけた人であっても、時代の空気から離れて生きることはできなかったと言うべきかもしれない。
私の文章も、何年かして読んでみれば現在は本人だけでなく、同時代の誰も気づいていない偏見に満ちたものとわかるだろう。
ところで、森の経験についての考えを、私は次のように理解している。ある出来事が起こると身体と精神が感覚として受け止める。この時点で起こるのは条件反射的で情緒的反応。その感覚の反応を自分の言葉と身体で見つめなおすことが経験。
その出来事は何だったか、そのときの自分にとってどんな意味があったか、そのとき自分はどう反応したか、なぜそのような反応をしたか。そして現在の自分にとってはどんな意味があるか。そのような反省を通じて、自分の外側で起きたこと、自分のなかで無意識に起きたことを、意識化することが定義。
経験は、その出来事を追体験するように、何度も繰り返される。この感覚、経験、定義を繰り返して生きること、すなわち日々自己を反省しながら生きることが、思想を生きるということ。
その意味では、思想とは、どこかに目標があってたどり着いた先にあるものではない。たどりつこうとする過程そのものが思想。
ところが「砂漠」ではフランス語が完璧に習得されなければフランス文学はわからない、というような考え方が、ところどころに見られる。この考え方が西欧中心主義と合わさると、病的な劣等感に陥ってしまいかねない。「あせらない、発酵するのを待つ」というのが、本来森が思索するときの姿勢のはず。この点を見ても、歴史的な呪縛だけでなく、人間的な弱さも「砂漠」には散見され、茫漠とした雰囲気を醸し出している。
西欧対日本という構図は、森有正のなかで抜き差しならない問題。従って日本からパリへ移り住んだということは、森にとっては一大事だった。ただし、傍から見れば、森の生活には大きく変わっていない点もある。
移住の前も後も教員であるし、空襲後の焼け野原とはいえ、住んでいたのも首都なら移り住んだのも首都。実際、森は徹底的に都会人。彼が日本の自然として懐かしがっているのは、東京の一部分の風景でしかない。その他の自然については、友人宅で高地ネパールの写真を見て、「日本の自然に似ている」と単純に感心してしまうくらい、非常に平板な図象しか思い描いていない。
確かに敗戦直後に渡仏するという体験は、天地が覆るような出来事であったかもしれない。それでも、連続している点への注意がほとんどないために、非連続の点への注目度がかえって高められてしまったようにも思える。ここでもやはり、そうした連続面への無感覚が西欧中心主義を助長していたことは否めない。
要するに「砂漠に向かって」は不安定な作品であり、ある意味、わきの甘い作品と言える。いまの知識や第三者の冷静な視点から読むといくらでも批判が可能になる。巻末の解説でも、現代言語学の視点から、森の単純な言語観への批判がなされている。
それでも、森のエッセーにはじっくり読み込みたいと思わせる魅力があると言いたい。その魅力の源泉は、解説でも述べられているように、考えることに対する誠実さにある。
「城門」は、森自らが認めているように、彼の思索がたどりついた一つの到達点。茫漠とした「砂漠」を読むと、そこへ到るまでにどれほど無為な思索が重ねられ、多くの言葉が浪費されたのかをうかがい知ることができる。
森は「思想とは茶碗の洗い方一つにもあらわれる」と述べている。絶えざる反省を言葉で表現するだけではなく、生きるすべての場面で自らの行動に活かしていかなければ思想とは言えない。森有正がそれに成功したかどうか、彼を個人的に知らない私には知る由もない。
森有正が己に向けて問いかけていることは、著作を通じ読者である私に向けられる。そして、私が森に向かって書いているつもりでいても、実は、すべて本書に対する批判ですらなく、本書を読んだ私自身に向けられる。
茶碗の洗い方にさえ表われる思想とはどのようなものか。思想を生活全般、いってみれば生きざまにまで広げるとすれば、茶碗の洗い方を問う前に考えるべきことも多岐にわたる。
今の職業でいいのか、今の住まいでいいのか、今の食生活でいいのか、今の金銭感覚でいいのか、服装は、姿勢は、言葉遣いは、振る舞いは⋯⋯⋯⋯。今の私のあり方は、私の思想を反映しているだろうか。あるいは反対に私の思想は(そういうものがあるとして)私の生活によって裏付けられているだろうか。
森有正をとりまいていた存在拘束をあげつらうとするのはさして難しいことではない。ほんとうに難しいことは彼のように思索を続けること、言葉を換えれば、茶碗の洗い方に自らの思想を反映させようと努めること。
森有正を読んでいて感じるのは考えさせるという要請ではない。考えながら生きようという激励。これだけ内省的な手記で、文体に悲壮感さえ溢れているにもかかわらず森の思想はけっして厭世的ではない。森はいつも生きることをあきらめない。
原口統三、汐見茂思、奥浩平、高野悦子、岡真史。彼らは森がエッセーを書きはじめた年齢よりずっと若い。こうした思春期から青春期に書かれた日本語の手記は、内省を深めていった結果、皆自らを破滅させてしまった。
森の思索は徹底的に自己を批判し、ときには激しく責めながらも、自己の生そのものを追い詰めるようなことはしない。あくまでも、生きるための思想を追い求める。
森有正がそうした姿勢を維持できた理由は、デカルトに代表されるフランス思想の合理主義的な思想の影響や、キリスト教信仰のおかげだろう。いずれにしても、その精神力の強靭さが、読者を畏怖させ、また激励してやまない。
uto_midoriXyahoo.co.jp