夏の海の色、夏の海の色、辻邦生、中公文庫、1992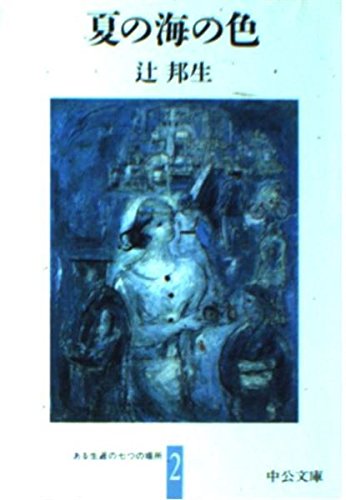
「夏の海の色」は確か中学三年の国語教科書の巻末に載っていた。出版社は光村。短編とはいえこれだけの長さの小説を授業であつかう余裕はない。読書へのいざないとして掲載されていたのだろう。 「夏の海の色」という題名はすっかり忘れていた。ぼんやりと覚えていたのは、夏、海、という題名の断片と海辺の風景。辻邦生の作品であることは覚えていたので、インターネットと図書館のおかげで見つけだすことができた。ところで、辻は辶のように点は二つでなければいけないのだけれど、いまのところ表示できない。 旅先での淡い恋心、美しい年上の女性に隠された秘密、失恋と帰郷。 そんな題材から思い出されるのは福永武彦「廃市」。主人公の年齢も違うし、舞台になる街も「夏の海の色」は海辺、「廃市」は運河沿いと異なっている。 それでも似通った雰囲気を感じるのは、水のせいではないか。水面に映る光と影が物語を印象的なものにしている。どちらの作品にも映像的な美しさがある。 辻邦生と福永武彦。二人には、フランス文学の素養という共通点もある。そのことと映像的であることに関連があるのかはわからない。まだ見ていないけれど、「廃市」は大林宣彦によって映像化されているらしい。 辻邦生は、「戦争前の一時期の、地方の小都市の静けさを思い描くには、現在では相当の想像力を必要とする」と書いている。 そんな文章から、「地方の小都市の静けさ」を舞台にするのを得意とする大林の映画が思い出され、作品に映像性を感じさせたのかもしれない。 15年以上が過ぎたいま読み返してみると、なぜこの作品を忘れることがなかったか、わかった気がする。甘酸っぱいといえばあまりに紋切りだけど、読んだころの思い出と、「あの頃」の重々しく苦々しい体験とがまざまざとよみがえってくる。 たった一度だけ読んだ短い小説の中に記憶が封印されていた。優れた小説はタイムマシーンになる。 |
碧岡烏兎 |