【演奏者プロフィール】
姜 建華(ジャン・ジェンホワ) 二胡
中国、上海に生まれる。10歳の時、叔父から二胡を学び、13歳から海外活動を開始。1974年北京中央音楽学院に入学、安如砺、蘭玉菘に師事。
1978年、指揮者小澤征爾が中国訪問の際、姜建華の演奏する"二泉映月"に感動し、タングルウッド音楽祭、ボストン響、サンフランシスコ響、ベルリ ン・フィルなどのソリストに招き、高度なテクニックと深い芸術性の両面で高い評価を得た。
1986年サントリーホールのオープニングで安生慶作曲「風影」を小澤征爾指揮、新日本フィルと演奏。1988年カザルスホール、1990年カーネギーホール100周年記念コンサート、1992年東京・王子ホールのオープニングコンサートに出演。国内外のオーケストラとはもとより、三味線奏者の本條秀太郎、りんけんバンド、林英哲、葉加瀬太郎、加古隆など幅広い分野の音楽家と交流を行っている。
2002年日中国交正常化30周年を記念、上海大劇院で初の二胡リサイタルを行い、あらためて二胡の可能性を中国にもたらしたと話題を呼んだ。
ビクターより7枚目のCD「故郷熱情」は中国、日本でリリース、2003年日本ゴールドディスク大賞特別賞を受賞。同年12月には、NHKドラマ「大地の子」のテーマ曲等を収めた、新しいアルバム「オーシャン・ロード・トゥー・チャイナ」をリリース。
郭 敏(ゴウ・ミン) 揚琴
中国、広東生まれ。中国音楽家協会会員。広東音楽院にて系統的な揚琴の奏法を学ぶ。数々のコンクールで入賞、一躍注目を集め、中国トップクラスの演奏家による特別編成の楽団に参加。中国を訪問する世界各国首脳たちの前で演奏を披露。1987年来日。各地でソロ・コンサートを行う。
1989年より東京芸術大学で民族音楽を学ぶ。新星日本交響楽団〈揚琴の伝統と現代〉、アジア作曲家連盟主催による〈アジア音楽祭in横浜〉に出演、東京FM「シルクロード・音夢紀行」「民族音楽を訪ねて」、NHK「花の舞台」、「名曲アルバム」、「スタジオパーク」などの放送に出演。映画音楽、CM音楽にも積極的に出演するなど幅広く活躍している。
【楽器豆知識】
二胡(にこ)
中国のリュート属弦鳴楽器の総称。ヘビ皮あるいは板を張った共鳴胴に棹をさしこみ、弦(2−4本)のあいだにはさんだ弓の張力を調節しながら擦奏する。調弦は5度がもっとも多い。胴の形は円形、六角形、半球形などがみられ、音色や音域も多様である。劇や語り物の伴奏音楽、器楽合奏などその用途はきわめて広い。「東洋のバイオリン」とも言われるように、二胡独特の暖かみのある音色は、人間の声ともっとも近く、主にメロディーを演奏する楽器となる。
揚琴(ようきん)
東アジアのサントゥール系統の弦鳴楽器。台形箱型の胴体の表面に数本ずつ組にして平行に張ったスティール弦を、両手に持った竹製のばちで打奏する。弦数は大きさによって異なる。民謡、地方芝居、語り物の伴奏や器楽合奏に使われ、朝鮮半島には18世紀に伝来し宴楽に使われた。音色は清らかに澄み渡り、2組以上の音を鳴らすことができるので、中国楽器やその他さまざまな楽器と素晴らしいハーモニーを奏でる。
【史跡案内】 金沢東別院
京都東本願寺の北陸の拠点で真宗大谷派金沢別院といい、地元では「別院さん」と呼ばれ親しまれている。
その歴史は、古く戦国時代までさかのぼり、一向一揆の拠点になったこともある。江戸時代に入り、「東末寺」として再建されたが、その後何度も火災に遭い、そのたびに復興されてきた。
大きな門の天井に描かれた、木村杏園の龍図が素晴らしい。
【会場案内図】 [拡大]
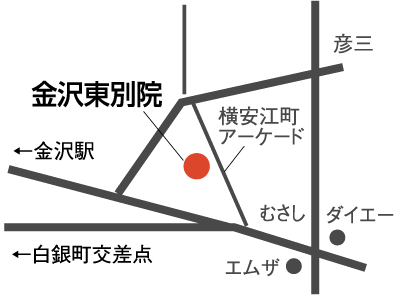
(金沢市安江町15-52)
| 【交通案内】 JR北陸本線 金沢駅東口より東へ 徒歩7分 |