【演奏者プロフィール】
SUKIYAKI STEEL ORCHESTRA(スキヤキ・スティール・オーケストラ)
日本でも数少ないスティールドラムだけで編成するオーケストラ。通称〈SSO〉。
95年8月に富山県福野町で開催のフェスティバル「スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド」前夜祭でデビューした。
トリニダード・トバゴの首都ポートオブスペインでは、毎年2月にカーニバルが開催される。国中のスティール・オーケストラが集まり、100人編成で演奏を競うコンクール「パノラマ」は、最も注目度の高いプログラムである。SSOは97年、このカーニバルの最終日に行われるチャンプス・イン・コンサートにゲスト出演した。
日本各地での演奏活動や、スティールドラムの本場でのゲスト出演など、その人気はますます高まり続けている。
【楽器豆知識】 スティールドラム
スティールドラム(スティールパンと呼ぶ)は、ドラム缶でできたメロディー楽器である。20世紀に発明された最後のアコースティック楽器とも言われ、カリブ海に浮かぶ島国トリニダード・トバゴがその発祥の地。
ソフトで美しい音色からは想像もできないが、アフリカなどから連れてこられた奴隷たちが、征服者との長く激しい闘いの中から生みだしたという歴史がある。
ドラム缶の底をハンマーで叩いて中華鍋のようにへこませ、そこにカメの甲羅のようにいくつもの面を作って輪切りにする。この面の大きさが大きければ低い音、小さければ高い音が出るというのがスティールドラムの原理。
いちばん高音のパートのシングルテナーは、1個のドラムから2オクターブを超える音階が出る。低音のパートになるにつれ、ドラム1個当たりの音の数が減ってくるので、ダブルテナーやダブルギターのように2個で一組、3チェロ、4チェロとドラムの数が増え、ベースに至ってはドラム缶6本を自分の周りに置いて演奏するかたちとなる。
また、一つの面だけを叩いても周りの面が共鳴するため、となりが和音になるように配列されている。ポワワ〜ンとした独特の音色の秘密はこの辺にあるようだ。
それゆえ、ピアノの鍵盤のようにドレミファが順番には並んでいない。
【史跡案内】 深谷温泉 元湯石屋
〜美肌と健康の湯として知られる珈琲色の薬湯〜
温泉は、1200年以上前から湧いていた伝えられています。泉質は、重曹硫黄泉で、ユニークな珈琲色をした「黒い湯」が特徴です。とろりとした感触があり、肌がすべすべになると好評です。
何千万年も昔の植物が土の中にたい積して、石炭や石油になる前に温泉になったと伝えられ、保たれたこの自然環境が土中にたい積した植物のエキスの溶け込んだ珈琲色の源泉を育みました。
珈琲色の湯に身を浸せば、植物エキスの効能により、身体の健康が保たれるという"天然の薬湯"。室町時代にこの地に滞在した日蓮宗のリーダー日像上人が、深谷温泉の名を広めたと言われ、また、倶利伽羅で木曽義仲に敗れた平家の落ち武者や剣豪・宮本武蔵が入湯したという伝説も残されています。
庭に能舞台があり、2階の大広間から観劇できる風流な宿。館内には加賀藩にゆかりの調度品などが展示されている。地元農家の野菜や米、地物の魚介類で、独創的な加賀会席でおもてなしいたします。
〜加賀宝生流の能舞台〜
日本古来の伝統芸術である能。
加賀藩前田家では歴代の藩主がその発展に力を注いできました。
加賀宝生流を愛した「石屋」先々代二左衛門は、出湯の里深谷の地に本格的な能舞台を作りました。
【会場案内図】 [拡大]
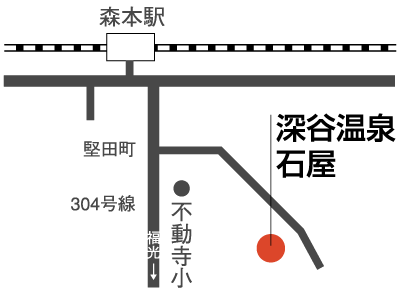
(金沢市深谷町チ95)