【演奏者プロフィール】 常味 裕司(つねみ ゆうじ)
1960年、東京生まれ。日本では数少ないウード演奏家。
民族音楽センター在籍中、アラブ音楽に出会う。スーダンのウード奏者ハムザ・エル=ディン氏のもとで演奏法を学び、89年、93年、00年、04年にチュニジアへ渡りアラブ世界を代表するウード奏者アリ・スリティ氏(チュニス国立音楽院ウード科教授)に師事、本格的にアラブ音楽を学ぶ。
93年のチュニジアでは、チュニス国営TV、メディナフェスティバルにてチュニジアの若手ウード演奏家モハメッド・ズィン・エル・アービディーン氏と共演。日本においては、アラブ・トルコ古典音楽を中心にソロ活動およびアラブ古典音楽団、自己のグループを主宰し、様々な演奏家、舞踊家、パフォーマーと共演。
これまでに大阪花博、浜松楽器博物館、琵琶湖芸術祭、京都建都1200年コンサート、奈良新薬師寺、戸隠五社奉納演奏、かなざわ史跡コンサート、大使館主催コンサート、国連大学、中東学会等でのコンサートで演奏を行う。またチュニジアより来日した女性楽団「エル・アズィフェット」との共演など、音楽を通した文化・国際交流も盛んに行っている。
最近では、シルクロードを音で旅する"東西琵琶物語"(ウード・リュート・中国琵琶・琵琶の共演)の企画にたずさわり、全国的にコンサートを展開している。
【楽器豆知識】 ウード
西洋梨形の木胴の表面に響孔があり、フレットのない棹に曲頸をもつ撥弦楽器。調弦は4度を基本とする。ペルシアに起源し、7世紀にはすでに西アジアで使われていた。
10世紀以降アラブ音楽でより重要視され、古来多くの理論書がこの楽器をもとに音律論を展開した。おもに地中海、イタリア半島をへて12世紀以降南ヨーロッパ(スペイン)、東ヨーロッパで変形され用いられたが、中世以降のラウテやリュートはそのなかでも重要なものである。
またウードの祖バルバット(ペルシア)は中国、日本の琵琶の祖でもあるため、ウードと日本の琵琶は同源から発生した楽器ともいえる。
【史跡案内】 心蓮社
心蓮社は、慶長17年(1612)に休誉露月上人により金沢塩屋町に開かれた名刹である。
寛永14年(1637)、三代藩主利常公より現在地に二千坪たらずの替地をたまわり、移転、移築したが、文化12年(1815)、大衆免石屋小路から出火した大火で類焼、堂宇は悉く灰尽に帰したと言われている。以後、本堂などは再建されたが、庭は江戸時代のままである。
寺宝には国の重要文化財「絹本著色阿弥陀三尊来迎図」、また芭蕉十哲の立花北枝、藩政改革の先駆者・寺島蔵人の墓などがある。市の名勝に指定される庭園は「めでた造り」と言われる遠州流庭園である。
【会場案内図】 [拡大]
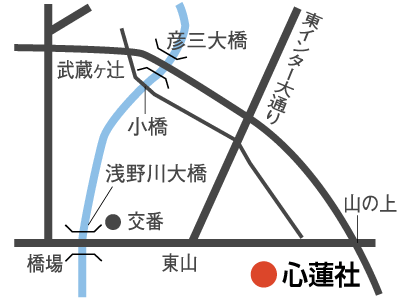
(金沢市山の上町4-11)
| 【交通案内】 北鉄バス 80番(柳橋行き)、84・85番(木越行き) →「森山」下車 徒歩10分 |