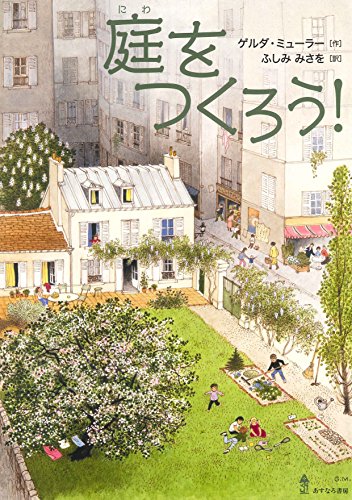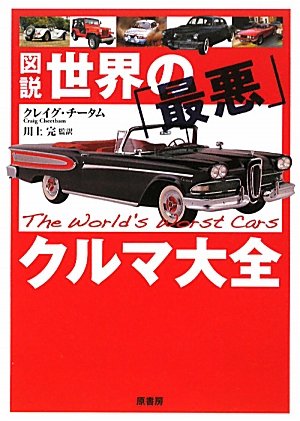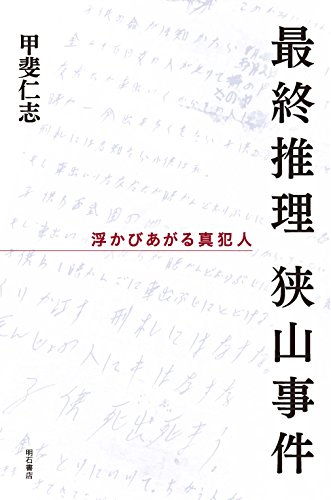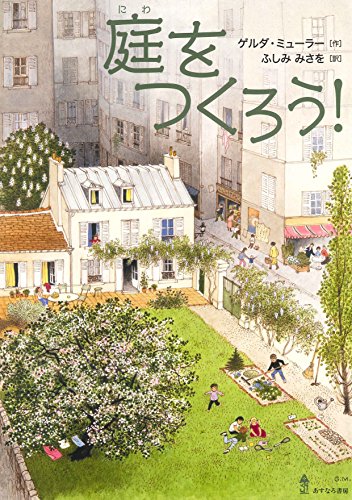
小さいながらも庭があるので、花や野菜を植える庭いじりをしたいと思っていながら、もう5年も過ぎてしまった。
この作品では、舞台は街中の家なので、庭はそれほど広くはない。といっても我が家の庭よりはずっと広い。
幼い頃に繰り返し読んでもらった読んだ絵本『パディントンの庭作り』を思い出した。
共通しているのは、子ども一人一人に場所を与えて自由に作らせるところ。
子どもが幼かった頃、寝る前に読んでほしい絵本を一冊ずつ自分で選ばせた。庭づくりまでは一緒に楽しむことはできなかった。
『パディントン』といえば、大人になって読み返したときに、パディントンが「暗黒のペルーから来た」と言っていることに驚いた。
修正されないままでいるけれど、『ちびくろ・さんぼ』と同じくらい問題のある表現に思える。
この雑誌は定期的につく別冊付録が面白い。付録といっても本編に負けないほど厚く、写真も多い。今回は「国産名車の奇跡 昭和〜平成」。
大衆車でも高級車でも、またスポーティカーでも、70年代は各社各様、個性的なデザインが多かった。80年代になると直線を引いたデザインが主流となる。
90年代を過ぎると、緻密な空気抵抗計算の結果なのか、メーカー間での違いもわかりづらくなり、同じメーカーの車種でさえ、世代の違いもはっきりしない。80年代までは世代ごとに思い切ったデザイン変更があった。
国内では市場が成熟してしまい、メーカーは「キープ・コンセプト」から逸脱する勇気をなかなかもてないのかもしれない。
ならば、70年代の日本車のデザインがよかったかというと、そういうわけではない。あの頃、自動車評論家の徳大寺有恒は、デザインも性能もドイツのVWゴルフを絶賛し、ほとんどの日本車については、「実用性が低い、後方視界が悪すぎる、フロントマスクが下品」など、強烈な毒舌を吐いていたのだから。
そのせいか、80年代には日本車でもゴルフのデザイナーだったジウジアーロ風が流行した。それ以降、数だけではなく、デザイン、性能、品質、それらの総合であるブランド力においても、日本車は独自性と優位性を獲得していった。
徳大寺の毒舌は、日本車の進化に少なからぬ功績があったと思う。
さくいん:70年代、徳大寺有恒、80年代
別冊付録「日本の名車 カタロググラフィティ 70's」に掲載されたクルマの中に、自動車雑誌を小遣いで毎月買うほどクルマが好きだった小学生だった「あの頃」、憧れていたクルマが多く掲載されている。
- セリカ(初代)
- スカイライン(C110、ケン・メリ)
- サバンナ(RX-3)
- レオーネ(初代)
- フロンテ(3代目)
ホンダがビートを復活させてS660を発売した。スズキもフロンテやその後継となった初代セルボをリメイクしてくれないか?
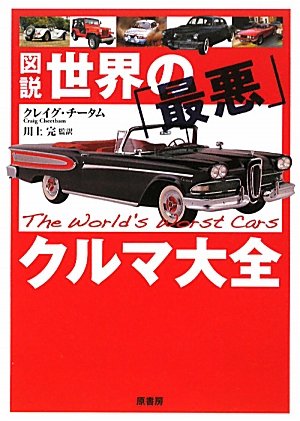
面白い。商業的に失敗したクルマを150台も紹介している。解説にもあるように、言い回しがユニークで読んでいると何度も吹き出しそうになる。
吹き出しそうになった見出しをいくつか拾うと「走るサウナ」「ダメデザインの見本」「戦慄のハンドリングと落胆のパフォーマンス」「血統書付きの駄馬」「センス皆無の高級車」(ちなみにこれはレクサスSC430)「車輪の付いたゴキブリ」「狼の皮を被った羊」。
著者が「最悪」クルマを選出した基準。
150のクルマは以下の5つに分類したーー「作りが悪いにもほどがある」「設計ミスもはなはだしい」「少しは採算も考えろ」「名前を変えればいいってものじゃない」「とにもかくにもひどい」。(まえがき)
なぜ「最悪」クルマが生産され販売されてしまうのか。原著の副題には“From Pioneering Failures to Million Dollars Disaster”とある。最新技術を十分検証せずに投入してしまったせいで、結果的に市場で失敗することもあれば、設計・販売・経営の足並みが揃っていないことも原因になる。とくにヨーロッパでは労働組合と経営側の関係が悪いとクルマの質も悪くなる例がいくつも挙げられている。
多くの優秀な設計者や経営者を抱える世界規模の大企業が、なぜ、誰もが首をかしげるような奇想天外なデザインや性能劣悪な「商品」を世に出してしまうのか。本書の指摘によれば、マーケティング・機械・内外のデザインなど、社内の各部門間での連携が円滑でないと「船頭多くして」誰も想像していなかった「ダメクルマ」が作られるという。
90年代までは防さび対策が自動車生産の最重要課題だったことを知った。
これができていないと、どれほど素晴らしいデザインでも高性能なエンジンでも、市場では成功しなかった。
大笑いしながら読んでいくうちに、自動車業界の構造の一端もわかる有益な本。
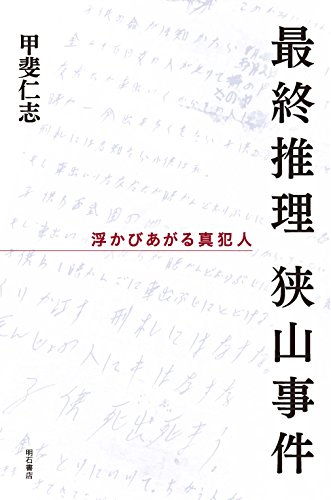
書名と内容はすこし異なる。本書では、これまで公開された証拠や裁判記録から「どのような人物が犯人か?」という、いわゆるプロファイリングをしているけれど、真犯人を名指ししてはいない。その手の本やウェブサイトは数多くすでに存在している。
著者は、今となっては、真犯人探しが「狭山事件」について考える際に重要なことではないし、それどころか、有害と考えている。
「狭山事件」は重大な冤罪案件。最も大切なことは、石川一雄さんの再審・無罪判決を裁判所から引き出すこと。
その観点から、本書は、警察、検察、裁判の改革の必要性を訴え、詳しく論じている。
「ミステリーごっこ」を期待する読者は失望するだろう。
「狭山事件」をきっかけに冤罪に関心を持つようになった読者は、日本の警察・検察・裁判の問題点について多くを学ぶだろう。