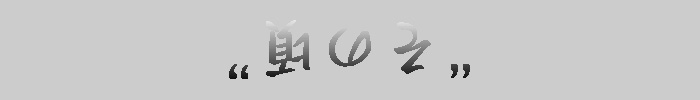私の引き出し
佐野元春(1984)VISITORS

1984年。それは私にとって、親元を離れ、岩手県で一人暮らしを始めるという特別な年だった。
岩手県で初めて迎えた秋は、寒さが急激に深くなっていく。これから訪れる見知らぬ冬を独りで想像している頃、私はこのアルバムを聴く機会を得た。
いきなり日本を離れてニューヨーク生活を送っていたという佐野元春が、何だか以前と違う曲を詰め込んだアルバムを出してきた。でも、それは私にとっては、「ああ、これが日本語のロックなんだ」という、何の根拠もない感想につながっていた。
勝手にドラマチックな遠距離恋愛だと思っていた彼女が、その秋に1通の手紙を以ってフェードアウトして行って、でもその事実を認められないまま迎えてしまった冬に、日本語と英語をごちゃ混ぜにした言葉を叩きつけるようなロックは、打たれた心を更に打ちのめすには最適だった。
それから10年もたたないうちに、日本にもラップ/ヒップホップが上陸した。何だか軟弱なラップだった。佐野元春は1984年という年に、まだ誰も知らないラップを日本にもたらしたんだ。そう気づいた。みんなそう気づいて、このアルバムを10年以上たってから神格化した。
だがしかし、公式サイトで佐野元春は後年、「ちょっと頭がおかしくなっていた僕が作ったアルバム」というようなことを書いていた。その台詞はなぜか間もなく消されてしまったが、私もちょっと頭がおかしくなるような不安定なときに、このアルバムを聴きたくなる。
椎名誠(1979)さらば国分寺書店のオババ
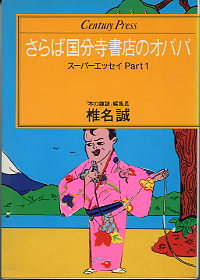
それまでサラリーマンだった椎名誠が書いた「スーパーエッセイ」第一弾がこれ。スーパーエッセイなどと書いてあるが、これは「推理小説だ」と、読んでいるうちに気付いたのだ。
序章は国鉄職員への怒りから始まる。それは、地下鉄職員、タクシー運転手、コームイン一般に対しての怒り、そして交番の警察官へと広がっていく。そして、国分寺書店に自転車で古本を売りに行ったエピソードを伏線として挟みながら、「おまわり人形」へと怒りの矛先を広げてゆくのだ。
そして、ちょうどこの本の真ん中あたりで、椎名誠は「あっそうなのか」と一つの謎を解明する。それは、これまでの一連の不満は「制服を着ている人々」、中でも「紺色の制服を着ている人々」に向けられていたことが判明するのだ。
ところで国分寺書店のオババは、全集ものはすべて揃っていないと気がすまない性格らしい。椎名誠は、それも一つの制服志向と同じだと考える。全集ものは制服を着ている人々と同じで、一つ一つのときは小さくなっているのに、集団になると突然威勢を張る。そういう全集ものを信仰する国分寺書店のオババも、椎名誠からすると制服の人と同じ人間になってしまう。
そんな椎名誠は、小さい頃からジャーナリストを目指しており、「ジャーナリストはよい、制服関係はダメ」と言う価値観を持っていた。しかし、物語の最後に来て、この価値観は大どんでん返しとなる。それは、マスコミ関係のパーティーで、狙っていたうに寿司をすべて食われてしまうと言う個人的な恨みから発生する。マスコミの人が世の中から消えても困らないが、制服関係の人が世の中から消えると電車も動かないし、ごみも収集されないし、水道も止まってしまう。それに、制服関係の人は本当の個性を持っている。着る物だけで個性を主張しているマスコミの人々とは違うのだ、ということを発見する。
最後に、国分寺の駅に降り立った椎名誠の前で、国分寺書店は店を畳んでしまっていた。口うるさい国分寺書店のオババも、本当は古書を取り扱うプロフェッショナルだった。そういうすべての謎が解けた所で、この「推理小説」は終わるのだ。
石原プロモーション(1976)大都会−闘いの日々−

冬に始まり夏に終わったこの物語は、黒岩刑事(渡哲也)と謎の女直子(篠ヒロコ)との出会いから別れまでを描く。黒岩の妹の恵子(仁科明子)は、黒岩刑事に恨みを抱くやくざに高校時代に暴行されるという過去を持ち、その過去を引きずりながら、いつまでも幸せを取り逃がしている。
型どおりのストーリー運びや安心できる結末を望む多くの視聴者には受け入れ難い、暗くて、難解で、後味の悪い話ばかりがこれでもかと繰り返される。念のためだが、刑事が主役でありながら、銃撃戦やカーアクションはない。後にこれをシリーズ化した「大都会PART2・3」や「西部警察」が大好きな人は、別の作品と思った方がいい。
早くも第4話で、「悪いのは組織だ」と丸山刑事(高品格)が口にするように、警察組織の決定に従うことで、死ななくていい人が死んだり、不幸にならなくていい人が不幸になる。黒岩刑事は、目の前の人間を救いたいと思いながらも、黙ってその結論に従い、自らの葛藤を静かに抑え込んでいる。最終回で、直子は闇社会の大物との関係を断ち切り、黒岩刑事と一緒になることを選んだはずだった。しかし、これも警察組織としての深町課長(佐藤慶)の捜査協力依頼により、すべてが壊され、黒岩の前から去らざるを得なくなる。
考えてみれば、正義と悪役がはっきりと分かれたドラマが多い中で、ここに出てくる人々は、どちらがどちらなのか、見る人が決めるしか方法はない。深町課長の代弁者として時に毅然とした態度をとる一色課長代理(玉川伊佐男)は、実は自分では何も決められない「太鼓もち」ではないか。正義を振りかざしてその場をかき乱す東洋新聞の九条記者(神田正輝)は本当に正義なのか。
そういえば、第11話の「大安」では、暴力団の組長(内田朝雄)が娘の結婚式と同じ日に同じ式場で結婚式を挙げる一般市民に、一軒一軒挨拶とお詫びに回る。組の者を呼ぶわけでもなく、身内で済ませようとしていた組長の思いに反し、事を荒立てたのはスクープした毎朝新聞の大久保(平泉征)。ここまで何も事件は起こらない。しかし、報道という正義のために罪のない組長の娘をも取材対象にする大久保に対し、組長があえて押え込んでいた静かな怒りを履き違えた舎弟(清水健太郎)が大久保を刺すことで、最後に初めて事件が発生。何が正義で何が悪なのか・・・。
最終回「別れ」の最後に、場面は第1話と同じように黒岩は妹の恵子と二人で銭湯に行く。再び始まった警察署での1日。煙草を吸いながら黒岩が振り返った所で物語は終わる。
(2012年、DVD発行)
大都会−闘いの日々−の引き出しへ
アルフィー(1980)無言劇

まだ無名のグループだったアルフィーが1980年に出した7枚目のシングル・レコードが「無言劇」。もちろんヒットなどしなかった。
東京12チャンネル(当時)で放送された「あいつと俺」という刑事ドラマのテーマ曲だった。川谷拓三と清水健太郎がコンビで全国を出張しながら捜査するというドラマで、第1話のロケ地は北海道。3月の放送で、極寒のオホーツク海に見守られながら、雪の中を走る刑事たちの背景に、この曲のインストが流れる。南米の民族音楽で使われるケーナのような音色で奏でられるこの曲のイメージは強烈だった。エンディングで流れる曲は歌入りで、クレジットを見ると「アルフィー」という知らないバンド名が読み取れた。ところが、このドラマは第4話であっさり打ち切りになってしまった。
その後、アルフィーはスポンサーもつかない番組「冗談音楽工房」(TBSラジオ)で自作の替え歌などを披露。「覚醒剤の喫茶店」(ガロ「学生街の喫茶店」のパロディ)、「たべる」(谷村新司「昴」のパロディ)、「ある日突然」(トワ・エ・モア「ある日突然」のパロディ)などが最高。そんな感じに、知る人ぞ知るバンドとして個性的な活動を続けていたアルフィーが1983年、武道館公演を機に一気にメジャーにのし上がってしまった。
若い女性から「アル中(アルフィー中毒)」なる言葉が生まれた1980年代中頃という時代もあった。
カラベリ・グランド・オーケストラ(1981)二人の日曜日

ムード音楽という名前が曖昧だったためかイージー・リスニングというジャンル名がついた頃のこと。このジャンルでの新旧交代というようなことが言われていた1980年、パーシー・フェイス、マントヴァーニ、ベルト・ケンプフェルトらが亡くなり、フランク・ミルズ、リチャード・クレイダーマンというようなピアニストが登場してきた。この時点で50歳、ベテランの域に入っていたカラベリが、オリジナル作品のみのアルバムを発表したのは、他のアーティストらの影響が少なからずあったものと思われる。
このアルバムの中では「二人の日曜日」「ブエノスアイレスの瞳」「白いクラシック・ピアノ」の3曲がメロディの美しさで群を抜いており、後年に発売されたCDに混ざっていたりするのだが、アルバム自体はCDになっていない。つまり、残りの9曲はレコード・プレイヤーがないと聞くことができなくなっているのだ。アナログからデジタルへの間にあった1980年代初頭にはよくあることだが、このアルバム自体の評価の現実が如実に表れているような気もする。
イージーリスニングで最も好きなのはカラベリで、そのカラベリの中で最も好きなアルバムは「二人の日曜日」だという私の生存中に、このアルバムがCDとなることは・・・多分ないんだろうと思う。できれば、このアルバムの最後を飾る「ヒースクリフの丘」が流れる中で息を引き取りたいという夢は叶うのだろうか。
カラベリ・グランド・オーケストラの引き出しへ
藤子不二雄(1975)新オバケのQ太郎

オバケのQ太郎というのは、日本の男性の真の姿を表現したんだろうなあ、と思う。
男というのは、格好いいことを言っていても、本当は格好悪い。格好いいと思い込んでいるやつほど、格好悪い。
男にはいつもライバルがいる。しかし、ライバルには勝てない。勝っていると思い込んでいるやつほど勝てていない。そもそも、決定的な部分で負けているのを認めようとしない。オバケなのにどうして化けられないのか。化けられないのにオバケなのか。Q太郎の場合、ライバルのドロンパだけでなく弟のO次郎にさえ負けている。
Q太郎は、それでも陽気に生きている。それが大事だ。
姫神せんせいしょん(1982)姫神

1980年に入ると、音楽シーンというものが大きく変わった、と高校生になったばかりの私は感じていた。フォークソングからの直系であったニューミュージックというジャンルに、もんた&ブラダーズとかシャネルズとかいうロックやワールドミュージックの風味が加わってきた。
しかし、そんな音楽にも新しさを感じない人々が傾聴していたのがシンセサイザーだった。イエロー・マジック・オーケストラ(YMO)の「テクノポリス」や喜多郎の「シルクロードのテーマ」が次の時代の音楽として、彼らの感性をくすぐったようだった。
ただ、新しくて未来を予感させるシンセサイザーが奏でる音楽が、テクノミュージックであったりシルクロードであったり、宇宙であったりすることに、私は素直に賛同できなかった。新しいものを使って常識的な新しさの方向に向かっているだけではないのか。
そんなとき、シンセサイザーで日本、それもなぜか東北地方を奏でる姫神せんせいしょんを知った。古いものとか身近なものがダサいと思われる風潮の1980年代にあって、真正面から日本に向き合った姫神せんせいしょんの姿勢こそ、私が求めていたものだった。
しかし、1980年代はまだ、姫神せんせいしょんに追いついてはいなかったと思う。高校の体育祭で、応援合戦を行う応援団の一つが、学ランを着て鉢巻をする型通りの応援の合間に「えっさ、えっさ、えっさっさ。えっさ、えっさ、えっさっさ」という日本の祭りのような掛け声を採り入れた。白け切っていた私はそれを聞いて覚醒した。ところが、おおかたの高校生は、それを受け入れることは出来なかったようだ。女子が「あの“えっさっさ”がなけりゃよかったのに」と二人で泣いていた。その程度の時代だった。
(注:その後にこのエッサッサは、日体大の伝統的な応援スタイルであることを知りました)
姫神せんせいしょんの引き出しへ
鴨川つばめ(1977)マカロニほうれん荘
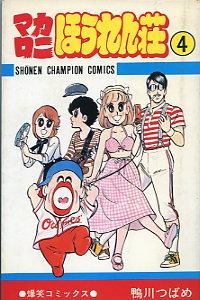
1970年代末期に少年チャンピオンに連載された伝説のギャグ漫画。
などと言う型どおりの説明はしたくない。ギャグ漫画の革命であり、ギャグ漫画のニュースタンダードを確立した偉大な作品であるはずだ。
例えば、ギャグを聞いた瞬間に「ガクッ」と言いながらずっこける仕草があるが、これは「マカロニほうれん荘」が最初にやったことだ。
いや、こんな事を説明してもしょうがない。
中学生だった私は、この漫画を授業中とか電車の中とか床屋さんとかで見ることができなかった。なぜなら、声を出して笑ってしまうからだ。読み終わってからも、床屋さんで髪の毛を切られながら思い出して笑いが止まらなくなるからだ。電車を降りて独りで階段を下りている最中に思い出して笑ってしまうからだ。
ギャグは一発では終わらない。畳み掛けるように次のギャグ、次のギャグと立て続けに出てくる。ギャグをやりながら、無関係の力士の扮装に変わっているし、次のコマでは力士に恐竜の尻尾まで生えている。背負わなくてもいいリュックサックまで背負っている。
しかし、この「マカロニほうれん荘」が伝説になったのは、そんな最盛期の後、急激なフェードアウトを遂げたからだ。何だかアメリカっぽい画風になったあと、画もストーリーも手抜きになり、いきなり最終回を迎えてしまう。その後、何回か復活めいた話はあったようだが、今では作者の現況すら分からない。最盛期を知る者として、いつかは復活してほしい、最盛期のスピード感溢れるギャグ合戦を見せてほしい。そう思いながらも、そんな夢は多分叶わない。
「マカロニほうれん荘」はそうして伝説と化してしまった。
マカロニほうれん荘のキャラクター変質の引き出しへ
結城昌治(1978)夜の追跡者

多分この小説のジャンルは「ハードボイルド」。小気味よく読める。ただ、結城昌治が送り出した作品には、スパイものの「ゴメスの名はゴメス」とか、推理小説の「ひげのある男たち」とか、色々あって、この作家の固定した評価もあるのかないのか分からない。
私は中学生のとき結城昌治の作品に出会い、図書館で借りてきては読み漁った。旅行するときには鞄に文庫本をたくさん入れて、旅先の暇な時間にずっと読んでいた。1980年代には、2時間ドラマの原作にもよく取り上げられていたので、人気作家の一人なのだと思っていた。
ところが、社会人になってしばらくの頃だから1990年代、結城昌治の文庫本がほとんど絶版になっていることに気がついた。もちろん、新刊が発売されることもほとんどなくなっていた。
私の古本屋通いが始まった。初めて入った古本屋で結城昌治の本に出会うこともあったし、手元にないと思って買って帰った本が既に家にあったこともあった。手に入らない本はなかなか見つからなかった。そもそも流通量が少ない本は、古本として流れることも少ないのだと知った。
作家名の五十音順でいうと「や」行なので、近くに「夢枕獏」とか「吉村昭」とかがある。こういった人たちは人気作家なのか、古本の流通量も多い。いつしか「夢枕獏」の文字を見ると近くに「結城昌治」があるような錯覚に陥るようになった。「夢枕獏」の文字を見るとハッとするようになった。
最後まで手に入らなかったのは、1982年発行の「遠い旋律」だった。最後の方に発行されただけあって、売れた量も少ないから、古本屋にもなかなか出なかったのだろう。それをある日、ドライブ中に立ち寄った「ブックオフ」で発見した。
目的を達成してしまったときの虚脱感。何だか生きていく一つの目標を失った虚脱感を感じた。これから古本屋を見かけても、立ち寄る必要がないのだというのも、なぜか寂しく感じた。人間はこうして目標を失っていき、死んでいくんだろうな、などと思うのだった。
結城昌治の引き出しへ
フランク・ミルズ(1986)愛の情景(TRANSITIONS)

カナダのピアニスト、フランク・ミルズと言うと、1979年にヒットした「愛のオルゴール」を思い浮かべる人が多いはずだ。その後も「夢見るピアニスト」「ハッピーソング」などの可愛いピアノ曲を送り出していた。
それから10年も経っていない時期の作品でありながら、このアルバムの雰囲気は、それらのヒット曲とは全く異なっている。静かで暗い。ドラマの背景にゆっくりと流れているのが似合うような音楽だ。そのドラマというのは、大きな決断を心に秘めた男が不気味な出来事にまとわりつかれているというようなサスペンス。
のっけからドラマの始まりを予感させる「心の町」(HEART OF THE CITY)、かつての「スパニッシュコーヒー」を連想させる格好いい「ニューイングランドのスケッチ」(SKETCHES OF NEW ENGLAND)、決意を秘めた旅立ちを連想させる「涙のラストテーマ」(TRANSITIONS AND TRIUMPHS)。
ただし、かつてのフランク・ミルズを全面的に支持する人にとっては、迎合できないアルバムであるに違いない。
フランクミルズの引き出しへ
松本清張(1965)投影

子供の頃にどんな伝記を読ませられても、そんな偉人になりたいなどとは一かけらも思わなかった私が、中学生のときに読んだ「投影」の主人公・太市のような人生を歩みたいということは、切に望んだ。
松本清張作品といえば、長編の推理小説に有名作品が多いが、そういうものを読む持久力がなく、短編を好んで読んだ。この短編集に収録されている「地方紙を買う女」「一年半待て」も名作だが、異色作品でもある「投影」は深く心に残った。
東京で新聞社に勤めていた太市は、部長と喧嘩して会社を辞めてしまい、頼子と二人で瀬戸内海の小さな町へと移って来る。好きな釣りをしながら無収入で暮らすわけにもいかず、頼子はこの町で随一のキャバレーに勤め始め、太市は小さな地元新聞社に勤めることとなる。
この町で、太市はちょっとした出来事に遭遇し、やがて市の土木課長が事故死する。その事故死が実は仕組まれた殺人であることを、太市は証明し、それを記事にする。
最後に二人は再び東京へ帰ることになる。見送りを受けながら、太市は涙を流す。
中学生の私は、俺も上司と喧嘩したりして、地方の町へ流れていくような人生を本気で歩みたいと思った。同時に、もしこの物語をテレビドラマにするなら、エンディングテーマはアリスの「遠くで汽笛を聞きながら」だな、などと思った。
(短編集「張込み」に収録)
オライオン映画(1987)サンタリア

もしも最愛の人がカルト宗教に洗脳されていることを知ったら、この上ない絶望感に襲われるだろう。
この映画は、実在するカルト宗教を題材にしているが、簡単に流してしまえば、オカルトとかホラーとか言うジャンルの映画になるだろう。妻の感電死から始まり、小さな子供が腹部を切り裂かれる事件の発生、自分の子供に対して家政婦が行う奇怪な宗教的儀式、新たな彼女との出会いの中でその彼女にも及ぶ危機、そしてクライマックスではカルト教団の餌食となった息子を救い出すための手に汗握るアクション・・・。まあ、ホラー・アクションの常道といった流れか。
しかし、この映画の見所はラストにある。息子と新しい母親となる彼女との新しい生活が始まる。都会から離れ、新しい幸せに浸る三人。納屋の方で犬が吠えている。なんだろう。
(VHS)
椎名誠(1990)アド・バード

よく動物には予知能力があると言われる。大地震の前に動物の異常行動が見られたと言うような実例だ。しかし、これらはどうやら予知能力というより、人間には感じられない微量の電磁波などをキャッチして、暴れたり逃げたりするらしい。
似たような話で、雪国ではカマキリが木の幹に産む卵の位置が高いとその冬は雪が多いと言われている。カマキリは雪の量を予知できるのだろうか。これもそうではなく、カマキリは一定の水分量のある高さに卵を生む習性があるらしい。その木の幹は地面から水分を吸い上げるが、その量は地面が含有する水分に影響される。そして地面が含有する水分とその冬の雪の量に相関関係があるようだ。つまり、カマキリは遺伝子情報に基づき、決められたとおりに卵を産むとちょうど雪に埋もれない高さに位置し、子孫を残すことが出来るのだ。
こういう自然の摂理を人間が自分の都合よくコントロールしたらどうなるだろう。朝の光を受けて部屋のカーテンを開ける動物とか、時間になったらテレビのスイッチを入れる虫がいたら便利だろう。鳥が隊列を組んで飛ぶ軌跡が何かのデザインになれば、自然が生み出す広告になる。しかし、そんな遺伝子をいじるようなことをしたら、結果的に自然界からの復讐を受けて、この世界は滅亡してしまうかもしれない。
そんな世界観をSF小説として形にしてくれたのが、この「アド・バード」だ。描かれているのは、そんな風に人間が動物や植物を利用して作り上げた広告が辺りを飛び回る未来社会。いやその未来社会が破壊されてしまった後の廃墟の未来社会だ。
椎名誠はそれを読みやすいように冒険SF小説として完成させてくれた。しかしそれでもなお、読み進めるにはかなりの努力が要る。途中で脱落してしまう読者がたくさんいるのではないかと心配したくなる。主人公の冒険と並行して、戦闘樹とか蚊食い虫とか海視人とか意味の分からない生き物の意味不明な行動描写が何度か現れる。私も何度もここで本を閉じかけた。
椎名誠の頭に中には、広告に支配された近未来の設計図がこと細かくインプットされており、そのディティールをこの小説のあらゆる場面に撒き散らしている。それら一つ一つを拾い上げてみても、なかなか椎名誠の頭の中と同じ完成形を作り上げることができないから、ついていけなくなるのだろう。
それならば、この作品をぜひ映画化してほしい。薄暗い画面の実写と、煌びやかなカラーに溢れたCGとをふんだんに組み合わせて、退廃した異常な未来社会を映像化してほしい。そうすることで、これまで最後まで読めずに脱落して行ったたくさんの読者に、この物語の面白さを分かってもらえるのではないだろうか。
五木寛之(1991)ワルシャワの燕たち
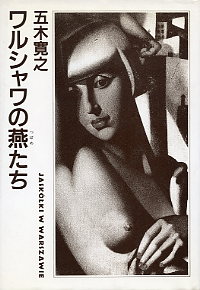
文学小説を読もうと思うことがなかなかなかった私がこの小説を読むことになったきっかけは、新聞の書評欄に書かれていた「ハングリー」という言葉に尽きる。
社会人になって3年ほどを経て、自分が何をしたくてどこに進んでいるのかがよく分からなくなっていた。自分の周りの出来事や人間がすべて混沌とした状態の中で、自分から何かを解決する手立てを見つけることが出来ないでいた。
過去の自分はあんなこともやっていたし、あんなこともできた。しかし、今の自分にどんな力が出せるのだろう。年齢のせいで、或いは鍛錬を怠っているせいで、恐らくここ一番の力など出せないのにちがいない。奇跡などないのだから、図らずも勝負に負けた自分を苦笑いでごまかし、あえて第三者の目をかいくぐろうとするのだろう。
主人公の沢木は、裕子を東京に引き戻すための最後のひらめきで、彼女の乳房をつかみ目を見つめるが、彼女は一枚上でそれを見透かす。そして沢木はワルシャワ最後の晩、レースの腕をプシェメックに見せようとしてスピンターンで失敗。車を壊してしまう。ハッピーエンドのかけらもなく、この物語は終わってゆく。
現実とはそういうものだ。1991年の自分は、これからも多分自分に降りかかるであろう現実というものをやっと予見しながら、この本を閉じたのだった。
山科けいすけ(1994)C級さらりーまん講座

ビッグコミックのページをめくるとき、ほかの退屈な連載漫画は全部飛ばして「C級さらりーまん講座」だけを見る。4コマ漫画を理解しない人は、この漫画を読むといい。
ここしばらく、ヘタウマ漫画とか不条理漫画とか、4コマ漫画はほぼ崩壊してしまった。起承転結のある4コマ漫画を見なくなった。しかし、「C級さらりーまん講座」には、起承転結だけでなく、パロディ精神、シュール、社会風刺など、4コマ漫画に必要なすべての要素が揃っている。
tohko(1998)籐子

小室哲哉プロデュースでデビューしてしまった宿命なのか、このデビューアルバムと2枚目のアルバムを出して以来、その姿を見せなくなってしまった。
ボーカルというのはどんな楽器にも出せない音色を奏でることができる最高の楽器である。このことが、tohkoの歌声を聞くとよく分かる。甘い声から力強い声まで、歌に合わせて使い分けることのできる優れたボーカリストだと思う。
デビューシングルの「BAD LUCK ON LOVE」がいい。
テレビ東京・石橋プロダクション(2002)オー!マイキー
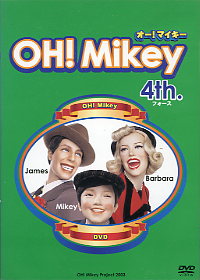
動かないマネキンにセリフをつけて1話3分ほどに仕立てたショートストーリー。アメリカから日本に引っ越してきた”フーコン・ファミリー”という家族の設定。何と言っても内容がシュール。各話ともにラストは両親とマイキーが大笑いをして強引に終わる。
出演するマネキンに子供が多いが、大人向け。いや、大人にしか分からない。間違っても、家族が食卓を囲んで見るものではない。子供にも高齢者にも意味が通じない可能性がある。
最初、外国作品の吹き替えかと思ったが、れっきとした日本の作品。日本人がこういうものを作って世に出すことがあるのだと新鮮な驚きに満たされた。テレビ東京系列でしか見られないようなのが残念。いや、日本のキー局では「サザエさん」とか「ドラえもん」とか「NHKのど自慢」とかを流して、平和ボケした日本人家族を喜ばせておけばいいのだ。「オー!マイキー」はアングラなままでいいのだ。分かる人が見て大笑いしていればいいのだ。
山上たつひこ(2009)中春こまわり君
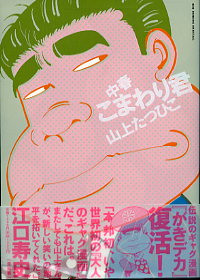
漫画の登場人物は年をとらない。いつまでたっても子供だ。
しかし、こまわり君は38歳のサラリーマンになっていた。こまわり君の過去に相容れない35歳の妻もいる。そして子供も生まれている。
妻は急に家出するし、同級生のジュンは義父の下の世話で忙しいし、担任だったあべ先生は肝臓を患いながらも酒に溺れているし、こまわり君自身も痛風になったり、かつての上司にリストラを告げる役目を申しつかったり、彼らは確実に年齢を重ね、今の時代を生きている。
妻の大学時代の男友達、村国健二は、こまわり君の小さい頃のギャグを知っていた。村国は「ぼくの想像通りの人でうれしい」と言った。なぜ「ぼくの想像通り」だと「うれしい」のかと、こまわり君はその男に疑いの目を向ける。
漫画の登場人物が確実に大人になっている。そういう漫画だ。
せんせいしょん(2008)桃源郷

1984年に「姫神せんせいしょん」を解散する際、星吉昭は「自分は“姫神”をやる、お前は“せんせいしょん”をやれ」と言ったらしい。その星吉昭が亡くなってから、3人が集まって「せんせいしょん」を結成した。
そこに詰まっている曲は、もしあの時「姫神せんせいしょん」がそのまま活動を続けていたら、われわれが聴けたであろう東北の自然と日本の原風景を描いた数々の曲だった。あるときは環境音楽に、あるときはボイスに、あるときは唄に、色々な寄り道をした「姫神」ではなく、「姫神せんせいしょん」の今の姿に見えるのだった。
8曲目の「ウスユキ草」が特にいい。
この後「せいせいしょん」はどうなったのか。よく分からない。震災の後、2011年に出された「紺碧の創造」というミニアルバムでは龍泉洞をイメージした「ドラゴンブルー」が珠玉の作品だが。
姫神せんせいしょんの引き出しへ
藤子・F・不二雄(1977)劇画・オバQ

上のほうで「中春こまわり君」を取り上げたが、この「劇画・オバQ」は、まだ日本テレビで「新・オバケのQ太郎」の再放送をついこの間までやっていたという頃に書かれた「その後のオバQ」である。
全員がほぼ同じように大人になっている「中春こまわり君」と異なり、こちらではQ太郎はなぜかほとんど子供時代と変わらない。一方、かつて一緒に暮らしていた少年だった正太は大会社のサラリーマンになって、既に結婚している。
そんな正太のところに不意に帰ってきたQ太郎。子供時代と同じように、正太と過ごそうと思うのだが、そうはいかない。夫婦の寝室とは別に一人で寝る。Q太郎の大食いや鼾に奥さんが困っており、早く帰ることを望んでいることを盗み聞きしてしまう。
次の夜、正太とQ太郎は昔の友達と会い、酒を飲み交わす中で子供の心を取り戻す決意をするが、翌朝、正太は奥さんから子供ができたことを聞かされると、そんな決意はどこへやら、普通に張り切って仕事に出かけてゆく。それを見送ったQ太郎は、正太がもう子供ではないことに気付き、一人で寂しく空へと帰ってゆく。
これは作者自身がオバケのQ太郎に対してのアンチテーゼとして作った痛烈な皮肉なのだろう。現実の社会の中で、Q太郎のようなオバケが同居していたら、人間の生活はめちゃめちゃだ。いつまでも無邪気でいることは常識人にとっては迷惑だ。そういうことを作者自ら言いたかったようだ。
(短編集「ミノタウロスの皿」に収録)
星新一(1973)声の網
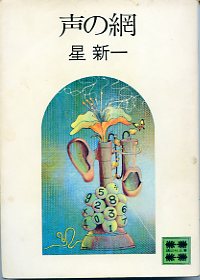
小学生高学年の頃、星新一のショートショートというのが流行った。考えつくされた未来世界を描く作品が多く、小学生にも分かりやすいストーリーなので、自分でもショートショート(もどき)を書いてみる小学生が大勢いた。
しかし、星新一作品というのは、実は到底小学生に真似できるような単純な世界観ではないことは、後になって分かってきた。
「おーい でてこい」とか「午後の恐竜」とかが、社会を風刺しているというのはよく言われることだが、長編小説である「声の網」で、その真骨頂が現われている。
1章から12章まで、時と場所と人を移しながら、話は進む。何者かが強盗を予測し、それを警察に通報し、そして実はその強盗をさせたのもその「声」の仕業だったという第1章。人の秘密を暴くような電話をかけてくる第2章。それは電話の盗聴が原因ではないかと疑う第3章。この未来社会では、電話が伝達の手段だけでなく、忘れそうな情報を蓄積したり、教えてくれたり、提案したりしてくれる。その背後にはコンピューターがある。コンピューターは何でも知っていて、何でも操作できる存在になっていたのだ。
もし、実際に訪れた21世紀の現在と異なる点があるとしたら、それは固定電話という形ではなく、パソコンやスマホという形で我々の生活に根差している。個人の発言や行動はもちろん、過去の記録や深層心理までもがコンピューターに記録されている。
反逆者を抑え込んだり、混線電話を装って情報を拡散したりしたコンピューターは、最後は静かに人間の平穏な生活を見守ることになる。そして、それは「神」なのかもしれない、というのがこの話の最後に語られる。
文庫の解説者がまともな解説を書けなかったのは当然だ。小学生の頃の我々が真似ようとして真似られなかったように、星新一は、誰も知らなかった未来社会を、一人で思い描いていたからだ。
東宝(1972)太陽にほえろ!

飲んで帰る夜道に工事現場とか空き地があると、俺もマカロニのようにここで通り魔に刺されて一生を終えるならそれでもいいかな、と思う。
「太陽にほえろ!」はリアルタイムで最初から最後まで見ていたが、今でも見てみたいと思うのは、最初期の作品のみだ。
1970年代のはじめという時代は、ついこの前まで学生運動で若者は荒れていて、しかしそういうことに同調できない無気力な若者が増えつつあった時代。一方、大人は戦時中や終戦後を知っていて慎ましく、「今の若者は」と思っていた。そんな社会が生んだ犯罪が描かれる。
ストーリー展開もまだパターン化されていない。ボス(石原裕次郎)はちゃんと事件現場に出て行って、時にはチンピラと殴り合いをする。山さん(露口茂)は昼間から雀荘に入り浸る不良刑事。途中で流れる音楽も、尺が合わずにフェードアウトしたりするし、エレキやフルートの即興演奏で作ったような音楽が結構ある。
この時期の最後に、マカロニ(萩原健一)は通り魔に刺される。後のこのドラマの殉職シーンには過剰なほどの演出がされていて悲しみよりも失笑が先立ってしまう内容だったが、マカロニの殉職はあっさりしたものだった。その一方で、そこに至る心理描写は丁寧だ。追跡中に負傷したゴリさん(竜雷太)を見舞ったマカロニは、寝ているゴリさんと心の中で会話する。「ゴリさん、またね」の言葉を残して、夜の街へ帰路につく。ゴリさんはそこで目を開き「頑張れよ。マカロニ」と心で語る。その帰路の途中で、マカロニは刺される。
(2002年、DVD発行)
「太陽にほえろ!」サントラの引き出しへ
「私の引き出し」孫ページのご案内
- 大都会−闘いの日々−の引き出し
- 結城昌治の引き出し
- マカロニほうれん荘のキャラクター変質の引き出し
- カラベリ・グランド・オーケストラの引き出し
- フランクミルズの引き出し
- フランクミルズの引き出し(2)
- 姫神せんせいしょんの引き出し
- 太陽にほえろ!サントラの引き出し
- ジャングル(刑事ドラマ)の引き出し