岩波講座宗教3 宗教史の可能性、編集委員、池上良正、小田淑子、島薗進、末木文美士、関一敏、鶴岡賀雄、岩波書店、2004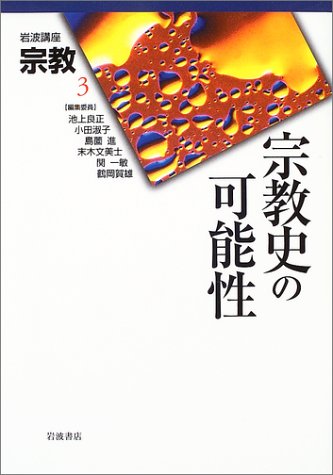
新聞や雑誌でみかける宗教についての議論は、どれも、ある宗教を擁護したり非難したり、中立的でもないし、普遍的な問題意識にも欠けているように感じる。マス・メディアで知られた学者でさえ、そういう傾向がある。もしくはそういう刺激的な発言をする人がメディアでもてはやされるのかもしれない。もう少し、冷静な考察はないか、期待しながら、新しい講座本を読んでみることにした。 普遍的な問題意識をもって個別の対象にあたるという姿勢が、期待通り全体を貫いている。何々教という存在はもとより、宗教という概念さえも、無前提にはされていない。むしろ、「宗教なるもの」や何々教という社会的に通じる概念が生み出される社会的な背景、歴史的な文脈に各論者は焦点をあてている。 これまで自分のなかでは、宗教とは、教義、教団、教会といった制度を備えたもの、信念とは、超越的なものへの内面的な、ただし素朴な関わり、そして信仰とは、信念に加え、死生観や世界観、宇宙観、歴史観などを配した総合的な観念のあり方、と考えてきた。 信念という言葉は、思想史では時代精神と呼ばれるものに近い。宗教学では心性といわれているらしい。現在の宗教社会学の研究成果をみると、これら三つの関連がどのように歴史的に変遷してきたか、どのように地域、社会によって異なるか、を問題の中心にすえているようにみえる。 総論は何となくわかった気になれないこともないけれど、専門用語があふれる各論はどれも難しい。難しいながらも面白く読んだのは、遠藤潤「『神道』からみた近世と近代」。遠藤は、最近読んだ井上章一『日本人とキリスト教』(講談社現代新書、2001)とは反対の位置から日本の宗教をみる。 井上は、西洋に発したキリスト教がどのように日本社会に受容されたか、信仰とは異なる、制度や制度を支える精神の受容の仕方を検証する。遠藤の場合は、日本固有といわれる神道が、どのようにして素朴で多様なあり方をもっていた心性から社会制度、宗教集団へと変遷したかの過程をみる。もっとも、一般読者を対象に書かれた新書とは異なり、講座本とはいえ本格的な研究。予備知識をもたない私には、全体の論旨を把握するのが精一杯。 私が読み取ったところ、江戸以前の神道は、宗教、心性、信仰の位相は明確に区切られてはおらず、またそれぞれに多様だった、と遠藤は見ている。つまり、神道という宗教の中にさまざまな宗派があるという横の関係も、聖職者、教団、信徒という縦の関係も一元的には存在していなかった。 複雑なのは、明治初期に神道は宗教化しながら、政治化した点。その過程でさまざまな教義を拡充して信仰として確立する一方、制度、集団という宗教の側面も強化されていった。しかもそのいずれの動きも、国家からの上からの関わりをともなっていた。そのため、宗教ではない、つまり国民精神の一部という面と、仏教やキリスト教と並列される表面的に自由になった信仰の一種類という面との矛盾を抱え込まされた。 この矛盾は、信仰としての神道にとっては不幸にちがいない。そして現在も、その矛盾と不幸は続いている。8月のたびに政治的にしか脚光を浴びない靖国神社は、象徴的な例。知らない人には、ときの首相が行ったり行かなかったりする場所でしかない。そこは、ある人々にとっては信仰を深める場所であるかもしれないのに。 すべての宗教が普遍的なものを目指しているわけではない。しかし、宗教は人間の内面にある超越的なものへの指向性にはじまるとすれば、その思いは無限に広がる可能性をもっているはず。ところが、教義、教団などの宗教的な制度や、国家のような政治的な制度は、そうした無限に広がろうとする思いをある枠へと閉じ込めようとする。 枠に当てはめてしまうことは、過去の宗教の実態を誤解するだけではない。現在の宗教の広がりも妨害することにもなる。日本とは何か、神道とは何かを問わないまま、つまり、それぞれが内包する多様性を無視して「日本古来の神道」と言えば、人々がもつ多様な心性や信仰を、後からできた枠で囲い込むことになる。 こういうことが起きているのは神道だけではない。イスラームはアラブ固有の宗教であり、西洋文明とは必ず敵対する、という思い込みは、イスラームの外側だけでなく、内側にいる人々をも抑圧しているに違いない。 抑圧の原動力は、たいてい宗教や信仰の内在的な原理よりも、政治的な力学や金銭的な欲望。要するに、普遍的な精神へ個別的な行動や表現を通じて向かおうとしても、現実には、普遍的な方法で個別的な試みが抑えつけられている。 個別的な方法で表現されたものを通じて、普遍的なものへいかにして通じるか、ここに人が作品に触れる批評、人と人とが触れ合うコミュニケーションの意味がある。ただし、問題はここで終わらない。日本とは何かを問わずに、日本古来の精神が理解できないように、普遍的といっても何において「あまねく」なのかを考えなければ、その意味は同じように単なる掛け声か、別の抑圧装置にしかならない。 この問題は簡単ではない。普遍的とは、どこにとって普遍なのか。今の世界にとってか、それとも過去や未来を含むのか、動物や植物はどうか。問題は深く、広くなり、とてもすぐには答えられそうにない。 ともかくまじめな学者たちは、「日本の宗教は神道」とか「日本人には仏教の遺伝子がある」などと、大雑把で横暴なことは何も言っていないことは、本書を読んではっきりわかった。 事件は現場で起きている、ということは学問にもあてはまる。新聞に出ているインタビューだけでは、学問の現在はわからない。現場の研究者の地道な成果は、それでもこうして、講座本で素人も垣間見ることができる。 |
碧岡烏兎 |