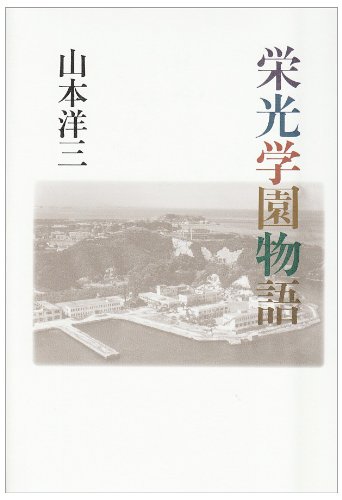栄光学園といえば、神奈川県だけではなく全国的にも名前の知られた進学校。私立学校のなかの様子は関係者以外にはあまり知られない。この学校のように、一学年四学級という小所帯を開校以来維持していればなおさら。だから、たいてい名前だけで勝手な想像をしている。
同じ神奈川県出身でありながら、個人的な知り合いもいないため、本書に書かれた学校の歴史や様子は、ほとんど何も知らなかった。最初に書かれている、栄光学園が戦後できたという事実からして知らなかった。
栄光学園は、日本海軍の基地跡を戦後復興と平和の基地にしようと考えたカトリックの米軍将校たちがイエズス会にはたらきかけてできた学校という。戦争に勝つだけでなく勝ったあとの敗戦国の教育を考える、その教育を自らの信仰する宗教を布教する修道会に要請する、そして34歳の若い神父に実現を委ねる、そのいずれにも単純な想像や説明ではすまされない物語を感じさせる。
実際、山本が叙述するのは私立学校の歴史だけではない。一つの学校を生み、育ててきた人々の物語。多くのエピソードから見えてくるのは、学校とは、人と人とが触れ合い、物語を作り出す場所ということ。
鷲田清一は『「聴く」ことの力』のあとがきで、学校ではわかりきった知識を伝えるのではなく、わからない真理を探す力を育てなければならない、そのためには教員がわかっている知識を生徒に問いただすような言葉づかいや態度をやめなければならない、と鷲田は書いていた。これを読んだとき、理念としてはそうかもしれないけれども、実際問題としてそうできるものだろうか、ではその折り合いはどうつくのか、疑問が残った。
教育とは本来、理不尽な権力ではないだろうか。どの子どもにも育つ力があるとしても、それが伸びてくるまでずっと待っているわけにもいかない。限られた時間と空間のなかで、すでにできあがっている社会で生きるための知識や作法を伝授しなければならない。とりわけ、初等教育においては、放任と強制は永遠のジレンマと言える。
栄光学園でも、34歳で学園長を引き受けたフォス神父は、熱心であると同時にかなり強引なところもあったらしい。彼がはじめた行事や習慣のなかにも、生徒たちには理不尽にしかみえないものもあった。
それでも山本の回想だけでなく、巻末に添えられた養老孟司ら初期の卒業生が参加した座談会は、そうした理不尽ささえ懐かしく思い出している。それは出版のために用意された美辞麗句ばかりでもなさそう。
理不尽だったことが懐かしく思い出せるということは、確かにある。不合理なことが単なる苦々しい記憶でいるか、思い出になるかは、どこで決まるのか。
それは、人間が人間として人間に向き合うこと、ではないか。教育を施す側が相手を処理すべき材料とみたり、管理統制すべき対象としかみないのであれば、どれほど上辺を飾っていても記憶には残らない。まして暴力的な不条理は、苦痛をともなう記憶としてしか残らないだろう。
このことは学校に限らない。会社でも家庭でも、人間が人間として扱われなければ、理不尽な扱いは永遠に思い出に変わることはない。では、人間が人間として人間に向き合うとは、どういうことか。「どんな状況の中でも、栄光学園の教育に携わってきた人々は『本当の教育とは何か』という問を忘れたことは一度もない」と、山本は書いている。問い続け、試し続けることが、教育する側とされる側が人間として向き合う学校の伝統をつくる。そこに物語が生まれるのだろう。
ところで、本書の後半は山本自身の高校時代の回想記となっている。書かれた内容の多くはすでにネット上でも公開されている。過去に書かれた文章と本になった文章とを読み比べてみると、二つのことに気づく。
一つは、内容の簡潔さ、あるいは圧縮度。これまで書かれた多くのエピソードが織り込まれている分、それぞれのエピソードは簡潔にまとめられ、場合によってはたった一行になっているものもある。しばらく前に読んだビル・ローバック『人生の物語を書きたいあなたへ』では、たくさん書いて、それでも作品として仕上げるためには思い切って分量を半分にするくらいの気持ちが必要と書かれていた。
山本も、おそらく、これまで書いた文章を大胆に削らなければならなかっただろう。とはいえ、削ったり、圧縮されたりした部分は、不必要な部分というわけではない。たった一行になっているということは、その一行に以前書いたときの思いが凝縮されているということでもある。本書のように、いわば草稿から読むことができると、文章のリズムや厚みがどのように作られるかがわかる。文章の現場に居合わせたような感じがする。
もう一つ、気づいたことは文体の変化。山本は学生時代、森有正の思想に傾倒していたという。確かに学生時代に書かれた文章には森の影響がみられ、少し堅苦しいところもある。現在の文体は、肩の力の抜けていてユーモアも豊富。同じエピソードも、書かれる文体によって、受け止め方もだいぶ違う。
硬い文章が悪いわけではない。人によっては、軽い文章から硬い文章に移っていくことが成長となる場合もあるだろう。山本の場合は、洒脱な文章によって、回想が当時の生々しい文章よりもかえって明瞭に伝わってくる。
若い中学生、高校生と長年向き合っているからかもしれない。年齢を重ねて、高邁にみせる言葉を吐くようになる人は少なくない。そういう人がむしろ多い。年齢を重ねて、軽やかな表現を見につけることは、きっと簡単なことではない。
uto_midoriXyahoo.co.jp