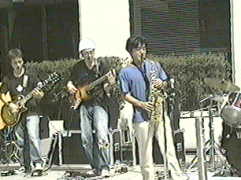|
大阪、フェスティバルホールというところで、ローザンヌ歌劇場、オペラ「カルメン」を観てきました。
今回の上演のサイト:http://www.konzerthausjapan.com/pro3.html
いや~。良かったですね。
一言で言うと、”本物”って感じでした。感動しました。どう形容してよいのかわかりませんが、本当に観に行って良かったです。
ストーリーもわかっているし、音楽もほぼ全部覚えているにも関わらず、感動できました。全幕終了したときにブラボーと叫びたくなるような、またスタンディングオペレーションを心からしたくなる気持ちがわかりました。
僕の予想では、音楽的な解釈等、演ずる方達によって様々なので、あたりはずれ(あくまで演奏レベル等ではなくて、自分の好みの問題です)があるかなと思っていたのですが、そんなことはまったくありませんでした。本当に全部聞き入っちゃいました。
チケットは春ぐらいにもう押さえていました。せっかくだから良い席でと思い、結構いい値段がする席で観ましたが、金額では計れないですね。お金では換算できない何かすばらしいものに遭遇しました。
今、サックスで、カルメン幻想曲というのをやっていますが、何か参考にしようとかそういう気もおきません(演奏するのは自分なので、なんらかの影響はあるとは思いますが・・・)。ただ単純にオペラ「カルメン」には、やっぱり、何か限りない魅力がある、ということのみ感じます。
ひとつだけちょっと思うのは、今回は2,700人が入る大きなキャパのホールだったのですが、もっと小さなホールで聞いたらどうなるんだろう、ということは思いました。贅沢言ってすみませんという気持ちですが。
本当にすばらしいこのような上演が観れて幸せです。自分がこういったものに出会えることと、この上演に尽力されている方々に、感謝ですね。
|
 音楽関係
音楽関係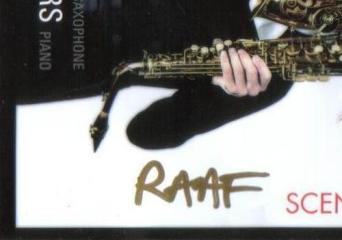

 クレッシェンドの状況です。音源はMP3にしてアップしようと考えていますが、もうしばらく時間がかかります。
クレッシェンドの状況です。音源はMP3にしてアップしようと考えていますが、もうしばらく時間がかかります。