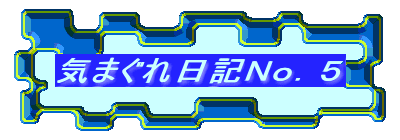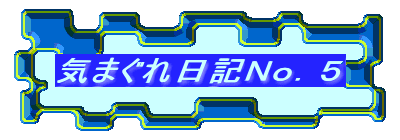�@�Q�����e�l�Ń��W�I�ԑg����Ă��܂��B�ڂ�����
�v�������f���@�������̃y�[�W�ŁB
�@�@���U���P�R��������
�u�C�܂�����L�m��.�U�v�ֈڂ�܂����B
���i�W�T�j�Q�O�O�T�N�@�@�T���R�O��
�u�ł��Ȃ����Ƃ��������낢�v
�@�Ȃ�ɂł��Â萫�Ȏ��͎Љ�l�ɂȂ��Ă���������Ȃ��ƂɔM�����܂����B���̂Ȃ��ł��X�L�[�ƃe�j�X�͂��Ȃ�ꐶ��������Ă��܂����B�ȂƂ������Ă��Ƃ��Ɖ^���_�o�̈������͎w������R�[�`�̌��������Ȃ��Ȃ����H�ł��Ȃ��̂ł����A���̂���藝�_���������{�͂悭�ǂ�ł��ď��X���ł������̃X�|�[�c�}���������悤�ł��B�����Ȃ�̉��߂ŗ��K�ۑ������ČJ��Ԃ��J��Ԃ��g�̂Ɋo�������Ă䂭�Ƃ��������ł����B��X������Ă���A�}�`���A���x���̃e�j�X�ł́A�̗͂Ǝ��Ԃ��g���Đ��������K�������҂��m���ɏ�肭�Ȃ�܂��̂ŁA���������̒��̂��Ȃ�̎��Ԃ��e�j�X�ɔ�₵�Ă����킯�ł��B���Ƃ����Ă����܂ŏ��X���������Ă����X�|�[�c�̕���ŔF�߂Ă��炤�Ƃ������Ƃɂ͊i�ʂ̉���������܂��B
�@3�O�˂���ɂ͈ꎞ�A�p��b�ɋÂ�������������܂������A������w�Z���セ�����ӂłȂ������p��𗬒��ɂ���ׂ��Ă݂����Ƃ������ƂŁA�����Ƃ��Ă͂��Ȃ肫�т����p��w�Z�֒ʂ��Ă��܂����B�N���X�͊w�����܂ߎႢ�l��������ŁA���T���y�[�W�ɂ��킽�钷�����ۈËL�������Ă��܂����B�Ō�ɂ͎����P��Ȃǂ��o���������āA���ꂱ���������p��Ђ��̐����ł����B�p�����Ƃ�����A�ꋉ��ڎw���Ă݂��̂ł����A�ƈꋉ�ɂ͑����ȃ��x�����������āA�ƂĂ��ʂ肻���ɂȂ��f�O�B���Ƃł�������l���Ă݂�ƁA���̂悤�ɂ��Ƃ��Ɠ��{��̉���Ȏ҂��p�ꂾ����肭����ׂ��Ȃ�Ă��Ƃ͂��肦�Ȃ��̂ł��B
�@�ŋ߁A�����N�̃J���`���[�X�N�[�����嗬�s�ł����A�݂�ȍ��܂Ŏ������ł��Ȃ��������Ƃɖ����������Ă���Ă݂�悤�ł��B�Ⴂ���ɂł��Ȃ��������Ƃ������ɍ˔\�̂Ȃ��悤�Ȃ��ƂɌ��\�������Ђ������̂ł��B
�@���̉��y�̎d�����A���Ƃ��Ƒ債���˔\���Ȃ��������炨�����낭�Ĉꐶ��������Ă���ꂽ�̂�������܂���B
���i�W�S�j�Q�O�O�T�N�@�@�T���Q�R��
�u�Ӓ����A�T�c�L�����J�v
�@�܂����N����������̌Ӓ������炫�܂����B�Ƃ����Ă��������b�����Ă���킯�ł͂Ȃ��A�Ȃ����Ă���̂ł����A���ԂɌӒ������炫�ւ��Ă���ƖL���ȋC���ɂȂ�܂��B��N�̋C�܂�����L������ƂT���̏��߂ɂ͍炫������Ă����悤�ł����A���N�͋��N���C�����Ⴂ�悤�ŏ����x���悤�ł��B��N�͉Ԍs���O�\�{���炢�A���N�͓�\���{�Ŏ�����Ă��܂����A�܂��炢�Ă��Ȃ��̂���������܂��̂ł��ꂩ��܂��܂��y���߂܂��B�������Ȃ��̂ɁA�����������Ă��鋏�Ԃł��ꂾ���炩����͉̂䂪�Ƃ��炢�ŁA�݂�Ȃɕs�v�c�����Ă��܂��B
�@�@�@



�@�Ƃ̊_���̐Ί_�̂Ƃ���̃T�c�L�����N�͂�������Ԃ����Ă���܂����B�����H�Ɏ}�t���ۂ��萮���Ă����̂ł����A�u�W�����ɂ͗��N�̉ԉ肪���̂ŏH�Ɏ}�肷��Ɖԉ�����Ă��܂���v�ƒ��ӂ���A�H���ɂ͐�Ȃ��悤�ɂ����̂��悩�����悤�ŁA���܂łł�����Ԃ����Ă��܂��B
�@���j���ɂ͔N�ɉ��������Ă��鏬�w�Z�̃N���X�����P�T���قǏW�܂�܂������A�����N�ސE��N���A���N�Ƃ����悤�Șb�肪�����Ȃ�܂��B���N�͊җ�̍ł��̂Ŋw�N�S�̂̓����������Ƃ��E�E�E�B
���i�W�R�j�Q�O�O�T�N�@�@�T���P�U��
�u���Ȃ��A��v
�@��������̂��v�w�ɗU���Ď����v�w���v���U��ɗ��R�֍s���܂����B�ό��ł����ł��Ȃ��A�ړI�́u�A��v�̂��Ȃ���H�ׂ邽�߂ł��B�u�A��v�̂���l�����̓X�ɂ͎��X�����Ă���̂ł����A�����g�͗��R�̂��X�ɍs���̂͏��߂Ăł����B�������炭�͖{�i�I�Ȃ��Ȃ�������ŐH�������͏��Ȃ������̂Ŋy���݂ɂ��čs���܂������A�]���ǂ���Ŗ����A���\���܂����B�����ł͂���������Ă��炵�������Ȃ��̂ŁA�����Ƃ͂����������ɐl�C�̂��X�A���x�������ł������Ċό��q���A����ŖZ�������ԑтł����B���ւ��ē����������Ĉ��݂Ȃ��炵�炭�҂������ƁA�_�炩���g�́u�������v�u���܂��v�u�����z���v�Ȃǂ̂���.�u���ȏd�v���o�Ă��܂������A���̂����̕���������̑�𒍕����Ă�����Ă����悤�ł����B�u�A��v�̂��Ȃ��́A�����Y�őf�Ă��̂��Ə����Ă���ĂяĂ��������A��`�̃^���͍]�ˎ��ォ��̓`�����p�������̂Ƃ������ƂŁA�{���ɔ��������_�炩�ȁu���Ȃ��v�����̒��Ŏ��R�ɂƂ낯�Ă��܂��܂��B���Ƃ��Ƒ�H�ƂłȂ����Ƃ��ẮA���ȏd�̑�͂������ɂ�����ƐH�߂��ł������A���̂����Ō�Ƀf�U�[�g�܂ł����������̂ŗ[�H�͔����B
�@���̔ӁA���܂��܃e���r������ƒ����ʏ����u�A��v��K��A����l���e���r�ł���ׂ��Ă����Ăт�����ł����B
�@���T�͎��̃��W�I�̎��^�A���j���͒������ꂳ��̃M�^�[�ƃt���[�g�ƃs�A�m�̃R���T�[�g�֍s���܂����B
���i�W�Q�j�Q�O�O�T�N�@�@�T���X��
��S�[���f���E�B�[�N�v
�@�����Ƃ����Ԃɂf�v���I����Ă��܂��܂����B�f�v�ł�������x�݂�����Ƃ����Ă���X���c�Ƃ̎҂ɂͤ�c�Ɠ����������Ĕ��オ����킯�ŁA���̂Ƃ���̌i�C�̏ł͂��܂���ł������܂���B�Ⴂ���͂f�v�ɃV�[�Y���Ō�̃X�L�[�֍s���Ă������̂ł����A�ŋ߂͂����߂��ŗV��ł��邱�Ƃ������ł��B
�@���N�͑�w����̗F�l���������i�ΔȂł̃o�[�׃L���[�ɗU���Ă���܂����B���c�Ƒ��Â̊Ԃ̌Ί݂ŁA�i�F���悭�A���V�C�������ōō��ł����B�F�B���Q��CD���W�J�Z�ʼn��������t�H�[�N�\���O�������ĉ̂��Ă����̂ł����A���̎Ⴂ�҂��猩��Ƥ��X�̎Ⴂ���ɂ�������������C�ё��Y�ⓡ�R��Y���Ă���悤�Ȃ��낤�Ƃ����b�ő���B
�@�܂����̂f�v�̊ԂɐV���̏�z���炽������̎R�𑗂��Ă��炢�܂����B�u�����݁v�u�^���̉�v�u�j�|�v�u�J�^�N���̉�v�u�R�V�A�v���v�u�R�E�h�v�u�A�T�c�L�v�u�R�Ԃ��v�u�t�̂Ƃ��v�̘e�A�R���A�T���ȂǂȂǁE�E�E�E�B�������R����ł��̂ŁA���ꂼ��̐H�ו�����������Ă��܂����B�V�Ղ�ɂ�����A�����Ɠ������Đ|�݂��ŐH�ׂ���A���������ɂ�����A�u�A�T�c�L�v�̓s���b�Ɛh���ł������̂܂ܖ��X�����ĐH�ׂ܂��B�ǂ���t�̍��肢���ς��Ŏ��̍�ɂ̓s�c�^���ł��B
�@�f�v�̌㔼�́A���̎R�̗����������āA�ƂŒm�l���W�܂��ĂQ���ԉ���B
���i�W�P�j�Q�O�O�T�N�@�@�T���Q��
�u����v
�@�W���M���O���Ă��Ă��X�ɐV�����t�����V���ƂĂ����ꂢ�Ȃ̂ł����A�Ƃ̒�̖X���傢�ɐL�тč���܂��B����Ƃ���������̂悤�Ȃ��������Ȃ��Ƃ����Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ł����A���̎����͂ǂ����Ă���̐��b�����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�ȑO�͐e�������Ă���Ă����̂ł����A�e�����S���ȂȂ��Ă��炱�����N�͎������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂����B�����������Ƃɂ͂܂������������Ȃ���肾�����̂ł����A�ق����Ă����ƒ��͂����}�͐L�т邵����߂ĉƂ̕\���̂悭������Ƃ��낾���ł��ƁA���悤���Ȃ�����Ă���킯�ł��B
�@����ꂪ�K�v�Ȗ͊_���̃T���S�W���V�`�W�{�ƁA�和�̗��T�C�h�ɂ��郂�~�W�ƃJ�C�d�J�C�u�L�����ł��B���̊_���̃T���S�W���Ƃ����͍�����Â��t�������V�����t���łāA�ǂ�ǂ�}���L�т܂��B�E���܂̎U�z���x���Ə����Ȗђ����V�����t��H�אs�����Ă��܂��܂��B�܂����̖ђ��͐g�̂ɕt���Ɣ��]���ł����肵�܂��̂ŁA�R�����̐V�肪�o��O����h���܂��U�z���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�}��͑S�̂̍��������킹�āA�O��ɂ͂ݏo���Ă��镔������đ����邾���Ȃ̂ł����A����Ȃ����ɂ͌��\��ςȎd���ł��B�ȑO�͍��������킹�邽�߂ɐ����ɕR����������Ă��܂���������Y�z���ɂȂ��āi����Ă��āj���͑傴���ςł��B
�@�܂����~�W�̖��ŏ��͂ǂ����Đ����炢�����̂�������Ȃ������̂ł����A�H���ɂ悻�̉Ƃ̐��������~�W�̖����ĕ����Ă��܂��B������{�̃J�C�d�J�C�u�L�͂��Ƃ��ƎU�炵�ʂƂ����X�^�C���ō��E�A�㉺�ɂۂ�����_�������Ă���悤�Ȍ`�ɐ����Ă����̂ł������͖��c�ł��B�ŏ��͐A�؉������ꂢ�Ȍ`�ɐ����Ă��ꂽ�̂ł����A�N�X������x�Ɍ`������Ă��Ă��܂��B�S�̂��Y��Ȍ`�ɐ�����͔̂��ɓ���A�ǂ̓��ł��v���͂��������̂��Ɗ��S���܂��B����̌����Ȃ��Ƃ���ɂ����{���ق����炩���̖�����܂����A�������Ƃ��̒��ɂ��鏼�̖�5�Z���`�ȏ������ђ��������ς����Ă��đ�Q�ĂŎE���U�z�B
�@����ȕ��Ɍ��悤���^���Ȃ���A����ł����N�������m�����ӂ��ċZ�p�͌��サ�Ă��Ă��܂��B
���i�W�O�j�Q�O�O�T�N�@�@�S���Q�T��
�u���Z�~�j������v
�@����A���Z�̃~�j����������܂����B���̊��ŔN�ɐ���e�������ԂŏW�܂��Ă���̂ł����A����͎���A���͂��Ƃ�蓌���������X�����W�܂�܂����B�����̐�������悢���N�ԋ߂ŁA�d���̏�ł������ȗ���̎҂����܂��B���܂��ɑ��Ƃ̖����Ńo���o���d�������Ă���ҁA��N�O�ɑސE���Ēn���ōďA�E�����ҁA���܂ł̎d���̉����œƗ����Ď��Ƃ��������ҁA��؎d��������ނ��Ă������Ǝ�̐������y����ł���Ƃ����D��Ȏ҂ȂǁE�E�E�B���ꂼ�ꎩ���̐������Ől�����������Ă��܂��B
�@�������͂��ꂼ�ꂢ�낢��Ȃ̂ł����A�݂�ȓ���I�ɃX�|�[�c�N���u�֒ʂ�����A�E�H�[�L���O��������W���M���O��������ƌ��N�̂��߂ɂ͉����ƋC�������Ă���悤�ł��B���ł��R�o��i�R�����j�̎�������Ă���҂������ȏア��̂ɂ͋����܂����B�R�̘b��ɂȂ�ƌ��\����オ���Ęb���e�݂܂��B
�@�����̏㍂�n�֍s�����ҁA���{�S���R�̂��������Z�\�ȏ��o�����҂����܂��B���钇�Ԃ͂��܂��Ɋ�o������Ă��āA���ׂ̈ɐg�̂�b���Ă��āA����Ɉ����R���R��������悤�Ȃ���̂����܂��B����W�܂������Ԃ̂����ł�����ȂɎR�D���̎҂�����̂ł�����A�ẴA���v�X�̎R�������卬�G����̂������̂Ȃ����Ƃ̂悤�ł��B�݂�Ȃ̎R�̘b���Ɏh������Ď������N�͐���A�k�A���v�X�֍s���Ă݂����̂ł����͂����Ď��Ԃ�����ł��傤���B
�@�����m�点�F���T���S���R�O���i�y�j�̐[��Q���́A�����̂e�l�ԑg�������ł��B
���i�V�X�j�Q�O�O�T�N�@�@�S���P�W��
�u�����哰�v
�@�������낻��X�̒��̍��͏I�肻���ł����A�܂��܂��Ԃɂ��Ă����ȏ������낤�낵�Ă��܂��܂��B��T�͎R�Ȃ̔����哰�֍s���Ă݂܂����B�R�ȉw����̋������H�͉Ԍ��q�ň��Ă��āA�l���݂������킯�ԂŒʂ��čs���̂��C���Ђ��܂��B�r���̑a�������̓����A���i�͐Â��Ȕ����哰���l�ƍ��Ŗ��J�ł��B�����哰�̎}������͉��N���O�̂i�q�̂b�l�u�������I���s�֍s�����v�ȂǂłƂ肠�����Ă���悯���ɗL���ɂȂ��ĖK���l���������悤�ł��B���̔����哰����啶���R�ւ̃n�C�L���O�R�[�X������܂����A�����o��̎R��������čŌ�ɑ�̎��̉Ώ��ɒ����ēW�]���J�������͊������̂ł��B�a���������܂߂Ă܂�������肱�̂����������Ă݂������̂ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����哰�̎}�����
���i�V�W�j�Q�O�O�T�N�@�@�S���P�P��
�u�ύ����C�u�v
�@�X���ɋ��s��q�̖����������̂����̊ύ���Ţ���q�݂��U�@���C�u�v�������Ē����܂����B��b�R���،i�ɂ�������ł̉��O���C�u�ł����������̑u�₩�Ȃ��V�C�B���ꂾ���Ŋύ���Ƃ��Ă͔����ȏ�͐��������悤�Ȃ��̂ł��B����~�Ȃǂ̉Ԃ����ł��A�������̉�A�g�t���≮�O�ł̃X�|�[�c�C�x���g�A�n�C�L���O�A�o�[�׃L���[�̉�Ȃǂ͐���Ă��邾���Ŕ����͐����ł��B�傫�ȃC�x���g�͂��Ȃ葁��������������߂Ă�����킯�ŁA�Ȃ��Ȃ��C��̏����Ƀs�^���ƍ��킹��͓̂�����̂ł��B���̓��͋��s�������疞�J�ł������A�����̎}��������ߑO���ɒ��������͂Q�A�R���炫�ł�����Ƒ����������ȂƂ��������ł������A�������߂��郉�C�u�̍��ɂ�5�A�U���炫�ɂȂ邭�炢�܂ō炢�Ă��Ă����b�����z�b�ƈꑧ�ł��B
�@�����͓X�̂ق��ɂ��k�C�����珗���T�������s�̍������ɗ���ꂲ���X����܂������A���̎����ɗ��s���v�悵�ăs�b�^�����J���ɏo��邱�Ƃ͒��������Ƃł��B�H�̍g�t�̂ق������ɔ�ׂĊό��V�[�Y���������̂ł����A����ł��g�t�̂��������ɏ�肭���������킹�ė��s�̌v�������̂͂Ȃ��Ȃ���ςł��B�G�߂͋C�܂���ŁA���ɍ��̃V�[�Y���͊��Ԃ��Z����u�ŏI����Ă��܂��܂��̂ŁA��Ԃ��������ɓ��������͔��Ƀ��b�L�[�ł��B��N�Ȃǂ͂R���ō��͏I����Ă��܂��Ă��܂����킯�ł�����B���N�͖��J���T���œ��j���͗[������J���~��Ƃ��łX���A�P�O���͋��s�������Ղ�̂悤�ł��B���͂����̂ł����ǂ��֍s���̂ɂ��Ԃ̑�a�ō����Ă��܂��܂��B

�@�@�@�@�@�i�o�������獂���㗬��]�ށj
���i�V�V�j�Q�O�O�T�N�@�@�S���S��
�u���炫���v
�@���s�ł͕���_�Ђ̒��̊@���Ƃ�������ނ̍������s�ň�ԑ����炭�Ƃ������ƂŁA������T����炢�Ă���炵���̂ł����A���̐������ň�Ԑ�ɍ炭�̂͌��o�C�p�X�̓���H�𓌂ւ������Ƃ���̍��ƁA���R�����̖k���p�ɍ炭���̂ł��B
�@���o�C�p�X�̂��͓̂��R�̃g���l���̎�O�Q�O�O�����炢�̂Ƃ���̖k�����H�����ɍ炢�Ă�����̂ŁA���N�ǂ������������h�ȉԂ������Ă���܂��B���N����T�����Y��ȃs���N�F�̉ԂŖ��J��ԂɂȂ��Ă���̂ł����A�ǂ�����N�ɓ��H���ɂ͂ݏo�Ă����}��傫�����Ă��܂�ꂽ�悤�ŁA�c�O�Ȃ��獡�N�͏������Ėڗ����Ȃ����Ă��܂��܂����B���R�����̂��͍̂��������ق̕~�n���ɂ�����ł����O������悭�����܂��B�����ۂ��F�̉Ԃ�����傫�ȍ��ŁA��������łɈ�T�ԑO����Ԃ����Ă��܂��B
�@�����炱���炩�炳����J�Ԃ̃j���[�X������A���s�ł������i�S���Q���j�J�Ԑ錾����A�ό��ɗ�����l�̐��������Ȃ��Ă����悤�ł��B��T����_������̃��C�g�A�b�v���n�܂�܂������A������Ƒ��������悤�ł��B�X�̑O�̔���̍����炢�Ă��܂����B�X�̑O�̍��͓��R�ʂɋ߂�������炢�Ă��܂����A�������T����������ł��傤�B���N�͗�N�����s���N�F���Z���Ĕ����������܂��B�܂��Ȃ����s�������J�ł��B
���i�V�U�j�Q�O�O�T�N�@�@�R���Q�W��
�u�܁v
�@�v���U��ɉE��̐l�����w�̒܂������Ă��܂��܂����B���͂����ƃK�b�g�M�^�[���g���Ẳ��t�ŁA�������}�C�N�ʼn����Ђ������A�p�[�e�B�[�ł̓G���A�R���g�����肷��̂ł����A�E��̐e�w�ɃT���s�b�N���邾���ő��́A�����ɒ܂Œe���Ă��܂��B�ʏ�͂Q�o�قǐL���Ă���̂ł����A�����Ȓ����̈Ⴂ�A����Ȃǂɂ���Ēe���ɂ��������肵�܂��B�N���V�b�N�̃M�^�[���X�g�Ȃǂ͂����Ɛ_�o���Œ��J�ɐ�����A���X���Ŗ����āA�ŏI�͔��ɍׂ����T���h�y�[�p�[���g���Đ����܂��B�܂��p�x���v���C���[���ƂɍD�݂������āA���ꂼ��ɂ����Ȑ�������Ă��܂��B�܂̃J�b�g�̗ǂ����������t�̏o���ɂ��傫���e�����Ă��܂��B�܂��A���Ƃ��ƒ܂̎����ア�l�͉��t��O�Ƀ}�j���L���A��h�����肵�ĕ⋭�����Ă��܂��B�w�̒܂������܂Ƃ��[�܂Ƃ��Ő������̗ǂ��Ȃ��l�̓N���V�b�N�M�^�[�̃v���C���[�Ƃ��Ă̓n���f�C�[�ɂȂ�ł��傤�B
�@���͎w�ɒ܂�L���Ă���W�ŁA�������ۂ��肾�Ƃ����邱�Ƃ�����܂��B�ł�����̐����ł͈�ʂ̐l�Ɖ��炩���Ȃ��킯�ŁA�X�|�[�c�ł��e�j�X�Ƃ��X�L�[�Ƃ��S���t�Ƃ������Ă����킯�ł����A�{�[�����O�����̓{�[���̌��ɒ܂����������Ċ����Ă��܂������Ƃ������Ă���ȍ~���܂���B
�@���������ӎ��̂����ɑ����͒܂ɋC�����Ă���̂ł����A���܂ɂ͕s���ӂłЂ������Ċ���邱�Ƃ�����܂��B�܂ɂЂт��������ꍇ���Ȃ�ׂ��d����A�傫���͐肽���Ȃ��̂ł����A������Ђ����߂ɐ��ĉ��t���Ă���ƁA���̏����Ȋ���ڂ��傫���Ȃ��Ă����Č��ǂЂǂ����ɂȂ��Ă��܂��܂��B�ŏ��Ɏv�����Ċ���ڂ�菭�����߂ɐ�悤�ɂ��Ă��܂��B
�@���i�͒܂��悭�L�тĎ������ʓ|�������Ǝv���̂ł����A��������Z�����Ă��܂��ƂȂ��Ȃ��L�тȂ��Ɗ�������̂ł��B����Ȏ��ɉ��t�̎d���Ȃǂ�����ƍ���̂ł����A��������傤�ǃ��C�u�̒J�Ԃł悩�����ł��B
���i�V�T�j�Q�O�O�T�N�@�@�R���Q�P��
�u�e�l���W�I�ԑg�v
�@�o�^�o�^���Ă��ď������s�\���ȏ�Ԃő�Q��ڂ̃��W�I�ԑg�̘^�������܂����B�������̂őO��̘^����������ꌎ�����Ă��܂����킯�ł��B�Q���͓��������Ȃ��̂ł悯���ɑ��������܂��B���Ƃ��Ƃ���ׂ�̂͋��Ŕԑg�g�[�N�����Ƃŕ����Ɣ��Ȃ��鎖����Œp��������������ł��B�ȂƓ�l�ł���ׂ��Ă���̂ł����A�قƂ�NjȂ̏��ԈȊO�͑ł����킹�̂Ȃ��t���[�g�[�N�ł��B�Ȃ͂��Ƃ��ƃA�i�E���T�[�u�]���������Ƃ������ăX���[�X�Ɍ��t���łĂ���悤�ł����A���̓{�L���u�����[�s���ł܂��Ă͎��s����ł��B�ԑg������悤�ɂȂ��Ă���́A�e���r��W�I�̃g�[�N�ԑg���S�������ĕ����̂ł����A�A�i�E���T�[�͂Ƃ������^�����g�������݂�Ȃ�����ׂ�͒B�҂ŁA�������猩��Ƃ݂�ȓV�˂��Ɗ��S���Ă��܂��B
�@����A���q�݂��U�̋ȈȊO�Ɏ����̃I���W�i������P�ȂƁA���������t�H�[�N�\���O����P�ȉ̂��Ă��܂��B����́u�p�b�`�M�v�Ƃ����f��������ゾ�����̂ŁA���̒��̑}���̂���u�C���W���́v���̂��܂����B�Q��ڂ��Â��t�H�[�N�ł������w�Z�̓���������������Ă��܂����u�V���[�x���c�v�Ƃ����O���[�v�̑�q�b�g�ȁu���v���̂��Ă��܂��B�̂�����i�}���o�ł��̂ŏo���̗ǂ������͕ʂƂ��Ę^���̎����قƂ�Lj��A�ꔭ�^���ł��܂��Ă��܂��B
�@�O��Q���̕������͂Q�����܂ł݂�Ȃŋ������ň����ƃ^�N�V�[�ɏ���Ď����̔ԑg���Ȃ���A��܂������A�^�N�V�[�Ŏ����̐����Ă���̂��s�v�c�Ȋ����ł��B�������R���Q�U���i�y�j�[��Q���i�Q�U���j�`�ł����A���̒m�l�A���q�l�͂قƂ�ǐQ�Ă��鎞�ԂŁA���Ƃ���l�b�g�ŕ����Ċ��z�����������܂��B�����̂��q�l�̒��ɂ́A�����[�H�̌イ�����Q���āA���̎��Ԃɂ͋N���Ă�����Ƃ�������������悤�ł����A����ȕ��͕ʂƂ��āA�������̎��Ԃ��܂��܋N���Ă���ꂽ��悤�ł����牺��Ȃ���ׂ���Ă݂ĉ������B
�@���b�c�v���[���g
�@�ԑg�̃X�|���T�[��莄���̢���q�݂��U�@������̐��E�v�̂b�c���v���[���g����܂��B
�@�R���R�P���܂łɉ��L�́u���W�I�J�t�F�ԑg�v���[���g�W��v����ǂ����B
�@
http://radioafepresent.seesaa.net/article/2281178.html
���i�V�S�j�Q�O�O�T�N�@�@�R���P�S��
�u���v
�@�O��L�ڂ̋��Âł�ꂽ�u���v�Ƃ������͏��̌��̂��̂ł����B�̂͒n���œ�□�X�`�Ȃǂɂ�����Ă������炢�ŁA�قƂ�lj��l�̂Ȃ����������悤�ł��B���O�̗R���ࢉ��̉��̋��v�Ƃ����Ӗ����炫�Ă��āA���̏ꍇ�͊����Łu�����v�Ə����炵���B�Ƃ��낪���̂Ƃ���̃O�����u�[���Ƃ��ʼn₩�ɋr�������тĂ����킯�ŁA�ŋ߂͍ō��ɂ��܂����������Ƃ����Ӗ��Łu�����v�Ƃ���ꍇ�����邻���ł��B���[�R�O�O���ȏ�̗�C����ɐ�������̂Œ�����Ԃŕߊl���܂����A���Ђꂪ�Ȃ�����������ޕ��̋C�����̈������ł��B�܂��O��̓[���`����Ő��������������ɂ���Ɣ��Ă�����ׂ��̂悤�ɂȂ�̂ł����A��������\���������炵���B�Ă��ĐH�ׂ鎞�͏Ă������Ȃ��悤�ɒ��ӁB�Ă�������Ƃ���łȂ��Ă����Ȃ��g�����ł��ɂȂ��ĐH�ׂ�Ƃ��낪�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��悤�ł��B�����͂Ă�Ղ�ł��������܂������A���g�̂������肵���g�ł܂��̓[���`�����̏_�炩���ɂ��ɂ�銴�ō��܂ŐH�ׂ��܂��B���܂��`�Ȃǂɓ����Ƃ����̂悤�Ȋ����̋��ɂȂ�炵���B�~�̕x�R�֍s����܂����琥�ܖ����B
�@�S�����ȉ��y�A���Ƃ����쎌�ƁA��ȉƂ̒c�̂���W�����ȃR���e�X�g�Ŏ��́u�C���]����v�Ƃ����Ȃ��O�����v���ɑI��܂����B��N�A���É��̌䉒���ōs��ꂽ�J���I�P�S�����̗D���҂ɒ���܂��B�ȑO�ɂ����̂悤�ȑ��Ŏ��̍�i���I�ꂽ���͂���̂ł����A�Ȃ��Ȃ��q�b�g�ȂɂȂ�͓̂���ł��B
���i�V�R�j�Q�O�O�T�N�@�@�R���V��
�u�x�R���C�u�v
�@��T�A���ׂ��������Ȃ��܂ܕx�R�֏o�����邱�ƂɂȂ�܂����B�������X�͓���ԗՎ��x�Ƃł��B�x�R�Ƃ����Ă��x�R�̖k�̒[�Ńg���l�����z����Ƃ����V�����̐e�s�m�ł��B��̑������̎����ɖk���n���փ��C�u�ōs�����Ƃ͂܂��Ȃ��̂ł����A��������̂��b���ł����̂ŏ[���Ɋo������߂Ă��܂����B�͂��߂͓��R���̓��ׂ̈ɃX�m�[�^�C�����w��������肾�����̂ł����A���q���S��̎Ԃ�݂��Ă�����Ƃ��A�X�^�b�h���X�^�C����݂��Ă�����Ƃ��A�����Șb�����������Ĉ��S���Ă����Ƃ��뒼�O�ɂȂ��Ă��ׂă_���ɂȂ��Ă��܂��܂����B�^�C���͂�����Ƃ̂��ƂŃT�C�Y������Ȃ������肷��悤�ł��B���܂��܋C������������Ȃ������Ȃ̂ōŐV�̃`�F�[�������w�����āA���ԓI�ɏ\���ȗ]�T�����ăm�[�}���̃^�C���ŋ��s���邱�Ƃɂ��܂����B����ځA�S����͂Ȃ������ɋ��Ó����B��N�\���Ƀ��C�u�������Ē����������֊���ē����̃z�e�����Ƃ��Ē������Ƃ���̂ł����A�����Ȃ̂ɋ��Ẫz�e���͖����ł��B�����d�q�n�̍H�ꂪ���Âɂł���Ƃ��ŘA����������̐l�����܂��Ă�����悤�ł��B���Ǘׂ̍����̉w�O�̃z�e�����Ƃ��Ă��������Ė�A��������i�q�ɏ���ċ��Âň�t���邱�ƂɂȂ�܂����B���������Âɂ����Ƃ̍H�ꂪ��������ł���ȕӂ҂ȏ��ɂ��Ă͓s��̃r�W�l�X�}���ň��Ă���͈̂ȊO�Ȋ��������܂����B���Âł͒��x�{�̐��ق��邢���A�J���n�M�A�u���A���̃X�e�[�L�A�܂��x�R�ł����H�ׂ��Ȃ��Q���Q�Ƃ������̂Ă�Ղ�Ȃǂ��Ղ��Ċ��\���܂����i���Ƃ������ɂ��Ă͂܂�����ɂł������Ă݂����Ǝv���܂��j�B���̂��ƃN���u�A�X�i�b�N�Ȃǂɂ��ē����Ă��������ċ��Â̖�i�B���Â͂��đS���ł��w�܂�̔ɉ؊X�������炵���_���ɂ����Ă������悤�Ȃ������Ȃ��X����������܂����B�����̓��C�u�̂��߂��������Ő�グ�A�^�N�V�[�ɂĂP�Q���O�ɍ����̃z�e���A��B
�@�����͓��P���̃��C�u���̂����ւP�O���ɓ����B�o�`�̏��������Čߌ�R���̉��t�܂őҋ@�B���ς�炸���ׂ͑S���Ƃ͌����������o�邩�ǂ��������s���ł������A���Ƃ��P�����ނ��Ƃ��Ȃ������ɃR���T�[�g�I���B���̔ӂ͏��쉷��Ƃ����鋫�̃z�e���ɔ��߂Ă��������܂����B���쉷��͌㗧�R�A���n�A�M�ւȂ��钩���x�̉��R�H�ɂ�����悤�ȏꏊ�ŁA������r�̐l�͂�������ł��k��������ʂ��Ē����x�o�R�Ŕ��n�x�ɍs����o�R���ł��B�쉈���̐�p���H�A��p�̃g���l������ƈꌬ�����Ȃ��u�z�e��������v�ɓ����B��~�钆�A�w�̘I�V���C��I�V�̊╗�C�ɓ����ĉ�������\�A���������ؔłő喞���ł����B
�@�����A�����ɂ����A�Ɋ���ċA�H�ɂ��܂������݂���ƉJ�ƕ��̒��A���̃{���̈��Ԃ������ȃy�[�X�ő����ăX���[�X�ɋA���ė���܂����B�[���U���O�Ɏ�����A�U�����ɂ͂����X�ɂłĂ��܂������A��͂���܂����B
���i�V�Q�j�Q�O�O�T�N�@�@�Q���Q�W��
�u�S��跗��v
�@�d������ɕ��ׂ��Ђ����Ƃ��ł��܂���B��������אS�̒��ӂ��Ă��Ă�����N�ȏ㕗�ׂ��Ђ��Ă��܂���ł����B�����ł����ׂ炵�������������Ƃ����ɖ������łقƂ�ǂЂ��O�ɒ����Ă��܂����B���ꂭ�炢�p�S���Ă���ƁA�����ꐶ���ׂ��Ђ����͂Ȃ����낤�Ǝv���Ă��܂����B�Ƃ��낪����x�R�ł̃��C�u�܂�10���Ƃ��������ɂȂ��čȂ��R�X�A�U�x�̔M���o�����炢�̕��ׂ��Ђ��ĐQ����ł��܂��܂����B�X�ɂ��o���Ȃ����炢�̏d�ǂł߂��炵����҂ɍs���ē_�H�����Ă��炢�܂����̂ł��̂��Ə����������ɂ͌������Ă��܂��B���͐�Ɉڂ�Ȃ��ł������Ɩ������ז������ŗ}���Ă����̂ł����A���C�u�̓��܂łS���Ƃ������j���ɂȂ��Ăǂ����g�̑S�̂����邭�A�厖������Ĉ�����Q�Ă����̂ł����A�Ȃ�ƂȂ����܂ł������{�[�b�Ƃ���̂Ŗ�ɂȂ��đ̉��𑪂��Ă݂�ƂR�X�x�������Ď������g�����R�B�Ȃ���҂������Ă����M���܂��̍�������߂Ďg���A�X�ł����܂��₵�Ă��炤�Ƒ����B�������X�[�p�[�}���A�M�͂P���Ԕ��قǂ̊Ԃɂ݂�݂鉺�����Ă䂫�܂����i�X�[�p�[�}���Ȃ畗�ׂ��Ђ��Ȃ����I�j�B�M�͉��������̂ł����A�H�~�͂Ȃ���̉��̕��ɕ��ׂ̋ۂ݂����Ȃ��̂�����悤�Ŏ��܌������P�����ށB���ƂR���ŕx�R�ł̃��C�u�֏o���A����܂łɒ����Ȃ���Α�ςł��B�̂ǃX�v���[�A�̂Lj��Ȃǂ��ʂɔ����ĂЂ�����{���ɖ��߁A�J���I�P�̃��b�X���Ȃǂ����Ȃ����̂ł����A����Ȏ��Ɍ����ēX�ł͂��ꂱ��̂����N�G�X�g����č����Ă��܂��܂��B
���i�V�P�j�Q�O�O�T�N�@�@�Q���Q�P��
��ΐؐ_�Ёv
�@�ȑO���炨�ӂ��낪�s�������Ƃ����Ă��܂����̂Őΐؐ_�Ёi�ΐ،����_�Ёj�֍s�����ƂɂȂ�܂����B�����s�������Ƃ͂Ȃ��A�ǂ��ɂ���̂����l�b�g�Œ��ׂċ��s����ߓS�œޗǂ̐��厛�܂��ōs�����Ƃɂ��܂����B�����A�d�Ԃɏ�邱�Ƃ̂͏��Ȃ��̂ŁA��芷�����ɗ�Ԃ��m���߂Ȃ���s���܂��B���ɋߓS���𗘗p���鎖�͂قƂ�ǂȂ��̂ŁA�Ƃ肠�����R�Ȃ��狞�s�w�ŋߓS�ɏ�芷���ĂƎv���Ă��܂������A�N����A��Ă��܂��̂łȂ�ׂ���芷�����֗��Ȃ悤�ɂƒ|�c�w�܂ōs�����̂͐����ŁA�����z�[���ォ��ߓS�ɏ�芷�����厛�ցA���厛�����g�s���̉����}�s�Ő���ցA��������e��ŐΐցB�ΐ̉w���牺���̎Q�����Q�O���قǕ����̂ł����A���s�̐_�ЁA���@�̎Q���̂��݂₰������Ƃ͑S���Ⴄ�Ɠ��̌Õ��ȉ��������͋C�̏��X�X�ł��B�G�݉��A�������A�m�i�X�Ȃǂ����ȓX�������Č|�\�l�����X���ꂽ�A�e���r�ŏЉ�ꂽ�Ƃ����悤�Ȑ�`���傪�������������̓X�ɓ\���Ă����āA���ł����ɋ������̂͐肢�̓X�����\�������肱�Ƃł��B�R���s���[�^�[�肢����J�^�A�h�o�C�X�A�������k�Ȃǎd��ꂽ�����u�[�X�̒��ɂ���������Ă����������Ă��܂��B�܂����X�Ɛ肢�t��W�̊Ŕ��łĂ���̂��������낢�B�����������邤���ɐΐؐ_�Ђɓ����B�����Ƒ傫�Ȑ_�Ђ�z�����Ă��܂������ȊO�Ə����Ȑ_�Ђł����B�{�a�O�ɂ͎O�\���ʂ̐l����ɃR�����������Ă��S�x�݂ŕ����Ă����܂����A�����������i�����߂Ă̂��̂ł��B���Ƃ��Ɛΐ���̓f���{�i�o�����j�̐_�l�炵���I�f�L�A�j�L�r�A���̎�ᇂȂǂł��Q��ɗ�����悤�ł��B�Ђƒʂ肨�Q�肵����A�N����A��Ă��̍⓹���܂��R�O���߂������̂͂炢�̂ŁA��������܂�����~��ĐV�ΐ؉w�֍s������֖߂��đ��֏o�ċA�邱�Ƃɂ��܂����B����������g�֏o�Ă����̂�����ƃi���o�p�[�N�X�A�i���o�V�e�B�[�ɂ�����Ă݂܂������A������ƕ������߂����悤�ł��B�����������͂��܂�C���t���Ȃ��̂ł����A�N����A��ēd�Ԃ���芷���Ă���ƁA�ӊO�ƃG���x�[�^�[�A�G�X�J���[�^�[�����Ȃ��T���ĕ����̂���ςŁA�o���A�t���[�̐����͂܂��܂��\���ł͂Ȃ��悤�ł��B
�����T���Q�U���i�y�j�[��Q���`�Q���R�O���e�l�̕������n�܂�܂��B
�@�@�@�@�@�@���R��j�E�R���́u���q�݂��U�̐��E�v
���i�V�O�j�Q�O�O�T�N�@�@�Q���P�S��
�u�������v
�@�~��ɂ͓��{���̔M�����悭�����̂ł����A�����r�[����ӓ|�̎��͂��܂ɓ��{��������ł݂�̂ł����A�����������邩�ɂ瑊�����悷����̂��A�g�̒��ւ̂܂�肪���������ɐ����Ă��܂��܂��̂Ŕ�����悤�ɂ��Ă��܂��B���̂����Ƃ����Ă͂Ȃ�ł����������֘A�̗����͉��ł���D���ł��B�ȑO�̌i�C�̗ǂ�����ɂ͖��N�A���������̂��������Ղ�̎�������Ղ��Ă��܂����̂ŗF�l�ɂ�������A�e�j�X�R�[�g�Ɏ����Ă����ĕ����ŏĂ��č����������ŐH�ׂ�������Ă��܂������C�ŋ߂͂Ȃ��Ȃ��ǎ��̎����������炤���Ƃ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B�Ƃ�킯�������ō��Î��͑�D���ō��̂��̂����f�R���������Ǝv���܂����@���ł��傤�B��Ȃǂ͕ۑ��H�Ƃ��Ă��܂ɋ��̂����Ђ��Ȃǂ�������肵�Ă��܂������A������Ă����ɉ����E���E�ɂȂ�܂����i�ʂ̖��킢������܂��B
�@�ł���͂�~��͉��Ƃ����Ă������`�ł��傤�B�����`�����X�Œ�������Ɩ{�i�I�Ȃ��͍̂��̓��Ȃǂ����Ď����������Ղ�̂��̂Ȃ̂ł����A���̓��Ȃǂ�����Ə������L���Ȃ��Ă��܂��܂��̂Ŏ��͂��܂�Ȃ��߂܂���B�܂��K�x�Ƀ~�\���������Ă�����̂̕��������H�ׂ₷���ł��B���Ƃ��Ɖ䂪�Ƃł͕�e������̖��X�`�ɂ�������������ꂽ�肵�Ă��Ă����炢�ŁA�������ɂ͎q���̂��납��e����ł��܂������A���܂苛�͓��ꂽ���Ƃ��Ȃ������悤�Ɏv���܂��B���̍Ȃ������������܂肩���`���D���łȂ��A���̃��N�G�X�g�ō�鎞�́A�ŏ��ɓ؏`������čȂ̕����ɂƂ��Ă����āA���̕��ɂ������������č���Ă��܂������A�ƂƂ��ɖ��o���ς��Ă䂭���̂ōŋ߂͂܂�������R���Ȃ��悤�ł��B
���i�U�X�j�Q�O�O�T�N�@�@�Q���V��
�u�ߕ��v
�@�ߕ��̓��i�Q���R���j�ɕ�Ɩ�������_�Ђ̐ߕ��Ղɍs���Ƃ����̂ő����Ă��܂����B�����g�͐ߕ��Ղ̂��Q��ɂ͈�x���s�������Ƃ͂Ȃ��̂ł����A�ꂽ���͓��ʂɐM�S������킯�ł��Ȃ��̂ł������N�s���Ă��܂��B�ꂽ���͂��̂��Ɣ��₳������Ďl���a��H�ɂ����a�����ŗL���Ȗڎ��i�߂�݁j�n������ɂ��Q����������ƍ������֊��A�юs����o�R���đ�ۂ֍s���Ă��낤�낵�����A�G�ۂ���d�ԁA�o�X�����p���ŋA���Ă����炵���̂ł����A�̂��ɂ͂��Ȃ�̋�����������悤�ŋ����܂����B���̓��͌��C�������悤�ł����A�����W�U�ɂ��Ȃ낤���ƍł����炳�����ɗ����͏��X��ꂪ�łĂ����悤�ł��B�܂����C�ŕ�����Ȃɂ��ł��B�ߕ��Ղ͋��s�ł������ȏ��ōs���Ă���̂ł����A���Ƃ��Ă͗��N�ɂł�ḎR��������ֈ�x�s���Ă݂����Ǝv���Ă��܂��B���������Ȃǂ͐ߕ��ɂ����H�ׂȂ��̂ł����A���܂ɐH�ׂ�ƌ��\���������V���v���ŁA�َq�̌��_�̂悤�ȋC�����܂��B
�@���̓��A�_�����ł́u�ߕ������v�Ƃ����Č|�W����A���W����z�X�e�X����Ȃǂ����������镗�K������܂��B���Ƃ��Ƌ��s�̌Â����K�ŋ������̐ߕ��̓��ɉ������Đ_�Ђ����Q������āu�S��������������͂炤�v�̈Ӗ������邻���ł����A�̂͐ߕ��̓��ɖ���̂��߂Ɂu���Δ��i���j�v�Ƃ��������������̂��N�����Ƃ��B�������j���̊i�D��������A���j��̐l���ɂȂ�����A�j�������W����̊i�D�������肵�đ��l�ɉ����A�S����g���B�����߂ɕ��i�ƈႤ�i�D������K�킵�ł��B���͋_�����̂��V�тƂ��Ďp����Ă��Ĉ�ʂ̕��͂قƂ�Ǎs���܂��A���ɂ͂킴�킴���̓��A�u�����v�̉��������邽�߂ɉ������痈�����������悤�ł��B�[���̎��̏o�Ύ��ɂ͂����_�����Ɂu�����v�̐l�������`���z���B
�@�ߕ��̊������i�̊ۂ��Ԃ�Ƃ������K��������n�܂����̂ł��傤���H���̎q�������ɂ͂���ȏK���͂���܂���ł����B�o�����^�C���̃`���R���[�g�����َq������̐�`�w�͂Ŏn�܂��ĕ��y���܂������A�ۂ��Ԃ���A�����i������̉A�d�̂悤�ȋC�����܂��B�m���e���r�ō��N�̌b���͐��쐼�ƌ����Ă܂����̂œX�őS���ł�����Ɍ������Ċۂ��Ԃ肵�܂������A���Ƃł��낢�뒲�ׂĂ݂�ƁA���N�͓��k���Ƃ̂��ƂőS�������B�܂��ǂ����ł��������I
���i�U�W�j�Q�O�O�T�N�@�@�P���R�P��
�u�p�b�`�M�v
�@�v���U��ɉf������ɍs���܂����B�䓛�a�K�ḗu�p�b�`�M�v�Ƃ����^�C�g���̉f��ŁA���a�S�O�N��O���̋��s��ɓ����̎�҂̐t��`�������̂ł����B�G���L�M�^�[�̂f�r�u�[������t�H�[�N�N���Z�C�_�[�X����n�܂�t�H�[�N�u�[���A�x�g�i���푈����V�O�N���ۓ����ւƑ����w���^���B�ǂ����X�c��̐t���̂��̂ł����B�����ăo�b�N�ɂ͑S�҂�ʂ��ē����̌��̖��ȁu�C���W���́v������Ă��܂����B������X�c��͗ǂ��ɂ��������ɂ��b��ɂ���Ă�����ł����A�݂�Ȑ��̃x�r�[�u�[���̑��l���̒��ŁA�����A���ЁA�d��������݂��ɐ��������A�����������w�͂����Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�Ȋ��̒��ň���Ă�������ł��B����Ӗ��A���{�̍��x�o�ϐ�����S���Ă����Ƃ�������ł�����܂����A�Â�����Ƌ}���ɔ��W�A�ϗe�����V��������Ƃ̂Ȃ����ł��������悤�ȋC�����܂��B�܂��Ȃ����̐��N�̂����ɁA���̒c��̐���̂قƂ�ǂ���N���}���A�ސE���Ă䂭���ƂƂȂ�܂����A���̕n�������ォ��A���̂Ƃ���s�i�C�Ƃ͂����̂Ɣ�ׂ�ƕ����I�ɂ͖L���ȂɂȂ��������A�Љ���l�̐S���傫���ς��Ă��܂����悤�Ɏv���܂��B
�@������V���L���Ŗڂ��^���悤�ȋL�����o�Ă��܂����B���N���茧�����ێs�ŏ��U�̏��������������J�b�^�[�i�C�t�ŎE�Q����Ƃ�������������܂������A���̎��������茧�̋���ψ�������̏����w����Ώۂɢ���Ǝ��̃C���[�W�v�Ɋւ���ӎ����������܂����Ƃ���A�u���l�������Ԃ�v�Ǝv���Ă���q�������w���Ŗ�P�S���A���w�Q�N���ł�.�P�W�D�T��������Ƃ������Ƃł��B���̗��R�ɂ��Đq�˂�Ɓu�e���r��{�Ő����Ԃ�b���������Ƃ����邩��v�Ɠ����A��R�O���́u�e���r��f��Ő����Ԃ�Ƃ�����������Ƃ����邩��v�A��V���́u�Q�[���Ń��Z�b�g�ł��邩��v�Ɖ����Ƃ̂��ƁB���w�Q�N���̖�Q�������u���l�������Ԃ�v�Ǝv���Ă��邱�Ƃ͑S���̏Ռ��ŁA�u���v�ɑ���l���̌y���ɋ����܂��B�ȑO�ɂ��ƂŎ����Ă����J�u�g���V������ł��܂����̂œd�r��ւ��Ă���Ƃ����q��������Ƃ����b���������Ƃ�����܂������A���̑����ɂ��Ă̔F��������Ă��Ă��鎖�͊m���Ȃ悤�ł��B
�@��T�̓��C�I���Y�N���u�̃J���I�P���D��̂��m�Ó��B����͉��̋ȂQ�ȂŁA�k�R�������u�Г��ؕ��v�A�^���Ƃ݁u���H��v�B�u�Г��ؕ��v�͖��N���܂���I���R���ɓo��̃����O�q�b�g�Ȃł��B
���i�U�V�j�Q�O�O�T�N�@�@�P���Q�S��
�u���~�̏㍂�n�v
�@��N�̒��x������ɗF�B���㍂�n�֍s���ĎB���Ă����ʐ^�ł��B�ŋ߂͗��s��Њ��́u�~�̏㍂�n�E�H�[�L���O�c�A�[�v������悤�ŁA����Ȃɐ��ꂽ���ꂢ�Ȏʐ^����������ƑA�܂����āA�����x�~��ɍs���Ă݂����Ǝv���܂��B



�@�c�A�[�͖�ɋ��s���o���A���������ɒ����Ē��H���ď�����A�V�������犘�g���l��������Ă䂭�悤�ł��B�V�`�W�l�̃O���[�v�Ɏw��������l���Ĉēऐ��������Ă����悤�ł��B�g���l���ȊO�͉E�̎ʐ^�̂悤�ȃX�m�[�V���[�𗚂��ĕ����܂��B��N�V�������g���l���i�S���U�X�O���j���ł��āA���܂ł�蓹�����R�{�������Ē��̏Ɩ������邭�A�����ĂQ�O�����炢�Ŕ�������悤�ł��B
�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`
�@��T�͓��{�i�b�i�N��c���j�̋��s��c�i�m���D�P�U�Q�Ɓj�Ť���N�͍�ʌ������R�s�̔��i�b�̃����o�[�������X�B�݂�ȑf�G�Ȋy���������o�[�ł����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
���C�܂�����L�m���D�S���@�@�@�@�@�@
���C�܂�����L�m���D�R��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
���C�܂�����L�m���D�Q���@�@�@�@�@�@
�����܂�����L�m���D�P��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
���C�܂�����L�m��.�U���@�@�@�@�@�@�@
���g�b�v�y�[�W�֖߂�