
その 2. 
目次へ戻る
8.八畳の滝 森下雨村
吉野三郎にまだダムなど全くない頃のこと
”折角ここまで来たのだから”、と云われて十里以上の山道を
鮎溯上のどんづまり八畳の滝まで’のし’た
八畳の滝
「折角ここまできたついでじゃ、舟戸まで足をのばしなされ。舟戸のAさんところへいって、田井の久米川から聞いてきたといえば、囮の心配も、宿の世話もしてくれる。」
久米川老人にそういわれて、いささか二の足を踏む思いをしながら、まだ見ぬ山峡に心もひかれて、田井の町はずれを吉野川の右岸ぞいに、それでも元気よく踏み出したのは、もう午下りの一時ごろ。それからの四里近い上り道がえらかった。
太陽はかんかんと照りつける。額から襟元から、全身汗でぐしょぐしょになりながら、咽喉をいやす一滴の水もない上り坂を、それも眼下はるかに吉野川の奔流激湍を見下ろしながら喘ぎ喘ぎの一人旅である。リュックがだんだんと重くなり、肩の竿まで荷厄介になってくる。
半分道も来たかと思うころ、後を追ってきた一人の男と道づれになった。旅は道づれとはよくいったもの、おかげで助かったような思いであった。が、この暑さに和服姿の裾をからげ、小衣の釦もきちんとはめ、頭に古ぼけた檜笠を不恰好にのせた草鞋ばきのその男はなかなかの健脚であった。祖谷のもので、これから白滝の鉱山へ行くところだと語りあっている間にも、こっちはついおくれがちになって小走りに歩調をあわせた。
ほんとうに喘ぎ喘ぎで、もう山峡の景観も渓谷の眺めも目に映らなくなったころ、やっと舟戸の宿に飛びこんだ。午後の四時過ぎであったであろうか。日の長い絶頂ではあったが、太陽はまだ見上げるような高い山の上にあった。四里の路を三時間そこそこで突っ走ったわけだ。
思わぬ珍客を迎えたAさんは、手拭をしぼりお茶をくんでよろこんでくれたが、さて釣りの話となると、いかにも困惑した顔をして、この日照りつづきで、鮎は淵へもぐってしまい、一日やっても二、三尾がむつかしい。折角、ここまで来なさったからには、今夜はこの上の宿屋に泊って、明日、八畳の滝へのしてごらんなされ。昨日のこと、この近所の若い者が出かけていって、なかなかよい漁をしてきました。三十匁から四十匁の粒ぞろいで見事なものでございました。自分も用さえなければお伴をしたいが、折悪しく約束ごとがあって、――
その代り、これから出かけて囮だけはとって上げる、―― という。
これで「折角ここまで来たからには」の三度目である。いずこも同じ旱天渇水、新荘、仁淀の行きなれた川筋では、全然魚影見えず、かかる時こそ吉野川の激流が面白かろうと、四日間の予定ではるばると土讃線を穴内駅に下車したのは昨日の正午。
釣友M君をたずねると、このところ全然不漁、わるい時をよりによって来たものだ。でも、一尾、二尾は当るかもしれない、囮は飼ってあるからと、痩せ気味ながらピチピチした囮を一尾わけてくれた。去年、面白い漁をした吉野川橋の下も手、深淵に落ちこむ荒瀬を二時間余りも丹念にひいてみたが、コツンとも便りがない。いくら用心してかかっても荒瀬では大切な囮をいじめるばかりである。もういい加減くたくたになった囮を生簀にうつして、今度は流のゆるい上み手の柳の瀬に移動する。そこへM君が応援にきてくれて、二人で夕方近くまで長い瀬を根気よく上へ下へとひいてみたが、結局M君がやっと一尾を上げたきり。そこでM君が、「いよいよ望みなしだ。あきらめよう。が、折角、ここまで来たからには、ついでの餅だ。田井まで上って見たまえ。あすこは釣人も少いし、もっと魚も濃いだろう――、」
それが「折角ここまで」の第一声。つぎが久米川老人。Aさんで三度目というわけである。
そのAさんが、文字通り苦心惨憺でとってくれた一尾の囮を抱えて、半里ばかり上み手の本川村川崎在の和田屋に草鞋をぬいだ。山峡の旅籠とは思えない二階建ての手広い宿で、五十近い主人の親切なもてなしと、二階の便所の壁に「わが妻は三国一の――」と後の文句は忘れたが半紙いっぱいに書いて貼りつけてあったのが、愛妻家らしい主人の気心を語っているようで、ほほえましくも嬉しかった。
翌朝は四時起床、囮缶を手にまだ明けきらぬ薄暗い山道を八畳の滝を目指して急いだ。Aさんも宿の主人からも、道は左岸にそうた一本の山道、時折、川原へさしかかると道は消える。
人の足跡をさがしてはまた山道へよじ上る。滝壷まで約二里半。その間人家は一軒もない。目標は山道の左下に石工の細工場だった杉皮葺きの小舎が見える。小舎にそって下れば、淵があり、八段になった滝が上み手に見える。八畳は八段、吉野川の大鮎もさすがに八段の滝は遡上しかねて、そこが魚どめの終点となっているときかされていた。
五百メートルもいかないのに往還はきえて川原となった。夜明けの白みに、どうやら人の足跡をひらって、向うの山道へ辿りついたはいいが、深淵と激流を足下に、木の間を縫うて曲りくねるその山道が木の根岩角、一歩つまずきよろめいたら、それっきりである。用心しろ、あわてるな、―夜が明けはなれても、繰り返し繰り返し自分で自分にいって聞かしたほど、足もとが危険だった。
でも、心はせく。ただ一尾の囮が気にかかってならないのだ。この調子では、二里半の路に三時間はゆっくりかかる。かけがえのない囮が大丈夫元気でいてくれるかどうか。水をかえてやりたい。が、いくら行っても谷川がない。足の下には渦巻く奔流がどうどう音をたてているが、そこまで下りて行ける足がかりがない。缶のなかの囮をのぞく。どうやら呼吸が苦しいらしく、ぐつたりとなっている様子である。
缶をゆさぶりゆさぶり元気をつけてやりながら、ひとりでに足は木の根をとんで小走りとなる。
やっとのこと小さい谷川が目の前にあった。駆けるように近ずいて、せせらぎの石をかきわけながら缶をひたした。まだどうにか尾鰭が動いているのを見てホッと胸なでおろした気持であった。
その時、ふと便通をもよおした。人ひとり通らない山道の渓流。囮の元気回復にはできるだけ時間をかけてやりたい。ゆっくり構えて排便にかかった。ひんやりする静寂な木の間で、渓流のせせらぎを聞きながら、心ゆくまで野糞をたれる。まことに自然人の昔に還った快い気持である。が、それは一瞬にして現実の人間世界に呼びもどされた。ふいに向うから人の足音が聞えてきたのだ。
起ち上る閑はなかった。しゃがんだまま度胸をきめた。足音の主は十三、四歳の山の少年であった。少年の瞳はさすがにちょっと驚いたようであったし、またさりげない風でもあった。
驚いたのは、そこに予期しなかった人間を見たからで、うずくまっているこっちの姿に驚いたのではなかったであろう。
「どこへ行くの?」
わたしは快適な排便をつづけながら、少年の顔を見上げた。色は黒いが、眼もとの涼しい可愛いい少年であった。
「白滝まで―。」
「たれかに会いにいくの?」
「うん、父に―。」
少年は足もとめずに、そういつて向うへ消えていった。道ずれになった男も白滝の鉱山へ行くといった。あの男はおそらく働きに行くのであろうが、今の少年はなにか急ぎの用でもあってそこで働いている父に会いにいくのらしい。吉野川の渓谷でめぐりあう人達は、みな国境を越えた鉱山にかかりあいをもっている。ほかに往来の用のない山峡の道である。
後半分の道は駈足であった。杉皮葺きの小舎があった。ころげるように淵に下りた。囮缶を流にひたして、白い腹を見せた囮を見つめたまま、滝の音も眼前にひらけたひろい淵も目にいる余裕はなかった。
十分、二十分。ついに元気恢復の望みはなかった。
痛嘆胸をえぐるの思いである。午前四時起床、二里半の難行も徒労に帰した。いや、二里半の山道ではない。穴内から、森村、舟戸と三日間がかりの行程が一切徒労に帰したのだ。ああ、やんぬる哉と大きな声で、空に向いて叫びたいほどのやるせない気持であった。
「よし乗るかそるかでやってみよう。」
半死半生の囮に、重い錘をつけて万に一つをかける釣法である。セルロイド製の囮さえ試みられたことがある。十匁もの錘をつけて、あの滝壷に投げてみようと思いついた。
淵の浅場を渡って、滝よりの右岸へよじ上った。囮はたぎり立つ滝壷に投げこまれた。万に一つの僥倖を祈る切羽つまった試みだった。がこれもやはり従労でしかなかった。十匁の錘も落下する激湍の泡の中に奔弄されるだけの試みにすぎなかったのだ。
空の囮缶をおいたもとの左岸に帰って、呆然自失の幾時が過ぎた。今朝、宿を出てから忘れていた煙草の幾本かが味もなく煙となって口もとに消えていた。
心頭減却すれば、である。そのうちに是非もない諦めが、心をかすめて、心機一転とまではいかないが、目の前にひろがる八畳の滝の異様なる景観がはじめてしっかりとわたしの目をとらえた。
七つだか八つだか、はっきりと見きわめもつかぬ数段の瀑布がどうどうの音と霧雨の泡沫を立てながら、いかにも大河のどんづめらしい威容を見せて落ちている。が、その滝壷を迎える下も手の淵はどうだ。この山峡にこんなひろびろとした淵が隠れていたかと疑ぐられるほど下流へむいてひろがっている。すぐ下も手に淵へ突き出た大きな岩角があって、ひろびろとした淵の全貌は望めないが、百メートル近い川幅をして、まるで山峡の中に隠れた大古ながらの湖といった感じである。数段の飛沫を上げて落下する上み手の滝壷にくらべて、それはまたなんと静寂そのものであろう。しかも、そこにはまるで、多島海の島々のように、幾十とない大小の岩々が、思い思いの姿を浮かべて、両岸にそそり立つ山の峡間に森閑として眠るように横たわっていた。
吉野川の渓谷美は大歩危、小歩危につきるとは土讃線開通と同時にうたわれた唄い文句である。トンネルづくしの車窓から垣問見る大歩危、小歩危の眺めも満更ではないが、いかにもせせっこましい箱庭式の感じがしないでもない。そこに渓谷の美があるとはいえばそれまでだが、同じく箱庭式の渓谷美なら昨日汗だくで這いあがった森村から舟戸への途中にも、いくらも足をとめるほどの眺めはあった。が、いま眼の前に見るひろびろとした淵の景観は、その趣きがまるっきり型をやぶって、大歩危、小歩危のせせっこましさや、とげとげしさとは反対に、おうらかな落ちつきと、寛容さを見せて、そこにはなにか神秘な自然の黙示がただよっているような感じさえせられるのだ。
夢からさめた気持ちで時計を見た。九時をまわっていた。この淵へ駆けおりてから、ざっと三時間も呆然としていたのだ。
すべてを諦めて、空っぽになった缶をリュックにおさめ、とぼとぼ帰路につこうとしていた。すると、ふいに下も手の岩角の蔭から姿をあらわした素っ裸の少年の姿が日にうつった。
箱ビンと引っかけの道具を手に、獲物の鮎を腰の揮にぶらさげた十五、六才の少年であった。
「君、引っかけをもってるね。囮を一尾とってくれないか!」
わたしは救いの神にめぐりあった気持でせっかちに声をかけた。
「囮が死んで困っているんだ。たのむよ、君。」
見も知らぬ男に突然声をかけられて、少年はあきらかに面くらった面持だった。
「今日は調子がわるくて掛らないよ。」
少年は腰の獲物に目をやりながら面目なげに答えた。獲物は二尾だった。
「このへん、魚はいないかね?」
「おるよ、いっぱいおるが、調子がわるくて掛らないよ。」
少年はそういって、しずかに箱ビンを水にあてて、のぞいていたと思うと、
「おるよ、三つも四つも、そこの岩についておるよ。大きなやつが―、」
と、わたしの方に箱ビンを差しだして、のぞいてみよというのだった。箱ビンに目をあてると、なるほど、すぐ目の前の小さい岩に垢をはみながら友を通う大きな鮎がちらちら見える。
「君、あれを引っかけてくれよ。」
「小父さん、やってみ。ぼくは調子がわるいんだもん。」
わたしはたいていのことはやってみたが、玉掛けと引っ掛けだけは経験がなかった。人の好さそうな少年は頼むといわれた責任感に一層固くなったらしい。あっちへいき、こっちへもどり二時間近くもかかって、それでも背がかりの三十匁からの一尾の囮をやっとものにしてくれた。
少年の嬉しそうな歓びの顔が、わたしにはまたなく美しく映った。感謝と歓喜にわたしの心はおどるようであった。
鼻環をとおす指先がふるえた。囮がいく。綸がはる。追う気配。タッチの感触。げに五秒とはまたない一瞬であった。からみあい、もつれあう二尾の鮎の強引な引きが、五間竿の穂先を弓のようにたわめて、ゆっくりと獲物を手網に取りこむまでの刻々はいっさいこれ忘我、友釣りならではの釣三味の境地であった。
垢はぺっとりとついていたが、それにしては追いがよかった。水温の関係からであったろうか、それとも吉野川終点の大淵とあって川底いっぱいの鮎ででもあったであろうか、囮を取りかえるのも、もどかしいほど後から後からと、よくかかった。あるいは正午近く、垢食みの時が来ていたためだったかもしれない。
缶の中に大きな鮎が十尾近くもたまった時、わたしは空腹をおぼえて竿をおいた。するとその時まで、わたしから閑却されていた少年がおずおずと傍へきて、
「小父さん、ぼくに仕掛をかしておくれんか。」
と、いかにも言いにくそうにおずおずといった。
「ほう、君も囮掛けをやるのかね?」
わたしは、ちょっと意外な思いでききかえした。
「うん、やるけんど、小父さんのとは仕掛けがちがうよ。」
「そう、お安いご用だ。竿をもっておいで、仕掛けはこしらえて上げるから。」
少年が嬉しそうに背後の山路を駈け上った。弁当をつかって一服していると、少年が竿をもってもどってきた。自分で伐り立てて枝をはらっただけの、まだ青味ののこったぼくしょうな竿には、四厘柄のねり糸に寸近い横がけ用の鈎が三本バラに結えてあった。それでも鼻環だけは型は古いがどうにか間にあう代物だった。
わたしが道糸から掛鈎いっさいの仕掛けをあたえて、元気な囮を出してやると、少年はわたしの邪魔をしないようにとの心づかいであろう、岩角をまわって下も手の方へ消えていった。
午後も調子よくかかった。時ならぬ山峡の驟雨にみまわれ、頭からぐしょ濡れになっても、わたしはまだ竿をしっかりと握っていた。いつの間にか、淵の中程に近い大きな岩の上に立っていた少年が、岩をおりてこっちへ近ずいてきた時は、もうあたりは夕靄につつまれて、どこかで河鹿の鳴く声がした。滝の音に消されていたでもあろう、釣りに夢中になっていたせいでもあろう。わたしはその時初めて河鹿の声を聞いたのだった。いやに疳高い澄みきった声であった。
と同時に、わたしはハッとなった。山峡の淵に釣り暮れてしまったことに気がついたのだ。
本川の旅籠まで二里半の山道は危険そのものである。どこかこの近くに一夜の宿を乞うところはないであろうか。わたしは途方にくれて少年にたずねた。
「うちの父は、人がええから話してみな。泊めてくれるよ。」
少年は気安げに答えてくれた。網の目も盛り上るほどにふくれた缶こを川岸に半ば埋めて、わたしは少年の後から山道を上りはじめた。夕暗につつまれた傾斜の急な小径は、ともすれば足を踏みすべらすほど嶮しかった。少年の後に寄りそうようにして、五、六百メートルも這い上ると、よくも、こんなところにと思われるほど急な斜面に、仄暗いランプのともった一軒の建物があった。
狭い坪先を右手に釜屋の方へまわると、もう少年が耳うちしたと見えて、五十年輩の男が顔を出した。その顔もはっきりとは見えないほどあたりは暗かったが、がっしりしたわりと丈の高い人の好さそうな山の男だった。―
それが少年の父福島さんであった。
「よう、お出でなさった。せまくるしい家だが、さあどうぞ、― そのままでよいが、そこに水もある―。」
福島さんは竹の皮をよった鼻緒のちび下駄をつかんで、崖から落ちる筧のところまでつれていってくれた。行きとどいた親切さに、わたしは恐縮しながら、山の人の親情がうれしかった。
大きないろりをかこんで、少年のお母さんと小さい二人の弟が、もの珍しげに遠来の客を見まもっていた。そのお母さんも見るからに人の好さそうな女だった。雨にぬれたわたしの上衣を、とって脱ぐようにして、いろりの上にぶら下った自在鍵にかけてくれたりもした。いろりには榾火がもえて、大きな薬鑵の湯がたぎっていた。
ふと気がつくと、次の表の間に、小さい皿鉢ともり鉢が三つほど列んで、どうやら酒宴でもするらしい模様だった。が、事情はすぐわかった。折も折、今日はこのあたりの神祭で、いまに神官さんが見えるから、しばらく待ってほしい、ひもじゅうもあろうがと主人夫妻の口上があったからである。
白い衣をつけた、まだ若々しい神官が、提灯の灯を消して、表の間へとおったのは、それから間もなくであった。紙垂をかざった榊を中に床の間にかかった天照皇大神宮の掛軸の前にうやうやしく祝詞のりとを捧げる声がしばらくつづいて、やがて酒宴がはじまったが、小衣一枚のわたしは、神官さんの手前、しつこい遠慮をつづけとおした。まだ二軒ほどまわらなければならないといって、神官が提灯をつけて出ていくと、わたしも遠慮をしないで福島さんの盃をうけた。どぶろくの味がすきっ腹にしみ、山の料理が咽をならして胃に走った。
「佐川といえば、高知から十里近くもあるだろうに、遠いところからようお出でなさった。辺鄙な山の中で、ごらんのとおりなにもご馳走はないが、五日や十日お前さんが滞在しても、食うものには事欠きません。お口にはあうまいが去年の粟がまだ―、」
あけはなした縁側の片隅に積みかさねた叺を指して、
「少々は余っております。まあ、ゆっくりかまえて釣っておいでなされ。今日はよい漁をなされたそうで、― それに栄吉も釣らしてもろうたそうで―、」
その栄吉少年も二人の小さい弟も、いろりの薬鑵から大きな徳利をはこぶお母さんもいっしょになって、にぎやかなだんらんがつづいた。
飛びいりのわたしは年に一度の神祭に、ご馳走を頬ばり、楽しげにはしゃぐ子供たちに気兼ねをさせてはと、なるべく控え目にして、聞きとりにくい子供たちの話に笑顔を見せて応えていたが、そのうちに目の前のご馳走も残り少なになると、子供たちはいろりの方へ引き上げて、後は主人と差向かいの二人きりになった。
浅黒い福島さんの顔が耳から頬のあたリヘかけて、ぽっと酔のまわった色があった。わたしもそろそろほどよい気持になっていた。
「お宅はずいがん旧家とお見うけしますが、―あのお位牌を見ても―」
この部屋へ入った時から、天照皇大神宮の軸物のかかった床の間に、ずらりと並んだ位牌が、みようにわたしの気にかかっていた。かぞえてはみなかったが三十基以上はあろう、それが煤けた釜屋の天丼同様、漆のように黒光りがしている。わたしは、それを見た瞬間、昨日、道ずれになった祖谷の男から、平家の落人部落を連想し、もしかするとこの家も、あの煤けた位牌から見て、由緒ある落人の家柄ではないだろうかと、それが気にかかっていたのだった。
「曾父、曾々父のことは話にきいておりますが、それから前のことはわかりません。しかし先祖代々ここで生まれて、ここで死んだことはまちがいがなく、上の墓場には位牌の数だけの碑がならんでおります。お前さん方から見れば、よくもまあこんな山の奥で先祖代々何百年も暮らしてきたとお考えになりましょぅが、山で生まれたものは、やっばり山におる方がまちがいがのうて―」
福島さんは大きな徳利をとってすすめながら、
「わたしが子供の時分には、この谷間にも三十軒からの家があったもので、寄りや、祭りの日には、谷から谷へ呼びかけて、今日、釣りなさった八畳の滝の社へみんなが集って賑かなものでございました。それがだんだんとみんな奈路(平坦地)へ出たがりまして、一人へり二人へって、いまはたった七軒になってしまいました。それで神祭といっても、もう寂しいもので、神社へ集ることもなく、お気の毒だが神官さんに来ていただくことになりました。わずか四、五十年の間に、変れば変るものでございます。― それで奈路へ出た連中は、その当座こそ便りもあり、こちらから出かけて見ると、きれいな生活をしておりますが、二年、三年とたつうちに、次第に便りも遠くなり、今度たずねていきますと、もうどこへ去ったか近所の人にきいても、行方もわかりません。山のものは、やっぱり山におる方がまちがいはないようでございます―。」
先刻から、茶の間でラジオが鳴っていたが、主人にも客にもラジオの唄声なんど聞えなかった。ちょっと話がとぎれた後で、
「あの写真は?」
と正面の欄間にかかった額縁入りの写真を見上げて聞いてみた。軍帽をかぶった白衣の胸に小さい勲章らしいものをつけた写真であった。
「日露戦争にご奉公をした時の写真でございます。負傷をして、広島の野戦病院へ還ってきた時、記念にうつしましたもので―、」
ちらと目をやって、言葉すくなに答えながら、こんどはつと耳を立ててラジオに聞きいっている風だった。わたしの耳にも不拡大方針だの、盧溝橋だのという言葉が断片的に聞えてきた。
「また戦がはじまりましたが、火ぶたをきったからには、どうせこのままではおさまりますまい。長男はいまあちらへまいっておりますが、この様子ではいずれあの友明にもお召しがあるでございましょう。あの子もその覚悟で、週に三日、青訓へまいって訓練をうけております。」
主人の福島さんの瞳が棚間から床の掛軸にうつったと思うと、急に改ったような低い声で、
「日本は神様の国でございます。天子様は天照皇大神のご子孫でございます。その天子様からのお召しとあれば、友明ばかりではございません。このわたしも、いつ何時でもお役に立つ覚悟をきめております―」
黙って頭を低げたまま、わたしは心のなかでつぶやいていた。
―山の奥には人がいる。日本はまだまだ亡びはしない― と。
山奥で出あった見知らぬ人同士でも、お互いを信頼して親情で接していた時代こと。
この話は、聞こえてきたラジオ放送からすると、昭和12年の7月末頃のことだろう。
ここに出てくる旅籠や地名は現在は早明浦ダムの底に沈んでいる。
八畳の滝は、早明浦ダムの上の大橋ダムのあたりであったのだろうか?
9.鎌井田の瀬 森下雨村
鎌井田は、部落の人々がみんなそろって純朴そのもので人柄が良かった。
鎌井田の漁師だけは、よそからの素人釣師をを心からよろこんで迎えてくれた。
それは明治村の村長を永年勤めていたFさんによるところだった。
そんな土地柄と、どちらかといえば閑寂すぎる釣場を垢石に見せたかつたのだ。
鎌井田の瀬
垢石父子がはるばると土佐までやってきたのは、もう一と昔から前である。土佐の鮎を釣ってみたい、それも吉野川の大鮎をぜひ釣ってみたいとわたしの顔を見る度に口癖のようにいっていたのが、紀州熊野川をたずねた足をのばして、ついに多年の宿望を遂げたわけである。
そのころ、わたしは右関節の神経痛に悩んで、出迎えにも家内と子供をやったことであったが、久々で垢石の顔をみると神維痛もふっとんで、到来二日目に仁淀川の中流鎌井田へ同行した。吉野川は情況がわからなかったばかりでなく、仮りにわかっていたとしても足をひきずりながらあの激流に竿を出すことは、とうてい覚束なかったからであった。それと一つには垢石にわたしたちの好きな釣場鎌井田を紹介したかったということもあった。
鎌井田は仁淀川の上、下流を通じて、わたしたち釣仲間の一番好きな釣揚であった。いまこそバスが走っているが、そのころは松山街道の越知町から下流へ二里の道を歩かなければならなかった。運動神経の極度ににぶいわたしは自転車修行に再度の失敗を繰返して、爾来一切テクと肝をきめ、釣仲間から疎外されたもので、鎌井田行きの日は、仲間より一時間も早く家を出て、川沿の二里の道をテクるか、越知町から山越えの近道を這い上るかして、自転車の仲間よりはいつも一と足先きに辿りついたものであった。そうした交通の不便が一般の釣師をせきとめて、ほとんど外来の釣客はなく、いつ出かけても顔見知りの連中ばかりで心しずかに竿が出せた。それと鎌井田の瀬を中心に上下約一里もの間、いたるところに釣場があった。三つ石、赤石、上の瀬、下の瀬、かしらづき――、それらの釣場をつなぐ淵もよし、瀞もよかった。ただ川幅もあり、水量もあって自由に渡渉はできなかったが、向岸へわたりたい時は土地の漁師に声をかければ、こころよく舟を寄せてくれる。
どの川筋でも、その土地の職業漁師が、よそからの素人釣師を歓迎しないのは同じであり、無理からぬふしもあるが、鎌井田の漁師だけは、わたしたちを心からよろこんで迎えてくれた。友釣りの専業、眼鏡での引っかけ漁師が五人ばかりいたが、わたしたちを見ていやな顔をするものは一人もなかった。それどころかいつでもよろこんで囮をわけてくれ、今日のよい釣場はどの瀬どの淵だと教えてまでくれた。別して川筋きっての友がけの名手だといわれたKさんは、舟の生簀にいる囮の中から、自分で選んで一番元気のいい囮をわけてくれた。そして昨日は下の瀬でだれが何尾、あの瀬肩で何尾揚げた。今日は上の瀬をねらってみるがよかろう。何尾くらいはたしかに釣れると、親切に釣場を教えてくれる。そればかりか、自分の教えた釣場はもとより、よその釣人が竿を出している釣場へは絶対に近づかないというのが、この土地の職業漁師の道義であった。
一度Kさんに教えられて下の瀬を左岸の川原から釣っていた。昨日はあの瀬が面白くなかった。今日は水色もいいし十尾はかかるであろうといってくれた。わたしは上み手から下も手へ、繰返し繰返し夕方近くまで引いてみたが、かけはずしも算用にいれてやつと七尾の釣果であった。下も手からKさんが帰りかかってきた。舟を瀬から押上げて、成績はどうかときくので手とり五尾、かけはずし二尾と報告すると、ちょっと小首をかしげて川底をのぞきながら、錨を入れてもよいかという。十尾は釣れるだろうといった手前がある。が、邪魔にはならないかというのである。さあ、どうぞとわたしが竿を傍へおくとKさんはぐっと上み手に錨を入れ、生簀の囮を泳がした。五分とたたないのに一尾あげた。囮をとりかえてまた一尾。するすると綱をのばして、やや上み手でさらに一尾。三十分そこそこで三尾をあげて竿をおいた。技であり、腕であることはもとよりだが、わたしは、その腕よりもKさんの責任感といつたようなものに、つくづく頭のさがる思いをしたことだった。
そうした人柄の良さは漁師ばかりではなかった。戸数三十戸そこそこの部落の人々がみんなそろって純朴そのものであった。わたしは三、四年もの間、夏はたいがい鎌井田の瀬で釣り暮らしたので、土地の人とはたいてい顔なじみになってはいたが、たまにあう人々でも必ずお辞儀をし挨拶をかわして通り過ぎた。
これは交通の使がわるく、土地の人が人ずれをしていないからでもあつた。が、土地の漁師までが利害を忘れて、外来のわたしたちを親切に扱ってくれたのは、ほかに大きな原動力があったことを見逃してはなるまい。それは村長のFさんが朝に夕に、機会ある毎に土地の人々や、わけても職業漁師たちに、外来の釣人を大切にするように、はるばるとこの土地を訪れてくれる遠来の客人である、一にも親切、二にも親切。それはやがてこの寒村の繁栄の一助にもなるであろうことを忘れるなと説きつづけたのが、皆の頭にしみこんでしまったというのである。
そのFさんは、鎌井田の部落と下流片岡、その他の部落をいっしょにした明治村の村長を永年勤めていたが、やはり釣狂で、日曜日にはわが家の真下にあたる下の瀬に、いつも胸まで立ちこんで大ものをねらった豪の者だったそうである。ところが二年前、片岡の役場からの帰りに自転車から落ちて、背や脚にひどい怪我をして再起覚束なく、いまは病床から毎日川を眺めて牌肉を嘆じている、と聞いて、わたしは一度Fさんを見舞ったことであった。村人のみんなに慕われた人格者で、気性も人一倍強い方ではあったが、足掛け三年の療養生活で、だんだんと衰弱もくわわり、このごろはめっきり気が弱くなって、だれかれが時折、鮎をとどけると、ポロポロ泪をこぼして嬉し泣きに泣かれるので困りいると、これはその後Kさんから聞いた話であつた。
鎌井田はこういう土地である。わたしは人情の厚い、どちらかといえば閑寂すぎる釣場を垢石に見せたかつた。釣果はともかく、釣人のごみごみした川筋よりも、だれにも邪魔されずのんびりとたのしめる方が、遠来の客にも心愉しかろうと思ったからである。前夜夕餉の膳をかこんで、いま言ったような話をすると垢石は、腕をまくって盃をふくみながら大いにわが意を得たりとよろこんだ。
翌朝、越知町までバス。たのんであつた舟の便をかりて川を下った。瀬あり、淵あり、両岸には山高く、仁淀川下りも観光の一つといわれたほどで、風光も満更ではない。舟は徒歩よりもはるかに速く、約一時間で三ツ岩の隘路をぬけると、その辺からもう鎌井田の領分である。
わたしは下の瀬の右岸よりをねらっていた。足場がよく、川底は遠浅だが石が荒くて大物がでる。それと山裾の榎の大木がかつこうな日蔭をつくつて、弁当をひろげるにいい。いま一つ鎌井田の部落は目の前にあって、上み手には渡場もある。たいへん便利だと思ったからだつたが、そこにはもう土地の漁師が四はいも舟をかけていた。二はいは瀬肩の引っかけ、二はいは友釣りで、その一人はKさんだつた。
わたしは舟子にいって舟を瀬の右岸につけさせた。声をかけるまでもなかった。Kさんは竿の手をとめて、こっちを見たが見かけない客人の姿に、ちょっと意外そうな面持ちだった。わたしが遠方のお客様だが、どこへ案内したらいいかと訊くと、即座に、「かしらづきまで下りなさい。ひとり下へいったが、あすこまではいっていまい。」
といって囮は、と聞いた。あんたを当てにして来たのだというと、丁度かかりのいいのが二尾ある。一尾は腹がかりだが、どうにか使えるだろうといって、錨を上げて囮を三尾わけてくれた。
「おしあわせよう!」Kさんの言葉を後に舟が浅瀬を下って深い淵へ出ると、垢石が後を振り返って、
「なるほど姿勢がいい。竿の持ち方も立派だ。それにいい男前だ!」
といった。Kさんは体格は普通だが、体から風貌から、どこか常人とちがう凛としたところがあった。目もとも口もとも引きしまって、いわば男らしい男前であった。口数も少なく、減多に笑顔を見せなかったので、初対面の人にはぶあいそうな人間のような印象をあたえたかもしれないが、つきあっていると、なんとも言いようのない親近感をおぼえる肌合のよさがあった。竿をもって舳につっ立ったKさんの釣姿にひと目で惚れこんだ垢石の眼識もさすがであった。Kさんは七、八つのころから友釣り一式で通してきたベテランである。釣仲間のだれかれが引っかけに手を出すといやな顔をして、酒もいっしよに飲まなかったほどの友釣り至上主義者だつた。それだけに川筋のことも鎌井田の領域にかけては、過去何十年の河床の変遷からその変化にともなう魚つきの場所はもとより、年毎に変る河底の石の一つ一つまで眼底にあつたと思われるほどくわしかつた。だから鎌井田のKさんといえば、川筋きっての漁師としてだれも異議をはさむものはなかつた。Kさんにはわたしも訓えられるところが多かつた。聞けば何事でも自分の経験から惜しみなく教えてくれたが、その時はいかにもと感嘆しながら、たいがいは片っぱしから忘れてしまつて、今更ら書きとめておけばよかったと悔まれる。が、一つ二つは記憶の底にのこつている。
瀬肩を釣って、白っぽい魚がかかつたら、居つきの魚はいないと思え、だれかが釣った後である。秋口の魚は体をいとつて辺地による、水きわの浅場を踏んではならぬ、といつた類である。人柄はよかったが、きかぬ気、負けぬ気も強かつた。不漁の日、仲間に釣られたと思うような日は、夕暮が迫って鈎素が見えなくなってもまだ頑張りつづけてやめなかつた。
そうした気性と長い間の経験が、自然とKさんの釣り姿や竿の操作に、これも一かどのベテランである垢石をして一目惚れさせたであろうと、わたしは後から思ったことだった。
かしらづきはやや勾配をもった瀞とも瀬とも言いがたいが、下も手には中洲をはさんで淵へ落ちこむ荒瀬もあり、緩急いずれでもという釣場で、上にも下にも釣人の影はなかった。二人は早速竿を出した。上み手から垢石二世、垢石、わたしは立ちこむのをきらつて下も手にまわった。
垢石と釣りをともにするのは魚野川以来であった。あの時、わたしは次女を喪って傷心の極であった。たまたま先行の垢石から後を追うてくるようにと勧説の手紙があり、心の痛手をまぎらそうと、ふらふらと出かけていったわけであった。待ちわびていた彼は、まず酒をくんでわたしを励まし慰めてくれた。その親情はうれしかったが、翌日からの魚野川の釣りは、わたしには大した興味もなかった。釣りをたのしむ気分に心からなれなかったのはもとよりであつたが、土佐の荒川に馴れていたわたしには、魚野川は川も小さく、流れもわるく、いわば物足りない感じが先きに立った。川底の石も砂利のようで、放流魚はまだ型が小さく、その場で釣り上げて手綱にとれた。印象に強くのこったのは、その前年、垢石がやられたというつつが虫の恐怖と、川を上って宿への帰途、田圃のなかに黄金色にうれた美事な胡瓜を百姓に所望して、それを肴に呑みほした冷たいビールの味である。
久々で竿をならべながら第一日の成績は両人とも大したこともなかった。しかしいい釣場だ、来てよかったと喜んでもらったほどの釣果はあつた。浅瀬を左岸にわたって小一里の道を鎌井田に引返し、その夜はわたしの定宿にしている旅館に泊った。タ暮近く、わたしはKさんの家を訪ねて囮の謝礼をしながら、垢石に土産話の一つにもなろうかと宿まで案内しようとしたが、Kさんは遠慮して、また明日、川でお日にかかろうと辞退しつづけた。
二日目は宿の真下の上の瀬をねらったが面白くなかつた。通りがかつた舟をよんで、向う岸にわたってみたが、これも同様であつた。やっぱりKさんに聞いてからにすべきであった。後で聞いたところによると、前の日、上流から来た金突きの一隊が、上の瀬まで荒して引き上げていったということだった。
三日日はなんと尺余の増水で、水は黒にごりであった。上流にひどい驟雨があったらしい。川原に集った土地の漁師もこの濁りでは、今日、明日は駄日だと嘆息をついて、舟や道具の手入れをしたり、中にはゴロ引きの準備にかかっているものもあつた。残念ながらわたしたちも諦めをつけて、足の重い二里の道をとぼとぼと引上げるほかなかった。
新荘川や物部川へも案内したかった。が、垢石は一図に吉野川の大鮎をねらって、矢も楯もといったように気負い立っていた。昔、新聞社にいたころ徳島県出身のM社長に、吉野川の大鮎を釣らないでは鮎を口にする資格がないと頭ごなしにやられたのが癪でと、いかにも口惜しそうにその時の無念さを述懐するのを一度ならず聞いていたわたしは、足さえ元気であれば柳の瀬から岩原へかけて吉野川のあの釣場、この釣場を案内してやりたかった。折角はるばると土佐路へ足を踏みこんだ彼に、と思ったことであるが、チクリチクリと痛むわたしの足では吉野川の急流激湍に立ち向う自信がなかった。
その翌日、垢石父子は土讃線で吉野川に向った。四、五日もしてハガキが来た。
「大歩危、小歩危をねらったが、こちらも増水、駅長に無理だととめられ、恨をのんで宇高連絡船で本州に渡る」とあった。
(注:垢石が土佐・佐川を訪れたのは、昭和十六年八月のことであった。)
雨村は、ほかの釣仲間が自転車で行くところを、テクテク歩いたのだ。
というのも、五十を過ぎて初めて自転車の練習をしたのか、若い頃に練習してもダメだったのか、
自転車に乗れるようにはならなかったからだ。
それにしても、昔の人は2里や3里を平気で歩いたものだ。
老化防止をかねて、少しは歩くように心がけよう。
10.令嬢アユ 太宰治 (昭和16年)
女性には叱られるかもしれませんが、男にとっては過ぎ去りし良き時代?のお話です。
しかし、出征する若者やその家族には酷い時代でもありました。
令嬢アユ
佐野君は、私の友人である。私のほうが佐野君より十一も年上なのであるが、それでも友人である。佐野君は、いま、東京の或る大学の文科に籍を置いているのであるが、あまり出来ないようである。いまに落第するかも知れない。少し勉強したらどうか、と私は言いにくい忠告をした事もあったが、その時、佐野君は腕組みをして頸垂れ、もうこうなれば、小説家になるより他は無い、と低い声で呟いたので、私は苦笑した。学問のきらいな頭のわるい人間だけが小説家になるものだと思い込んでいるらしい。それは、ともかくとして、佐野君は此の頃いよいよ本気に、小説家になるより他は無い、と覚悟を固めて来た様子である。日、一日と落第が確定的になって来たのかも知れない。もうこうなれば、小説家になるより他は無い、と今は冗談でなく腹をきめたせいか、此の頃の佐野君の日常生活は、実に悠々たるものである。かれは未だ二十二歳の筈であるが、その、本郷の下宿屋の一室に於いて、端然と正座し、囲碁の独り稽古にふけっている有様を望見するに、どこやら雲中白鶴の趣さえ感ぜられる。時々、背広服を着て旅に出る。鞄には原稿用紙とペン、インク、悪の華、新約聖書、戦争と平和第一巻、その他がいれられて在る。温泉宿の一室に於いて、床柱を背負って泰然とおさまり、机の上には原稿用紙をひろげ、もの憂げに煙草のけむりの行末を眺め、長髪を掻き上げて、軽く咳ばらいするところなど、すでに一個の文人墨客の風情がある。けれども、その、むだなポオズにも、すぐ疲れて来る様子で、立ち上って散歩に出かける。宿から釣竿を借りて、渓流の山女釣りを試みる時もある。一匹も釣れた事は無い。実は、そんなにも釣を好きでは無いのである。餌を附けかえるのが、面倒くさくてかなわない。だから、たいてい蚊針を用いる。東京で上等の蚊針を数種買い求め、財布にいれて旅に出るのだ。そんなにも好きで無いのに、なぜ、わざわざ釣針を買い求め旅行先に持参してまで、釣を実行しなければならないのか。なんという事も無い、ただ、ただ、隠君子の心境を味わってみたいこころからである。
ことしの六月、鮎の解禁の日にも、佐野君は原稿用紙やらペンやら、戦争と平和やらを鞄にいれ、財布には、数種の蚊針を秘めて伊豆の或る温泉場へ出かけた。
四五日して、たくさんの鮎を、買って帰京した。柳の葉くらいの鮎を二匹、釣り上げて得意顔で宿に持って帰ったところ、宿の人たちに大いに笑われて、頗るまごついたそうである。その二匹は、それでもフライにしてもらって晩ごはんの時に食べたが、大きいお皿に小指くらいの「かけら」が二つころがっている様を見たら、かれは余りの恥ずかしさに、立腹したそうである。私の家にも、美事な鮎を、お土産に持って来てくれた。伊豆のさかなやから買って来たという事を、かれは、卑怯な言いかたで告白した。「これくらいの鮎を、わけなく釣っている人もあるにはあるが、僕は釣らなかった。これくらいの鮎は、てれくさくて釣れるものではない。僕は、わけを話してゆずってもらって来た。」と奇妙な告白のしかたをしたのである。
ところで、その時の旅行には、もう一つ、へんなお土産があった。かれが、結婚したいと言い出したのである。伊豆で、いいひとを見つけて来たというのであった。
「そうかね。」私は、くわしく聞きたくもなかった。私は、ひとの恋愛談を聞く事は、あまり好きでない。恋愛談には、かならず、どこかに言い繕いがあるからである。
私が気乗りのしない生返事をしていたのだが、佐野君はそれにはお構いなしに、かれの見つけて来たという、その、いいひとに就いて澱みなく語った。割に嘘の無い、素直な語りかただったので、私も、おしまいまで、そんなにいらいらせずに聞く事が出来た。
かれが伊豆に出かけて行ったのは、五月三十一日の夜で、その夜は宿でビイルを一本飲んで寝て、翌朝は宿のひとに早く起してもらって、釣竿をかついで悠然と宿を出た。多少、ねむそうな顔をしているが、それでもどこかに、ひとかどの風騒の士の構えを示して、夏草を踏みわけ河原へ向った。草の露が冷たくて、いい気持。土堤にのぼる。松葉牡丹が咲いている。姫百合が咲いている。ふと前方を見ると、緑いろの寝巻を着た令嬢が、白い長い両脚を膝よりも、もっと上まであらわして、素足で青草を踏んで歩いている。清潔な、ああ、綺麗。十メエトルと離れていない。
「やあ!」佐野君は、無邪気である。思わず歓声を挙げて、しかもその透きとおるような柔い脚を確実に指さしてしまった。令嬢は、そんなにも驚かぬ。少し笑いながら裾をおろした。これは日課の、朝の散歩なのかも知れない。佐野君は、自分の、指さした右手の処置に、少し困った。初対面の令嬢の脚を、指さしたり等して、失礼であった、と後悔した。「だめですよ、そんな、――」と意味のはっきりしない言葉を、非難の口調で呟いて、颯っと令嬢の傍をすり抜けて、後を振り向かず、いそいで歩いた。躓いた。こんどは、ゆっくり歩いた。
河原へ降りた。幹が一抱え以上もある柳の樹蔭に腰をおろして、釣糸を垂れた。釣れる場所か、釣れない場所か、それは問題じゃない。他の釣師が一人もいなくて、静かな場所ならそれでいいのだ。釣の妙趣は、魚を多量に釣り上げる事にあるのでは無くて、釣糸を垂れながら静かに四季の風物を眺め楽しむ事にあるのだ、と露伴先生も教えているそうであるが、佐野君も、それは全くそれに違いないと思っている。もともと佐野君は、文人としての魂魄を練るために、釣をはじめたのだから、釣れる釣れないは、いよいよ問題でないのだ。静かに釣糸を垂れ、もっぱら四季の風物を眺め楽しんでいるのである。水は、囁きながら流れている。鮎が、すっと泳ぎ寄って蚊針をつつき、ひらと身をひるがえして逃れ去る。素早いものだ、と佐野君は感心する。対岸には、紫陽花が咲いている。竹藪の中で、赤く咲いているのは夾竹桃らしい。眠くなって来た。
「釣れますか?」女の声である。
もの憂げに振り向くと、先刻の令嬢が、白い簡単服を着て立っている。肩には釣竿をかついでいる。
「いや、釣れるものではありません。」へんな言いかたである。
「そうですか。」令嬢は笑った。二十歳にはなるまい。歯が綺麗だ。眼が綺麗だ。喉は、白くふっくらして溶けるようで、可愛い。みんな綺麗だ。釣竿を肩から、おろして、「きょうは解禁の日ですから、子供にでも、わけなく釣れるのですけど。」
「釣れなくたっていいんです。」佐野君は、釣竿を河原の青草の上にそっと置いて、煙草をふかした。佐野君は、好色の青年ではない。迂濶なほうである。もう、その令嬢を問題にしていないという澄ました顔で、悠然と煙草のけむりを吐いて、そうして四季の風物を眺めている。
「ちょっと、拝見させて。」令嬢は、佐野君の釣竿を手に取り、糸を引き寄せて針をひとめ見て、「これじゃ、だめよ。鮠の蚊針じゃないの。」
佐野君は、恥をかかされたと思った。ごろりと仰向に河原に寝ころんだ。「同じ事ですよ。その針でも、一二匹釣れました。」嘘を言った。
「あたしの針を一つあげましょう。」令嬢は胸のポケットから小さい紙包をつまみ出して、佐野君の傍にしゃがみ、蚊針の仕掛けに取りかかった。佐野君は寝ころび、雲を眺めている。
「この蚊針はね、」と令嬢は、金色の小さい蚊針を佐野君の釣糸に結びつけてやりながら呟く。「この蚊針はね、おそめという名前です。いい蚊針には、いちいち名前があるのよ。これは、おそめ。可愛い名でしょう?」
「そうですか、ありがとう。」佐野君は、野暮である。何が、おそめだ。おせっかいは、もうやめて、早く向うへ行ってくれたらいい。気まぐれの御親切は、ありがた迷惑だ。
「さあ、出来ました。こんどは釣れますよ。ここは、とても釣れるところなのです。あたしは、いつも、あの岩の上で釣っているの。」
「あなたは、」佐野君は起き上って、「東京の人ですか?」
「あら、どうして?」
「いや、ただ、――」佐野君は狼狽した。顔が赤くなった。
「あたしは、この土地のものよ。」令嬢の顔も、少し赤くなった。うつむいて、くすくす笑いながら岩のほうへ歩いて行った。
佐野君は、釣竿を手に取って、再び静かに釣糸を垂れ、四季の風物を眺めた。ジャボリという大きな音がした。たしかに、ジャボリという音であった。見ると令嬢は、見事に岩から落ちている。胸まで水に没している。釣竿を固く握って、「あら、あら。」と言いながら岸に這い上って来た。まさしく濡れ鼠のすがたである。白いドレスが両脚にぴったり吸いついている。
佐野君は、笑った。実に愉快そうに笑った。ざまを見ろという小気味のいい感じだけで、同情の心は起らなかった。ふと笑いを引っ込めて、叫んだ。
「血が!」
令嬢の胸を指さした。けさは脚を、こんどは胸を、指さした。令嬢の白い簡単服の胸のあたりに血が、薔薇の花くらいの大きさでにじんでいる。
令嬢は、自分の胸を、うつむいてちらと見て、 「桑の実よ。」と平気な顔をして言った。「胸のポケットに、桑の実をいれて置いたのよ。あとで食べようと思っていたら、損をした。」
岩から滑り落ちる時に、その桑の実が押しつぶされたのであろう。佐野君は再び、恥をかかされた、と思った。
令嬢は、「見ては、いやよ。」と言い残して川岸の、山吹の茂みの中に姿を消してそれっきり、翌日も、翌々日も河原へ出ては来なかった。佐野君だけは、相かわらず悠々と、あの柳の木の下で、釣糸を垂れ、四季の風物を眺め楽しんでいる。あの令嬢と、また逢いたいとも思っていない様子である。佐野君は、そんなに好色な青年ではない。迂濶すぎるほどである。
三日間、四季の風物を眺め楽しみ、二匹の鮎を釣り上げた。「おそめ」という蚊針のおかげと思うより他は無い。釣り上げた鮎は、柳の葉ほどの大きさであった。これは、宿でフライにしてもらって食べたそうだが、浮かぬ気持であったそうである。四日目に帰京したのであるが、その朝、お土産の鮎を買いに宿を出たら、あの令嬢に逢ったという。令嬢は黄色い絹のドレスを着て、自転車に乗っていた。
「やあ、おはよう。」佐野君は無邪気である。大声で、挨拶した。
令嬢は軽く頭をさげただけで、走り去った。なんだか、まじめな顔つきをしていた。自転車のうしろには、菖蒲の花束が載せられていた。白や紫の菖蒲の花が、ゆらゆら首を振っていた。
その日の昼すこし前に宿を引き上げて、れいの鞄を右手に、氷詰めの鮎の箱を左手に持って宿から、バスの停留場まで五丁ほどの途を歩いた。ほこりっぽい田舎道である。時々立ちどまり、荷物を下に置いて汗を拭いた。それから溜息をついて、また歩いた。三丁ほど歩いたころに、
「おかえりですか。」と背後から声をかけられ、振り向くと、あの令嬢が笑っている。手に小さい国旗を持っている。黄色い絹のドレスも上品だし、髪につけているコスモスの造花も、いい趣味だ。田舎のじいさんと一緒である。じいさんは、木綿の縞の着物を着て、小柄な実直そうな人である。ふしくれだった黒い大きい右手には、先刻の菖蒲の花束を持っている。さては此の、じいさんに差し上げる為に、けさ自転車で走りまわっていたのだな、と佐野君は、ひそかに合点した。
「どう? 釣れた?」からかうような口調である。
「いや、」佐野君は苦笑して、「あなたが落ちたので、鮎がおどろいていなくなったようです。」佐野君にしては上乗の応酬である。
「水が濁ったのかしら。」令嬢は笑わずに、低く呟いた。
じいさんは、幽かに笑って、歩いている。
「どうして旗を持っているのです。」佐野君は話題の転換をこころみた。
「出征したのよ。」
「誰が?」
「わしの甥ですよ。」じいさんが答えた。「きのう出発しました。わしは、飲みすぎて、ここへ泊ってしまいました。」まぶしそうな表情であった。
「それは、おめでとう。」佐野君は、こだわらずに言った。事変のはじまったばかりの頃は、佐野君は此の祝辞を、なんだか言いにくかった。でも、いまは、こだわりもなく祝辞を言える。だんだん、このように気持が統一されて行くのであろう。いいことだ、と佐野君は思った。
「可愛いがっていた甥御さんだったから、」令嬢は利巧そうな、落ちついた口調で説明した。「おじさんが、やっぱり、ゆうべは淋しがって、とうとう泊っちゃったの。わるい事じゃないわね。あたしは、おじさんに力をつけてやりたくて、けさは、お花を買ってあげたの。それから旗を持って送って来たの。」
「あなたのお家は、宿屋なの?」佐野君は、何も知らない。令嬢も、じいさんも笑った。
停留場についた。佐野君と、じいさんは、バスに乗った。令嬢は、窓のそとで、ひらひらと国旗を振った。
「おじさん、しょげちゃ駄目よ。誰でも、みんな行くんだわ。」
バスは出発した。佐野君は、なぜだか泣きたくなった。
いいひとだ、あの令嬢は、いいひとだ、結婚したいと、佐野君は、まじめな顔で言うのだが、私は閉口した。もう私には、わかっているのだ。
「馬鹿だね、君は。なんて馬鹿なんだろう。そのひとは、宿屋の令嬢なんかじゃないよ。考えてごらん。そのひとは六月一日に、朝から大威張りで散歩して、釣をしたりして遊んでいたようだが、他の日は、遊べないのだ。どこにも姿を見せなかったろう? その筈だ。毎月、一日だけ休みなんだ。わかるかね。」
「そうかあ。カフェの女給か。」
「そうだといいんだけど、どうも、そうでもないようだ。おじいさんが君に、てれていたろう? 泊った事を、てれていたろう?」
「わあっ! そうかあ。なあんだ。」佐野君は、こぶしをかためて、テーブルをどんとたたいた。もうこうなれば、小説家になるより他は無い、といよいよ覚悟のほどを固くした様子であった。
令嬢。よっぽど、いい家庭のお嬢さんよりも、その、鮎の娘さんのほうが、はるかにいいのだ、本当の令嬢だ、とも思うのだけれども、嗚呼、やはり私は俗人なのかも知れぬ、そのような境遇の娘さんと、私の友人が結婚するというならば、私は、頑固に反対するのである。
| . |
 |
「お染」は、梅雨時の笹濁りに向き、深場で大型が釣れる鈎として
現在も使われています。
先巻き(ツノの針先側)が緑色のものは「青お染」と呼ばれます。
お染、青お染とも赤ツノと黄ツノがあります。
(2005/05/26訂正)
毛鈎各部の名称はこちらでご確認下さい。 |
11.釣り宿 須藤均治
今年2005年8月にようやく訪れることのできた追良瀬川の60年ほど前の様子である。
昔から津軽ではアユの川として名が通っていたことが分かる。
釣り宿
青森県西津軽郡深浦町大字松原。この部落に、私の行きつけの釣り宿がある。
松原部落は、秋田県と青森県境の分水嶺に源を発して流程八十五キロ、日本海に注ぐ追良瀬川の河口から六キロ上流の山峡に、ちんまりと茅葺き屋根を寄せ合っている、戸数十九の小さな集落である。
可耕反別が限られているために、むかしからの不文律で次・三男の分家を許さなかったので、永年ふえも減りもしない″十七軒部落〃だったのが、戦後分教場の教員住宅と電力会社の保線係の住宅が出来て十九軒を数えることになった。このうち十六戸が自作農だが、どの家も山仕事や土木工事の日雇いなどの手間仕事があって、山村の暮らしとしては、むしろ楽といっていいだろう。
ただ一筋のせまい森林軌道が取りはずされて、トラック道路に改修される数年前までは、使い用がないから自転車が一台もなく、電灯や電話の引っ込み線がきていないので、電灯や電話やラジオがなかった。秋口になると、部落の田んぼや分教場の校庭にしきりに熊が現われた。
これはいまも同じである。熊とりマタギも二、三人はいる。
―― その頃、河口の村から歩きづらい森林軌道を六キロもたどって、翠巒に囲まれた部落のたたずまいを望見し、のどかな鶏犬の声をきくと、おもわず足を休めてうっとりと眺め入ったものである。桃源境! というと、もとより誇張にすぎるが、平家の落人の部落だという怪し気な伝説も、まんざらでもないわい、とおもわれた。山も水も豊かで、イワナ・ヤマメ・アユなどの魚影も濃く、まさに〃わが谷は緑なりき〃であった……。
部落の南はずれに、日用品雑貨品をごちゃごちゃ並べている店がある。″坂崎の店コ〃または単に″店コ〃と呼ばれている。食料品はもちろん、荒物や酒類も売っており、下駄だって十足くらい並んでいる。これが私の釣り宿である。宿屋営業をしているわけではないが、釣り人たちや山役人などがたいていここに泊めてもらう。私とは十数年の馴染みである。ヤマメ釣りの季節はそれ程でもないが、アユの解禁になると、時には十人以上も混み合って、えらくにぎやかなことになる。奥の十畳間と六畳間を開放して、雑魚寝の格好だが、寝具はいつも比較的清潔だし、ノミや蚊などもいないから寝心地はそうは悪くない。
〃店コ〃のカッチヤ(おかみ)の名前は、いまもって私は知らないが、なにしろ大変な働き者だ。
私みたいなわがままな泊まり客の世話から、十円玉を握って「買るゥ」と言ってとびこんでくる洟たれ子供たちの応待、部落ただ一つの電話の取り次ぎもせねばならず、家事はもちろん、その上土間続きの小屋でぎゃァぎゃァ喚きたてる五頭の豚と十四頭の子豚の世話まで、一切カッチャの仕事である。四十七、八になる亭主は、上流の道路工事と伐木の二つの飯場に納める日用物資の仕入れや店のために、たいてい朝早くバイクで町へ出かけるし、二人の子供は学校だから、陽のあるうちはカッチャの独り舞台である。
小柄だがガッチリと堅太りしたカッチャは、年がら年中、乱暴な高調子で、客や豚どもと騒々しく渡り合って、一向疲れをみせない。
「―― カッチャよ、カッチャ、豚まで飼って、なんぼ慾たがれだば。蔵建てるたて、この部落だば場所もねえベョ」と、ひやかしても馬耳東風、でかい腰をふりふり家の内外を走り回っている。まンず平家の匂いがこれっぽちもしない、カッチヤのもの腰格好である。
この九月の初めにも、釣り友達と一晩泊まりでアユの友釣りに出かけた。台風のなごりで、意外に水かさが多く、初日の午後は面白い釣りになったが、翌日はにわか雨にたたられた上に、数々のへまをやった。体をふき着替えをすませて、さて十畳間の真中に大胡坐になるなり「カッチャよ、ビール、ビール……」と連呼したら「あい、あい、朝から冷蔵庫さ入れて置いだテ」と相変わらず成勢のいい返事だった。間もなく、降りつづいていた小雨が大粒の沛然たるさまに変わった。開け放した雨戸からすぐ稲田が展け、その果てが鬱蒼たる原生林の低山の連互で、その脚部を溪流が洗っている、緑一色の眼前風景。
眉に迫る翠巒に雨が白い線を描いている。白雨というやつだろう。溪流の響きも淙々と一段とたかまってきた……。
いまはもう九月も下旬、ぼつぼつ産卵期にはいったアユは、秋水にのって河口近くのザラ場を指して降り始める。落ちアユである。これからは、メスをオトリにしないことには友釣りにはなるまいが、どうしてももう一度だけ松原にでかけたい、と私はしきりにおもいつめ、ぐずつき勝ちな天気予報を按じているのである。
この頃、この川のアユを銀鮎と呼んでいたのかは、書かれていない。
それにしても何里もの道を苦にもせず歩いてアユ釣りに行った昔の人の熱意には脱帽する。
今回05年の釣行日記(8/5)に載せた「見入観音堂」がある場所の地名が「松原」というそうです。
12.ぼくは原始人 大下宇陀児
年とともに原始人になりたいような、なっていくような気がしてくる。
ぼくは原始人
ぼくは原始人
計算ずくだとばかばかしい。
鮎の季節に百貨店の魚売場へ行くと、型のよいのが二百円どまりで買える。だのに、ぼくは買う気がしない。釣ったのでないと鮎ではないように思う。
リュックを背負い、長い竿を肩にして家を出るが、正直にいうと、ぼくの釣りは上手じゃないのだろう。泊りがけで、舟と船頭さんを雇ってやって一匹も釣れないことがあるし、だから家へ持って帰った鮎は、一尾あたりが数千円に当ることになる。でも、後悔せずにまた出かける。
ということは、竿先きをしぼられて魚と引っ張りっこする。あの醍醐味に千金の値打ちがあるからだが、では、なぜそれを醍醐味と感じるか、ひらたく言えば、なぜ釣りが面白いか、ときかれると、原始人の狩猟本能が残っているからだ、とでも答えるよりほかない。つまりぼくは、甚だ原始人的である。
少しく健康を害している。激しい運動はいけない、と医者から注意をうけている。
けれども、川へ行くと、朝の四時にはじめて、夕まづめの手もとが暗くなるまで、ちょっと休むことがあるものの、大体は竿をふりまわしている。おかげで去年は、担架で川から家まで帰らねばならぬか、と思ったことがある。そして、いまは、鮎の解禁を首をのばして待っている。
度し難し、とはこれかもしれない。
仏典に曰く、「菩提心を発すというは、己れ末だ度らざる前に一切衆生を度さんと発願し営むなり――
その形、陋しというとも、此心を発せばすでに一切衆生の導帥なり、たとい七歳の女流なりとも――
、即ち四衆の導師なり、衆生の慈父なり―― これ仏道極妙の法則なり。」
とあるが、釣りでは、他衆生に自分の釣場をとられてはならぬ。ことに、況んや鮎においておやだ、他の渡らざる前に我が渡って、お目あての釣場に糸を垂れようというのだから、衆生の導師たるには遠くはるかで、おまけに釣り上げた魚は、時によると生きたまま、熱湯へ投げこんでその風味を賞するというわけだから、死んだら地獄行きは免れず、それは覚悟の上で、命のつづくかざりはこの殺生をやろうと思っている。
さりながら困るのは、川が年ごとに悪くなることである。
こないだも新聞に出た。多摩川で、十万尾の魚が浮いたのだそうな。工場の廃液のせいだろう。工場がふえるだけじゃない。ビルや道路工事で砂利を採取する。川は赤く濁るし、川底が荒れ、年々歳々川の魚は減るばかりだ。
戦前の多摩川を思うと、涙が出るほどだ。二子や登戸で、大型のソク釣りをやった日もあったのに、今は相模まで行って、カラ竿かついで帰るということもある。但し自慢じゃないが去年の相模は、どこも悪いといわれたのに、秋口の釣りで、大型四十匁を頭に四十数尾をあげたのだから、やっばり釣りはやめられない。
釣りのため、ずいぶん義理をかく。出かけるときめておいた日に、あいにくなことで、黒枠つきの葬式通知がくる。
行けなくなるはずだけれども、弔電で義埋を果せる場合だと、いささか良心の苛責を感じつつ、そのまま川へ行ってしまって、「逝くものはかくの如し、昼夜をおかず、南無阿弥陀仏。」と唱える。
そのくらいだから、季節がくると、催しものや会合への返事は、なるべく出さないことにしている。出席の返事を出したら欠席しては悪いし、せっかくのいい日なみ、心も身も全くさしさわりないというとき、会のため釣りがダメだとなれば、その日一日おもしろくなくて、誰の顔を見ても癪にさわる。
そんなとき、女を相手に酒でも飲んで、心の憂さの捨てどころがあると助かるのだが、お医者さまはおっしゃった。酒はいけませんよ。またあれは、いちばん危険ですね。ずっと昔、陸軍大将で総理大臣だった人があったでしょうと。
義理を欠くのは、しかし、釣りばかりではないだろう。山田風太郎は、麻雀で同じことがありはしないか。水谷準ときたら、雨の日雪の日風の日もゴルフだ。そのため、顔が出るはずの会へ行っても会えやしない。会わなくてもさしつかえないけれども、ぼくよりも会を欠席することはたしかだ。してみると準も、相当な原始人だということになる。
原始人のぼくは、原始人である証拠には、現代文化の特産物を欲しいと思わない。パリヘも行きたくない。よいカメラやよい時計、よい万年筆ですらとくに欲しいとは思わない。欲しいのは、よく釣れる、静かな、そして足場のいい川だけだ。
釣りウソ
アユをつりたさの一念で、ぼくはいくどもウソをついた。ここにつつしんで告白し謝罪しますから、どうぞや地獄の閻魔さま、ぼくの舌を引きぬかないでください。
増水のあとの川が理想的な澄み口に向かった。風弱く曇れども大雨なしという予報だ。前の晩から竿の手人れもし、鈎サックの中もあかずながめ、ワラジとビク、寒いときのセーター、雨具も忘れずリュックにつめて、さて朝は魔法びんの氷など用意しているとき黒枠つきのはがきが舞いこみ、または電話でだれそれが死んだと知らせてくる。おくやみにかけつけねばならぬとなった場合の、やるせなさ悲しさ情なさ、味気なさ。
弔電でよかったら、もしくは代わりの家人ですむのならまことにありがたい。良心にとがめられつつも、そのまま川へ出かけてしまう。先方へは、カゼで腹痛で旅行中だとウソをつく。甲の会合と乙の会合とあって、どちらへも顔を出すべきだ。が、甲へは乙の会合へ先約したといい、乙ヘは甲の会合への先約をしたのだという。出席の返事をしてあっても、あいにくとその日が絶好の釣りびよりとなったら、出席しようかどうしようかと迷い、返事は出席だったから、幹事はその予定で、会費の点でも困るだろうと、千々に心を砕きつつ、幸いにもぼくは持病がある。持病が起こって不安だからとウソをついて、犯人のごとく顔見知りに会うのをおそれつつ、目ざす釣り場へ出かけてしまう。
自由職業で、ウイークデーもおかまいなし、いつでも行ける立場にいて、そのくせ最高にスゴイ会心の釣りというものは、一年のうちに、いや生涯のうちに、そうたくさんあるものではない。泊まりがけでも柳っぱ一匹ということだってあるし、だからして、行ける限りは精出して行っておかなくちゃならない。もちろん、黒枠の友人知己が、釣りのことなど思わせないほど、ぼくを悲しませるのだったらべつの話だけども。
そんなにまでして行ってみたら、川がジャリ取りで濁っていたり、お目あての釣り場を占領されていたり、でなくともアユのキゲンが悪かったりで、やっとこさアタリがあったと思えば、黒く光ってヌラヌラするダボハゼだったということもあるのだけれど、ウグイスやコジュケイの鳴く山を背に、流れ渦巻き淵を作る水を見つめ、竿を上げ下げしているうちは、義理を欠きウソをついたことを忘れている。思うのはただ、フワリとかすかなアタリがあって、それから竿先をはげしくしぼりこむような、でっかいやつが来ないかということだけである。
閻魔さまに申し上げます。ぼくは子どものころウソついたかもしれません。がいまのぼくは、とっても正直な人間で、ほかにウソはつきません。税務署へでもです。だから、年齢と健康が許すうち、アユ釣りのウソをかんべんしておいてくださいませ。
落ちアユ三話
深まさる秋
十一号台風の前に、相模川のアユは色づいているのがあった。落ちアュを児ると秋のわびしさが身にしみる。今年は少し早いようだ。
けれどもほんとうにアユの豪快な引きを味わうのは、この落ちアユの季節からでもあろうか。まったくの話、百グラム以上のアユとなれば、こっちの息の根がとまる思いだ。私はくやしいことに、百三十グラム以上のをつったことがない。足と心臓との関係から、思うがままの釣り場まで行けないせいもある。千曲川では百五十グラムがざらだそうだ。囮にかかると、河原を釣り師は競馬のように走らねばならぬ、と、こないだ立野信之氏が話していた。が、聞いただけで私は行けない。いまはもっばら酒匂か、でなくば本年無残な成績の相模だ。それも相模は舟からでなければやらない。酒匂は釣り場までの往復、バスかタクシーがきいて、足場がよく川へ立ちこまずやれるところだけだ。心筋梗塞で、ニトログリセリン以下いくつもの薬品を携帯し、向こう岸の釣り師にあおられても気にしまいときめ、休み休みやっている。あまりデカイのは来ない方が身のためだと、われとわが心に負け惜しみを言い聞かせつつ、竿を寝かし、秋空を映す水色に見入る。
それでいて釣り方はこのところ、コロガンかシャクリ専門だ。囮やドブからは、さだめし野蛮で下等なやつだと軽蔑されることであろう。落ちアユともなれば、またドブがつれだす。が、ドブの鈎すの細さは、大型ではどうも不安だ。囮は数を望めない上に舟でやると、私の腕前ではふなばたへぶつけてのバラシが多い。舟でやる私のコロガンは見た日よりはるかに体力がいらず、少なくともドブよりも疲れなくて、大型をより多く楽しめる、という打算からである。
もっともこないだ酒匂へ行った。午後いっばいやってたった二尾。だのに駅へきてみると、朝からで四十という人がいた。えい、たっしゃならなアと歯がみをし、この次の作戦をいま練っている。
釣り師の誇り
昨年の落ちアユのとき、いや、少しまだ早かったか。
相模の釣り宿へ電話したら、釣り帥が死んでまだ死体が上がらぬ、気味が悪いからくるな、と船頭さんから断わってきた。
場所はカネカケだ。胸まである深いゴム長をはき、腰に生かしビクをつけていたが、砂利穴の傾斜ヘズルズルとはいった。ゴム長は河原の石の上ではいたりぬいだりするだけでも骨が折れる。とっさにぬげるものではない。そこへ水が流れ込み、胸から下へおもりをぶら下げたと同じになった。
この釣り師の気持ちはよくわかる。竿を、たとえ一寸でも、遠くへのばしたい。砂利穴の危険は知っていたが、つい足が穴のふちを越したのである。
すぐ下流の荒瀬で、流される釣り師の姿がチラと見えたがどうにもならない。ウドマリの淵へ流れ込んだらしいが、前から大きかったこの淵が、砂利とりのため、さらに湖水のようになって、死体は四日間見つからない。
こっちはがまんできず、その四日目に出かけた。淵の上流に舟を出していると下手の舟からわめき声が響いてきた。死体が発見されたのである。いつも私が泊まるガケ下の小屋から、すぐ見おろせる場所だった。泊まったら淵の底から「おいでおいで」をしたかもしれない。
死人は、ゴム長の重みがあるから、水深五メートルの底に、四日間立っていたのだろう。腰のビクにはアユがはいっていた。どれも型ぞろいのいいアユだったと聞いた。釣り師は獲物を見せて誇りとする。気の毒ではあるが死人は、見てもらうことだけできた。せめてもの本懐であり満足だったろう。こちらの舟の私は、白木の棺が運ばれて行くのをはるかに見送り、念仏を唱えつつサオの操作にかかった。この日は豊漁だったと記憶する。ガケのセミが鳴きやみ、カラスの大群が川上へ飛んだ。そして私は淵にのぞむ小屋へひとりきり泊まり、太古に戻ったように暗くひっそりした夜をながめた。
国家と釣り師
空襲が盛んだったころにも、釣り師はアユを追い、爆撃をながめて肝を冷やした、という話を聞いた。それで思いだすのは狩野川の落ちアユだ。太平洋戦争の始まった年の秋深く、私はせっせと狩野川へ通った。
落ちアユがどこの川も十月十五日禁漁になるが、狩野川には禁漁がないと知り、ドブ釣りに出かけた。主として大仁の手前の田京だった。田んぼの間をぬけて出ると、荒瀬の手前の水がゆるみ、沈床の石を足場にしての、ほれぼれする釣り場があった。
ただしはじめはアユだけがお目あてだったのに、瀬のガンガンヘハリを入れると、めっぽう大型のハヤがくる。ハヤは、おもでなく上っぱりだけだ。上っぱりを、ヤマベ瀬釣り用のにとっかえた。 ハヤがおもしろくなった。午前中だけで四キロもつった。健康はまだ十分だったし、日帰りの無理がきく。たまには泊まったが、十一月の末までを通いつめた。そこへ海軍から講演旅行をせよという命令をうけたわけである。
新潟をふりだしに東北へ、本村毅氏が隊長で竹円敏彦、戸川貞雄氏などもいた。
山手樹一郎氏が世話役だった。いい気なものだ。樹一郎さんを先乗りさせたり酒買いに使った。十二月八日朝、盛岡の宿で真珠湾爆撃と聞き、すわ報復の敵機が東京へも来るぞと、その日東京へ戻ってきた。
私はこの講演旅行で狩野川の釣りがダメになったのが残念でたまらない。それでも戦雲が気になり三日ほど東京をはなれずにいたが、どうやら空襲の気配もなく、さらばと竿袋肩に、またも狩野川へ出かけてみた。国家の非常時を、釣り師は忘れた顔でいたいのである。しかし、行ってみると、アユはもういなかった。たった一匹だけつれた。ハヤもどうしてか少なかった。まるで川が変わったかと思うほどだった。川岸でカニ取りのおっさんと戦争の話をし、私は疲れて帰宅した。そのとききり、あの釣り場へ行ったことがない。狩野川台風のあとどうなったかと気になっている。
釣りと車
若いうちにすればよかったのを、しなかったばかりに損をした、と後悔することはいろいろある。
教訓めいた言い方をするなら、学問の勉強はむろんその一つだ。非教訓的には、道楽の各種もそのうちに含まれる。中学を卒業して五十年になるが、その中学の老友相会しての一席で、めいめいが女についての体験を、かくさず正直に語り合ったとき、その中の一人は、子どものときからの石部金吉、だまってみなの話に耳を傾けていたが、最後に叫んだ。ああおれは一生損をしたなアと。
その悲痛な声と表情を、あれから数年になるが私は忘れない。
老後は誰もそんなものだろうか。
私の後悔の一つは、そうなにも悲痛がるほどのことではないが、車の運転を習わなかったということだ。もっとも、まだずっと若かったころは、自分の車を持てるなどということは、夢にも思ったことはなく、したがって習ったとしても、タクシーかトラックの運転手になって、それをわが生業とするぐらいが落ちだったろうが、七、八年ほど前に、どうやら車を買えるようになり、買ったあとでがっかりしたのは、もう私の年では、車の運転を習えないということだった。
教習所へ通えば、習うだけは習える。法規も税務中告の説明書を読むほど骨を折らなくても覚えられるにきまっている。だから免許は簡単にとれるはずだが、その道の先輩に、悪いことはいわない、よしなさいといわれた。年が年だから、注意力が足りず運動神経が鈍くなっていて、半年ほどのうちには、ガッチャンコのパタンキューと死ぬ。でなくても、車がスイスイ走るのは、見ているほど楽なものじゃない。肉休も精神もひどく疲れる。ガチャンコがなくても、せいぜい一年ぐらいしか身体がもたない。新車ならポンコツになるまで、三年や五年は持つが死んだあとに車が残ってもつまらない。
死ぬのがいやだったら、貰った免許証は、仏壇の抽斗へしまっとくといいが、それもやっぱりつまらないだろうからねえ、というわけだった。
わが七十年の生涯に、知人先輩からうけた忠告のうち、こんなにも切実で掛引きなしのありがたい忠告はそう多くない。忠告にしたがい、私は車の運転を習わなかった。少々無理して、車はすでに三台買った。けれども結果として乗るのは、娘か娘の亭主、つまり婿どんが、どこへ出かける用事もなくて、といって家にいてもすることがなくて、そうして機嫌のよい時だけに限る。もう一つ、ガソリンがなくなりかけると、よく乗せてもらえるが、でないとダメである。したがって私は、せっかく車を持ちながら、私ひとりきりで、誰にも知らせないで行きたいところへ行くことができない。そのひとりきりで行きたいと思う場所は、誰にも知らせたくないなどというと、非教訓的な邪推をする人もあろうけれど、決してそんな意味の所ではない。誰にも邪魔されず、自然の中に人間はわれ一人というような孤独さにあって、ゆっくりのんびりと釣りのできる場所のことだ。
旅に出ることがたまにある。
列車はいくつかの名の知れぬ河を渡る。また窓の彼方に、瀬となり落込みとなり、曲がりくねった長いトロ場となって河が流れている。大きな有名な河の支流で、末は木曾とか天竜とか最上とかいうのへ入るのだろう。水面に雲を写し陽を踊らせ、岸は岩であったり河原が広がっていたり、柳や声の茂りが見え、ヨシキリが鳴いているかもしれない。古びた小さな舟がもやってあるとか、農具を洗う人の姿が見えたりはするが、釣師の姿は見あたらない。水量の豊かさもほどほどで、青く美しく澄み、魚がたくさんいるにちがいない。私はその河で釣りをしたくなる。けれども一瞬にして列車は走り去り、河が視界から消えてしまう。
そんな静かな河へ出かけたいとは思うものの、たいていそれは駅から遠く、不便なところにきまっている。泊りがけは構わない。農家へ無理にでも頼んで、蚤虱馬の尿する藁の床でも、釣のためとあれば我慢できる。しかし生まれつき足が弱く、とくに最近は歩けない。鮎ともなれば、生きのいいところを持って帰りたいから、重いアイスボックスも必要だし、立ち込みの長いゴム靴もあるのだから、荷物を持たせるための家来をつれていない限り、三キロ以上は歩きたくない。家来というのがまた、日当を出して頼めばあるだろう。ナニ、釣りのためなら高い日当も惜しくはない。けれども、釣りをする間、家来をポツンと待たせておくのは気が引ける。家来が退屈だろうな、気の毒にと思うだけで、釣りに浸り切れない。だったら、家来もいっしょに釣らせたら、ということになるが、それだと竿から仕掛けからゴム長まで、家来の分を用意してやらなくちゃならない。同好の釣り師はどうか。しかしこっちの荷物を持ってくれるほど友情ある釣師はあるはずがない。それに私は、ひとりきりで、誰への遠慮気兼ねなく、相手にするのは河の中の魚だけで釣りをしたいというのだから、同好の士の同行はありがたくないのだ。
すばらしいアナ場所を見つけましたよ、でかいのがウヨウョいます、立ち込まずに三間竿で十分、こないだは二十センチ級六十でした、いっしょに行きませんか、と誘われる。
そりゃ羨ましい、ぜひこんど、と私はばつを合わせて誘いに乗った返事をするが、内心いっしょに行くつもりはない。場所を教わり、足の便、宿の便だけは聞いておくが、実はひとりで出かける。
ひとりきりでないと、どうも堪能した気持になれないのだ。文壇にはザコ倶業部があるし、ほかに釣りの会がいくつかあって、釣りの競技会などをやっている。その写真を見たり記事を読んだりすると楽しそうだが、さてその仲間になれと勧められると、お断りを申し上げることになっている。釣りのだいごみは、漁獲の多寡を論ぜぬところにあるとするならば、技を競うことにないのは当然だ。ひとり天と地と空気と水と、そして魚を相手にすることだと感じている。死んだオカミさんをよく、いっしょにつれて行ったのは、オカミさんへの愛情からだ。もしくは、異心同体であるという潜在意識のせいだった、といまは解釈している。
相模の上流に、今年こそはと期待している私の釣り場がある。そこは舟がないと行けない淵だ。船頭さんが、私を乗せてそこへ行くと、私が竿を出してから、そこで釣れると見込みがつくまでは、そばでじっと私の釣りを見守っている。悪ければ、ほかへ舟を移そうという親切心からで、その点はありがたいと感謝しながら、見守っていられるのが、かなり欝陶しい気持がある。大丈夫、そのうちにここで釣れるのだから、ほっといてくれ、おっさんはもう帰れよ、と胸のうちで咳きつつ、でもほかによい場所があるなら、そっちもやってみたいなどと、心は千々に迷いつつ、川底の様子を探っている。実際は、場所を移った方が釣れたという経験が多い。とくに鮎は、舟がただ一間移動しただけで、釣果は十倍にも二十倍にも増えることがある。それをよく承知していながら、船頭さんを邪魔だと思うのは、よくよくのこと私がひとりきりになりたいからだ。
釣りをおぼえたのは、信州伊那の天竜川で、父親にあの土地でいう蚊がしら、東京でいう瀬釣りまたは毛ばりを教わったときだ。小学校の三年坊主だった。おぼえると、もうひとりきりで行くくせがついた。沈床の枠にはりが絡み、それをはずそうとしたら滑りおちて、ひとりだからすんでのこと溺れかけたのを、辛うじて助かってから、釣りには泳ぎも知らぬといけぬと思い、その夏から泳ぎに精出した記憶もある。三つ子の魂百までで、いまにいたるも釣りはひとりきりのものときめてしまっている。
そんなわけで、車を習わなかったのは一生の不覚。よく習熟していたなら、釣り仕度と仕掛けをトランクに納め、気ままに行き着いた先きの河のほとりで、インスタントラーメンの三、四日分を用意して車の中で寝てもいいから、釣りの三昧境に浸れるものをと、後悔したところでもう追いつかない。後悔の埋め合わせに娘夫婦に釣りを教えることにした。彼と彼女は、親父が親切で釣りに誘ってくれる、と思っているかもしれない。親切がないこともないが、本音は釣りを覚えさせたら、きっと二人が面白くなり、私を申で運び、よい釣場を探すことに協力するだろうという宏遠な計略である。
計略はほぼ図に当たった。婿どんがとくに釣り好きになったから、今年は鮎を手ほどきしようと思っている。度がすぎて、本業の歯科医を怠け、患者をほったらかしにする危険もあるが、そこは教え方だ。当たりばりの選び方など、ほんとうには教えずにおこう、とひそかに考えている。
自分も ”鮎とか鯛とかは釣ってきて食すもの” という感覚が染み付いてしまっている。
鮎や鯛を買ってくるなどとは思った事もない。
13.釣友達 瀧井孝作
相模川は昭和22年に相模ダムで遮られてしまい、大アユ釣り場はダムの底に沈んだ。
桂川は相模ダムの上流である。
釣友達
同声相応同気相求
一
昭和二十六年、六月十九日。朝淡く曇つて、釣支度にレインコートも用意して、私は、七時十分に宅を出た。八王子駅七時二十九分発の下り列車で、鳥沢の桂川に出かけるので。けふは、釣友の桜井書店の桜井均さんが新宿からこの汽車で。また、今年初めて釣友達になつた、能役者の今春流の桜間道雄さんと、同じく幸清流の小鼓の宗家の幸圓次郎さんと、二人づれがこの汽車でくる筈で。私はけふはこの仲間を案内する筈で。
―― 私は昨日は、桜間道雄さんと二人づれで、鳥沢駅の下で、友釣をした。道雄さんは鮎釣は未だ初心で、昨年初めて幸圓次郎さんと共に大月の方に行つて、友釣で三尾釣つたが、まだ独りでは、囮鮎の鼻環をうまく通すことができない位と云ふ話で、また、友釣の仕掛も私共の仕掛と同じ物をほしいと云はれて、私は、友釣の仕掛を一通り造つてやつたり、また昨日は手始めに、囮の鼻環も附けてやつて、「あとは自分でやりなさい、自分でやらぬといつまでたつても覚はらないから」と云つたりした。そして、鳥沢駅の真下の今年好い瀬の出来た釣場で夕方までに、道雄さんは七尾釣れた。私は二十尾釣れた。「どうも囮を痛め相で、自分では只一遍付け替へたきりですが…… 」「それでは駄目、同じ囮を長く曳張つてゐては、弱つてしまふから、囮は、次ぎから次ぎ新しく釣れた元気な奴と取替へなけや、茲で一つ掴み出して鼻環を附ける稽古をしなさい」と、夕方、川からあがる時、水際で話したりした。茲の桂川は、六月十五日の解禁の日に、雨で、二三尺も水が出て、昨日はその出水の濁りが澄んで、澄み口なので魚が活躍してよく釣れた。この分だと明日も釣れるから、小金井在住の道雄さんに、同じ小金井在住の幸圓次郎さんに知らせて、明日は誘ってくるやうにと云つた。桜間道雄さんは幸圓次郎さんとは、この六月十三日に、相模川の荒川橋にドブ釣に行つたといふ話もした。その日一向釣れなかつたが、圓次郎さんは、夕まづめには喰いがたつから日のくれるまで辛抱しようと云ひ、暗くなるまで岩の上に坐ってゐて、川からあがったのが晩の九時で、バスも無く、荒川橋から橋本駅まで二里程歩くことになって、十一時すぎると電車もなく、宅に帰れないかと思ったが、恰度トラックが通り掛ったので、トラックに乗せてもらって、漸つと戻った。「圓次郎君は辛抱づよくて実に釣好きですからネ」と道雄さんは話した。私はこの話から、一向釣れないのに日のくれるまで共に辛抱した道雄さんも、亦、釣熱狂だナと思った。このような釣り友達に、釣れる時に釣らせたい気持で、明日は必ず釣れるから、圓次郎さんも誘ひなさいと云った。私は亦、桜井書店に電話で誘ふことにして。桜井均さんは、以前に佐藤垢石さんなどに伴われて、魚野川の小出町あたりや富士川の岩淵や狩野川の修善寺、嵯峨沢などにも出かけて、私も近年相模川の田名や桂川の鳥沢に同行したが、桜井均さんはこんなに友釣に出かけてゐながら、いつまでも初心のおもむきで……。ともかく今年の桂川は魚が濃く、それに今は澄み口で誰にでも釣れるから、この機会はのがせない、で、電話をかけたら、悦んで、出かけてくると云つた。―
―
私は、七時十分に宅を出たが、停車場の見える所にきて、釣支度の草鞋をわすれたと分つて、宅に草鞋をとりに戻つて、そして、八王子駅の歩廊に行つた時は、恰度汽車が入つてきた。汽車の窓に桜井均さんが顔出して、呼んだので、私はそこに行つたが、前の方から二両目に、桜間さんと幸さんと二人づれがゐる筈で、私はすぐ探しに行つた。
二両目は、空席がいくつもあつて、中程の席に、能舞台で顔馴染の幸圓次郎さんが、一人でゐた。私は近づいて、「八王子の瀧井です」と云つたら、「あ、初めまして、私は、幸圓次郎です」と初対面の挨拶され、私の方はこの能役者の顔は目馴染だが、圓次郎さんの方は初対面に相違なかつた。「桜間さんは」と尋ねると、「道ツちやんは、今、あんたの方を探しに出ました」と、さう云はれた、道雄さんの方は歩廊に出て立つてゐた。それで、私はまた中程の車両から、桜井均さんを伴つて共に二両目の車室に移つて、四人づれは共に腰かけられた。桜井均さんは二人に初対面で名刺も出し、両人の能役者は名刺も持たない方で。
幸圓次郎さんは、将棋の木村名人と顔が似てゐる所があつて、眉や目もとはそつくりで、亦、恰幅がよく、殿様然として、江戸ツ子で、いくぶん巻舌口調にみえた。桜間道雄さんの方は、小柄で、かざりけのない率直の方。話声は低い枯れ声で、この人から、彼の謡の地頭の大きい調子が出るとは、一寸思はれなんだ。列車が動き出してから徐ろに、圓次郎さんは、朝飯をたべはじめ、折詰の海苔包のにぎりめしを箸ではさみながら、「けふは、食欲が無エやうだ、元気が無エンだ」と云ひ、道雄さんは「ずうつと、飲みつづけだろ」と云つたりした。
私は、桜井均さんとは、去年の解禁の日鳥沢駅下に同行した以来で、普段は会ふ折がなく、恰度一年目で出会つたが、気持はちつとも渝らなかつた。私は、八王子の釣士仲間とも、普段の交際はない方だが、鮎釣の時節になると、急に親しく往来して、普段のつきあひもなしに鮎釣の時節に限って、ひどく親しく話し合つて、それがをかしくも思はれなかつたが… …。
「昨日は八王子の連中は、鳥沢の上ミ手の吊橋の方で、皆が、三十、四十、五十尾も釣つたやうで、今日もそつちに行つた筈です。出水で水垢が流れて、垢の残つた所に魚が集つてゐるから。僕らはずつと川上ミの、鳥沢と猿橋との中間位の所に、好い場所があるからそこに行きませう」と云つて、今日は大分歩くので、成べく身軽にして、川越しもするので、ズボンなども脱いだり、魔法瓶や何かの持物は、駅前の宿屋にあづけたらよい、と話した。幸圓次郎さんは、 ニツカーポツカーズのズボンに、きやはんに地下足袋で、「私は、このまま川にたちこんでいつもぬらしてしまふ方です」と云つた。桜井均さんは、背広に下駄ばきだから、宿屋にあづける事にした。
「僕の囮箱と桜井さんの囮箱と、両方に囮鮎を買つて入れて行きませう」と云つたら、桜井さんは、あみ棚から荷物を下ろして、囮箱も出した。その時、新刊書三冊、私の手に渡した。「ヤスペルスの翻訳ですが、売行はどうか分らんけど、原著者から翻訳権を取つたもので、刊行の責任があるので出しましたが」と云つた。これはヤスペルスの論文を訳した本、「戦争の責罪』『哲学と科学』『ニーチエとキリスト教』といふ三冊で、私は、「むつかしさうな本だが、現在の独逸の人の考へが分るから、折を見て読んでみませう」と云つた。又、桜井さんは、小瓶入りの″食物保存剤ブレザバリン,
といふ瓶も取り出して、私に一つ呉れた。私は、その小瓶を手にとつてみて、今から十数年も以前に、″生魚の防腐剤ハンザミン″といふ薬が売出されて、私はそれを飛騨の山家ヘ山女魚つりに持つて行つて、これは「山女魚」といふ短篇の中に書いた記憶があるが、その″ハンザミン″に似たものだらうと考へたりした。
鳥沢駅に著いて、釣士は、二三十人余り下車したが、八王子の連中は大方この前の汽車で行つたやうで、知合ひには出会はなんだ。駅前の宿屋で、囮箱四尾と入漁券も買つて、圓次郎さんと均さんとは草鞋も買つて、大型の魔法瓶や背広服やレインコートなども、風呂敷包にして、預けた。
空は情れて、上天気で、四人づれは、街道筋を西に向つて歩いて行つた。釣場に出向く時は、気持がはずんで、解き放されたやうで。亦、鮎の川の山里は、目にも快かつた。茲の街道筋では、川原の広い釣場所が目の下に見えて、「彼所の吊橋の上ミ下モで、昨日八王子の連中は相当釣つたのです」と指さして云つた。昨晩電話かけた、メリヤス工場の中山老は、一番汽車で茲の吊橋の下に先に行つて、囮をとつておくから来なさい、と云はれたが、今、四人づれでじやまするのはわるいので、吊橋の方には行かず、尚街道筋を上ミヘ歩いた。十数丁歩き、街道筋の疎らの人家の前には、水道も引いてあり、水道栓の蛇口捻つて、囮箱の水も替へた。
猿橋のほうから土地の年寄が歩いてきて、私共に声かけた。「もう川から上つたのか」「これから川へ下りる所だ」「昨日、猿橋の方では、八十め釣つたのが一番の竿頭ぢやつた」「それは少ないネ、八十匁ぢや」と、私は云つたりして、土地の釣好きの年寄とは別れた。が、あとで考へたら、八十めと聞えて、目方で八十匁七八尾位かと思つたが、これは八十匁でなく、「八十尾も釣つたのが竿頭ぢやつた」と云はれたわけで、魚の集つた所では、八十尾の大釣した人も、昨日の水色の工合では、本当に思はれた。猿橋の大淵の肩の瀬なら大釣もあり相に考へられた。
今日の目的の釣場に向ひ、畑道から、山坂の急な小径を下つて、川原に出た。昨年私は茲で良い釣をした場所で、大きい石がいくつも川の中に在つて、型のいい鮎がつれたが、今みると、大きい石は、大分埋つて、流れも平たく浅くなつた。四人づれは、草鞋をはき、釣竿を出し、支度した。私は素草鞋、圓次郎さんと均さんとは地下足袋に草鞋をはいた。道維さんは地下足袋は脱いで、毛糸の手編の足袋の上に草鞋をつけた。昨日もこれで、水色の美しい毛糸の足袋は一日で穴があいたが、道雄さんは、足の先が水で冷えると痛い、これは、足をはげしく使ふ能の稽古から、足の先は冷えると痛む、(例へば、能の獅子などの場合、膝を出げて下にドンと坐つたり、すぐ起ち上つたりする場合に、足の指先が反り返る形で弾条の工合になり、足の指先で体全体を支へるわけで)これで、足の先を大切にしてゐる、と話した。圓次郎さんは、手甲を附けた。囃子方で手を大切にするわけで。
私は先づ川に入つてみて、川底に水垢もないし、四人共にやれる場所ではないやうで、下モ手は好い瀬だが七八人もゐたから、「向う岸では一人位入つてやられる、それから、彼所の淵の下モの長い一本瀬の方がやり易いから、先きに行つてごらんなさい」と話して、桜井さんは、川を徒渉して行き、向う岸ではじめる事にした。圓次郎さんも小さい囮箱に囮一つ入れて、ズボンもぬらして対岸に渉り、川原を下つて行つた。道雄さんは少時見物してゐたが、これも対岸に渉つて、向う岸から亦見てゐた。
私は、昨年釣れた石のまはりに、囮をいれてみたら、やがて一尾釣れた。又、一つ釣れた。しかし川が広いので、四間半竿一杯に出して水に立込んで、一尾掛ると岸の方までジヤブジヤブ歩いて引ぱつて来なければならず、不馴れな人には、骨の折れる場所で、すすめることはできなんだ。私は竿を措いて、対岸へ川越して、向う岸に待つてゐた道雄さんに、元気のよい囮を一つやつて、「圓次郎さんが下モ手の方でやつてゐますから、下モ手の一本瀬の方が短い竿でもやり易いから、そこへ行つてみなさい」と云ひ、道雄さんは下モ手に向つた。その時、桜井さんは、大石の間で一つ釣つた。これはいい工合だと見て、「この辺の大きい石のまはりをさぐれば、いくつか出ますヨ」と話して、私は亦、川越して、元の釣竿を措いた所に戻つた。上ミ手の瀞の石の間には垢も残つて、好い川に見えた。水の流れが平らにゆるやかで、静かに釣らぬと魚が散つてしまふやうで、一人で釣るほかなかつた。この瀞で二つ二つ釣れて、しばらく釣れないと、又下モ手の瀬や大石の間を漁つたりして、五六十間の長さの区域を行き戻りして、探り釣りした。
十五六の少年がきて、話した。「昨日、おいらは二十も釣つたヨ」「どれ位の大きさだネ」「おめえの囮位はあるサ」放流鮎だから型は大体同じで、子供に二十位釣れるなら、この辺は魚が濃いと思はれた。「友釣はつれたかネ」「おいらは友はやんないけど、他の衆は大方友釣だヨ、けど、今日は友よりサクリの方が釣れるべ」少年はこんな事を話して、下モ手の瀬の方に行き、桜井さんの竿を出してゐる方に、桜井さんと向ひ合つて瀬ザクリをした。
私は一人で十尾程釣つた間に、日も高くのぼつて、日は今真上に見えた。弁当を入れた背負籠の所に行き、時計をみると十二時。まだ茲では釣れさうだが、皆の方に行つて、昼飯にしようと、籠も背負つて釣竿を肩に囮箱さげて、対岸に渉り、桜井さんに「昼飯にしませう」と誘つて、共に下モ手の一本瀬の方に場所替へした。
淵の開きから流れだす、瀬頭の所に、道雄さんと、圓次郎さんと、二人がゐた。道雄さんは、十以上も釣れたが中で三尾つり落し、二尾は活しビクから跳ね出して逃げられたと話した。圓次郎さんの場所は、荒瀬になつたやりにく相な所で、囮が弱つて口を明いてゐたのを曳寄せた。「この荒瀬に垢はありますか」「垢は、ごくうすいやうですネ」と話した。
そして、四人づれは、川原で昼飯にした。圓次郎さんは、無口で悠つたりしてゐた。無口は、けふは元気が出ないせゐかとも思はれた。道雄さんは、ビクから逃げられたのと釣り落しを、惜し相に繰返した。私は「鮎釣も年季を入れなけや、謡に年期を入れて上達するのと同じですヨ」と云つた。均さんは、「けふは手始めに、囮の鼻から血を出して、血をみたら囮が可哀相でまた囮箱に戻してやつたが、又思ひ返して鼻環を通して、曳出してみたが……」と話した。均さんは、へんに気の弱いやうな、初心のやうな所のぬけない人にみえた。
昼飯のあと、私は川検分に、下モの方まで山岸伝ひに行つてみた。茲は三丁余り連続の長い一本瀬で、激流と緩流と大石とのつづく、実に良い友釣場所に見えた。釣士は両側から竿出して立ち並んで、私共が割込む所もない位に、賑かに見えた。ずつと瀬尻の方に、八王子連中が居て、私は顔馴染の釣士の某氏に、「どうですか」と尋ねたら、某氏は「ここにきてわたしは十ばかり釣りましたが、すぐ下モの建亀は昼迄に三十位釣つたし、向ひに見えるのは菊池原さんですが、彼所では二十位つれたらしい」と云はれ、私はその方の釣士を見た。建亀といふ選手は、汀に休んで笑顔で、小柄の菊池原老は、水に立込んでしきりに釣つてゐた。この連中は、昨日は吊橋附近にゐて、今日は茲を見込んで茲までのぼつてきたらしい。
私は、瀬頭の所の、けふの仲間の傍に戻つて、私もわりこんで竿を出したが、稍ゝ窮屈で、午前の場所の方に、桜井さんと共に戻る事にした。背負籠は茲に措いて、釣竿と囮箱だけ提げて。私は、道雄さんのやつてゐる場所を見渡して、目の前からすぐ上ミの瀞瀬を指さして、「このトロはまだやらないでせう、茲からあすこの淵の開きの、水かぶり石のあたりまで、囮を入れて、静かに撫てみなさい、きつと釣れますヨ」と話した。
川原を釣士連は、上ミヘ下モヘ、やはり移動したりして、鮎の川は実に賑かに見えた。私は午前の場所の向ひ側から竿を出しながら七、八尾釣つた。午後三時頃、瀬頭の方の籠を措いた所に戻つてみたら、長い一本瀬の所の釣士連も移動して、場所はすいてゐた。
桜井さんも又戻つてきた。
私は、圓次郎さんに、「夕方五時半の汽中で帰りますか、五時半の次の、七時五十分の汽車にしますか」と、きいたら、「ゆつくり遊んでゆきませうヨ」と云はれた。私もその傍で竿を出した。圓次郎さんは、囮箱と竿を持つて、上ミ手の淵の開きを渉つて、向う岸に移つて、向ひ側から竿を出した。私共が茲にきたので、何気なく向う岸に移つた、その神経の細かさも宜かつた。私は圓次郎さんの釣つた跡の荒瀬に、囮を入れると十五匁位のがつづけて二つ釣れた。それからまた二十匁位の成長鮎が一つ釣れた。これまでは大方、十二三匁の若鮎ばかりだから、この二十匁鮎がばかに大きく思はれた。
夕方川の水が減つて来て、囮箱を沈めて石でおさへて措いた、その石がすつかり頭を出して、水の減り工合が見えた。荒瀬の水の勢もそがれて、減水が目立つた。降雨の出水から、常の平水に戻つたわけだが、こんなに水量が少くては、魚のかくれ場所もなく、釣手が多いから、魚は皆攻め切られて、放流鮎も大きく育つひまがないかと思はれた。兎に角、こんなに攻手が多くては、放流鮎は目にみえて減る一方だと思はれた。
夕景の七時に、川からあがる事にした。私共は淵の開きの砂川を渉つて行き、共に、草鞋もぬぎ、ズボンも附けてから、囮箱の水を切つて鮎は野締めにした。私は、数へたら、二十二尾、道雄さんは十三尾、圓次郎さんも同じ位、均さんは十一尾。「道雄さんの釣つた場所は、実にやり易い所で、淵の開きの流れ出しの、好い垢のある所で、今日の一等席ですョ、僕が一日中やれば、三四十尾も釣れたでせう」と話した。川原づたひに下つて、下モ手の『三ツ石』といふ有名なドブ釣場の、岩石の淵の景色も看えた。圓次郎さんは、「これからドブ釣をやれば釣れるがネエ」と、残り惜し相で、この人は夕釣のくせがあるらしかつた。私は、「烏沢もこんなに釣手が集つては、たまらないから、大月の方がまだしづかで宜いでせう、こんどは、大月に出かけなさい、大月の学校下の釣場は、長い平川で釣り易いでせう」とすすめた。
日ぐれの鳥沢の町に入つたら、町の街路の上では、麦扱むぎこきの筵を片付けたり、山のやうな麦埃麦わらも、焚いて燃して、わら灰に拵へてゐたりした。
二
六月二十四日。第四日曜。喜多会の例会能の見物に、染井の能楽単に出かけた。私は、鮎つりにも出たかつたが、能も見たかつた。――
鮎つりは、二十一日に桜井均さんと,二人づれで、猿橋の枝川の葛野川に入つて釣れず、ついでに大月に廻つて、大月でも一向釣れず。それから昨日は、桜間道雄さんと桜井均さんと私と三人づれで、猿橋と鳥沢との中間の、例の場所に行つて、こんどは余り場所を移動せずに一日辛施して、相当に釣れたが。――
けふの能は、後藤得三さんの『歌占』と、後藤栄夫さんの『杜若』。二人共に私の心持でのひいき役者だから、これはかねて見たいと思つてゐたので、けふは染井に出かけた。私は連日の釣行で、体が綿のやうに採みほぐされた風で、能の見所にぢつと坐つてゐると、眠気がきざして仕方がなかつた。得三さんの『歌占』は、直面で、力づよくて亦滋味があつた。ヂカの味が快かつた。『杜若』が始つて、囃子方の小鼓は、みると、幸圓次郎さんが出てゐた。番組には他の名前で、今日は圓次郎さんが代役で出たわけで、私はけふ茲で会へるとは思ひがけなかつた。私は『杜若』がすんだら、楽屋口に訪ねて、圓次郎さんと釣の話も宜いと考へたりした。けふの『杜若』のシテの女面は、喜多会のいつもの小面とちがふ、初めてみる小面で、格別何といふ特長はないけど美しい面だと見た。衣装も見事な唐織が出た。栄夫さんに花をもたせようとの楽屋の方の心持も思はれた。栄夫さんも無事に勤めた。
能がすんでから、私は、私の伴れには先きに帰つてもらつて、一人残つて、楽屋口で、喜多節世さんに出会つたので、「幸圓次郎さんに会ひたいのですが、此所にゐますから、御用がすんだら、茲で会ひたい、と伝へて下さい」と云つて、喫煙室で待つてゐたら、節世さんが少時して出てきて、「楽屋の方へおいで下さい」と、案内された。鏡の間を通りぬけて、広い楽屋の長い縁側を通り、カギの手に曲つて亦縁側のある、裏の方の離れざしき風の室に、案内された。私は、能楽堂の楽屋といふものは、けふ初めて見たわけだが、わりに広広として、茲は楽屋の方が表の見所よりも広い位に思はれた。尤も、茲は、大正八年に、紳士能の連中が建築したもので、楽屋の方は格別に悠つくりした間取りに造つてある、と云はれたが…… )裏の離れざしき風の囃子方の楽屋も十畳余の広さで、赤まうせんを敷いた所に、大柄の圓次郎さんは、肥えた頸すぢやら二の腕やらの汗を拭きながら、休んでゐた。私が行くと、「先日は、お世話かけました、有難うございました」と挨拶された。それから小鼓をはづして、古い蒔絵の胴は胴の袋に入れ、美しい色の鼓の皮は円型の袋に入れ、傍のスーツケースの中に片付けた。洋服が壁に掛けてあつたが、圓次郎さんは未だ紋付袴のなり悠つくりして、他の囃子方はさつさと片付けて、帰つた。喜多実さんが『杜若』のシテの腰巻にした、赤地に金色の美しい唐織を持つてきて、「けふは涼しいから大丈大と思つて、いい唐織を出したが、やはり失敗した、よく失敗するんだが」と、汗になつたその唐織の裾などひろげて、囃子方の大鼓をあぶる大きい火鉢の上にかざし、乾かした。六平太翁が見えて「それが乾いたら、よく風を通してからたたむやうに」と云はれたりした。大切な唐織と見た。
この楽屋らしい有様もみて、私は、圓次郎さんと釣の話に移つた。まづ、先日大月の方に行く事をすすめておいたので、大月に、私共が行つて失敗した語をした。「二十一日の午後にちよつと大月の方に行つてみましたが、大月橋の下に降りてみると、今年は水量が昨年の半分位で、あすこは大きい石の間に小流れがあるやうな川になつて、駄目ですネ、それで川伝ひに浅利橋といふ橋の方まで下つて、浅利橋の上ミ手にはいい川があつて、大勢やつてゐたから、そこで二時間程やつて一つ釣つたきりで、帰りました。瀬ザクリでは出ますが、魚は小さい、大月も水量がすくないから、石に泥垢がついて、鮎は育ちません、今年は昨年ほどよくありません」と話した。圓次郎さんは黙つてぢつと聞いて、私が話し終ると、「私も、大月へ行つて、ちよいと面白い釣をしましたヨ、二十日に、一人で大月へ行つてネ、あすこの入漁券を売る所の人と一緒に川へ下りて、囮もわけてもらつて、学校の下でやつてみましたが、十時頃までに二つ釣れたきり。下モの方なら釣れると云はれて、歩いて行くと、小さい淵とも云へない溜りツコがあつた、石の頭が、三つ四つ並んで水が流れこんでコボコボして、小場所ですが、囮をいれてみたらすぐ掛かる、又いれるとすぐ掛かる、二間位のせまい所で、どこにいれても、グ、グイと掛かって、魚は大方これ位の四五寸で、六寸位のも十幾つ交って、四十も釣れました。さう大月橋の下のすぐ上ミ手の所です、夕方ドブ釣もやって帰りました、家に帰ってかぞへたら、四十には足らん三十八でネ、小さいけれど」と云われた。私は、はじめに大月が駄目だと云ったから、ちょっとやられた恰好で。
「私共はまた昨日は、先日四人で行った例のあすこでやりましたが、桜間道雄さんと桜井均さんと三人で、私は二十、桜間さんは十七、桜井さんは十三釣れて、二人はすっかり友釣のファンになつて、又明後日、火曜日に、行かうと云ってゐましたが、如何ですか、私は仕事がせはしくなるので出られないけど」と話した。「私は旅行に出るので、当分行かれないと思って、むりに二日つづけて行つちまつたんでネ」「旅行はどちらです」「会津の方から、越後佐渡の方にも行きます、来月の五日に帰つてきて、それからまた北海道の方にも行き、北海道では、山女魚釣りもしたいと思つてましてネ、来月の六日頃にはまた行けます。今度の火曜日には、あの二人が行けば、いいコンビでせうネ」と云はれた。
道雄さんと均さんとはいいコンビだと云はれ、これはズケリとした毒舌だと思つた。圓次郎さんはゆつたりとした中に、亦こんな辛辣な気ツ風もあると分つた。毒舌と云つても、親し味からだが、ヂカなズバズバした所は快かつた。能役者には、かういふ気ツ風も有つて然るべきだ、と、能の厳しさからも考へられた。
 |
左から井伏鱒二、土師清二、瀧井孝作
昭和前期、岐阜県馬瀬川での友釣姿
皆足には草鞋を履いている。
|
14.依田川の牛 島村利正
依田川は、しなの鉄道大屋駅の下手で千曲川に合流する。
現在丸子町は合併で上田市となっている。
依田川の牛
千曲川の支流になる、長県野、丸子町のほとりを流れている依田川は、なかなかいい友釣りの川である。ぼくは数年前、二、三人の仲間と一緒に出かけて、おもしろい釣りをしたことがあるが、そのとき、最高の獲物、五〇匁の大アユを、危うく牛のためにバラしそうになった、トンだ経験がある。
町を出はずれた上流には、いくつものいい瀬がつづいていて、都会を遠くはなれたこの川には、釣り人の影もまばらで、ぼくらは上下にわかれて、段々に釣りあがっていった。一つの瀬から、二、三尾を拾い釣りのように釣りあげると、すぐに次の瀬に移ってゆく。昼飯までには釣りあがることにして、飯のあとは、逆に釣り下ってくることにした。
第一日目は二四、五尾。二日目は三〇尾を越えた。いずれも三〇匁ぐらいのアユである。二日目の夕刻、町の近くまで下ってきて、橋の上方に、まだ竿を入れない、長い大きな瀬がのこっている のに気がついた。釣り仲間はもう竿をたたみはじめていたが、ぼくはふと欲を出して、この瀬をひとつ試してみようと思い、元気そうな囮りアユを通い筒に入れ、その瀬がしらにそっと近づいていった。
「お―い、まだやるのか」
と、仲間が遠くから声をかけてきたが、ぼくは通い筒をちょっと高く差しあげて合図しただけで、声では返事をしなかった。こういう大きな瀬には、どんな奴がひそんでいるか知れないのだ。
ぼくは瀬がしらから、その瀬を見おろしながら、囮りアユの鉤の具合を丁寧にしらべた。そして囮りアユを静かにおよがせて、白い飛沫をあげている激流のなかに、ぐいと落しこんでやった。
するとすぐに、ガガッときた。猛烈な手応えは全身にひびいて、ぼくは三〇メートルほど、竿をつよく握りしめたまま、夢中で、アユと一緒に川ふちを駈けおりた。その辺から瀬はいくらかゆるやかになっていたが、掛りアユはよほど大きな奴とみえて、いっこうにヘチに引きよせられない。
それどころか、ぐんぐん引っ張る強引なちからは、囮りアユをひいて、流心へ流心へと向かい、そして更らに下流へ向かって、力いっぱい逸走してゆこうとする。
ぼくの竿も腰も弓なりにまがって、その引きにジリジリ引っぱられていったが、ふと気がつくと、 一〇メートルほど先きの川ふちに、黒い巨きな雄牛が、こちらを向いたまま、悠々と寝そべっているのが目にのった。ぼくはその瞬間、う―
ンとうなるような気持になった。しかし、アユの引きはいっこうに衰えない。あと数歩も下がれば、完全に、その巨牛にぶつかってしまう。牛がもし猛然とたちあがってきたら、アユどころの騒ぎではない。しかし、この巨アユも、ここまできてバラしたくない。神に祈るとは、こういうときのことをいうのだろうか。
ぼくはそこで、足にちからを入れると、そのまま動かず、懸命の操作で、竿をねかせてジリジリと引きよせた。眼の前までよせられてきた掛りアユは、水のなかではあったが、囮りアユの倍ほどもある大物だった。ぼくは道糸に手をかけると、だんだんに手操りよせ、ぐいと引き抜いて、手網のなかに素ばやく取り入れた。そして思わず、大きな呼吸をついた。するとそのとき、なんと思ったのか、眼の前の雄牛が、とつぜん「モウウン」と、大きくないた。ぼくはおどろいて牛をみたが牛の表情は、眠いような眼をしたまま、例の、ものに動じない、何事もなかったような面構えで、ただ口をモグモグ動かしているだけだった。
”ぼくは通い筒をちょっと高く差しあげて合図した”と書かれている。
「通い筒」 懐かしいなー。 昭和50年代まではよく使われた。
今時、通い筒など使う人はもういないだろうなー。
15.鮎の食べ方 川端 進
やはり、あゆの食べ方はあれにかぎる、といっている。
昔からその食べ方は、産地で食すものと言われている。
鮎の食べ方
あらい
せごし
甘露煮
粕漬け
ぎょでん
煮びたし
あゆこく
あゆなます
あゆのフライ
まだまだあるあるあゆ料理
あゆずしにあゆ飯にあゆ雑炊
葛の葉蒸しやあゆの天茶なんてものもある
だがなんといってもあゆを食べるには
あれにかぎるねあれにね
簡単な料理のひとつ
あゆの塩焼き
その塩焼きなんだが
釣りたてのあゆに竹串をうち
近からず遠からずの炭火のまわりに頭を下にしてたて
あぶらがすっかり落ちつくすまで焼くんだ
焼きあがったばかりの熱々のやつを
炎天下汗をたらたら落としながら
頭と尻尾を両手でつかみ
腹からがぶり
とやるんだ
がぶりと
火傷かくごでね
どう 食べてみたい
とは思わない
――詩集「釣人知らず」より――
釣りたてを食べられるのは釣り人の特権みたいなものだ。
あぶらがすっかり落ちつくすまで焼く?のかどうかは好みの分かれるところだろうな。
(その3)へ
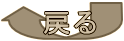


![]()

