

+α Web絵本 お孫さんがいらっしゃる方はご一緒にお楽しみ下さい。




1.尺鮎誌 (「つり姿」 昭和17年刊)
「尺鮎誌」は、鮎釣をこよなく愛した佐藤垢石が標した
在りし日の奥利根挽歌である。
時空を超えて心に深く沁みる。
尺 鮎 誌
一
私は、利根川の水に生まれ、利根川の水に育つた。
利根川の幽偉にして、抱擁力の豊かな姿を想ふと、温き慈母のふところに在るなつかしさが、ひとりでに胸へこみあげてくる。私は、幼いときから利根川の水を呑んだ。泳いだ。釣つた。
上州と、越後の國境に聳え立つ山々へは、冬のくるのが早い。十月下旬に、もう雪が降る。大赤城の山裾は長く西へ伸び、榛名山の裾は東へ伸びて、その合する峽の奥に白い頭を尖らした山々が私の生まれた平野の村から、遙かに望める季節になれば、もう秋も終に近い。
尖つた山は、武尊嶽だ。子持山と、小野子山を繋ぐ樽の上に、圓い白い頭をだして下界を覗いてゐるのは、谷川嶽である。その隣りの三角山は、茂倉岳だ。
上越國境を信州の方ヘ、遠く走つてゐるのは三國峠の連山だ。これも白い。大利根川はこれ等の山の雪の滴りを、豊かに懐に抱いて下つてくるのである。
だが、大利根のほんたうの水源は、それ等の山々のさらに奥の奥に隱れてゐる。水源は奥山の巨巌に自然に刻まれた阿彌陀如来の立像の臍の穴から、一滴づゝ落つる水であると父母からきかされた。少年の私は、父母にも替難き利根川の水の源に瞳れて、少年幾たび大刀寧岳の姿を、夢に描いたことであらう。
水温む春がくれば、鮠を釣つた。夏がくれば、鮎を釣つた。秋がくれば、木の葉に親しんだ。冬がくれば、寒寄りの鯎が道糸の目標につけた水鳥の白羽を搖する振舞に、幼い胸をときめかした。
大洪水がくると、上流から大木が流れてきた。家も、馬も流れてきた。初夏の夜、しめやかな雨が降ると、東南の微風が訪れて、利根の瀨音を寝てゐる私の耳へ傳へてきた。その瀨音が、忘れられぬ。
眞夏がくると、川千鳥が、河原の上を舞つた。千鳥は、河原の石の下へ卵を生むのである。少年の私は、孵つたばかりの千鳥の子を追つて、石に躓き生爪を剥がして泣いたことも、二度や三度ではない。
秋がくると、北風が流れの面を、音もなく渡つた。私は、その小波を侘しく眺めた。
冬。利根川は、うら枯れた。
春になれば、私の村は養蠶の準備に忙しかつた。母と姉が、汀に近い底石に乗つて、蠶蓆を洗つた。洗ひ汁の臭みを慕つて、小鯎の群が集つてきた。四月の雪代水は、まだ冷たい。冷水に浸つた母と姉の脛が眞紅に凍てた色は、まだ記憶に新だ。
もう、下流遠く下總國の方から、若鮎が溯つてくる季節は、間もないことであらう。
二
私の少年の頃には、鮎釣に禁漁期といふものがなかつた。それは、私がよほど大きくなるまでそのまゝであつた。
そんなわけで、私は五六年の頃から、父のあとへ従って、村の地先へ若鮎釣に行つた。やさしい父であつた。釣の上手な父であつた。五十年も昔には、鮎は隨分數多く下流から溯つてきたのであらうが、それにしても父の鈎へはよく掛つた。いつも、大笊の魚籠へ鮎が一杯となつたのである。
毛釣を流れに沈めて二三尺下流へ斜めに流し、僅かについと竿先をあげて鈎合はせを呉れると、三四寸の若鮎が一荷づゝ掛つてきた。そのときの魚の振舞が、手に響いてきた少年の感觸は、忘れやうとして忘れられぬ。
父は、健康の關係から、大して友釣を好まなかつたけれど、大きくなると私は友釣を習つた。吾妻川の毒水のために、私の村あたりは面白い友釣がやれなかつたので、私は村から五里上流、利根川と吾妻川との合流點から上流へ遠征したのである。合流點から上流は名にし負ふ坂東太郎の激流と深淵の連續である。白井の簗、雛段、樽、天堂、左又、宮田のノドット、龍宮方面へと釣り上つて行つた。
とりわけ、宮田のノドツトには大ものがゐた。一町も下流へ走らねば、掛つた鮎が汀ヘ寄つてこなかつた。猫瀧、芝河原、長つ瀧、圓石、櫻の木方面の釣興も素敵であつた。初心のころ、圓石の流心で大漁したことは、私の釣の歴史に特筆したい。芝河原では、不漁のために、鮎の習性について、いろいろ敎へられた記憶がある。猫瀧は凄い瀨だ。
さらに上流、烏山新道から棚下、綾戸、中河原、岩本地先などの上流へ遠征する頃には私の友釣技術もよほど上達してゐた。綾戸の簗の下手では、激流に脚を浚はれて、命拾ひしたことがある。中河原の岸壁の中腹を、横這ひに這ふときは、恐しかつた。こゝらあたりでは、七月中旬から八月はじめになると、ほんたうの尺鮎が釣れたのである。
水量は多く川幅は廣く、瀨は荒い。非力の私でさへ五間半の長竿を使はねばならぬのであつたが、體力のある職業釣師は六間半以上、七間などゝいふべら棒に長い竿を振りまはしてゐた。そんな竿でなければ届かないほど遠い流心に、大きな鮎は石の垢を食つてゐたのだ。
岩本へは、近鄕近在から釣人が集つてきて、甚だ川は賑やかであつた。棚下や綾戸は、両岸截り立つて利根川は峽流をなしてゐるが、岩本地先は割合に廣い磧を持ち、割合に足場が楽である。そのために、こゝは人氣があつたのである。岩本には、利根川隨一の名人茂市がいまなほ達者で釣つてゐる。
支流の片品川へも分けいつた。片品川は、尾瀨沼に近い山々に水源を持つ、清冽の水を盛つた鼕々たる急流である。この地方の人々は、この川に棲む鮎を鼻曲り鮎と稱した。醤油屋の瀨は、思はぬ大漁に味を占めたことがある。それは、夕立水の澄み口であつた。糸の瀨には十日あまりも滞在して、鼻曲り鮎の友釣に堪能した。
片品川との合流點から上流の利根川は、次第次第に潺をなして奔下する水貌だ。戸鹿野橋や杉山下。次いで、曲つ瀧、曲つ瀧は、大利根百里の全川中、隨一として指されてゐるところの難所である。瀨は、樋から吐き出すやうに流れ落ちる。瀨の中に頑張つてゐる岩は家ほどもある。その急流へ立込んで、水に脚を浚はれゝば、もうあの世行きである。
釣りあげてみて、よくもまあ吾が腕に、と思ふほど大ものが棲んでいる。竿は、六間半以上でないと、うまい場へ囮鮎は泳いで行かない。
鷺石橋の上下は、平場になつてゐて、まことに釣り易い場所だ。
三
沼田を過ぎて、薄根川との合流點から間庭地先も、ザラ場續きで足場がよい。
次は、後閑地先である。月夜野橋を中心として、上下いづれにも無數に釣場がある。鮎の姿が立派であるのと、艶の鮮やかであるのは、全川中後閑が第一等である。下總の銚子にある利根河口からこゝまでは、七八十里もあらう。一寸か一寸五分に育つた鮎が、太平洋の海水に別れるのは、三月初旬であるかも知れない。それが、長い長い放路を經て、後閑まで達するには、もう夏の土用に入らうとする七月中旬だ。
その旅の月日の間に、鮎は何んなに水や岩と闘つたか知れない。後閑地先へ足を止めたとき、鮎は頑健そのものになつてゐる。身の上八九寸、四五十匁から百匁近いまで育つてゐる。そして、野鯉のやうに細身で、筒胴の姿である。胴が筒と同じに細くなつてゐなければ、瀧なす潺湍は乘切れない。
肉がしまつてゐる。香気が高い。背の色が、濃藍だ。敏捷であるのと、體力的であるのと、争闘心の強いのと、強引であるのとは、恰も密林に住む虎か、豹にたとへられよう。
掛つた。釣人は、先づ足許に注意せねばならない。でないと、踏んだ石の水垢に辷つてでんぐり返る。囮鮎も、掛り鮎も、竿もめちやくちやだ。足の速力が、鮎の逸走の速力に伴はねば、道糸を切られてしまふのである。釣人は、まるで夢中だ。下流へ走りに走つて漸く手網へ技取つたあとでも、しばらく心臓の皷動はやまない。そして、この邊は水源に近く雪橋から滴り落つる水も、長い時間太陽の恵みを得てゐないから、温度が低いのである。土用の最中でも、水へ立込むと、ひやりとする。だから、鮎が丈夫だ。
月夜野橋から上流には西海子前、長どぶ、病院裏、地獄などの釣場があるが、地獄の瀧も凄寒を催す眺めである。
水上温泉から二里下流の小松に、東電の發電所が竣成したのは、隨分古い昔である。小松に發電所ができてからは、天然鮎ではその放水路まで達するのが、最も長い旅を續けたことになる。
私は、月夜野橋の下流の瀨が、龍宮の崖に突當つた落込みで、百匁以上の鮎を釣つたことがある。つひに取るには取つたが、私はその鮎と囮鮎を入れてしまふと、磧へ尻餅ついて長い間、溜め息を吐いてゐた。
後関の對岸で、本流へ合するのは、谷川の溪水と、三國山の溪水とを集めて下り來つた赤谷川である。赤谷川は、水温が割合に高いために、後閑まで旅してきた本流の鮎は、この支流へ溯上しなかつた。
赤谷川は、下流から中流へかけては、山女魚専門の川である。上流の谷川嶽の麓までわけ入れば、岩魚ばかりであるが、近年奥利根地方は、温泉鄕が賑やかになつたために、溪流魚に値打が出てきたので、職業釣人は腕に撚をかけて釣るやうになつた。そんな次第で赤谷川の溪流魚は、四月一杯位で殆んど釣り絶やされてしまふ。
四
大きな姿と、味の立派であることでは日本一の鮎を有てる利根川。旅の釣人垢石を生んだ利根川は、悲しい哉いまは亡びた。
若鮎が、利根川の中流鳥川との合流點の埼玉縣本庄町裏の廣場へ達するのは、遅い年で四月中旬、早い年には三月下旬であつた。それが下の宮、藤川前、新堀、横手、萩原を經て、早い年には四月の二十日頃、私の村の地先へ達してゐたのである。
さらに、前橋の縣廳を通り坂東橋を抜けて吾妻川との合流點を過ぎ、利根川本然の姿の大溪谷へ入つて行くのは五月中旬であつた。若鮎は、續いて躍進して行つた。猫、烏山、綾戸の難を越して岩本と森下とが相對する峽流へは、六月上旬に姿を現した。この時代には、もう若鮎は少年期から青年期に移らうとして、躰躯に逞しい肉がついてゐた。
戸鹿野橋の下流で群は二つに別れた。右を指す群は、片品川へ。左を指す群は、本流へ。片品へ入つた一群は、ひた溯りに溯つて、五里上流の吹割瀧の瀧壺まで達した。本流を辿る一群は、曲つ瀧の奔流と闘ひ、上川田村の肩を曲がり、茂左衛門地藏の前を通つて、地獄や靑岩に一瞥をくれ、小松まで泳ぎついて、ほつとするのは、六月もおはりの頃であつた。顧みれば、銚子の海に別辭を殘してから、既に何十里の旅を續けたらう。恐らく、百里に近くはあるまいか。
若鮎は、一人前の生活力が、からだから溢れるのを感じてゐた。
しかしながら、利根川は水温の低い大河である。吾妻川との合流點から上流は、六月に入つてからでも、攝氏の十二度を超えまい。また水量の多い川である。
坂東橋の橋下で、平均六千個といふのだ。これでは、なかなか水は温まらないのである。そして、水源に抉り込んだ深谿には、四季雪原と雪橋が消えないのだ。上州側には大刀寧岳と劔ケ倉、澤山、越後側に聳ゆる兎嶽、越後澤山、八海山、越後駒ケ嶽などを合はせた山彙は標高僅かに七八千尺に過ぎないけれど、人里遠いことに於ては、日本一である。その山彙から滴りでゝ、深い谿の底の落葉を潜り、陽の目を見ないで奔下する水であるから、眞夏になつてからでも、朝夕は身に泌みる冷たさを覺えるのは、當り前であらう。
さういふ性質の流水であるから、東海道の諸川や、栃木茨木方面の川が、六月一日の解禁日から、もう盛んに友釣に掛るといふのに、利根川の鮎は早くとも七月に入らなければ囮鮎を追はなかつた。尤も、數十年罕なことであつた。大正十三年には、驚くほど水温が高まつて六月十五日から、圓石の簗の尻で友釣に掛つたが、それは例外である。
綾戸の荒瀨を境として下流は七月初旬、上流は七月中旬。後閑を中心とした最上流では七月下旬を迎へなければ、鮎は友釣の鈎に掛らぬのを普通とした。だが、一旦囮鮎を追ひはじめると、中断することなく、九月上旬まで、忙しいほど釣れ盛つた。
五
ところが、人間どもが憎惡すべき、恐怖すべき、飛んでもないたくらみを起した。
大正末年、大川平三郎は金儲けのために、片品川の水を糸之瀨で悉く堰きあげ、森下に發電所を起し、下流へ一滴の水も落とさない仕事を完成した。と同時に、浅野總一郎は事業慾のために、利根本流の四五千個の水量を,岩本地先の大堰堤で締めきり、これを五里下流の眞壁村へ運び、大發電所をこしらへた。ために、吾妻川合流點と發電所までの間は吾妻川の延長となつた。毒水が、黄色を呈して、河心を滔々と流れた。
これで、利根川の鮎の運命はきまつた。
でも、大川平三郎は糸之瀨から一滴の水も下流へこぼさなかつたが、浅野總一郎は岩本の堰堤から、ぎこちない魚梯を通して、僅かの水を下流へ送った。そんな障害物が川の眞ん中へ横たはつてから、遙々太平洋に別れて溯ってきた若鮎の群は、大堰堤の下へ集つて、怨めしさうに、高い高いコンクリートの壁を見あげた。
一群のうち、からだの頑丈な、もう十五六匁に達した若ものは、魚梯から僅かにこぼれ落ちる水の中へ、突込んで行つた。そして、たうとう魚梯を登りつめて、大堰堤の上へ滿々と溜つた淵へ躍り込んだ。これは、並大抵の勞苦ではない。
この勇敢な、體力的な若鮎は、一群のうちさう大した數がゐるものではない。多くの力の弱い意氣地ない連中は、自分たちに爲し能はざるを観念して、すごすごと下流の方へ引返して行つた。そして、手頃の石についた水垢を食つて、育つた。
魚梯を登つて行つた連中は、昔と同じやうに堅肉に肥えて、強い力で釣人の鈎に掛つた。しかし、そんなことは二三年で終つてしまつた。次第次第に、川の條件が惡くなつてくると共に、海からくる鮎の數が減つて行つた。魚梯から落ちる水が、雀の涙ほどに量が少くなつて行つたからだ。それ以來、堰堤から上流は、まれにしか天然鮎の姿を見ぬやうになつたのである。
堰堤から下流も、悲慘な状態を呈した。堰堤からのこぼれ水では、吾妻川の合流點から上流へ、鮎は安心して溯上し得るものでなかつた。合流點と堰堤までの間には、南雲澤を頭として各所に細い自然湧水があるけれど、これは僅かに二三百個に過ぎない。昔の水量に比べると、十分の一にも足りないのだ。
こんな風では、鮎は利根川への生活をあきらめるより外に術はない。
こんな結果に陥ることを豫期して、利根漁業組合では、堰堤が竣成した年から、琵琶湖産の稚鮎を買入れて、上流へも下流へも放流したのである。だが、あの大きな川へ僅かばかりの鮎を放流したところで、地球上に散在する金剛石のやうなもので、まことに寥々としてゐる。その上、琵琶湖産はおいしくない。力がない。釣興索然として、釣人はぼんやりとしてしまつた。
つひに、大利根川の尺鮎は亡びた。
近年も、相變わらず放流鮎を續けてゐるが、それは十五萬尾か、二十萬尾にしか過ぎない。それは、十五六里位にわたる範圍に放流するのであるから、釣れたとてほんの短い期間である。そこで、利根川筋の釣人は、鮎を求め上越線を利用し、擧つて越後國の魚野川の方へ遠征する次第になつたのだ。
大正十三年に、岩本の名人茂市は七八のニケ月で賣揚七百五十圓の鮎を釣つた。最近ならば、大したことなないが、當時の七百五十圓といへば、莫大な額だ。田地を、二反五畝も買へたのである。鮎を釣つて、田地を買ふといふのは、面白い話であると思ふ。
六
前橋市を中心として、上流は坂東橋附近、下流は新堀地先までの利根川でやる若鮎釣の技術は、獨特のものである。日本全國に、ちよいと類を見ない。
二間一尺の輕竿。道糸を竿丈より一尺短くして、三匁乃至五匁の銃丸形の錘をつけ、鮎毛釣に蛆をさして、瀨脇へ振込み、右の腕を前方へ眞つ直に伸ばして、こちら合はせで、すいすいと美しい若鮎を抜きあげる上州人の釣姿は、恰も巧みな藝能人の風があつた。
それも、もう幾年ならずして、亡びてしまふであらう。
原本にある振り仮名は“ほたか”と“さいかち”の二つだけです。
西海子は、まめ科サイカチ属。落葉高木。枝にトゲがあり、大木になる。
や幹の棘は10センチ以上の長さがあり、実は洗剤として使用された。
JR吾妻線市城駅(中之条町)から歩いてすぐ近くに
樹齢が推定500年を超える群馬県天然記念物“さいかちの木”があるそうです。
2. 釣趣自叙 抄 (「釣の本」 佐藤垢石 昭和13年刊)
垢石が初めて友釣を試みたのは、母と共に二夏を過ごした酒匂村であった。
今から百年ほど前の明治41年(1908)頃、酒匂川下流、
職漁者風の老人が大きな鮎を釣っているのを見たからである。
釣趣自叙 (抄)
想ひ出
十五、六歳になつてからは、しばらく釣から遠ざかつた。学校の方が忙しかつたからである。
二十歳前後になつてまたはじめた。
母と共に、二年続けて夏を相州小田原在、松林のこんもりとした酒匂村の海岸に過ごしたことがある。炎天を、毎日海辺の川尻の黒鯛釣や鮠釣に専念して、第一年の夏は終つたのであつたが、第二年は六月のはじめから鮎釣をやつて見た。
五月下旬の或る日、ふと東海道の木橋の上手に在る沈床の岸に立つて瀬脇をながめると、溯りに向つた若鮎が盛んに水面に跳りあがるのを発見した。
「この川にも、鮎が沢山ゐるのだな」
と、昔の友に会つたやうに感じた。
子供の時から利根川で、父と共に若鮎に親しんでゐた私であるから、こゝで鮎の跳ねるのを見て、矢も楯も堪らなくなつたのは当然であつた。
すぐその足で、小田原町本町一丁日の「猫」と言ふ異名を持つ釣道具屋へ訪ねて行つて、竿と毛鈎を求めたのである。まだその頃は、関東地方へきてゐる加賀鈎や土佐鈎の種類も少く、私は青お染、日ぐらし、吉野、そのほか二、三を撰んだのであつた。
竿は、若鮎竿として我が意を得たものがなかつたから、長さ二間ばかりの東京出来の鮒竿で、割合にしつかりしたものを買つた。その頃、小田原地方では静岡地方と同じやうに、加賀鈎や土佐鈎の毛鈎を使ふ沈み釣を、石川釣と言つて、ドブ釣とは言はなかつた。ドブ釣とは、多摩川を中心とした釣人が造つた言葉であつたからであらう。
石川釣をやる人も、また酒匂川筋では罕であつて、多くは石亀(川虫)を餌にした虫釣か、十本五銭位で買へる菜種鈎と言ふ黄色い粗末な毛鈎で、浮木流しをやつてゐるのと、職業漁師が友釣と、ゴロ引きをやつてゐた。
六月一日の鮎漁解禁日がくると、引続いて毎日出かけた。利根川式の鈎合せで釣ると、並んで釣つてゐる誰よりも、一番数多く私に釣れた。深い場所では青お染、浅い場所では吉野が成績をあげたのである。
解禁後、一週間ばかり過ぎると、余り釣れなくなつた。そこで、人々はあきらめたと見へて、川へ姿を見せる者は少くなつた。けれども、私は根気よく続けてゐた。或る日、朝飯をゆつくり済して、国道の木橋の土手の釣場へ行つて見ると、一人の職漁者風の老人が、私の佇む岸より少し上手の荒瀬で友釣を引いてゐた。私はいつもの通り、道具を竿につけて、静かに竿を上げ下げしたが、その日はどうした訳か全く駄目で、田作ほどの小鮎が二、三尾釣れたばかりであつた。
私は、竿を磧へ投げ出して、木床の上へ跼つた。梅雨がくるにはまだ四、五日間がある。空は、からゝゝと晴れてゐる。
跼つたまゝ、友釣の老人の竿捌きを眺めた。一時間ばかりの間に、五、六尾釣りあげて宙抜きに手網で受けるのを見た。技術も上手であるが、鮎も沢山ゐるらしい。
私は、老人の魚籠を覗いた。老人は囮箱でなく、竹で編んだ魚籠を使つてゐたのである。大きな籠のなかには、四、五十尾の鮎が、生き生きと群れてゐた。私が毎日釣つてゐる若鮎に比べると、幾倍と言ふほど大きい。十四、五匁から、二十匁近くもあらうと思はれる鮎ばかりであつた。
私は、讐へやうのない興奮を感じた。
毎年、夏になると私の村の傍を流れる大利根川の上流で、職漁釣師が勇壮な姿を激湍の真んなかに躍らせて、友釣を操つてゐる風景を想ひ出した。五間もある長竿で、一歩踏み誤れば溺れねばならないほどの奔流へ、胸のあたりまで立ち込む利根川の釣は楽しみよりも苦しみであらう。かう想像して若鮎釣だけで満足し、大河の友釣には手を出さなかつた自分であつた。
ところが、いま見るこの友釣は三間か三間半の短い竿で、大きな鮎が掛つても三、四歩下流へ足を運ぶだけで、宙抜きで手網へ入れてゐる。これなら、自分にもやれさうだ。私の胸は、異常に躍つてきた。
「おぢさん、友釣つてむづかしいものだらうね」
私は、一心不乱に釣つてゐる老人のうしろから、かう問ふて見た。けれど、老人はうるさい、と言つたやうな一瞥を与へただけで、何とも答へて呉れなかつた。
しばらくすると、釣れが遠くなつた。老人は腰から叺を抜き出して、一服つけた。私は、この機会を逸してはと考へた。
「私に友釣を教へて呉れませんか」
と、率直に申し込んだ。
「いままで、石川釣をやつてゐたんだが、どこも面白くない」
と、つけ加へたのである。
「お前さんは何処だい? 」
「酒匂へきてゐるんですよ。上州の方から」
「ふん。だが、友釣はむづかしいよ」
老人は漸くこれだけ口をきいたのであるが、お前のやうな青二才に友釣などが、さうたやすく覚えられるものか、と言つた態度と口吻である。
「どうか、手ほどきして貰ひたいと思ふんですが」
私も、執拗であつた。
「夜、おれの家へきな。教へるから――」
この場で、一通りの説明だけをして貰ひたかった私は、この言葉を聞いて癪に触つた。老人の住所を、聞いて置かうと思つたが、止めにした。
けれど、試みに老人が磧に倒して置いた竿を握つて見た。長さは三間あまり、全体の重量が手にこたへるほどの調子で先穂の硬い、二、三十年も使ひ古したと思はれるやうな、男竹の延竿であつた。
「竿に、手をかけちやいけない!」
老人は、咽から絞り出すやうな声で私を叱つた。そして、ひつたくるやうに私の手から竿を取つたのである。何と、憎々しい爺だらう。
私は、黙つてその場を立つて、自分の竿のあるところへ行き、道具をかたして堤防の上へ登つた。広々として、涯しのない酒匂の河原を望んだ。足柄村の点々とした家を隔てヽ、久野の山から道了山の方へ、緑の林が続いてゐる。金時山の肩から片側出した富士の頂は、残雪がまだ厚いのであらう、冴えたやうに白い。遠く眺める明星ケ岳や、双子山の山肌を包む叢は、まだ若芽へもえたつたばかりであるかも知れない。やはらかい浅緑が、真昼の陽に輝いてゐる。
酒匂の川尻の砂浜にくだける白い波濤は、快い響きを立てゝゐる。東から吹く初夏の風を帆に孕ませて、沖合遥か西の灘へ辷つて行く船は、真鶴港の石船であらうか。
翌日は、午後から、小田原在足柄村多胡の釣道具屋に行つた。店主に頼んで、友釣の釣道具一切をこしらへて貰つたのである。
鼻鐶は、木綿針を長さ八分ほどに裁り落し、真んなかを麻糸で括つた撞木式。テグスの鈎素へ、鈎を麻で結びつけた鈎付け。鈎は袖形であつたが、鮎掛鈎としてはモドリのついた珍しいものであつた。いまから考へると、まことに旧式な仕掛の出来であつた。
私は、喜んでその道具を蟇ロヘ入れ、きのふ「猫」で買つた鮒竿を舁いで、足どり軽く飯泉橋を酒匂川の東岸へ渡つた。飯泉橋はいまの小田原行電車の足柄駅から遠くはないが、その当時と、この頃では酒匂川の様子が、まるで変つてゐる。
道了大薩陀の奥から出てくる狩川と、酒匂川とは飯泉橋の上手で合流してゐる。その橋の東の袂に、飯泉村を貫いて流れ出てくる清澄な小川があつた。その小川が、酒匂川と狩川の合流点へ注ぐ角に木床工事があつて、深さ一尺五寸ばかりの巻き返しになつてゐた。そこに、大小無数の鮎が群れてゐるのを発見して喜んだ。
急いで、竿へ毛鈎の道具を結びつけ、抜き足して岸へ近づいた。そして、一尾の囮鮎を釣りあげようとして、熱心に鈎を上げ下げして、一時間も辛棒したが、鮎は鈎の方を見向きもしない。場所を替へて、そこから三十間ばかり上流の沈床のかげを試みたが、やはり釣れなかつた。
けれど、為になるものを見た。それは、熱心に川面を見つめ瞶めながら釣を上げ下げしてゐると、沈床のかげから、二、三尾の大鮎が追ひつ、追はれつして、互に絡りながら泳ぎ出してきた。そして、沈床の肩の瀬の落ち込みへ突進して行くのである。いつぞや父から、友釣と言ふのは、鮎の闘争性を利用した釣であると教へられたが、では今この沈床のかげから出てきた鮎のやうに、囮鮎と川鮎とが激しく闘ふうち、つひに囮鮎に仕掛けた鈎に川鮎が引つ掛つてしまふのであらう、と考へた。
漸くにして、五寸ばかりの鮎を釣つた。雀躍りして、上流の沈床の上へ取つて帰つて竿へ友釣の仕掛をつけ、この鮎を囮とした。師匠もない、道具も揃はない俄か仕立ての友釣を試みる自分である。手網も、囮箱も、通ひ筒も持たぬ。魚籠のなかの鮎を掌で補へ、そこでそのまゝ、かねて聞き覚えの通り撞木の鼻鐶を鼻の穴へ突き通して、瀬のなかへ放り込んだのであつた。
長さ二間の鮒竿、川幅はおよそ五間。沈床の肩に立つて斜に上流に向ひ、瀬の吐き出しへ囮鮎を遊ばせた。ぎこちないフオームで待つこと五分間ばかり、だしぬけに竿先が重くなると一緒に、下流へ猛烈な勢ひで引いて行くものがある。
「やつ。掛つた!」
と、直感した。いままで、一度も経験したことのない魚の強引が腕にこたへる。
「愚図/\ 、してゐれば、逃げられてしまふかどうか分らない」
下手へ十歩ばかり下つた時、かう考へて矢庭に瀬のなかから、牛蒡抜きに掛り鮎、囮鮎共に宙ヘ抜きあげた。と、同時に右の手が無意識に働いて、麦藁のカン/\帽が頭から離れると、二尾の鮎は帽子の底に、音を立てゝ跳ね続けた。
こんな機会から、私は旅先で鮎の友釣を学んだのであつた。
水の遍路
それからと言ふもの、私は暇さへあれば諸国を釣り歩いた。渓流、平野の川、海、湖水。何処であらうと、嫌ふところなく釣を楽しんだ。
故郷上州の水は、殊に親しみ深い。我が家の近くを、奥深い上越国境大利根岳から流れ出て、岩を削つて奔り、関東平野を帯のやうに百里あまりも悠々と旅して行く利根川のことは、こゝに説明するまでもない。
片品川、赤谷川、湯檜曾川、谷川、寶川、楢俟川、薄根川、大尻川、根利沢、砂沢、南雲沢、吾妻川など利根川へ注ぐ数多い支流へは、幾度も幾度も分け入つた。
浅間山麓六里ケ原を流れるさまざまの渓流も忘れ得られない。碓氷峠の山水を飾る碓氷川、霧積川、坂本川も長い年月我が釣意を誘ふところである。
妙義山の南麓から出る西牧川と南牧川を合せる鏑川の水は美しい。おいしい鮎が大きく育つ。分けて南牧川の支流青倉川と塩沢川の山女魚には、数々の想ひ出がある。
裏秩父と、御荷穂とがはさむ渓谷には、深い神流川が流れてゐる。秩父古生層の洒麗な岩の間から、滴り落つるこの川の水は、冷徹そのものである。鬼石の町から坂原を越へ、万場へ出て中里村、上野村へ入れば次第に山の景観は深邃を加へ、渓の魚も濃い。
赤城山上の大沼、榛名湖など湖上の釣も静かな心を養ふに足りた。城沼、多々良沼など館林地方の平野の水には、廬荻の間に葭切が鳴いて初夏の釣遊が忘れられぬ。上州と野州の国境で渡良瀬川へ注ぐ桐生川の山女魚と、矢田川の鮠も、吾が故郷では特筆すべき釣場であつた。
野州へも、足を重ねた。
那珂川の上流、箒川、荒川などで鮎を釣つた。鬼怒川の本流、雄鹿川、湯西川、三依川、十呂部川の岩魚と山女魚の姿は大きい。古峯ケ原の大芦川は幽谷の趣がある。思川と小倉川へも、鮎と山女魚を追ふて行つた。新古河の渡良瀬川では寒中の鯉釣と、夏の鱸釣に耽つたのである。
奥日光の湯川では、猛然と鈎に飛びつく鱒に深い興趣を求めたのであるが、あの戦場ケ原を取り繞く大きな山々の景観には、幾度か心を惹かれた。初夏、浅緑の掩ふ渓の汀に佇めば、前白根に続いた近い斜面の叢林が美しい。
金精峠を越して菅沼へも、丸沼へも行つた。そして、大尻川を下つて鎌田へ出で、さらに戸倉の部落を過ぎて尾瀬沼と尾瀬ケ原の方へも行つた。
茨城県にも釣場は多い。霞ケ浦を中心とした水郷地方は、釣を楽しむ者で殆んど知らぬは少いであらう。大利根川の鱸と鯉と鮒と鮠は有名だ。水戸を東へ三里、涸沼と涸沼川はほんたうに魚が多い。そして、大洗海岸も、夏場は磯魚がよく釣れる。湊の河口も棄て難いのである。
那珂川の中流は、鮎が多いので幾年も友釣に堪能した。下流の鱸と鮠は素敵だ。殊にこゝの鱸は、亡き父と二年続けて試みて想ひ出が深いのである。久慈川には、関東一と言はれるほど、姿も味も立派な鮎が棲んでゐる。太子町の上流に掛つた簗小屋に幾日か過して、我が釣つた鮎を葛の葉の火土焼にして食べた味は、永久に忘れまい。
雍の原では、山女魚を追ふた。筑波のみなの川では、鮠を試みた。
尾瀬ケ原から、只見川の渓谷へ入つて、岩代国の岩魚を釣つたこともある。山形県の最上川も覗いた。荷口村の養鱒場で、美味口に奢る虹鱒の饌も嗜んだ。
越後の魚沼川へは、遠く信州から直江津を廻つて遠征したことがある。上越線が開通してからは足繁く行つた。小出、浦佐、堀の内を中心として八月中旬過ぎには円々と肥つた大きな鮎が、友釣竿を引き絞るやうにして掛つてくる。その支流の破間川の鮎は一層麗容に恵まれてゐる。
信濃国もいゝ。戸隠の谷から出て長野の傍で信濃川へ注ぐ裾花川に、岩魚を釣ったのはもう十年前にならうか。小諸の近くを流れる千曲川。
こゝの鮎は、数が少いが引きが強くて面白い。北アルプス白馬の方から出てくる高瀬川に岩魚を探つた夏の景色は雄大であつた。草津温泉の渋峠を越へて、渋温泉の方へ渓流魚を探りながら下つて行つたところ、この辺の渓にはほとんど魚の影がなく、空魚籠を提げて帰つてきたのも、微笑ましかつた。
武州の荒川は、長瀞の上流下流で幾度か鮎の友釣を試みた。三峰川と中津川では山女魚釣に谷を跋渉した。高麗川と名栗川へも行つた。多摩川と奥多摩川、日原川、秋川などはこゝで説明するまでもない。江戸川、中川、綾瀬川など勿論のことだ。
相州の相模川は、与瀬から下流厚木附近まで東京の鮎釣人で知らぬ人はあるまい。さらにその下流の馬入川では、淡水魚と海魚が混へて釣れる。酒匂川は、私の友釣を生んだ場所である。箱根から流れ出る早川の鮎は、水電事業のために滅亡したのと同じやうになつたのは悲しい。須雲川の山女魚は、いま尚健在である。
真鶴、小田原、国府津、大磯、江ノ島などの海釣は、まだ都会人を満足させるだけに発達してゐない。舟宿と船頭に、いろ/\の研究を乞ふてやまない。それに引換へ、三浦半島の海釣はよく発達してゐる。野島、走水、横須賀、鴨井、九里浜、三崎港と鯛や鱸釣をはじめとして、船頭はよく都会人を遊ばせることを心得てゐる。幾度遊びに行つても飽きないのだ。
これと同じに、房総半島の海も快い。湊、大貫、竹岡には数多い遊漁船があつて四季いつでも釣れる魚がゐる。鯛、鱸、鰈、黒鯛など、婦人が行つても釣れることができる。安房の南端布良の釣遊は豪壮であつた。外房勝浦方面の遊釣案内舟は、いま一段の改善が欲しいと考へて見たこともあつた。利根川河口銚子港の釣も盛んである。
形も味も立派ではないが、この半島の養老川と、夷隅川には鮎がゐた。
甲州は、渓流魚に恵まれてゐる国である。
相模川の上流とその支流笹子川、笛吹川、日川、御岳昇仙峡と黒平の荒川、釜無などへは山女魚を求めて度重つた。塩川の上流、金峰山の懐ろから源を発する本谷川の山女魚と岩魚はなつかしい。富士川の支流早川と雨畑川、常盤川、波木井川、戸栗川、福士川、佐野川、稲子川、芝川など渓流魚が多いのである。南アルプス北岳の肩から出る早川の上流野呂川へも岩魚を志して行つたことがある。
富士川本流の、鮎の友釣は豪快である。私はその中心地波高島と身延へは、年に四、五回も行つて幾日も滞在する。これから後は、一層精出して行かうと思ふ。
静岡県は、東は伊豆から西は遠州まで、ほんたうに数多い釣場に恵まれてゐる。伊豆の長津呂から下田港へかけては、冬の釣場として国内屈指の地である。網代と初島のまわりはあまりにも有名だ。伊東温泉には海も河もあり、鯛も平目も、鮎も山女魚もゐる。修善寺温泉を中心とした狩野川と大見川の漁帥は、友釣技術に於ては全国に冠たりと言はれてゐるほどだ。そして山女魚もゐる。
東海道岩淵で大平洋へ注ぐ富士川本流の大鮎と、支流芝川や内房川の渓流魚は我等の昔から楽しんだところである。興津川の鮎と山女魚はいまさら説くまでもあるまい。三保の松原が囲んだ清水湾、こゝには黒鯛と鱸と鰡と、いくらでも遊釣人を楽しませてくれる。また、こゝの遊釣舟は近年大した発達を示した。外洋では、大きな真鯛も釣れる。
静岡の安倍川と藁科川。私は、こゝでも鮎と共に幾年か過した。久能山に近い中島の海岸で、太平洋へ注ぐ安倍川の白い波を眺めながら、石持魚の投げ釣に興じたこともあつた。静岡の御城のまわりのお濠で、鮠と鮒を釣つたこともある。遠州掛川の奥へ入り込み、太田川へ旅したこともあつた。焼津の朝日奈川でも、鮎を釣つた。
遠州の舞坂と、新居を繋ぐ今切の東海道線鉄橋の下で、浜名湖の淡水を求めて溯つて行く黒鯛釣に興じたのも記憶に新ただ。
三州豊橋の傍を流れる豊川へは、上流長篠の近くまで鮎を追つて溯つて行つた。牟呂の海では鰡と白鱚と沙魚を釣つた。美濃へも、表飛騨へも鮎釣の旅をした。殊に、裏飛騨の釣旅は感銘が深かつた。
神通川は、飛越国境の蟹寺で東の高平川と、西の宮川とに分れるが、宮川の鮎は日本では最も姿の大きい一つに数へられるであらう。そのうちでも、打保から巣ノ内へかけての宮川は、峡流岩を噛む間に勇ましき友釣姿を見て深渓の釣興に一層の趣を添へたのであつた。
京都の保津川では、鮠釣と友釣を楽しんだ。丹後の由良川でも釣を試みたが、和知鉄橋附近に鰔の多いのに驚いたことがあつた。土佐の鏡川でも、鮎の群に眺め入つた。
顧れば、私の釣の年月は永かつた。だが、これからも亦、布衣を纏ふていつまでも渓に海に竿と綸とに親しむ吾れであらうと思ふ。
【跼まる】せぐくまる =背をまるめてこごむ。
釣具屋に頼んでこしらえてもらった仕掛けは『鼻鐶は撞木式、鮎掛鈎としてはモドリのついた珍しいもので、まことに旧式な仕掛の出来であつた。』と書かれている。
”モドリのついた鮎掛鈎”は〈 「日本水産捕採誌」、十二鮎友釣:図62の②相模の国酒匂川地方〉に描かれた掛鈎と同じようで、モドリのついた鮎掛鈎が酒匂川で長く使用されていたことを裏付ける貴重な記述である。「日本水産捕採誌」は明治二十年代に取材編纂されたものであり、以来十数年酒匂では同じ掛鈎が使われていたようだ。
自分も、友釣では大きな鮎が釣れると聞き、街の釣具屋で道具を揃え釣り方を教わったのはもう三十年以上も前の昭和四十年代後半ことだった。
『鰔』はウグイと読んで良いのか? あるいはカレイと読むべきなのか?
1.尺鮎誌では、”うぐい”に「魚偏に成」の字を使っているので、最終行から3行目の『鰔』は”かれい”と読むべきなのか?。【魚介方言図説(田中茂穂)】ではウグイにこの字『鰔』をあてているが、別の説明ではカレイにもこの文字を使うと出ていた。。
水の遍路で、房総半島の湊、大貫、竹岡の釣りで「鰈」の文字を使っているので、『鰔』は”うぐい”と読むことにした。 が、『鰔』は、由良川の鉄橋の下に汽水域のカレイがいるのであれば「カレイ」と読み、カレイがいないのなら「ウグイ」と読むのが正解ということになる。由良川の魚に詳しい方、どちらの読み方が妥当なのか教えて下さい。
 |
埼玉県荒川で友釣を楽しむ佐藤垢石。
文人友釣師たちのパイオニアといわれ
多くの釣り人を育てた。 |
3.律儀 (「つり姿」 佐藤垢石 昭和17年刊)
大正から昭和十年代にかけての魚野川の様子である。
律儀に先祖伝来の釣法を守っていた越後人の様子が目に見えるようである。
律義
一
越後の魚野川は、みごとな鮎の棲む川である。私は二十數年あまりも前から、鮎を訪ねてこの川へ旅したのである。そのころは、まだ上越線が工事に着手してゐないので、釣友五六人と共に、信越線に乗つて長岡から小千谷へ出で、そこから釣場の中心地である小出町へ歩いて行つた。
ある年は、上州と越後である三國境をぼつぼつと歩き越へ、疲れた足を引摺つて、湯澤温泉へ下り込み、さらに浦佐村から小出町へ辿つて行つたのである。想へば、私の魚野川への旅の歴史は長い。
十二三年位前まで、この川へは天然鮎が、日本海から夥しく溯つてきた。そのころ、どんな條件によるのであるか、この川の鮎は旧盆、つまり八月十五六日すぎでないと、友釣に掛らなかつた。だが、魚野川の鮎はおそくとも六月には信濃川から溯り込んでゐるのであるから、八月中旬にならねば、囮鮎を追はぬといふ理窟はないと考へたことがある。
その理窟を根據にして、震災前のある年の七月下旬、四五人の釣友と共に、遙々魚野河畔の小出町まで旅して行つた。その年は、魚野川は珍らしい渇水で、も少し水が枯れゝば流心の底石までが、頭を出しさうな有様であつた。しかし、渇水であるからといつて、常に水量豊富な魚野川である。鮎が育つのに、差支へるといふほどではない。却つて渇水の方が、釣るのに樂の場合が多いのである。私等は渇水であるのを喜んだ。
ところが、着いた翌日川へ行つてみたところ、誰も釣つてゐない。これでは、囮鮎が手に入らないのである。やむを得ないから、釣友が手分けをして、あちらの瀬、こちらのザラ場といつた風に、ゴロ引をやつてみた。けれど、一尾も掛らない。やはり、八月半ばにならねば鮎は出てこぬのかな、と考へたが既に六月中には溯つてきてゐる鮎が、全然一尾もゴロ引に掛らぬ理窟はないときめて、さらに盛んに川底を引掻きまはしたが、なんぼやつても掛らない。
下流へ行つてみよう、といふことになつた。私等は歩きはじめた。堀の内から、新道島まで往復五六里の道を歩いた。七月下旬は、土用の最中である。越後の眞夏は暑い。咽が乾いて、田の泥水まで飲んであちこち歩いた。堀の内地先の五六ヶ所の瀬、新道島地先の荒瀬を丁寧にやつたが、やはり一尾の小鮎さへも掛らないのだ。
私等は諦めた。自分たちの理窟は屁理窟であることが分かつた。しかし、分からぬのは八月中旬にならねば、釣れぬといふ現實であつた。たうとう、越後くんだりまで旅して行つて、一尾の鮎も釣らないで帰つてきたことがある。
魚野川は、新潟縣南魚沼郡の南端に聳え立つ、萬太郎山の山襞に水源を持ち、石打、湯澤、塩澤、六日町と流れ下つて六日町と五日町の間で、八海山や越後駒ケ嶽から流れ出る五十澤川と三國川を合はせ浦佐、小出、堀の内を過ぎ川口町の下流で、本流信濃川に合する流程二十里あまりの清流だ。
水量は、相模川ほどもあらうか。支流の三國川や五十澤川、破間川の水源方面は古生層の岩質を持つてゐるために、水質が清く立派で、鮎の常食としてゐるところの水垢が、まことによろしい。従つて六日町から下流に育つた鮎は、姿も香気も味も賞美し得るのである。だが、底石は大きいとは言へない。ところで、底石が小さい割合に勾配が急であるから、水の流れは早い。
鮎の引きは、強い方だ。
二
さて、近年魚野川へは、天然鮎の溯上が極めて尠くなつた。といふのは、信濃川分水の寺泊の堰堤が完成したために、そこで海から溯つてきた若鮎が悉く堰きとめられてしまふからである。また信濃川本流の方は、近年文化の發達のために、惡水が流れ込むので、若鮎は本流へも志さぬ。
ところが、七八年前から新潟縣水産試験場の盡力で、魚野川漁業組合が、寺泊の堰堤下から、若鮎を掬ひあげ、これを活魚自動車に積んで、下流の川口附近から上流の湯澤附近まで運びあげ、魚野川へ放流するやうになつたのである。尤も、その前から琵琶湖の稚鮎を放流したこともあるけれど、これはほんの少い數で問題にはならなかつた。
そこで、興味深いことがある。一昔前、この川へ盛んに天然鮎が溯ってきた時代は、魚野川筋の釣人の技は、甚だ幼稚でほんたうに時代遅れであつたのである。ところが、げん數年縣と組合と協力して、若鮎を放流するやうになつてからは、俄かに腕をあげてきた。そこに、越後人の律義な一面がある。
されど、他國の釣人の刺戟には、律義な越後の釣人も堪へ得られなかつた。
今から二十數年前、私等四五人の同好者がはじめて魚野川の磧の石を踏んだころは、私等が十尾釣るうちに、越後の人には一尾位の割にしか釣れなかつた。私等が、川へ竿を出すとその近所に釣つてゐた越後の釣人は逃げだすか、竿を畳んで磧に腰を下ろし、手を拱いて私等の釣姿を黙々として、眺めてゐたものであつた。
當時、その人々の持つてゐた竿は、旗竿の先へ硬い穂先を繋いだだ三間半ほどの、ブツキラ棒のもので、調子も具合もあつたものではない。道糸は太い麻糸か、人造テグス。鈎素は三厘程の人造テグスで、鍾は十五匁から二十匁位の重いものだ。それに囮鮎をつけて瀬のなかへ投げ込むのであるから、鍾は水底へ固着して、囮鮎はさつばり活動しないのだ。これでは釣れる筈がない。
これを見た私等遠征の人々は、竿は胴に調子を持つて全體にやはらかく、殊に穂先は柔軟のものを選んだがよろしい。道糸は一厘柄のテグス、鈎素は一厘二毛乃至一厘五毛を用ひれば、極めて輕い鍾でも囮鮎は、荒瀬の底へ泳いで行く。瀞や淵であつたなら、鍾は全然不用であらう。
囮鮎の負擔を輕くすることは、囮鮎の活動を自由にすることであるから、仕掛全體はでき得る限り細い糸を用ひるのが理想的で、重い錘を避けねばならぬ。竿をやはらかく、輕くすることは、道糸への抵抗を弱くするものであるから、細い道糸を用ひても、切られる心配はないものだ。と、いろいろ細かく説明したのであるけれど、越後の釣人はそれに答へて、いや自分たちはこの竿、この仕掛でよろしい。この竿、この仕掛けは先祖傅来のものであるから、これを俄かに改變することは先祖に對して申譯がない。釣れないでもよろしいのであるといふのである。
そして、相變らず重い錘を瀬のなかへ放り込み、汀に佇立したまゝ、幾時間でも同じ場所に頑張つてゐるのだ。掛け鈎を、鋭利に研ぐことが、友釣の生命である。であるのに、鈎を一日に僅かに一回か二回、鑢にかけるのみで、鈎先が磨滅しても平気でやつてゐる。これでは、釣れないのが當然だ。
三
昭和十一二年頃まで、越後の釣人は旧来の竿と、仕掛と釣法を固守してきた。
ところが、縣と組合が協力して魚野川へ數多い若鮎を放流するやうになつてから、こゝへ他縣の釣人が何十人何百人といふほど押しかけてきた。その釣人は主として群馬縣の職業漁師であつたが、この群馬縣の職業漁師の釣法が巧みで、越後の釣人が一日に百匁釣るならば、一貫五百匁も二貫目も釣り上げる腕を持つてゐる。
縣と組合が、熱心に放流したところで、鮎を悉く他縣の釣人に釣られてしまつたのでは、土地の漁師の懐は肥えない。と、いふことに氣がついた。そこでたうとう、越後の釣人は、小出町の警察署へ他縣の釣人を追つ拂つて貰ひ度いと陳情した事件など起つた。
それを機會として組合では、他縣からきた釣人に對して、入漁料を徴収するやうになつたのだが、根本問題を考へてみれば、自分たちが、いつまでも旧式の竿や、仕掛、釣法を固守してゐたのでは、成績が上るわけがない。と、悟つたのである。律義の越後人も、この悟りに達すると、果然先祖傅来の竿と仕掛と釣法を、棄てゝしまつた。そして、群馬縣からきた釣人の敎へを受けるやうになつたのである。
群馬縣の釣人も、昔から友釣の技法に巧みなわけではなかつた。伊豆の狩野川の、職業漁師の技法を傅へたのである。群馬縣の鮎は、利根川が代表してゐた。名にし負ふ日本の大河である。昔から利根川へは、夥しい鮎が太平洋から溯つてきた。しかし、利根川の釣人も釣技は下手であつた。
明治四十年前後であつたと思ふ。偶々、伊豆の狩野川の職業漁師が利根川の豊漁を傅ヘきいで、遠征してきた。狩野川の漁師は、神さまのやうに友釣が上手だ。日本一であると稱して差支へない。
利根川の漁師は、忽ち狩野川の漁師が持つ竿と仕掛と釣法とを學んだ。一両年の間に、上達したのである。だから、利根川の漁師の釣法は狩野川式であるといつてよろしいのである。ところが、大正十五年に、詳馬縣利根郡川田村岩本驛地先へ、關東水力電氣會社の大堰堤が竣成してからといふもの、さしも夥しく溯つてきた鮎は、殆んど全滅の姿となつたのである。
十年間ばかりといふもの、利根川の漁師は不漁に悩んだ。そのうちに、上越線が開通して、上州から越後への交通路を得た。と、同時に魚野川の豊漁を利根川の釣人は、傅へきいたのである。大擧して、魚野川へ遠征して行つた。そのころから、魚野川の若鮎放流事業は、ますます盛んとなつて、利根川の漁師は釣季の終わると共に、懐を重くして故郷へ帰つたのであつた。
越後の釣人は、利根川の釣人に對して、競争意識が旺んとなつた。ために、近年ではまだ利根川の漁師を凌駕するといふわけにはゆかぬが、十年前に比べれば、見違へるほどに上手になつたのである。こんな譯であるから、越後の釣人も、伊豆の狩野川の系統をひいてゐるといへよう。
以上の話は、小出町を中心としての、ことである。
しかし、小出町から三里上流の浦佐を中心とした附近の釣人は、その後も遅れた釣法を固守してゐた。昭和十三年の八月である。私は、小出町附近の釣場に飽いたので、一人の釣友と共に、浦佐地先の魚野川を釣つてみた。随分、よく釣れるのである。一日に、一尾二十五匁前後の鮎を、三十や四十釣るには、少しも骨が折れない。だが、土地の釣人の竿には、さつぱり掛らないのだ。
浦佐の釣人も、魚野川獨特の昔風の竿、仕掛、釣法をやつてゐる。その上に、朝九時すぎなければ、川へ出てこぬし、夕方は四時頃になると、川から引あげてしまふ。
或る日、土地の老釣人が、私等の釣り方を熟々と観察してゐた。そして、その釣り方を敎へてくれといふのである。どんなにでも敎へてやる。この魚野川にゐる鮎の數は、夥しいものだ。これは、土地の人も他縣人も精一杯釣るがよい。釣らないで置けば、秋になると下流へ下つてしまふ。それは、つまらぬことだ。共に、大いに釣りませう。今夜、私の旅館へたづねて來給へ。共に、釣り方について、研究しょうではないか。と、私等は答へた。
四
その夜、浦佐附近の七八人の漁師が私の宿を訪ねてきた。私は利根河畔で生まれた人間であったから、利根川式の釣り方について語つた。つまり、狩野川式の竿、仕掛、釣法について、知ってゐるだけのことを説いた。先年、小出町の漁師に敎へたやうに、輕い錘を用ひて、囮鮎を自由に水底に遊ばせなければ、川鮎は挑みかゝらぬものであると、説いたのである。
殊に、諸君は朝は遅く、夕は早く竿を畳んで帰つてしまふのは心得ぬことだ。鮎といふ魚は、早朝あたりの閑静の時間には、安心して汀近くの石についた水垢を食ひに寄るけれど、陽が高くなつてくると、沖へ出てしまふ。諸君が、九時ごろになつてから川へ行つたのでは、鮎は沖へ出てしまつたあとだ。
早朝の鮎は、食慾が旺盛だ。従つて、掛りが早い。だから、諸君は一日のうち最も釣れる時間を見遁してゐるわけになる。
また夕方の時間のことも注意を要する。陽が西に傾いた午後四時すぎになると、鮎は再び汀近くの水垢を慕って集つてくる。磧に釣人がゐたのでは、人を恐れて汀近くへ寄来らぬが、あたりが静かになると、薄暮の頃に至るまで、鮎は邊地の石の水垢を争ひ食つてゐる。この時間に、鮎は激しい闘争性を發揮する。これを、日暮れの食ひだしといふ。
こゝが、釣人の狙ひどきなのだ。
であるのに、諸君は四時すぎた頃には、もう竿を舁いで帰つてしまふではないか。それで、釣果があがるわけがない。日中の鮎は、潮の眞ん中に遊んでゐるから、これを釣るのに釣人は骨を折らねばならないけれど、汀近いところに遊んでゐる鮎を釣るには、大してからだに骨が折れるものではない。そして、汀に近いところや、浅い瀞の鮎を釣るには、いろいろと研究せねばならぬ點がある、その研究に没頭するだけでも樂しいことだ。日中荒瀬の眞ん中ばかり狙ふのが、友釣の技法ではない。
こんな風に、物語つたところ、浦佐の釣人はいづれも半信半疑の態であつた。しかし、翌朝からは研究のためとあつて、前夜私の宿へ訪ねてきた釣人たちは、時間を早めて、川へ出で、夕方も手許が暗くなるまで頑張つてゐた。
それから次第次第に、竿も仕掛も釣法も私の説いた通りに改めて行つたところ、数日前に比較すると、倍以上に達する釣果を得るやうになつた。
その結果、職業釣人ではないが浦佐郵便局長關久治氏や素封家牛木四郎氏など、いまでは職業漁師も遠く及ばぬほどの腕に達してゐる。魚野川は流れの姿が立派だ。水質がよろしい。鮎の味も、賞喫するに足りる。こゝの釣人は幸福だ。
五
魚野川漁業組合では、昭和十四年に百萬尾近い若鮎を放流した。ために、素晴しく釣れた。十二年は、寺泊の堰堤で若鮎が不漁であつたから、充分の放流をなし得なかつたけれど、十六年は百二十萬尾ばかりの放流をなし得たのであつた。
それに、十六年は多少の自然鮎の溯上を混へたのであつたから、夥しい鮎の數であつた。解禁が、七月十五日。天然鮎専門當時は、八月中旬がこなければ川鮎は囮鮎を追はぬのであつたが、放流鮎となつてから、七月十五日の解禁當日から、ぼつぼつ掛釣に掛るのである。
私は、七月末から伜を伴ふて、浦佐地先の魚野川を志して行つた。そして、八月下旬まで小出地先、支流の破間川、五日町、六日町地先などを釣りあるいた。豊漁であつた。八月上旬は平均一尾二十匁に達しなかつたが、中旬すぎると平均一尾三十匁に達した日さヘあつた。
職業人でない私は、終日ゆるゆるとした氣持で釣つた。疲れぬやうに、荒瀬へたち込まぬやうに、他の釣人の邪魔をせぬやうに、あせらず釣つても一日に一貫目近く釣つた日さへあつた。私の、小伜にもよく掛つた。
同じ放流鮎であつても、琵琶湖産の稚鮎と、信濃川口から溯つてきた若鮎を掬ひあげ、これを自動車で上流へ運んで放流したものとは、囮鮎に對する態度や、鈎へ掛つてからの動作が違ふ。寺泊の堰下で掬ふ若鮎は、若し寺泊に堰堤が無かつたならば、信濃川を経て魚野川へ溯り込む運命を持つてゐるのだ。つまり、これは放流鮎であつても天然鮎と同じ性質を持つてゐる。
江戸川で掬つた若鮎を、奥多摩へ放流したものと同じ性質を持つてゐよう。また相州小田和の若鮎や、清水灣の若鮎とも同じ性質を持つてゐよう。
ところが、琵琶湖の稚鮎は、有史以前から琵琶湖へ陸封された鮎の子孫であるから、急流へ放流されても、そこに幾分習性の異つたものを現すのではあるまいか。琵琶湖の稚鮎を急流へ放すと、一尾が四五十匁以上百匁近くまで大きく育つのは誰も知つてゐる。けれどこの鮎は、放流した場所からあまり遠方へ離れない。一個所に集つてゐる。従つて、二萬や三萬放流した數ならば、半日か一日で釣りきつてしまふのである。放流した場所を遠く離れないばかりでなく、甚だ執拗に囮鮎を追ふ習性を持つてゐる。そこで、そこにゐるだけ鈎に掛つてしまふのではあるまいか。
これに反して、天然稚鮎を故流したものは、放流した場所から遠く溯上散在して發育する。だから、一個所に集團をなすことは、産卵期の下江時代に至らねば見ることができない。そんなわけで、この鮎は一日や二日で釣りきつてしまふわけに行かぬ。漁期中、永く樂しめることになるのである。
琵琶湖の放流鮎は、大きく育つても力が弱く、引きが強くない。ところが、天然の放流鮎は甚だ力が強いのである。琵琶湖ものがデブ漢であれば、天然ものは筋肉型だ。
魚野川では、その差別がはつきり感じられる。
六
魚野川水系は、鮎ばかりでなく溪流魚にも恵まれてゐる。山女魚、岩魚などが數多いのである。
湯澤温泉から上流の、水源に近い方は、十年ばかり前までは、随分溪流魚が豊富に棲んでゐたのであるけれど、一體水源地方は釣人の狙ひ場所になつてゐる。それがために、この魚野川の上流も、近年山女魚や岩魚が、めつきり減つた。
ところが、この魚野川は他の川と異つて、現在では却つて下流の方に、溪流魚が多いのであるから驚くのである。それは、釣人が下流に棲む溪流魚に對して、なにも知らぬによるであらうが、魚野川は右岸つまり八海山側の崖や砂礫の間から、多量の清水を湧きださせてくる。それに、比較的水温の低い支流は右岸の方にのみ存在するのである。そしてそれは、いづれも六日町から下流にばかり多いのだ。
以上の關係で山女魚は、盛夏の候であつても六日町から下流、小出町附近にまで棲んでゐるのだ。盛夏であつても、溪流魚の棲むのに水温が好適であるからである。五日町や浦佐地先あたりで友釣をやつてゐると、七八月の頃に、時たま山女魚が引掛つてくるのを見ても解るのである。
岩魚も、盛夏の候に浦佐地先に棲んでゐる。それは、右岸に限られてゐるが、やはり右岸から冷たい清水が湧き出るからである。浦佐の簗へは、眞夏でも岩魚が落ちる。簗の上下には殊に山女魚や岩魚が多い。
支流にも、まことに溪流魚が多いのである。殊に駒ヶ嶽に源を發する三國川の奥は、利根川の源流と分水嶺をなしてゐるだけに、岩魚が豊富だ。案内人を連れて里を離れ、ぜんまい小屋や岩屋に泊つて深溪を釣りまはれ三貫日や四貫目得るのは雑作はない。その下流は、出女魚と岩魚まぢりだ。
八海山を源とする五十澤川にも多いが、三國川ほどではない。浦佐の對岸で魚野川へ注ぐ水無川は、駒ケ嶽の北側から源を發するが、こゝも山女魚は豊富だ。水無川が魚野川ヘ合流する少し上手に、細い清水の注ぐ場所がある。こゝでは、盛夏の候に餌釣で面白い釣をやれるのである。
小出町の東南で魚野川へ注ぐ佐梨川の上流も、溪流魚が多い。佐梨川へは、やはり鮎を放流するが、本流ほどには大きく育たぬ。しかし、この川は岩質がよろしいので、鮎の味は本流以上といへよう。
破間川の上流、會津境の方はまだ都會人の足跡が至つてゐない。それだけに、岩魚は多いのである。小出町から會津へ抜ける鐵道が完成したならば、この方面へ志すのに便利とならう。土地の人は、破間川の鮎を指して、味もよし姿も立派であるといつてゐるが、私等が見ると、破間川の鮎は本流のものに劣つてゐるのである。それは、海底や磧に轉積する石に花崗岩が混じつてゐるためであると思ふ。
七
魚野川の鱒の子は、見遁せない。
この川へは、初夏の候になると日本海から日本鱒が溯つてくる。これは、昔から日本にゐた鱒で、近年アメリカから移入した川鱒や紅鱒。北海道から持つてきた姫鱒などとは異ふ。一貫五六百匁位まで大きく育ち、力が強く味は米國系や姫鱒とは、比較にならぬほどおいしのは誰も知つてゐる。
この鱒は、九月中旬から十一月中旬かけて、魚野川で産卵するのである。孵化した子は、親鱒が産卵したあたりで育ちながら、雪の一冬を越すのである。これが、五月頃までに四五寸の長さ、十四五匁の大きさになる。越後國は、上州方面から見ると、雪解の季節が遅れる。四月下旬から、五月中が雪代水の最盛期だ。
その雪代水が終期に近づかうとするころ、四五寸に育つた鱒の子は、薄温りの水に乗つて下江をはじめる。親の育つた遠い海の方へ帰つて行くのだ。この下江の途中を狙つて釣るのが、鱒の子づりである。釣り方は山女魚釣と變つたところなない。
餌も同じだ。鱒の子の味は、山女魚以上であると私は思ふ。
鮭も、九月に入ると魚野川ヘ日本海から溯つてくる。そして、十月から十二月初旬の初雪がくる前頃までに、小出町から上流五日町あたりで産卵する。孵化した子は、翌年の五六月頃までに、二三寸に育つがこれも雪代水が消えた季節に海へ下つて行くのである。鮭の子も釣れば釣れるのであるけれど、魚野川で鮭の子を釣る話はきかぬ。
頑固なまでに先祖伝来の釣法を守っていた越後の人が、昭和十一二年頃、群馬県奥利根の職漁師を通じて狩野川式釣法を学んだこと。奥利根の漁師は明治四十年頃に遠征してきた狩野川の漁師から釣法を学んだこと。など、友釣釣法伝播の一端がわかる貴重な文である。また、琵琶湖産と海産の違いも的確に書かれている。
(参考:鼻環、逆針は狩野川職漁師によって考案され、大正後期、土屋嘉一によって奥利根にもたらされた。 参照⇒「伝説的狩野川漁師の軌跡」)
4.恙蟲と下見酒 (「つり姿」 佐藤垢石 昭和17年刊)
恙蟲の高熱に侵され死の恐怖を味わう
が、その高熱は恙蟲のせいではなかった。
恙蟲と下見酒
私は、今年の夏の七月二十六日から、八月二十五日まで、越後の魚野川で鮎の友釣をやつてゐた。魚野川の川べりには、人間の生命を取る恐しい恙蟲がすんでゐるのだ。
なぜ、そんな恐しい蟲がゐる川へ遊びに行くかといふと、魚野川の河原から眺める景色が、素敵に雄大であるからである。新潟縣南魚沼郡浦佐村と五日町の地先から望む山々の景観と、流れの姿は人を魅する力を持つてゐるのだ。そして、この川には青銀色うららかな、また鮮味舌に愬へる大きな鮎がすんでゐるからである。
東の方、會津と越後を境する連山の間に、七八千尺級の越後駒ヶ嶽と八海山が聳えて盛夏の候にも殘雪を、きらきらと谷間に光らせ、南の方の奥深い上越國境の山々には、いつ
も薄い雲がかゝつてゐる。それに續いて、西の空には八千尺の苗場山が屹立して、下界の樹林を壓してゐる。殊に夕立のあとがいゝ。雷雨が霽れ去ると、日が沒する日本海と思ヘる方の低い空から、東は會津の銀山平の方へ、雄大な七彩のかけ橋が泛かぶ。川の畔の草木は、蒼々と露に霑れて、虹の麗色を映し受けるのである。朝夕は、涼しい。
もう私は、この魚野川の鮎に親しんでから、二十年あまりの歳月を經た。ところで、今年の初夏のころ、今年もまた魚野川へ旅する考へであると、水産講習所の釣友殖田三郎敎授に話したところ、殖田敎授は眼をむいて、それは物騒だ、生命が惜しいと思つたら、魚野川へ行つちやいけない。過去廿十年の間に一度も、恙蟲にやられなかつたといふのは、貴公に惡運の強いところがあるからだから、もう決して魚野川の鮎など、戀しがらないで、どこかほかの川へ志した方がいゝと思ふ。と、忠告してくれるのである。私はほんたうに、なるほどと思つた。だが、それから四五日過ぎると殖田敎授の忠告など忘れてしまひ、越後國の鮎の夢ばかりみてゐた。
七月末になると、たうとう殖田敎授には、ないしよで魚野川へ旅してしまつた。私が、浦佐村の旅館に滞在してゐると、釣友である日本評論社長鈴木利貞氏や、探偵小説家森下雨村氏などが、二度も三度も訪ねてきて、死んだら死んだときさ、なんぞとのんきなことをいつて、大膽にも恙蟲がうようよゐるといふ魚野河畔の草むらを分けて、流れへはいり込んで行くのである。いのち知らずは、私ばかりではないと思つた。
土地の人々の話をきくと、今年は特に繁殖がよろしいといふのだ。この蟲は、長さが一ミリの三分の一ぐらゐ、薄い橙色で漸く肉眼で見えるか見えないほどである。螫されると翌日から熱がでて、からだがものうくなり、三日目には三十八度、四日目には三十九度、それから次第に熱がのぼつて行つて、四十一度以上に達する。つひに熱のために心臓が闘ひ負けて、人間は昇天する。人生一巻の終だ。
そんなに數多くゐる恙蟲なら、この邊の人類は悉く螫し殺されて民族は減亡してしまふはずぢやないかと問ふと、いやそれは心配せんでもよろしい。この近所の村に、赤蟲婆さんといふのがゐて、恙蟲が人間の皮膚の奥深く螫しこんだなら、多年の經験でその螫しこんだ場所を發見し、木綿針で堀りだしてくれるから、生命をとりとめる。魚野川の沿岸では、恙蟲を赤蟲と呼んでゐるのだ。 だが、手遅れになつては、いけない。螫された當日か、遅くも三日目くらゐまでに、赤蟲婆さんの診察を受けないといふと、やはり人間昇天の巻きであるといふ。
恙蟲がでる季節は、六月から九月までゞ、すでに今年はこの地方で十人ほどやられたといふ話を、八月になつてからきいた。してみると、鮎の友釣と季節を同じくするのであるから、われわれが最も害毒のはげしいころに、魚野川へやつてきてゐるといふわけになるのだ。ところでこの恙蟲といふやつは、甚だ不躾の動物で、人間の内股を愛好するのである。内股の肉のやはらかいところとか、圖々しいのは、睾丸などを狙つてくる。まことに、油断もすきもならぬ。
婦人に対しては、文字や口で説明できぬところへ窺ひ寄るから、赤蟲婆さんも手を下し兼ねる。そんなわけで、死亡率は女の方に多いといふ話である。
われわれは、恙蟲に対して以上の程度の知識を持つてゐて、用心に用心を重ねながら、竿を舁いで毎日、川べりを歩くのである。ところが、たうとう私に熱がでた。三十九度の高熱で、私は床の上で、うんうんと唸つた。それは、八月の下旬に入つてからだ。釣友だちは、てつきり恙蟲にやられたのだといつて、大騒動を反してゐる。赤蟲婆さんを呼んでこようかといふことになつたが、生憎この婆さんは、老齢のため二三年前に、冥土の旅ヘのぼつたといふのだ。私はもう一切をあきらめた。
しかし一度だけ、醫者に診て貰はうといふわけになつて、村の醫者を迎へに行くと風邪で外出はできぬから、病人を連れてこい。と、おつしやるのださうだ。そこで、友人たちは三十九度の私を肩に掛けて歩かせた。私は、半分魂を失つた人間のやうに、まるでふらふらだ。
先生は、簡単に私を診察してから、症状から判斷すると、恙蟲に螫されたやうでもあるし、チフスのやうな容態でもある。だが、はつきりしたことは分からない。そこで、念のためきいて置くが、ほかに異状のあるところはないかと問ふのである。
實は毎日、私はあまり長い間水に浸つてゐるため、足の指の間を、水蟲に食はれてひどくたゞれてゐる。數日は、跛ひきひき釣つてゐる始末だ。そこで、釣友である浦佐郵便局長の關さんが、どこからか胡桃の果を探してきて、この皮から汁を絞つて、その汁を水蟲の患部へ塗れば、一夜にして癒つてしまふと、親切に勸めてくれた。私は、ひどく喜んだ。一刻も早く、水蟲を癒して颯爽と竿を振りまはしたいと考へ、一夜に胡桃の汁を三回も四回も患部へなすりつけた。
ところが、胡桃の汁は水蟲に特効はあるが、一回以上塗布してはいけないのださうである。それを知らないで、無闇と塗布したから、足の裏と指の間が、厚く膨れ上つた。これこの通りでございますといつて、醫者の前へ足をだすと、これぢやこれぢやと醫者は、はつきりいつて、膏藥を一貝くれた。
その膏藥を水蟲へなすりつけたら、三十九度の熱は次第に下つて行つた。恙蟲ぢやなかつた。助かつた。
それにしても、御用心、御用心だ。もう、魚野川を逃げださうといふ次第になつて、いのち知らずの数人の釣友を宿へ殘し、森下氏と二人で、上りの汽車に乗つたのである。
さて、汽車の窓から越後の平野を眺めると、稻田が廣々として青い。今年は豊作であらうか、いかがなものであらうか。それが、心配になる。東京へ歸れば、例の外米だ。過去一ケ月間、越後の地米に親しんだのは、私らの儲けものであるから、東京へ歸つての外米を嫌ふわけではないが、いづれにしても豊作であつてほしい。
今秋における農林省の稻作収穫豫想は、豊とでるか、凶とでるか。窓外に走る田面を眺めながら、そんなことを考へてゐると、偶と下見酒の話が頭に泛かんだ。
私の故郷は、上州高崎在の一農村である。御維新以前、私の村は天領であつた。つまり徳川家の直領であつたのである。だから、高崎藩からも厩橋藩からも支配を受けず、岩鼻代官の管下となつてゐた。
岩鼻代官所といふのは、幕府が天保のころから、關東地方へ派出した八州さまの一人で素晴しい威力を持つてゐた。代官といふのは、農民を苦しめる猛獸であつたから、私の村などでは、子供が泣くと、それ代官さまがきたぞ。と、おどせば直ぐ默つてしまつたものだ。その代官さまは、稻作収穫の秋がくると、ますます猛威を逞しうするのである。
秋がくると、代官さまは、管下の農村ヘ毛見に歩くのである。その毛見の次第により、豊凶を定めて、年貢米の額を決定するのであるが、代官さま自身が毛見に出る前、代官の下役が、下見といふのをやるのだ。
代官さまは、江戸で育つた人間だから、田圃を見渡したところで、稻の波の間から、豊凶の程度を見別ける眼識など持つてゐない。そこで下役が下見をし、それを代官に報告して、年貢米の額を定める慣はしとなつてゐたのである。だから、實際には代官さま自身が
農村を見まはるのは、罕であつた。
下役にも、稻の豊凶は、はつきり分からないのである。そこで、下役は農村へ出張してくると、名主の家へ、とぐろをまいて、酒ばかり飮んでゐる。私の家も昔は名主をつとめてゐたから、秋がくると代官の下役が必ずやつてきたと、祖父はしばしば私に語つた。
豊凶の報告は名主の家で下役を接待する方法の、上手か下手かによつて分かれるのだ。つまり、下見にきた役人に、たらふく酒を御馳走するか、しないかによつて、その豊凶の区別がつくのである。農民として、凶作の報告をして貰へば、願つたり叶つたりであるが、豊作といふ報告では、どんなに莫大な額の年貢米を課せられるか、知れたものではない。そこで、名主と村の役人は、下見の役人に、今年は凶作にございます、凶作にございますと唱へながら、腰が抜けるほど酒をのませるのである。これが、下見酒だ。
そして、下見の役人が歸るとき、十分な袖の下を使ふことを忘れない。ところが下見酒と袖の下が十分でないと、つひに豊作となるのである。凶作の秋を迎へるためには、名主と農民は一方ならぬ苦心を重ねたものである。
幕末のころ、私の故郷上州で猛威を揮つたものは、この下見の役人と、渡世人と稱するところの博徒である。博徒らは、物持らしい善良な農家に、目星をつけると、
―― 一番、あいつをしたんでやらう――
かういつた惡業が、幕末から明治へかけて、上州では流行つた。この下見は、強請だ。
ちょい、ちょいしたまれては、やりきれぬ。
(昭和十六年夏)
この頃は抗生物質などないから、恙虫に刺されると一巻の終わりだった。
皆様も、特にご婦人は、甚だ不躾な恙虫には御用心、御用心
5.鱒二、垢石に友釣を教わる
井伏鱒二の『釣師と釣場』の一編「水郷通いの釣師」のなかで、千葉県佐原付近の水郷の寒鮒釣りの名人真野源一さんとの対談に、源一さんが昭和3年、鱒二が昭和5、6年頃に垢石から鮎釣りを教わったときの様子が書かれている。
水郷通いの釣師 (抄)
・・・・・・・・・・(中略)・・・・・・・・
「佐藤垢石を御存知ですか。最初、私は鮎釣りを垢石老に教わりました。」
と源一さんが云った。
鮎釣りは私も初め垢石に教わった。源一さんが教わったのは三十年前だそうだから、私の方が三年か四年か後輩の弟子ということになる。
私は垢石に教わるとき、囮を粗末にして、ひどく叱られた話をした。源一さんも囮を茶化して垢石に叱られた話をした。越後の魚野川で教わったときのことだそうだ。
鮎の囮を激流に沈めるには道糸を相当に長くする。ところが道糸を長くすると、竿を立てても糸が張らないので囮が沖に出て行かない。私も最初のうちはそれに頭を悩ませた。ふと思いついたのは、囮を浅瀬に入れておいて、自分が三歩か四歩か川上に行ってから竿を立てたらどうかということであった。これなら足場さえ悪くなければ通用する方法である。
源一さんも初め魚野川では囮の操作に手こずった。釣宿に帰ってからいろいろ考えた末、その翌日は風呂場の焚口にあった渋団扇を持って川へ行き、沖へ出て行かない鮎をその団扇で煽ぎたてた。囮はみるみる沖に出て行った。すると垢石が遠くのほうからそれを見て、わざわざ叱りにやって来た。
「お前、さっき妙な真似をしていたな。その腰に差しているのは、いったい何だ。」
「団扇だ。暑いからね。」
垢石はたいへん怒ったそうである。
そのときの垢石の激昂ぶりには私にもほぼ想像がつく。たいていの釣師がそうであるように垢石も濁声だが、人を叱るときには特に異色ある濁声を張りあげていた。囮を粗末にすることを何よりも禁忌として、川底に引っかかった囮を一かばちかぐっと引抜くことを厳禁した。私が富士川の十島で初めて垢石に教わったとき、囮を川底に引っかけると、垢石が私に厳命した。
「俺が竿を持っててやるから、川のなかにもぐって囮を外して来い。これは友釣の原則だ。」
当時、まだ十島にはその上流にダムが出来ていなかったので、川の流れが相当に激しかった。富士川や木曽川なども、遠くから汽車で見ると何でもない川のように見えている。ところが、川っぷちに立って見ると案外そうではない。向岸に渡るために浅瀬を辿って行くときでも、足もとの砂が水で激されて掘れるので、リュクサックに大きな石を入れて重しにしなくては足を掬われて流される。
垢石は私が尻込をすると、
「お前は、水というものを知らなくっちゃいけねえ。抱けるだけの大きな石を抱いてもぐるんだ。」
と睨みをきかせた。
私は止むなくパンツ一つになって、抱けるだけの大きな石を抱いて流れのなかにもぐった。囮を外して川から出ると、私の腕時計は硝子が毀れダイヤルが毀れて用をなさないことになっていた。当時、腕時計は紐を外に、時計を内側にする風習が一部にあったので、私もそれに従っていた。
「しかし垢石翁は、鮎を釣るときには、姿も技術も心境も見事でしたね。」
私がそう云うと、
「ほんと、きたない釣服を着てましたが、川へ行くと実に立派でしたね。」
と源一さんが云った。
鮎を釣って囮をつけかえるときの垢石は、いつも釣竿をまっすぐに立てていた。軽妙に囮を扱っていた。五間の竿を片手で軽々とあげていた。囮箱を持って身軽に山裾の小道を歩いていた。
垢石は東京にいるときには飲んだくれていたが、川へ行くとがらりと人が変ったように謹直になっていた。宿に着くと節酒して早く寝た。朝は、私のまだ寝ている間に、川のコンディションを調べて来て、それから私と一緒に朝飯を食べた。初めての土地へ行くと、その土地の釣師に宿へ来てもらって、川の様子や特徴を根ほり葉ほり聞いていた。どういうものか私は、世間の釣師の云うような垢石のデカダンぶりは、旅先では一度も見たことがない。今でも私は垢石のことを立派な釣師であったと思っている。
自分が友釣を始めた昭和四十年代でも、手尻は一尋ほどとるのが普通で、はじめのうちは囮鮎を送り出すのに難渋した。掛かった鮎は竿でタメ、道糸を手繰ってタモに落とし込んだ。当時友竿の長さは四間前後がほとんどだった。
昭和初めの五間の竿といえば少なくとも7~800グラム位の重さがあったと想像され、それを垢石は片手で軽々と扱っていたというのだから尋常の釣師ではない。友釣中興の祖といわれたのもうなずける
さて、初めての友釣で、鱒二が石を抱いて流れにもぐり根ガカリを外した時の様子を、彼に友釣を教えたほうの垢石は「つり姿」(昭和17年発行)のなかの一編、「釣姿漫筆」のなかで次のように書いている。
釣姿漫筆 (抄)
・・・・・・・・・・(中略)・・・・・・・・
私の釣友の一人である小説家の井伏鱒二の釣姿は、まことに悠々迫らぬ趣を持ってゐる。静かにそしてゆるやかに、釣趣を耽味するといふ風だ。
鱒二の文章には、鱒二の人柄がよくでてゐる。誰の文章でも、個性は失はぬものだが、鱒二の文章を讀むと、鱒二が飄々と野路を歩いてゐるのに、逢うような想ひがする。釣りも同じで、その人々によって姿とか振舞とかに異なったところのあるものであるけれども、鱒二の釣場に在る持味といふのは、寒山拾得の匂ひがある。全く、枯れきってゐる。
だからと言って、鱒二は不満に思ふかも知れないが、鱒二の釣は永年の經驗を持つものではない。しかしながら、鱒二に竿を持たせて水邉に立てると、その釣姿が板についてゐる。まことに、妙なことであると思ふ。
實をいふと、鱒二は私の釣弟子なのである。四五年前、甲州の富士川の十島河原へ伴って行って、鮎の友釣の手ほどきをしたことがある。そのときは、八月の末か九月のはじめで、鮎は肥育の絶頂に達して、七八寸の長さで四五十匁。まれには、六七十匁の大ものが掛かってくる季節であった。
鈎の結び具合から、囮鮎の鼻の穴へ鼻鐶を通す次第。竿捌きのあんばい、囮鮎を水底へ巧に泳がせる方法など、私が細やかに實演してみせると、鱒二は直ぐ會得してしまったらしい。やがて、鱒二は自ら竿をとって、私が敎へた通りにやりはじめた。見ると、からだのこなしや、竿の持ち方まで、はじめて友釣を試みる釣人とは思へぬほどである。静かに竿を上流へ引きあげて行くうちに掛かった。彼は、苦心に苦心を重ねて掛かった鮎を、汀へ引寄せそれを手網で掬ひとった。
それがなんと五十匁もある大鮎ではないか。沈着の彼でも、さすがに胸の動悸を抑へきれぬといふ態である。囮鮎をとりかへてから、さらにそれを急流のなかへ泳がせて行ったところが、少し錘が重過ぎたためか、綸が水底の岩に噛まれて、上がってこない。このまま綸を切ってしまへば、囮鮎を失ってしまふことになる。
そこで、私が言った。鮎の友釣には、囮鮎を大切にすることが、作法である。だから、ここで綸を切ってはならぬのだ。この激流のなかへ飛び込み、潜り込んで綸を岩からはずし、囮鮎を取ってくるのがよい。しかし、この奔湍の底へ潜ぐり込むのは、大抵の業ではない。それには、一貫目程度の石を左の腕に抱へ、頭を下にして潜り込めば、容易に水底に達する。これは、なかなか恐ろしいことだが、貴公にやれるかと問ふたところ、師匠の敎へとあらば、敢然としてやると言ふのだ。
つひに、彼は決心したらしい。裸になり石を抱へ、ざんぶと流水のなかへ飛込み、水底へ潜り込んで、囮鮎を取ってきた。それで、安心した。が、水へ入るとき腕から時計をはづして置くのを忘れたため、彼が大枚を投じて求めた腕時計は、水底の石に當ってめちゃめちゃに壊れてゐた。向かふ脛からも肉が破れて、鮮血が流れてゐた。
途方もないことを敎へたものだ。と、私は悔いた。けれども、鱒二の勇気と、釣りの作法に忠實なるには驚いた。貴公は、將來一かどの釣人になれるであらう。と、言って大いに劬つたものだ。
それから、また釣りはじめた。彼は自分の釣場を守り、釣場の個性を味ふやうに、一二町の間を上下して、決して私等の釣場の方へ色目など使ふ風は無かったのである。釣には、嫉妬心を最も禁物とする。他の釣人が、いかに數多く釣らうと、それをねたむ心が起こってはならぬ。自分は自分で、自分の釣場を研究し、親しんでそこで釣らねばならない。と、いふ道理があるのである。鱒二は、いつの間にか、この道理を心に解してゐたと見える。
脇目もふらず虚心の姿で釣ってゐたが、たうたう夕方河から引きあげるまでに、大ものを七八尾釣りあげた。初心者としては、素晴しい手柄であった。
これは、鱒二が虚心の姿で、わが釣場を物してゐたためであったらう。
釣の道は、人生の道と相通ふところがある。釣に嫉妬は禁物であるやうに、人生にも嫉妬心は魔物である。その心に打克つことは、一つの修養である。やきもちは、人間の弱點だ。これを抑える一つの修養でも、並大抵のことではない。
他人が發見した釣場へ割り込んで、そして數多く魚を釣つたところで、それは自ら顧みて愉快ではないのである。人間が世に處する道も、これを撰ばない。吾等は、先輩の訓へをよく守り、そして人生のわが釣場に、謙虚な心を持つて、親しまう。
(*注;古くは、釣り糸を緡糸(ビンシ)といい綸(リン)ともいった。緡と綸は同じ意味である。)
この二人は大人だ。 言いも言ったり! やりもやったり!
「釣には、嫉妬心を最も禁物とする。」とここに書いてある。 確かにそうだ。
しかし、他の者が多く釣るのをねたんだり羨やんだりせずに悠々と釣りをするというのは凡人には為し難いことだ。
6.釣 人 井伏鱒二
これは垢石との思い出を綴ったものである。
釣 人
十何年前のこと。佐藤垢石氏が亡くなって間もないころ、得山さんという釣好きの老人が、垢石先生の書翰または短冊を、得山さん所蔵の骨董品と交換してくれと手紙で云って来た。当人は目下病臥中のため、口述して枕頭の者に代筆させていると断わってあった。女性の筆蹟である。この手紙を私は他の古手紙と一緒に蔵っていたが、ちょっと参考のため今ここに取出した。ずいぶん長い文面だから、原稿二枚程度ですむように抄出する。
このたび、はからずも佐藤垢石先生の訃を新聞で知った。哀悼にたえない次第である。不躾ながら貴殿は垢石先生の鮎釣の弟子と聞いている。おそらく貴殿も落胆されたことだろう。謹んで弔意を表したい。
さて、自分は垢石先生と相識の間ではなかったが、かつて鮎の釣場に於て他所ながら見かけたことが再三再四に及ぶ。その釣姿はまざまざと自分の脳裡に残っている。服装は粗末で古風だが、竿をかまえている姿、竿を立て鮎を引寄せるときの姿が見事であった。ことに囮の鮎を附けかえるとき、一般の釣師と違って竿を垂直に立て、囮をつけかえる操作をしながらも、穂先を微動だにさせないのは神技であった。自分は目近くそれを見て、あれは頬と肩と、折りまげた膝とで竿の手元を挟み、垂直に立てることによって竿の重さを消しながら、安定を保たさせているものと見た。爾来、自分は囮をつけかえるにその型を真似て来た。これを釣師としての自分の誇とした。
御承知の如く友釣は奥が深い。自分は不惑の年から友釣を習い、遅蒔きながらその快味を覚えたので、反って執心の仕方が只ならぬものであった。釣のために会社を縮尻ったこともある。今では病床にあるため川にも釣具屋にも行けないが、釣場の思い出は鬱屈した今日の自分の気持を引きたててくれる。ついては僣越ながら垢石先生の筆蹟を表装して床の間を飾り、先生の神技を偲ぶよすがとしたい。もし貴殿に於て垢石先生真筆の色紙または書翰の類を御所蔵なら、自分の所蔵する骨董品の何かと交換して頂きたい。
自分は一度、渋川の釣場に於て垢石先生の魚拓を見た。一尺ちかい鮎を巧みに刷り,釣った年月日と御名前が書いてあった。しっかりした筆蹟だと思った。
右のような次第であるが、どうか病床に伏す年老いたる釣の虫を喜ばせるようにして頂きたい。
―― 以上。
私は昭和二年から現在まで、日記を書く手間を省くため、人から貰った印象の深い手紙を選んで溜めて来た。嬉しい手紙、悲しい手紙、用件の手紙、第三者のことについての手紙、旅行に出る打ちあわせの手紙、寄書の手紙、飲友達の書いてくれた送状など、各種各様だが、月に大体十通ぐらいの割で手文庫に入れ、ときたまそれを纏め、紐で縛って押入のなかの大箱に蔵って置く。垢石の手紙も何通かある筈だが、毛筆で書いた書翰を垢石から貰った記憶がない。鉛筆やペンで書いたものばかりだ。
巻紙や詩箋のようなものは使わなかった人だろうか。得山さんへの返事には、せっかくのところ毛筆のものがないから、御期待に添いかねると書いた。
話は別だが、先月か先々月、「林芙美子を語る対談会」に出ることになったので、 押入のなかの古手紙の束をほぐしてみた。昭和四年か五年ごろ、林さんが尾道へ講演旅行に出かけた年月日と、講演を引受けた経緯を確かめたいためであった。確か昭和四年の春ではなかったかと思う。
そのころ私のうちでは電話を引いてなかったので、ちょっとしたことでも葉書か手紙で用を弁じていた。旅行の打ちあわせとなると、日取の変更とか同行者の都合など、いろいろ手紙で打ちあわせをするから林さんの手紙も何通かある筈だが、なかなかそれが見つかってくれなかった。まだか、まだか、と忙しく繰っていると、私の実の兄貴のよこした親展書留の手紙が出た。意外であった。兄貴の手紙は一通も保存してなかった筈なのに、東京市外井荻町下井草一八一〇(現在の東京都杉並区清水一ノ一七ノ一)の私宛である。消印は昭和三年二月二十日となっている。
そのころ、私の兄貴は生れ在所で元気に暮していた。私によこす手紙には、いつも兄貴風を吹かすようなことを書いていたが、太平洋戦争の最中、昭和十七年に私が徴用でマレー半島へ行っている間に亡くなった。急性肺炎で僅か六日患っただけである。その訃報はシンガポールの徴用員事務所で受取った。爾来、二十八年ぶりに兄貴の手紙を(古手紙だが)手に取ることが出来た。もうこれ一通以外には、私宛の兄貴の書翰は残っていない。
その手紙の中身を、私は見ないで保存するだけにしてやろうかと思った。兄貴風を吹かされていたら厭である。でも、ちょっと封筒の匂を嗅いでみた。手の平に載せて重さがあるかと揺すってみた。それから中身を出してみると、兄貴の手紙のほかに佐藤垢石の手紙が入っていた。
兄貴の手紙を先に読んだ。
拝復
お手紙拝見。(中略)の為替を送ります。半端の分は配当金としてもらったものですが、そのまま送ります。そして、この半端の分は「二月十五日」のお前の誕生日のお祝いとして。
十一日の紀元節の日、田和の安夫さんに逢い法成寺村を訪れました。一月二日、私を田和家で招待してくれたのですが、忙しくて行けなかった。これは二日に、お婆さんの七十七の賀があったそうで、草浦の医者と私を呼んだのであったと言っていました。半日話して帰りました。
小説もお前が下積みで苦労することは承知の上だし、私はかまわぬけれども世間体からは、ちょつとぐらい売れてくれるのは悪い事ではない。お前は学業も途中で止めたりしているし、勤めてみても長く続く事でもあるまいし、行く道は一つときめて今の仕事を成就してくれなくては困る。
急ぐ事もないわけだが努力は統けなくては、と思います。
二月十九日
文 郎
鱒二殿
追伸。三月八日は亡父の命日です。その頃、法事をする考えです。お前は帰らぬでもよいでしょう。
「世間体からは、かね。」つい私は、心のなかで云ってみた。大事な亡父の法事に、文学青年やつれのすがれた舎弟が東京からのこのこやって来て、親戚や近所の人の集る席に顔を出す。兄貴としては、たまったものではない。世間体からは具合のよいことではないのにきまっている。
こんな手紙を貰ったことは忘れていたが、読みなおしているうちに、半端の金をつけた為替を兄貴から受取ったことを思い出した。それでまた消印の日附を確かめて繰返し読んでいるうちに、だんだんと思い出すことが重なって昨日のことのようにはっきりした記憶になって来た。私が高利貸へ払う金を送ってくれたときの兄貴の手紙である。昭和二年の夏から三年にかけ、私は代田橋の高利貸に払う利息に追われていた。月末ごとに、その高利貸がジンジン端折りに自転車でやって来て、「いったい払う気か払わない気か、はっきり云って、どっちだね」と高飛車に云うかと思うと、手のひらを反したように、「いや、大した金額でもございませんからね、すぐお払い下さいますね」と云ったりした。慇懃尾籠というのがこれだ。血の出るような金をしぼるには、この手を使うのも一方法だろう。こちらは纏めて払うことが出来ないので、利息だけ払って引取って行ってもらう。
実際、大した金ではないが、無い袖は振れないのであった。月末とか年末というものが嫌いになった。
昭和二年の四月上旬、私は現在居住するこの地所へ家を建てることにして、家が出来あがるまでの予定で荻窪八丁通りの平野屋酒店に下宿した。建築費は纏めて兄貴から送って貫い、たまたま地所をさがしていて知りあいになった老人の紹介してくれた棟梁に、前金で建築費をみんな手渡した。棟梁はいつも酒を飲んで現易へ来るお人好しのような男だが、どうしたことか建前を終って屋根瓦を上げたきり雲隠れしてしまった。下請の大工は年とった方も若い方も、棟梁の住所を知らないと云った。
それで紹介してくれた老人のところへ棟梁の住所を訊きに、若い方の大工を連れて行くと、
いきなり向うは居丈高になって大工を叱りつけた。
「無礼者。ここは、大工ごとき者の来るべきところでない」。
えらい剣幕で大工を先ず縮みあがらせた。私には言葉をにごして話を有耶無耶にさせてしまった。こいつ、ずるいぞと痛感したが、なぜ老人がそんなにまでずるくして言を左右にするのか、わけがわからなかった。
私は泣き寝入りの気持で兄貴にまた助けを求めたが、お前の芸者買いの尻ぬぐいは出来ないと云って来た。そんな高踏的なことで困っているのではない。嘘ではないのだ。だが、仕方がないので、膝とも相談という気になって、平野屋酒店の主人に事情を打ちあけ、主人の細君の紹介で代田橋の高利貸から借りた。その金で他の大工に家の恰好をつけてもらったが、てんびき日歩十二銭という借金だから難儀なことであった。結局、兄貴から別口の送金を受けて、気掛りな代田橋の方の始末をつけた。兄貴からのそのときの送状が、昭和三年二月二十日附のこの手紙である。
「おい、こんな手紙が見つかった。ちょっと、これを見てくれ」と私は家内を呼んだ。「亡父の法事はするが、僕には帰らなくてもよいと云ってるよ。よっぼど世間体を気にしてたな。」
「眼鏡がなくては」と家内は、手紙を茶の間に持って行った。
私はこの手紙と一つ封筒に入っていた佐藤垢石の手紙を読んだ。年代は不明だが六月二十六日の日附である。垢石に初めて友釣を教えてもらうとき、日取の打ちあわせを兼ね、釣道具について詳しく指示して来ている手紙だから、昭和五年か六年ごろのものである。それにしても、どうしてこれが昭和三年の兄貴の手紙と同居していたのかわからない。
「読みました」と、家内が手紙を返しに来た。「法事のときのことは、私たちに汽車賃を倹約させるためなんでしょう。あのころ、あなたは電車賃にも不自由しましたものね。」
「なんだ、そういう考えかたか。それなら、もういいよ。」
「でも、よほど思ってらしたのね、お兄さんは。ちょっとぐらい売れてくれるのは、悪いことではない。うまいこと仰有るわ。」
「もう結構。」
わざわざ手紙を読ませて置いて、もう結構もないものだが、ちぐはぐの会話をするのが私のところでは相互間の常例である。外出するときでも、今日は着物で出かけると云えば背広がいいでしょうと云い、今日は洋服でお出かけでしょうと訊かれると、和服で出かけると云う。
私は垢石の手紙を読んだ。これは鮎の友釣を教えてもらうため、私が送った依頼の手紙に答えてよこした返事である。友釣を全く知らない者へよこした手紙だから、微に入り細に入り、噛んで含めるように書いている。
拝復
益々御健勝の趣にて祝着に存じます。小生、先週より久慈川へ行き、川のこんでっしょん最良にして快味満喫して一昨日帰りました。
さて御申越の件、仔細承知仕りました。昨日の情報では富士川の十島上々とのことですから、今月三十日に植田氏と同行する予定にしていたところです。大雨のない限り当日出発します。植田氏はキノケン先生(木下謙次郎)の甥御さんで水産講習所の先生です。鮎の食むヌラ、珪藻や藍藻の研究で理学博士になった人ですが、釣はまだ下手で三年前から小生の釣弟子になっています。遠慮の要らない人です。大兄が今度の十島行に参加されても後口が悪くないと思います。
ついては出発の日時と、持参すべき道具類を記します。予定変更のときは改めて電報で申します。
友釣の仕掛の仕方は汽車のなかで見本をお目にかけます。そのとき覚えて下さい。
予定――三十日午後三時、東京駅一二等待合室に集合。但、切符は三等にて行先は富士駅。富士駅から身延鉄道で十島駅下車。この駅の待合室で夜を明かし、雑貨屋で囮を譲ってもらう。すでに手紙で交渉済。
釣道具、並びに服装その他――釣道具は阿佐ケ谷の釣具屋で仕入れて下さい。
○鮎の友釣用の竿(三間半。初心者はすぐ駄目にするから、値段の安いもので間に合わすこと。竿は竿袋に入れること)
○道糸(人造テグス一巻き、太さ二厘りん)
○ テグス(一厘半を三本、二厘を五本。但、みがきテグスのこと)
○鉤(掛鉤、一寸のもの。逆鉤と共に)
○ おもり(三匁のもの三つ、二匁のもの二つ)
○鼻鐶(三箇から五箇ぐらい)
○ たも網(友釣用)
○やすり(掛鉤を磨く小さい鑢)
○魔法瓶(筒型)
○通い筒(釣具屋になければ、竹筒一節にても宜し)
O目じるし(二つ。水鳥の羽に限る)
○赤い絹糸(長さ二尺ほど。これは捻って穂先につける。裁縫用のもみにても宜し)
○脚絆、わらじ(二足。わらじが無ければ足中草履二足。但、足中の場合は、二尺ぐらいの古繃帯を二本添えること。足首にくくりつけるため必要なり)
○古足袋(一足。素足にては、わらじの紐で足にまめが出る。富士川の十島で荒瀬を渉る必要あり、足ごしらへ堅固にすべきなり)
○服装は軽快なるを旨とすること。
○弁当(二日分持参のこと。二日目の昼飯用と夕飯用は食パンが宜しい。握飯に梅干を入れないこと。釣場に梅干を持込むこと禁物なり。釣に出る朝も梅干しは食べないこと)
十島には宿屋兼業の店屋もあれば、我々は終車にて十島駅に着き、黎明より川へ向う予定につき、駅の待合室にて仮寝する。旅費節約のためもあり、匠気もあるのです。
以上の通りです。この手紙を阿佐ケ谷の釣具屋に見せて御頼み下さい。 敬具
六月二十六日 佐藤垢石
井伏鱒二様
私は大体この手紙に云ってある通りにして出発したが、囮箱を提げ、たも網をくくりつけた太い釣竿を持って、リュクサックを背負っているのだから、われながら仰々しい恰好だと思った。弁慶の七つ道具のようなもので、これが友釣をする者の通有な姿であった。当時は竿袋も今のような頑丈なズック製でなく、たいていの釣師が白木綿か鬱金の木綿でつくった自家製のものを持っていた。ぎりぎりいっぱいに竿が入っている袋である。だから通りすがりに釣師を見ても何を釣りに行くところかすぐわかった。
十島へ行くときの佐藤垢石は、甚平を着て寸の短いよれよれの上張を羽織り、黒儒子の釣竿袋を持っていた。その中身は、漆を少しも表に出さない四間竿である。高崎竿と云って胴調子だそうだ。障害物のない河原なら胴調子のものがいいと聞かされた。植田さんの釣竿は長さも大さも私の記憶にない。
垢石は汽車が動きだすと、テグスの結びかたや友釣の仕掛のつくりかたを教えてくれた。それを言葉のままには覚えてないが、仮に垢石の日ごろの口癖を真似ながら、記憶のかけらを繋いでみる。
「おい井伏や。本テグスは一重むすびにしても大丈夫だ。人造テグスは二重むすびにしなくっちやいけねえよ。さもないと、水のなかで、すっぽ抜けちゃって、始末が悪い。まアるで駄目だ。」
一重むすびや二重むすびのほかに、藤むすびという簡単な結びかたも教えてくれた。山の木樵が薪を藤蔓で縛るときの結びかたである。赤い絹糸も、熟練した手つきで縒ってくれた。これは鮎の鼻に通す鼻鐶を、あまり窮屈でないように仕掛の附根のところに留めるための部品である。これについての垢石の説明は、さっきと同じ流儀で纏めると、こんな風なものではなかったかと思う。
「おい井伏や。鼻鐶は、こうやって、囮の鼻に通してやる。手柔らかに、すっと鼻の穴に通す。それでなくっちやいけねえよ。鮎の鼻は右の穴と左の穴が、奥の方で軟骨でつながってるからね。無理やり捩込むてえと、囮のやつ、鼻血を出して、やっこさん脳震盪を起しちまう。まアるで駄日だ。」
私は教わった通りに糸を結び、見本を真似て仕掛を二つ三つ拵えた。その掛鉤の研ぎかたも垢石が教えてくれた。鑢で鉤先を鋭くするのだが、鎗の穂先のように三面から尖らすのが最良であると教えられた。
「鉤は、しょつちゅう研がなくちやいけねえよ。拇指の爪に、突きたつぐらい切れなくっちゃ。あのな井伏や、川に来たら鉤を研ぎに来たと思え。」
鉤先は外側が二面になるように磨き、内側を平らに研ぐのが原則であるそうだ。(私はずっと最後までそのやりかたを守って来たが、最近の或る釣の書物に、掛鉤の先は外側を一面に、内側を二面に研いだ方が効果的だと書いてあった。研ぎかたにも変遷があるようだ)
富士駅に着くと待合室で弁当を食べた。それから町見物をしたような気がするが、植田さんが酒屋で正宗の一升瓶を買った以外のことは記憶にない。とにかく私たちは身延鉄道の終車で十島駅に着き、後は垢石の手紙に書いてある予定通りにした。
そのころ十島の近くのダムはまだ出来ていなかった。今では富士川も十島附近はみすぼらしい流れになっているが、当時は豊富な水量で右岸寄りに凄みのある荒瀬をつくり、石畳の下手に大きな青い淵があった。橋はどこにも見えなかった。だが、石畳のところが目的のあな場だから、奮発して荒瀬を渡らなくてはならなかった。垢石は褌ひとつになって草鞋の紐をしめなおし、脱いだズボンや上張を河原の丸石と共にリュックサックに入れた。丸石は二つも三つも入れた。植田さんも私もサルマタひとつになって草鞋で足ごしらえしたが、私が丸石をリュクサックに入れないので垢石が叱った。
「おい、リュクサックに石を入れること。お前、知らねえか。洪水のとき、川の鰍は小石を腹のなかに呑みこむよ。水に流されねえように、自分の体に重みをつける。やつらの習性だ。」
無論、確かな記憶はないが、そういったような云いかたをした。私も植田さんも、メロンよりずっと大きな丸石を二つ三つリュクサックに入れた。
荒瀬を渡る辛さがよくわかった。否応もないのである。垢石が何やら云うのも川瀬の音で掻き消された。流されまいとして釣竿を突っかい棒にしようとすると、流れが竿を吹きあげる。足を踏んばって一息つくと、足の草鞋で水が滾って足元の砂が掘れる。その穴へずるずると草鞋がずれて行く。川底の石に乗ったら草鞋ばきでも滑ってしまう。私たちは辛うじて向岸に辿り着くことが出来た。リェクサックのなかのずぶ濡れのものは、太陽で乾かすため石畳の上に取並べた。弁当の包みも濡れていた。
苦労した甲斐あって、ここは絶好の釣場であった。八、九寸の囮で八、九寸の鮎が釣れるので、植田さんは二尾同時に掛けた途端、二厘の道糸を切られた。無論、囮に逃げられた。それで細い銅線の釣糸に取りかえた。
私も二厘の道糸を使っていた。いい道糸であったのだろう。一度も糸を切られることはなかったが、囮が水底の何かに引っかかったときにまごついた。あまり強く引張ると糸が切れるのはわかっている。軽く引張ったくらいでは抜けないので、川下にいた植田さんに「植田さん、助けてくれ」と音をあげた。すると川上にいた垢石がやって来て、
「俺が竿を持っててやるから、お前、川に潜って行って囮をはずせ。流されねえように、大きな石を抱いて潜れ。抱けるだけ大きな石を抱け。もうちょっと、川上から水に入って行け草鞋も脱げ。」
そう云って竿を持ってくれた。私は草鞋を脱ぎ眼鏡を取り、サルマタ一つで大きな丸石を抱いて水に入って行った。大体の見当つけた位置で石を離す途端、道糸をさぐり当てると、水底の石と石との間に錘が爽まっているのがわかった。私は囮に手は触れなかったが錘に手を触れたので囮が流れに吹きあげられた。これで囮は助かった。私は川下に流されて、石畳の下の崖の出っばりに無事漂着したが、腕時計をはずすのを忘れていたので、硝子が毀れて針も無くなっていた。(当時、腕時計は腕の内側に向けて着用するのが流行っていた)垢石は竿を私に返すとき、「なあ井伏や。お前、見込みがあるよ。水というものを知ってるじゃねえか」と讃めてくれた。これは私の一生忘れられない言葉の一つである。
昼の弁当は水気のある食パンで我慢した。垢石が三人の囮箱を調べると、植田さんは三尾、私は九尾、垢石は十八尾釣れていた。
この釣場で、垢石は自分で釣る前に私に竿の持ちかたから教えた。たも網の使いかたも、足のくばりかたも教えてくれた。そのときの感想を私は数日後に雑文に書いたので、垢石の云った釣師の心得を今でも覚えている。
「のう井伏や、釣をするときは、お前、山川草木に融けこまなくっちゃいけねえよ」。
垢石自身もこのときの釣について、ずっと後に随筆に書いて雑誌に出した。私が大鮎を十二尾も釣ったと書いていた。私に代って法螺を吹いてくれたのだ。
私は林芙美子の古手紙を捜しかけたまま、ふとして見つけた垢石の手紙で四十年前の釣場の情景を思い浮かべていた。釣をするときには、あたりの風景など見る気はないが、なぜだかはっきり記憶に残っている。この記憶している風景と、実際の風景を実地に較べてみたくなった。それを実行する代りに垢石の手紙を読みなおした。こんなことでは用に足りないのはわかっているが、「いや、ちょっと待て。ついでに、もう一つか二つ垢石の手紙を見てやろう」と、別の手紙の束をほぐしてみた。意地悪いもので捜そうとすると出て来ない。
「おい、ちょっと来てくれ。なあ、かあさんや」。私は垢石の口真似をして、
椽側にばんやり腰かけている家内を呼んだ。「この手紙の束から、垢石老の手紙か葉書を捜してくれ。」
「そんな捜しものをするのは、大阪では、おお辛気くさと云うでしょう。お茶を持って来ます」と家内は、椽側の日向ぼっこを切りあげた。
古手紙も昭和六年ごろから二十四年までのものは半分以上、あとさき混ぜこぜでハトロンの袋に入れてある。いつか新潮社版の太宰治集に入れる「作品解説」を書く際に、太宰君の古手紙を資料にするため取出して、用済みのあとはかまわず乱雑に他の人の手紙と一括してハトロンの袋に入れて置いた。ごたごたにして年代順も何もない。
この袋のなかに、垢石のよこした絵葉書一枚と、普通の葉書一枚と、手紙が二つあった。絵葉書には、昭和十三年八月二十一日、富山・八尾局の消印がある。普通の莱書の方は、昭和十九年九月十日、大連・中央局となっている。十三年ごろから十九年までのころは、垢石の釣技が円熟して釣姿もひとしお立派な時代ではなかったろうか。戦争さえなかったら、油が乗りきって釣に生き甲斐があるとしていた期間ではなかったろうか。釣には妙諦というものがあり、それを会得するには「姿・心境・技」の三つが揃わなくてはならぬと垢石が云っていた。姿は大事らしい。
絵葉書は「室牧川瀬戸の鮎」三尾の写真版で、鉛筆で書いてある。
釣の旅へ出て八日也。越後の魚沼川、加賀の国の手取川、富山の九頭龍川を廻り、昨朝、越中の室牧川へ来たりて釣る。近年稀れに美味なる鮎を食べました。本日は飛騨の○川(不明)へ向い蟹寺に一泊、明日は高山を経て下呂温泉に向う予定。山には初秋の風そよぎ居り候。
八月二十一日 下の名温泉にて 垢石
自分の好きな川をはるばる尋ねて行って存分に釣りまくり、昼弁当を食べると囮箱をさげて次のあなへすたすた歩いて行く。そういう釣人垢石の姿が偲ばれる。越前、越中、越後の川の鮎は、八月中旬ごろに凌い馬鹿力を出すそうだ。私は垢石から何度もそれを聞かされている。
垢石は身が軽くて足が早かった。ことに囮箱を持って畦道などを行くときには、こちらは半ば駈足にならなくてはついて行けなかった。一刻も早く囮を流れに漬けて、新しい水を飲ましてやろうとして大事にするからだ。
いま一つの、大連中央局の消印のある葉書は寄書でよこしている。戦争中の満洲国の葉書だから、表の裾のところに「決戦だ 理窟は抜きだ 実践だ」と、冷やりとさせられる標語が印刷されている。
八月十日東京発、十七日新京着、直ちに釣旅につき、東満の鏡旧湖、老爺嶺の渓流、大興安嶺の清流等にて大物を釣り、五六日前、撫順に来たり附近を釣り、昨日大連着。本日、旅順に向い海釣をなす。中旬、新京に帰り吉林を釣り、さらに二十日過ぎ蒙古界の川にて大物タイメンを釣る予定なり。満洲には酒極めて潤沢、美味豊富、この頃少し体重回復せる模様なり。(垢石)
垢石老との旅は辛い。しかし愉快至極です。辛いというのは渓流を歩かせられるからです。大興安嶺下の老の釣姿は立派でした。(熊)
九月十四日
大連市遼東ホテル五階 佐藤垢石
「熊」と署名しているのは、元報知新聞にいた熊田さんのことで、通称「鎌倉の熊さん」である。関東大震災後、報知新聞が図抜けて華やかなころ社会部次長を勤めていた。当時、垢石もそこに籍を置いていた。永井龍男の次兄永井二郎さんもそこにいた。これは通称「ジロさん」と云う。部長は御手洗みたらい辰雄氏であった。
この葉書の宛書は「大日本帝国東京都杉並区清水町二四」の私の名前になっている。久しぶりに見る国名である。その大日本帝国の「大」の字のわきに、附箋を剥がしたあとが微かに残っているのに気がついた。
「そうだ、僕がもう疎開していたころだ。」
私は十九年七月に甲州甲運村へ疎開して、この葉書が来る九月ごろは、晴雨にかかわらず毎日のように笛吹川で鮎を釣っていた。釣場は、差出の磯の目がね橋の下である。ここは笛吹川での私の釣の師匠に当る塩山町の矢崎さんという人が、友釣の根城にするのは今年はこの場所だと教えてくれたところである。おかげでよく釣れた。私が垢石に連れて行かれたいろいろの川のうち、笛吹川で最初に釣った場所もここである。そのせいか、この場所に親しみを持ち続けることが出来た。橋の下手の広々としたふかんどに貝殻型の大岩石が突き出して、矢崎さんの云っていた通りその岩の膝元あたりがよく釣れた。笛吹川の漁業組合は、その年には近江から取寄せた稚魚を一とまとめにこの淵に放流したそうだ。それに雨が少くて鮎がここから動こうとしないので成長が後れていた。
「かたは小さいが、釣れることは釣れる。しかし馬鹿な放流の仕方をしたものです」と矢崎さんが云った。それでも釣れる日もあり釣れない日もあった。
垢石と私がこの釣場へ行ったのは、昭和十五年の盛夏ではなかったかと思う。三宅島噴火の直後に行ったのは確かだから、大体そのころと思って間違いない。
三宅島が噴火したのは七月十五日の真夜中であった。私は三宅島噴火のことを「御神火」という題の小説に書いたから月日も覚えている。島の中央雄山の中腹から、いきなり巨大な火柱が中天に噴きあげて、その柱の根元のところから斜めに向けて細い火の線が噴出した。島じゅう大騒動になった。御神火を畏れ奉る古代人の思想が一夜にして復活した。その夜は本土も大雨で、ことに奥伊豆に大洪水が出た。折から谷津温泉の南豆荘に泊っていた私は、連れの亀井勝一郎君や太宰君夫妻と這々の態で逃げ帰った。
もう少しのことで避難するところであった。濁流が滝のように窓から入って来て、柱に突きあたる流木のうちには、祠の小さい鳥居や櫺子や将棋盤などもあった。竿袋にしまって壁に立てかけて置いた私の釣竿は、濁流に浚われて川下の橋桁に引っかかっていた。水が引いてからそれを見つけた土地の釣師が、「これは南豆荘の客の竿だ」と云って、わざわざ持って来てくれた。阿佐ケ谷の釣具屋で買った大衆竿という安物だが、けばけばしく赤漆を塗ってあったので、自家製の竿しか使わないこの土地では人目についていたのだろう。そのころ漆を塗った竿を持って来る釣師は、ここではまだ減多に見られなかった。
私と垢石が笛吹川へ行ったのは、帰りに甲府へ寄って鰻を食べたいためもあった。釣竿は谷津で流されそこねたのを持って行った。濁流のなかに何時間も潰かっていたせいで、竿師が手を加えた箇所の縒が戻って勝手放題になったので、抜くときに手数をかけなければならなかった。垢石は釣旅行に出たときの常例として、日下部町の宿屋で私の釣道具を点検して釣竿を見ると、「まアるで駄日だ」と云った。「これでも遭難記念の竿だ」と私が云うと、「こんな竿では、囮が難儀をする」と云った。垢石が何かにつけて思うのは囮の姿であったようだ。
その晩、甲府の町の釣師が垢石の入峡を歓迎する意味で宿へ訪ねて来た。この客人は垢石のために、この宿の部屋を予約して置いてくれたのだそうだ。すぐ近くに川が流れていて釣師が集って来る宿だから、大事をとってくれたのだ。私は二人の話を傍で聞いていた。垢石は客人に喋らせるように話を仕向け、笛吹川や釜無川の釣場について不自然なほど詳しく訊いた。いつかも云っていたが、報知新聞時代の垢石は、ひところ甲府支局詰になって釣ばかりしていたそうだ。この辺の川ならよく知っている筈なのに、好きなビールも一本きりにして、最後まで聞く側になっていた。東京に帰ると町の大酒飲になるのに不思議なほどであつた。
翌朝は、私がまだ寝ているうちに、垢石は川の様子を見届けて来て、それから私を起してくれた。釣に対して用意周到な気組である。笛吹川へ行く四、五年前、私と銀座の官坂普久さんを連れて久慈川の奥へ行ったときも、釣の前夜はビールを一本きりで止した。やはりこのときも、垢石を歓迎するために、十人ちかくも土地の人が酒やビールを持って来て酒宴を開いた。釣宿の主人が前もって、釣人佐藤垢石の来泊する日を近隣へ触れてまわって置いたためである。垢石は照れも気取りもせず、自分が喋るよりも訊く方を先にして、その附近の釣場のこと、流れこむ枝川のこと、この土地の釣師の仕掛などについてこまごま質問した。私と普久さんは客人が帰るまで酒のつきあいをしたが、垢石はいつの間にか早いとこ消えていた。「土遁の術、火遁の術。釣宿へ泊ると、いつもあれだ」と普久さんが云った。翌朝は、私がまだ目をさます前に川の様子を見て来た上で、私と普久さんを起してくれた。それでも何となく当然のことのように思わせてくれるので、こちらは勿体ないという気もしなかった。
私は甲州に疎開中、笛吹川の釣の師匠の矢崎さんに一度だけだが叱られた。矢崎さんの選んでくれた釣場は、垢石と一緒に釣ったのと同じ場所であった。この釣場の様子も私は雑文に書いたことがある。だから記憶に残っている。貝殻型の大岩の上に出て釣っているとよく釣れるので、鮎が掛かると水際まで歩いて行く代りに、ちょっと遊び半分の気で、しゃがんで滑って行ってたも網を使った。二度三度そんな釣りかたをしていると、川下の方のざら場で釣っていた矢崎さんがやって来て、「まじめに釣らなくては駄目じゃないですか」と怖い目で叱った。垢石の山川草木説と同じ傾向の言葉である。ふざけてみたり投げやりにしたりしてはいけないのだ。囮を粗末にすると「囮、囮……」と垢石が凄く怒鳴るのは、私たちをただびっくりさせるためばかりのものではない。東伊豆河津川の谷津で私の釣の師匠になってくれたカワセミの親爺という老人は、私が上の空で釣っていても叱らなかった。この老釣師のことも雑文に語いたことがある。記憶に残っているのはそのためでもあるようだ。この老人は子供のころからの川魚専門の漁師だから、どうせこちらが保養がてらの隠居釣に来ていると思っていたようだが、一度だけ例外があった。或るとき私が、面倒だから弱った囮を取りかえないで釣っていると、「なあ、お前さん」とカワセミの親爺が、そっと後ろにやって来て、私の耳もとで「もそっとお前さん、川に食らいつかなくっちゃいけねえ」と云った。
このカワセミの親爺と私は、お互に河津川で釣をするときだけのつきあいだが、昭和七、八年ごろから釣の師匠と弟子の関係を保って来た。その間に私が聞いて覚えている訓戒は「お前さん、もそっと川に食らいつけ」という言葉だけである。趣旨から云って、これも塩山町の矢崎さんから聞いた叱言に似通っている。垢石の山川草木説にも通ずるところがある。
いま私は気がついたが、カワセミの親爺は銅鑼声であった。矢崎さんも垢石もそうであった。人間の声帯は川瀬の音と何か関係を持っているのだろうか。野鳥も水鳥はがらがら声を出す。
カワセミの親爺も七、八年前に亡くなった。詳しい事情は知らないが、南豆荘の人たちの話では、山のなかの木の枝に首をくくって死んでいたという……。
「おい、カワセミの親爺さんと垢石老は、どっちが釣が上手だったろう」と、自分で訊いて自分で答えた。「確かにどっちも上手だが、どっちこっちというところだろうか。しかし、カワセミの親爺の方が数だけはたくさん揚げるだろう。垢石の二倍は釣る。いや、一倍半ぐらいかな。」
見ると机の上に、お盆に載せて湯呑と急須が置いてあった。
お茶は冷めていた。私は机の上に古手紙をどっさり撒いて、トランプをやりなおすときのように掻きまわした。垢石の手紙が二通、立て続けに見つかった。
一通は浦和市北浦和からよこしたもので、消印は浦和局、昭和十五年七月二十二日となっている。
これは鮎の習性について問いあわせた私の手紙に対する返事である。さっきも思い出していたように、この年の七月中旬ごろ、亀井君と一緒に東伊豆の谷津へ出かけ、そこへ折から湯ケ野に滞在中の太宰君が細君を連れて来て三人で釣をした。亀井君も太宰君も友釣は初めてだから、カワセミの親爺に頼んで囮を附けてもらい、たも網や竿の扱いかたも実演の即席教授で教えてもらった。囮の鮎は他の釣師から譲ってもらったもので、少し傷んでいたからカワセミの親爺が交換してくれた。この老人は自分で釣るときには、手間どるのを省くため道絲を少し短くして囮を宙吊しにして沖ヘ出すが、亀井君たちには基本的なやりかたで実演してみせた。垢石の釣りかたと瓜二つである。
私は亀非君たちの釣っている川下に行き、ふかんどのところでカワセミの親爺と並んで竿を入れた。ところが囮の鮎の動きが不断よりも激しく、水の底を稲妻型に游いでいるような手応えを受けた。錘をつけないせいかと思って鉛をつけてみたが、大きく右に左に動いているような手応えである。どうも変だと思った。カワセミの親爺に訊くと、今日は夕立が来るようだから、鮎も石の苔を食い溜めする了見で気が立っているんだろうと云った。まさか鼻鐶で自由を失っている囮の鮎は、それどころではないだろうと云うと、「じゃ、囮をつけかえてみな」と云って、囮箱の鮎を一尾くれた。それで囮の代金として五十銭玉を渡すと、「俺の竿で釣ってみな」と、竿を私に持たせて川から出て行った。こんなのはいつものことで、老人は囮の代金を受取ると、きまって橋のたもとの一杯屋へ焼酎を飲みに行く。たいてい一時間もすると引返して来て、「やあ有難う」と、焼酎の匂をぶんぶんさせながら竿を受取るのであった。
私はカワセミの親爺から預かった竿をかまえていたが、やっばり囮が稲妻型に引くような手応えであった。手製の無骨な感じの竿だが、軽くて感度も私のよりずっと優っている。囮の動きが極めて身近に感得できる。
やがてカワセミの親爺が引返して来て、「やあ有難う」と焼酎の匂をさせながら竿を受取った。
私は橋の直下の浅瀬のわきで囮をつけかえた。ところが不意に大夕立がやって来た。橋の下にも、しぶき雨が吹きこんだ。太さがステッキほどもあるかと見える雨である。時計はないが腹時計では午後三時ごろのようであった。
太宰君も亀井君も大急ぎで竿を収め、私たちはずぶ濡れになって宿へ駈込んだ。夜になっても雨は降り続き、私が蚊帳のなかに入ったとき早鐘が鳴りだしたが、火事はこの土砂降りの雨が消してくれるだろうとたかをくくっていた。真夜中すぎ、「水だ水だ……」と宿の女主人が、けたたましく触れまわった。私は飛び起きて電気をつけ、蒲団が畳と共に水に浮いているのを見て、自分は浮巣の上に寝ていたようなものだと気がついた。棚の上のリュクサックを取ろうと立って行くと、自分の踏む畳が沈んで、他の浮いている畳のふちで向臑を打った。
「みなさん、二階に避難して下さい、二階です」と女主人の金切声が聞えた。「いま、郵使局に電話しました。助船を頼みました。間もなく船で助けに来てくれます。さっき真夜中ごろ、三宅島が噴火したそうです。東京の新聞社が大騒ぎしているそうです。郵便局が知らせてくれました。」
助船と云っても、ここの川には小さな川船があるだけだ。とても濁流のなかを遡るような奇蹟は起り得ない。
私はリェクサックを持って階段を駈けあがった。障子を明けひろげてある部屋に亀井君がいるのを見た。蒲団を積み重ねて腰をかけ、夜空の稲びかりのする方角をじっと見つめていた。
「亀井君、どうしたらいいだろう」と訊ねても、身動きもしなかった。毅然とした風に、天の一角を睨んでいる。さすがに学生のころ共産党に入っていただけあって、大洪水に取囲まれてもびくともしない。私はそう思った。
そこへ太宰君夫妻が入って来た。続いて二人の青年が入って来た。これは卒業論文を書きに来ていた慶応大学の学生である。太宰君はもう死ぬ覚悟だから「人間は死ぬときが大事だ」と云って、細君に向い「あのね、失礼して、ズロースをはいて来なさい。死ぬときが大事です」と云った。細君の方は、ただ俯向くだけで、不断と同じようにきちんとかしこまっていた。水は刻々に増えて行く一方だから、階下の部屋からそんなものを持って来るのは命がけの仕事である。太宰夫妻は中庭の離れに泊っていたのだが、いずれにしても余計なことを云ったものだ。それでも細君は手早く身仕度したと見え、着物を着て帯をしめていた。太宰君は角帯をしめて白足袋をはいていた。二人の大学生は、「洪水のときは、水と米が大事だそうだ」「僕たち、決死隊になろう」と打ちあわせ、台所から米俵を運んで来るため階段を駈降りて行った。亀井君は夜空の方をじっと睨み続けていた。稲びかりは物凌いが、不思議に雷鳴を伴わない。方角はぴったり大島の真上と見えた。
私も台所へ降りて行った。入って来る濁水が膝上までの深さを持っていた。女主人が消防組へ電話をかけていると、若い方の女中が「ぎゃッ」と叫んで濁水のなかに引きずりこまれそうになった。二人の大学生がそれを助け起した。床板を留めた釘が朽ちているためか、床がめくり取られ、そのところに穴ぼこが出来ていると女中が言った。床下は流れが凄く、穴ぼこに吸いこまれた足が搾られるようであったそうだ。私たちがみんな二階に引返してから、女中は片方の足を脛から下だけ見せてくれた。針の先か何かで引っかいたような線状の薄疵が、脹脛に二本か三本、髪の毛よりもまだ細く微かについていた。
女主人は階段の下を見巡って来て、台所の壁に取附けてある電話機がもう水に沈んで、郵便局ヘも消防組へも電話をかけられないと云った。
それから、きちんとかしこまって、「お客さまがたに、何とも申訳がございません。もし万一のことがございましたら。いえ、どうか、そんなことのございませぬように。まことに申訳ございません」と両手をついて畳に届くほど深く頭を下げた。二度も三度もそれを繰返した。
着物も尻端折にして襟もはだかっているのだから、頭を下げると、ふところから何通かの貯金帳がばらばらと落ちた。傍から娘さんが「まあ、お母さん、みっともない」と、それをふところに入れてやるのだが、また平身低頭するからばらばらと落ちた。
夜の明けかかったころ、二階の廊下から物干竿で計ってみると濁流が八尺ほどの水深になっていた。風は吹いていなかったが水が渦巻くので、つむじ風にいたがられるように庭木の枝が揺れていた。少し高めになっている庭の隅で、大きな一とかたまりになっている紫陽花が水に責められて、大きく右に左に揺れ動いていた。幾つもの花が、朝の薄明りで異様に凄いものに見えた。
夜が明けると雨が止んだ。午後三時ごろになると道も歩けるようになったので、私たちは床下浸水ですんだ峯温泉の宿へ移って行った。その途中の道ばたに、カワセミの親爺が気色ばんだ顔つきで腕組をして、岸とすれすれまで減水している川を見ていた。「ゆうべは、びっくりしたろうな。もうお帰りか」と云うから、「当分、駄目だろう」と云うと「あと一週間したら、凄く釣れる。「ほんとだ」と云った。
私は東京に帰ってから垢石老に、伊豆で洪水に遭ったことを報告した。いま垢石の古手紙を見て、それを思い出した。天変地異がある前には、囮の鮎が稲妻型に逃げまどうものか。手紙でそれを質問したことも思い出した。伊豆大島の方角で稲びかりがしていたことも書いた。
後日、亀井君の話では、洪水が怖くて蒲団に尻餅をつき観音経を読もうとしたが、冒頭の文句を思い出せなくて途中の文句を思い出した。それで続きを読んでいると、冒頭の文句を読むことが出来るようになったそうだ。太宰君はそれを聞くと「あのとき亀井のやつ、腰を抜かしていたのだ」と云った。
垢石の返事は長文だから次に抄出する。
手紙を見た。河津川で水魔に見舞われた由、大変だったと思う。しかし無事で何よりだ。さて、囮のそよぎかたと三宅島大噴火に関する件、微妙な話の如く思惟する。だが小生に於ては、そのような現象にはまだ一度も気づいたこと無是、貴台の思いすごしではないか。または囮の勢いがよすぎたのではなかったか。貴台、その類の究理の意慾湧く場合は、囮でなくて自然の鮎を観察するがよい。鮎は、橋の上から真下に見れば動きがよくわかる。参考のため、鮎の習性についての調査記録を二篇同封する。いずれも雑誌の切抜だが、よく調べて書いてある。小生には不要だから返送しなくてよい。
返事として甚だ曖味なものになった。尚、三宅島で早春三月に作附の甘藷が腐り、正月に桜が狂い咲きしたとのこと。地震噴火のある年は、このこと大いに有り得ると伝承されている。
先日は送本してくれて感謝する。実は、自分も少し纏まったものを書き度いと思う。心が急く。しかし原稿の註文はない。妙なものだ。とにかく鮎禁漁日までは何も手につかぬと思う。そのうちお会いしたいものだ。
纏まったものを書きたくて、心急くと云っている。何か手きたい材料を心に温めていたのだろうか。世評の高かった随筆集「たぬき汁」を出したのは、この手紙をよこしてくれたころより後ではなかったかと思う。
もう一つの手紙は、ペン書きだが少し筆が枯れていて美しい。消印は栃木県塩原局、昭和三十年十月十七日。表書は、東京都杉並区清水町二四の私宛。裏は、栃木県塩原温泉門前町、公立塩原病院内、佐藤垢石である。習字の稽古を重ねた人の筆蹟のように見える。
謹啓
長らく御無沙汰いたしお詫び申上げます。釣の季節になりましたが釣運は如何です。
今夏の鮎も御盛んなことと察し申上げ羨ましく存じます。老生微恙のため昨年来、表記のところに転地加療しております。その後次第に経過よろしく十一月末には退院いたしたいと思っております。
さて、甚だ失礼な御願いでありますが、老生、近く笑の泉社より愚著出版することになりました。ついては大兄の序文一篇(四百字一枚)給わり度く枉げて御願いいたします。近日中に社員が御宅へ参上することと思いますが、何卒よろしく御願いいたします。
塩原の箒ほうき川では只今、山女魚と鮠が少々釣れています。(中略)次第に寒くなりました、塩原の山は紅葉盛んにて、間もなく雪が降りましょう。
御養生のほど御願いいたします。酒の美味しくなる季節だと思うにつけ――世の中が羨ましい。
敬具
佐藤垢石
尚、人間六十過ぎたら、友釣、ごろびき、山女魚釣の如何を問わず、川へ立ちこむ釣は禁物です。とっくの昔に繰返して大兄に云ったと思いますが、水の流れが刻々に体温を持ち去ります。
釣場から釣宿への帰りに、濡れたズボンをはいているのもよくありません、為念。
私は序文か跋文か書いた記憶がある。原稿一枚か二枚か忘れたが、書いたり消したりして、やっと脱稿したことを思い出した。
垢石老は「人間、六十過ぎたら」と書いているが、以前、私は「人間、五十過ぎたら」と聞いたように覚えている。何回も聞いたことだから記憶違いではない筈だ。「五十過ぎたら」と訂正してもらいたい。現に私は、五十過ぎても水に立ちこむ釣をして神経痛を拗らせてしまった。私のうちから荻窪駅まで六丁。その道を大通りに出るあたりまで行くと腰痛がこみあげて来る。たいていは我慢するのだが、痛くて仕様がなければ床屋へ寄って散髪してもらう。床屋の椅子は人を仰向けに寝かせるからいいのだろうか。とにかく床屋を出るときには痛みが治まって、実にいい気持になれる。
鮠竿を持ちリェクサックを背負って行く旅に出て、田舎道で腰痛が出ると床屋を尋ねて行って顔を剃ってもらう。すると、もう痛みが治まって、再びリュクサックを背負い床屋を出たときの気持は朗かなものである。必要ないのに忙しげに、すたすた歩いて行きながら、思わず釣竿をステッキのように振りまわしていることがある。どうして垢石老は「人間、六十過ぎたら」と改悪したか。
それにしても、入院中によこしたこの手紙は、病みあがりで弱気になっている垢石の心情を伝えている。風のたよりというのとはまた別もので、そこはかとなくといった風に伝えて来る。風のたよりという向きから云えば、つまり人の噂で聞くと、垢石は塩原病院に入院中、酒が飲みたい一心で病院から逃げだしたということであった。この手紙をくれるより前だったか後だったろうか。また或る人の話では、垢石老は東京の芸者を月賦で請出したという。人間が一本気だからそんなこともするのだろう。だが、危険を冒して病院から逃げたのは、お酒の飲みたさも然りながら、その芸者に会いたいためではなかったろうか。その結果が「まアるで駄目」でなかったら私は祝福する。
その反対であったら、実に遣瀬がなかったことだろうと云わなくてはならぬ。月賦で芸者を請出したのは、嘗て酒を一升飲む実績のあった人が、飲屋で附にして一升飲むようなもので、あとは月賦で払ってもいいわけだ。理に反することとは云われまい。
今度、私が垢石の書翰を見て初めて気がついたのは、一通ごとに文体が別様になっていることである。酒落た文章など書こうという匠気はなくて、そのつどその場の気分で気儘に筆を運んでいるのだろう。自分の文章に自己嫌悪も感じないし、自信を持ったこともなかったろう。垢石は人の前でとぼけることも、毅然とした態度をとることも、神妙にすることも、磊落になることも出来た。その場の雰囲気で変化することが出来たし、それがみんな板にもついていた。だが、私は垢石が偉そうにするところだけは見たことがない。
こういった人だから、文章をそのつど書きわけることが出来たのだろう。他人の文章もそっくり真似て書けたろうか。名著と云われる木下謙次郎氏の「美味求真」は、木下氏所蔵の資料を使って垢石が代作し、御手洗辰雄氏が文章を添削したという噂を聞いた。ところが垢石老とどこかへ釣に行ったとき、あの名著は老が代作したそうだが本当かと訊くと、返事をする代りに口髭を食い反らした。
「美味求真」のほかに、よほど前に「文藝春秋」連載の「政界夜話」も垢石が代作しているという噂を聞いた。これは満洲事変の前から日支事変のころまで満十年間にわたって、「城南隠士」という筆名で毎月掲載され、絶えず変転する政界の動向を明快に説明してあった。当時、文藝春秋社の諸雑誌のうち、愛読者の数が多いのは「オール読物」の「銭形平次」と、「文藝春秋」の「政界夜話」だと云われていた。社内評でもその通りであったような形跡がある。そういう呼物の一つを垢石が代作しているとは大した筆力の人だと感心させられた。単行本になってから奥附を見ると佐藤垢石の名前がある。これほどの人が、何で随筆や雑文を雑誌社へ持込むのか気がしれない。私も一度、「中央公論」の佐藤観次郎記者のところへ、三十枚あまりの垢石の雑文を持込んで断わられたことがあった。どうも腑に落ちなかったので、たぶん小貝川へ行く車中だったと思うが、「あの『政界夜話』は老が代作しているのか」と訊くと、何とも云わずに嘯くような顔つきをした。その表情と気脈を通じさせて口髭を食い反らした。やっぱり老が書いたのだと思った。
私は垢石の手紙や葉書を一つにまとめ、セロハンの袋に入れて地袋戸棚に蔵った。近く垢石老の思い出を雑文に書こうと思ったからである。しかし「美味求真」や「政界夜話」について、人の噂だけで書いては困るので、数日後に将棋会で私と対局した永井龍男氏に訊いてみた。鮨屋で二次会をしているときの席だから傍に何人かの客がいた。垢石の思い出を書きたいからと云うと、「そうだな、それは君」と永井君が云った。「真相は、御手洗さんに訊けばわかるだろう。あの人は、そういったことには返事をくれる人だ。僕は文藝春秋社に入る前に、御手洗さんのお宅に寄食させてもらっていたことがある。ずいぶん世話になったものだ。いま、敷居が高いがね」。
私は御手洗さんには三十年近く前に、垢石老の会で一度逢ったきりである。テレビでは最近、正力読売社長の追憶座談会に出た御手洗さんを見た。三十年前は頭の髪形が角刈に近くて全身に精悍な感じが溢れていたが、今度は髪が目立たぬ普通の刈方のせいか、精悍の気が迫力というようなものと入れかわっていると見た。この人が生前の垢石の面倒をよく見たのであった。何かにつけて垢石が誇を隠してよく噂していた人である。
私は永井君と将棋を指した翌日、「美味求真」並びに「政界夜話」と垢石老とのつながりについて、質問の手紙を御手洗さんに出した。垢石に友釣を教えてもらったことも、永井君に智恵をつけてもらったことも書き添えた。垢石老のことを「新潮」正月号に書きたいということも書いた。
返事が来た。次のような大意である。
「美味求真」は、前篇を木下謙次郎先生御自身が執筆された。後篇は佐藤垢石の執筆している部分が多い。材料は木下先生自身、多年にわたって蒐集され、一方また、先生の親友北里柴三郎博士を煩わし、各国に派遣されていた北里研究所の人々に調査してもらって大成されたものである。
木下先生に垢石を推薦したのは自分だが、原稿には全く関係がない。ある年の暮、垢石が木下先生に若干の借金を申入れた。その頃、先生も貧乏(落選して浪人)で、それを断わったので、以来、垢石は先生から遠のいていた。その後、先生は関東庁長官の顕職を経て、悠々自適の身になった。あるとき自分に金一封(たぶん千円か)を渡し、垢石に渡してくれとの依頼があった。それを垢石に渡そうとしたが、彼もあんな男だから受取らなかったので妙な幕切れに終った。
文春の「政界夜話」は、自分の病臥中、二、三回、垢石に口述して代作を頼んだことがある。上巻の奥附を垢石としたのは、当時、絶対に匿名にするのが菊池社長との条件であった。また、取材する上でもその必要があった。
御手洗辰雄
垢石老が嘯くような顔をしたことも、髭を食い反らしたことも、この手紙で謎が解けた。「あんな男だから」とは「あんな一徹な男だから」の意味だろう。
鮎の友釣を教えてもらう依頼の手紙に答えてよこした垢石の返事に
「握飯に梅干を入れないこと。釣場に梅干を持込むこと禁物なり。」と書かれている。
何時の頃から梅干は”魚のアタリ”も無くしてしまうということになったのだろうか。
垢石からの絵葉書「飛騨の○川(不明)へ向い蟹寺に一泊」の○川は、宮川だろう。
7.河津川筋 井伏鱒二
昭和40年代頃までは狩野川筋の鮎釣師が上手だというのが定説だった。
河 津 川 筋
いつか作家の小山いと子さんから問いあわせがあった。
「海釣ができて、川釣ができて、山の猟ができて、温泉があって、鄙びていて、おっとりした感じのところ。それも、東京からあまり遠くないところ。この条件に適うところがあったら紹介してもらいたい。小説に取入れたいと思う。また、自分も出かけて行きたいと思う。」
二、三年前のことであったか、そういう注文の手紙をもらった。海釣ができて川釣ができて、山の猟ができるところと云ったら、はて、どこだろうと私は思案した。しかし私は温泉場をそんなにたくさん知らないので、大して長たらしい思案をする必要もなかった。取敢えず次のような返事を書いた。
「僕は見聞が広くないので、お気に召すような場所を云いあてることができるかどうかわかりませんが、伊豆東海岸の河津川筋は大体において、あなたの仰有る条件に適っているかと思います。バスを河津浜で降りて、徒歩五分のところにあるのが谷津温泉。そこから少し川上にあるのが峯温泉。ここなら鮎釣もできるし、散歩がてらの歩行範囲内に岩礁の多い海辺があります。その辺の海に大きな敷設網がありますから魚類もいることでしょう。」
そういう意味の返事を出した後、谷津にすぐ近い今井浜の温泉場を書き落としたことに気がついた。ここが鄙びているところかどうかともかくも、鄙びていないにしても小山さん自身がここに来て、自他ともに鄙びていると思えばいいわけだろう。
私は今井浜のことはよく知らないが、河津川や谷津温泉のことなら幾らか知っている。河津川は一見平凡な様相でありながら、鮎をねらう釣師にはかなり魅力のある川である。
しかし伊豆の人は、河津川筋の人でも狩野川筋の人でも、釣の技術にはすぐれている。私は土地の子供と並んで釣っていても、ときどき恥ずかしい思いをさせられることがある。いつぞや滝井孝作さんが云っていたが、鮎の解禁の日に狩野川へ出かけたところ、川に入らないで帰って来たそうであった。土地の子供が囮の鮎を扱っているのを見て、あまりにも上手なので自分が恥ずかしくなって帰って来たと云っていた。
なぜ伊豆の釣師は友釣がうまいのだろう。去年、私は長良川へ行って土地の釣師と座談したが、伊豆の釣師にはかなわないと云っていた。私の釣の師匠の佐藤垢石も、河津川の川端さんや狩野川の中島さんは神技の釣師だと云っていた。
「どこがそんなに違うのか。技術が優れているのか。」と聞くと、「技術もすぐれている。釣る姿もすぐれている。釣るときの心境も立派だ。この三つが揃わなくっちゃ、立派な釣師とはいえない。」と垢石が云った。
私は河津川では、カワセミのおッさんという老人に釣の手ほどきをしてもらった。この老人は私が上の空で釣っているのを見て、「お前さん、川に食らいつかなくっちゃいけえ。」と嗜めた。釣ばかりではなく、万事、この気組でなくては適わない。去年の夏、私はカワセミのおッさんに逢うのが楽しみで河津川へ出かけたが、谷津の南豆荘で聞くと、おッさんは山へ行って亡くなったということであった。
谷津(註、正確にいえば縄地)には大久保石見守の屋敷趾がある。最近まで私はそれを知らなかったからそう思うのかもしれないが、この屋敷趾のことは一般に知られていないのではなかろうか。石見守は江戸初期の頃の金山奉行で、金山師としては天才的な人であった。伊豆の金山、石見の銀山、佐渡のきんざんを支配して、徳川家を潤おす一方、自分でも豪華を極めていた人である。そのことだけは一般に知られているようだが、その邸宅が谷津にあったことはあまり知られていないのではなかろうか。石見守の一家一族、謀反人の汚名を受けて悲業な最期を果げたので、お上を憚って伏せておいたのだろうか。しかし架空の鮮血物語ではない。再度の吟味をする人があってもいいのではないか。
この話は昭和三十年代半ばのことである。
(その2)へ
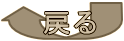


![]()


