
その 3. 
目次へ戻る
16.利休と遠州 薄田泣菫
ことのおこりは四百年ほど前のことでございました。
人さまの噂や評判を鵜呑みにし、それが権威のものと錯覚してしまうと
時には、と〜んでもないトホホな事がおきてしまうものでございます。
利休と遠州
一
むかし、堺衆の一人に某といふ数寄者がありました。その頃の流行にかぶれて、大枚の金子を払つて出入りの道具屋から、雲山といふ肩衝の茶入を手に入れました。太閤様御秘蔵の北野肩衝も、徳川家御自慢の初花肩衝も、よもやこれに見勝るやうなことはあるまいと思ふにつけて、某はその頃の名高い茶博士から、何とか折紙つきの歎賞の言葉を得て、雲山の誉れとしたいものだと思つてゐました。
機会は来ました。ある日のこと、某は当時の大宗匠千利休を招いて、茶会を催すこととなりました。
かねて主人の口から、この茶入について幾度ならず吹聴せられてゐた利休は、主人の手から若狭盆に載せられたこの茶入を受け取つてぢつと見入りました。名だたる宗匠の口から歎美の一言を待ち設けた主人の眼は、火のやうに燃えながら、利休の眼を追つて幾度か茶入の肩から置形の上を走りました。
あらゆる物の形を徹してその心を見、その心の上に物の調和を味はふことに馴れてゐる利休の眼は、最初にちらとこの肩衝を見た時から、この茶入の持つ心持がどうも気に入らなかつた。しかしできるだけその物の持つてゐる美しい点を見逃すまいとする利休の平素からの心掛けは、隠れた美しさを求めて、幾度か掌面の茶入を見直さしました。肩の張りやうにも難がありました。置形にも批の打ちどころがありました。一口に言へば衒気に満ちた作品でした。
利休は何にも言はないで、静かにその肩衝を若狭盆の上に返さうとしました。その折でした。利休が自分に注がれた主人の鋭い眼付きを発見しましたのは。その眼には驕慢と押しつけがましさとが光つてゐました。利休はその一刹那に、主人の表情に茶入の心持を見てとりました。茶入の表情に主人の心持を味はひました。
主人は得意さうに利休の一言を待ち構へてゐました。利休は何にも言ひませんでした。狭い茶室はこの沈黙に息づまるやうに感ぜられました。
湯はしづかに煮え沸つてゐました。主人の顔からはいつのまにか押しつけがましさが消えて、物を頼むときのやうな弱々しい表情が見え出しました。利休は眼ざとくそれを見て取りましたが、何事にも気のつかない振りをしてゐました。いつだつたか、利休は前田玄以の茶会で、主人の玄以が胴高の茶入を持ち出してきて、
「この肩衝が……」 と、茶入の胴高なのに気がつかないで、しきりと肩衝を繰り返して、利休の意見を聞きたがつてゐるのに出会つたことがありました。利休はいまさらそれを胴高だと教へもならず、をかしさをこらへてただ黙つてゐると、それがひどく玄以の機嫌を損じたかして、その後はうばうで自分のことを悪様に言ひふらし、果ては太閤殿下にまで讒訴を試みてゐるといふことを聞いてゐるので、こんな場合の沈黙が、どうかすると自分の一身にとんでもない災難をもたらさないものでもないことをよく知つてゐました。しかし自分はこの道の宗匠である。自分の一挙手一投足は長くこの道の規範として残り、自分の一言は器の真の価値を定める最後の判断であるのを思ふと、滅多なことは口に出せませんでした。利休はただ黙つてゐました。
茶がすんで、利休が席を退くと、その少し前からやつと気持の平静を取り返したらしい主人は、雲山の肩衝を手のひらに載せて、しばらくぢつと見とれてゐましたが、いきなりそれを炉の五徳に叩きつけました。茶入は音をたてて砕け散りました。
「何をなされます、こんな名器を……」
席に居残つて、何かと世間話に興じてゐた二人の相客は、びつくりして主人の顔を見つめました。
主人はそれには何も答へないで、静かに羽箒を取つてそこらに飛び散つた挽茶の細かい粉を払つてゐました。
「何をそんなにお腹立ちで、こんな名器をお毀しなされた」
二人の客はいくらか不興げな顔をして、腑に落ちなささうに訊きました。
「いま時利休が賞め言ひとつ申さぬものを……」主人はどうかすると興奮しさうになる自分の心を、強ひて抑へつけるやうに、一語一語力を籠めながら、ぼつりぼつりと息を切つて言ひました。
「賞め言ひとつ申さぬものを秘蔵したとあつては、末代までの恥辱でござるからな」
誇りを持つた主人の言前に、二人の客は顔を見合せて口を噤むよりほかには仕方がありませんでした。急に茶室のなかが薄暗くなつたかと思ふと、時雨がはらはらと軒の板庇を叩いて通りました。
「御主人……」しばらくしてから客の一人が口を切りました。
「少し趣向もござれば、その茶入の破片は拙者において所望いたしたい」
「最早手前には無用の品、どうか御随意になされますやう」
主人はほがらかな気持で答へました。その客は静かに炉縁ににじり寄つて、灰のなかから茶入の破片をこくめいに拾ひ上げました。
時雨はいつか通り過ぎたかして、室のなかはまたぱつと明るくなつてきました。
二
雲山肩衝の破片を拾ひ集めた茶人の手で、間もなく茶会がまた催されました。
客の一人としてその席に招かれた利休の顔は、若狭盆に載せられた肩衝の茶入が眼につくと、驚きの色で輝きました。それはばらばらに幾つかに毀れたのを、無雑作に継ぎ合せたもので、なかには破片と破片とが互ひに入違ひになつてゐるところもあつて、誰の眼にも素人の手で繕はれたものとはすぐに見別けられました。
が、利休の驚いたのは、この席で疵入りの肩衝を見つけたからではありません。その茶入が紛ふ方もなく、ついこなひだ堺衆なにがしの茶席で見かけた雲山そのものだつたからでした。それに気がつくと同時に、利休の眼の前には、驕慢と押しつけがましさとで火のやうに燃えてゐたその持主の顔が描き出されました。
「たうとう割りをつたな」利休は心のなかでさう思ひました。「大抵の者ならば、割るよりもまづ売るはうを考へたらうにな」
利休はしづかに盆の上から茶入をとりあげました。そして初めて気付いたもののやうに言ひました。
「ほう、これはいつぞやの雲山でござるな」見ると素人の手でへたに繕はれただけに、茶入には以前の衒気は跡方もなく消えてゐました。利休にはそれが以前の持主の名器に対する執着の抛擲のやうにも見えました。利休は独語のやうに言ひました。「これでこそ、結構至極ぢや……」
三
「利休が結構至極と折紙をつけたさうな」
この評判は、たちまちその頃の茶人たちのなかに拡がりました。そして前にはこれを見て何ひとつ言はなかつた利休に、結構至極と折紙をつけさせるやうになつたのは、茶入の割れ目を繕つたその無雑作加減が、茶道の極意にかなつたからだと噂されました。
「こんな名器を貰ひ徳にしておいては、茶人冥利につきまいものでもない」
かう思つた持主は、その肩衝を持参して、訳を話して以前の持主に返さうとしました。以前の持主は強くかぶりをふつて、
「うち砕いて土に戻した雲山に、まためぐりあはふなどとは思ひもかけませぬことぢやて」
といつて、てんで相手にもしなかつたさうです。
四
「利休が結構至極と折紙をつけたさうな」
この評判は器の値打をだんだんとせり上げました。疵入の雲山は数寄者から富豪へ、富豪から大名へと、次々に譲渡されて、最後にすばらしい値打と評判とをもつて、ある東国の大名の手に納まりました。
それを聞きつけたのが、その頃丹後宮津の城主であつた京極安知でした。安知は茶器のためだつたら自分の家来はいふまでもないこと、ただひとつしか持つてゐなかつた小さな魂をも売るのを厭はないといつた性の大名でした。
「雲山が所持したい。あれさへ所持できたなら、茶入の望みは生涯またと持つまいに」
安知はかう言つて、しみじみと歎きました。そして病気にさへなりました。その容態を看るべく京極家に迎へられた某といふ医者は、安知の病気が自分の持ち合せの医薬では、とても治らないことを見てとりました。そして別の医療法をとることに決めました。別の医療法といふのは、
「欲しがるものは与へる」
といふことでした。医者は雲山肩衝の今の持主である東国の大名にも出入りを許されてゐましたから、早速その旨を通じました。
「京極侯には、雲山を所望して病気にまで罹られたとか。それはお気の毒なことぢや。さやうに所望せらるれば遣はさないものでもないが、あれは利休も結構至極と賞めた当家秘蔵の品ぢやによつて、金二駄を少しでも欠いでは………」
その大名はかう言つて笑ひました。この人は京極安知よりも、人間が少し賢く生れてゐましたから、頭から拒ねつけないで、金二駄ならば相談に乗つてもいいと答へたのです。金二駄と言へば一万二千両ですから、小藩の京極家では指をくはへて引つ込むよりほかには仕方があるまいといふ腹なのでした。しかし、ものに溺れやすい安知には、そんな銭勘定を飛び越すくらゐは何でもなかつたのです。医者から事情を聞いた彼は、
「利休の賞め立てた品ぢや。金二駄は安からうて」
といつて喜びました。案に相違したのは東国の大名です。この場合唯一の方法は、
「あれは戯談ぢや」
と逃げを打つことでしたが、大名といふものは、仮にも戯談なぞ言ふものではないと、常々からたしなめられてゐましたから、さうも言へませんでした。で、雲山は金二駄を身の代として、めでたく京極家に引きとられました。
京極安知は、気のくさくさするときには、いつも雲山を二重箱の中から取り出しました。そして、
「利休がこれを見て、結構至極ぢやと言つたさうな」
と、口のなかで呟きながら、幾度か見直し、見直ししてゐると、心はおのづとこんな名器を秘蔵してゐる誇りに満たされて、言はうやうのない安慰を覚えるのでした。
が、こんなことを繰り返してゐるうちに、安知は不思議なことを発見しました。それは茶入の割れ目があまりぞんざいに継がれて、破片と破片とが互ひに入れ違ひになつてゐるところのあるのが、どうも気になつてならないといふことでした。
「その無雑作なのがいい、茶道の極意にかなつてゐるところぢや」
安知は世間の評判を言葉通りに胸のなかで繰り返してみました。しかし、これまで長い間いろんな名器から訓練せられた彼の趣味と鑑識とは、さういふ口の下からむつくりと頭を持ち上げて、
「さうかと言つて、この疵が……」
と強く不服を唱へました。そして入れ違ひになつてゐるその破片を、も一度正しく継ぎ直したなら、茶入はもつと見栄えがするやうになるだらうと考へました。
安知は思ひあまつて、自分の茶道の師範役である小堀遠州に相談を持ちかけました。
遠州は雲山を取り上げて、仔細に見直しました。
「京極侯のお言葉には、いかにももつともな節がある。さりながら……」
遠州はその瞬間、 「利休が結構至極ぢやと言つたさうな」 といふ世間の言伝へを思ひ出しました。そして腑に落ちない節はありながら、古い宗匠の言ひ遺した言葉は、そのままに立てておいたはうが無難であると思ひました。
「この茶入は、継ぎ目の合はぬところこそ、利休にも面白がられ、世間にも取り囃されたので、どうかこのまま大事に残しおかるるやうに」
遠州はかう言つて返事をしました。
五
遠州は間もなく亡くなりました。
寂しい、灰色の死の国をさまよつてゐるうちに、遠州はゆくりなくも大樹のかげで一人の老人を見かけました。粒桐の紋の小袖に八徳を着、角頭巾を右へなげ、尻切れをはき、杖をついて遠見をしてゐるらしいその姿は、遠州をしてすぐに宗匠利休を思はせました。そのむかし、利休自身の手で大徳寺の山門の上に置かれたのを、太閤の命令で船岡山に投げ捨てられたこの茶人の木像を、遠州は一、二度見かけたことがありました。
「これは、これは、利休宗匠でいらせられますか」
遠州は自分の工風した遠州流のものごしで叮嚀に挨拶しました。
「あんたはどなたかな」
利休は悲しさうな眼をしよぼしよぼさせて訊きました。
「私は小堀政一と申して、宗匠の流れを汲む茶人の一人でございます」
「ほう、茶をやられるか。それは奇特なことぢやな」
利休はなつかしさうに言つて、生前に茶器を鑑定した時のやうな眼つきをして、しげしげと遠州の顔を見ました。
その眼つきを見ると、遠州はふとあることを思ひ出しましたので、顔を老人の耳にすりつけるやうにして言ひました。
「宗匠、ここでお目にかかりましたのを御縁に、ちよつとしたことをお訊ね申したいと思ひますが……」
「何か訊ねたいといはつしやるか」
利休は、老人が年下のものに何か訊かれる折のやうに、意地悪く気取つて見せましたが、それは気の毒なほど弱々しいものでした。
「はい。お伺ひしたいのは、実はあの雲山のことですが、……」
「雲山?」老人はその名前がどうしても飲み込めないやうに訊き返しました。「雲山といふとどなたのことかな」
遠州はちよつと笑ひ顔を見せました。
「雲山と申しますのは、肩衝の名前です」
「肩衝? 肩衝といふと――」老人の寂しい顔に一脈の火が点ぜられました。言葉にも何となく元気がありました。「太閤御秘蔵の北野肩衝、徳川家の初花肩衝、そのほか肩衝にはいろいろあるが、雲山といふのは一向覚えがない」
遠州はもどかしさうに声を高めました。
「雲山と申しますのは、以前堺衆が秘蔵してゐたのを、宗匠の御挨拶がなかつたばかりに五徳に叩きつけて割りました……」
老人はやつと記憶を取り返しました。
「さう、さう。そんなこともあるにはあつたやうぢやな。しかし、そんなことを訊いてどうしなさるのぢや」
遠州は言葉を次ぎました。
「その後、茶入が素人の手で無雑作に継がれたのを御覧になつて、宗匠がこれでこそ結構至極と、その肩衝をお賞めなさいました」
「いや、違ふ。それは違ふ」老人は樹の枝のやうな手を振りながら、遠州の言葉を抑へました。「わしが賞めたのは、千金にも代へ難いその誇りと執着とを、茶器とともに叩き割つた持主のほがらかな心の持ち方ぢや。ただそれだけの話ぢや」
「それでは、茶入をお賞めになつたのぢや……」遠州は呆気にとられて、老人の顔を見つめました。
「さうとも。さうとも。賞めたのは、ただその心持ばかりぢや」
老人はきつぱりと言ひ切りました。
それを聞くと、遠州はすぐにあの茶入に対する世間の評判を思ひ出しました。今の持主の京極安知が彼に相談したことを思ひ出しました。そしてそれに対する自分の返事をそつと思ひ出して、覚えず顔を赤らめました。
老人はそれには一向気がつかない容子でした。
〔昭和2年刊『猫の微笑』〕
【衒気】げんき
自分の学問や才能をひけらかしたがる気持ち。てらい。
「―のある人」
【讒訴】ざんそ
(名)スル
人を陥れるために悪く告げ口をすること。また、かげぐち。
「主人に―する」
「あなたは僕の事を何かお父さんに―しやしないか/それから(漱石)」
【放擲/抛擲】ほうてき はう―
(名)スル
ほうってしまうこと。うちすてること。
「地位も名誉も―して隠棲する」
雲山肩衝が飢饉の民を救った史実
 |
| 初花肩衝 |
寛永17〜18年におきた飛騨の大ききんの時のことである。
時の郡上藩3代藩主金森重頼は江戸にいてその報を聞き、どうしたものかと伊達政宗に相談した。
政宗は「金森氏は大変な宝を持っている。その宝である『雲山肩衝(うんざんかたつき…中国の揚貴妃が化粧の油つぼとして使っていたといわれるもの…)』の茶つぼを売れば、2年や3年分の米が買える値で売れる。こういう時に生かしてこそ宝物だ。」と答えたという。
そこでこの茶つぼは、京極丹後守高広に慶長大判3000枚分の値段で買い取られた。
金森氏はその金で江戸からお助け米を送って、飛騨の人々を救った。
(写真のような形の茶入れを肩衝といいます。初花は南宋−元時代の唐物で、織田信長、徳川家康、豊臣秀吉、宇喜多秀家などの所有を経て、関ヶ原の戦い後に再び家康へ献じられた。)
郡上藩金森氏その後:
6代藩主・金森頼錦(よりかね)は、九代将軍家重の時幕府の御奏者役に任ぜられた。頼錦の風雅な生活と奏者番としての社交的な散財が財政を逼迫させ、度重なる増税を領民に課した(相場より5割高い年貢の金納分、生糸4倍、牛馬通行税、畳・障子にまで課税など)。宝暦4年(1754年)、年貢米の取り立てに、従来の一定の年貢をとるやり方『定免取り
( じょうめんどり)』 にかえ、その年の出来高によって年貢を変える『検見取り(けみとり)』を実施しようとした。
農民が検見法実施の廃止願いとその他16項目についての『検見取りお断り願い』嘆願書を提出したことに始まったのが、5年間に渡る大一揆、後に「宝暦騒動」とか「郡上一揆」と呼ばれるものである。(「郡上一揆」は、前谷村定次郎=緒方直人主演で映画化された。)
江戸での駕籠訴、箱訴などによって、漸く幕府のとりあげるところとなり、評定所の吟味、裁定の結果、金森藩は「郡上一揆」とともに、ほぼ同時期に起こった「石徹白(いとしろ)騒動」に対する失政を問われ、金森家はお家断絶、家老は遠島となった。老中以下の幕府の役人も大量に処罰された。
郡上藩は天領となり、青木氏が藩主となり明治まで続いた。
この郡上一揆の物語は、白鳥踊り「八ツ坂(ヤッサカ)」「宝暦郡上義民伝」、 郡上踊りの「やっちく」「郡上義民伝の巻き」として、今も唄い継がれている。
<郡上義民伝の歌詞>
これは過ぎにし其の物語 聞くも哀れな義民の話
時は宝暦五年の春よ 所は濃州郡上の藩に
・・・
小堀遠州(こぼりえんしゅう) (1579〜1647)
本名・正一といい、遠州とは通称。慶長13年(1608)普請奉行として駿河城を築城した功で遠江守に任ぜらたことにより、「遠州」と呼ばれるようになりました。駿河城を築城のほかにも、二条城、名古屋城などの建築・造園にも才能を発揮し、また、書画・和歌・茶道にもすぐれた才能を発揮しました。特に茶道については、彼独自の茶道である「きれいさび」を創り上げ、後世の茶道に多大な影響を与えました。「将軍家茶道師範名」にも抜擢され、遠州流を起こすなど、美術工芸・茶道・建築など幅広い分野において活躍した。正保4年(1647年)没。世寿69歳。
17.庄内竿 本間祐介(本間美術館館長)
用の美の一典型である庄内竿の解説です。
庄内竿は魚を多く釣るというよりは、釣を楽しむための竿であったようです。
庄内竿
庄内では二百年も前から、他地方のものとは違う独特の釣竿が発達していながら、他所の人は全然知らないでおったと云うことは、考えて見ると何か庄内人の沈黙の性と云うか、宣伝嫌いと云うか、よく庄内人の性格が出ていると思います。
庄内竿と云うのは、この地方特産の苦竹と云う竹で作った竿のことを云うのです。苦竹と云うのは、筍が苦くて食べられぬところからその名があるので、庄内地方以外には殆んど生えない竹で、篠竹、つるべ竹が、形がやや似ていると思います。この若竹は、二年コまでは竿にするように、うら(穂先)がついているので、女竹系統のものでは他に類がありません。
庄内竿が他の地方の竿と違うところは、一口で云うと延竿として作られたもので、継竿として作られたもので無いと云うことです。若し必要があれば継ぐと云うのです。
他地方の竿は継竿が主で、延竿と云うのは漁師向きの唐竹の延竿とか、ホテイ竹の延竿とか、子供向きのもの等です。
継竿として出来上った一本の竿は、他の竹と合わせて作る場合が多いのですが、庄内竿の場合は、延竿は勿論ですが、継竿でも延竿を二つ或は三つに切って、それを継ぐのですから、生れ乍らにして立派な竿になる素質を持った竹でないと竿の材料にはならない訳です。それで何千本か何万本かある竹藪の中から、数本とか十数本とか選んで、とって来る訳ですが、一本の竿に仕上げるまでには、非常な苦心が要ることなのです。まあ大体、まともな竿を作るとなると、竹をとってから四、五年経たないと、竿として完成した竿にはなりません。
他地方の竿は、技術の面から云いますと、非常に優れた竿が沢山あるのですが、これは飽まで作る竿なんです。庄内の竿は素質のよさを何処までも生かして、一本の完成した竿に仕上げるのです。作ると云う事とは全然違うんです。他地方の竿は皮をとって糸を巻き、漆を塗って曲らないように、折れないように補強しているのです。庄内竿は生地のままを生かすことで、塗りをかけたりしては、もう価値が無くなります。皮のついたままに磨きをかけて、美しい光沢を観賞する訳です。
それから庄内竿には根がついておりますが他地方の竿は根がついておりません。根で釣るものでは無いと云う考え方なんです。
庄内竿も根で釣る訳では無いのですが、美しい根のついていることは、庄内竿としては立派な見どころになっている訳です。又技術の方から云っても、根を満足に伸ばせると云うことは最高の技術なんです。この位難しいところはありません。要するに首尾全きもので無いと庄内竿としては、いいものでは無いのです。単に観賞だけで無しに、掌の中のおさまり具合にも関係するのですが手に持った感じでも、他所の竿は軽快さと云うか、重さを感ぜずに、魚の敏捷な動きに対してより軽く、うまく合せて釣り上げる。まあ能率一点張りに出来ている。庄内竿では軽快な竿は、竿のうちに入らない。手にして一種の、しっとりとした感じと云うものが無いといけません。こう云う竿は魚の響の伝わり方にも、非常にコクがあるものなんです。
上方の竿は魚を釣った時はちっとも味が無いんです。お茶を飲む場合、楽焼か何かの茶碗で呑むのと、アルミの器で飲むのとの違いみたいなものでしょうか。単に魚と斗うと云う面から考えると、他地方の竿の方が理屈に合っていますが、庄内竿は魚を多く釣ると云うことよりも、魚と遊ぶといいますか、楽しんで釣ると云う竿になっているようです。
こう云う点は矢張り、士族が修業のようなつもりで釣をやったことから、こう云うさおになったものでしょう。
本当にいい竿になるかならんかと云うことは、第一回目のひと伸ばしにかかります。その竿の運命の半分はここで決まってしまう。まあ人間の初等教育のようなものでしょうか。
竹敷から採って来たままでは、竿に使えるものは一本も無い訳で、火に当て、それを矯木て強く矯めるんですが、その場合、例えば右に三十度曲がった竹なら、左に十度位まで曲げて冷めぎわに垂直に伸ばす。これが名人のコツなんですが、ここで折ってしまう率が非常に多いのです。
しかしこの第一回目で癖を矯めて置かないと、いい癖をつけることが難しい。こうやって煤棚に上げて乾燥させ、翌春また伸ばす訳です。その後毎年一遍ずつ軽く矯木を当てますと、四、五年もすればギチッと竹がしまって、癖も出て来ない竿になる訳です。無論素性のよい竹を選ぶと云うことは、根本的に大事なことです。また第一回目の時に何でも逆に嬌めればよいと云う訳でも無いので、竹の質が一本一本皆違うんですから、この竹ならここまで矯めても折れないと云う、きわどい見極めと云うものが、見識になる訳です。そこに上手、下手が分れて来る訳です。
庄内竿の名人と云われた人は全部士族で、所謂職人の手に成った名竿と云うものは、殆んどありません。
当時の士たちが、名竿を自慢にしたのは、恰も戦国時代の武士が名馬を誇ったり、名刀をたばさんで誇りにしたと同じ意味だったと思います。自分で竿を作れない人は、友達の手のいい人に頼んで、相当思い切った金を出して作って貰ったことでしょう。
こう云う過程を経て発達した庄内竿と云うものは、何と云っても非常に気品の高い竿になっております。
売ることを考えないで作るのですから、手間ひまをいとわない。工賃を全然考えない作り方なのです。材料の吟味にしても、製作の過程にしても、早く作って間に合せよう等と云う考えは、微塵もないのです。
庄内竿がそのように発達したと云うことは、釣が非常に盛んだったと云うことに因るのですが、では一体誰れが釣を盛んにしたのかと云うことです。古老の云い伝えによりますと、庄内の藩公が、士族たちが太平の世に慣れて、尚武の気性が段々薄れてゆくことを憂えて、釣を奨励し、御自分も釣をされたと云うことですが、恐らくそれに間違いあるまいと思っております。若し酒井公が酒田に居られたとしたら、そう云う御奨励はなさらなかっただろうと思うのです。何故かと云いますと酒田は海辺の街ですから、朝夕釣をやったんでは、これは尚武どころか怠け者になってしまう。鶴岡から庄内浜の釣場までは、三里から四、五里の道を歩いて、しかも山を越えて行くのです。乗物も何も無い時代に、夜中から出かけて行くのですから、そこに自然と体力を鍛え胆力を練るのに非常にいい条件が備わっておったと思うのです。
そう云うことで奨励された釣りが、段々盛んになりまして、勝負―― 庄内では獲物のことをそう云う――
を人に示すのに、魚拓が一番よかったので、魚拓―― 庄内では魚の摺型と云う――
が盛んに行われるようになったのは自然の道理だと思います。同時に又、釣は禄を食んでいる、つまり食うに困らぬ士族の、半ば公認されたスポーツでもあるのですから、釣竿もただ釣ればよいと云うような物から、可成ぜいたくな、自慢出来る竿を用いたくなってくるのも、自然の人情なのでしょう。
ところで現在残っている名竿では、古い方から云うと、陶山運平
と云う人の作ったもの、この人は文化から文久頃までの人ですが、この竿は仲々気品のある竿で、四間位の細い竿ですが、今も陶山家に残っています。
それに次ぐのは丹羽庄エ門と云う人で、これは明治初年に盛んに作った人で、四間の標準竿と称する非常に細い竿で美事なものです。同じ丹羽の竿で、維新当時のに庄内藩の家老をした菅臥牛が、明治十何年かに求めたと云うことを彫ってある竿が、いま、酒井家にあります。これなどは四間と三寸位ありますが、所謂下磯で相当の技術派でなければ使いこなせないような細い竿で、美事なものです。
その後を継いだ人としては、上林義勝と云う人が明治の末期から大正の初めにかけて、名竿を残しています。この人の竿は荒興屋の五十嵐弥一郎氏に代表的なものが相当残っていて、いずれも宝物の如く大切に保存されていますが、正にその価値十分の名竿です。
大正末期から昭和にかけて山内善作と云う人がおって、まあこの人が、有終の美を成したようなもので、その後はどうも名竿を作る環境に恵まれないもののようです。
こうした変遷を経て来た中に、一人毛色の変った名人がいました。これは幕末から明治二十年頃までの人で、平野勘兵エと云う弓帥ですが、この人は庄内藩のお抱えの弓師で、明治の初年から四枚合わせの合わせ竿を作りました。
この竿は小物用で、庄内ではクロコ、東京辺ではメジナ等と云う風の強い波の荒い時に釣れる小さい魚を釣るのに最も適している竿です。
外国の合わせ竿は竹の皮を取って、身だけ合わせてあるのですが、平野の合わせ竿は皮と身と、皮と身とを合わせて、針の先のように細いところまで四本にバツチリ合わせてあります。これなども恐らく合わせ竿としては日本の嚆矢であるばかりで無く、世界でもこんな巧妙な合わせ竿はこれが始めてだろうと思います。この竿を手本として昭和に入って再び合わせ竹のけずり竿を造った人に中山賢士が居ります。
庄内の名竿は数が少いので、皆手に入れようと虎視たんたんとして狙っています。誰それが亡くなったと云うと、好きな連中は殺到しますよ。
是非譲って呉れと云う訳です。もっと烈しいものになりますと、貴方が使えなくなったら、あの竿は是非私に譲って呉れと云う、いい竿には大抵これがついています。
それが次の代だけでなしに、二代目も三代目も決っているのがあります。竿もこうなりますと、実用だけでなしに姿や気品に於いて、書や名画や名刀のように、立派に観賞の対象として、私たちの救いとなっている訳です。
こちら「庄内三代目碧水の館」に庄内竿の話や歴史が出ています。
こちら山形県ホームページの「山形の匠」のページに数少ない庄内竿師が紹介されています。
庄内竿師の一人・丸山松治さん(1998年当時76歳)はいまも健在でしょうか。
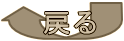


![]()
