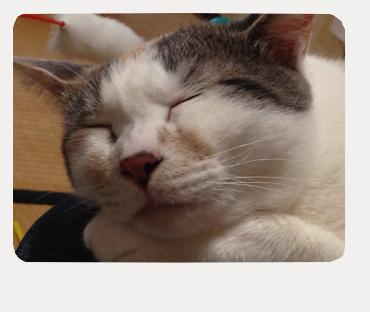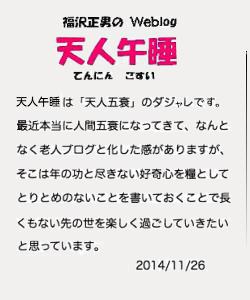2015年12月29日(火) 祝!Windows10 Upgrade
先月のことだが、「非常勤」で出社した時、会社のあまたあるPCたちのWindows10へのバージョンアップのことが話題になった。年明けにもアップせねばならないのだが、手分けしてさっと一気に済ませたいので手伝って欲しいと言われた。そこで、試しに自分のWindowsPC(Windows7 Home Edition 2GBRAM 32bit )をアップすることにした。本当はW7のままで十分なのだが、そういう事情で気の進まぬまま実行に移してみたのだ。結果は惨敗。何度やっても「Windows10を設定しています…」のメッセージのまま進捗25パーセント以上には進まなかった。足掛け3日は頑張ってみた。おかげで元のW7に戻した後もなんだか調子が悪くなってとうとうリカバリすることになってしまった。まあ、データのほとんどはMacBookの方に移動していたので実害はなかったが挫折感はけっこう大きかったぞ。で、「ま、W10なんかどうせ使わないからいいか」程度で結論し、会社の方へも「失敗しました。アップデートは中々大変そうです」と報告しておいた。ところが今日、久しぶりにリカバリしたばっかりのW7PCを起動したら「Windows10 へのアップグレードをお勧めします。アップグレードは簡単です」云々のメッセージが出てきた。「ホントか?」とばかり「今すぐアップグレード」のボタンを押してみるとなんとすらすら進んで30分程度で済んでしまったではないか!
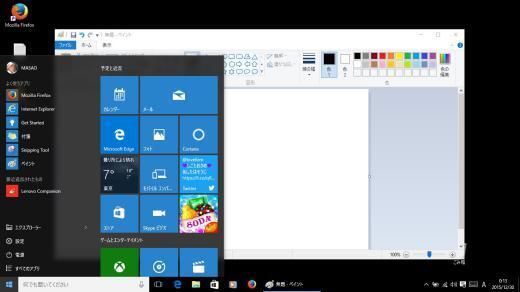 おお!Winsows10だ。
おお!Winsows10だ。
もう一つ、今日マネーツリーKKというところからメールが来て、クレジットカード会社(セゾン)のシステムリニューアルに対応した旨を知らせてきた。いつもiPhoneのアプリ「MoneyTree」で利用していたクレジットカードの明細履歴が最近表示されなくなったので問い合わせしておいたのだ。メールにある通り一度PCからクレジット会社にログインしてからiPhoneを見てみるとちゃんと明細が表示された!最近はどこの銀行やクレジットカード会社もセキュリティが厳しくなってこういうアプリはいちいちそれに対応しなくてはならないから大変である。こっちは無料で(Free)使わせてもらっているのだが、無料ユーザにもきちんと対応しているのがとても好感が持てる。法人向けの有料サービスもあるようだが、うちのような個人自由業には必要ない機能なのでこのままFreeでよろしくお願いします。m(_ _)m
今日はきのうiTunesStoreからDLした「1」(Beetles2015Version¥1400)を聴きながらトイレの掃除も済ませた。「Hey Jude」のところでは懐かしさのあまりちょっと涙が出た。なんだかいろいろな課題が年内に片付いてとても気持ちがいい。
2015年12月28日(月) 年末開始
今日は我がPCメンテ稼業のお得意さんの一人であるD幸さんのご招待で忘年会(昼食)に行った。毎年恒例のアルコール抜きしゃぶしゃぶ食べ放題である。食べ放題のうえお呼ばれなわけだから子供の頃から食い物にはイヤしい育ちの私はこういうときはなかなか遠慮しない。いつもながら食べ過ぎて苦しい思いをする。それでも今年は肉は2人前のみとし、主に野菜をいっぱい食べた。D幸さんごちそうさまでしたm(^ ^)m。帰ってから腹が張って苦しいのを我慢しながら溜まった録画を片付けようとし、溝口健二監督の「赤線地帯」という映画を見た。夫や息子のために体を売っている女性たちの生き地獄の話である。それを飽食の自分が見ていることに忸怩たる思いがした。売春の宿には馴染みがないが映画に出てくる街中の景色はまさしく自分の少年時代である。息子のために身を売ったのにその息子から縁を切られるようなことを言われて気が触れてしまう母親とか、口べらしに働きに出てついには親のために売春婦になる少女など、ついこの間まではあんな社会だったのだ。


愛用ギターと新規に買ったYAMAHAのギター弦のパッケージ
今毎日弾いているギターは、もう20数年も前、当時住んでいた所の大ゴミの廃棄所で拾ってきた!もので、YAMAHAのブランド品である。もう3回は弦を替えている。今回は同じYAMAHAの純正(?)弦を買ってみた。前回の弦(AUGUSTINE BLUE)は千円くらいだったが今度のは1,560円もした。気のせいか音が良くなったし、何より引きやすくなった。1本の指で6本の弦を押さえる(Fコードでおなじみ)のが前より楽である。
武満徹の「サマータイム」もだいたい全体を把握はした(^ ^;。あとは反復練習のみ。ちらとみると次の曲は中田章作曲「早春賦」である。正月明けから始めれば2月(早春)に間に合うかもしれない。楽しみである。
「非常勤」の仕事の方はなんとか先週までに終えた。ギリギリだったのでいろいろ不手際がありそう。年明けにメンテ(バグ潰し?)のためまた呼ばれるかもしれない。それはともかくいよいよ年末である。そうそう好き勝手なことばかりやってはいられない。明日からは大掃除にかかろうと思っている。
2015年12月23日(水) Xmas Eve・eveに
年に一度だけ聞くビング・クロスビーのクリスマス・ソングCDを聞いている。今日か明日聞かないと聞くときがない。ずっと昔どこかでケーキを買った時におまけでもらったものだ。その時はもっとメジャーな歌手のをくれればいいのにと思ったが、今になってみると古いのに(1901年5月3日生の歌手byWikipedia)全然古くないのだからいいものをもらったのだと感謝している。昔のアメリカ映画などでこの名前を見つけてはすごい人だったんだなと思い知らされている。
 ビング・クロスビー「ホワイトクリスマス」のCDのジャケット。この中では「1901年5月2日生れ」になっている)
ビング・クロスビー「ホワイトクリスマス」のCDのジャケット。この中では「1901年5月2日生れ」になっている)
さて、年末あわただしい中、昨日まで珍しく土日を挟んで1週間仕事だった(まだ「非常勤」なのだ)。定型業務の仕様変更のためシステムを一部改装する仕事で思いの外手こずっている。今日は祭日で休みだが明日も1日まるまるかかりそうだ。面白いのは(別に面白くないか)肝心のシステム改装よりそれ以前の段取りの段階で手こずっているのだ。昔からどんな仕事でも「段取り8分」と教えられてきたが、まさにその通りでこの頃は何かにつけてひしひしと思い知らされている。
大掃除の季節だが、掃除でも段取りの大切さはやってから気づくことが多い。ただやみくもに始めるのと、道具や洗剤を揃え、いつ・どこをどのように作業するかを考えてやるのとでは仕上がりが違ってくる。必要なものは以外と家にないことが多いからH.S.(ホームセンター)や100均などで買ってくるところから始まるが、ヘタをすると買い物も2度手間になる。ただ、自分は性分としてはどちらかというと「やみくも派」で、お世辞にも段取り上手とは言えないし、それを変えたいとも思っていない。プログラミングの仕事でも設計図を書いてからというよりいきなりコードを書き出す方で、いわゆる試行錯誤を繰り返す方が好きである。だから結果が出るまでにずいぶん遠回りをする。途中のしくじりや迷いが好きなのかもしれない。これは仕事には向かないからよく叱られる。
システム作りなどは絶対に段取り派でなくてはならないだろう。最近多い社会事件としてのシステム障害などは明らかにテストが不十分なところからきているが、これは段取りが不十分な事でもある。手抜きなどは論外だが、十分な時間をかけて段取りが行われていないのではないか。段取りとは、目的と手段を必要十分に決定することである。言ってみれば人間の労働の本質のような作業である。マルクスは資本論第1巻で「蜜蜂は、その蝋製の巣の建築によって、幾多の人間建築師を赤面させる。だが、もっとも拙劣な建築師でも、もっとも優秀な蜜蜂よりもそもそもから優越している所以は、建築師は巣を蝋で建築する前にすでにそれを自分の頭の中で建築しているということである。」(長谷部文雄訳 1967年)と述べている。これは「段取り」が人間労働の本質的側面を表すことを意味している。
いわゆるやみくも派でも、作業の途中の試行錯誤はいちいち段取りをしている(見直している)ことに他ならないのだから、人間の行なうことにはすべて段取りが伴っているのだ。従って問題はそれを作業の初めにしっかり行なっているかということである。
社会的な作業には必ず「納期」というものがある。納期は段取り中の重要な決定事項である。いつまでにやるということは資本主義社会では鉄則である。1日でも早い納期は競争に打ち勝つ大きな条件となる。逆にそれを破れば様々な罰則を伴う。これを守れない構成員は不適格者の烙印が押され、現場から排除される。納期を守るために前準備と最後の試験にかかる労役は極力減らされ、そこに段取りの不十分さを生む背景が生まれる。目的と手段の必要かつ十分な決定がおろそかにされる。こうして様々な事件が起こる。
2015年12月13日(日 ) ヨガマット
今年の誕生日のお祝いということで珍しく自分からおねだりしてヨガマットを買ってもらった。

これを使って朝と夜、第一ラジオ体操や腹筋、柔軟、スクワット、腕立て伏せなどを無理のない程度に行なう。ただ開脚の柔軟の時、幅60cmしかないので毛布と違って足がはみ出てしまう。ヨガ用なので仕方ないが、もう少し体が柔らかくなればマット内に収まると期待している。
 まだ紅葉が…。13日、名古屋市北区の公園で 。クリックで拡大可
まだ紅葉が…。13日、名古屋市北区の公園で 。クリックで拡大可
2015年12月10日(木) シベリウスとガーシュウィン
もう過ぎてしまったが、おととい8日はフィンランドの大作曲家J・シベリウスの生誕150周年のその日であった。おかげで今年は彼の曲がたくさん聞けた。今も今夜のNHK-FMの録音でシベリウスの特集を聴きながらこれを書いている。シベリウスのことを少しでも知るようになったのは吉田秀和氏の「名曲の楽しみ」のおかげであるが、それ以後特に7曲の交響曲の変遷について興味を持っている。と言っても特に専門書を読んだりするのではなく、ただ曲を聴いて(それも主にFM番組だけで)だんだん理解していくようにしている。自分の聴解力だけを頼りにこの変遷について考えてみたい。特に意識しているのは第4番について「無駄な音が一つもない」という(この曲を紹介するときに必ずと行っていいほど言われる)評価である。これが「正当な」(つまり自分でも納得できる)評価なのかどうか、というとことだ。このことに自分なりの結論を出してみたいと思っている。しかし昔から変わらずに好きなのはバイオリン協奏曲と交響曲第2番である。これはおおかたのファンも同じかと思う(ちょうど今バイオリン協奏曲が終わったところ)。バイオリン協奏曲の方はとうとう楽譜も買ってしまった(ヤマハビルではなくてアマゾンだが)。
次はギターの話。
武満徹の「ギターのための12の歌」の2曲目は「オーバー・ザ・レインボー」で、これは練習を始めて1か月くらいで弾けるようになった。といってもいろいろインチキ(難しいところは弾ける程度に「再編曲」?)をして暗譜で最後までなんとか弾けるという程度ではあるが。楽譜を買ったのが6月で、1曲目の「「ロンドンデリーの歌」には4か月かかっているから相当な進歩(?)である。そして今日から3曲目「サマータイム」に入った。この原曲はJ・ガーシュウィンの歌劇「ボーギーとベス」の第1幕で歌われるアリアというか子守唄である。ガーシュウィンは「ラプソディ・イン・ブルー」を中学生のときに聞いて以来好きで彼の音楽からジャズもだんだん好きになった。映画「巴里のアメリカ人」も彼の交響詩名でもあることから見るようになり、それでジーン・ケリーを知ったくらいである。
話がそれたが、この楽譜の最初のところにそろばんの珠のような音符がたくさんある。
 武満徹《ギターのための12の歌》のオーバー・部分の画像 ショット・ミュージック株式会社発行
武満徹《ギターのための12の歌》のオーバー・部分の画像 ショット・ミュージック株式会社発行
2015年12月08日(火) 「イオンモール常滑」
昨日、今月4日に開店した「イオンモール常滑」に家族で行ってきた。さすがに週末は混雑するだろうから月曜日にしたのだが、それでもすごい人出だった。思い切って全部高速道路で行った。連絡がよく名古屋高速から知多半島道路、そして知多横断道路と軽快に走って「りんくう」というICで降りるとすぐなのだが、そこから何百メートルという渋滞でとても駐車場に入れない。とりあえずモール全体をぐるりと一回りしてみると何とか入れそうなところがあった。駐車場入り口が何カ所もあるので渋滞している車ももっとバラけたらいいのかもしれない。しかし駐車場ゲートを通ってからもやはりのろのろして進まない。それぞれのクルマが駐車の空きを探しているからだ。結局3階の屋上駐車場まで登ってやっと止めることができた。駐車は6時間(!)までは無料とある。6時間も無料ならもう無料開放でもいいくらいだが、管理や集計などで必要なのかもしれない。
月曜なのに店の中はすごい人。常滑焼(?)の招き猫の像があちこちにある。最たるものが巨大な「おたふく」だが、みなさん大勢で撮っているので、ウチのはあわててしまい、おたふくが一部しか写っていない。

 (左は http://tokoname-aeonmall.com/files/special/23/thumb_photo1.jpg より。)
(左は http://tokoname-aeonmall.com/files/special/23/thumb_photo1.jpg より。)
店に戻って合流しもう一度フードコートに行ってみたが結局ここでの昼食はあきらめ、モールを出ることに。街へ出ていつもの回転寿司へ行こうと言ったらS子は「もっと(新しい店を)開拓したら」とやや不満顔。それはそうだが自分としては勝手のわかったところのほうが気兼ねが入らないのだ。というわけでかっぱ寿司半田店でやっとお昼にする。あとはまた高速道路ですんなり帰宅。お金はかかるが便利なものである。
2015年11月28日(土 ) 今年のもみじ
11月が終わってしまうので何か書いておこうと思って。今月から「うちの晩ごはん」と題してS子(妻)さんの作る晩ごはんのコーナーを作っている。こういうプライベートなものを載せることがどのくらいみっともないのかわからないが、恥ずかしい自覚がないうちはいいのだと思う。(^ ^;
おととい、もうお声はかからないと思っていた旧勤務先から久しぶりに呼び出しがあった。私が主に書いたPRGの仕様変更に対応してほしいということだった。年末に向けてちょっとでも収入がほしいのでとてもありがたい。これだけ間が空くと(8か月ぶり)PRGを書いていた頃のこともすっかり忘れているが、それでも、もう自分のマシンではないWindowsの画面に向かい合って1日かけて環境づくりしていると、いろいろ思い出してくるものだ。なんとかなりそうである。
今日は「今年のもみじ」として鳴谷山宝聖寺へ家族で行ってきた。三重県いなべ市。紅葉の写真3枚。
先週には、東山植物園にも行ってみたが、やっぱり早かったのか、去年のような感動には出会えなかった。同じ時期に同じ場所で見てもこうも違うものかと思った。
2015年11月03日(火) 高齢化と恒例化
ハロウィンも終わって今年もあと2か月。思い起こせば恥ずかしきことの数々…は寅さんのセリフだが、心境は同じである。もう2週間前になるが、今年後半期のG腰がやってきた。去年も10月に襲来しているので春と秋2回はもう恒例化している。高齢化に伴い恒例化…なんてイヤなダジャレだ。いつもと違ったのは「うっ」という瞬間がなかったことだ。いわゆる魔女の一撃がないまま、徐々に痛みが増してきて「ああ、なんかやってしまったな」と思い至った。そして数日の安静によってまた去って行った。心当たりといえば、第3日曜は団地の棟清掃日に当たるので、その日の作業がちょっときつかったかなというくらいである。それでも症状が出てきたのは水曜日くらいからだから原因といえるかどうか…。
読書はしばらく休んで去年ここにUPした「ガロア理論の初等的解題」の改訂作業をしようと思っていたのに、「戦争と平和」の返却ついでに「源氏物語(1)」を借りてきてしまった(小学館「日本古典文学全集20」)。とても貸出期間(2週間)では読めないと思うががんばってみよう。この作品も生きているうちに一度は読んでおきたい本である。いろいろ断片的な知識は入ってきているが、いかんせん原作を読んでいないので是非の判断がつかない。思えば若い頃引っ越す前の家で友人たちと岩波文庫版をテキストにこの作品の学習会を持ったこともあったなぁ。源氏物語というとこのことを思い出して我ながら微笑ましい。四畳半の部屋にこたつを囲んで5〜6人もいたか。ほんの数回で立ち消えになってしまった覚えだが、今回ちょっと読んでみるとスラスラとまではいかなくても本文の上下にある注解や現代語訳を照らして行けば意外にも読み進めるのに苦労はない。まぁトシの功もあるかもしれないが。
2015年10月21日(水) 「戦争と平和」を読む
図書館の本でトルストイの「戦争と平和」を読んだ。最寄りの図書館にはなくてネットで予約し、熱田図書館から取り寄せてもらった。到着するとメールでお知らせがあるので散歩のついでに取りに行くだけである。便利になった。\(^ ^)/3分冊だったので1冊よんでは次のを予約というやり方だったが、貸出期間中に読むため日課の最優先事項になった。おかげでほぼ1か月で読むことができた(頁の頭としっぽだけ読んで次頁というところもあったが)。筋書きは大体知っていた通りだったが、一番興味を持ったのは随所に開陳される著者の戦争論や歴史論だった。これは初めて読んだ。なんと最終的な結論は「史的唯物論」ではないか!
特に「エピローグ第2編」では人間の歴史には法則があることをはっきり主張している。
もし歴史が対象とするのが、人々の生活のエピソードなどではなく、諸民族や人類の研究であるとしたら、原因の観念をわきへしりぞけて、どれもが対等で互いに分かちがたく結びついている、無限に小さな自由の要素に共通する法則を探求せねばならない。(中央公論社 新集「世界の文学19 トルストイ「戦争と平和」(原卓也訳 ) エピローグ第2編より)トルストイは史的唯物論などという言葉は使っていないが、明らかに人間の歴史には人間の自由の意思を前提とした上でさらにそれらを貫く法則があると認めている。すべてが神のみわざという見解を捨てるならば、歴史上の様々な出来事をひとりまたは数人の「英雄」たちの「自由意志」によって説明するなどという主張がいかに間違っているかを詳しく論じている。
小説の全編は、ロシアにおける1812年戦役が、ナポレオンやアレクサンドル・ロシア皇帝の個人的な意思などとは全く無関係に始まり、継続し、そしてフランス軍の退却に終わったことを連綿と綴っている。数百人という登場人物一人ひとりがそうした背景の中でいかに翻弄され、悩み、生き抜いていったかその意識と行動が天才の筆によって生き生きと描かれる。ほんの1頁にしか登場しない兵卒が強い印象を持って描かれる。中でも全編を通じてのナターシャの描写は圧巻であろう。われわれの世代にはソビエト映画のリュドミラ・サベーリエワのイメージが強いかもしれない(1967年、自分の成人式の日に観に行った記憶がある)。
「戦争と平和」は、プーシキンに始まるロシア・リアリズムの頂点である。この作品に比べれば、のちの作品「アンナ・カレーニナ」や「復活」は教訓性・宗教色が濃いと思う。自分はトルストイでは「復活」が一番好きなのだが(ロマンチストなので?)、客観的には「戦争と平和」をトルストイだけでなくロシア文学の最高傑作としたいと今回再読(?)してつくづく思った(もちろんこれまでに読んだ中でであるが)。
2015年10月15日(木) 武満徹編曲「ロンドンデリーの歌」
9月14日付のこの欄で国保料の減免手続きのことを書いたが、その結果が届いた。おかげで10月以降の保険料が4000円ほど安くなった。これは大きい!来年はさらに安くなるはずである。なんといっても無職なのだから税金も取りようがないはずなのに「保険料」の名を借りて国保だの介護だのと取っていくのは理不尽である。水戸黄門に出てくる悪代官と同じである。保険料は何十年も取っておきながら払うときになってそこから税金を取るのは詐欺といってもいい。こんな手法が通用するなら今後様々な口実を設けていくらでも取り上げることができるではないか!一方で大企業の法人税は年々下がっていくのはどう考えても庶民のカネが大企業に回っているとしか思えない。もともと自民党はキライだが、安保法といい消費税増税といい今ほど総理大臣のカオが憎たらしく思えることはなかった。アノ人は自民党でさえないと思える。チョビひげをつけると誰かに似ていないか?——思わず筆が走ってしまったが、やはり生活に直結したウラミは根が深い。これからの選挙を思い知るがいい、…と言いたいのだがその選挙も小選挙区制によって3割の得票で8割の議席を持っていくのだからタチが悪すぎる。われわれもいい加減目を覚まさなければいけない。
今日は武満徹のことを書くつもりだったのに、最先の悪いスタートにしてしまった。気を取り直して。
ギターは相変わらず続けているが、なかなか上達しない。明らかにトシのせいだ。「禁じられた遊び」「アルハンブラ宮殿の思い出」そして武満徹編曲の「ロンドンデリーの歌」を繰り返し練習している。すべて運指がうまくいかないし、アルハンブラは曲の命とも言えるトレモロが遅くてキタナイ。そして途中で疲れてしまう。こう書くといいとこなしだが、曲がりなりにも弾けるようになったのだから進歩はしている。ただ進み方が遅いのだ。
「ロンドンデリーの歌」は武満の「ギターのための12の歌」の最初の曲だが、右手の運指が極端に難しいところがあって思わず楽譜に「できるか!」と書き込んでしまった。しかし繰り返し練習してなんとか曲らしくなってくると武満の編曲の妙が感じられるようになって嬉しい。
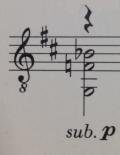
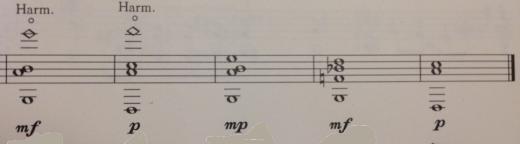 ショット・ミュージック株式会社発行「武満徹《ギターのための12の歌》」より
ショット・ミュージック株式会社発行「武満徹《ギターのための12の歌》」より
2015年10月14日(水) auのLTEフラットについて(続)
8月14日のこの欄で書いたように、auのLTEフラットを解約してから初めての請求がきた。au料金毎月1.6万円だったのがなんと8,500円に! LTEフラット2人分の11,000円が請求から消え、その代わり機種代金の月割りサービスがなくなっての請求金額である。ある意味大成功なのだが、メールとLINEが自由に使えないため多少不便にはなった(自宅でのWiFiだけで送受信するのでタイムラグが発生する)。そこでメールとLINEだけを復活するとどのくらい課金されるのか試してみようと思い、iPhoneの設定を変えてみた。そして昨日散歩しながら家にいたS子(妻)と何回かメールとLINEのやりとりをしてみた(GoogleMapも少し使った)。すると今日、iPhoneアプリ「auサポート」で料金を見ると10月分のパケット通信料が二人合わせて既に5,000円を超えているではないか、驚愕仰天!たった1日モバイルデータ通信を使用しただけでこの金額である。成程、人によっては数十万円の請求になるわけだ。残念だけどまたiPhoneの設定「モバイルデータ通信」をOFFに戻すことになった。それでも「多少不便」なだけで特に困ることはないのでたぶんこのままの状態を続けることになるだろうと思う。
 S子(妻)の最新作。名前は「Little Princess」(クリックで拡大可)
S子(妻)の最新作。名前は「Little Princess」(クリックで拡大可)
2015年10月10日 「刑事フォイル」
ほぼ1ヶ月ぶり。気づいたが、ブログとか日記というものはクセがあるようで、続くときは毎日でも書けるが、ひとたび休むとよほどのことがないと書かないものだ(自分だけかも(^ ^;))。で、今回の「よほどのこと」とは、NHKBSプレミアムのドラマ「刑事フォイル」(毎週日曜日午後9時)である。とてもいいドラマが始まったと思っていたら本国イギリスでは2002年から放送されていてすでに今年で終了(予定?)とのことである(参考「https://ja.wikipedia.org/wiki/刑事フォイル」)。何よりこのドラマの背景となっているイギリスにおける第二次世界大戦勃発時と今の日本を重ね合わせてみてしまう。いわゆる「平和安全法制」(参考「http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/gaiyou-heiwaanzenhousei.pdf」)が成立して以後、2015年10月現在は、まだ日本は世界のどの国とも実戦状態になっていないが、それでも大きく一歩その状態に近づいたことは否めない。そのことがこのドラマを他人事に見られないリアルなものにしている。
(以下ネタバレあり)日本でのシリーズ第1作(第1,2回)では海岸でピクニックをしてスナップを撮っていた夫婦がスパイ容疑で収容所に入れられる。第2作(第3,4回)ではイギリスの反ユダヤ・親ナチス団体が暗躍する様を描いている。つい昨日見た第3作(第5,6回)は兵役を拒否する文学者を留置所でいじめ殺す看守や、賄賂をもらって特定の人物を「良心的」兵役拒否者と裁定する判事が自分の秘密を知った少年を殺してしまうなどという暗鬱で悲惨な話が続いている。
見ていて本当に重い暗いドラマなのだが(それも魅力ではあるが)、幾つかの救いがあって、何より主役のフォイル警視正がむつかしい社会情勢の中でも信念を持って仕事をする正義漢ぶりが痛快である。それと専属の女性運転手サム(本当はサマンサというらしい)の明るいはっきりとした性格に救われる。毎回のゲスト役の俳優さんたちのキャラの立った役も魅力的である。
2015年09月14日(月) ミシマとスギちゃんとしろ
三島由紀夫「午後の曳航」は何とも後味の悪い小説だった!まだ読んでいない人には悪いが、あえて筋書きを述べると、横浜で店を持つ未亡人と小学生の船好きな息子がある夏二等航海士の船員と出会う。船員と未亡人は関係を持つ。船員は一度航海に出るがそれを終えて帰国した冬未亡人と結婚の決意をする。早熟な息子は二人の寝室を覗くようなことをしながら大人たちの無理解を理由に仲間とつるんで船員を殺害する…という話である。「これだからミシマは嫌いだ」というのが読後感だ。こんな美しい題を持ちながらあのような筋立ての小説を書くのだなと失望した(三島の作品はみなすばらしい題を持っている)。何か期待したものがあっただけ裏切られた気持ち(しかし「金閣寺」の評価は変わらない)。こういう小説に共感を持って評価する自分でないことにほっとした。ま、これでミシマから卒業(中退か)しようと思ったことである。

——昨日は低所得市民の一員として国保料のことを愚痴ってみたが、今日、役所へ行って国保料の減免申請を行なってきた。もう今年度分の半分は支払済なので以後いくら安くなるかは来月のお楽しみ。
妹の肥満対策としては食事の他にはやはり散歩(ウォーキング)しかないと思い、これまでのような一人でぶらぶらするだけの散歩はやめてちゃんと1万歩を目標にまた一緒に歩こうということになった。S子(妻)は「わたしのことは考えてくれないの」というので、じゃあ「S子改造計画」も立ち上げようかというと「もうちょっと涼しくなってからね」という。ダイエットは明日からという奴に限って成功したためしはない(v_v;)。
というわけで久しぶりに妹と大曽根まで歩いた。久しぶりに「スギちゃん」にも会ってきた。前にスギちゃんのことを書いたのはもう2年半前だが、実はその後も時々会ってはいる。それでも久しぶりには違いなかった。何度呼んでもこのスタイル以上には反応してくれなかったが元気そうではある。
 大曽根で久しぶりに会った犬の画像。外の犬小屋に繋がれている。
大曽根で久しぶりに会った犬の画像。外の犬小屋に繋がれている。
スギちゃんは相変わらず臭かったが、じつはウチにもおんなじ匂いをさせているネコがいる。「しろ」という18歳(!)になる老ネコだが、もうガリガリに痩せてとてもかわいいとはいえない(2013年まではこのHPの巻頭を飾っていたが、今は引退した)。一日中台所の隅で寝そべっていて毛繕いもしないからか汚れ放題である。何度も「死んでいるのか?」と思わせたが、大声で呼ぶと首をもたげるので生きているのがわかる。洗ってやろうとすると残り少ない体力を全部使って抵抗するので無理ができない。拭いてやるくらいでは落ちない汚れである。それでいて人間のご飯どきにはそばへ来ておねだりをするので食欲はある。夜中に時々異様に大きい声で鳴いたりする。少しボケがきているかもと思わせるフシがある。「老醜」とか「明日は我が身」という言葉を思い浮かべるが、一方「せっかくここまで生きたのだから20歳まで頑張ってみたら?」と言い聞かせたりもしている。本人に悪いから近況写真は載せない。
2015年09月13日(日 ) 健康診断から
先日、T子(妹)が作業所からもらってきた健康診断の結果を見てびっくりした。「健康診断個人票」の判定が真っ赤だ。中性脂肪、LDLコレステロール、BMI、血圧、X線検査等が「要医療」や「要精査」判定になっていた。なにより体重が前回検査のときより?kg(あえて伏す)も増えている(おまけに身長が1cm縮んでいた!)。確かに見た目にも腹の出具合が尋常ではないし、二の腕も私より太い。毎日のようにウォーキングしているが、まったく効果はなかったのだ。妹の個人的一級秘密情報を洩らして悪い兄貴だが、かくいう私もこの一年(会社を辞めて以来)で2kgは太ってしまった。妹に負けないくらいハラが出ている。いったい何が入っているのかと思うくらいだ(S子(妻)のことを書かないのは優しさからではない(^ ^;)。
肥満はともかく「X線検査」の「要精査」については放っておけないので、すぐ妻にかかりつけの病院に連れて行ってもらった。そして「西部医療センター」というところに紹介状を書いてもらって再検査した結果、先生が「はっきりわからないのでよければ『CT造影検査』をしたい」ということになった。妻が電話で相談してきたが、私は即座にそれはしなくていいからと返事した。造影剤の注入は(私も経験があるが)本人にはかなりの負担であるし、いろいろな注意事項や同意書の作成など面倒だったのだ。それに多分問題はないだろうという素人判断があった。これまでにも何度か再検査を家族で行なってきたがみんなシロだった(一度などは妹がバリウム検査で「精密検査を要す」となって胃カメラを「飲む」ことになったのだが本人の拒否反応がすさまじく先生もこれはムリだということになった。もう20年も前のことなので胃カメラも飲みにくかったのかもしれないが)。
医者や病院に対する不信感は我ながら相当なものである(そのくせ大病したときなどは半べそかきながらすがりついたものだが)。決して医者が儲けることばかり考えているとは思っていないが、実際に患者は検査漬けや薬漬けにされてはいないだろうか。妹は障碍者のため医療費には補助があるので、経済的な理由で医者にかからないわけではない。医者にかかる度合いは私に比べると多い(時々名古屋市から配布されてくる「医療費のお知らせ」による)。こちらが支払う毎月の国民健康保険料(税金)も決して安くはないのに、病院の窓口で支払う金額もまた実費の3割と高い。保険料を払うからには窓口は無料が原則のはずだ。

「減税日本」などという名古屋の地域政党があるが、市県民税など1割下げてもらっても低所得住民には年間数百円しか恩恵がない。それを言うなら「減・国保料日本」でお願いしたい。本気で国保料を下げよという政党は市民・国民のための政党であることの間違いのない指標であろう。
2015年09月11日(金) 「金閣寺」を読む(2)
「金閣寺」は難解である。難解ではあるが、読めないことはない。知らない語彙もたくさんあり、辞書(といってもPCでだが)で調べながら読んだ。こんな読み方をすることも珍しくなった。それだけ自分が古典や歴史的「名著」などを読まなくなったわけだが、たまに読むと「やはり古典はいいな」となる。
それにしても作家の語彙の豊富さはすごいと思った。すこし揚げてみよう。「光彩陸離」「羈絆」「逕庭」「遁辞」「揣摩」「搏つ」「憫笑」「杜鵑花」「知悉」「喫緊」「偏頗」「倨傲」・・・。要するに私自身が知らない難しいと思う語彙にすぎないのだが、辞書を引いてでもこの文章の意味を把握したいと思わせる筆力に驚く。彼(三島)はこうした語彙を駆使して主人公(姓を溝口というが名は設定されていない。他の男性人物も同様。女性は名のみが多い)が金閣を「焼く」までの心理的道程を説得力を持って読むものにせまる。
この作品にはモデルとなる事件が実在するが、ことさらそれについての興味を引き起こす作品ではない。あくまで主人公すなわち作者の美に対する思想遍歴が主題である。思想は抽象的ではあるが、耽美的でありながら強い写実の力によって主人公の具体的な外的体験と密接に関連している。例えば、
私には有為子は生前から、そういう二重の世界を自由に出入りしていたように思われる。あの悲劇的な事件のときも、彼女はこの世界を拒むかと思うと、次には又受け容れていた。死も有為子にとっては、かりそめの事件であったかもしれない。彼女が金剛院の渡殿に残した血は、朝、窓をあけると同時に飛び翔った蝶が、窓枠に残して行った鱗粉のようなものにすぎなかったのかもしれない。美しい文章である。主人公の内的独白の形式による長所を活かして叙情性と写実性が一体化している。こうした描写を全編にちりばめているのだから読まないわけにはいかなくなる。(小学館「昭和文学全集15 石川淳・三島由紀夫・武田泰淳・安部公房」より)
消失前(と思われる)の金閣の微にいり細にいった描写は、再建になる現在のそれよりも読む人を魅惑するに十分である。主人公または作者は焼くからにはどれだけ美しいかを口(筆?)を極めて描かなければならないと思っているようだ。戦時中に空襲によって「遠からず灰になる」のであれば「現実の金閣は…心象の金閣に劣らず美しいものにな」るはずが、終戦により焼け残った金閣は主人公に対立した「未来永劫存在する」「永遠なるもの」となってしまった云々…。様々な経緯を経て突然「『金閣を焼かなければならぬ』」決意に至るまでの主人公の内的彷徨と外界の荒涼とした風景描写は小説のクライマックスの作り方の典型であろうか。
まるで作者が焼いたかのような点火のシーンなども三島の文章の魅力となっている。写実というより、空想力・妄想力の凄まじさである。人は、あるいは作家はこのような力を持っていることで小説家になり得るのだと我々素人に思い知らせる。
この小学館の本では「金閣寺」の末ページの次に同じ作者の「午後の曳航」という美しい題が見えていた。引き続き読むつもりである。
2015年09月10日(木) 栃木・茨城県の水害
朝起きてびっくり!栃木・茨城県に大雨特別警報がでている。台風18号直撃とも言える愛知県よりやや離れた関東でとんでもない雨が降っているのだ。これは18号だけでなくもっと東にある17号の影響もあるらしい。


鬼怒川の堤防が切れたという9/10 正午のNHKニュースのテレビ画面の画像(9/10 正午のNHKニュースより)
恐ろしいことだ。堤防が切れ、家や車が濁流に流されている。何人かが濁流の中を流されていくのを見たという人がいる。救助を求めながらその後連絡が取れなくなった人がいる。鬼怒川の堤防は補強工事が継続中で決壊・破堤したところはまだ工事が行われなかったところだという。もし間に合っていればあるいはと思われるのに残念だ。
つくづく2011年9月の台風15号の水害を思い出す(参考:「平成 23年9月の台風 15号による名古屋市の浸水被害」(置内大助・堀華日明・丸山陽央))
2015年09月09日(水) 「金閣寺」を読む(1)
大したことないと思っていた台風18号が意外に大きな爪あとを残していった。日本海に抜けて温低になったが、まだ雨が降っていて、今、カミナリも鳴った。秋雨前線の仕業か。明日もこんな様子らしい。
 9月3日、散歩で撮ったイネ。大丈夫だったろうか
9月3日、散歩で撮ったイネ。大丈夫だったろうか
たしかテレビで映画「金閣寺」をやるので、録画しておいてまず原作を読もうと思ったような気がしているのだが、わがHDDレコーダにはそんなものは入っていないし、どこのチャンネルにも放映履歴や予定がない。市川雷蔵主演の「炎上」でも探してみたがやはりない。
以前はこんなことがあればとことん原因を突き詰めたものだが、最近はそれはあまり意味のないことだと思うようになった。きっかけなどどうでもいい。とにかく読んだのだ!
三島由紀夫の小説は十代の頃同性愛への興味から「仮面の告白」を読んだ。以後、三島由紀夫には、あの1970年の「楯の会事件」や映画「憂国」等の右翼的イメージから偏見を持つようになり、だから彼の小説には近づこうとしなかった。ノーベル文学賞候補にもなっていたが言語道断だと思っていた。
それがひょんなことだが、自分のペンネームのひとつに「天人午睡」というのがあるが(このHPの名称もそうだ)、三島の最後の作品「豊饒の海」の第4巻が「天人五衰」である。私は「今昔物語」を読んでいたときに出てきた仏教用語から採ったのであって、もちろん三島の作品から拝借したのではない。だが、妙に意識するようになり、数年前「春の雪」「奔馬」を各100円(!)で買ったのを機会に読みかけ、その後また105円で「現代日本の文学・三島由紀夫集」(学研・昭和47年3月発行)で「沈める滝」と「青の時代」を読んだ。読書歴はそれだけだがどれも面白く、読み出すと途中で投げ出すことはなかった。
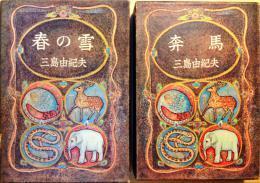 昭和45(1970)年・新潮社発行の三島由紀夫選集の表紙の画像。
昭和45(1970)年・新潮社発行の三島由紀夫選集の表紙の画像。
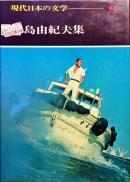 昭和47(1972)年・学研「現代日本の文学」35 (BOOKOFFの¥105が貼られたまま)
昭和47(1972)年・学研「現代日本の文学」35 (BOOKOFFの¥105が貼られたまま)
2015年09月01日(火) 防災の日と「戦争と平和」
今日は防災の日。去年の今頃防災訓練に参加したが、今年は特に呼び出しもなく自宅待機。ニュースで流しているのは東京の災害訓練ばかりでアベさんの顔が出てきたりして気分を悪くした。なぜ福島での原発事故を再想定した訓練を全国で行なわないのか。アベさんもぜひ原子力発電所のあるところへ行って、そこで最悪の状況が起きた場合を想定した訓練をして欲しい。地震と火山と津波と台風が最大規模で同時に原発を襲ったらどうなるのか、それくらいはだれでも想定できるのだから、そうした訓練を行なうべきだろう。退社一周年でもある。「『非常勤』がなくなってはや5か月」と、この間(8月14日)書いたばかりだが、27日久しぶりに呼び出された。仕事(=カネ)が欲しいのはやまやまだが、いざとなると面倒なものだ(スミマセン<(^ ^;)。毎日がfreeだとそれなりに日課も決まってくるのでそれが中断されることへのいらだちもある。ヒマといえばヒマだが、ほんとうに1日ボーッとしているわけではない。家事もよくやるようになったし、読書やギターなどもうわべでなく突っ込んだことができる。資本論の再読などは今こそチャンスだ。
 子ネコもだんだん飼い主に似てきた…
子ネコもだんだん飼い主に似てきた…
そんなこんなでけっこう忙しい。
2015年08月20日(木) SEALDs 長棟はなみさんの国会前スピーチ
今日の「赤旗」で「SEALDs 長棟はなみさんの国会前スピーチ」(要旨)を読んで感銘を受けたのでここに書き写すことにした。(「書き写す」とはコピーではなく、読みながらタイプしたということなので以下の筆責はこのブログの筆者(福沢)にある。引用は「赤旗」2015年8月20日付から)夏が来るたびこの国は戦争のにおいがして、光輝く夏は少しかげりを見るような気がしていました。私が小さいころ、広島に近い山口県に住んでいたので、なおさらだったのかもしれません。書き写しながら何度か目が潤んで手が止まった。戦争法案に対して何もしていない自分を叱咤激励している。なんと頼もしい若者かと感動した。戦後教育の成果を身を持って証明している。自分の近頃の若者に対する偏見を洗い流してくれるようなすばらしい文章だ。
8月6日、毎年同じ日、同じ時間に、遠くから聞こえるサイレンをお母さんと一緒に手を合わせて聞きました。ああ今年も夏が来たなあ、と毎年感じていました。「火垂るの墓」をきょうだいで泣きながら見たり、『はだしのゲン』を夢に出るほど読んだり。学校では毎年戦争の授業があって、戦争の話を聞きました。
嫌がりながら日本国憲法を覚えたり、9条のプリントだけなぜか配られたり。戦争は理不尽なもの、あってはならないものと幼いころから学んできたように感じます。
高校生になってから、実際に戦争を経験された方がたからお話を聞く機会ができました。空襲から逃げまどった人。日本兵として人を刀で斬った人。守るために自分の母親と弟の首を自分の手で絞めて殺した人。雨のように降り注ぐ砲弾の中を逃げた人。ピカドンを見て片目をなくした人。
「慰安婦」にされた人。壮絶な話でした。想像もできない事実でした。彼らはいいました。「二度と繰り返さない。そのために私は語るのだ」と。
今回、この戦争法案が話題になったとき、戦争を知らない若い世代が、「戦争はイヤだ」といいました。なぜかと考えると、戦争を間接的に学び、戦争を知っているつもりだからです。私を含めた彼らは、戦争というものを想像するしかありません。しかし、知っているのです。あの戦争の痛みを、悲しみを、苦しみを、多くの戦争を体験した世代から受け継いだのです。
この国は、日本国憲法、とくに9条とそれによる平和を誇り、しっかりと教育してきた国だと私は思っています。私が受けた教育は間違っていなかった。いまここで声を上げる私をつくりました。私はそんな国と学校を誇りに思っているし、これからもそうありたい。
70年間戦争をしなかった、他の国の人に対し直接銃口を向けなかった、一人も殺さなかった、という事実がこの国を守っている。このことを誇りに思うべきです。
しかし、他国から日本が直接攻撃されていないにもかかわらず武力行使ができるというのは、違うんじゃないでしょうか。なぜ他国との戦争に日本が参加するのでしょうか。
どうか、だれかのいう「きれいごと」「理想」をここで叫ばせてほしい。戦争はしたくない。人を殺したくない。殺されたくない。武力ではなく対話を。この叫びが「きれいごと」であってたまるか。
先の戦争はまちがっていました。私は日本人として、なにより人間として、戦争を繰り返してはならないという、意志と責任をたくさんの命から受け継いだのです。
私は私の言葉を語ります。言葉が足らずとも若くとも、私は現政権と安全保障関連法案に断固反対します。
(14日、国会正門前)
しかし一方でこのSEALDsの若者たちを「自分中心、極端な利己的考え」だと批判する若手自民党議員がいる(19日離党)。この議員は「利己的個人主義がここまで蔓延(まんえん)したのは戦後教育のせいだろうと思うが、非常に残念だ」とTwitterで述べている(「赤旗」2015年8月4日)らしいが、彼も同じ戦後教育を受けているはずだ。彼には自分もSEALDsの若者たちと同じ戦後教育を受けているという自覚はないのだろうか。
教育は押し付けではなく、自分で考え、行動していくための力を身につける環境のことだから、同じ教育を受けても人はそれぞれの人生を歩む。それは「戦後」教育に限らず戦前の「軍国」教育のなかでも反戦思想を貫いた人たちがいたことと同じだ。ただ、命をかけて戦争に反対する人たちと、人を殺し殺される戦争に送り出す者たちを同列に扱うことはできない。だからこの議員も同じ教育を受けながら人それぞれだと認めるわけにはいかない。
2015年08月14日(金) auのLTEフラットについて
「非常勤」がなくなってはや5か月。もはや「正式」にクビの状態。そろそろ本気で次の仕事を考えなくては。というわけでハローワークなどを覗いてみたが(HP)、地域、職種等で絞ると皆無である。地域の範囲をやや広げればあるにはあるが多分年齢的に難しい。最近は年齢を雇用条件にするのはオモテムキはだめらしいので書いてないが、明らかにムリだろう。右往左往、前途多難、暗中模索、五里霧中、七転八倒、絶体絶命。
 もえ。エリザベスカラーも取れて自由を回復。つい舌も仕舞い忘れていねむりを...
もえ。エリザベスカラーも取れて自由を回復。つい舌も仕舞い忘れていねむりを...
白羽の矢はiPhoneに当たった。夫婦ともにiPhoneというのは年金生活の今となっては実に贅沢だ(T子(妹)はCメールだけのガラケーなので問題外)。iPhone2台でおよそ1.6万円。まずこれをなんとかしよう!
いろいろググってみるとauの携帯料金がタカいという意見は多い。auのWebサービスはまず「LTE NET」(月額¥300+税)という インターネット接続サービスに入ることでネットやメールが使えるようになる。このままだと「従量制」といって通信量によって課金されるので外出先で動画などを見ようものならびっくりする高額請求が来る(上限はあるらしいが)。そこでさらにパケット通信料定額サービス「LTEフラット」(およそ月額5〜6千円)を契約してネット使い放題になるのだが、このLTEフラットというのがタカいのだ。これをやめてしまおうという提案がネット上に多く見られた。正確にはやめるのではなく定額制から従量制に変えるのだが、何かの間違いで高額請求にならないようにLTE NETもやめようという意見もあった。つまり外出中はiPhoneを単なる携帯電話としてのみ使用するか、別のより安価なモバイルルータを契約するということである。
無職の今は自宅以外でのネットはどうしても必要なことはないが、でもまあLINEとGoogleMap(ナビ)くらいは欲しいなと思う。せっかくのITの進歩(?)を満喫できないのはくやしい。そこでLTE NETは残し、従量制に注意しながら外でのネットはWi2のような公衆無線LANを使うことを考えている。iPhoneは「設定」で「Wi-Fi」や「モバイルデータ通信」のON/OFFが可能だし、アプリごとのモバイルデータ通信の使用をON/OFFできるので、まず自分のiPhoneだけLTEフラットをやめて様子を見る。うまくいきそうならカミさんのiPhoneもやめてしまう。
そんなことをS子に提案すると賛成してくれた。彼女自身かなり無駄だと思っていたようである。
2015年08月06日(木) 父の夢
昨夜の寝苦しさのせいだろうか、朝は必ず時間通りに起きるはずのT子(妹)も珍しく寝過ごした。体調でも壊したかと心配したほどだ。私もなかなか眠れず、久しぶりにNHK-FMの「ラジオ深夜便」を聴いていた。藤山一郎の歌をやっていた。明け方、久しぶりに父親の夢を見た。何と父を原付バイクの後ろに乗せて走っていて、ある陸橋に差しかかったらお巡りさんが見えたのであわててバイクを降り、素知らぬ顔で近くの喫茶店に入った。気になったのでバイクを見に行くともうなかった——という夢である。いつもだと必ずといっていいほどトイレを探すのだが、この日は喫茶店の出入りに不思議な階段を昇降するだけだった。夢の中で父と特に会話するでもなかったが、知った人物は父だけだった。この夢にいったいどういう意味があるのだろう。
私が生まれたのは父が57歳の時だ。私が知っている父の姿はちょうど今の私くらいのトシ(67歳)以降だから、今の自分が父にぴったり重なることになる(まあ最近は年齢によるイメージがムカシより若くなっているからこのままではないだろうが)。いわば兄弟のような老人が原付バイクに二人乗りしていたという夢になる。笑えない(ーー;)。夢の中では自分はいったい何歳だったのだろう。

映画の「鉄道員(ぽっぽや)」に幼く死んだ娘の幽霊が出てくる。映画「父と暮らせば」でも父親と娘が特に不思議にも思わず会話している。身内の幽霊は怖くないというが、私もそう思うし、身内の幽霊というものは実際にいてもいいとさえ思っている。出てくる方も驚かそうと思って出てくるわけではないし、出会った方は会いたかったのだから自然なことである。私は若い時から何度か危険な目にあった時、あとでふと母親が守ってくれたという気がしたことが何度もある。肉親というものは超自然的なことが自然に思えるものである。夢に母ではなく父が出てくるのは私が出てきてほしいからではなく、父の方で出てきたいのかもしれない。私がなにか父のことで誤解したままになっていることがあるのかもしれない。父のことをもう一度考え直してみなければならないのかな。
2015年08月05日(水) 終戦70周年の月
8月。今年は終戦70周年、ヒロシマ・ナガサキの原爆被爆も70周年。ひときわ祈念すべきこの年に、自分は今年も広島には行かないんだろうか。こうして一年延ばしにしている間にホントに行けないトシになってしまうのかも知れない。今なら時間はあるし、健康的にも問題はない。あとは実行するだけだ。
2015年07月28日(火) もえの勇姿
昨年12月15日に我が家に来たもえ(三毛猫♀)が早くも妙な声で鳴くようになった。あてねのときもそうだったが、猫は生まれて半年でもう妊娠可能期に入るのだ。暑くなってきて網戸だけになっているところで外に向かって「あお〜、あお〜」というような大声で鳴く。ふだん小声で短く鳴くだけなので驚いた。近所に迷惑だし、うるさい。直ちに手術を決意。かかりつけ病院で診察・予約・執行。昨今は避妊手術も日帰りである。
 帰ってきて少し落ち着いたところ…
帰ってきて少し落ち着いたところ…
ギターは相変わらず「アルハンブラ」を練習しているが、運指を覚えただけでちっとも上達しない。トレモロは遅いし汚いし、弦は唸るし(ー ー;)。
始まったばかりのLINE MUSICでパク・キュヒの曲をいろいろ聞いた(現在無料トライアルキャンペーン実施中)。「森に夢みる」は例によってトレモロが美しい。今まで聞いたことのない曲だったが、すっかり魅了されてしまった。自分で弾くのはとうてい無理だが、メロディだけでもと採譜してみた。
 森に夢みるという曲の一部の手書きの楽譜。これをトレモロで弾くと妙なる響きに…?
森に夢みるという曲の一部の手書きの楽譜。これをトレモロで弾くと妙なる響きに…?
この暑いのに散歩もしている。ほぼ2時間、4〜5kmくらい。毎日の熱中症情報が「危険」となっているので休憩と水分補給に気をつけて、今のところ元気に歩いている。なるべく日陰を選ぶが炎天下では(日傘の替わりに)持参の雨傘を差す。見た目は良くないが効果抜群。疲労感がまったく違う。男用の日傘も売って欲しいと思う→売ってる〜!
技評の「世界一受けたいiPhoneアプリ開発の授業」も一応終わった。サンプル用のリストもすべて打ってみた。ときどき原因不明のエラーで動かなくなるが、その時は最初からやり直してみるとちゃんと動いたので自分のミスだなとわかる。が、原因不明のままなので気持ちが悪い。swiftはやはりVBAなどよりはかなりむつかしいようだ。いろいろなことを覚えたはずだし、自分でもアプリを作ってみようと思って始めたはずなのにどうもイマイチ気が乗らない。それより今ある色々なアプリを利用することを工夫した方がいいのではと思っている。実際、今も家計簿やレシート読み取りなどのアプリを使っていて、これらを自作するなんてことは思いもよらない。まず何を作りたいかが決まっていないのだ。しばらくはこの模索が続くのだろうか。
2015年06月20日(土) 「アルハンブラ宮殿の思い出」
ひと月以上HPの更新の間を空けてしまった。「音楽の思い出」を書いているうちにむか〜しの(およそ半世紀前!)作曲ノートを引っ張り出していくつかの作品をPDFにしてUPしている(感謝:MuseScore様)のだが、さらにこれらをメロディだけではなくギターでちゃんと演奏できる曲に仕上げたいという欲求にかられた。
ギターは10代から始めて、例の「愛のロマンス」(禁じられた遊び)をなんとなく弾けるところまでやったが、その後は時々爪弾くくらいで本格的に練習することがなかった。有名な「カルカッシ・ギター教則本」(全音楽譜出版社)も買ってはみたがほとんど活用していない。
しかし、やはり自作の曲をギターで弾くにはある程度のテクニックが必要である。で、またぞろ古くなって垢もついているような愛器を取り出しちゃんと掃除もして試弾してみるとまだまだいい音色がする。何十年ぶりでチャレンジし出したたのがこれまた有名な「アルハンブラ宮殿の思い出」(タレガ作曲)である!
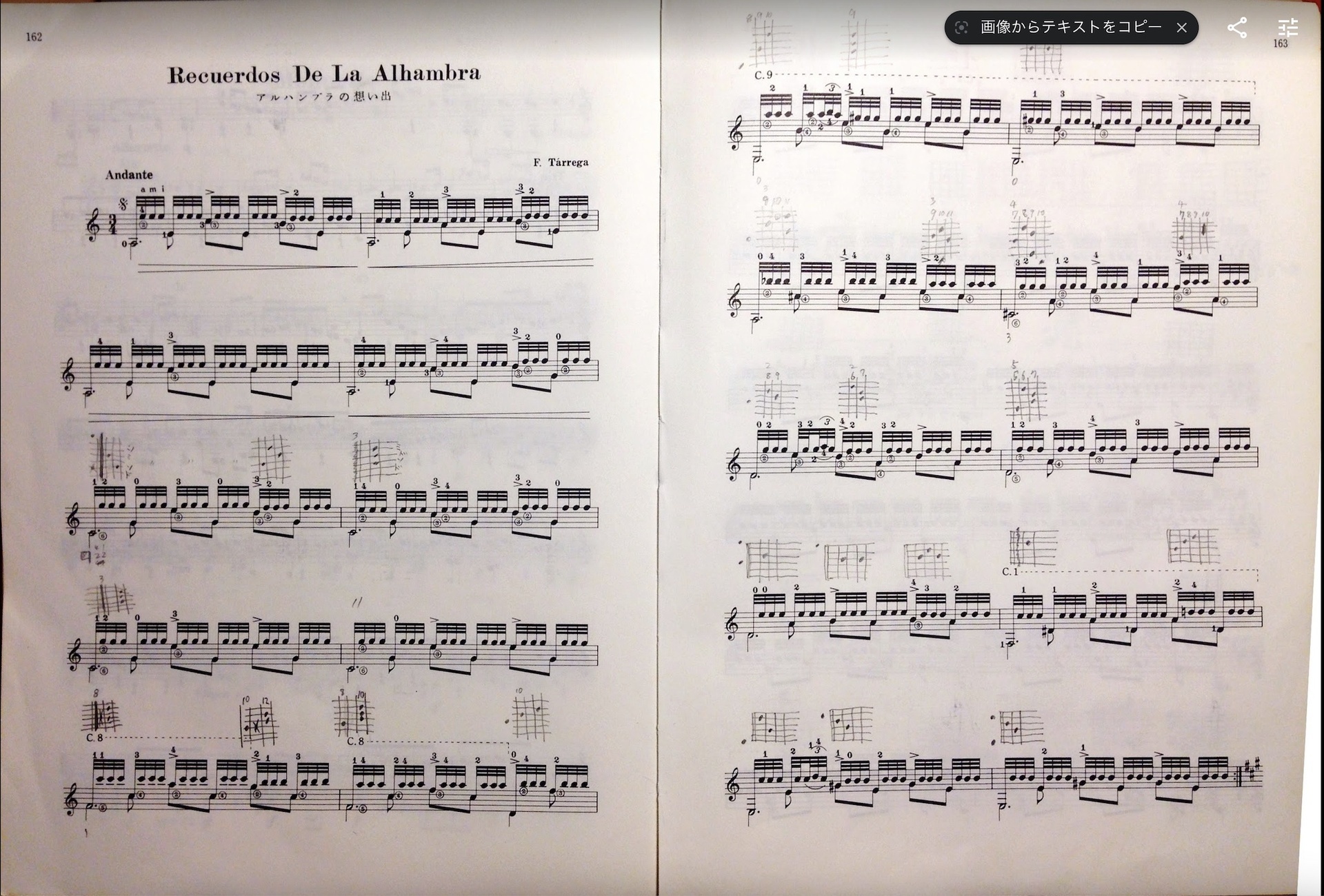 誰でも一度は聞いたことのある名曲!(カルカッシ教則本に掲載)クリックで拡大可
誰でも一度は聞いたことのある名曲!(カルカッシ教則本に掲載)クリックで拡大可
一念発起から一ヶ月。楽譜には強いので一応左手の運指は覚えた。トレモロも少しは弾けるようになってきた。あとは反復練習のみである。今は左手の指先の痛みに耐えかねる毎日である。
そして今回無謀にも武満徹「ギターのための12の歌」(ショット・ミュージック株式会社発行の楽譜。¥2,100)を買った。以前、NHK-FM「気ままにクラシック 」で鈴木大介の演奏でそのうちの何曲かを聞いてずっと心に残っていた。ロンドンデリーの歌とかオーバー・ザ・レインボーなど有名な曲ばかりの武満による編曲なのだが、さすがに楽譜を見て息を呑む。オニムズイとかマジかんべんという変な言葉が口を出る。しかし12もあるんだからひとつくらいは何とかなるだろう…。
2015年05月12日(火) 音楽の思い出(2)
昭和35(1960)年、中学一年の時、教育用にサカホーンという楽器を買わされた。弾き方などを教えに来た人が「軍艦マーチ」などをとても上手く弾いて(当たり前)すっかり魅了された。その日から虜になり、明けても暮れても弾きまくっていた。この楽器はハーモニカとそっくりだが、2段ある吹き口の下は普通の音(ピアノの白鍵)、上の段は下の音の半音上の音が出る。楽譜の線上の音は吹く、線間の音は吸う、♯や♭の音は上の段というように五線譜とてても相性が良いのですぐ覚えられる。この楽器のおかげで楽譜も読めるようになったと思う。
このサカホーンで童謡、唱歌、歌謡曲、クラシックの名曲のメロディやテレビドラマの主題歌など、あらゆる曲を吹きまくった。さぞ周りには迷惑だったことと思う。この楽器を私はついこの間まで後生大事に持っていたが、去年ついに捨てた(;_;)。一方で音楽に目覚めた(?)ことから、吹奏楽部に入ってクラリネットをやるようにもなった。
好きなジャンルは結局はクラシックに留まった。定番通りベートーベンから始まり、交響曲5番や7番には夢中になった。7番の第二楽章などには言いようのないほどの強い感動を受けた。やがて彼の前後の時代の作曲家へと広がっていった。
作曲もかなり早くから試みるようになったが、これには大きなきっかけがあった。同級生のO田君という子が、お姉さんがクラシックの楽譜をたくさん持っているというので無理に頼み込んで何冊か貸してもらった。モーツァルトの弦楽セレナード(アイネ・クライネ・ナハトムジーク)やシューベルトの未完成交響曲、ベートーベンのピアノ協奏曲(皇帝)などである。またピアノのピースやソナタアルバムなども貸してもらった。なんと私はこれらを返却もせず今でも持っているのだ!<(~ ~;) 当時の私の道徳観はどうなっていたのだろう。こういうところに「育ちの悪さ」のようなものが出ているのかもしれない。
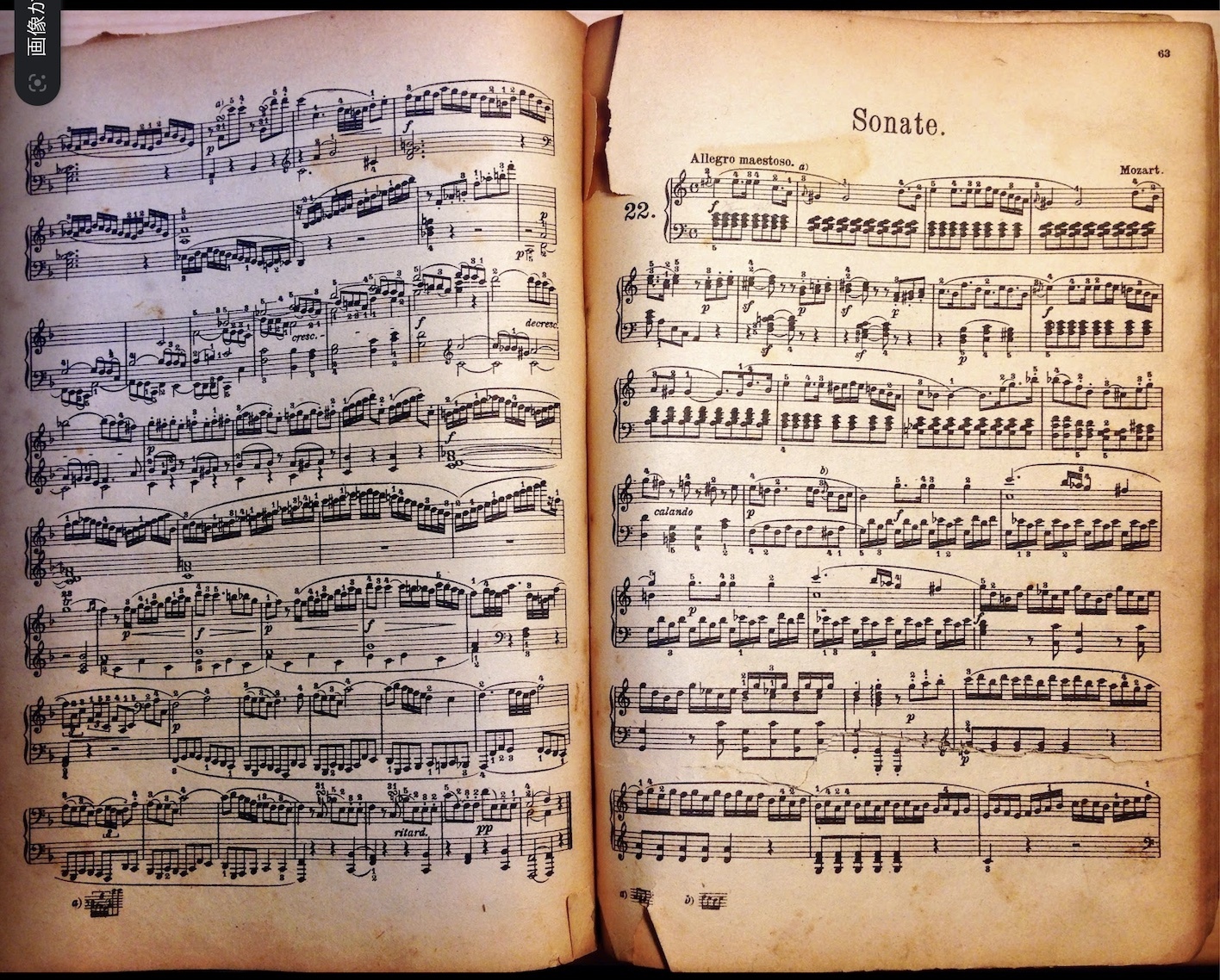
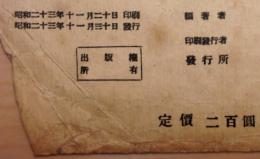
全音楽譜出版社の昭和二十三年発行のソナタアルバムとその奥付。楽譜はクリックで拡大可(右ページの曲はモーツァルトのK.310)
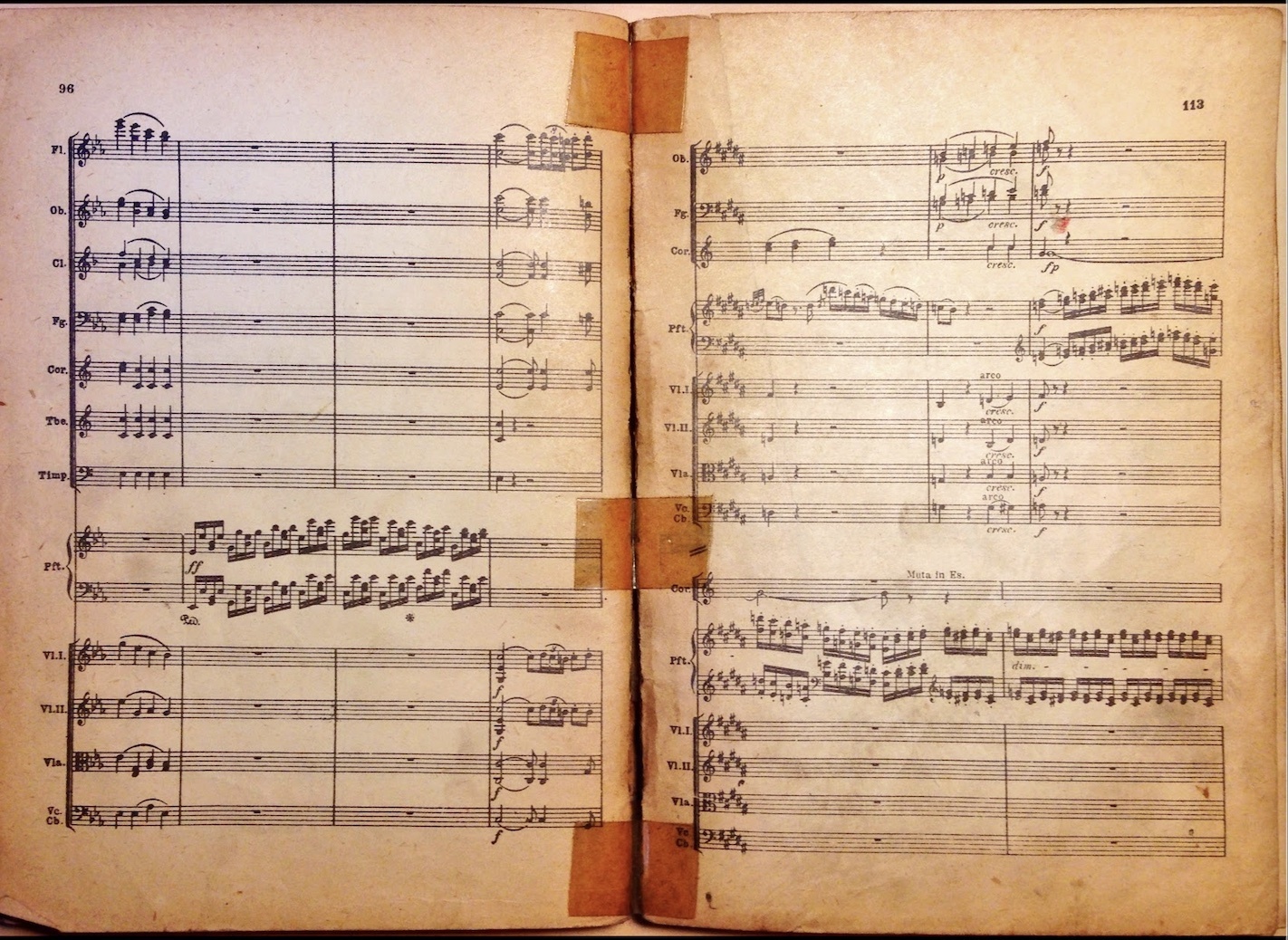 (日本楽譜出版社1950年発行のベートーベンのピアノ協奏曲「皇帝」。クリックで拡大可
(日本楽譜出版社1950年発行のベートーベンのピアノ協奏曲「皇帝」。クリックで拡大可
中学卒業後は岐阜に縁故就職することになり、音楽どころか高校も行けなくなったが、会社の寮生活をそれなりに楽しみ、例によって人のものを無神経に自分のものとしてしまう厚かましさから同じ部屋の人のレコードプレーヤーを私物化してよく当時大ヒットした舟木一夫や橋幸夫などの歌謡曲を聴いていた。さすがにドーナツ盤の「高校三年生」は自分で買った(と思う(^^;)。
父が病気になり1年半で名古屋に帰ってきた私はやがて本格的に作曲家になる決心をした。(つづく)
2015年04月20日(月) 音楽の思い出(1)
今年から英語のブログも立ててみようという無謀な試みを始めたので、本来の日本語ブログの方がややおろそかになっているかも知れない。自由に書かれたブログを(自分の文章とはいえ)中学生程度の英語力で英作文にすることやはり無理なので、ほとんどがgoogle翻訳とWeblio翻訳を利用して翻訳しているだけである(感謝m(_ _)m)。できたものが英文として実際に通用するものか一切検証を取っていない。一度英訳したものはほとんど見直していないし、誰かに診てもらっているわけでもない。まあ、こういう英語の勉強の仕方もあるのだという気持ちでやっているが、「英語が上達した」という自覚もこれまたほとんどない。(^ ^;
 名残りの桜(4/7 春日井市にて)…
名残りの桜(4/7 春日井市にて)…
さて1ヶ月ぶりの日本語ブログで、この間に桜もすっかり散ってしまった。今年もいっぱい見たし、それなりに感慨もあるのだが、毎年同じ事を思うので改めて書く事もない。
file:///Users/fkzwmso/Documents/tennin/gazou/809.jpg
唐突だが自分の若い頃からの音楽についての思い出を書いてみようと思う。ずっと前から考えていた事ではある。
人生で一番初めに音楽に「出会った」という記憶は、小学2〜3年生ごろのオルゴールである。それもオルゴール時計である。幼い頃我が家には父のコレクター趣味の結果だと思うが、子供にとってはけっこう珍しいものがいくつかあった。望遠鏡(測量用?)とか飛行機のプロペラの模型とか。その中にいかにも古いタイプのオルゴール時計があった。本体は一見真鍮製のような縦長の直方体で本体よりやや大きい天板と土台が付いており、天板には手提げも付いていた。正面はローマ数字が書かれた丸い文字盤で、裏にはフタがあって開けると大小のギアがたくさん詰め込まれていた。昔のゼンマイ式柱時計と同じゼンマイを巻いて動かすのだが、ある時刻になるとオルゴールが鳴る。その曲が今思うとドヴォルザークの「ユーモレスク」だった。オルゴールは土台の裏側に付いていた。男の子の常として仕組みを知ろうといじくっては壊してしまい、やがて曲も鳴らなくなってしまったが、何となく音のする仕掛けがわかった気がした。「ユーモレスク」に再度出会うのは中学生になってからであるから、それまでは曲は覚えても曲名はわからないままだった。
次には、小学校で習った唱歌多数。「子ぎつね」とか「もみじ」「灯台守」などは今でも好きだ。5、6年生のときに習った歌にベートーベンの「花売り」という曲があったはずなのだが、その後およそ50年間聞いたことがない。こんにちでこそネットやYouTubeで聴くことができるが、小学生から還暦までテレビ・ラジオで一度も聴いた記憶がない。たぶん放送はしていても耳にする機会がなかっただけなのだろうが。哀調を帯びたメロディに子供にはちょっとむつかしい歌詞をつけていた。ネットから仕入れた知識によると(http://blog.goo.ne.jp/kenkou27/e/135e274d1293959c0e9c87b97f1fb27f)ベートーベンが若い頃ゲーテの詩に作曲したものだそうである。外国の旅芸人が歌っているYouTubeの画像を見た限りではやはりどこか悲しげな曲調だった。
 立てば芍薬坐れば牡丹…の牡丹です
立てば芍薬坐れば牡丹…の牡丹です
2015年03月19日(木) 大高城址と「メグロ」…
2月28日、念願(?)だった緑区の鷲津・丸根砦を一人で見に行った。「信長公記」(角川ソフィア文庫/奥野高広・岩沢愿彦校注)を読んでいるとこの辺の地名がよく出てくる。自分の住んでいる所で戦国時代の歴史的人物たちが若き日に活躍していたかと思うと何百年という時間を超えて親しみを覚える。この本によれば、鷲津・丸根砦は織田方が今川義元の抑えとして築いたところで、ここから南西数百メートルの所にある大高城と北東1kmの所にある鳴海城(いずれも今川方の陣地)の間にあってこの二つの城を分断する位置関係にある(参照:名古屋市教育委員会「鷲巣砦跡」案内看板)。


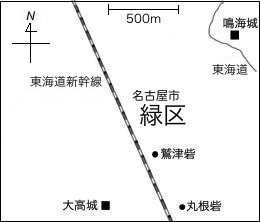
新幹線を挟んで東西に鷲津・丸根砦趾がある。右は鳴海城趾との位置関係を示した略図。
「信長公記」によれば、桶狭間の合戦の直前、重臣たちとの談義のあと、有名な「敦盛」を舞って出陣、鷲津・丸根砦の「落去」を知った信長は家来一同に次のような檄を飛ばす(本文54ページ、( )は引用者)。
「各々よくゝゝ承り候へ。あの武者(今川方)、宵に兵糧つかひて夜もすがら來り、大高へ兵糧入れ、鷲巣・丸根砦に手を砕き、心労してつかれたる武者なり。こなた(織田方)は新手なり。其上小軍ニシテ大敵ヲ怖ルゝコトナカレ、運ハ天ニ在リ、此語(後?)は知らざる哉。懸からばひけ、しりぞかば引付くべし。是非に稠(「ネリ」と読む)倒し、追崩すべき事案の内なり。分捕をなすべからず、打捨てたるべし。軍に勝ちぬれば此場へ乗ったる者は家の面目、末代の高名たるべし。只励むべし」名文である。これは信長より7つ年長で彼に仕え、慶長年間まで存命した著者・太田牛一の記述だから実際にこの通りの内容であったのだろう。
映画・ドラマで何度も観た桶狭間の戦いは、まさに信長、秀吉、家康たちの命がけの青春であった。信長26歳、秀吉23歳、家康は17歳。秀吉はまだ木下藤吉郎で信長の一家来、ねねとも夫婦になる前である。家康は今川義元の家来(というより人質)で名も松平元康であった。桶狭間の戦いでは先陣を命じられ決死の覚悟で大高城への「兵糧入れ」に成功している。彼ら皆、のちに戦国の英雄として名を残し三英傑などと呼ばれることなど思いもよらず、ただひたすら生き残るために日々の努力を連ねていた頃である。また、勝ち残って行ったからこそ後の世からその功罪を評価され、徹底的に研究されることで彼らの生きた時代を解き明かすこともできるのである。
そして次に3月13日、今度は家族3人で大高城址を見に出かけた。地図では城跡公園としてあるのでクルマですぐ到着と思っていたが、近ずくにつれ道が狭くクルマが通れない、駐車場もない。歩いてアプローチしようとしたが、駐車場探しに手間取った。ほんの近くにコミセンがあったが部外者の駐車はダメということで(当たり前)、近辺を回ってやっとアオキスーパーを見つけ、そこから歩いて行くことにした。ここまででくたびれてしまい、珍しく喫茶店に入る。普通の農家風の民家をそのまま喫茶店にしたお店で、畳に和机という席でコーヒーとトーストを取った。ここで帰りがけに玄関で古いメグロのバイクを見つけ、いきなりテンションが上がった。あわててお店の奥に声をかけ写真の許可をもらう。
 メグロのロゴが見える。手前はイタリア製 ITALJET か。クリックで拡大可
メグロのロゴが見える。手前はイタリア製 ITALJET か。クリックで拡大可
話がそれたが、大高城趾はその喫茶店から歩いて10分ほどせまい路地道を登って到着した。頂にはかなり広い広場がありさらに一段高い所に城趾の石碑とその隣に城山八幡社がお祀りしてあった。内堀跡もはっきり残っている。

2015年03月11日(水) 大震災4年
昨日から思いがけぬ雪である。会社からの帰り、吹雪(名古屋人には)の中を自転車で走ってきた。(^^;
 愛車もご覧のとおり...
愛車もご覧のとおり...
今日は東日本大震災からちょうど4年の日。テレビも新聞もこの4年間の検証に詳しい。LINEの首相官邸からも安倍首相のメッセージが届いていた。首相の被災地訪問と国民に東北へ行こうと呼びかけた内容である。今朝のフジテレビ「とくダネ!」では津波で破壊された家屋にそのまま住み続けている一人暮らしの人の家からの中継をしていた。家の修理の援助を受けてしまうと被災者用住宅への入居資格を失うためやくなく壊れたままの家に住み続けているという。水道はあるがガスはなく、カセットコンロで煮炊きする生活。しかも修理援助の金額ではとても全面修復は無理とのことである。「赤旗」のトップ記事は毎年恒例に行なってきた「被災者300人本誌調査」。健康状態の悪化、生活と生業再建への公的支援が不足という人が8割というアンケート結果を載せている。「安倍首相がやっているのは弱い者いじめ。庶民のことがわからない政治だ」の声。「失業中」という人は38%、「『アベノミクス』は役に立っていると思いますか」の問いに66%の人が「思わない」、「原発事故前に住んでいた地域に戻る展望はありますか」には62%の人が「展望はない・戻ることはあきらめた」等々、生々しい実態が浮き彫りにされていた。
自分は震災が起きたあと1万円の募金をしただけでこの4年間被災地を援助する何の活動も行なわなかった。津波の威力におびえ、原発事故に経験したことのない恐怖を覚えていながら、自分には何ができるかを深く問い詰めることもなく、早く心の安定を得たいとばかりの4年間だったように思う(思えば数学の論文執筆に執心したことなどもそうした心の表れだったのかもしれない)。反原発の集会にも関心を持ちながらまだ一度も参加していないので今年はぜひ参加したい。
 昨日からの雪を被ったけさの梅の花
昨日からの雪を被ったけさの梅の花
この遺跡巡回中、八王子神社の一角に名古屋城築城時の石垣用の石を運ぶ時、落としてしまった石は落城につながるとして縁起が悪いのでここに祀ってあることを初めて知った。これが妙に気になっていて、後日であるが、
忘れ石神社の奥に名を残す
花もなき神社の奥の忘れ石
という句がふと浮かんだ。あとの句は俳句になっているかもしれない。短歌にはならなかったから「投稿」はしなかった。(^^;
2015年02月12日(木) Macのデータベース
WindowsからMacへの乗り換えで一番の課題がデータベース(以下DB)だ。WindowsではAccessを使っていた。Access95からのユーザである。いくつか自前のアプリケーションを作ってあったのを、さてMacではどうしようかと思っている。DBソフトはMS-DOS時代からdBXLなどを使ってきて一番興味のあるジャンルだった。WindowsになるとdBXLが使えなくなり、やむなくAccessに乗り換えたがdBXLのようには好きになれなかった。途中「FileMaker Pro Ver.3」を購入したこともあったが、何だか取っつきにくくて結局Accessから移行できなかった。 Mac用のDBとしてはこのFileMaker(現在はVer.13らしい)ばかりを考えていたが、値段の高さから二の足を踏んでいた。4万円もするのだ。
おととい「Mac データベース」という検索語で「TapForms」というソフトを見つけた(App Storeで¥3500 高!)。これだとAccessのテーブルをテキストファイルにすることで「フォーム」(TapFormsではAccessのテーブルに当たるものをフォームという)に読み込むことができる。ただリレーショナルDBではないのでフォームとフォームをリレーションすることはできない。
このアプリには「ピックリスト」という機能があって、一行に一項目だけのテキストリストを作り、フォームのフィールドにこのピックリストを関連付けておけばデータ入力のときに参照することができる。これがちょっとリレーショナルな雰囲気を持っているのが面白い。ピックリストを別のフォームにするだけでリレーショナルDBにできるのではと思わせる。
今のところ蓄積したデータを参照するだけなのでこれで十分。いよいよWindowsとはお別れかな。
2015年02月09日(月) 妹の還暦
今日は晴れながら雪が降るという、ややこしい天気だった。晴れていて雨ならばキツネの嫁入りなどというが、晴れで雪ならばさしづめ雪女の嫁入りか(今日は友引)。散歩に出かけてすぐ雪が降ってきたが、地面に落ちるとすぐ消えてしまうような淡い雪でそれを陽の光の中で見ているととても美しい。そのまま散歩を続けた。ただ、新川中橋を北向きに渡ったときは半端なく寒かった。寒風身に沁むという言葉が実感できた。行きつけの百均で猫の爪研ぎ防止シールとともにもえのためにネズミのおもちゃを買う。こんなところは孫のためにお土産を買っていくじいじの心境と一緒かもしれない。まあ、自覚しているならば特に問題はない...と思うが。(^ ^; 今日はT子(妹)の誕生日で、しかも還暦である。といっても大したことはしないが、たまたま家族皆自由日だったので、昼も夜もいっしょに食事をし、型通りにささやかなプレゼントとお祝いのケーキを食べた。今日はその他に、彼女のETCカードの登録を区役所で行なった。重度の障害者には「有料道路障害者割引制度」というのがあって2年ごとに更新があるのだが、今回はETCカードも作ってみた。本人名義のカードで高速道路を通行すると料金がほぼ半額になるというありがたい制度だ。これまでも病院へ連れて行く時など料金ゲートで障害者手帳を掲示すれば割引が受けられたが、料金ゲートでのやり取りが面倒で自分のETCカードで無線通行してS子(妻)とケンカになったりしたこともあった。
手続きは面倒ではないがやや時間がかかる。まず、本人名義のクレジットカードを作る。カードが届くのに1週間。それから今度はそのカードを元にETCカードを申し込む。これも1週間。それを持って区役所へ行く(車検証やETC車載器の管理番号などが必要)。さらにそこで作ってもらった書類を「有料道路事業者」宛に郵送し、2週間ほどで認可通知が届きやっと通行可能になる。誕生日のお祝いではないが、いい記念になったと思う。
2015年01月21日(水) 塗装入門
ここ2、3日風邪気味である。昨年秋からヒマになった(パート勤務をリタイア)こともあって手の届く範囲で家のリフレッシュを行なっている。といっても団地住まいだから大したことはできない。これまでにベランダの網戸張り替え、風呂場のカビ取り、洗濯機の交換、洗面所の引き戸の戸車交換、そして今回は玄関ドアの塗装にチャレンジした。
何年か前、団地全体の塗装工事があった時にもちろんドアも塗り直されたのだが、そのあとドアに学習塾の募集の張り紙をした。とくに考えもせずA4のシール用紙をべったり貼ったものだから、あとでシールを剝がしたときに塗料が禿げて下地の青色が出てしまった。
 →
→

我が家の玄関の塗装が剥がれている画像と塗装後の画像。あまり出来は良くない。
まずは塗装面の清掃だが、これは適当に済ませる。新聞紙(赤旗しんぶん)をちぎって養生テープで塗装面を囲うように貼り付ける。団地の玄関は北向きで風も強くとても寒かった。これで風邪をこじらせたかも知れない。
次にスプレー缶で塗りを実行。やっぱり素人で塗料がタレたりしたが、二度塗りするつもりなのでそのままにし、翌日乾いているのを確認して軽くペーパーをかけ、タレを目立たなくする。缶に書いてある説明によると、スプレー缶とドアの距離を開けて平行に移動しながら塗るとタレないとある。なるほどタレない(説明書は塗る前に読まなくてはいけない(^^;)。
そしてまた翌日、やっと新聞紙を剥がし、完成(?)を確認。う〜ん、あまり気に入っていない。
 あまり気に入っていない (;_;)
あまり気に入っていない (;_;)
2015年01月18日(日 ) 北名古屋市西春町
今日の散歩は西春駅周辺。実は先週金曜日にも一度来てみたのだが、駐車場(無料)が見つからずクルマで駅周辺をぐるぐる廻ってみただけで帰ってしまった。ところが帰ってから地図を見るとほんの近くに北名古屋市役所があるではないか。というわけで今日はそのカタキ討ちで市役所の駐車場に停めさせてもらってからのウォーキング。市役所から東へ伸びている道は古くからの道筋のようで昭和っぽい店が並んでいる。
 民家の一角に立つポスト(現役)。お隣は「とうきや」というお店(陶器か)
民家の一角に立つポスト(現役)。お隣は「とうきや」というお店(陶器か)
 全方向性の風力発電機
全方向性の風力発電機
2015年01月15日(木) 初仕事
常勤していた会社はやめたものの、個人的にPCメンテナンスをしているお客さんが何人かいる。今週はその一人であるGさんのPCのメンテナンスが今年の初仕事になった。GさんはこれまでWindows Me(!)で売上管理を行なってきたが、昨年末、長年愛用してきたドットインパクト方式のプリンタが壊れてしまった。メーカーに問い合わせるともう修理もできないとのことである。ネットで相当の機種を探しても中々見つからない。それにPCも怪しい動きをするようになったので(起動を繰り返すなど)、もう使わなくなっていた別のPC(XP)にシステムを載せ換えて、プリンタもインクジェット方式に変えたいとの要望があった。お安い御用と安請け合いしたのだが、プリンタはともかくXPマシンに必須ツールであるエディタ(EmEditor Free)がインストールできないのだ。どうもWindowsXP SP3の「データ実行防止」(DEP)機能が邪魔しているらしい。Windows Installer が動かない。
C:¥boot.ini に「/NoExecute=AlwaysOff」を追加することまでは突き止めたが、今度はインストーラが破壊されているというメッセージが出る。結局PCをお預かりして自宅でネットで色々な情報を得ながら対処した。同じように苦労していた方達がいたようで、ネット上には色々な情報が流れていた。
自宅でああでもないこうでもないとやっているうちに諦めモードになり、ふと思い出したのが、Gさんの上司であるYさん(Gさんと同じシステムを使用)に以前予備としてウチで不用になったPCを預けてあったこと。これをGさんに回そうと考え、Yさんに電話した。快諾を得て翌日引き取りに行き、自宅でシステムの移行処理を行なったのだが、それが一段落してから最後にもう一度GさんのXPの修復をやってみた。何回もやってみた処理だったのだが、なんとこれが成功したのだ! あっという間にインストールが終わった。何が良かったのか悪かったのか、唖然としてしまった。
結局Yさんからお預かりしたPCは必要なくなったが、これを引き取ってきたあとに修復できたということが、なんとなく納得であった。これが有名な「マーフィの法則」である(!?)
 三役揃い踏み。手前がちょっと大きくなったもえです。
三役揃い踏み。手前がちょっと大きくなったもえです。
 これは今日のもえ。昼夜明暗問わず遊ぶ。
これは今日のもえ。昼夜明暗問わず遊ぶ。
2015年01月10日(土) 数学夜話(3)
整数論の勉強が続いているが、今はちょっと高木(貞治)先生の本を離れて自分の頭で自然数から実数までの数体系を構築してみることにチャレンジしている。うまくいったらこれが次の論文になるかもしれないという期待もある。方法として意識的に弁証法を用いている。その骨子は2008年09月25日のブログですでに書いていた。我ながら考え方がほとんど変わっていないことに驚く。進歩がないのだ。それがかえって不安である。ただ、実際に論を進めてみるとやはり山あり谷ありで、そこを気合いで押し切ってしまっているところもある。これはまずい。文章としては自然数から整数への発展までは記述したが、頭の中ではその先の実数の連続性をどうするかにいっている。やはりデデキントの「切断」しかないのだろうか。
 本文とは関係ないが、めずらしかったので…
本文とは関係ないが、めずらしかったので…
「連續性は分離的なものの統一として、ただ連關的で、純一な統一であるが、またこのようなものとして措定されたものであるから、それはもはや單なる契機ではなくて、むしろ量の全體である。このようなものが卽ち連續量である。」(引用書では強調したところが傍点。また随所にカナにした原語(ドイツ語?)が振ってある)。何だかわけのわからない文章だが、ここから思い至ったことは、
(量のところを数に置き換えて)数は(もともと)連続性と分離性の対立的な二契機を持っている。だから分離性から連続性に転化する方法は分離性を否定することではないのか。「分離する」とは言い換えれば分割することだから、それを否定するとは「分割できない」ようにすることだ。例えば有理数を「2乗したとき2より小さい数」と「2乗したとき2以上の数」に分けるとこれは分割になる。2乗して2になる有理数はないからだ。デデキントはこのような分割自体を「実数」にした。つまり分離を否定したものとしての実数を確立した。この新しい数の定義に基づいて数体系を再構築した(これは弁証法の常套手段である「否定の否定」)。これが彼の「切断」の本質なのだ、と。「切断」以外に興味をもっているのは「アルキメデスの公理」(リンク先に説明あり)である。これは一見明晰な表現であるが深い内容を秘めている。この公理のみを用いて実数の構築ができないかを今、目論んでいる。
もう少ししたらちょっと大きくなったもえをご披露しよう。
2015年01月03日(土) 明けましておめでとうございます
恭賀新年。2015年になった。年明けなので昨年分のブログとはページを変えようかと思ったが、しばらくは前年分も同じページの方が何かと都合が(自分にとって)いいので、しばらくはこのまま続けることにした。取りあえずは、恒例の真澄田神社ショットを披露(2日)。
 右がS子(妻)。フードが似合いすぎかも…
右がS子(妻)。フードが似合いすぎかも…
今年のお正月は全国的に大雪で、名古屋でも元日から降った。1日はもう出かけないつもりで朝から飲んでしまい、1日中テレビ三昧。2日に初詣に出かけたらすぐに雪になり、ちょっと不安に。おかげで恒例ショットもこの有様(フード)。でも風もなくてそんなに寒くはない。午後には雪もやむ。初詣の帰りに、これも恒例のH井君宅に年始に立ち寄り、御節とALL-FREEを戴く。共通の友人から先月結婚したという年賀状が来ていてその話題で盛り上がっていたらそこへちょうど本人から電話もかかってきてさらに盛り上がる。
今日3日は名古屋市北区の有名な羊神社へ3人でお雑煮の腹ごなしを兼ねて徒歩で初詣に出かけた。干支が当たり年なので混雑が目に見えていたけれど、T子(妹)が年女なのでどうしても行っておきたいと思ったのだ。昨年末散歩を兼ねて下見をした時にもお正月に向けて準備をしていた神社の人たちの気迫が感じられて元日はさぞやと思われた。案の定3日の今日でもすごい人出で、我々が到着した時で約百人、お参りを済ませた頃には参道が数百人の人で埋まっていた。

 3日の羊神社。
3日の羊神社。
2014年12月27日(土 ) ワーグナーの音楽
ここ毎晩、NHK-FMで年末恒例のバイロイト音楽祭をやっている。「ローエングリン」、「ニーベルングの指輪」の全曲等。今日は「指輪」の最終日「神々のたそがれ」で、これを聞きながら書いている。今年の7月に「ヴァーグナー オペラ・楽劇全作品対訳集」全2巻(井形ちずる訳・水曜社 2014年3月初版発行 ¥7,020)を衝動買いした。1ページを2列に分け左にドイツ語原文、右に日本語訳と文字通り逐次対訳されており、わかりやすくとてもおもしろい。これを読んで「さまよえるオランダ人」や「タンホイザー」が女性によって魂の救済を得るというテーマになっているのを初めて知った。「ローエングリン」もこの本で劇の筋を知った。これは逆に(逆か?)女性が白鳥の騎士に救われながら彼への誓いを破ったために死に至るという悲劇だが、ある意味究極のロマンチシズムで、バイエルン王ルートヴィヒ2世が夢中になって時代錯誤のお城まで作ったという有名な逸話も理解できそうな気がする。このお城は現在ではロマンチック街道の一番の人気スポットだとのことである。
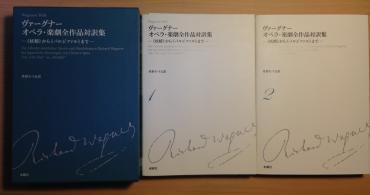
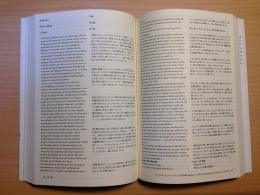
「ローエングリン」中の「結婚行進曲」はメンデルスゾーンの「夏の夜の夢」中の同名の曲と双璧をなす有名な曲だが、実際の結婚式ではメンデルスゾーンの方がちょっと多いような気がしていた(特にデータ的な根拠はない(^ ^;)。ひょっとするとその差は式場の人が「ローエングリン」の悲劇性を敬遠していたのかなと今では思う。私は自分の結婚式を当時大勢いた友人たちの計らいでいわゆる会費制で挙げたのだが、そこで意識的にワーグナーの曲の方を友人たちにリクエストしたことを今でもよく覚えている。それはメンデルスゾーンの方を何となく俗っぽいと思っていてそれに反発していたからなのだが、また当時ワーグナーの方の曲には誰ともなく「たかさごや、たかさごや〜♪このうらふねにほをあげて〜♫」などというフレーズをつけて茶化し気味に歌われていたことへの不満があった(ラジオで聞いたのかも)。当時クラシック音楽に心酔していた自分としてはそれが許せないという気持ちがあったのだ。
2014年12月23日(火) 師勝町と豊山町
今散歩から帰ったところ。師勝町のナフコから北部市場へ回り、県営豊山団地から楠公園というコース。およそ1万歩、8kmほど、2時間弱。風があると耳が冷たくなるが、ひなたを選んで歩けばそれほど寒さも感じない。
 歩道の脇に、誰が置いたのやら(^v^)…
歩道の脇に、誰が置いたのやら(^v^)…
わが町北区味鋺はもと西春日井郡楠町であり、一時は豊山町の前身豊場村・青山村との合併の話もあったらしい(http://ja.wikipedia.org/wiki/楠村 (愛知県)より)。それを聞くとより親しみがある(なぜ破談になったのかにも興味あるが)。町内の八所神社からエアポートウォーク名古屋までの道は農業村としての古き良き名残が多く見られて好きな散歩コースにしている。ただ一つの西春日井郡としていつまでも頑張って欲しい。
2014年12月18日(木) 4日目のもえ
これが我が家へ来て4日目のもえ(子猫)である。
 猫好きにはたまらん絵ですねぇ…
猫好きにはたまらん絵ですねぇ…
14日が総選挙投票日だったので選挙結果について何か書こうと思っていたのに、すっかりもえに気が入ってしまってあまり書くことが浮かんでこない。テレビの報道が与党の「圧勝」ばかりで面白くなかったのを「赤旗」を読んで溜飲を下げる。沖縄での完勝が万歳。明らかに沖縄は明日の日本である。
今朝は起きてみたら前日の予報通り一面の雪。北海道は大変なことになっているが、名古屋でも23cm降ったとのこと。朝ごはんを食べていると外で雪かきをしているスコップの音がする。ゴミ出しのための道を(多分自治会役員さんが)確保してくださっているようだ。腰を痛めているので手伝わないが、「ご苦労さま」と声をかけに行くのも変だ。会社に行かなくなってからはあまり天気にこだわらなくなった。散歩にはどうかなと思う程度だ。T子(妹)は今日は通っている作業所の日帰り旅行の予定が、前日に中止になっていた。
昨日は風呂場の年末掃除をする。団地の浴室は洗い場が防水コンクリートむき出しなのですのこを敷いているのだが、これを年に1、2回取り替える。カーマへ行って同じ寸法のものを買う(そういえば16日に居間の蛍光灯をLED式に替えたのだが、このとき天井のローゼット(というのかな)がネジで天井に取り付けてあるはずが片方のネジがなくなっていたのでこのネジもカーマで買った)。ついでに壁のカビや水垢を落とす。なかなか落ちない。手にちょっとしたケガをした。
で、今日は掃除はやめ。散歩もできないのでめずらしく朝から机に向かう。ガスファンヒーターももったいないので点けない。電気毛布の小型版みたいな膝掛けで足元を温めてながら厚着をしてマスクをして読みかけの本をいくつか進める。頭寒足熱がいいのかかなり進捗がいい。Macで書きかけの原稿も書いてみた。S子(妻)は雪の中を出勤。T子は洗濯物を家の中に干しているようだ。なんだか晴耕雨読みたいで理想の生活風景だ。
2014年12月15日(月) 誕生日のプレゼント!?
今日はわが67歳の誕生日。昨夜いつも風呂上がりに計測するタニタの体脂肪計の年齢設定を1年インクリメントした。その結果これまで一度も50代になったことがない体脂肪年齢表示がついに50歳になった。ショックであった。(^ ^;S子(妻)が「今日は(レジの仕事が)休みなので1日お殿様でいいよ。なんでも言ってね」などと言っているが、来年の彼女の誕生日への返礼が怖いのであまり嬉しくはない。散歩にも一緒に付き合うという。運動不足の妻にも散歩はいいことで、いつもできるだけ連れ出したいと思っていたので、まあいいかと久しぶりにお揃いで出かける。例によって足が遅い。こっちが普段のペースで歩くと後ろから開いた間隔を狭めようと小走りに付いてくる。仕方がないのでペースを落とす。途中、別小江神社にお参りする。加藤清正の石引きの図などを見る。
こんな調子で北区辻町まで来た。この辺には以前友人のH井君一家が住んでいたことがあって、「今、どうなっているだろうね」ということでちょっと寄り道をした。すると同じ歩道の先方に犬を連れた中年の女性がじっと一箇所を見据えて立ちすくんでいる。我々が近ずくと「ねえ、ちょっと、かわいそうに」と話しかけてきた。見ると片手に乗るような子猫が建物の陰でぶるぶる震えている。あきらかに捨て猫だ。
こんなのにS子が出会ってしまったらもう覚悟を決めなくてはならない。無駄な抵抗と知りつつ「ぜったい飼わないからね!さ、行くぞ」と先にずんずん歩く。振り返ると案の定、猫の前で立ちすくんだまま動かない。「だめだといったらだめ!」「置いてけない。だって今日、誕生日だよ」
え?何の関係があるのだ。どんなつもりで言っているのだ? まさか誕生日のプレゼントではないだろう。あるいは誕生日に捨て猫を見殺しにしたら寝覚めが悪いだろうってか?...
いずれにしてもこの一言でこっちの負けだった。仕方なくカバンからタオルを出して「ほら」と渡す。S子が不器用にタオルでくるみ、コートの中に抱き込む。タクシーとかバスとか考えたが、結局歩いて帰ることにした。彼女のスローペースがいらいらしてきたので途中で子猫を受け取り、被っていたニット帽の中に子猫を放り込み、コートの懐に入れてS子を無視した歩き方で帰路を急いだ。こうして家に連れてきたのがこの子である。
 命名もえ。雑種(?)の三毛猫。推定生後1ヶ月
命名もえ。雑種(?)の三毛猫。推定生後1ヶ月
さて、初めはおくるみの中でぶるぶる震えているばかりだったもえだが、人肌に温めた牛乳を指先に付けて口に持っていくとやがて舐めだし、ついには指をかじるようになった。子猫ながら牙もあり痛い。で、小皿に注いだ牛乳を差し出すと自分で飲む。次にはS子が近所のコンビニで買ってきた子猫用のキャットフードを与えるとこれもすごい食欲でちゃんと食べる。お腹いっぱいになったらしくお皿を離れたので試しに猫のトイレに連れて行くとちゃんとおしっこもウンチもする。なかなかかしこい子猫である!
次の課題は猫の先輩たちとの付き合いである。面白いのはあっちゃん(あてね。黒猫・メス・8歳)をお母さんのように慕い出したことだ。あてねは迷惑がって逃げ回るが、けっこう大きな声をだして追いかけまわす。とうとうあてねはお出かけしてしまった。いっぽうもえの二百倍くらい生きているシロはもうすっかりおかんむりで、いまにも食い殺しそうな声を出して忌み嫌う。が、襲いかかりはしないようで一安心。もえもさすがに一定以上は近づかないが、恐れている様子はない。たいした子猫である。
今時のネコは20年くらいは生きるということだから、もえの未来や如何。この子の最後を看取ることができるだろうか、それともこの子に見送られるのではないだろうか、中々印象深い誕生日になってしまった。
2014年11月27日(木) 東山植物園
紅葉を見る機会をうかがってきたが、二日間続いた雨が上がって最高の秋晴れになった。行き先は東山植物園。以前、週末に行った時、駐車場の料金と混雑のことを考えてちょっと離れたところにあるスーパーに駐車し、そこから2kmほど歩いて行ったことがある。そもそも散歩が主な目的だから歩くことは厭わない。で、今日も同じ所に駐めさせてもらった<(^ ^;
スーパーから県道に沿って地下鉄星ヶ丘駅まで起伏のある道が続き、そこから植物園「星ヶ丘門」までほぼ登り坂。ここは黄金の銀杏並木。いい運動になる。門で100円払って(一般500円。Thanks敬老手帳!)有名な化石のトンネルを抜けると早速一本紅葉の木がお出迎え。その後もすばらしい紅葉のラッシュ!


2014年11月24日(月) 初めての東別院
https://tenningosui.up.seesaa.net/blog_photo1/g1171.jpg 名古屋に生まれ住んで67年、今更だが初めて東別院(真宗大谷派名古屋別院)を訪れた。もちろん名前は若い時から馴染んでいる(地下鉄の駅名になっている)し、近くは何度も通っている。ひょっとしたら何かの用で「東別院会館」へは一度くらいきているかもしれない。しかしお寺としてお参りしたことはなかった。今日初めて訪ねる気になったのは「古渡城址」を見るためである。「信長公記」(角川ソフィア文庫)の注に古渡城の現在地として「東本願寺別院内」とあったからである。

 いずれもクリックで拡大可
いずれもクリックで拡大可
真宗大谷派 名古屋別院山門 県史跡・古渡城址
信仰心のない者が名古屋の名所旧跡としてこの写真を載せるのは気がひけるが、寺院(戦後の再建)の大きさに改めて宗教の持つ力をまざまざと見る思いである。教科書などで戦国時代の一向一揆をみると当時の力は戦国大名並みである。織田信長が比叡山と一向一揆を根絶やしにしたことでその後の秀吉や家康がどれほど武家政権の全国統一がやりやすくなったことか。
その信長の父である信秀が居城したのが古渡城で、信長もここで元服したとのことである(信長公記)。「古渡」という地名もよく馴染んでいるが、それは尾頭橋と山王橋の間の地名としてである。「古渡橋」があるからだろう。50年ほど前に「古渡に場外馬券売り場ができる」というので地域住民の反対運動が起き、民青の一員としてそれに参加した記憶がある。仲間とビラを撒いていて警察に追われ怖い思いをした。馬券売り場は今も「ウインズ名古屋」という名で存続しているようだ。
次に日置神社。神社沿革には織田信長が桶狭間の戦いの前に当神社に「祈誓、戦勝後に報賽のため神域に松樹千本を植える」とある。日置という地名も自分には懐かしいのだが、自分が知っている日置とは実は西日置のことで、どうも西日置の「鹽竈(塩釜)神社」のことを日置神社だと思っていたふしがある。西日置は子どもの頃遊びのテリトリー(学区?)の境界区域のようなイメージだった。だからここ(中区)に日置があるのは自分としては意外感があるのだ。
ついでに大須まで足を延ばす。「真福寺大悲殿」(大須観音)や、紙張地蔵で有名な「陽秀院」、毎月28日の縁日が賑わう「大光院」などをめぐってからお東さんに戻ったが、途中「栄国寺」というお寺の「切支丹遺蹟資料館」という石の表札に目をとめて境内に入った。昔、尾張徳川二代藩主光友の時代に数千人のキリシタンがここで処刑されたその供養塔があるという。資料館拝観は日を改めることにし、刑場の跡(と思しき所)に建てられた石碑を見た。他にも観音堂など大きくはないが古い建物が建ち並び、都会の中のちょっとした異界の感じを受けた。
2014年11月09日(日 ) 生棚川
今日は間違いなく雨だろうという空の中、カサ持参で外に出た。この頃は腰だけでなく膝(以前は右足で今は左足も)も痛いのだが、そういうことに負けてしまうことがいかにもイヤで、なるべく毎日少しでも歩きたいのだ。iPhoneに入れた「Walker」というアプリ(¥100)が歩数・距離・消費カロリーだけでなく歩いた軌跡が地図に出るのが面白く励みにもなっている。今日は北区の生棚川(なまたながわ・準用河川)沿いを歩いてみた。地図で見ると北区最北端の六が池町にある六が池から新地蔵川までを流れる人工の川だが、これを新地蔵川合流地点から遡ってみた。やっぱりすぐ雨が降り出したが面白そうだったのでこのまま歩くことにした。
 新地蔵川に流れ込む生棚川の水門
新地蔵川に流れ込む生棚川の水門
上の写真の水門は普段は空いているようだ。大雨の時に閉めるのか、それは新地蔵川の水が生棚川に逆流しないようにするためか、それとも生棚川の水が新地蔵川に入らないように?しかしそれだと今度は生棚川の水が溢れてしまわないのか?この辺の調整のしかたがよくわからない。
何枚か写真を撮ったがあまりキレイではないのでここに載せるほどのものはない。ただ生棚川は100%人工の川(もとになる小さな流れはあったかも)なのでその造形には興味がある。


生棚川の造形。右側歩道は川の上に張り出している。ひとつひとつの橋に施工者名のプレートが。
2014年11月02日(日 ) 庄内川の汚染
曇り空だったが傘を持って散歩に出た。いつ降り出してもいいように近場を廻ろうと考え、正月の初詣コースを歩いた。地元の7つの神社・お寺を順にお参りするのだ。老人趣味の極みであるが、単なる散歩コースであまり信心深い方ではない。(^ ^; 水分橋を北から南へ渡ると橋の下で何かイベントをやっている。「矢田・庄内川をきれいにする会」主催の「アユ遡上100万匹大作戦」と称して魚釣り大会をやっている。けっこうな人数で子供もたくさん来ていて面白そうだ。



確かにいつもふれあい橋や新川中橋を渡る時、矢田川に比べて庄内川はあまりきれいではないと思っていた。臭いもある。ちょっと上流にはいつも煙を出している製紙工場が見えている。自分でも時々散歩がてらこの工場付近を歩いてみるが、会社の社宅敷地内にはケヤキやサクラなどをたくさん植えて中々いい環境作りをしている。大会社はやっぱりいいなあとつくづく思った。しかしやはり川に対しては問題があるのだなと気づかされた。
2014年11月01日(土 ) ヘーゲルの弁証法
久々の出勤で疲れたのか(?)1日土曜日は一日中寝ていたが、寝ながら夢うつつに考えていた。今勉強している数学のテキストは高木貞治著「初等整数論講義」で、いずれは類体論を目指しているのだが、まだまだ先の話。読んでいてもどうも気持ちがもやもやしている。うまく言えないが「整数論とは何か」みたいな素朴な疑問が浮かんでは消えるのだ。で、思いついたのがもう一度ヘーゲルの「大論理学」を読んでみようということだ。ずいぶん昔に買っていっとき熱心に読んだ(「’76年」の書き込みがあった)。何度かの蔵書整理にも耐えて(?)まだ本棚に残っている。「大論理学」のなかの「量」について述べられているところは数学や数学者にとってとても参考になるところである。
ヘーゲルは弁証法の大家である。個別の弁証法ではマルクス以上に参考になると読んでいて思ったものだ。彼の弁証法は基本的に観念論なのだが、あちこちに出てくる具体的な例が唯物的で面白い。水が温度の下降・上昇によって氷になったり気体(水蒸気)になったりするとか、畑は大きくても小さくても畑だがそこに木を植えてしまえば野や森になるなど。要するに彼は自然界に行なわれるダイナミックな弁証法的事象は観念の反映であるとするのだが、マルクスはそれを「逆である」と批判し、人間の観念こそ自然の弁証法を反映したものだとして、弁証法的唯物論を確立したのである。「弁証法的唯物論」とはナマエはものものしいが、自然があって人間があり、人間の考えることは自然界に起きていることを意識の上に反映しているのだという、われわれの日常生活の常識に最も近いそれこそごく自然な哲学である。誤解を恐れずにいえば、あらゆる学問はこの哲学を導きの糸とするべきなのである。
2014年10月31日(金) 非常勤勤務
久しぶりに出勤した。月に2日も出勤すれば立派な「非常勤」だろう。まだクビではないのだ。 この日のご用命は新しいデスクトップPCの設定であった。XpからW7への引っ越しである。大体順調に移行できたが、ひとつ手こずったのは visio というソフトをVer5からVer2013に(W7では使えないので)バージョンアップしたのだが、これが今までに作った古いファイルを開けないのだ。ネットで調べてみるとどうも互換性はないらしい。しかたがないのでこれまでVer5で作った図面などをもう一度Ver2013で作り直してもらうことになった。OSが変わってソフトを変えたのにデータの移行ができないのは腑に落ちないことである。疲れた〜
 疲れた〜
疲れた〜
2014年10月30日(木) 川の道、花の道
今日は名古屋市と春日井市の境界付近を歩いてみた。以前は小川か用水のあったところを暗渠(下水道?)にした道で、それがJR味美駅付近まで続いている。暗渠になっているところは住宅の裏口に面したところをうねって通り、歩行者専用のいい散歩道である。自然繁殖したような大型の植物もあるが多くは沿道の家の人たちが丹精している花々らしく、今頃は花と果実の両方が楽しめる。花の名前を知っているとより楽しいのにとは思うが、皆目わからない(雑草の方が少しは知っている)。スマートフォンなどで写真を撮って検索ができればいいなと以前から思っているがまだできないよね。植物図鑑を持ち歩いたこともあったがコンパクトでもけっこう重いし、現物との同定がなかなかむつかしい。一番いいのは名札を付けておいてくれることだ。ハナミズキとかサルスベリなどはそれで覚えた。
途中で川筋(道筋?)がわからなくなったので、広い通りに出てエアポートウォーク名古屋を到着地点にした。一息入れてからまた徒歩で帰宅。ほとんど汗もかかず快適でした。いい季節だ。
2014年10月28日(火) 「天人午睡」をリニューアル
このHPをリニューアルした。大掛かりなリニューアルは2回目だが、画面のフォーマットはあまり変わっていない。リニューアルの一番の理由は、現在では「index.html」ソースでフレーム<frame>タグを使ってはイケナイということを学んだからだ。フレームで作られたHPでは index.html の中身はフレームの定義式だけが記入されていて、実際のコンテンツはindexファイルから<frame src="他のhtmlファイルのパス名">で呼び出される。これがまずいのは、実際のコンテンツが検索等で引っかかった時にはフレーム無しで(予期しない形で)画面が表示されるのである。自分で自分のHPを検索してみてよくそんなことがあった。
ではどうしたらいいかとググってみるとちゃんとありました。やっぱり CSS なんだなと思ったことである!
 やっとわかったか、愚かもの!といわれているような...。
やっとわかったか、愚かもの!といわれているような...。
フレームがだめな理由と「正しい」やり方がわかれば一刻も早く直したい。で、3日かけてリニューアルしたのが今のこのスタイルである。今度はトップページの内容はすべて index のなかに入り、他のコンテンツはこれまで通りルート以下のフォルダにある。以前は他のコンテンツはトップページ内の一つのフレームに表示していたが、それをやめて全画面で表示することにした。これでもし検索でトップページ以外が引っかかっても問題はないことになる。ただ、フレームを使って画面を作ることが悪いと言っているのではない。ブラウザが対応している間はどうやってつくろうが作る人の好みの問題である。CSS はわれわれド素人にはやっぱりまだむつかしい。今回だって3日でできたのは数多ある CSS 学習HP内のヒトサマの労作をコピーさせてもらったからに他ならない。(それにしてもこれら「学習」用のHP内になんと広告(アフィリエイト?)が多いことか。中には本文と広告が紛らわしくしてあるアザトイものも。)
2014年10月23日(木) リニア・鉄道館へ
部分入れ歯にも慣れた22日、初めて「リニア・鉄道館」に行ってきた。友人のH君と一緒である。うわさ通り素晴らしい博物館であった。新幹線モデルもたくさん展示されていたが、われわれ(自分だけ?)には古い列車のほうが良かった。大正時代に国産された木造の電車(モハ1035)にはとてつもなく感動した。今でも走ってほしいと願う人は多いのではないだろうか。
老若男女誰でも興奮するのが「鉄道ジオラマ」である。20分のイベント時間があっという間である。スカイツリーからお伊勢さん、奈良薬師寺も。火事や交通事故が起きていたり、遊び心満載である。これを見るだけでも行ってみる価値あり(リニア・鉄道館HPにビデオがあります)。
パノラマスクリーンが大迫力の新幹線N700の運転シミュレータは、人のするのをみていても面白かった。東京から名古屋までを約10分かけて運転できる。名古屋駅到着でホームにぴたりと止まると思わず拍手したくなる(スタッフの方の「手引き」が相当あると思うが)。
リニア新幹線ももちろん力を入れて展示されている。つい先日着工にゴーサインが出たことでもある。館名に「リニア」と付いているのは、「鉄道館へ行こう」というより「リニアへ行こう」と言ってもらいたい気持ちがありありである。しかし問題山積だぞ。
2014年10月11日(土 ) ブリッジ元年
ブリッジと書いたのは入れ歯のことである。先日に引き続き老人ネタで申し訳ないが、9月18日友人とクルマで話しながらグミを噛んでいたら右上奥のかぶせが突然取れた。チラリと見るとかぶせてあった金属だけでなく根っこごと取れたようだ。
というわけで毎週金曜日が歯医者通いとなり、昨日晴れて入れ歯装着となった。歯医者の窓口で試供品のポリデントを戴いたときはかなりショックであった。まだ1本とはいえ入れ歯には違いない。これで心はともかく身体的には完全に老人の仲間入りである。覚悟を決めなくてはならないわけだ。
思えば歯の丈夫さは数少ない自慢のひとつだった。衛生的には並以下の家庭で育ち、15歳になるまで歯を磨く習慣がなかったにもかかわらず虫歯の記憶がない。2002年、今回取れた右上奥歯が欠けたとき初めて近所の歯医者にかかった。そのときは先生が抜きましょうと言ったのを抵抗してかぶせにしてもらった。次が2008年で今度は左上奥歯にもかぶせてもらった。それ以来であるからよく持ったものだと思うが、今回先生の言うにはかなりあちこちの歯が歯槽膿漏でやられているし、虫歯も2本ありましたよということである。こうなると老人になったからというよりはG腰と一緒で普段の不養生・不摂生・不衛生が祟っているとしか思えない。
 人生の大先輩、シロ。1997年生まれ(のはず)だからもう17歳だ。人間でいうと100歳くらい?!...
人生の大先輩、シロ。1997年生まれ(のはず)だからもう17歳だ。人間でいうと100歳くらい?!...
現代はネコも長生きになり、代替わりがゆっくりになった。それはいいことだが、S子(妻)に言わせるとおかげで野良の子猫を引き取る人が少なくなったという。
2014年10月09日(木) 恒例G腰襲来...
8月まで勤めていた会社に用ができて(クビではなくいちおう「非常勤」なので(^^;)、6日の朝久しぶりに出勤するつもりでいたら、台風18号のため暴風雨警報がでていた。どうしようかとも思ったが、外は以外に大したことがなく、雨も降っていないくらいだったので行くことにした。団地の自転車置き場へ行ってみると自分のだけでなく軒並み倒れている。やれやれと端っこから順に起こそうとしてやってしまった...G腰である!これはヤバい(正しい使い方?)と思ったが、その場にくずおれることもなく何とか自分の自転車までは起こせたので、痛いのを我慢してそのまま出かけた。午前中頑張ってみたがやはりあの独特の痛さに負け、用件半ばに退社した。そのまま3日間寝たきりになってしまった(トイレや食事はがんばって起きるのだが、これがつらい。十何年まえに購入した腰の コルセットと杖のありがたいこと!)。
 コルセットの方は以前に載せたので今日は杖を...もうすっかり老人のブログである。
コルセットの方は以前に載せたので今日は杖を...もうすっかり老人のブログである。
老人趣味のついでにちょっと前だが面白い木を見つけて写真にしたものがあった。
そのときは面白いと思って撮ったのだが、こうして改めてみるとなんか身につまされる思いである。。
2014年10月03日(金) 秋
今日は初秋の色シリーズを。秋の散策は本当に楽しい。草花は夏以上に豊富だし、可憐でとてもきれいだ。工事現場の柵に絡まって咲いている萩など、花の中でもっとも美しいと思う。
まだ暑い日差しの中で甲羅干しをするカメや、来るべき厳しい冬をどう越すのか何も考えていない野良のネコたちにも何となく秋色を感じるのはなぜか。
2014年09月23日(火) 悔しさの比較
確かに秋めいてきてはいるが、まだまだ暑い。朝夕はそうでもないが、日中の散歩はかなり厳しい。散歩を兼ねて近くのカーマホームセンターへカーテン用のリングとフックを買いに行った。突っ張り棒にリングを通してカーテンを下げようとしたのである。リングは1袋5個入り375円を2袋とフックは1袋429円で計1179円もした。
そのままいつもの散歩コースをたどり、よく立ち寄る100均のお店にも寄ってみた。なんと、リングもフックも108円で売られていた!(見た目は多少違うが機能的に同じ)。しかもリングは1袋で8個入っている。そのときの悔しさといったら! 思わずコマゴマと計算してしまった。単純差し引きで963円の損、約5分の1だ(リングは2個少ないがフックは余分に入っていた)。
 知風草(カゼクサ)。好きな秋の雑草だが、アレルギー源でもあるらしい...
知風草(カゼクサ)。好きな秋の雑草だが、アレルギー源でもあるらしい...
2014年09月12日(金) アタマが柔らかいS子(妻)さん
今日は小話をひとつ。朝、S子(妻)とT子(妹)が出かける時、妻が居間の照明のリモコンで寝室の照明を消そうとしたので、歯磨きの最中だった私はリモコンを指差して「オアエワ、アアア!」(お前は馬鹿か)と叫んだ。何を叫んでいるかわからなかった妻はそれを無視して「じゃあね」と玄関に向かった。あわてて口をゆすいだ私は今度はちゃんと通じるように「なんでこっちのリモコンで消そうとするのだ?お前、アタマおかしいぞ」といった。すると妻は「いいじゃない。消えるんだから」と涼しい顔。「え?」と私が消灯を確認に行くと成る程消えているではないか!
「ええっ、どうして?」
「知らないけど消えるんでいつもこっちので消してるよ」
二人が出かけたあとで試してみると、居間の照明Aと妻の寝室の照明Bはメーカーも違えば仕組みもかなり違うのにAのリモコンでBが消えるのだ。しかも点灯もできる。ちなみに逆はできない。BのリモコンではAは何の反応も示さない。
私はもともとAでBを点けたり消したりしようという発想がない。AとBは違う器具だからだ。しかし妻はBのリモコンがベッドの枕元にあって部屋の外からは遠いのでAのリモコンで試してみたのかもしれない。つまり「器具として違うから無理」なのではなく「どっちも照明器具なんだから同じでは」と思ったのかもしれない。不便さが彼女にこれを発見させたのだろうが、私もその不便さは常々感じていたのだから条件は同じである。私のアタマがカタいのか、妻のアタマがテキトーなのでこんな場合には適しているのか…

帰り道、堤防の上で萩の上を舞飛ぶクロアゲハが見事。おなじみの赤とんぼもたくさん見た。あまり広くないテリトリーをいつまでものんびり廻っている赤とんぼはこよなく好きだ。いつまでも見ていて飽きない。他のとんぼではそうならない。シオカラトンボには何も感じないし、もしヤンマだったら興奮して追いかけ回すだろう。赤とんぼだけ何故かじっと見てしまう。そしておセンチになるのだ。いったいなぜだろう。毎年同じである。
2014年09月06日(土 ) 退社日前後
退社して1週間が経った。晴れない日が多く、それでいて蒸し暑い日々だった。気象庁は今年の8月を「異常気象」と決定したそうだ(http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/longfcst/extreme_japan/monitor/extreme20140903.pdf)が、それが9月になっても続いているような気がする。退社2日目の8月31日、「名古屋市民総ぐるみ総合防災訓練」があり、自治会代表の一員として参加。警察や消防署も参加し中々真剣だった。広島の土砂災害直後でもあり、我々はいざという時は被災者をフォローする側になるので、和やかな中にも人ごとではない気持ちが感じられた。
 消防署レスキュー隊(だと思う)のデモンストレーション
消防署レスキュー隊(だと思う)のデモンストレーション
翌9月1日は友人のH君宅で光ケーブル接続工事に立ち会い、NDSの工事担当者やPC設定サービス担当者らから興味ある話を伺った。H君は今まで約10年の長きに渡りダイヤルアップのみでインターネットしてきたというツワモノ。これで色んなネットサービスや各種申し込みをしてきたらしいから、案外インターネットってダイヤルアップだけでも十分かしらと思ったことよ。無事開通後、今度は新品の多機能プリンタ(Canon製品)の無線接続をお手伝い。中々むつかしかったがなんとか成功。無線で印刷するのは自分でも初めてだったので後学のためになる。
実は退社日の前日、我が家でも光ケーブルの契約変更(「フレッツ光品目変更」)の工事があった。ヤマダ電機でH君のPC購入に立ち会った時、話の成り行きで自分とこもやってしまおう(Bフレッツ→フレッツ光ネクスト)ということになったのだ。おかげで通信速度は40Mbpsそこそこだったのが「90Mbps(最大100Mbps)まで出ました」(工事担当者)というから2倍以上は早くなっていた(らしい(^^;)。使ってみて確かに実感もある。おおむね満足。ついでに固定電話も「ひかり電話」にしたのだが、2、3日後、留守中の宅配便を受け取るために運転手直通の携帯電話に掛けたところ、「最初に00が付く番号はお繋ぎできません」云々のメッセージで「なんだそれ?」状態に。ネットで調べてみると、電話機が勝手に0033を付けて発信しているらしい。普通の固定電話ならそれで通話料が安くなるというNTTのサービス(「携帯とくとくダイヤル機能」)だが、ひかり電話ではダメということなので取説を引っ張りだしてこれを「使用しない」にして解決。さらにはプロバイダー(biglobe)での設定変更なども課題である。…さて新契約で請求料金がいくら安くなっているか楽しみなことである。
 花屋さんの美しすぎる猫(散歩の途中で)
花屋さんの美しすぎる猫(散歩の途中で)
その後、H君宅にはもう一度メールの設定で訪問。このとき近くの「豊月」という麺類屋で蕎麦をごちそうになったが、おばあさんがひとりでやっているそうで年期の入った昭和のお店。県道に面していてクルマが通るたびにガラス戸がガタガタ揺れる。H君の家は何度か内装のリフォームはしているものの、原型は昔と変わっていない僕にとっても懐かしいところだ。小学生の頃毎日のように訪ね、テレビをみせてもらった。彼のお母さんがやさしい人で、いろいろ親切にしてもらった。早く死んだぼくの母親を見知っていて、大人になってから話を聞いたことがある。
2014年08月13日(水) 久々に散歩らしく
台風11号が行った翌日は友人の新規PC購入に付き合い、ついでにじぶん家のBフレッツをフレッツ光ネクストに変える手続きをしてきた(byヤマダデンキテックランド名古屋本店)。昨日は栄まで好物のめかぶを買いにいった。初めは自転車で出かけたのだが、途中で雨が降ってきたので引き返し、クルマで出直し。今日は一念発起、暑い中を久々に遠出の散歩を決行! 最近は体調不良のせいもあるが散歩が激減している。T子(妹)は元気に毎日出かけるので感心していて、以前とは逆にこっちが叱咤されているようだ。取りあえず平安通りまで行こうとふれあい橋を渡る。橋の上から庄内川の岸で炎天下上半身裸で釣りをしているツルツル頭のオジサンを見た。日よけも何もない。暑いはずなのにと心配するやら感心するやら。
庄内用水に沿って歩く。途中、若いお父さんとシャボン玉を吹いているかわいい女の子に出会う。満面の笑みで近寄ってきてシャボン玉を吹き、何やら話しかけてくれたのだが、よく聞こえなかった。わあ、きれいだねと応えると両手でばいばあいと手を振ってくれた。カメラに収めたいが今のご時勢はそれもできない。上飯田に出てそこから平安通りへ。まだ歩けそうなので大曽根方面に向かう。蒸し暑い中、日陰を拾いながら名鉄瀬戸線の高架に出て一息つく。途中久しぶりに犬のスギちゃんに会う。元気そうで安心した。

さて、瀬戸線の高架を気持ちよく歩いて「名鉄清水」に着いたら次のバスまで10分ほどある。おじさんが一人バス停の待ち椅子に座っている。じっとしているよりはと思って高架下をもうちょっと歩いてみた。適当にUターンして戻るとき目先の41号線を右から左に市バスが通っていくのが見えた。時計を見るとまだ5分以上もある。「うそだろ!」と思ったが、バス停のおじさんはもういない。前のが遅かったのか次のが早く来たのかもわからない。時刻表があてにならない。ひょっとして(今は盆休みなので)休日ダイヤかと思ったがそうでもない。腹が立つより自分のマヌケさがおかしかった。
帰ってから一寝入り。S子(妻)が2時ごろレジの仕事から帰ってきたので大急ぎで久しぶりに「松禄庵」の蕎麦を食べにいく。いつもの天ざるそばを食べて二人ともご機嫌。ここの蕎麦はほんとうにうまい。常連さんも多く、いつも昼時は満員である。近所のコインパーキングも満員が多い。まさか松禄庵だけのせいではないと思うが。(^ ^;
2014年08月05日(火) ヒロシマ前夜に
明日は広島被爆69周年の祈念日。毎年のように行かなくてはと思いながら暑さに気後れして、まだ一度も行っていない。20歳のころ、大江健三郎の「ヒロシマ・ノート」を読んで以来、この気持ちが続いている。もういい加減に行かないと体が持たない。ヒロシマの本では、他に井上靖の「城砦」が強い印象を持った。もう一度読みたい本だ。引っ越しで文庫本を処分してしまった。できたら同じ文庫で読みたいのだが、BOOKOFFでなかなか見つからない。AMAZONで探せば一発だが、なぜかそうしない。この辺、妙にこだわっている。



昭和ブームというか、各地の民俗資料館で昭和時代の文物を蒐集しているようだが、これは一過性のものではないと思う。我々の世代(昭和30年代の子供)だけではなく、もっと若い世代でも興味があるようだ。彼らから見れば昭和は前近代なのだろう。テレビもクルマも何でも一応あるのだが、呼び名と機能は同じでも今とは全く違うシロモノで、隔世の感を味わえるからか。われわれは単純に懐かしいだけなのだが…。
ヒロシマ前夜などと題しながら、何の関係もないことを書いてしまった。すみません…
2014年08月01日(金) いろいろな意味で…
4ヶ月ぶりの登場。やっとガロア理論の小論文を書き上げた。今、このHPにアップした。「ガロア理論の初等的解題」というのがそれである。ほとんど毎日のように取り組んで、我ながら最近にない打ち込みようであった.出来映えはともかく、これでガロア理論に対して一区切りをつけることにする。次はいよいよ「類体論」である。これも数年を要する取り組みになると思うが、まるでそれを支援(?)するように会社を退社することになった。
昨日、専務に呼ばれて行ってみると、「あまりいい話ではないんだが」と切り出され、8月末で退社するように言われた。月末ということで、ひと月の猶予で身の振り方を考えろという意味なのだろう。
確かにクビを言い渡されていい気はしないが、どこかにそれを待っていたようなところがある。類体論もそうだが、今まで何十年ゆっくりと過ごすということがなかったこともその理由である。いつかはそういう時をまとまって持ちたいというのが本音だ。しかし生活のことがあるので収入が途絶えるのはとても不安である。わずかな、それも年々減らされていくような年金(K泉の野郎…怨)では「ゆっくりと過ごす」など夢のような話である。
 わが居住団地の自由猫(うちのネコではない)
わが居住団地の自由猫(うちのネコではない)
それでもいつかは働けなくなる時が来る。仕事と生活と夢と現実と…若いときからずっと繰り返してきた心の葛藤がまた始まる。今月はいろいろな意味で重要な月になりそうだ。もうすぐお盆休みもある.実質残り2週間働けば、今度は有り余るような余裕とともに生活の不安が始まる。あまり起伏のなかった人生であるが、少しは「年の功」のようなものが活かされないかと儚い期待を抱く月の初めである。
2014年04月05日(土 ) 桜
今年の桜は天候の不順と曜日の巡り合わせが悪くて今日あたりはもう花吹雪が始まっていた。それでもまだこのとおり見事な咲きっぷりであった。2014年03月31日(月) Gショック!
もうすぐ4月になってしまうので急いで書いておくが(何で?)、今月の8日にまたしてもG腰になってしまった。しかも前回昨年7月13日のときと同じ土曜日だった。何か法則でもあるのだろうか。初めの3日間がとてもつらい。今回も会社を1週間休んでしまった。その1週間前、3月2日にMacBook Airを買ってしまった(^^; 前回のこの欄で「購入予告」のような書き方をしていたが、あのときもうすでに決心していたのだ。名目は...正直にいえば自分もMacが欲しくなったのである。Gショックのおかげで(!?)ベッドで好きなだけMacBookをいじることができたし、恒例により溜まった録画も片付けた。。14日に半日だけ出社し、17日からフルタイムで復帰した。しかししばらくはクルマと自転車でし、徒歩通勤を見合わせていた。
 竜巻!(3/31 16:10 名古屋市北区味鋺から西の空。クリックで拡大可)
竜巻!(3/31 16:10 名古屋市北区味鋺から西の空。クリックで拡大可)
ちなみに(別にちなんではいないか)、この日のブログは覚えたてのMacで「mi」と「FileZilla」を使ってアップした。我ながら小さな記念日となった。
2014年02月13日(木) iPad Airを購入!
来月の3日はS子(妻)の誕生日で、毎年何かをプレゼントしなくてはならない(^^;。で、時には策を弄して自分の欲しいものをあたかも贈り物にかこつけて購入するという手段を使うことがあるm(_ _)m。今年は久しぶりにその手を使ってiPad Airを買った。これまでS子が使ってきたNECの中古ノートパソコンがさすがに古くなり(WindowsVISTAである)、スマホ携帯とパソコンとどっちがいいと聞くと、スマホは操作が難しいからパソコンかなというので、ではiPadにしようということにしたのだ。
iPadは以前から気になっていた機種である。Appleという会社にはこれまでずっと興味を持っていたが、ハードが高価であることや仕事にはWindowsでなくてはならないことなどで中々購入には踏み切れなかったのだが、自分の携帯をiPhoneにしたことがきっかけでとうとう買う気になった。
 今年のプレゼントはこれ!(剛力彩芽ちゃん風に(^^;) ¥51,800
今年のプレゼントはこれ!(剛力彩芽ちゃん風に(^^;) ¥51,800
これまで使ってきたケータイはAndroid(TOSHIBA REGZA au IS04)だったのだが、ハードの条件からかバージョンは2.2.2止まりでそれ以上は上げられなかった。世間ではAndroid Ver4がどうのといい始めていたので、「これは限界だな」と思って次期機種を何となく探していてこんな結果になったのだ。渡りに船というのかもしれない。
その乗った船がAppleだったことはもちろん承知の上だ。iPhoneも5まで来るとアイテムとしてはほとんど完成の域に達しているといってよい。それを手にしたのだからもうiPadやMac Bookに進むのは一本道だろう。次は本当にMacBook Airを自分へのプレゼントとして買うかも知れない(名目は特にないが・・・(^^;)
2014年01月28日(火) 稲沢市荻須高徳記念美術館にて
26日の日曜日に稲沢市の「荻須高徳記念美術館」に行ってきた。


半世紀以上前の、フランスという外国の、生活観あふれる異国情緒に感動したのだと思う。これまで外国生活にあこがれるというようなことはまったくなかった自分にこういう気持ちがあることに驚いた。これは荻須の絵でも同じで、彼の絵が好きな理由がまったく同じものだとはっきり言えるのだ。例えばこの美術館で一番気に入った絵はこの「オー・ヴォン・ヴィヴァン」というレストランの絵だ。
 この絵が表紙になった画集を受付で購入した(¥1,700)、その写真です。
この絵が表紙になった画集を受付で購入した(¥1,700)、その写真です。
2014年01月16日(木) iPhoneの顛末
以下、iPhoneについての顛末。結局あれからずっとダメで、またぞろ予約を取って名古屋・栄のApple Storeに行ってみた。14日の午後しか予約できなかったので会社を午前中で切り上げる。ぴったりの時間に店に到着。2階に上がってiPadを手に受付のような仕事をしている若い人に予約の件を話すと「お呼びするまでお待ちください」とのこと。先日書いたように椅子もない店内をぶらぶらして待つ。例によってすごい人。20分くらい待たされてやっと白ぶちの眼鏡を掛けたスタッフに名前を呼ばれた。カウンタのようなテーブルに寄りかかってわけを話す。いろいろいじっているとまたしても声が聞こえるようになった。スタッフに「どうやったんですか?」と聞くと「いや、特に何をしたわけでもないのですが」とのこと。やはり時々直るのだ。
とても不安ではあったがとりあえず帰ることにする。店を出てスクランブル交差点の信号待ちをしながら天気予報を聞いてみる。ちゃんと聞こえる。ホントに直ったかも・・・。ところが交差点を渡って松坂屋の前を歩きながら自宅にかけて見ると呼び出し音がしない。例によって接続されて時間の経過が表示されるが無音である。やっぱりダメだと店に引き返す。また受付の若い人に事情を話す。またしばらく待たされる。やがてさっきと同じスタッフが来て故障を確認し、「わかりました。交換させていただきます」ということになった。やれうれしや、それが一番いいのだ。
昨年末に書いたように本当にiPhoneが死んでしまった。
各種データは自分でiTunesから復元するということで、店で旧器のデータ消去を自分で確認し、スタッフの差し出したiPhoneにひとさし指で手書きのサインをした。Appleの受領書なのだろう。紙による手続きなどは一切ない。いかにもAppleである。いずれすべての店がこうなるだろうと思わせるが、日本の店舗がこうなるには時間がかかるだろう。去年の春わが愛車の購入で何枚の紙に住所や名前を書いたことか。
新しいiPhoneをもらって店を出た。気分は上々である。スタッフの対応もよかった。ひょっとして故障器と同じものがなくてiPhone5sになるかもと一瞬期待したが、同型器だった(*_*)、当たり前か。ただ、iOSが6のままだったので、帰宅してからの復元がけっこうたいへんだった。深夜までかかったが、写真も音楽もEvernoteも、ダウンロードしたアプリも全部復元できた。ただ肝心の連絡先だけが復元できなかった!(*_*; 原因はわからない。何度もやり直してみたがダメだった。
連絡先の件数は多くない方なので、自分としては他のデータが元通りというだけで十分だったが、人によっては致命傷となる人も多いだろう。くれぐれも連絡先は二重三重のバックアップが大事である。それとバックアップの中身が目に見えるといいのだが、そういうことはあまりAppleはやってくれないらしい。
結局あきらめて連絡先は手で入力しなおした。1時間くらいですっかり元通りになった。めでたし、めでたし。(^v^
2014年01月06日(月) おめでとうございます。iPhone5も復活!・・・と思いきや
新年おめでとうございます。昨年最後の日記をiPhone5の故障記事で締めくくったが、正月3日さっそくAppleストア名古屋栄のジーニアスバーとやらをWEBから予約した。6日午後というのが直近の予約可能時間で、幸い仕事は6日まで休みにしてあったので予約を取ることができた。
ところが、6日の朝試しに(故障以来ずっと毎日試していたが)電話を掛けてみるとちゃんとつながるではないか!いや、つながることはずっとつながっていたのだが、会話ができなかったのができるようになったのだ。時報を聞いたり自宅の固定電話で掛けたり掛けられたりしてみた。すべてOK。いったい何だったのか、わけがわからない。<(*_*)m とりあえず予約は取り消す。
ということで、とりあえず、新年恒例の真澄田神社ショット。

2日の真澄田神社でもそうだったが、特に警備員が規制しているでもないのに、参拝者が何列かきちんと行列してお参りしているのがどうも違和感がある。こっちの信心が足りないせいかも知れない。
9連休という長い休暇だったが、充実していた。特にヒマを見ては書いていたガロア論文が少しずつ進んでいくのが嬉しかった。夢うつつのなかで考えていると、よく「そーだったのか!」という思いをする。覚めてみると大したことはないのだが、それでも気分のいいものだ。現在およそ6〜7割くらいできたかなという感じ。春までには完成させてここに載せたい。
さて、以下は夜になってからの記述。
「iPhone5も復活」と銘打ってわけもわからないまま直ってしまったiPhoneだが、今日はせっかく休暇までとってあったのでジーニアスバーの予約は取り消したものの栄のアップルショップへT子(妹)と行ってみた。世間はもう正月の休みも終わったはずだが、すごい人だった。いかにもアップルらしいハイセンスでエレガントな、悪く言うととっつきにくい硬質な店舗だ。アップルの商品をアップルの商品でプレゼンしているのでパンフのような紙類はほとんどない。イスもない。店員もいかにもスキルの高そうな(生意気そうな?)応対が傍からも目に付いた。われわれのような老人はあまりお世話にはなりたくないと思った。
そんなことはどうでもいい。実はこの店を出てから一緒に言ったT子に試しにiPhoneで電話してみると、なんと直っていないではないか。またしてもつながるのに無音になってしまった。「えぇ〜っ!!!!!」と思わず声が出てしまった。
こんなことなら予約を取り消さず、そのまま店で相談すればよかったのだとつくづく思った。いや、予約なんかどうでもいいからすぐ店に引き返して「実は故障していたが何故か直ってしまい、喜んでいたらしばらくしてまた・・・」と説明すればよかったのか? 予約がないときはケンモホロロに応対されるかもという恐怖(?)から足が遠のいてしまった気がする。もし店員の応対などでアップルを嫌いになってしまったら自分の気性からしてすぐ他のスマホに替えてしまうだろうと思う。これまでにも他のことでそんなことがあったから想像がつく。お願いだからこういう高価な精密機器は故障しないで欲しいものだ。
・・・今、夜の10時半。iPhoneはまた直っている・・・。いったい何なのだろう・・・。
2013年12月28日(土 ) iPhone5の死
3ヶ月ぶりの日記。早くも年末・・・。この間、ずっと(でもないか)ガロアの論文を書いていた。「ガロア理論の初等的解題」というのである。この日記でも時々ガロアに触れて、群や体について述べたりしていた。それが本格化したのだ。書いていて7〜8割出来たかと思うと、次はあれ、その次はこれという具合で常に新たな課題が出てきて完成が先延ばしになる。論文とはそういうものかと思う。
 クリスマスにS子(妻)が買ってきたあっちゃんワインPriKatz。中々おいしかった!
クリスマスにS子(妻)が買ってきたあっちゃんワインPriKatz。中々おいしかった!
死んだというのは、iPhone5が「電話」であるという前提で、電話として使えなくなってしまったということ。あとの機能はすべて正常。着信はするのだが、電話に出てもまったく無音なのである。掛けてきた人に会って聞いてみると、何度掛けても声がしないので別の携帯で掛けてみたり、電話会社に問い合わせたりしてくれたそうだ。こっちから掛けたのも向こうに着信はするようでどうも課金もされているようだ。でも会話はできないので自宅の固定電話やS子(妻)やT子(妹)の携帯に掛けたり、天気予報や時刻などずいぶん無駄金を使って試行してみた。この日夜中までいろいろな情報を得ながら出来る限りのことはやってみたが、結論的にはどうも自分のiPhone5の故障ということになった。しかも年末のことでAppleストアの「ジーニアスバー」とかも正月3日まで予約できない状態。この年末年始は携帯電話は使えないで過ごすことになった。
ただそれ以外の、メールやネットや、音楽再生、カメラ、USBでのファイル移動などはすべて正常なので、ま、いいかと腹をくくった。もともとiPhone5を電話として使うことは少ない方だ。仕事はしているが、緊急の用件を電話で授受することはほとんどなく、たいていメールで済ませているので実害はたいしてない。ある意味理想的(?)ではある。いっそこの際携帯電話なしで生活できないか試してみようか。メールがあれば(つまりインターネットがあれば)他者との通信は十分ではないか。緊急のときは人の携帯をアテにしよう(^^;。
2013年09月18日(水) 2年前のこと
台風18号は京都、福井などに大変な被害を出して去った。「大雨特別警報」などという新用語も生まれ、われわれはこれから一年の大半を大雨・洪水・突風・竜巻・暴風・雷・高潮、それに噴火などにおびえながら暮らさなくてはならなくなった。一刻一刻雨が激しくなるとき国土交通省のHPで「川の防災情報」を見ていた。名古屋はともかく三重県のいくつかの河川はいわゆる警戒水位ぎりぎりまで増水しているのがわかった。おととしの大雨のときの恐怖が甦ってきた。2年前、ちょうど時期も今頃だった。いつものように出社していたが、だんだん雨がひどくなってきてとうとう会社のすぐそばを流れる八田川の水が堤防を越えて溢れ出し、社内にも浸水し始めた。間一髪でサーバなどを2階に避難させたが、他になすすべもなく社員みんな退社した。あとで聞くと、会社の駐車場も膝まで水が来ていて、転んだため溺れかけた人もいたそうである。私は八田川の堤防の上をクルマで帰宅したが、もう堤防すれすれまで増水しており、これまで経験したことのない恐怖を感じた。八田川は水分橋で庄内川に合流するのだが、その庄内川が恐ろしいほどの増水と濁流で、もう氾濫は時間の問題かと思った。家に帰ってすぐ、テレビや広報車でこの地域にも「避難指示」が出たのを知った。ここへ転居して来て初めてである。団地住まいなので階上へ逃げれば済むとも考えたが、避難すること事態を体験することにもなると思い、家族3人で指示された避難所へクルマで行くことにした。猫2匹も連れて行きたかったが、いろいろ考えあきらめた。水が来たら箪笥の上にでも逃げてくれと無責任にも置いていくことにした。まだ心のどこかに余裕のようなものがあった。
避難の途中、地蔵川の橋の上の両側にはクルマがぎっしり駐車されていた。この川の橋はいわゆる太鼓橋型で真ん中が高くなっているので洪水からクルマを守ろうとしたのか。2000年の東海豪雨のときには団地の駐車場にあった車も多くが水にやられたそうである。ただ、ウソかホントか知らないが、橋の上の車はこのあとすぐに警察の取締り(駐禁)にあったといううわさを聞いた。
避難所は名古屋市立北高校を指定されていた。学校に着くと校門で市の職員のような人から駐車場を教えてもらい、中庭のようなところへ駐車した。体育館までは暗い慣れない通路で遠かった。
 北高体育館避難所にて(2011年9月20日撮影)
北高体育館避難所にて(2011年9月20日撮影)
帰りには雨も止んでおり、街中はすっかり落ち伝いていた。帰宅したのは11時ごろだった。水はまったく来なかった。
2013年09月15日(日 ) iPhone5について
iPhone5との苦闘が続いている。本体を手に取ろうとするときに薄いうえに滑る(薄いのは長所なんだが...)。ストラップが付けられないので胸ポケットに留められない。SMSとかMMSとかメールの設定が自分でできない(^^;、などなど。
一方、びっくり感激したのはiTunesの同期を取ってPC本体に入っている数ギガの音楽ライブラリがiPhoneで聴けるようになったこと。うまくいけばこのままクルマに持ち込んでFMトランスミッターで聴けるかもしれない。
そして先日、アマゾンで買ったサンワサプライのiPhoneカバー(¥1,008)が届き、念願のストラップも付いた。このカバーは手触りがちょっとしっとりしていて滑り止めにもなっている。これでいきなり弱点を2つ克服した。
ところで自分としては、携帯電話のストラップなどはまったく当たり前に必要なものだと思っていたのだが、世の中なかなかどうして、iPhoneにストラップは必要ないという考えもあるのだと知った。アップルのS.ジョブズ氏の開発思想に基づくとの説もある。彼が来日時に見たという日本女子のケータイに(が?)付いていたストラップの塊に嫌悪したなどという伝説も楽しい。
また、Google MapsやGoogle Earth もダウンロードしてノートPC並みに使えるようになったのも嬉しい。これまでは一応ソフトはあっても使えなかった。
次に面白いのは、「Siri」という組み込みソフト。言葉で命令してちょっとしたことをiPhoneにやらせることができる。電話、メールはもちろんお天気、挨拶、簡単な日常会話もできる。
そしてついにかねてからの念願であった、ベートーベンの「ピアノソナタ『テンペスト』第3楽章」の冒頭を着メロにすることに成功した! これは前の携帯の時から挑戦していたのだが中々うまくいかなかった。できたのはもちろんネットの情報のおかげである(http://iphone.f-tools.net/QandA/Chakumero-Setting.html#TOP)。こうした情報が多いのもiPhoneのメリットだ。
2013年09月10日(火) クルマのキーとスマホの話
先日の集中豪雨の日、家人を迎えに行った時にはなんともなかったのに、翌日クルマに乗ろうとしてキーの異常に気が付いた。いわゆるリモコンキーで、キーの柄の部分がプラスチックのカバーになっていてその中にリモコンの電波を送る本体があるのだが、それがごっそりなくなっていた。ドア用とトランク用の2個の押しボタンがあるところがぽっかり穴になっていて、中の空洞がよく見えた。キーをよく見ると小さなビスでカバーを止めてあるが、にもかかわらずカバーがパカッと開いてしまう。しかしまたすぐパチンと閉じることもできる。つまり何かの拍子にカバーが開いて中身がどこかに落ちてしまい、また閉じて気付かなかったのだ。ポケットやクルマの中など心当たりを探してみたが中身はどこにも見つからなかった。キーそのものは無事なので乗降や運転には差し支えはないが、リモコンに慣れているので不便である。さっそくクルマの購入先に電話してみると大体1万数千円かかるという。ちょっと(かなり!)高いが仕方がないので修理を頼んだ。


さて、ここからはiPhoneの話である。
クルマを購入したメーカーはいわゆるNTP(名古屋トヨペット)なのだが、NTPは最近「pipit」という携帯電話を扱う店もやっていて、キーのことで応対してくれたNTPのセールスの人がpipitを薦め(営業成績につながるようだ)、途中は省くが結局スマホをiPhone5に替えることになった。上のキーの写真はそのiPhoneで撮って初めてここに載せたものになる(右のiPhone5の写真はデジカメで撮影・壁紙はもちろんあてね)。
特に念願だったというわけではないが、これまでのREGZAの2年縛りが明けて、さてどうしようかと思っていた矢先だったこともあり、渡りに船で決めてしまった。いよいよ自分もAppleファミリーの一員だ。
pipitはヒマそうで、au携帯を購入する人にはオススメかもしれない。土日にauショップで買おうものなら1〜2時間は待たされるだろう。店員も親切でゆっくり時間をかけて説明してくれた。クルマのキーのカバー交換とpipitの応対の良さがiPhone購入の決めてになったようだ。
iPhoneはまだ使い込んでいないので批評はいずれということで。しかし、ストラップの穴がないとはなあ・・・
2013年09月08日(日 ) 祝!東京招致決定・・・?
5日付けのここで「まだ咳が止まらない」と書いた翌日から咳が収まってきた。嬉しい。もうこれからは風邪を引かないこと。季節の変わり目には特に注意することを肝に銘じたい。
朝から2020年オリンピック東京招致決定のニュースで喧(カマビス)しい。安部首相のほっとした嬉しそうな顔が何度もテレビに映っている。そういう自分でも今朝早朝に目が覚めたとき、「どこになったんだろう」とすぐテレビを点けて画面の右上に「東京招致決定!」という文字を確認してまた寝てしまった。そのときの気持ちは「ふ〜ん、やっぱりか」であった…。前回の東京オリンピックが1964年だから56年ぶりとなる。ハレー彗星ほどではないがやはり稀有のことなのだろう。いつだったか「名古屋オリンピック」が開催決定間際まで行きながらソウルに敗れたことがあった。あのときと何が違うのか。
一番大きな違いは東日本大震災の経験である。政府や安部晋三首相は復興日本を世界にアピールしたいなどといっているが、まだ日本は明らかに復興していない。だいいち、福島原発事故が収束していない状態で「復興」の2文字は使えないだろう。経済成長にも「明らかにプラス」だとも言っているが、プラスになるのは大企業にとってだけである。国民はオリンピックのためと称して様々な我慢を強いられる。8〜10%の消費税をを払わさせられ、社会福祉は大企業の「公共投資」のために削減されるだろう。こうした懸念が消えないので「ふ〜ん、やっぱりか」程度の関心しか持てないのである。
 柳ヶ瀬の猫
柳ヶ瀬の猫
2013年09月05日(木) 打ち水の提唱
昨日の大雨は2000年の「東海集中豪雨」を思い出させた。昨日は夏風邪もあって3時に早退して、おかげで一滴も濡れることなく帰宅できた。しかし今にも降り出しそうな空模様で心配していたところ、案の定4時ごろからすごい降りになった。作業所に行っているT子(妹)が足止めを食っていて、迎えにくるように連絡があったのでクルマで出かけた。乗車するまでにひとしきり濡れた。あまりの降りにワイパーも利かない。半分勘で走るようにして作業所に到着。降りて先生たちに挨拶し妹を呼ぶと、玄関先で「傘がない」といっている。誰か間違えて持っていったようで、「まあいいからナシで行こう」と傘無しで乗車。またひとしきり濡れる。やっとのことで帰宅するが駐車場から家までにまた濡れる。結局二人でびしょ濡れ。無事に帰れたことでよしとするが、雨はそれから1時間も降ったか。
5時半ころ、「広報なごや」の有線放送で「避難勧告準備」情報が出た。間延びした放送で緊急性が感じられない。まだ「準備」段階だからいいかと様子を見ているとだんだん雨も落ち着いてきた。あとから見たニュースではこのころ100ミリ/時間以上の雨が降っていたようだ。道路の冠水、地下駐車場の埋没、交通手段のマヒ・・・最近は日常茶飯事になってきた。今年の夏は異常気象と決定したとの事だが(http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/longfcst/extreme_japan/monitor/extreme20130902.pdf)、これがこれからの日本の普通の夏になるのではないか。
この異常気象の原因が地球温暖化にあることはもう議論の余地はない。議論をしている場合ではない。対策は待ったなしといわれて久しいが、この国の政府にとっては蛙のツラになんとやらである。暑夏に対して何の政策も持たず、消費税増税とTPPと原発再稼動に忙しい。事態は緊急である。私はいわゆるヒートアイランド対策として日本中の家庭と会社が一日の一番暑いときにエアコンを停め、建物の回りに打ち水をするのがいいと思っているが、これも風呂の水とか貯め水などではなくてはっきり水道の水でもいいと思っている。一部では実施されて入るもののパフォーマンスに過ぎない。国民が自分たちで何かをするという意味もあり、何もしない政府へのデモンストレーションにもなる。少なくともその効果を試してみる必要はあると思う。
——まだ咳が止まらない。今年はこの症状に何度も悩まされている。どうも咳喘息のようだ。それならそれでしかたがないが、これが原因で死ぬのもイヤだから何とかしようとは思う。とりあえず咳止めを飲んでいるが例によって効き目がない。素人療法だから無理もないが、これ以上すべきことがない。それほど苦しいものではないが回りに迷惑である。特に職場では同僚たちに迷惑をかけている。みんな「ゆっくり休んだら?」といってくれるが、休むほどでもないのだ。 2013年08月31日(土 ) 夏風邪
先週末ちょっと涼しくなった夜、いつもの調子で裸に近い格好で寝てしまい、扇風機もタイマーを忘れ朝まで回っていた。翌早朝から頭痛がしてだるくなり、多少熱っぽくもあった。それでも動けないことはないので頭痛薬だけ飲んで普段通りにしていた。しかし体調は戻らず、その翌日には発熱してきた。日曜にもかかわらず(?)おとなしく寝ていたが、月曜には咳が始まった。出社はしたものの続けざまの咳に苦しめられ、同僚たちから迷惑そうな心配顔でお見舞いを受けた。その日は午前中で退社し、以後3日連続で早退した。今日で1週間になるがまだ咳が収まらない。今、咳止めを買ってきて飲んだところ。今年2月にもひどい風邪を引いたことをここに書いているが、夏風邪は本当に久しぶりだ。
 天人午睡...
天人午睡...
それはそれとして、早退が多かったので時間ができ、おかげでまたHD録画ビデオの消化が進んだ。「風速40米」「俺たちに明日はない」「めまい」「青い山脈(吉永小百合様主演)」「あなたへ」「ノッティングヒルの恋人」「かくて神風は吹く」「梟の城(高千穂ひづる出演)」「折鶴駕籠」、他に「刑事コロンボ」数本など。お互い何の脈絡もないが、TV放映されている映画は膨大なもので、それとなく録画選択に嗜好が反映されているようである。
「あまちゃん」と再放送の「てっぱん」もかかさない。「あまちゃん」は始め大震災を思い出させるので敬遠していたが、主役の能年玲奈にハマって、ずっと見るようになった。「てっぱん」も主役の瀧本美織が好きなので見ている。「妻は、くの一」も第1回以外を見た(このドラマは第1回を見なくては意味がないが)。
とにかく早く風邪が治ってほしい。
2013年08月15日(木) 柳ケ瀬
夏季休暇に入って5日目の昨日14日、岐阜の柳ケ瀬に行ってみた。多少覚悟はしていたが、案の定国道302号線から国道22号線に入るところで渋滞していた。ここを抜けるだけで30分くらいかかった。そもそも岐阜へ行くのにここを通る方が間違いなのか。とはいえ、あとはだいたい渋滞なし。
50年前、中学を卒業して就職した先が岐阜市内の中小企業で、1年ほど住み込みで働いていたことがあった。会社での会話の中によく「柳ケ瀬」が出てきて、大人の遊び場でちょっといかがわしいところというイメージが作られたが、行った記憶はない。その後名古屋に帰ってしばらくしたころ「柳ケ瀬ブルース」が流行って自分が持っていたイメージどおりの処だなと思ったことがある。
あのころの自分を今でも何かと引きずっているのは、やはり十代の多感な青春時代の思い出ということなのかもしれない。初めて小説らしいものが書けて同人誌の活字になったのもこのときの話だったし、クルマの免許を取って最初に遠出した場所もこの会社の寮だった。
——ここまでを15日の朝書いてからお昼を食べに出かけようとクルマに乗ったら、カーラジオのNHK-FMで12:30からの「旅ラジふるさとうた巡り 東海・北陸編」が始まり、1曲目がなんと「柳ケ瀬ブルース」だった。偶然も面白いが、「東海・北陸」を代表する歌謡曲がこの曲なんだなと思ったことよ!
さて、到着して適当にコインパーキングに駐車し、徘徊開始。初めはいわゆるシャッター通りでちょっとさびしい感じがしたが、高島屋辺りからはとてもにぎやかになった。ドンキホーテもある。昔バスで通って目なじみになっていた「徹明町」のバス停もあった(名鉄バスだったけど)。
 (最近熊本県のゆるキャラにハマっている S子(妻))
(最近熊本県のゆるキャラにハマっている S子(妻))

国道256号線に出たところで「ふるほん書店(自由書房)」という本屋を見つけ立ち寄る。1階は購入した古本を煩雑に置いてあるだけに見えたが、2階は充実していて特に文学作品が多くとても面白かった。「武藏野」(國木田獨歩著)の復刻版を買った(¥900)。これは好きな本である(2006年10月26日参照)。マスクをしていた女性店員がやさしく応対してくれた。何となく美人そうに思えてテレビドラマの「ビブリア古書堂の事件手帖」を思い出した。
もう一軒気になる店を発見。このふるほん書店の2軒隣にHush Pappiesがあった! 残念ながら定休日だったが、帰ってからgoogle mapのストリートビューで確認するとちゃんとお店が開いている。私はこのブランドが好きで、このPCのスクリーンセーバーにもおなじみのイヌが活躍している。ショッピングモールなどでは行きつけているが、こういう通り沿いで一軒構えた店舗はまだ見たことがなかったのだ。
こうしてアーケードのある通りのほんの一部を歩いただけだったが(とにかく暑かった!)、いわゆる昭和の香りぷんぷんで、懐かしさは十分味わえた。いろんな意味できっとまた来るぞと駐車場に戻った。
2013年08月11日(日 ) 2013年夏季休暇
今年の夏季休暇は8月10日〜18日になった。土日があるので実質は12〜16日の5日間であるが、昔のことを思うと長い。行楽として行きたいところはたくさんあるが、この暑さと時期的な混雑がいやで、とりあえずたまったHDD録画を片付けながら、腰の具合と相談しながらこのHPをいじっている。最近会社でもHPを作ったりしてCSS(Cascading Style Sheet)というものを知った。名前しか知らなかったがおもしろそうなので自分のHPでも使ってみたくなった。
この欄の日付と題を、CSSを使う前(旧) と後(新)でHTML文で比較すると、
(旧) <font size=+1 color="green"><b><a name="20130811"> 2013年08月11日(日) </a></span><span size=+1> 2013年夏季休暇 </b></font><p> (新) <h3><a name="20130811"> 2013年08月11日(<b>日</b>) 2013年夏季休暇</h3>と、ずいぶん短くなった。そしてこの(新)の<h3>に対応するCSSの文が、
h3{
font-size: large; /*フォントの大きさ/*
font-weight: bold; /* 文字を太字に */
margin: 0; /* マージン */
padding-bottom: 0.7em; /* 底辺のパディング(内側の余白) */
color: black; /* 文字の色 */
background-color: white; /* 背景色 */
}
h3 a{color: green;} /* h3の中で<a>を使用するときの色 */
h3 strong{color: red;} /* h3の中で<strong>を使用するときの色 */
である。要するにHTML本文で指定している定型的要素(h3)のプロパティ(color等)をCSSで予め指定しておき、ブラウザはHTMLファイルを起動する時にCSS(文またはファイル)を読み込んで表示するのだ。新しい技術とかアイデアを実感すると、いつでもそうだがとても感動する。このCSSもそうである。 そもそもHTML言語のタグがすばらしい! 昔勉強したTeX(数式をパソコン画面に表示する)もタグであった。テキストで書いたものをソフト(TeXやブラウザ)が読んで望みどおりの画面を出してくれる。すばらしい技術である!
2013年08月04日(日 ) 久しぶりの大須
きのうは久しぶりに名鉄清水まで散歩してみた。腰の調子は良かったが暑さに参った。今日はS子(妻)の提案で久しぶりに大須へ行ってみた。家計簿で調べて見ると去年の1月以来だ。毎年盆正月には欠かさなかったが、最近何となく足が遠のいているのは駐車場がないせいだ。
今日は夏祭りということでとても現地での駐車は無理だろうから、黒川のコインパーキングに停め、そこから地下鉄で上前津まで行った。案の定ものすごい人手で、万松寺通りなどは「人混みでごった返す」という定型句がぴったりだった。祭りのイベントにもなっているコスプレ参加者がとても多かった。昼時だったのでいつもの「あした葉」で昼食をと思っていたが、10人くらい並んでいたのであきらめ、そのまま観音様へ向かう。
境内もすごい人。それにつきものの屋台のお店。ライブコンサートもやっている。名物の鳩も今日は地上には降りられないだろう。何とかお参りを済ませてライブをちょっと見た。
この暑さの中でほんとに元気良く踊って歌う若い女子たちに感心した。一番左の子は確かランドセルを背負っていた。これもコスプレか!?
さてお昼だが、結局はさっきは入れなかった「あした葉」にもう一度寄ってみたら、混んではいたものの今度はすぐ順番が来そうだったのでここで待つことにした。ここではいつも店自慢のミニ天丼定食を頼むのだが、S子だけそれを頼み、自分は初めてざるそばを注文し、T子((妹)はころうどんとなった。ざるそばは最近凝っている食べ物である。いろいろ食べ歩いているが、我ながら好みがうるさく、今のところお気に入りの店は1軒しかない。あした葉も気に入ったとは言い難かった。
とにかく暑くてたまらない。昼食後は上前津交差点のコムロードだけちょっと見て早々に引き上げることにした。地下鉄の乗降階段を何度も上ったり降りたりして黒川に着いた。眼が悪いT子にはこの階段が苦痛であり危険である。やはり家族で出かけるのはクルマだけで行けるところでなければいけないかなと思った。車に乗るとホッとし、やはり欲が出て、マックへ行くことにした。それが今日のオチとなった。
2013年07月29日(月) 入院の思い出
まだ腰の調子がよくない。ここまで慣れてくるとどんな状況のときに勃発するかわかるような気がする。もちろん怖いので試してはいないが。毎日コルセットを巻いて出勤している。面倒だが、ちょっとでも無理な姿勢になるとコルセットが邪魔をして気付かせてくれる。幸い職場はデスクワークがほとんどで、一日中エアコンが寒いくらいに効いているので、暑いのは通勤の往復と家で休むときくらいである。
このコルセットは10数年前に椎間板ヘルニアで入院・手術したときに病院で実費で作ったものだ。一人ひとりの体型に合わせて作られており、手術後の起き伏しには必ず巻いていた。2〜3万円したと思う。所々にあったプラスチックの部位はもう完全になくなっているが、通気性のためかメッシュになった部分とちょうど背中に当たる場所の皮の部分と、あとは木綿の丈夫そうな網紐で作られている。体の前で合わせるところはマジックテープで、今でもしっかり繋ぎとめてくれる。年に1〜2回は大小取り混ぜて を起こすのでそのつど手放せない。
できるなら新品に替えたいが、そうするといろいろあって迷うのだ。腰痛のベテランに聞くとすごくいいのがあるそうだが、やはり人それぞれで、自分の気にいったものとなると今はこれである。
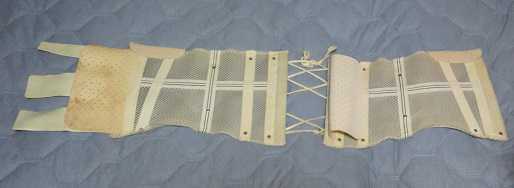
手術後の10日間は起き上がれなくてベッドで壁ばかりみて過ごした。眠れない夜中に壁のカレンダーの中の木がゆらゆら動いて見えたり、深夜唯一の退屈しのぎだった小型ラジオの液晶画面に、あるはずのないアニメーションが延々と見えたりした。また平衡感覚がおかしくなってベッドが垂直に立っている気がしてずり落ちないようにベッドの端をしっかり掴んでいたりした。
起き上がれるようになってから病院内を歩いてみると、足腰の筋力がすっかり落ちていて背伸びができなくなっていた。完全に戻ったのは退院し2ヶ月くらい経ったころだ。このときのリハビリを兼ねた散歩が現在まで続いているといっていい。しかし散歩やウォーキングをしていれば腰痛やG腰にならないわけではないことはその後の経験が示している。
2013年07月22日(月) G腰
例によってまた2か月ほど更新できなかった。主な理由は仕事である。気持ちがすっかり仕事に向いていて自分のブログにかまけていられなかった。ところがここ1週間ほどG腰(ぎっくり腰のこと)で動けなったことが幸い(?)して、またブログに眼が向くようになった。G腰は大体年に1〜2回やっている。13日の土曜日に、遅ればせながら夏向きに部屋の模様替えをしていて襲われた。今回はかなりひどくマグニチュード6クラスで、3日間は寝たっきりだった。10数年ほど前に椎間板ヘルニアを患ったが、そのときの痛さとはまた違って、腰の奥の方で内臓が何かに圧迫されるような、それでいて神経的な独特の痛みだ。悲鳴は「あ〜っ」ではなく「うっ」である。中腰のときに不意を襲ってくるのだ。4日目ごろから小康状態になって少し動けるようになったが、それでも立ち居振る舞いはとても不自由になる。
いつもそうだが、体調を崩して休んだりすると読書が進む。勉強が進む。いいことかどうかわからないが、何もしないよりはいい。ついでに溜まっていた録画ビデオも消化する。
今回は「天才ガロアの発想力」(小島寛之著・技術評論社2010年10月発行)を読んだ。何とかして一般の(数学専門家ではない)人たちにガロアの独創性を知ってもらおうという、著者の努力が伺われる本だ。少なくとも僕には伝わった。そのことをちょっと著者に伝えたいと思ったくらいだ。
ガロアの天才性は時代をはるかに超越しており、すでに200年もなろうという今日でさえ古くなっていない。おおげさに言えば、彼以後の数学(代数学に限らず)は、彼のその発想の上に敷衍されたものに過ぎない。その天才性をひとことで言うと「対象(彼の場合は体)を「群」として捉えることで、その(体の)本質をえぐりだす」ことである。あるいは前述の本の叙述に沿って言うと「群と体の間をいったりきたりすることで、数学的素性を明らかにする」(p26)ということである。
群は「gun」と読み、英語ではgroupであり、どちらもGが頭文字である。数学の記述ではよくGで表わされる。そしてわが生涯の持病もまたG腰である・・・。
2013年05月16日(木) 続・地図の読めない男
12日の話には続きがある。花フェスタ記念公園を出られなくなったことだ。

真夏のような天気の中で、人には聞かず、地図と景色を見比べながら、公園に入ってからの自分の記憶を頼りに東ゲートを探してみた。東ゲートの方向を示す案内板がなかったことと、地図と実際の方角を確認しなかったことなど、迷った理由はいくつかあるが、迷ったことを楽しんでもいたのは確かだ。普段でもかなりの方向音痴で、京都のように道が碁盤状になっていないと方向感覚がわからなくなる。まして上のような地図は自分のいるところさえつかめない。
地図は好きなのだが、それは実用というより人の作ったものを鑑賞する気持ちで見るのだ。実用もするがそのときは地図を作った人が実際の街や道をどう抽象化したかを確かめるのである。美しい地図も観賞用として必要である。上の地図で言うと、自分が迷ったから言うのであるが、これを作った人は実際に使うことより見た目の美しさを優先したように思ってしまう。実用的な地図は美しくてはいけない。
以上、地図の読めない男の繰言である。
2013年05月13日(月) 地図の読めない男
12日、クルマを替えてから最初の長距離ドライブとして岐阜県可児市の花フェスタ記念公園に(一人で)行ってみた。この行程で自分で気になったことを書いておく。この日はまずS子(妻)をスパガーラ(健康センター)で降ろしてからすぐ名古屋高速11号小牧線の堀の内から上がり、そのまま小牧ICで名神に移り西へ向かう・・・つもりが間違えて東へ行ってしまい、仕方なく次の春日井ICで降りて、降りたところが19号線の上り(名古屋方面)だが、これをUターンしてまた東名に乗らなければならない。で、春日井インター西という交差点で右折し、落合公園手前をさらに右折また右折して19号に出る。そして東名をくぐってすぐ高速入口から上がった。
・・・さて、ここまでアトラスの地図を見ながら書いてみて、上の記述が間違っていることに気付いた。まず「名神を西に向かう」つもりでいることが間違い。西へ行ってはいけない。つまり、「間違えて東へ」行ったのはカーナビの導きで正しかったのだ。もっとひどい間違いは小牧ICから実際は東へ走っているのに西へ向かっているつもりでいること、さらに小牧JCTで本当に間違えた。ここから中央道に分岐しなければならなかったのをそのまま東名を走ってしまい、カーナビの指摘で春日井ICで降りたのだった。あとは上の記述の通り。これが本当の自分の運転だった。
すべては無自覚な無責任運転のなせるわざ。こういう運転の仕方をしたのは、カーナビに100%頼っていることに原因がある。カーナビは道を間違えるとすぐに新たなコースを選定し、案内を始めるので、間違えてもあまり気にせず指図に従えばよい。これはとても便利で、いつもお世話になっている機能である。
しかし、上述の間違いは「誰にでもある」通常の間違いではない。これはバカである。方向音痴とか、地図が読めないとかのレベルではなく、クルマに乗る資格のない人間といっていい。恥ずかしいのを通り越して笑ってしまった。
自分のどこかに、カーナビにすべてまかせて何も考えずに目的地に到着できたら何と便利なことかと考えているところがある。近い将来ほんとにそういう交通システムができるかもしれない。すべての道路にセンサーや探知機が付いて一台一台のクルマと瞬時に情報交換をしながら乗客(?)たちを目的地に連れて行くのだ。極端に言うとクルマの中で寝ている間に、あるいは家にいるのと同じように生活しているうちにどこへでもいってしまうのだ。
だからといって今のカーナビにそれを求めるのはやっぱりバカである。現在のクルマは、ドライバーがしっかり自覚を持って距離、経路、時間などを図り、予定通りに目的地に着くように考えて運転しなければならない。それがクルマの魅力でもあるはずだ。
反省することしきりである・・・
2013年04月27日(土 ) G.W.始まる
今日からゴールデンウィークが始まった。あまり実感はないが、それでも今日から4連休なのが嬉しい(本当は5月6日まで10連休なのだが、月次更新の仕事で1日2日が出勤になった)。とりあえず日課(週課)の散歩を兼ねて、いつの間にか失くしたというT子(妹)の帽子を買いに一緒に出かけた。あまり寒くはなかったが、風が強く、いつも渡る庄内川の橋の上は特に強風だった。が、風に紛れてウグイスの声が聞こえてきた。川原に生えている背の高い木に留まっているらしい。「ケキョケキョ・・・」という谷渡りのあとにはっきり「ホーホケキョ」と聞こえた。ウグイスの鳴き声を文字に採るには「ホーホケキョ」か「ほーほけきょ」か「法、法華経」か、どれがいいだろうかなどと考えてしばらく聴いていた。2,3年前にも近くの神社の森で鳴く鮮やかな声を聴いたが、野鳥のウグイスは案外街の中にもいるのだ。
帽子の買い物を済ませて帰宅し、今度は一人で雁道商店街に出かけた(もちろんクルマで)。実は先週日曜日にも出かけたのだが、お目当ての本屋さんが休みで、今日はその敵討ちである。
今度のクルマではまだ高速道路を走っていなかったので、ETCカードのテストとクルマの調子を見るため名古屋高速を走ってみた。カーナビで「雁道商店街」を目的地に「有料優先」でコースを検索すると名古屋高速の堀田ICで下りることになる。それで正解だが、雁道へは堀田ICを降りて少し戻らなければならない。実際にICを下りるとき、カーナビが「大きく右方向です」と案内した。高速を下りてそのままUターンができると初めて知った。
さて、雁道の本屋さんは間口奥行きとも2間ほどの小さなお店で、雑誌や単行本や全集などがあるが、どれも昭和3〜40年代のものしかない。この商店街を訪れたときに「発見」し、気になっていた。店主のおじさんは、自分よりは年長だろうがそんなに上ではないかもしれない。店は趣味でやっているとしか思えない。
15分くらい物色し、率直に言って欲しくてたまらないものはなかったが、せっかく来たのだからと河出書房新社「世界文学全集7・E.A.ポオ、メルヴィル」を買った。本を取り出し財布をまさぐっていたら「200円でいいですよ」とご主人から声を掛けてくれた。いろいろ話を聴きたいのだが、また来ればいいかと思い、店を出た。もう1軒、今度は有田焼の看板が出ている瀬戸物屋さんに入った。最近そば猪口を意識的に買い集めていて、瀬戸物屋には必ず入って一個は買う。奥から奥さんが出てきて愛想よく見せてくれたが、今買ってきたばかりの本に目を留めて「何お読みですか」と聞くので、すぐそこの古本屋さんで200円で買ってきたというと、「あそこは古本屋ではないですよ。置いているのは新しい本ばかりですよ」と、耳を疑うようなことを言う。「え?でもこれなんか50年くらい前のですよ」「古くなっただけで古本ではないんです。わたしよく知ってますから」 確かにご近所だからよく知ってはいるだろうが、「古本屋」ではないというのには驚いた。ますます興味津々。
奥さんは本好きと見えて、今店番のときに読んでいるという本を見せてくれた。村上春樹「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」だった。しばらく本の話などしてから結局そば猪口を一個1050円のを買った。奥さんが「その本よりずいぶん高いですけど」と笑っていた。
2013年04月15日(月) クルマを買った
去年の夏、車検を受けてから、そしてカーステレオを買い換えてからまだ半年しか経っていないのに、これまでのクルマ(軽)を下取りに出して、別のクルマを買った。去年からセダンの普通車に乗り換えようと、探していたのだ。特にネットでよく見ていた。ずいぶんたくさんあって迷ったが、結局プレミオにしようと思い、友人のH井君に頼んでおいたらすぐ見つけてくれた。平成16年式、1800CC、8万6千kmも走っている中古車である。

後ろのシートを外すとトランクとつながり、とても広い荷室ができる。われわれくらいの小柄な人間なら十分横になって寝られるほど。床は平らにはならないが。
がっかりしたことも。今日になってやっと気付いたのだが、付属のMDがSP(標準モード)のみ再生可能だった。これまで自分で取り溜めしたMDはすべてLP(長時間モード)なのでどれも再生できない。これはショックだった。クルマの中で音楽を聴くことは人生の大きな楽しみのひとつである。このクルマにした大きなメリットがなくなってとても残念である。
2013年04月01日(月) 堀尾跡公園
いわゆる新年度になった。この1ヶ月仕事も忙しかったが、それよりこのHPの改造に時間をかけていた。以前を知っている人は誰もいないだろうけれど、我ながらずいぶん変わったと思う。毎年このころになるとお花見の話題を書いてきたが、今年も行く先は変わり映えもなく五条川である。
 3月31日「堀尾跡公園」にて
3月31日「堀尾跡公園」にて
「てんしやう十八ねん二月十八日おだはらへの御ぢん、ほりをきん助と申す十八になりたる子をたゝせてより、又ふためとも見ざるかなしさのあまりに、いま此はしをかける事、はゝの身にはらくるいともなり、そくしんじやうぶつ給へ、いつがんせいしゆんと、後のよの又のちまで、此かきつけを見る人、念仏申給へや、卅三年のくやう也」
33年経っても子供を失った親の悲しみは癒えないのだ。
2013年03月05日(火) 神宮と昭和の匂い
おととい3日はS子(妻)の誕生日だった。別にサプライズなどはしなかったが。最近のS子は週末が仕事になることが多く、その代わり平日はけっこう休めるので、好きなスーパー銭湯などにちょっとくらい遠くてもまめに出かけている。この寒い中、2回くらいのバス・地下鉄乗り換えは平気で風呂へ行くのだから気が知れない。私自身は風呂などあまり好きではないので積極的には付き合わないが、休みが一致したときには日頃は行くのが難しいような所へ車で出かけることはある。去年の「湯の華アイランド」(http://www.spa-yunohana.com/)とか、今年の豊公橋近くの「湯吉郎」(http://www.toukichirou.com/access/index.html)や江南の「天風の湯」(http://www.tenpunoyu.jp/matsutake/04.html)など。
どこもお湯は天然温泉というだけあってまあまあで、それなりに居心地も良かったのでまた行ってみたいとは思う。一方で「風呂なんか家で入ればいいじゃないか、めんどくさい」と身も蓋もないことを考える。

カーマから旧東海道に出てしばらく行くと姥堂と裁断橋の遺構(上の写真)。ずいぶん前に来たことがあるがあまり面影がない。ここからさらに北へ向かい、伝馬町に出て大きな交差点を渡ればもう熱田神宮だ。
神宮の森に沿って歩いていくと猫発見! 場所が場所なだけにアマテラスのお使いか!? 猫はあまりそういう恐れ多い御役はやらない。ずっと前、神棚で寝ている猫の写真を猫カレンダーで見たことがあるが、棚がしなって曲がっていた。そういう罰当たりなところが猫の本領である。
せっかく神宮前まで来たのだからと、神宮前商店街をぶらつく。シャッターの降りた店が多いが、今日は日曜で休みという店もあるだろう。いずれにしても昭和の匂いぷんぷんである。看板を見て歩くだけでも楽しい。神宮小路という飲み屋の並んだ路地も通り抜けてみた。夜ならとても入っていけないような(いつ行くのだ?)陰鬱とした雰囲気だった・・・。
 神宮前駅すぐ横のいつ取り外されるかも知れぬ跨線橋( こせんきょう)・・・クリックで拡大可
神宮前駅すぐ横のいつ取り外されるかも知れぬ跨線橋( こせんきょう)・・・クリックで拡大可
2013年03月03日(日 ) シベリウスとマーラー
音楽のこともたまには書いてみたい。クラシックの曲は大体毎日数時間は聴く(NHK-FMのミュージックプラザとベストオブクラシックだけで4時間になる)。録音してはBGMに使い、すぐ消してしまうが、曲によってはそのままとっておく(それが普通か)。
最近よく聞き込むようにしているのは、シベリウスとマーラーである。シベリウスは吉田秀和さんの「名曲の楽しみ」の影響で、よく聴くようになった。シベリウスの「交響曲第2番」は何度聴いてもすばらしいと思う。全楽章とも好きだが、やはり特に第4楽章のあの高揚感はなんと言っていいかわからないほど感動する。むかし、ベートーベンの第5交響曲の第4楽章を聴いたときにも同じような高揚感を味わったことを思い出す。ただ、今ではベートーベンを聴いてもあのときほどの感動は甦らない。
クラシックの曲でも、歌謡曲と同じように一時的には夢中になって聴くが、やがて興味が別の曲に移っていくものらしい。歌謡曲の場合は時代とともに新曲が作られそれを同時代的に聴くが、クラシックは既にあるものを自分で見つけて聴くのだといえるだろう。マイブームとはちょっと違うので「マイ発見」とでもいおうか。例えばエルガーのチェロ協奏曲などはここ最近のマイ発見であった。またオペラには若いときから距離を置いてきたのだが、ドボルザークの歌劇「ルサルカ」のアリア「月に寄せて」を聴いて以来、このごろは有名なアリアなどは聴く耳を持つようになった。これらは年齢的なこともあるが、最近はBS放送などで手軽にオペラが観られるようになったなど、メディア的な条件もあるかも知れない(おととし8月にはNHK-BSでバイロイト音楽祭の「ローエングリン」を通しで観た)。
シベリウスは交響詩「フィンランディア」に代表されるように、民族的あるいは国民学派的な作曲家である。特に交響曲1、2番には祖国フィンランドの自然観を思わせるものが濃厚である。代表作ともいえる「カレリア組曲」はもちろん「トゥオネラの白鳥」「バイオリン協奏曲」にも同様のことがいえる。行った事がない国の景色や国民性まで感じ取れるのは音楽の持つ力のひとつである。民謡などにはそれが顕著である。
しかし、後半生の曲では、例えば3番以降の交響曲ではかなり様相が変わってきているのではないか。むしろベートーベンのような絶対音楽に近いと思う。必ずしも人気の曲ではないが、渋く味わいのある曲が7番まで続いている。これらを聴きこんで初めてシベリウスの音楽を理解できるのだと楽しみにしている。
マーラーでは今のところ一番のお気に入りは交響曲第1番「巨人」である。一応1〜9番まで聴いてはいるが、好きなのは1番である。この曲はずっと昔おそらく小学生のころだからざっと55年ほど前、ある民放ラジオの番組(名は忘れた)がこの曲の第2楽章の冒頭をテーマ曲に使っていたことがあって、それをいつも聴くともなく聞いていたせいで、いわゆる刷り込みがなされている。だからのちになってこの曲に出会ったとき「あっ」と驚いたものである。この曲もすべての楽章がとても良い。もともと交響詩として作曲が始まったとのことであるが、第1楽章はいかにも交響詩的で森の朝という感じである。ただ、マーラーは本当に音楽が深刻で、聴くだけでもエネルギーがいる。「巨人」の親しみやすさはむしろ例外かも知れない。第9番などは本当に臨終を思わせるような終わり方だ。じっくり聴いてどうかしようということはないが、自分の葬式にBGMとして流してもらうのもいいかなと思う。だから嫌いではない。
2013年02月26日(火) 体調と御嶽山とボタン電池
正月以来、どうも体調が思わしくない。咳がなかなか止まらないし、時々強い胸やけもする。ここ2、3日は腰も痛めた。軽いぎっくり腰なのだろうが、思い当たるような出来事はない。これだけ悪いのなら医者へ行けばいいのだが、行ってもたぶん「風邪ですね」とか「腰に貼り薬出しておきますね」とか「続くようなら検査しますからまた来てください」とかで済んでしまうだろう。そして胃カメラやMRIやレントゲン検査でいろいろ振り回されるだけだと思ってしまう。それなら本格的に悪くなってから入院して直したいと思う。最悪手遅れになるかもしれないが、それでもいいのだ。
 小牧山から見た御嶽山。薄曇りの日でいまひとつ・・・クリックで拡大可
小牧山から見た御嶽山。薄曇りの日でいまひとつ・・・クリックで拡大可
内部情報保持のためにボタン電池が入っているのは何度か見たが、交換したのは初めてだった。ということは今まで電池交換前に新品PCに換えていたのだろうか。電池が長持ちするのか、PCの寿命が短いのかどっちだと思ったことである。
2013年02月22日(金) 合同式(2)
(前回のつづき)32x≡1(mod.57)を解こうとするのであるが、法57に対して、57x≡0(mod.57)となることは容易であろう。さらに合同式は方程式と同じように両辺に同じ数を足しても引いてもかけてもなり立つ(割り算は多少条件がある)。従って左辺どうし、右辺どうしの差もまた合同式になるという性質がある。よって、
57x≡0 (mod.57) …①
−)32x≡1 (mod.57) …②
25x≡-1(mod.57) …③
が成り立つ。あとはこれを繰り返して、xの係数が1になるまでこれらの合同式をもとに足したり引いたりすればよい。
75x≡-3 (mod.57) …③×3
−)64x≡2 (mod.57) …②×2
11x≡-5(mod.57) …④
ここで②のxの係数が32で、④の3倍が33になることに目を付けて、
33x≡-15 (mod.57) …④×3
−)32x≡1 (mod.57) …②
x≡-16(mod.57)
∴x≡41(mod.57)
合同式の解は最小の非負の整数で表わすのが普通なので、この最後の式は、x≡-16(mod.57)に57を1回足したものである。実際に32x≡1(mod.57)に代入してみると、32×41=1312で、1312÷57=23 余り1 で正しい!
中学・高校でも整数の問題には中々むつかしい問題が多いが、合同式はそれらを解くのに持って来いの道具になっている。ちょうど鶴亀算が方程式を使うと苦もなく解けるのに似ている(上の解法も連立方程式の加減法に似ている)。
(例題) 5で割ると4余り、6で割ると5余り、7で割ると6余る数で最小の自然数はいくつか。
(解) 題意を合同式で表わすと、それぞれx≡4(mod.5)、x≡5(mod.6)、x≡6(mod.7)となり、この問題はx≡a(mod.N)のa,Nを求めることになる。細かい理屈を抜きにして、高木貞治著「初等整数論講義」に出ている方法で解いてみよう。
まず、法となっている5,6,7から5×6×7=210を作り(これがNとなる)、この210から210÷5=42、210÷6=35、210÷7=30を作る。そして、仮の未知数tを用いて、42t1≡1(mod.5)、35t2≡1(mod.6)、30t3≡1(mod.7) を解くのである。
これらの解はそれそれ、t1≡3(mod.5)、t2≡5(mod.6)、t3≡4(mod.7)である(確認してください)。これで解は、
x≡(4×42×3)+(5×35×5)+(6×30×4)=2099(mod.210)、すなわち、x≡2099≡209(mod.210)となるという。
実際、209÷5=41余り4、209÷6=34余り5、209÷7=29余り6となるから209が正解である(209より小さいのはx≡-1(mod.210)だから自然数ではない)。
2013年02月20日(水) 合同式(1)
岩波新書「高木貞治/近代日本数学の父」(高瀬正仁著・今月14日購入)をとても興味深く読んだ。大体の略歴は本人の著書からなんとなく知ってはいても、これだけ詳しい評伝を読むと改めて高木先生の偉大さを思い知らされる。先生は自著の中で類体論を語ってもその功績を誇ることがない。先生を知る人たちの書くもの、話すことからその偉大さが浮かび上がってきて、さてそれに触れようとしてももちろん理解できるわけがない。
私が先生の著書にはじめて触れたのは、25年ほど前、鶴舞の有名な古書店大学堂書店で何気に手に取った「初等整数論講義」(下の写真)であった。ぱらぱら捲るとなんと全編漢字カタカナ文で書かれていた(序言は漢字かな文)。昭和21年9月発行(初版は昭和6年3月・共立出版)で、整数の整除から説かれていた。これは面白いと思って購入、さて読み出してみると、もうすっかりハマってしまった。何より、文章がとても魅力的である(注)。目の前で講義を聴いているようであり、含蓄と示唆に富み、素人数学者にはこれ以上のテキストはないと思った。この本はもう過去のものと思っていたので、ワープロでかな文に直しながら勉強した。急に数学が、というより整数論が面白くなり、それまでの方程式一辺倒からこの分野に移行していった。
自分としては古文書でも「発見」したような思いだったが、やがて高木貞治が世界的な数学者であること、著書の復刻版も多く出ていることを知って次々購入していった。それまではガロアだアーベルだといっていたのが高木貞治一色になっていた。
ただ、「初等整数論講義」は(シロウトには)とてもすべては読みこなせない本である。第1章は文字通り初等整数論であるが、この章だけでも合同式、フェルマーの小定理あたりでまずgive upする。参るのだが、しばらくするとまた読みたくなってくる。そして前よりは少し先に進むのだ。不思議な本である。
(以下、合同式の話)
例えば整数を5で割ると余りは、0,1,2,3,4の5通りあるが、余りが同じ数は同類と考えることにする。例えば38と13は5で割るとどちらも余りは3である。そこで、
38≡13 (mod.5)
と表わす。「38から13を引いたものは5の倍数」という意味でもある。これが合同式である。(mod.5)は「5で割った場合」という意味で5のことを「法」という。「38と13は5を法として等しい」といってもよい。合同式のどちらの辺に法の整数倍を加減しても意味はまったく変わらない。
38≡13≡38-25≡13+25≡13-10≡3・・・(mod.5)
例えば、3x≡2 (mod.5)という式があったとすると、これは、ある数xに3を掛けてから2を引いたら5の倍数になるという意味である。これが一次合同式である。ではこのx自身は5で割った場合の余りは何かという問題になっている。それを求めることを「合同式を解く」という。
普通の計算でこれを解くのは大変である。3x-2が5の倍数になることは、3x-2=5t と書ける(tは整数)。よって3x-5t=2・・・①。ここで3と5の互除法を行なう。互除法とは2つの数を大きい数を小さい数で割りながらその剰余でまたそれを繰り返すことである。3と5の剰余は2であり、2と3の剰余は1である。1になれば互除法は終わる。まず3と5の商は1だからx'=x-1tとおくと、x=x'+t(途中は省略。以下同様)、これを①式に代入すると、3x'-2t=2・・・②。次に3と2の商は1だから、t'=1x'-tとおくと、t=x'-t'。これを②に代入すると、x'+2t'=2、よってx'=2-2t'。これも②に代入すると、t=2-3t'。こうしてx'もtもt'で表わせたからこれらをx=x'+tに代入するとx=4-5t'となる。これはつまりxは5で割ると4余ることを示しているから、x≡4(mod.5)ということになる。例えば4自身がそういう数であるからこれを3x≡2 (mod.5)に代入してみると12≡2(mod.5)となって確かに12-2=10は5の倍数であるから正しいことがわかる。
実際にはこういう簡単な場合は直感で解く。3x-2=5tは要するに3の倍数から2を引いたら5の倍数になるということだから、例えば12-2=10などがそうだと直感で見つけられる。よってx=4となる。
だが、もし32x≡1(mod.57)のような問題だったら直感で解を見つけることは難しい。試みにこれを合同式の性質を使って解いてみよう。(つづく)
(注):例えば、「初等整数論講義」附録の末尾は『吾々ハ明媚ナル風景ニ魅惑セラレテ,イツカ豫定ノ目標ヲ超エテ,思ハズ深入リヲシタガ,コノアタリデ一先ヅ馬ヲ返サネバナルマイ.』という文章で終わっている。<戻る>
2013年02月16日(土 ) 名古屋、栄
今日の散歩は栄。ホントは「おらが蕎麦」で昼食のつもりだったが、時間がちょっと早かったので予定を変更してそのまま帰ることに。バスターミナルがあるOASIS21に行くと、10数人のアイドルグループらしい女子たちの公演が始まっていた。見ただけでは誰だかわからないのでスマホで確認すると「アイドリング!!!」らしい。先日の「チームしゃちほこ」といい今日のアイドリング!!!といい、いわゆるアイドルたちに続けざまに遭遇。いかにも時代である。時々テレビで見かける菊池亜美もいたのだろうか(このグループで知っているのはこの子だけである)。
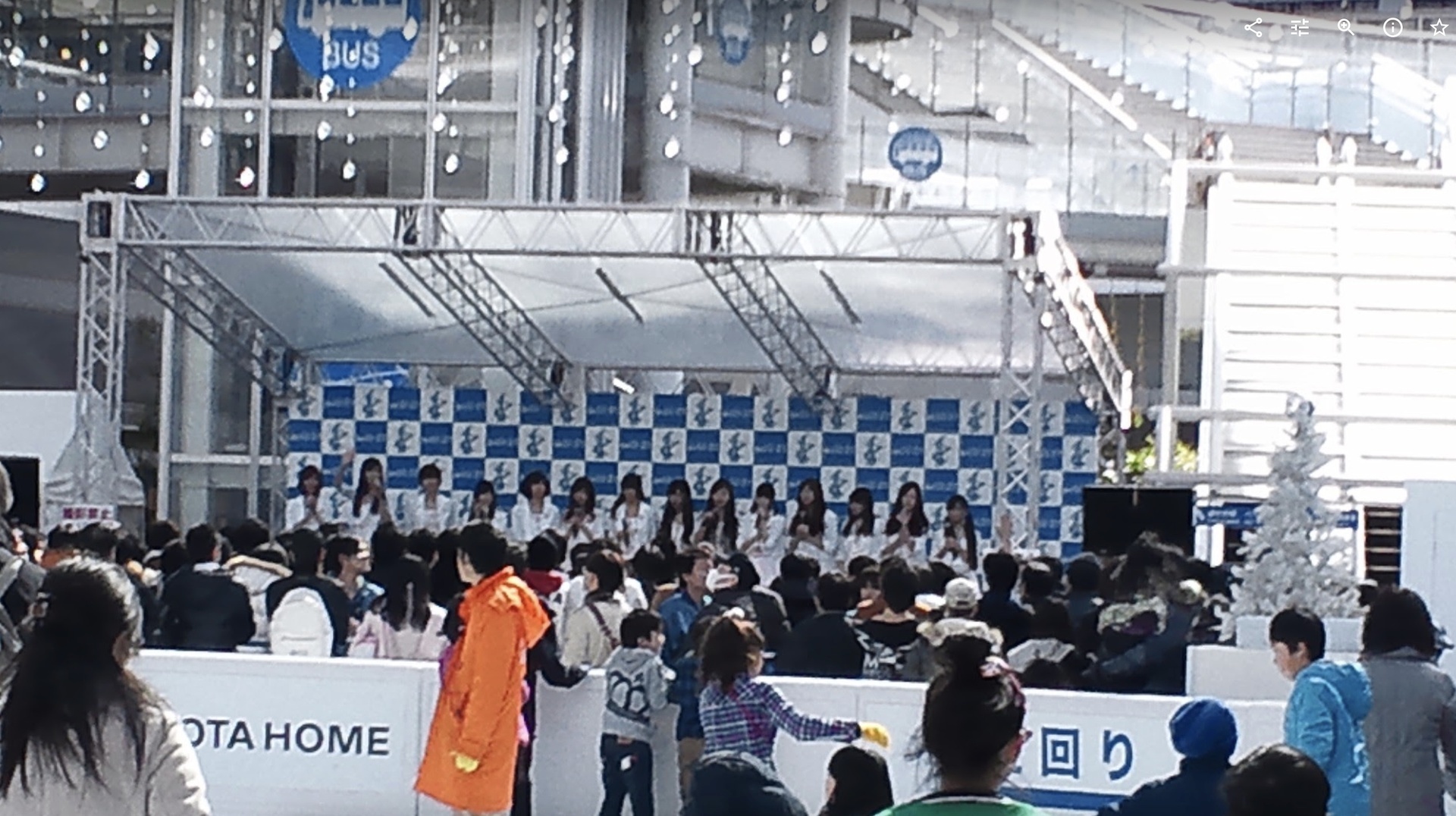 「撮影禁止」だそうだが、これだけ離れていればいいかな・・・クリックで拡大可
「撮影禁止」だそうだが、これだけ離れていればいいかな・・・クリックで拡大可
公演会場のすぐ隣は仮設のスケートリンクでこちらは家族連れでいっぱい。小さい子供たちが上手に滑っていた。

こういうところに来るといつも隔世の感を禁じ得ないのは、自分がトシを取ったせいか、それとも市の郊外にひっそり住んでいるせいか。栄の地下街で売っているものをみても自分に必要なものが見当たらない。ちゃらちゃらしたところもあれば、老舗のブランドもあり、一概に言えないが、あんな地代の高そうなところで何年も経営していけるということは、明らかに需要があるのだろう。それだけ社会に幅があるということなのだ。自分がその幅の中に入っているのか、それともそこからはみ出しているのかを自覚することは、老後を迎えるにあたりとても重要なことだと思う。世の中に置いていかれるとか、世間とずれるとか、疎外されるとか、色々な意味合いで老人の意識上の問題となるだろう。
2013年02月14日(木) 数学者とは
今日はSt. Valentine's day。けっこうチョコをもらった。岩波新書「高木貞治/近代日本数学の父」(高瀬正仁著)を買った。気付けば高瀬氏の本を何冊か買っている。高木貞治だけではなく、岡潔、ガロア、ガウス等の著書があるからだ。昭和26年生まれとのことだから僕より4つも若い。敬服している。
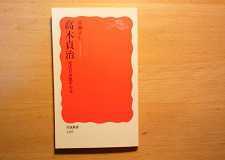
私は自分で町の数学者・文系の数学者などと称している。数学者というと変人扱いが多いが(好人好日、容疑者Xの献身など)、実はもちろん普通の人が数学者をしている場合が多い。生活に追われ、老後を心配しながら、カミさんと毎日けんかしては負けている、そのくせ頭の中はいつも数学で一杯なのだ。それは飲む・打つ・買うの世界とあまり変わらないのではないか。魅力に執り憑かれているのだ。ただ安心して執り憑かれていてよろしい。あまりお金にはならないが、お金を使うことはない。本をたくさん買わなければいけないと思うかもしれないが、そんなことはない。2〜3冊あればよい。大事なのは頭の中にひとつ問題を持つことだ。何も歴史的な大問題でなくても、自分が不思議に思っている、解きたいと思っている問題があればいい。これでだいたい一生退屈せずに暮らすことが出来る。時間はかかるがお金は要らないし、健康にもいい。散歩のようなものかもしれない。
今考えると自分の数学はだいたい人のあとを追っかけているだけである。アーベルやガロアの方程式論、高木貞治先生の「類体論」など、理解するだけで一生かかるようなものを考えていると、ずいぶん無駄な人生になるのかもしれない。でも、知識というものは人のアタマに宿ってこそ生きるもので、本の中にあるだけではそれは「存在」するとはいえない。数式もそうである。記号だけ並んでいてもそれを読み、理解する人がいなくては意味がない。ガロアの理論は論文がありながら誰も読まなかったため何十年も存在しなかった。それを理解する人間が存在してこそ、理論は存在する。自分はそういう数学を体現する人間でありたいと思う。
2013年02月11日(月) めじろとチームしゃちほこ
三連休の中日、昨日は最近お気に入りの岩倉の駅近くの和食屋「八尾初和蔵」で昼食。念願のひつまぶし定食。¥1,200。写真も撮ってきた。

この9日はT子(妹)の誕生日で、リクエストによるとショルダーバッグを欲しいとのことで、ランチのあと19号線沿いのLIVINモールへ行って女性用バッグを買った。値段も手ごろないいのがあった。このモールの外にあった喫茶店が閉店していた。子供の遊具もすっかり片付けられていて、なんとなく寂しくなっていた。
そのあと、今度は誕生ケーキをどこで買おうといろいろ話し合ったが、結局家の近くの「レニエ・デュ・ノール」という店になった。洋菓子では有名なお店らしい。どうも去年暮れの私の誕生日ケーキもそこだったらしい(S子(妻)が寒い中歩いて買いにいったのだ)。確かに甘さ控えめで中々おいしい。Googleで検索してみるといっぱい出てきた。
そして三連休最後の今日はエアポートウォークまで散歩。途中、豊山町の田舎道でメジロを見た(と思う)。メジロというとすぐ「メジロが来る山」という小学校で習った歌が口に出てくる。一番だけは全部歌える・・・と思っていたが、ネットで調べてみて「誰かコトリを鳴かしてる」だと思っていたら「誰かオトリを鳴かしてる」だったようで、50数年ぶりに訂正した。ネットの書き込みに「(この曲を)誰も知っている人に出会いません」云々というコメントがあって、思わず「そんなことはない!」と突っ込んでみた。
エアポートに着いてみると、この寒い中、表に何十メートルものすごい人の行列が出来ていた。あとで調べてみたら「チームしゃちほこ」(参考:http://official.stardust.co.jp/syachihoko/)というアイドルグループの「生誕祭」というイベントがあったそうでその開演待ちだったようだ。名前からしてローカルな響きだが、あの行列からすると中々の人気のようで、全然知らなかったのがちょっと恥ずかしかった。
2013年02月09日(土 ) 久しぶりのスギちゃん
久しぶりに散歩に出た。大曽根から名鉄の清水駅に回ってここからはバスで帰宅。約1万歩、6km。このコースは「逆大曽根コース」と呼んでいる。大曽根近くの杉村町あたりにワンちゃんがいて勝手にスギちゃんと名前を付け、そこを目標に歩くので「スギちゃんに会いに行く」ともいう。今話題のワイルド芸人スギちゃんよりも早く命名していたので、テレビにスギちゃんが出てきたときには「ん、どこかで聞いた名だなあ」と思ったことよ。
 これがスギちゃん。けっこうワイルドだろぉ〜
これがスギちゃん。けっこうワイルドだろぉ〜
ウチで飼ったイヌで一番心残りなのは「コロ」である。14年くらい生きたが、最後は乳がん(だと思う)でお乳のあたりを腫らして死んでいった。獣医には一度も診せなかった。もう今日明日というころ、仕事で家にいなかったが、S子(妻)からの電話で「今死んだよ」と聞いたとき、涙が出た。死に目に会えなかったことを未だに悔やんでいる。飼い犬の死ぬときくらい悲しいものはないと思っている人はきっと多いだろう。
 これがコロ。懐かしい・・・'89年12月頃
これがコロ。懐かしい・・・'89年12月頃
ある夏の日、久しぶりに洗ってやったときのこと、「さあ、済んだぞ」と裏庭の洗い場から開放してやると大喜びで玄関先に帰り、いつまでも体を舐めまわしていた。こっちもやれやれと後始末をして普段の状態に戻ったのだが、夕方の散歩のときになってやっと鎖に繋ぐのを忘れていたことに気づいた。が、本人(コロ)も気づかなかったようで、夏のことで玄関は開けっ放しにもかかわらずずっとそのままどこへも行かず大人しくしていたことがあった。つくづくいい犬だと思った。
2013年02月08日(金) ちょっとだけ復活!
やっと何とか食事も普通に食べられるようになり、久しぶりに会社にも行った。でもまだ咳が・・・。完全復活にはまだ遠い。先月から会社のHPの作成の仕事をしているが、その中でHPにアクセスしてきた人にキーワードを入れてもらってそれを管理するという処理が必要になり、どうしてもcgiプログラムを書かなくてはならなくなった。おかげでcgiもちょっとだがわかるようになった。ただ、このHPではたぶん使わないだろう。このブログにしたって、特にリアクションを求めているわけではないので必要ないし、phpだって本は買ったけど未だにぜんぜん読んでいない。
こんなふうに仕事を通して自分のスキルをアップしていくのは、しかもそれが自分でも興味のある分野であれば理想的といえるのかもしれない。このトシでこんな仕事をさせてもらえることはとても幸せなことである。
ただ、いつまでもこんな幸せが続くわけはない。世間では若者の仕事がなく、高学歴でありながら正社員にもなれない、その上社会保障はだんだん薄くなり、生活も子育ても老後もすべて自己責任を負わされ、消費税だけが跳ね上がっていく。自分だってやがて仕事もできなくなり、今回のように病気になればたちまち生活の危機にみまわれる。その不安は死ぬまで続く。頼りになるのは貯金と保険と家族だけだ。元気なうちに倹約してしっかり貯めなければ・・・、ああっそれなのにクルマがほしい・・・。今日、近所の中古車センターにお目当てにしていたクルマを見に行ったら「売約済み」の札が・・・。
2013年02月06日(水) 一次方程式の基本定理
すっかり風邪をこじらせてしまった・・・。1月16日(土)の夕方から熱が出て、ずっと大人しく寝ていたのに、どんどんひどくなっていった。
胃が痛くなって食欲もなくなる。インフルエンザではないとのことで一安心だったが、胃の痛みが気になり、薬も4種類になった。
しかし、それだけでは収まらなかった。翌週になって今度は咳が止まらない。また何日も寝込む。結局2週間ほどひどい目にあった。ここ数年風邪も引かずに来たのでショックだった。思えば正月の胃のかく乱もこの前兆だったかも。
しかし、無為に寝ていたばかりではない。この間、読みかけの本も進んだし、先月末に衝動買いしたユーキャンの朗読CDセット「やさしく聞ける日本の名作」を4〜5枚聴いた。何より最大の成果は、「代数学の基本定理」を一次方程式の場合に応用した(?)「一次方程式の基本定理」を証明したことである。
【一次方程式の基本定理】実数を係数に持つ一次方程式ax+b=0 は実数の中に少なくとも1つの解を持つ.以上は高木貞治著「代数学講義」の「代数学の基本定理」を翻案したものであるが、自分としてはこれを作ることで本来の定理をよりわかりやすく理解できたと思っている。
【証明】一次方程式 f(x)=ax+b=0 のxに対して f(r)≠0 となるような実数rを決める. このとき,正数hを次の条件;h>|r|,|f(-h)|>|f(r)|,|f(h)|>|f(r)|を,どれも満たすように定める. |f(x)|の値はいくらでも大きくできるので十分可能である.こうして, 関数 y=|f(x)|=|ax+b| の定義域として -h≦x≦h を与えると,関数 y の最小値は定義域の端点で得られるか, または 0 であることになる.しかし最小値は端点では得られない.なぜなら h は,|f(-h)|>|f(r)| , f(h)>|f(r)| となるように定めてあるので , |f(-h)|,|f(h)|は最小値にはなり得ないのである. ゆえに|f(x)| の最小値は 0 にならざるを得ない.すなわち f(x)=0 となる x の値がこの定義域内にある. 【証明終】
例をあげよう。
f(x)=2x+3=0 とする. r として 2 をとれば, f(2)=7≠0. これに対して 正数 h は 6 を取れば十分である. なぜなら, 6>|r|=|2|, |f(-6)|=9>|f(2)|=7, |f(6)|=15>|f(2)|=7 だから.
こうして, 関数 y=|2x+3|の定義域を -6≦x≦6 と定めると, yの最小値は定義域の端点 x=-6 でも x=6 でもないはずである(そういうふうになるようにr=6を定めたから)。そうするとyの最小値は 0 ということになり, y=|2x+3|が 0 になるようなxが存在することになるのである.
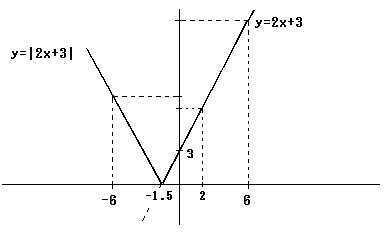
この証明には2つの重大な前提がある. ひとつは, 関数 y=|f(x)| に任意の実数 x を与えることで y の値をいくらでも大きくすることができるということ, もうひとつは, y の定義域 -h≦x≦h の端点(x=±h)に最小値がないときはその最小値が 0 になるということである.
この2つを「厳密に」証明するには実数の連続性の公理が必要である.
 Hush Puppies(c)のキャラクタ(ウチではロシ君)
Hush Puppies(c)のキャラクタ(ウチではロシ君)
2013年01月26日(土 ) 寒い日のお出かけ
昨日からずいぶん寒くなっているようだ。北国では大雪・吹雪が続いているらしい。こちらは雪はたいしたことはないが、寒いのは寒い!こんな日はうちで大人しくしているほうがいいと思うのだが、やっぱり出かけたいものだ。そこでS子(妻)の好きなダヤンの店が近くにないかとネットで探していたら、春日井の宮町というところの「サントレーム」という店にあるのを見つけた。そこで早速行ってみたのだが、バカなことに店の名前を忘れてしまい、宮町の「しまむら」という店の方に入ってしまった。女性専用の洋品店なのでなんとなくダヤンもいそうな感じがしたので店内を一巡した。キティちゃんやミッキーはいたがダヤンはいなかった。がっかりして外へ出たのだが、ふと見ると同じ敷地内にもう一軒ファンシィな店がある。店の名前がうろ覚えだったと思い、さてはあそこかと行ってみたら、案の定、一コーナーだがちゃんとダヤンがいた。それがサントレーム(「st-toremu」)だった。いろいろ見て結局紅茶用セットとご飯茶碗を一個買った。これでわが家にはダヤンが何匹になったことやら・・・。
もうお昼になっていたので、以前行った岩倉駅の和食屋のランチにしようかということになった。去年秋に岩倉街道を散歩する企画で家族で岩倉市に行ったとき、名鉄岩倉駅の近くで昼食を取った。それがとても気にってまた行こうと思っていたのだ。
 去年10月8日撮影
去年10月8日撮影
名鉄犬山線に来たのでその流れで、同じ線の前から気になっていた石仏駅を見に行った。石仏という名前の謂れは知らないが駅舎はなかなか風情があると思う。

2013年01月22日(火) 発熱と胃痛と
先週の土曜日、散歩が済んでちょっと自治会の仕事をしていたら何となく熱っぽくなってきて、とうとうそのまま寝込んでしまった。その夜は一緒に活動している会長さんと飲みに行く約束をいていたのだが、無理をせずキャンセルさせてもらった。発熱に続いて胃痛が来た。これは苦しかった。実は正月以来胃の調子が良くないのだ。たぶん食べ過ぎだと思うが(心当たりがある)、胃が弱っている所へ風邪を引いたのがいけなかったのかもしれない。週末で、休日医療も面倒なので2日我慢し、昨日月曜日にやっと近所の診療所へ行った。もう熱も下がっていたし、胃痛も収まっていたのだが、インフルエンザの可能性がないとは言えず、その確認を兼ねて。で、「インフルエンザ抗原精密測定」というのをオプション(?)としてやってもらい、陰性という結果をもらった。ほっとした。
この4日間、ずっと寝たっきりで過ごしたが、おかげで溜まっていたビデオを観るという作業が進んだ。昨年の夏にNHK-BSで録っておいた「人間の條件」(参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/人間の條件_(映画) )六部を観た。観たいというより観なけりゃいけない映画ということでずっと前から心に引っかかっていた映画だった。他にもいろいろあったのもついでに片付け、さらにユーキャンという会社から買った文芸作品の朗読CDも何枚か聴いた。聴いている間に眠ってしまうという幸福を久し振りに体験した。
朗読は昔から聴くのが好きだった。自分で声を出して読むのも好きだが、上手な人の読むのを聴くのは実はもっと好きだ。子供のころ、ラジオドラマをよく聞いていたせいかもしれない。「ルコック探偵」「ほえろアンデス」「髭の生えたパイプ」など同世代なら共有できる人も多いのでは(熊倉一雄という声優の名前をここで覚えたと思う。今ちょっとググってみたら、何と髭の生えたパイプは安部公房の原作だとか!)。有名な「笛吹童子」「紅孔雀」「鐘の鳴る丘」などは自分よりはもうちょっと上の人か。江戸川乱歩の少年探偵団もたしかラジオでやっていて、「サーカスの怪人」はなんとなく記憶がある。あと変わったところでは、午前中の民放ラジオ放送で「ぼんち」(山崎豊子原作?)をやっていたのを覚えている。
体調の方は、診療所でもらった薬のおかげですっかり良くなり、明日からまた仕事に復帰するのだが、診療所での問診の中で、(医師(女性))「もう年金生活で仕事はなさっていないのね」 (私)「いえ、まだ仕事はしています。でも社員とかパートではなくて…」(先生)「あらそう、日雇いなの?」(私)「…ええ、まあそうですね」なんていうやり取りがあってドキリとした。確かに体調崩して長く休んでいたらたちまちクチが干上がるのだ。消費税や国保で税金を納めていてもあまり国や自治体は当てにできない。確かに政治を変えていかなければいけないのだが、貯金もしていかなければと思った。ああっ、でもクルマもほしいなぁ・・・
2013年01月17日 吉田秀和先生
今頃書くのも変だが、昨年5月、吉田秀和さんが亡くなられた。Wikipediaによると98歳とのことである。googleのニュースだったか、新聞記事だったか、訃報を知って驚いたことを覚えている。FM放送の「名曲の楽しみ」でひところよりは声の張りがなくなったような気がしていたが、まだまだ仕事をされているのだから大丈夫だと思い込んでいた。突然という気がした。
「名曲の楽しみ」はその後も続けられ、7月までは吉田さんの肉声の録音で放送され、その後は生前に書きためてあった放送用台本をそのまま番組スタッフが読みあげる形で2012年末まで続いた。12月30日は特別番組も放送されたが、休日だったにもかかわらず聴き逃してしまった。肉声ではラフマニノフまでだったが、台本によってシベリウスが、それもほとんど生涯を網羅するまで放送された。「名曲の楽しみ、吉田秀和」という、あの簡潔な冒頭の語りから始まる放送は、もう聴けなくなってしまった。
FM放送のクラシックの番組は昔からだいたいチェックしていたから、今思うと「名曲の楽しみ」は、あまり意識しないで聴くともなく聴いていたように思う。意識して時々録音して保存するようになったのは、まだ数年前、ショスタコーヴィチくらいからだと思う。第7交響曲は衝撃だった。自分にとってショスタコーヴィチの再認識は、実に吉田先生の放送を聴かないではなかった。またシベリウスの3番以後の交響曲も昨年末の放送で初めて意識して聴いた。
2013年01月14日(月) また3連休
正月に10連休したばかりなのにまた3連休である。嬉しい…。今日は成人式のようである。もうすっかり関わりのなくなった祝日だが、団地の今年度の自治会会長さんは今頃地域の成人式に出席して色々裏方の仕事をしておられるはずである。自分も何年か前に会長職を勤めた時、式場の受付をした。今でもまだ荒れる成人式があるとのニュースが朝から流れていたが、一番喜んでいるのはマスコミかもしれない。荒れそうな地域へ行って式の前日から取材しているらしい。若者が何かにつけてハメを外して暴れるのは昔からどこでも変わらないことだ。
昨日は久し振りに鶴舞の古本屋を訪ねた。周辺をぐるぐる回ってコインパーキングを探し、やっと一台分を見つけて駐車し、大学堂書店へ行った。いきなり店頭のワゴン販売の300円均一で「近代文学鑑賞講座」(昭和42年・角川書店)なるものをみつけて、また本が増えてしまうのにと思いながら3冊衝動買いしてしまった。志賀直哉と島崎藤村と樋口一葉である。
このあと30分くらい店内を物色したが結局これだけの買物で済んだ。駐車料金は200円。最近はこの手の駐車場が増えてわりと繁華街でも駐車がしやすくなった。
昼食後は家族3人で小牧のラピオというショッピングモールにあるファニチャードームという家具屋を見に行った。あの「OH!Mikey」というマネキンのCMで有名な家具屋さんだ。去年偶然立ち寄った時、15年保証付きという洗濯物干しを買ってから面白い所だなと思っていたのだ。てっきり外国メーカーかと思っていたが、あの「やすいかぐ」の安井家具だそうだ。期待していくとやはり高い家具ばかりで味のある小物は思ったより少なかった。猫のマグネットフックを2個買ってきた。うちのあてねそっくりだったので(黒猫はみんなそっくりだが)…。ついでに白いのも買ってきた(@980!)。シロはこのブログの看板ネコである。

2013年01月06日(日 ) 恒例につき…
明けましておめでとうございます。恒例につき初詣の写真を。真澄田神社。
今年は1日に朝から飲んでしまい、どこへも出かけず、2日は近所の氏神様に順番に初詣(これも去年と一緒)、そしてこの日たぶん食べ過ぎでおなかを壊してしまい、3日はその続きで一日中寝ていた。で、これは4日の写真。

去年も書いたのだが、何といっても一昨年の水害の恐ろしさからどうしても龍神様、水神様にお願いしなくては気が済まなくなっている。今日は正月休みの最期の日だが、散歩の途中、新川中橋の真中に庄内川と矢田川を分ける堤防の上にあるお地蔵さまにもお参りしてきた。両側に河川敷を利用したゴルフ場があるところ。

2012年12月24日(月) 祝!前期高齢者突入
とうとう65歳になってしまった。確かにおめでたいのだが、やはりどこかさびしい気持になるのはなぜか? それを一番感じたのは市から「敬老手帳」というものが送られてきたときである。
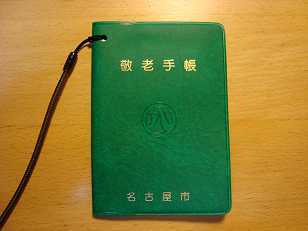
とはいえちゃっかりストラップを付けてみたり(写真)、表紙折り返しにすぐ写真を張り付けてみたりしてみた。この写真がまた手帳にぴったりのロージンだったのには笑った。もうあきらめなくてはならない…
ひとつ言いたいのは、バス・地下鉄用の敬老パスは無条件で無料になるのではなく所得に応じて負担金が必要なことである。昔懐かしい本山市長が初めて敬老パスを交付したときは制限はなかったのに(2004年以降有料化)。もちろん無条件に全員に送付するのではなくて必要な人に無料で支給すればいいと思うが。自分としては料金を払ってバスに乗ることがないので敬老パスは遠慮した。
散歩(ウォーキング)はここ数年ずっと続けている。これはとても楽しい。今日は久し振りに名古屋駅まで足を延ばしてみた。広小路を歩きながら、サカエの地下街でそば屋(「おらが蕎麦」)を発見したり、懐かしいヤマハビルに立ち寄ったり、納屋橋饅頭本店が引っ越していたり、名鉄セブンがなくなってヤマダ電機になっていたり(知るのが遅い?)、ちょっとしたウラシマ効果だ(ナナちゃんは健在だった)。
 明日にはもう着替えているはず…
明日にはもう着替えているはず…
とはいえ、ここに来ると普段はFMで聴いているだけの作曲家たちの楽譜を見ることができる。今でも若い時に感じた興奮と同じものを感じる。シベリウスのバイオリン協奏曲、武満徹のNOVEMBER STEPSなどが手に取れる。こんなところはそうそうない。
名古屋駅ではヤマダ電機をちらと見た程度ですぐに栄まで引き返し(地下鉄)、さっき見つけたおらが蕎麦でざるそばを食べた。450円だが量が多くて値段のわりにうまかった。疲れたので栄からはバスで帰宅。約12000歩8kmくらい。夕方までぐっすり寝た。
2012年05月15日(火) 体(タイ)について(1)
群についてはもっと多くを語らなければならないのだが、ひとまずおいて次は「体」について述べる。体とは、数の集合で四則(加減乗除)において閉じているものをいう。四則計算がいつでも行なえてその答えが同じ集合に属しているような集合をいうのである(もちろん0(ゼロ)で割ることは除いて考える)。
分数全体の集合を考えたとき、これは体になるが、普通これを「有理数の集合」という。分数±分数、分数×分数、分数÷分数などはいずれも答えがまた分数になる。これが体である。これを「有理数体」といい、Qで表わすことがある。
同様に実数の集合、複素数の集合なども体である。それぞれを「実数体R」「複素数体C」と呼ぶ。
体は他にもある。例えば2の正の平方根「ルート2」をr[2]で表わすことにすると、集合{a+b×r[2]|a,bは有理数}は体になる。ここで実際に計算するのはあまりにも煩雑になるのでやらないが、ぜひ試してみてほしい。
さて、この1個の例で類推できるように体はいくらでもあるのだが、これらの体の構造を調べることが必要なときがある。先ほどの体の例{a+b×r[2]|a,bは有理数}は、いってみれば有理数体Qにr[2]を付け加えたものということができる。そこでこれをQ(r[2])と表わそう。同様にQ(r[3])とかQ(r[5])などが作られるのがわかるだろう。
2012年03月13日(火) 一年…
もう、というかやっとというか、あの日から一年経った。去年の今頃はパニック状態だった。もちろん被災地の人たちとは比べ物にはならないが、毎日毎日恐怖と不安でいっぱいだった。
地震や津波ももちろんだが、一番恐ろしかったのはやはり原発事故だ。毎日仕事には行きながらも、今日は大丈夫か、明日は避難するか、避難といってどこへ逃げるのだとか、そんなことばかり考えていた。
政府や東電の発表に一喜一憂しながら、これから日本はどうなるのだろう、自分はどうしたらいいのだろうと考えていた。
昔、「渚にて」という映画があった。核兵器を使った戦争で世界中が放射能で汚染され、人類がやがて滅びていく過程を静かに描いていた。何度も何度もそれを思い出していた。
本も読めなかった。テレビも楽しめない。毎日おかしなCMが流され、いかにも平時ではない感じがした。津波や地震の恐ろしさは大昔から人間はよく知っているが、放射能の恐ろしさは現代のものだろう。自分が死ぬとか街が破壊されるとかいったレベルの恐怖ではなく、人間が人間の手によって滅びるのかもしれないという、今までは観念的には考えたことはあったが、そのことを現実的に身近に考えたことはなかった。
一年経って、改めてその頃に感じていた恐怖を思い出した。
2012年02月01日(水) 置換群(4)
…思わず(?)三日間(1月21,22,24日)、群について書いてしまったが、ついでなのでもう少し続けよう。ガロア理論で必要な群の知識はそんなに多くはない。部分群、共役部分群、正規部分群、正規列、可解群くらいである。
部分群とは、ある群の一部がまた小さな群になっているとき、それを部分群という。例えばG3には群表からもわかる通り、
G3a={σ1,σ2}
という部分群がある。なぜならσ1とσ2だけで演算の閉じた群表が出来るからである。
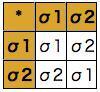
同様に
G3b={σ1,σ4}, G3c={σ1,σ5}
も部分群である。これらは互いに兄弟のような部分群なので共役部分群という。しかし、σ1とそれ以外の1個からなるものがみなG3の部分群というわけではない。例えば{σ1,σ3} は部分群ではない。σ3*σ3=σ6 であり、σ6 は {σ1,σ3} のなかにはないので演算が閉じていない。{σ1,σ6} も同様に部分群ではない。
どうしてこういう差ができるのかを、正三角形の置き換えに戻って考えてみよう。
部分群 G3a={σ1,σ2} でいう σ2 とは、ABC→ACB のことであったから、正三角形の頂点Aから底辺BCに引いた垂線を軸とする対称移動である。この移動は、もう一度行なうと元に戻る(σ2*σ2=σ1)。だから部分群になる。しかし σ3 (ABC→BCA)は反時計回りの120度の回転移動であるから同じ移動をもう一度行っても元通りにはならない。よって{σ1,σ3} は部分群にはならない。
しかし、{σ1,σ3} にもうひとつ σ6 を加えれば部分群になる。
G3A={σ1,σ3,σ6}
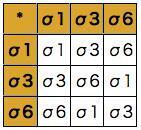
さらにこのG3Aには他の部分群にはない大きな特徴がある。それは共役部分群がない、いいかえればG3Aの共役部分群はG3Aだけであるということである。そういう部分群を正規部分群という。
他に、σ1 だけからなる G3e={σ1} や、G3自身もG3の部分群といってよいだろう。
これらの部分群の元の個数が、1個、2個、3個、6個というようにG3の個数6の約数になっていることも大きな特徴である。
2012年01月24日(火) 置換群(3)
群の定義とは次のようなものである。 「一般に、集合Gについて、あるひとつの演算が定義されていて、次の3つの条件、
A:演算の成立とその一意性
B:演算の結合法則
C:逆演算が可能
が満たされるとき、Gを群と呼ぶ」。
(参考:「群論入門」稲葉榮次著 培風館「新数学シリーズ7」昭和47年より)。
この定義でいう「演算」とは今の場合でいえば置換のかけ算のことになるが、一般的には「集合内の2つのものに一つのものを対応させる操作」のことである。普通の四則計算も一つ一つが演算である。演算の定義を広くとることで、群の範囲も広くなるのだ。「一意性」もほとんど自明といっていいだろうが、置換どうしの積が一通りに決まるのを確かめるために置換σ1〜σ6の積の「九九表」を作ってみよう。前回示した置換の積 σ3*σ2=σ4 のような「演算」をσ1からσ6まですべてで行ない、その結果を表にするのだ。
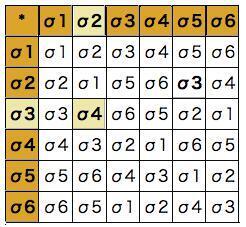
この表から気付いたことをあげてみよう。
まず、表全体には必ずσ1〜σ6のどれかが現れていてそれ以外のものがない。これが群の定義のA:「演算の成立」を示している。言い換えると演算が「閉じている」のだ。そしてどのマスにも1個の答えしかない。これが「一意性」である。
次に、どの行または列にもσ1〜σ6が必ず1個ずつ現れている。同じ行または列に同じものが2個以上出ることはない。
次に、群の定義 C:の「逆演算が可能」というのを表から考えてみよう。
逆演算とは、例えば整数の集合のかけ算を考える。2χ=6は、χ=3という解が存在するので、この場合は逆演算が可能であるが、2χ=5だと整数としての解がない。つまり解があるときとない時がある。よって整数の集合はかけ算の逆演算が(いつでも)可能とはいわない。
しかし、このG3の積の表では、σn*σχ=σm というとき、nやmが1〜6のどれであっても表からσχが求められる。例えば、n=2、m=3のときはσ2*σχ=σ3となるから、表で縦の列左端のσ2から右へ行き、σ3があるのでそこを上にたどればσχすなわちσ5が得られる。すなわちG3は置換の積について逆演算がいつでも可能なのである。
最期に、群の定義 「B:演算の結合法則」であるが、これは次のことを表わしている。
σ2*(σ3*σ4)=(σ2*σ3)*σ4
この式の左辺は、「まず置換σ4、次にσ3」を行ない(結果はσ5)、最後にσ2を行なった結果(=σ3)を示している。そして右辺は、「まずσ3を、続いてσ2」を行なった結果(=σ5)を保持しておき、σ4のあとに先の結果であるσ5を行なった結果(=σ3)を示す。それが同じだと言っている。表でもそれを確かめられる。もちろんσ1〜σ6のすべてにおいて成り立つ。
こうして、G3は「群」であることが確かめられた。上の表のことを「群表」という。
2012年01月22日(日 ) 置換群(2)
前日の置換の表現についての続き。このσ1,…σ6を使うと置換を次のように表現できる。例えば、文字列ABCに置換σ2を行なうことを、σ2(ABC)と表わし、その結果がACBなのだから、
σ2(ABC)=ACB
と書くことができる。同様にσ1(ABC)=ABC、σ3(ABC)=BCA、σ4(ABC)=BAC、σ5(ABC)=CBA、σ6(ABC)=CAB。
△ABCや文字列ABCに対してこれらの置換を繰り返し何回でも行うことができるが、その最後の結果は、最初の状態ABCに対して6つのどれかの置換をひとつ行なったのと同じになるはずである。
例えば、ABCに置換σ2を行ない、続けてσ3を行なうと、σ2(ABC)=ACB、σ3(ACB)=BAC。 つまりABCがBACになったのであるが、これはσ4を1回行ったのと同じである。σ4(ABC)=BACであるから。これを式に書くと、
σ3(σ2(ABC))=σ4(ABC)
ということである。ここで(ABC)はいつでも同じなので省略すれば、
σ3(σ2)=σ4
となる。ここまで来ると、まるで置換どうしを「掛けて計算した」ように見える。そこでこのことを置換の積と呼ぶことにするが、もう少し進めて、σ3(σ2)のカッコを取り、替わりに * を置いてみよう。すなわち、
σ3*σ2=σ4.
注意すべきこととして、σ3*σ2というのは、ABCにまず置換σ2を行ない、次にσ3を行なうという意味であることを忘れてはいけない。。「σ3掛けるσ2」と読んでしまうと元々の意味を外れてしまう。
もうひとつの注意は、「置換の掛け算」では交換法則が成り立たないことである。σ3*σ2 と σ2*σ3 では結果が異なるのだ。
さていよいよこのG3が「群」であることを示すのだが、そのために、数学で「群」といわれるものの定義を述べ、G3がその定義に当てはまることを次回に示そう。
2012年01月21日(土 ) 置換群(1)
おととい(19日)の「ガロア理論」に出てきた群とは、ガロアが初めて使いだした数学用語で、数ではないもの(数でもよいが)の集合がある性質を満たす時、それを群と呼ぶ。ガロア理論で群といえば置換群である。置換とはものの位置を置き換えることである。例えば正三角形△ABCを動かしてまた自分にぴったり重ねるとき、これを「△ABCの置換」ということにする。△ABCで頂点Aから辺BCに垂線を引いて、この垂線を軸にして対称移動させた時、△ABCはまた自分にぴったり重なるのでこの対称移動は置換である(頂点Bと頂点Cが入れ替わっている)。また△ABCの重心を中心として120度回転させることでも置換できる。
置換の中に、△ABCをまったく「動かさない置換」も含む(これを「恒等置換」と呼ぶ)ことにすると、これらの置換には全部で6通りある。
この6つの置換を記号で表現してみよう。△ABCの置換は抽象的にいえばA、B、Cという3つの文字を置き換えていると見ることもできる。よってこの6つの置換を正三角形という言葉を使わずに単に、3つの文字ABCがこの順からACBに、あるいはBCA等々に変わることと表現しても同じことである。これらの置換を次のように表わしてみよう。
置換の名前: σ1 σ2 σ3 σ4 σ5 σ6.(σは「シグマ」と読む)
実際の置換: (ABC→ABC),(ABC→ACB),(ABC→BCA),(ABC→BAC),(ABC→CBA),(ABC→CAB).
この6つの置換の集合にG3という名前を付ける。
G3={σ1,σ2,σ3,σ4,σ5,σ6} (σ1は恒等置換)
置換が6つあるのに「G3」と名付けるのは3個のものの置換という意味である。とにかく3つの「もの」の置き換えや並べ替えにはこのG3が使えることはすぐわかると思う。3!=6 というわけである。
2012年01月19日(木) 「ガロア理論」が佳境に
ガロア(理論)と付き合いを初めたのは、結婚する前だからもう40年以上も前になる。カミさんより長い付き合いである。やっとこのごろわかりかけてきたような気がする。ずいぶんかかったものだ。「体(タイ)の自己同型群の性質を調べることでその体の性質を知る」というのがガロア理論の精髄だが、これだけでは何のことやらさっぱりわからない。ただ、ひとたび理解すると、恐ろしい威力を発揮するのだ。
例えば、
「定規とコンパスによる一般角の三等分は可能か」
という、古代ギリシア以来の有名な難問がある(試しに60度の角を定規とコンパスだけで3等分してみて下さい。これが出来ないのです)。だが、これをガロア理論で説くと、
「この問題を代数方程式に置き換えるとその方程式は3次方程式になり、そのガロア体の次数は6である。また定規とコンパスによる作図は2次方程式の積み重ねによるのでそのガロア体の次数は2の累乗でなくてはならない。しかし6は2の累乗ではないので、一般角の三等分は不可能である」
ということになる。
また、「5次以上の一般の代数方程式を同じ代数的な解の公式で解くことはできない」という有名な「アーベルの定理」も、ガロア理論では、「一般の代数方程式のガロア群は対称群であり、5次以上の対称群は可解群ではないので、5次以上の方程式の解の公式は存在しない」となって証明が1行余で終わる。
この鮮やかさがとてつもなく魅力である。この意味がわかったらどんなに素晴らしいか、と思ったのがガロアと付き合おうと思った動機である。
40年も付き合ってきたのだからもうわかっていてもいいはずなのだが、そこが凡才の悲しさ。厳密な証明をひとつひとつ追ってきたことでわかったはずなのだが、やっぱりいまいちよくわからない。でもそれがまた尽きない魅力なのだ。
高等数学によくあることだが、とても簡明な定理なのに証明が半端なく難しいものがある(例えば「フェルマーの大定理」や「類対論」など)。理想としてはそれをまた簡明な証明によって理解することだ。できるなら高校2年程度の学力ですんなりわかるような証明法がないだろうか。厳密な証明でなくても感覚的に「あ、なるほど!」とだれもが納得のいくような理解法はないだろうか。そう、知りたいのは証明法より理解法である。これを追求したい。そのためにずっとガロアと付き合ってきたのだ。
2012年01月04日(水) 恭賀新年
新年になった。今年の初詣はまず元日に近所の神社3社を廻った。1つは土地の氏神ともいうべき味鋺神社だが、あと2つは西八竜社・東八竜社という「龍神様」である。去年の9月、我が家の周りはもう少しで洪水に見舞われるところだった。ふだんは堤防のずいぶん下の方を流れている庄内川が、この時はなんと堤防の上の道すれすれにまで増水したのだ。それを目の当たりに見たときの恐怖は今でも忘れない。実際に今勤めている会社では堤防を越えてきた水による浸水被害に遭った。もし決壊していたら命にかかわる事態になっていただろう。堤防沿いに家のある人たちは本当に肝を冷やしたことと思う。われわれ一家3人も夕方、広報車の避難指示に従って近くの学校に避難した。初めての体験である。
この辺——北区味鋺・楠地区——は大昔から水害の多い所で、庄内川等の川沿いには大小の水難除けの神様がたくさん祀ってある。その中に西八竜社・東八竜社というのが近所にあるのでまずそこにお年始に行ったのだ。龍神様に今年の無事を願わずにはいられなかった。
恒例の真澄田神社には2日に行った。今年も同じ場所で記念撮影。

2011年12月20日(火) 悪夢から希望へ
悪夢は始まったばかりである。人はそのことをすでに知っているのだ。周りの人もそういっている——近いうちに今度はここに大きな地震がくるぞ、と。こことは東海地方のことであり、その地震は東海・東南海・南海地震のことだ。この三つの地震は連動しているという。続けざまに来るという。M8〜9クラスの地震になることもあるという。もし事故や病気にならずにいたなら、たぶんその地震で死ぬのかもしれない。今住んでいる建物の下敷きになるか、あるいは火災にまきこまれるか、あるいは地震そのものからは助かっても、その後の様々な障害や困難に負けて、たぶんそのころはもう体の自由も効かない年寄りになっているだろう、そしてみじめに死んで行くのだろう、と。これが自分の最期だと——
こうした「悪夢」の考え方には大きな間違いがある。それは、人は一人で生きているのではないということだ。
先日も書いたが、天災には人間に対する悪意はない。それは起こるべくして起きるのだ。そのとき人はどうすべきか。ひとつしかない。助け合うことだ。人は常にそうしてきた。もちろんそうしない人もいるが、大きく言えば、人間はいつも協力し合うことであらゆる天災と戦ってきた。それが人間の本質であるといっていいだろう。そしてそこにこそ人間の未来への希望が見出される。
確かに自分は地震によって建物の下敷きになるかもしれない。そのまま死ぬかもしれないが、死なないかもしれない。そして誰かが助けてくれるかもしれない。また、たまたま自分は無傷で助かるかもしれない、その時は他の誰かを助ける側になるかもしれないし、そうしなくてはいられない。人間とはそうあるべきものなのだ。この希望によって人は生きていけるのである。
いまやるべきことは、ただちに原子力発電所をなくすことである。原子力発電を続けることは、放射能を出し続けることであり、そのこと自体がすでに事故である。原爆や水爆のように一挙に大気中に吐き出すのか、一か所に閉じ込めておくのかの違いだけである。今も一刻一刻生み出されている放射能はこのまま数十万年残って我々の子孫を死の恐怖に至らしめる。
地球上から原子力発電所をなくすことは人類の責務である。
2011年12月05日(月) 悪夢の始まり
3月11日—あっというまに9カ月が経ってしまった。
この間、何も書けなかった。あまりの出来ごとに肝をつぶしたといってよい。携帯電話の中の小さな映像に映った津波、あの中に何百何千という人が呑み込まれていた。家が次々に押しつぶされれば当然その中に人がいたのだ。そんなことが実際に起こっていたのである。
度重なる余震、そして原発事故の恐怖。まさに悪夢だった。もちろんそれは夢どころではなく現実に起こっているのだったが、悪夢という言葉がぴったりに思えた。
人はとても信じられないような出来事を「悪夢のようだ」という。それはまさに「悪夢」という現実なのである。人類と日本人は度重ねて悪夢を経験してきた。災害、貧困、疾病、戦争、等々。そしてとうとうそれらの頂点にあるものとしての福島県の原発事故が起こるべくして起きてしまった。
地震や津波は人から見れば天災である。人間とそれとのかかわりは自然と人間の営みそのものの一面であり、地球上に生まれた人類の宿命である。しかし、自然の営みとしての地震や津波は、おなじ営みから生まれてきた人類に対して悪意を持っているわけではない。植物や昆虫に対して日光や雨が降り注ぐのと変わりはない。人はそれに対して恐れおののきながらも知恵を使って身を守るすべを生み出しながら必死に生きてきた。今回の大きな犠牲は、まだまだ我々の知恵と努力が足りないことを、多くの人の命を引き換えに思い知ることになった。
しかし原発事故は違う。それは当然予想されていた。地震や津波が来たらどうなるかに対しても「想定」されていた。しかし、今日明日ではないだろうし、先々起こったとすればその時の人々が何とかするべきものとして見過ごされてきた。そしてそれが起こってしまったのだ。
原子力発電所は、そこにあるだけですでに反人類的存在である。特定の人たちが「原発を作ろう」と意志することはすでに反人類的意思である。それは未来の人たちを殺すことである。原発の生み出す放射能は、数十万年のあいだその間の人々をおびやかし続ける。それは現在の人々が自分たちのために未来の人の命を犠牲にする行為である。現在の人たちは誰も10万年もの先の責任を取ることを考えていない。今から10万年前のことを考えてみるといい。その頃の人類たちが今の我々のことを考えていたとは思えないだろう。それと同じである。しかし、放射能は厳として残るのだ!
原子力発電所のメルトダウンが象徴する事故は、人間が100パーセント責任を負う、悪夢の最たるものである。戦争ももちろんそうであるが、戦争は初めから人を殺戮することを目的としているのに対して、原子力発電は、戦争や殺人とは正反対の「平和利用」であるなどと称していることがひときわ悪辣である。それは未来の人たちに対する殺人行為であり、その責任を負うつもりなどまったくない反人類的所為である。
——やっとこれだけのことが書けるようになった。
2011年01月31日(月) 電動自転車
あっという間にひと月経ってしまった。今年はいつになく寒い冬だが、いわゆる異常気象ではないと思う。この程度なら普通である。子供のころに見た氷の厚さ、新聞配達をしていたころの朝の冷え方や雪の降り方を思えばまだまだ平気だ。実は去年の10月から自転車通勤をしている。おもな理由は会社の駐車場が空いていないことだが、何より関心のあるのは、実は電動自転車を買ったのである(Panasonic/BE-ENN632 ¥69800+α)。前から欲しかったのだが、うまい理由をみつけたわけだ。最初、3段のギア付きと知らずに乗ってみてギアが最低速になっていたので5回ペダルを回して2m(冗談)進む感じでがっかりしたのだが、すぐ気付いてトップギアにして電力を使うと、なんと軽快なことか! 出だしの軽さに慣れるともう普通の自転車には戻れない。何より坂道が楽しい。わざわざ坂道を選んで走ってしまうほどである。
私はもう60代で足腰もかなり弱って来ているが、この自転車ならどこまでも行けそうな気がする。通勤も10分ほどだが何の苦労もない(ただ、今はちょっと寒いが…)。この電動アシストがどの程度働いているかを知るために時々スイッチを切ってみる。たちまち足先にズシリとした重みと疲労感が襲ってくる。もっともスイッチを切れば今度はモーターを自分の力で回さなければならないので普通の自転車より重くなる。
人力が主で電力がそれを助けるという電動自転車の基本的なコンセプトは示唆に富んでいる。人力と電力の割合によって様々な人が様々な形態の乗り物を利用できる。一定の速さになるとアシストをやめる。最近では減速時に充電できるものもある。電池の発展によっては走行距離の飛躍的延長も期待される。
究極的な乗り物はdoor-to-doorを思うままの時間に乗り換えなしで寝ながら行ってしまうことだと思うが、そんなのはそうむつかしいことでない。いずれは出来てしまうだろう。それより、移動に対して人間がいかにどの程度関与するかが問題である。電動自転車は乗り物のひとつの理想形態を示していると思う。いずれは単一乾電池ほどの大きさで100〜200km位走行可能なものが出来て、自転車専用道路で名古屋ー東京間を往復できるようになって欲しいものだ。

2011年01月06日(木) 山本有三を読む
「昭和文学全集」(角川書店・1952年)の2巻目は山本有三で、もうすぐ読み終える。「波」」「路傍の石」「戦争と二人の婦人」等。特に「波」は面白かった。教師の見並行介が恋愛・結婚・子育てに悩みながら人生を送って行くという、一種の教養小説。しっかりしたリアリズムの筆致だが、文章に特徴があっていかにも時代を感じる。我々の世代には現代小説だが今の若い人たちには歴史小説だろう。ずいぶんたくさんの注釈がいるに違いない。実際、このあいだ買ったダイソー文学シリーズ「梶井基次郎」(¥105)には「驟雨」や「闊歩」という言葉にも注が付いていた。「路傍の石」も懐かしい。映画を観た人も多いはず。家庭を顧みない父親と内職で家庭を支える母親のもとで育った吾一少年が奉公(これも注釈がいるかも)に出されて苦労する話にほだされて涙を流したものだった。しかし、今回読んでまったく面白くなかった。たぶん昔の苦労話はもうたくさんという気持ちだったと思う。
それに比べて「戦争と二人の婦人」はとても勉強になった。クララ・バートンという女性はまったく知らなかったし、ストウ夫人もあの「アンクル・トムの小屋」の作者とだけしか知らなかった。前者はアメリカ赤十字の生みの親であり、後者はこの作品によって南北戦争の遠因を作ったとまで言われる人である。この作品は子供に読み聞かせるような文章で書かれ、多分に教育的である。しかし作者の率直な批評なども含まれており、たんなる偉人伝ではない。
この作品は1936(昭和11)年に発表されている。この年はいわゆる2・26事件の起きた年でもある。クララ・バートンのほうはその前年暮れに、ストウ夫人のほうはこの年の暮に発表されているのだ。作者はもちろん当時の日本のあり方を熟知しており、それに対する批判がこの作品には込められている。敵味方なく負傷兵を看護するとか、奴隷解放に尽力した作家の話など、戦争とその対極にあるべき女性を主人公にしたものをよくこの時代に発表できたと思う。「路傍の石」はこのころ着想され、書き連ねながら1940年ついに「ペンを折る」という断腸の思いの一章をもって未完に終わっているくらいだからやはり筆禍は招いているのだ。
 琵琶湖 2010/12/05
琵琶湖 2010/12/05
2011年01月02日(日 ) 様変わりお正月?
今日は毎年恒例の真澄田神社へ初詣。そして今年は交通安全のお守りを買わなかった。まさかそのせいではないと思うが、帰り道うっかり赤信号を見落として交差点を走り抜けてしまった。とんでもないことをしたと思った。背中に冷や汗が流れた。しかし、だからこそ自分で気をつけなくてはならない。神頼みをしないという意味ではなくて、お守りを買う買わないということに交通安全をゆだねてはいけないということだ。
 毎年同じ所で同じ写真を撮る
毎年同じ所で同じ写真を撮る
その友人とAPITAに行き、ダヤン(ネコのキャラクター) のグッズを扱っているお店を教えてもらったのだが、気に入ったものがなくてそのまま帰る。APITAやヨシヅヤなどがもう開いていた。S子(妻)も昨日の元日は仕事だった。これがいいことなのかどうか、便利ではあるが…。これも様変わりお正月のひとつか。
去年のこのブログを見ると元日はかなりの雪だった。今年は少しは降ったようだが、この辺より中国・九州地方が大変だったようだ。大みそかから元日を立ち往生したクルマの中で過ごした人もいた。
2010/12/28(火) 忘年会
自分の会社は今日までが仕事なのだが、それを半日で切り上げ、古いお得意である別の会社の社長さんからのお誘いで忘年会に参加した。しゃぶしゃぶ食べ放題の店でそれこそ腹いっぱいにごちそうになった。毎年誘ってくれるのである。その会社で使っている小さなシステムを作ったのがご縁でのお誘いなのだが、このシステムがいつ壊れるかわからないので、その時のために出来れば顔をつないでおきたいという社長さんの思惑がある。これはこちらにとってもありがたいことである。この会社の小さなシステムは5年前に中古で買ったPCでWindowsMeで動いている。スタンドアロンなのでいくら古くても動きさえすれば問題はない。こうして活躍しているマシンは全国にたくさんあることだろう。
しかし、いずれは新しく進化したPCやOSに取って代わって行くわけで、そのとき継承されるのはやはりソフトウェアである。言語やOSやマシンのスペックが向上するにつれて、具体的な仕事をするソフトはより快適に目的を達する。それが重要なことである。いつも忘年会に誘ってくれる社長さんもパソコンのことは何も知らないが、そのことはよくご存知で、もし今のPCが壊れてもマシンさえ買い替えればすぐにシステムが復帰できることを承知である。それは実は僕でなくても誰にでもできるとても簡単なことなのだが(新しいPCにソフトウェアをコピーするだけである)、そこはそれ、人と人のつながりという非システム的なところで成り立っているのだ。

2010年12月27日(月) 今年を振り返る?
1.論文「アーベル・ルフィニの定理」を書いたこと。2.四則や平方根の計算をテキストで行うプログラムを作ったこと。
3.横光利一「旅愁」を(大体だが)読んだこと。
4.湖北・向源寺の十一面観音を拝観したこと(12月5日)。
 (渡岸寺・歴史民俗資料館にて。これは写真の写真。実際の像は撮影禁止)
(渡岸寺・歴史民俗資料館にて。これは写真の写真。実際の像は撮影禁止)
「1」の論文はまだ十分ではない。自分の意図するところが達成できていない。今、「続編」としての「代数学の基本定理」を書いているのでこれと一緒にもっといいものに仕上げていきたい。
「2」は、もともと素数の研究(整数論)のために始めたもの。
「3」は20年も前に買った角川書店の「昭和文学全集」を生きている間に読んでおこうと思って始めたその1冊目。順調。
「4」は久しく遠出していなかったので、その前の奈良行きと合わせて今年できたことに入れた。しかしもともとは昨年のT子(妹)のための壷阪寺行きがきっかけになったのかもしれない。
「5」この歳で(今月15日で63歳になった)今のような仕事ができるのがありがたいと思っている。コンピュータのプログラミングは、今の自分にはとても刺激があって面白い。健康でさえあればまだ続けられそうなので来年もぜひ頑張りたい。

2010年09月09日(木) 3回目の車検
今月愛車ワゴンRの3回目の車検だった。総費用は約¥58,000で済んだ。前回(¥85,000位)に比べるとずいぶん安くなった。特に悪いところがないのとそんなに距離を乗っていないのでまあこんなものかもしれない。今回は自宅近所の整備工場にお願いしたのだが(㈲楠自動車)、ここはときどき団地の郵便ポストに社名入りのティッシュを配布していて、それで知った。最初はオイル交換だけお願いしたのだが、社長と奥さん、娘さん息子さんだけでやっているような(家族構成は私のかってな想像だが)、なんとなく三丁目の夕日の鈴木オート平成版みたいな感じの会社だ。ついでにETCやバッテリー交換などもお願いした。実は今回の車検は迷った。なんたって世はエコカー補助金エコカー減税で大騒ぎ。誰だって買い替えしたくなるというものだ。一度は普通車に(軽ではなく)乗ってみようかとか、「いつかはクラウン」なんてCMを思い出して本気で考えたり、新車が無理なら中古車でいいが、それじゃ補助金も出ない、などといろいろ逡巡していた。Tokyo-FMの「あ、安部礼司」のCMを聞いて近所の日産販売店へ「友の会」申し込みに行ったが、これも実は乗り換えのための下見をちょっと考えていたのだ(が、販売店の人がなぜか売り込みに乗り気ではなくて。クルマ屋なのに?…)。結局は今のクルマを乗り続けることにした。
別におおげさに考えるつもりはないが、この逡巡には中々の意味がある。各メディアの調査からも都会ではクルマ離れが今の若い人だけでなく、ムカシの若い人にも多くなっているそうである。このことが自分の意識のなかにも起きているのだと思った。つまり、いわゆるステータスとしての高級車志向もある一方、もうクルマの時代ではないとか、乗るならエコカーだとか、いろいろ揺れ動いているのだ。そして自分のこの意識の揺れに気づいてしまえば、逆に迷わなくなった。結局ステータスとしてクルマに乗るのはやめるが、でもまだ必要は必要なので、このまま車検を受けよう、となったのである。
2010年09月08日(水) 異常気象を乗り切る?
台風9号(アジア名:Malou)は今日午前すでに熱低になった。思いのほか名古屋の近くまで来て消えた。久しぶりの雨で涼しくなるかと思ったが、それほどでもない。それでも夜になってあの酷暑は和らいだ。今年は三〇年に一度程度の異常気象だそうである。確かに暑くてひょっとしたら死ぬかもと思った時が一度ならずあった。怖いくらいの暑さだった。このような夏はこれからも続くような気がする。明らかに地球温暖化のせいだが、それとともに都市のヒートアイランド現象による気温の上昇が大きい。これに対して最大かつ簡単な対策は打ち水である。水道代はかかるが、この際都市部の各家庭で一斉に打ち水をするのがいい。そしてそのときはどこでもエアコンを止めよう。一日一〇分でも効果があるだろう。少なくとも試してみる価値はある。温暖化対策としてのCo2削減はなかなか目に見えないが、打ち水はその場で効果が出る。まだまだ暑いそうだから是非みんなで試してみよう。

なんとか暑さを乗り切った?かもしれないが、来年は自信がない。前にも書いたがここ数十年内には必ず巨大地震が東海地方を襲う。たぶん自分はそれで死ぬのだろうと思っていたが、どうもその前に暑さでやられそうだ。 熱中症で死ぬのと地震による家屋倒壊で押しつぶされて死ぬのとではどっちがイヤか。究極の2択である。
2010年04月25日(日 ) 旧東海道?を歩く
昨日と今日とで熱田神宮から有松までの旧東海道を歩いてみた。昨日は、笠寺観音から有松まで、今日は笠寺から熱田神宮までを、なるべく旧の東海道を選んで歩いたのだが、有松コースはともかく、熱田神宮へは旧東海道がところどころでわからなくなってしまった。でも思ったより風情が残っていておもしろかった。
2010年04月20日(火) かけ算のプログラム
しばらくブログを書いていなかったが、主な理由はプログラムを作っていたことである。以前から考えていたのだが、四則計算を行うプログラムを作りたかったのだ。というのは、電卓やコンピュータの普通の四則計算はせいぜい30〜50桁が上限で、とても数千桁どうしのかけ算などは無理。そこで数を「テキスト文字」として扱うことで、ちょうど何万文字もの文章を書くようにして何万桁の計算ができないかと考え、そのプログラムを作ってみた。
もちろん、概算でいいのなら対数などを使えばいいのだが、例えばとてつもなく大きな数の素因数分解をしようと考えるとオーバーフローの心配のないプログラムが必要になる。
例えば、これはプログラム作成中にサンプルとして用いたのだが、
180(2127-1)2+1
という数は素数であることがわかっている(参考:http://primes.utm.edu/notes/FirstIn1951.html)参考)。これを普通の整数として表すとどうなるか。そのためには2の累乗などの計算が必要になる。これを電卓で求めると、
5.210644015679228794060694325391e+78
と表される。これはこれですごいのだが、今回作ったプログラムで計算すると、実際の数は、
5210644015679228794060694325390955853335898483908056458352183851018372555735221
という79桁の数になる。ここからが大変。この数が素数であることはどうやって証明したらいいのか。
一般に、「ある数が素数であるならば、その平方根以下のすべての素数で割り切れない」ので、とりあえずこの数の平方根(の整数部分)を求めてみる。それは、
2282683511939232629384542041599378633002
になった。これは40桁の数。これ以下の素数が今度は必要になった。
・・・というわけで、今は素数表を作成中。まだやっと7桁まできたところ。正直いってあきらめモード…
2010年01月04日(月) 年始休暇も終わり
三が日は散歩をさぼっていた。元日は大雪だったし、朝お雑煮を食べてそのままぐずぐずし、2日は初詣、昨日はお雑煮のあと家族みんなで出かけた。年中行事にはそれほど執着しているわけでもないのでこれでよし。ぐだぐだするのが正月だ。昨日はAIRPORT WALK(http://airportwalk.com/)へ行ってみた。案の定すごい人と車で、駐車場探しが大変だった。中もすごい人で、FOOD COURTでの昼食もあきらめていたら、運よく席が取れたので、行列のないかきあげ丼(@390)にした。これがけっこうおいしかった。牛丼以外のレパートリーが増えたかも。
そして今日、やっと初散歩。それもひとりで。ざっと7kmくらいだったが、かなり汗をかいた。これで年始の休暇も終わりである。特にこれといってなにもなかったが、心残りはやはり何も勉強しなかったこと。いつもやや長い休みがあると勉強しなくてはと思いながら、たいてい何もしないで終わってしまう。こんなことではいろいろ考えていることが何も進まない。
2010年01月02日(土 ) 賀正
あけましておめでとうございます。新年は雪で明けた。おもわず興奮して撮りまくった。



昨日は大雪警報でびっくりしたが、あれだけの雪が一日で消えてしまった。しかし一宮のほうはまだ田んぼ一面が真っ白でとてもきれいだった。
2009年12月31日(木) よいお年を
あっという間におおみそかだ。先日15日は62歳の誕生日だった。このくらいになると本当にめでたくもなんともないが、S子(妻)に言わせると「そんなことはない、とてもめでたい」そうである。「人間五十年」の時代からすればもう一回りを過ぎたのだから確かにそうかな。今日はS子が午後からパートの仕事だったので散歩は休み、大掃除のまねごとをする。ベランダの片付けはまるで春のような日差しの中で出来たのに、台所(北側)の窓拭きは死ぬほど寒かった。一軒の家の北と南で日本の北国と南国を体験しているようで面白かった。風呂場のノブを直し、換気扇をきれいにしたころから雪になった。
今、近所のうどんやで天ぷら蕎麦を食べに行ってきたのだが、出てきたのは天ぷらうどんだった。注文間違いをしたのかもしれない。それなりにうまかった。帰ってから紅白(歌合戦)をBGMに餅を切ったりカレンダを替えたりと恒例のイベントをこなし、そのあとS子お手製のから揚げで一杯飲る予定。いろいろ書きたいこともあるが、何はともあれ皆さんよいお年を。
2009年12月14日(月) コケて、はや十日
今月4日、使い慣れてきたパソコンがコケた。突然画面が真っ暗になり、そのまま息絶えた。うらやましいくらいの成仏だった。emachinesのJ3034という機種で、今調べたら2006年2月11日の購入だった。わずか3年半の命だった。もちろん、いろいろ起死回生を試みたが、無駄だった。一度だけ、あとから考えると兆候のようなものがあり、そのときにバックアップをとればよかったとつくづく思うのだが、もちろんあとの祭りである。おかげで前回のバックアップ以後のデータはすべて消えた。前回のバックアップがいつだったのかは恥ずかしくてここに書けない。
コケたのが金曜日の夜だったこともあり、もう次の日には新しいPCを買ってしまった。今度はlenoboのG550という名のノートパソコンである。コムロード春日井店で¥59,800
 lenobo G550 ¥59,800
lenobo G550 ¥59,800
今のところ、PCにも7にも問題はない。S子(妻)のノートがVistaで、時々触っていたので少しは環境に慣れていたつもり。ただ、なぜここまでXpから変えてしまったのかは相変わらず疑問だ。特にエクスプローラはとても使いにくい。「ライブラリ」てなんだ、普通にフォルダだけでいいじゃないかと思う。そのうち慣れて使い出すかもしれないが…
いずれにしてもこのページがlenoboでの最初のアップになる。
2009年11月16日(月) クロマチック・ハーモニカ
ハーモニカを買った。トンボ(参考:http://www.tombo-m.co.jp/index.html)のクロマチック・ハーモニカ「ユニカ・フォーマル」(アマゾン経由のオフプライス楽器サイト株式会社¥8,190)という楽器で、「ユニカ」は商品名、クロマチック(半音階)とは、右側にスライドレバーが付いていて、これを押して吹くと例えば「ド」が「#ド」になる。フォーマルは、3オクターブの音階の配列がドレミの順に並んでいることを表すが、「シ」と「ド」だけはハーモニカの常道で逆順になっている。

我々団塊の世代には、ハーモニカには何となく郷愁のようなものがある。小沢昭一の「ハーモニカブルース」は、ハーモニカも買えなかった子供の貧しさが歌われているが、我々はその後輩に当たる。ハーモニカは買えるがピアノは無理だった。戦後生まれた多くの日本人ピアニストの世界的活躍は、日本の経済的発展を抜きには考えられない。作曲家を目指した私は、ピアノが買えないことを理由にその夢を断念した(のかな?)。
今度、ハーモニカを<大人買い>したのは、今の自分に一番ぴったりの楽器だと思い至ったからだ。確かに今はピアノだってムリすれば買えるが、多分買ってもろくに弾けないまま宝の持ち腐れになるだろう。よけいに虚しいだけである。
2009年11月08日(土 ) 初冬のウォーキング
立冬の今日の散歩は久しぶりに庄内緑地公園。S子(妻)は仕事なのでT子(妹)と二人だけ。庄内川沿いのサイクルロードを下ってすぐ着いてしまう。途中鵜が羽を広げているのを見たし、カモもたくさん飛来してきていた。なぜか猫もいた。


公園内は野球やテニス、ジョギング・ウォーキングなど運動する人たちでいっぱいだった。コスモスもまだ咲いていた。

西区の蛇池公園の近くで3匹の子猫の兄弟(と思う)を見た(一匹わかりにくいので○印を付けてみました)。黒いやつはうちのあてねそっくりである(黒猫はすべて似ているが)。


2009年11月05日(木) 経済学のお勉強
ここしばらくは数学をしていないが、代わりにというか、経済学に手をだしている。それもケインズへの再挑戦だ。「一般理論」(正確には「雇用・利子および貨幣の一般理論」塩野谷九十九訳・東洋経済新報社/昭和53年¥2700)を買ったのはいつだか覚えていないが、ざっと30年前だろうか。ただそのときはまったく理解できず、またあまり気乗りもせずずっと放置してきた。二十代のとき「資本論」に触れて以来、マルクス経済学こそ資本主義社会を本当に解明するものと思っているし、それは今も変わらない。「近代経済学=俗流経済学」というマルクス主義側からの批判を鵜呑みにしてきたのは事実だ。ただ、ケインズについては、「ケインズ革命」とか「ニューディール政策の基礎理論」などといった評語から関心は持っていて、何とか理解したいものとは思っていた。。
しかし、今になっても「一般理論」はむつかしい! 「資本論」とは違う難しさだ。高等数学の応用は望むところだが、そのことが困難の理由ではない。そもそも「効用」とか「限界」といった概念が労働価値説になじんだ頭には理解できない。

「無差別曲線」とか「限界効用遁減の法則」などといったむつかしい概念がわかりやすく説明されていて、私のようなマルクス主義者(?)にもよく理解できるのだ。できるなら当分これにハマっていたいと思うようになった。
2009年10月30日(金) 子どものころ食べたうどん・・・
先日行った壷阪寺(参考:http://www.tsubosaka1300.or.jp/)内の食堂で天ぷらうどんを食べたのだが、そのおつゆの味がずいぶん懐かしく感じられた。それはどうもわが幼少のみぎり大阪で食べたうどんとおなじつゆのような気がするのだ。そして何故かその味の懐かしさはそのまま母の思い出に直結している。私の母は数奇な運命にもてあそばれた人で、もともとは大阪の「滝」という家の生まれで、それから「福沢」家へ養女に行き、さらに私の父と内縁の夫婦になったのだが、なぜか父と、大阪の母の実家とは付き合いがあったようで、私はそこへ連れて行かれたことがあった。
私が小学校へ上がる前、私たち親子3人は列車で大阪の滝家へ行った。そのときの蒸気機関車や、名古屋駅か大阪駅かわからないが駅の食堂で何か食べた記憶が、おぼろげだが、ある。そしてもっとも強烈な思い出が大阪での迷子の記憶である。
私は大阪でなぜか迷子になった。子供心に名古屋へ帰ろうと夕暮れの線路を歩いていた記憶があり、線路脇にいた子供たちとケンカしたことまで覚えている。そして次の記憶は、警察に保護されていて、母の言うには、「警官にうちはどこだと聞かれて『ナガラバシ』だと答えた」そうである。私の家は名古屋中川区の長良橋の近くだったのだが、大阪にも東淀川区から遠くないところに「長柄橋」という橋があるのだ(このことが今の自分にとって迷子の記憶が事実であることの裏づけになっている)。そして無事実家に帰ってから母が食べさせてくれたのが、きつねうどんだった。それが実家なのか、どこかのうどん屋なのかはわからない。
これらの記憶は何年も経つうちにたぶんいろいろ脚色され、変造されてきているに違いない。今となっては確かめようがない。しかし、味の懐かしさというものはどうしようもない。ある味に出会うと「あ、なんだか懐かしい」と思ってしまうのだ。
それから、同じうどんの思い出として、小学高学年から中学生の頃、家のすぐ近くの公設市場(「長良市場」という)内のうどん屋さんへ毎日のようにうどんを食べに行った。十円玉を持って市場の「田嶋屋」さんといううどん屋に行き、おやつ代わりにうどんを食べた。このときのおつゆは名古屋らしく濃い醤油のだし汁で、これはこれでたいへんおいしかった。同じ市場内に「ヤスベ」という肉屋さんがあって、そこで1個5円のコロッケを買ってうどんのどんぶりに入れると、世の中にこんなうまいものはない気がしたものだ。田嶋屋のおじさんは、毎日うどんの玉を作った後に出来るうどんの切れ端を、常連のお客さんのために取り置きしておいてくれるのだ。だから運がいいとたった十円で20円分の量を食べられるのである。
ある日、いつものように私が田嶋屋さんに行って「今日、(切れ端が)ある?」と聞くと、「ああ、今はないな」という返事だった。仕方なく十円分のうどんを食べて帰ろうとすると、おじさんが「ちょうど今、(切れ端が)出来たんだが、汁は飲んじゃったか?」という。「うん」「じゃあ、裏へ行っておが粉を釜にくべて来い」という。どうもうどんをゆでる釜の燃料の補給というお手伝いをすればおつゆをおマケしてくれそうな様子だった。私がせっせとお手伝いをしたのは当然である。
また、このことと時期の前後はわからないが、例によってうどんを食べに行くと、おじさんが「坊、今日はカネいらんから頼みを聞いてくれんか」「なに?」「坊はマンガがうまいそうだな」「うん」「ちょっとこれに描いてくれんか」 そういってマジックインキと大きなポスター紙をテーブルに持ってきた。「いいよ」といって私は得意げに月光仮面がオートバイにに乗っている絵を大きく描いた。その報酬としていつもより大きい中華そば用のどんぶりで腹いっぱい食べさせてもらったこともあった。ポスター用紙の裏に描かれた月光仮面はしばらく店の壁に貼られていた。
こんなことが私のうどんの思い出である。
2009年10月26日(月) 壷阪寺
10月24日(土)、壷阪寺(HPで「壺」ではなく「壷」となっている。参考:http://www.tsubosaka1300.or.jp/)へ。先日伊賀へ行って以来の遠出で、しかも倍以上の距離になった(往復約350km)。遠かった。朝9時に出発して着いたのは午後2時。往きだけで5時間かかってしまった。このお寺は目の観音様で有名(参考:http://www.tsubosaka1300.or.jp/treasure.html「本尊十一面千手観音菩薩像」・室町時代)で、お里沢市の伝説もある。妹の角膜移植の経過が無事であるようにという気持ちで以前からお参りしなくてはいけないと思っていたのである。


ただ、目の悪い人がお参りするところにしてはややバリアフリーの点で気になった(階段の手すりなどはあるが)。もっともこんな山の中までお参りに来ること自体がバリアフリー以前の問題ではあるが。
遅い昼食をここの「つぼさか茶屋」という食堂で済ませ、本尊のある八角円堂へ入る。さすが奈良! 国宝級の仏像などがたくさんあって、いつもの観光気分を露呈させてしまった。ぜひここ(参考:http://www.tsubosaka1300.or.jp/treasure.html)で見て欲しい。
帰りは橿原から国道24号線で西名阪へ出ようとして迷ってしまい(24号線は一部が重複しているのだ)、あげくやっとたどり着いた郡山ICの入り口を間違え、大阪に向かってしまった(~_~;)。 ナビで気づいて法隆寺ICで一旦降りてやり直し。おかげで200円余分に使ってしまった。
来るときもそうだったが、帰りも亀山から鈴鹿は大渋滞(これは新名神の合流が原因だと思う)、それが終わるとすぐ今度は鈴鹿から四日市までがまたまた大渋滞。結局家に着いたのは8時だった。この夜は牛丼で済ませ、みんな早々に寝てしまった。あ〜あ疲れた。
2009年10月22日(木) お気に入りの怪談
おとといのテレビ朝日で、たまたま「怪談レストラン」というアニメを見た。その中の「池のふちの道」というのがなかなか面白かった。もう終了した回なのであらすじを書いてもいいと思うが、たけしくんという小学生の子供がいるお父さんが、せがまれて釣りに行くことを約束した。そのあとちょっとした用でお父さんが自分の幼馴染の友人の家に行ったとき、たけしくんと釣りに行くことを話したら、その友人が眉をひそめて、「お前、あそこの池にタムラくんの幽霊が出るのを知っているか?」
「え、タムラくん?」
「覚えてないのか? 俺たちの同級生だったタムラくんだよ。あそこでおぼれて死んだんだが、それから時々あそこを通りかかった人が『助けて〜助けて〜』という声を聞くんだそうだぜ」
「まさか・・・」
一笑に付して我が家に帰ろうとしたら、途中から雨が降ってきた。そこで近道をしようとしたのだが、それがタムラくんの溺れたという池のふちの道だったのだ。
ちょっと薄気味悪い気持ちで小走りに通り抜けようとしたとき、どこからか「助けて〜助けて〜」という声が聞こえてきた。すっかり怖くなったお父さんは一目散に池の道を走り抜け、家に帰った。するとお母さんが、
「ね、あなた、途中でたけしに会わなかった?」
「え?どうしたんだ」
「お父さんと釣りに行けるのが嬉しくてちょっと下見に行ってくるって出かけちゃったのよ』
「なんだって!」
お父さんははっと思い当たった! さっきの声はタムラくんなんかではない、自分の子だったのだ!
「なんてことだ。ゆうれいが怖いからって、自分の子供の声もわからなかったのか・・・」
お父さんは急いで声の聞こえたところまで走った。そして池のふちの草むらに向かって「たけしー!」と呼んだ。すると「おとうさん、助けて、ぼくだよ」と、弱々しい声が聞こえた。あきらかにたけしの声だった。お父さんは危機一髪のところでわが子を救うことができた・・・という話である。
この話はここまででいいと思っているのだが、実は続きがあって、この男の子は池に落ちたとき胸に「タムラ」という名札をつけた子に助けられたというのである。
でも、それではなんだかやりすぎな感じがするのだが、みなさんはいかがでしょうか。
2009年10月20日(火) たまには仕事のことも・・・
あまり仕事のことは書かないつもりでいたが、少し記録しておこうという気になった。ただ、内容があまり具体的にならないようにする。読んでもわけがわからないかも・・・現在、ある販売会社の電算部で開発・メンテの仕事をしている。開発といっているのは、販売に必要な資料を作成することなので、ホントの開発とはちょっと違う。メンテは文字通り、現在会社で使用しているPCやプリンタのメンテナンスである。
ここ数日、販促に必要なある資料を作っていたのだが、期日的に間に合わないので、急遽別の販促用の資料フォーマットをそのまま使い、データだけ載せ替えて使用するという仕事をした。これは社長の命令でそうしたのだが、こういう発想が自分にはできない。というよりパートタイマーの立場ではそういうことをやる自由度がない。それでも資料を実際に必要としている人と、「頼まれて」作る人間との切実さの違いを見た思いである。
ひょっとすると、これはとても重要なことを示唆しているのか。つまり、フォーマットが代用で間に合うのなら改めて作成する必要はないのではないか。さらにいうならそういう仕事を会社は(自分に)求めているのではないか。
だとしたら仕事の仕方を変えなくてはならない。これまで、何でもすぐにゼロからプログラムを作ってそれでDBにアクセスし、必要な資料をアウトプットするやり方でやってきたが、それをできるだけ既成のプログラムを使って必要な資料を作成することを主眼としなければならない。簡単にいうと、「臨時的な」やり方を通常のやり方にするのだ。その目的は正確さより速さである。「とりあえず間に合う資料」をすぐに提供することだ。
そういえばいつも上司(社長)に怒られていたのは、「遅い!」ということだった。「早く(資料を)出せ」といわれ続けてきたのだ。これまでは「そういわれても出来ないものはできない」と言い訳してきたが、案外社長たちは「とりあえず間に合う資料」で満足だったのかもしれない。PCのリソースもかなり豊富になってきているのでこれはちょっと真剣に考えてみよう。
・・・ということを書いておきたかったのである。

2009年10月17日(土 ) 久々の散歩
角膜移植のため長く外出が出来なかったT子(妹)と久しぶりに一緒に散歩に出かける。夜中に雨が降ったらしく、朝もあまり天気が良くなかったので一応天気予報で確かめると「曇り」。まいいかと出かけようとしたら、洗濯物の出し入れのどさくさにあてね(飼い猫)が脱走した。家に誰もいなくなると家に入れなくなるので仕方なく帰りを待ちながら朝食も済ませる。散歩先での喫茶店のモーニングの楽しみを奪われ、結局9時半に出発。どんよりしたうす寒い日だ。
S子(妻)はお目当ての映画を実家のお姉さんと観る約束があって今日は別行動。我々は41号線をひたすら南下。


2009年10月14日(水) 台風一過
台風18号は全国的にはともかく我が家には大したこともなく過ぎた。最も近づいた8日は妹の角膜移植後最初の検診だったが、昨日(13日)に延びた。結果は、今のところ拒絶反応の兆候もなく、「良好」とのこと。一安心だが、拒絶反応への警戒は生涯必要だそうで、これが懸念材料。3連休(10−12日)は、さすが「体育の日」らしく秋晴れの好天が続き、出かけたくてうずうずしたが、妹の手前自重する。遠出は無理だが、それでも昼食や、買い物などには保護メガネを着けていっしょに出かけている。そのうち様子を見て、ぜひ壷阪寺に行こうと考えている。
2009年10月06日(水) 台風接近
「非常に強い」台風18号が近づいている。気象台のHP(http://www.jma.go.jp/)からデータを転載しておく。台風第18号 (メーロー) 平成21年10月06日22時50分 発表 <06日22時の実況> 大きさ - 強さ 非常に強い 存在地域 南大東島の南西 約80km 中心位置 北緯 25度20分(25.3度) 東経 130度35分(130.6度) 進行方向、速さ 北 20km/h(12kt) 中心気圧 940hPa 中心付近の最大風速 45m/s(85kt) 最大瞬間風速 60m/s(120kt) 25m/s以上の暴風域 全域 170km(90NM) 15m/s以上の強風域 東側 480km(260NM) 西側 430km(230NM)このうち、「メーロー(MELOR)」というのは台風のアジア名で、マレーシア語のジャスミンのことだそうである。台風をジャスミンというのはあまり戴けないが、固有名詞をつけることで何かいいことがあるのだろうか。我々の年代の人には昔々の台風に「キティ」とか「ジェーン」などというアメリカ女性の名前がついていたことを微かに思い出すのではないか。
今はこんなのんきなことを書いていられるが、明日の今頃にはもうすっかりびびりの境地にいることだろう。今の予想ではあさっての早朝が東海地方に最接近する。何時間もあの悪夢のような暴風雨が襲ってくるのだ。それだけならいいが、玄関側とかベランダ側のガラス戸がもし割れたりしたらもう処置なしとなる。吹き込む風に対してはなすすべがない。ちょうど50年前、伊勢湾台風のときに、当時住んでいた家の表側の雨戸を破られたとき、裏の雨戸も外して風を吹き抜けさせたことがあった。そうしないと天井が吹き込んだ風によって上へ吹き上げられてしまうのだ。今にも吹き飛ばされるかのように上下に煽っていた天井を恐怖におののきながら見ていた。小学6年のときだった。
このブログの続きが果たして無事に書き込めるだろうか・・・。
2009年10月04日(日 ) 中秋の月
この1週間、T子(妹)の目の手術(角膜移植)でばたばたしてしまったが、3日、晴れて退院した。全身麻酔だったのだが、目覚めのあと、1日体調が悪く、心配した。看護師さんの話では「よくあること」とのことだが、この1年で4回も全身麻酔をして始めての経験でずいぶん心配した。でも日に日に元気になって、退院前日には食事も全部食べられるようになった。過ぎてみれば予定通りの退院となった。写真右が妹(退院直前なのでもう平服に着替えている)。左はとても親切にしてくれた同室のAさん。仲良く手をつないでいる。


 2009/10/03 21:18 撮影
2009/10/03 21:18 撮影
2009年09月24日(木) 幸福論
今日、散歩しながら考えたことであるが、今の自分は幸福だと思った。これは物質的なことを言っている。とにかく住む処があり、クルマがあり、家賃も駐車場も安く、収入は低いが面白い仕事もある。やさしい奥さんもいるし、気の利く妹もいる。子どもはいないがそれは自分が選んだ道である。そしてそれらのことをよしとしている自分がいる。これは昔の自分と比べているのだ。60代の人たちで家も家族も仕事もない人たちが多くいるが、自分の育ち方を振り返ってみると、その中に自分がいてもまったく不思議ではない気がする。私は格別貧乏から抜け出そうという努力はしなかったし、今でも低所得者層の一員だが、そこから抜け出そうともがいてもいない。それは幸福だからなのだ。これは明らかに自己満足であるがバカげてはいない。知らず知らずとはいえ、確かに自分で獲得したものである。
生まれついた時の私は、確かに物心ともに恵まれていなかった。日本全体がまだ貧乏だった昭和20年代、その中でも目立つ方の貧乏であった。小学4年で母を亡くし、知恵遅れの妹と祖父のような年齢の父のもとでものごころを付け、同級生たちのように高校へは進学できず、しぶしぶ鉄工所に就職した。
そのころ、ひたすら考えていたのは、どうしたら好きなことをして生きていけるかということだった。本が好き、音楽が好き、数学が好きだった私は、どうかしてこれらのことを自由にできるようになりたかった。思えば50年くらい、私はそのことばかり考えてきたようである。そして今の自分はかなりそれが出来るようになった。
よく聴く言葉に「夢は願い続ければきっと叶う」というのがあるが、今の私はそれに近いものを感じている。しかし、そのことを教訓とするつもりはない。教訓どころか、我を通すことばかりを考えてきたのであるから、妻を初め、かなり人には迷惑をかけてきた。友人も何人かを失っている。一言でいえば「わがまま」である。ただ、それは許される範囲でのわがままだったと自分では思っている。それを許される程度には貧しかったのだ。もちろん自分よりもっと貧しい人が、昔も今もいることは承知しているが、とにかく自分の貧乏が納得いかなかった。端的にいえば高校や大学へ行ける程度の家庭であって欲しかった。成人してから自分で苦学してでも行けばいいのであるが、子供時代の環境としてそのくらいのものを心底願ったのだ。
結果として、自分は独学によって大学卒業程度の知識は身につけた(と思っている)。30年間学習塾を続けてこられたのは、もちろん通ってくれた生徒とその保護者たちのおかげであるが、自分の独学も役に立っている。その独学は今でも続いているし、それ自体が人生の目標でもある。数学だけでもその深奥をかいま見ることができるようになりたいと、今でも勉強を続けている。
30代のときに出会ったパソコン=パーソナルコンピュータは、私の人生に大きな希望を与えてくれた。自分が興味を持ったものが時代の先端を行くものであったことは、数学とともに私の生活をも支えてくれた。特に簡易言語によるプログラミングはとても面白く楽しいものであったし、社会的需要がとても大きいものだった。パソコンの必要性は時代とともに増えてきた。今もそれは変わらないし、ますます高性能化していくことでむしろプログラミングの需要はより増えていくだろう。問題は自分がそれに取り残されないことである。はっきり言えることは、30年も前に勉強したパソコンの知識は決して無駄にはなっていないし、いま学んでいることもこれから先それが必要がなくなることは決してないことである。パソコンもソフトもどんどん古くなっていくのだが、それらは消えていくのではなくて蓄積されていくのである。
 名城公園の風車
名城公園の風車
2009年09月22日(火) 散歩と温泉
シルバーウィーク3日目のきのう、特に予定もないので日課(週課?)の散歩に名城公園へ。途中コンビニでおこずかいをダウンロード(ATM引出)。日なたはまだ暑いので41号線の高速道路の高架下を一路南下、清水三丁目で西へ曲がればあとは突き当たり。一番ペースの遅いS子(妻)を時々待ちながら90分で到着(約5km)。


 ベンチの左端に黒猫2匹、右の女の子は膝に猫を抱いている。
ベンチの左端に黒猫2匹、右の女の子は膝に猫を抱いている。
S子の休日はもうこの日でお終いなので、「午後はスパガーラ(http://www.spagala.com/index.html)へ温泉三昧の大判振舞!」を私が提案したら、S子が「4,200円くれればワタシが回数券を買うから」という。意味がよくわからないので解説をお願いした。
スパガーラの入館料は普通「大人1人¥2,100」だが、会員制度があってそれに入会すると「大人一人¥1,470」になり、しかもその会員カードで他に3人まで同料金になるという。もちろんS子は会員である。だからこっちの出す分が¥4,200なのだが、そのほかに会員だけに「特別回数券」11枚セットというのが¥10,500で売られていて、それを買えば一枚が955円だという。なんと半額以下である。スパガーラのHPを(あとで)見ると、他にも「ETCカード提示で一人1,470円、4名様まで」というシステムもあるらしい(笑)。何のことはない、ETCなしのクルマで、いきなり飛び込みでやってきて会員にもなりたくない人だけが一人2,100円払わされるのだ。
そのETC自身もそうだ。電話会社もしかり。最近どこでもやっている割引制度。高い標準料金を設定しておいて各種の割引で顧客を勧誘する。実質の値下げなのに値下げはやらない。しかも会員制などと称して自分だけが得をしているような錯覚を覚えるのだ。度が過ぎていないか。
話がそれたが、結局言うがまま券を買って温泉に入り、昼食も済ませた頃、ステージでピエロの姿をした芸人さんが風船パフォーマンスを始めていたのでそれを見に行った。小さな子どもやお父さんを舞台に上げて相手をする。風船だけでなくパイプ椅子を使ったアクロバットも見事。とても楽しかった。自薦の音楽テープらしいBGMも品のよい雰囲気を作っていた。プロに向かってうまいという評価は失礼だが、最近こういう大道芸のレベルがとても高いと思う。
2009年09月20日(日 ) 刈谷ハイウェイオアシス
今日は団地の棟清掃日なので、散歩は休み。S子(妻)は午前中仕事で、私だけ参加。しゃがんでの草取り。腰と手が痛い。でもきれいになったあとを見るとまんざらでもない。午後は幸楽苑で昼食、そのあとすず(飼い猫)を動物病院に。そしてAPITAで買い物。冬の備えの布団など。シルバーウィーク初日の昨日は刈谷ハイウェイオアシスへ行ってみた。5連休だし、どこかへ行かねばならないが、こんな時の遠出は渋滞が目に見えているので、先週テレビで見た「シルバーウィーク特集」を参考にしてみた。前夜ネットで見てみるとなかなか面白そうだった。
ETCになってから二回目の高速道路である。名古屋高速は530円、伊勢湾岸道は200円。ホントに近かった! 30分で着いてしまった。伊勢湾岸道は確か将来は第2東名神の一部となるらしいが、実際に走るのは初体験である。目印の観覧車が見えるとあっという間に到着、空き駐車場もすぐみつかった。あるのは売店と公園と観覧車とお風呂。観覧車に乗った(¥600)。



フードコートは、ラーメン横綱、ザめしや等。大混雑。特に食べたいものもないので、昼食は帰ってからに。買って帰りたかったのは藤田屋の大あんまき。ところが藤田屋は建物が違っていて見つからず、結局買わずに帰る。また今度。
昼食は最近豊山町に出来た太田屋という讃岐うどん屋で。ここはついこの間までたしか「めりけん堂」というあんかけスパをやっていたはずなのだが、うどん屋に変身。先週試しに食べに行っておいしかったのでリピート。店のひとはまだ不慣れな感じで要領が悪いが、うどんの味はよい。S子がぶっかけの「大」を頼んだのに「中」が来た。なんだか変だなと思いながらも食べてからクレームをつけると100円帰ってきた。
2009年09月18日(金) まるで「民主連合政府」・・・今のところ
今日は団地を3周、つまり3km歩いた。まだ多少違和感はあるが、だいたい元に戻った感じ。これからは無理をしないよう、ちゃんとストレッチを行なってから歩くことにした。
 S子(妻)の洋ダンスの上はあてねだけのくつろぎの場。誰も上がって来れない。
S子(妻)の洋ダンスの上はあてねだけのくつろぎの場。誰も上がって来れない。
民主党政権になってからまだ2、3日だが、八ツ場ダム建設中止・後期高齢者医療制度の廃止の明言、来年度からの子ども手当てや生活保護の母子加算年内復活など、今のところ破竹の勢いである。多少でも共産党の政策に詳しい人なら、まるで「民主連合政府」が出来たみたいだと思うのではないか。これらの政策は「中止」とか「復活」というように自民党政権時代に行なわれた政策を元に戻しているだけである。それでもその清々しさは大きい。確かに大企業・財閥への課税や無駄遣い削減の対象に防衛費を入れていないところは中間政党の限界といえるが、それにしても自民党時代との違いは劇的でさえある。
その自民党は今日、新総裁選の立候補者3人がそろったところだが、特に新味はない。谷垣氏はあの小泉政権時代の閣僚だし、河野氏は父洋平氏ほどの器でもない。もう一人は失礼ながら名前も出てこない。誰が総裁になっても来年の参院選は勝てそうにない。
しかし、民主党にもアキレス腱はある。財界を敵に回せないことだ。今のところは世論の後押し(7割が支持)で意気揚々だが、いつ腰砕けになるか、油断はできない。まず当面の問題は「高速道路無料化」だろうか。世論調査では6割が反対という。私も反対だが、別にこないだETCを着けたから言うのではない。 マニフェストに書いたからといって何が何でも実施しなくてもいい。国民の多数が反対しているものは考え直せばよい。マニフェストに書いたのは勇み足なのだから、政府が調査して「反対が多いので中止」といえば通ると思う。
昨日のクイズの答え:☆は「干し」で干せるものに付いている。ダイコンは干せるので☆が正解 (クイズの出典は「世紀末クイズ」1991年)。
2009年09月17日(木) ぎっくり腰か?・・・
今週の月曜日の散歩(ランニング)で腰を痛めてしまった。ろくに準備体操(ストレッチ)もせずに急に走り出したのが原因で、200mくらいでひどく痛むようになり、当然散歩は中止。翌日は仕事も午前休。横になっていればやや楽になるが、炎症を起こしているらしく、起きて歩くのはつらい。それでも午後から仕事をした。翌日の散歩はもちろん中止したが、昨夜は恐る恐る1kmだけ歩いてみた。やはり怖い。今日はストレッチをしてから2km。少し不安はあるものの何とか歩けるようになった。こういう場合は一にも二にも安静だが、痛みの薄らぐのに連れて歩きたくなるものだ。「動物」とはよく言ったものである。
 この写真に、この子(あてね)のために行なったことが3つ写っている。さて、わかりますか(答えは次回のブログで)・・・
この写真に、この子(あてね)のために行なったことが3つ写っている。さて、わかりますか(答えは次回のブログで)・・・
ここに、昔、作っていた「読者だより」というのがあって、それに何かの本から転載したクイズがある。
①イチゴは○ ブドウは☆
②モモ は○ 柿 は☆
③桜 は○ 梅 は☆
では、ダイコンは?
というのがあった。今の私はまったく記憶がなく、答えがわからない。みなさん、わかりますか?(正解は次回のブログで)
・・・と書きながら声に出してクイズを読んでいたらわかった。思い出した!
2009年09月08日(火) 初秋の月
今夜も団地を散歩した。月がきれいだった。昨夜もきれいだったが、今夜は一段と美しい。空が晴れているせいだろう。月齢(参考:http://www.ajnet.ne.jp/dairy/)を見ると18.7で、満月から3日過ぎているのだが、9時〜10時というわが散歩の時間帯には、高さといい明るさといい、ちょうどいい。昼間の厳しい残暑(最高気温34度!)の名残もありながら、風はすっかり秋風で、かすかに汗ばんだ背中に気持ちがいい。いつものコースは、明かる過ぎるのと月を見るのに街路樹が邪魔なので、今夜は団地構内を横切る東西の道を何往復かして、月とのランデブーを楽しんだ。両側の棟から、子どもの喚声やちょうど風呂の時間なのだろう、ザーというお湯を浴びる音などがかすかに響いてくる。季節がら虫たちの合唱もたけなわである。リリリリ・・・、ジージー・・・、コロコロコロ・・・etc。ちょうど街灯の灯りが途切れる闇の中で一匹の猫に会った。猫との出会いは散歩の楽しみのひとつである。この猫は、尻尾は黒いが体は真っ白で、見ると目の下に斑点のような黒い模様がある。ちょうど殿上眉の反対でかわいいと思ったが、手持ちのライトで照らしてみると模様ではなく汚れだった。ちょっとがっかりしたが、おとなしい雌猫のようで逃げもしない。この団地ではけっこうな数の猫の姿を見る。飼い猫だけでなく、のらも多いようだ。
2009年09月01日(火) 2009年の衆議院選
選挙が終わった。民主党の圧勝に終わった。自民党に対しては、ざまあみろという気持ちであるが、これからすべてがよくなるわけではない。共産党が思いのほか伸び悩んだのが不思議だが、民主党の躍進をみればそれに蹴散らされた感じである。そう思えばよくやった方か。これからの政権運営で一番心配なのは、やはり「憲法改正」である。第9条を「改正」してくるのではないか。ある意味絶好のチャンスである。社民党と連立しても歯止めになるとは思えない。308対7では話にならない。社民党と手を組んだのはカムフラージュである。単独過半数のまま政権を担当すれば「独裁政治」の批判はまぬかれない。世論が油断すれば民主と自民とで楽々「憲法改正」は成る。
いずれにしてもこれから4年、また衆院選挙はないだろう。たとえ参議院で自民が復活して過半数を取り返したとしても、308議席を持つ民主党が衆議院を解散するわけがない。もしあるとすれば世論である。どう考えても政権に素人な民主党が致命的なミスを犯すのは目に見えている。もともと半数以上は元自民党であり、国民世論との乖離がひどい政党だから(例:高速道路の無料化など)、比較的早い時期に危機に陥るだろう。そこを、「やっぱり自民党」などといって自民党が巻き返しに出てくる。アメリカやイギリスなどのように二大保守党の政権交代が繰り返されるだろう。では、共産党の出る幕はあるのか? 共産党の言う「民主連合政府」の可能性は? これは共産党自体の勢力拡大しかその保証はない。そもそも高度な資本主義社会で共産主義政党が伸びること事態が不思議である(さっきは共産党が伸びなかったのが不思議といったではないか)。それだけ日本の資本主義は反社会性が強いということなのだ。
共産主義とは、その社会の中でもっとも進歩的な思想に基づいて行動することをいう。日本共産党がその党名に恥じない政党であることは十分認められるが、そのゆえに常に少数派であることは宿命といっていい。その宿命的少数政党が中心となって民主連合政府を築いていくことの危うさ・非現実性をどのように克服してゆくのか。これからの4年間、民主党のお手並みよりははるかに興味を覚える政治課題といえる。
2009年08月30日(日 ) 投票日だけど伊賀の話
今日は投票日である。今、朝の10時過ぎだけどまだ行っていない。奥さんが昼まで仕事なので帰ってからみんなで一緒に行くのだ。選挙の話はまた結果が出てからにして、今日はETCのことを書こう。我が愛車にもとうとうETC(三菱電機EP-500)が着いた。例の自民・公明の選挙用ばらまき政策「高速道路どこまで行っても1000円」(川柳みたい)にあがらえず、近所の自動車整備工場で着けてもらった(\18,750)。我が家ではT子(妹)が愛護手帳持参で同乗すれば高速料金が半額になるのだが、1000円には敵わない。以前からETC車と一般車への差別に怒りを感じ、ETC搭載には反発していたが、事ここに至っては万事休すとなった。今回の選挙での民主党のマニフェストには「高速料金の無料化」が挙げられている。政権交代が現実的なことからこれも実現するのであれば、我が家のETC購入は無駄になるかも。なので、この公約には反対である(笑)。ぜひその分を老人と子どもの医療費無料化に回すべきだ。
 愛車に装着されたETC車載機。左はGPSのアンテナ
愛車に装着されたETC車載機。左はGPSのアンテナ
東名阪名古屋亀山線を走るのは久しぶりで、SAもどこか変化しているなあと実感した。特に亀山付近は新名神高速道路の一部開通と相まって景色まで見慣れないものになっている。新名神なんて我々が現役のうちには走れないものだと思っていたのに、部分開通とはいえもう利用が始まっていたとは!(これは感動しているのではなくて、こんなところに税金を使っているんだなあとあきれているのである)
さて、伊賀上野はとてもいいところだった。到着してすぐ、お城のある上野公園近くの大衆食堂(「大判」)で忍者弁当(\800)というのを食べた。ここの店主が矍鑠(カクシャク)とした84歳のおじいさんで、おばあさんと二人で気楽に営業している感じがよかった。すぐ隣の食堂(「ニカク食堂」)がずいぶん繁盛していてそこを溢れたお客が入ってくるのだ(われわれも)。
店を出ると、何だかにぎやかなのが聞こえていたので見にいってみると、若者たちのパフォーマンスダンスの会場だった。ちょうど夏祭りらしく、そこから始まる商店街がずっと歩行者天国のようにとてもにぎやかだった。 縁日、イベント、ミニSL等々、楽しそうな人たちでいっぱいだ。衆院選候補者も祭りに来ている人たちに支持を訴えている。



結論:高速道路はタダにしなくていいから、もう少し1000円のまま続けてほしいものだ(今の予定では2011年3月31日までとのこと)。
2009年08月29日(土 ) 奇妙な夏
今日はせっかくの土曜日だが、散歩は中止。雲行きが変なのと体調が思わしくない。で、HPのメンテをしつつブログを書いているのだが、とにかく蒸し暑い。今年の夏は奇妙な夏だった・・・なんて書くと、去年もおととしも書いていた、少なくとも思っていたような気がするが、まあ、「今年の風邪は」とか、「今時の若者は」などと同じで、慣用句のようなものなのかも知れない。
それにしても梅雨は長かった。7月末ごろには青空が恋しくなったものだ。その中旬、関東地方で梅雨明け宣言したみたいだが、それから後もぐずついた天気が多かったようで、もし宣言発表をもう一日待ったならきっとそのまま東海地方並みの遅さになったのではないかと思う、どうでもいいけど・・・
 田んぼでおたまじゃくしを採っていた子どもたち(7/12)
田んぼでおたまじゃくしを採っていた子どもたち(7/12)
人間の手で自然環境を変えようなんて僭越もいいところだが、破壊・悪化させてきたのは紛れもなく人間だし、ほかの生き物たちへの責任もあるのだから、なんとかしなくてはならない。しかもここ数十年が勝負時だと思う。
子どものころ[少年サンデー」で手塚治虫先生の「0マン(ゼロマンと読む)」という漫画で、0マンという新人類(リスの進化系)が「電子冷凍機」という武器を使って地球を凍らせ、人類に代わって新たに地球を制服するという話を読んだ。我々人類はその攻撃になすすべもなく、地球は次第に氷河時代のように凍りついていった。仕掛けた0マンたちでさえ電子冷凍機をストップさせることができなくなくなってしまったのだ。主人公たちもあわや凍死するまでに追い詰められたとき、突如、ふと、自然はわれに帰るのである。ゆっくりと気温が上がり始め、太陽が顔を出す。そして氷が解け出し、洪水が始まる・・・。いったいどうなるのか息を呑んで読んでいたわたしは、その電子冷凍機の機能をストップさせたのが、なんと地球の自然そのものであったという手塚先生の思想にすっかり感服したのだった。子供心にも人知を超えた自然の偉大さのようなものを教えられた気がしたものだった。
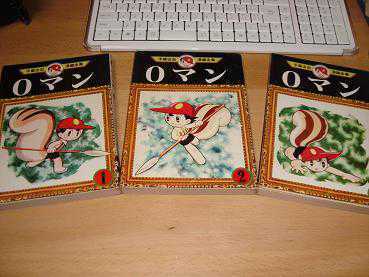 1978年講談社版「手塚治虫漫画全集」より
1978年講談社版「手塚治虫漫画全集」より

今日は夕方になってから一人で軽く歩きに出てみた。庄内川の橋の上から見た夕景色が美しかった。
2009年08月27日(木) 小論文をNewUp!
この半年間取り組んできた小論文、「アーベル・ルフィニの定理」を、自分のHPにアップデートした。これはある意味自分のライフワークであって、動機は十代にまで遡る。自分の人生の目的のひとつは、この定理を理解することだったといっても過言ではない。もちろん、まだ完成ではないが、とりあえずアップしておいて少しずつ改良していくつもり。
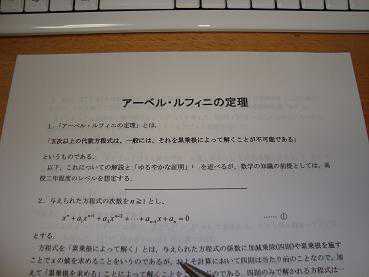 せっかくなので印刷もしてみた。
せっかくなので印刷もしてみた。
とにかく身辺的にはこれで一段落なので、しばらく休んでいたブログも小論文のアップを機に再開したい。

このごろは平日の夜も歩いている。ちょうどわが団地を1週すると1kmなので(測ってみました)、これを5周というのが日課になりつつある。とても調子がいい。時々は走ってみるが、たちまちへばるので、やっぱり歩くだけにしている。上の小論文を書いているときも、アイデアが出ることが多い。何か課題を抱えながら歩くと、閃くというほどではないが、ちょっとしたことを思いつくのだ。これはとても面白いことだ。
2009年03月10日(火) HP大改造
開設以来のHP改造をした。全体をブログ中心の構成に変えた。最初の画面もブログの最新ページになるようにした。ただ、小論文や評論は今までのままとした。動機はなによりもまず自分が更新したくなるような画面にしたかった。これまでのものもそれなりに好きだが、できるだけ更新を増やすにはやはりブログを前面に出すべきだと思ったのだ。
これまでこのブログには自分以外の人はほとんど訪れていない 。それはそれでいいという気持ちがどこかにあって、あまり熱心にHPに向き合ってこなかった。でもやはりこれからも自分はここでしか表現できないんだと思い、気持を引き締めたのだ。
何かのきっかけでここを訪れてくれた方々、これからもよろしくお願いします。
2009年02月23日(月) 祝!増設メモリ
長く本体メモリを512MBのままPC(デスクトップ)を使ってきたが、意を決して2GB(1GB×2)に増設した。なんと4倍! もっと早くそうすればよかったと後悔するくらい早くなった。一つにはメモリの値段が安くなった(アマゾンで¥5,930)ことによるが、もうひとつはまだこのまま今のPC(e-machine J3034)を使っていこう、VistaにはしないでXPのまま次期OS(Windows7?)の開発状況を見ていこうと思ったから。それに今度自分のを買うときはMacにしようかなという気持ちも多分にあるので、Windows系は仕事に必要な程度で済ませようという思惑も。2009年02月20日(金) 数学夜話(2)
毎週木曜日、NHK総合で「Q.E.D.〜証明終」というドラマを観ている。ちょうど我が家の夕食時でドラマが始まるとカレーの皿を持ってテレビの前へ座るくらい毎週楽しみにしている。昨日は「ポアンカレ予想」が数学のエピソ−ドとして使われていた。これはポアンカレという数学者が20世紀初頭に提出した問題で、「単連結な3次元閉多様体は3次元球面S3に同相である」『ウィキペディア(Wikipedia)』(参考:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%AC%E4%BA%88%E6%83%B3)より)というのであるが、私にもまったく意味が分からない。ドラマの探偵役の燈馬想(中村蒼)はこの問題で謎の“海賊ジャック”(袴田吉彦)と黒板に数式をいっぱい書いて戦うのだ(?) この「予想」はウィキペディアにもあるように2003年に解決されたことになっていて、ジャックはロシアの数学者に「先を越された」形になっている(それで海賊になった?)。袴田くんは、子供がそのまま大人になったような役どころを持ち味として好演した。ただ、最後に高校生たちから去っていく時にリムジンが迎えにきて部下と思しき人物に「会長が来日中とはつゆ知らず失礼を」と言わせているのは夢を壊した(数学者が大金持ちになるのはあまりいいものではない)。それはともかく、数学上の難問というのは本当に大変なもので、才能ある人間の一生を台無しにしてしまう魔力を持つらしい。有名な「フェルマーの最終定理」は300年間数学者を苦しめた。現在でも解かれていない問題も多い。「ゴールドバハの定理(推測)」などは問題そのものは簡単であるため(「2より大きい偶数は二つの素数の和で表わされる」)、格別人を狂わせる。
有名なギリシアの「作図3大問題」は、「1.一般角を三等分する」「2.立方体の体積を2倍にする」「3.円と等しい正方形を描く」というのであるが、いずれも定規とコンパスのみで作図することは不可能とされている。ところが、未だにこれらの問題に貴重な人生を浪費している人もいるという。
私も中学生の時、図書室の本でこれらの問題に出会って夢中になった懐かしい思い出があり、今でも愛着を持っている。角の三等分では「解けた!」と思って数学の先生のところに持ち込んだこともある(同じような経験者は多いようだ)。私の「解法」は次のようなものであった。
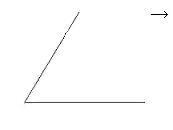
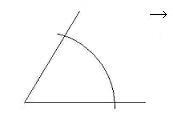

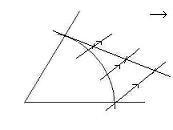
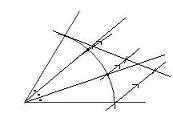
その後、数学への関心は方程式に移って、3次、4次方程式をがんばって理解したあと「5次以上の方程式は代数的には一般に解くことはできない」という記述に出会う。なぜ「5」なんだ? なぜ限界があるのだ? なぜやってみなくてもわかるのだろう?…ずいぶん不思議に思えたものだ。いや、一応は理解したのだ(と思っている)。今でも、なんだか「5」という数に神秘的なものを感じてしまう。ここにも弁証法が顔を出している。物には限界があり、量的な発展は質的な飛躍をもたらすのだ。この問題を十分に解決したガロアは文字通り代数学を根底から変えてしまった。彼の理論(ガロア理論)以後、代数学の対象は方程式の解法から群、環、体といった代数体の研究に移っていった。
2009年02月11日(水) 「建国記念の日」
今日は「建国記念の日」だ。うちでは「赤旗」(日本共産党中央機関紙)を購読しているが、毎年サービスでくれるカレンダーに今年初めてこの祝日名が記入されていた(ただしカッコ付きで)。これまでは数字こそ赤だったが何も記されていなかったのだ。去年の2月11日は日曜日だったので翌日の欄に「振替休日」とだけ記されていた。何も知らない人には落丁としか思えない。ちなみに4月29日「昭和の日」も去年は日曜だったので同様の扱いだったが、今年はちゃんと「昭和の日」も(カッコなしで)記入されている。なにも揶揄しているのではない。歓迎である。これまで「建国記念の日」(と「昭和の日」)だけ書き込まれていないことにやはり違和感があった。法律で制定されている(「国民の祝日に関する法律」(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO178.html))ものは書いてよいと思う。カッコ付きも主張が感じられて良い。「国民の祝日」には以前からメーデーと8月15日を加えてほしいと思っている。特にメーデーは、これが制定されるということはそれだけ国民(労働者)の政治に対する参加と関心の度合いが高まってきたということになるから、ぜひ実現したいものだ。今は特に不況を理由とした労働者の首切りが平然かつ大規模に行われているのだから、メーデーの祝日化は労働者の尊厳を高め、首切りを行う者たちにその手の血糊を自覚させるに効果があると思う。もっとも、だからこそ絶対祝日化はやらないだろうが・・・。
さて、我が家の休日は散歩で始まる。今日は一家3人で庄内川堤防を歩いてきたが、風もなくいいお天気でもうすっかり春といってもいい。まだあの「春は名のみの風の寒さや」(「早春賦」)の季節だというのに、まごうかたなき地球温暖化である!
鳥といえば去年の11月、T子(妹)との散歩で鶴舞公園を横切っていたら人だかりがするので行ってみると、「オオタカが餌を食べている」と教えてくれた。見物人の半数の人が大きなカメラを構えていた。市街地での野生のタカは珍しいらしい。
オオタカのおおきな画像はWikipediaでどうぞ(参考:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/H%C3%B8nsehauk.jpg)。
2009年02月09日(月) 地デジとFMアンテナ
世は押し並べて地デジ対応である。わが団地にも地デジの波が押し寄せ、昨年11月から室内のアンテナ端子が地デジ対応になった。うちのテレビは既に地デジ対応だったが、これまではたまたまこれまでのアンテナでも拾える地デジチャンネルしか見られず、CBCとかTVA(テレビ愛知)などは映らなかった。それがやっと全部見られるようになった。どうもアンテナを新設したのではなく、STARCAT(http://www.starcat.co.jp/)というケーブルテレビ会社のCATV導入によるものになったらしい。STARCATのHPでもわが団地が「CATV対応集合団地」に含まれているのを確認した。おかげですべての地デジチャンネルが視聴可能になった。それはいいのだが、一方で大変困ったことが起きた。FMファンなら同じことをやっている人も多いと思うが、これまでアナログの室内アンテナ端子から分波器でFMチューナにつないでFM放送を聴いてきた。VHFアンテナは最高のFMアンテナでもあったのだ。それがCATVになってからだめになった。入るには入るがひどい雑音である。とても音楽はムリ。CATVはFM放送には対応していないのだ。まあ誰に文句をいうわけにもいかないので、仕方なくFMアンテナを購入し(YAGIFMアンテナF-P2B-B。アマゾンで¥3,366)、ひとまず自室の天井付近に設置。ところがその時はいいかと思ったのだが、やはり時によって雑音が入り、せっかくのお気に入りの録音が台無しになることも。結局FMアンテナ用ケーブルを20m買ってきて(近くのケーズデンキで¥1,870)、アンテナをベランダに設置し直し、ベランダから私の部屋まで延々引っ張り込んだ(内緒だけどこの時押入れの隅に小さな穴を開けてしまった…)。それが昨日で、ようやくクリアな音が蘇った。

2008年09月25日(木) 数学夜話(1)
今日から(不定期に)数学について思いついたことを書いていきたい。以前にもここで弁証法のことを書いたが、数学は物理と並んでもっとも弁証法的な学問である。通常、数学でもっとも一般的な論理学は形式論理学であろう。しかし数学の二つの異なった分野の形式論理学を結んでいるのは弁証法的論理である。たとえば、自然数は加法について閉じた数の集合体であり、加法は形式論理学の基礎中の基礎といっていい。しかしひとたび加法の逆演算(=減法)を考えることで自然数は閉じた集合ではなくなり、それは整数へと発展する。これは形式論理学では説明ができない。弁証法ではこれを対立物の統一としてとらえる。つまり、自然数の中で加法を考えると、それは必然的にその対立物(反対物)である減法を自ら生み出し、相互作用によって統一性を持とうとする。その運動が自然数のカラを破り、整数を生む。その中でこそ加法と減法は対立的に統一できる。この中でこそ加法も(減法も)その形式性を完成させるのだ。
ここまでいえば当然に、では乗法と除法もそうではないかと類推できる。その通りで、自然数の中で閉じていた乗法がその反対概念である除法を生み、そこから分数が生まれ、整数との統一体として「有理数」が確立される。有理数はいわゆる四則の閉じた空間としてもっとも小さな集合体である。数学でもそういうもの(四則の閉じたもの)として「体」と呼ばれている。
では、四則以外の演算、たとえば累乗(例:2^3=8)からは何が生まれるだろうか。累乗も自然数内で閉じた演算であるが、その反対の演算=累乗根ではまったく奇妙な数を生み出す。それは無理数と虚数である。
2乗して4になる数は±2であるが、2乗して2になる数は有理数にはない。結論からいえばそれが実数であるが、実数の誕生には有理数のとてもダイナミックな営みが必要である。
もっとも著名な理論としてデデキントの「切断」を挙げる。デデキントは19-20世紀のドイツの数学者で、カントールとともに実数論の確立者としても名高い。彼は、有理数を「ある所」で、一方は他方より小さくない(大きくない)ものとして二つに分け(=切断)、この分け方自身を「実数」と呼んだのである。すなわち、「有理数の切断を実数という」と定義したのだ。
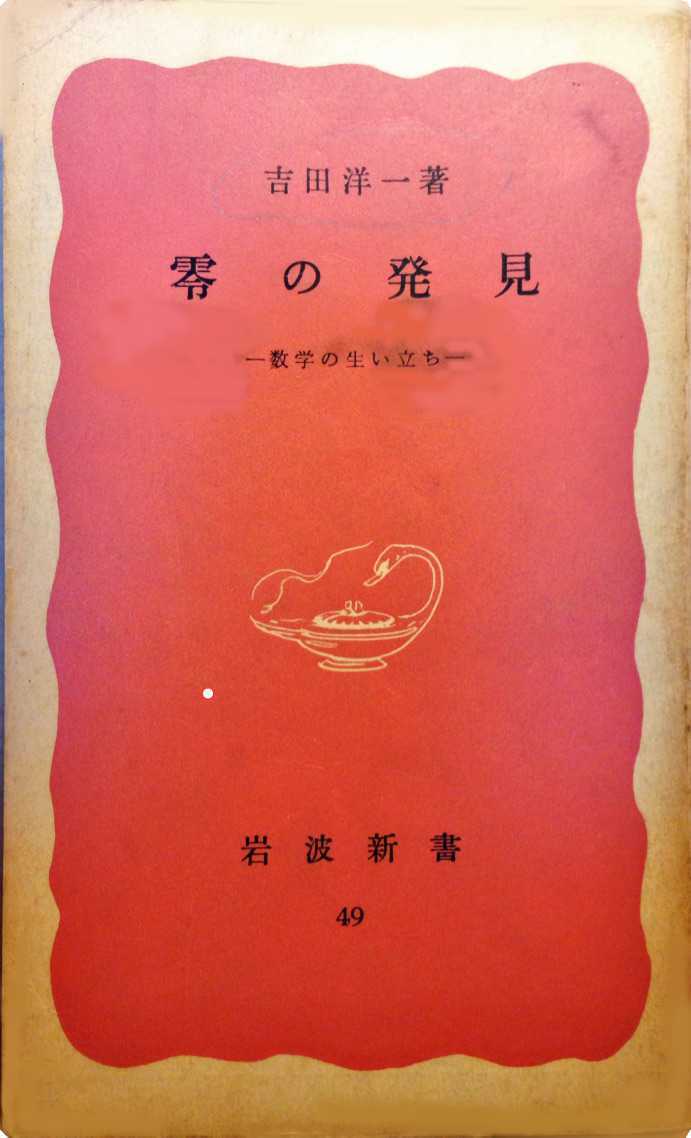 吉田洋一著「零の発見」(昭和38年第33版[第1刷は昭和14年]岩波新書) 歴史的名著。この本の後半に「直線を切る」がある。
吉田洋一著「零の発見」(昭和38年第33版[第1刷は昭和14年]岩波新書) 歴史的名著。この本の後半に「直線を切る」がある。
デデキントの発想は、直接には、直線(=実数)が左から右にまっすぐに伸びていて、それがどこで切っても必ずそこに「点」がある、言い換えれば「数」があるというるイメージから来ているようである。しかし、その発想の根底には「数の概念の飛躍」がある。
実数に比べると、虚数は形式的である。つまり、ルート2やルート3と同様にルートマイナス1という形で生み出されたように見える。虚数はその名前が示すように長い間得体のしれない、訳のわからないものとして考えられてきた。歴史的にその地位を確立するまで多くの時間がかかった。ガウスは虚数の本質をもっとも早く見抜いた数学者で、そのお陰で多くの定理や理論を残しているが、そのことを公にするに多大の注意を払った。例えば彼の数学者としての出発点となった有名な「正十七角形の作図」の発見にも、虚数が活躍しているが、かれの論文には虚数は非常に形式的にしか出てこない。
虚数は、嘘の数とか幻の数どころではなく、現実世界に実在する数といっていい。「じゃ、見せてみろ」と言われたなら、いわゆるガウス平面(普通の座標平面で、x軸が実軸、y軸が虚軸となっている)を示せばよい。2+3iという虚数(複素数)は座標が(2,3)になっている点である。「そんなのインチキだ」と言われるかもしれないが、そうではなく、数はすべてそういうものである。自然数さえそうだ。リンゴ一個をもってしてこれが「1」だといえばやはり「そんなバカな」となるであろう。
虚数の弁証法的なところは、その出自的なところではなく、むしろあらゆる数を結びつけているその本質による。誰だったか「i」と染め抜かれた風呂敷を持ってきて「愛i(=虚数)はすべてを包む」といったそうだが、とても意味深長な逸話である。「複素数」は数の完全体である(高木貞二著「代数学講義」第1章「付記」。1994年改訂新版25刷)。
弁証法的な世界は、形式論理学と異なり、(悪の)無限性を持たない。それは有限で、かつ発展的であるためそれを打ち破って新しい形態を持とうとする。数学は現在すでに数ではなく「構造」を対象にしている。「抽象数学」といわれる。それは数からはじまり数を越えていったのである。
2008年09月20日(土 ) 三連休(2)
連休2日目(14日)はS子(妻)も一緒にお馴染み大曽根コース。41号を清水まで南下し、そこから名鉄瀬戸線の高架下を大曽根まで。途中「ぱせり」という喫茶店に寄る。時々利用する所。よくあることだが4人席に一人客という状態の「満席」だった。「合い席で」といわれたが、「あ、いいです、いいです」といったん外へ出た。S子さんがちょっと不満そうだった。僕も未練気に振り返ると2人のお客さんが帰って行くところだった。続いて店のママさんが出てきて「大将、空けてもらったけど、行く?」と声をかけてくれた。もちろん戻った。この辺の気持ちを詳しく説明するのもナンだが、まず、自分ひとりならともかく家族3人で他の人と合い席は無理だろうし、つぎに4人席に1人で座っている人に他の人との合い席を頼めば、それでその人が帰るハメになったら、われわれが追い出したことになってしまう。だからまずこちらが引くところを示す、それで誰かが席を空けてくれればそれに甘える。もし誰もいなければそれはそれで仕方がない…そんなことを一瞬で考えたのだ。結果的には誰かが帰ってくれたことで朝食にありつけた。いまどきひとり300円でコーヒーにトーストと卵が付く。
さて、あとひと息で大曽根だが、駅の手前にユニー大曽根店があり、いつもここに寄って涼んでいく。時々は買い物もする。この日はT子(妹)用に折りたたみベッドを見つけ、購入を決めた。実は、今使っているベッドに猫がおしっこをしてしまい、今度は折りたたみがいいなと話していたのだ。3匹のうち誰が犯人なのかわかっていないのだが、限りなくクロに近いのがしろである(これが言いたくて書いてみた)。
ユニーを出るとあとは帰りのバス停まで炎天下を歩く。ずっと日陰だったがここだけはしかたがない。バスに乗ればまた涼める。ただ、時刻(行き先)によって自宅の最寄りのバス停が違っているので降りてからまた歩く場合もある。ありがたいのはT子の福祉乗車券のお陰で二人までは無料なこと(お陰でかなり遠くまで散歩に行ける)。
この日は午後、今度はクルマでユニーへさっきの折りたたみベッドを買いに行った。ところが商品が展示品しかなく、それも傷があるということで結局取り寄せということになった。こういう面倒なことは中々我慢しないほうだが、今日はこれからもうひとつ買い物を予定していたので渋々承知した。
それは、dysonのDC16という掃除機だ。前から自室の掃除用にハンディタイプの掃除機が欲しかったのだ。あの自信たっぷりのCMもさることながら、敬愛する森博嗣先生の「MORI LOG ACADEMY」の2008年08月28日のHRを読んでから決めていた。正直言って予算的にかなり苦しかったが、「これを買うまでは部屋を掃除しないぞ」というアホな決意でみるみる部屋が汚れるのを見て、もう二度と使わないつもりでいたクレジットカードを使ってしまった。この使用感についてはまた後日に。
 充電中の dyson DC16
充電中の dyson DC16
とはいうものの、この日以後体調をくずし、1週間たってもまだ調子が悪い。季節の替わり目というやつか。
2008年09月18日(木) 三連休(1)
今月13日から久しぶりの三連休があった。この頃は休みとなれば散歩、ウォーキングで、この時もT子(妹)と二人でよく歩いた。初日(土)は枇杷島まで歩き、帰りは城北線でという計画を実行した。41号線から庄内用水に沿って南西下し、西区の枇杷島スポーツセンターまで行き、ここで一休みしてから県道67号で庄内川の枇杷島橋を渡った。(写真は枇杷島橋から名鉄線を跨ぐ立体交差橋を望む)

城北線は枇杷島と春日井の勝川間のたった6つの駅の間を走るディーゼル機関車で、ほとんどが高架上を走り、眺めはいいが、枇杷島−勝川間430円とやや高い。写真は城北線のホーム。向かい側の電車はJR東海道本線の普通列車。

この日の夜、歩いて庄内川岸へ虫のすだく音を聴きに行った。月がきれいで写真も撮った。翌日の新聞で前夜が仲秋の名月と知って納得した。
2008年09月05日(金) 権力の構図
我が家で一番の老猫のすずが病気のようなので医者に連れて行った。いつも涎をたらしていて食べるのが辛そうである。体の毛もまるで毛玉のオバケだ。もう14歳になるのでトシかなと諦めていたのだが、先生の話では「口内炎です。あとは特に悪いところはないですよ」とのことで、注射を2本、あと体中を首と尻尾だけを残してバリカンで刈ってくれた。雄ライオンかプードルみたいな何ともいえないおかしい格好になったが、本人(猫)はいたって元気で一安心(今の写真はかわいそうなので昔のかわいい盛りの一枚を)。

元気がよく、すぐ家じゅうを動き回るようになった。怖いもの知らずで年長猫のミーコさん(当時5歳くらい)に飛びかかるようになった。親だと思っているのかも知れない。面白い見ものではあったが、ミーコさんには迷惑なことだ。我々も夜よく寝られない日が続いた。夜中にお乳欲しさに顔の上に乗ってきたりするのだからたまらない。
お乳を飲むときは両手(前足?)でしっかりと哺乳瓶を掴み、かっかっという調子で力強く飲む。これは見ていて感動する。命そのものという感じがする。
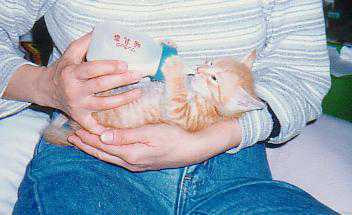

2008年08月31日(日 ) 洪水時のイメトレ?
8月も今日で終わり。久しぶりに一家3人で散歩。清水駅から大曽根へ回り、そこからバスで帰宅。暑さもやや納まり、すじ雲が見える。ただ、昨日おとといは県下大変な豪雨で、岡崎では死者が2人出た。あっという間に深さ2mもの濁流が家の中に入ってきたという。翌日には水は引いたが、家そのものが使えなくなったところがある。今まで自分がそういう被害に会うなんてあまり実感を持たなかったが、今回は初めて恐ろしいと感じた。実際28日の深夜の豪雨はすごかった。ザーッという雨音が恐怖を伴うのだ。それが長く長く続くととても不安になってくる。2000年の9.11東海集中豪雨のとき、自分ではそれほどに感じていなかった。あとでそのひどさを知ったのだ。今でも記憶に鮮明なのは、夕方退社後、すでに冠水が始まりひどい渋滞の国道19号線を車で走ったこと。左端で動けなくなっている車が何台もあり、その車内で必死に携帯電話をかけている人影を見たこと。行く方向がだんだんひどくなっているのを見て反対車線の方がまだましとUターンし、こちらもひどい渋滞の中をなるべく道路の中央をノロノロと進みながら当時の自宅(中川区富田町)へ帰ったことだ。帰ってからいよいよ雨がひどくなった。確か停電もあった。
今回も深夜になってから激しい雨が続き、次々に出される警報や聞きなれない「土砂災害警戒情報」などが一層不安をあおった。地域広報スピーカーが雷雨の中で初めて実際に使われるのを聞いた(いつも毎月1日の夕方にテストで流されていたのだ)。避難勧告がでたら速やかに避難するように、という内容だったと思う。一、二度玄関から外へ出てみたが、降りはすごいが団地の構内や駐車場などはまだ浸水していないようだったのでこの辺の川はまだ大丈夫だと思った。もし団地の構内に水が来るなどということがあれば、これはすぐ南を流れる庄内川の堤防の決壊を意味する。そうなったらもう命がけである。ベランダは地面から1m以上はあるが、2mを超える水が来たら部屋の中はもう逃げ場がない。家を捨てて団地の上階へ逃げることになるだろう。買ったばかりのテレビやパソコンの中のデータが消えてしまう。何をもって逃げようか、取りあえず現金と通帳と印鑑、保険証か。テレビやパソコンはテーブルの上に乗せておこうか。しかし、そんなヒマがあるだろうか。最後は家族3人の命が大事である。忘れていた、猫も3匹いるのだ。さあ、どうする…。
2008年08月25日(月) Tちゃんのお母さん
今夜はBSで「ジャイアンツ」という映画を観た。いろいろな意味で懐かしかった。確か3度目だ。うろ覚えだが、たぶん最初は自分が生まれ育った家の、近所の幼馴染の家でテレビを見せてもらったのだと思う。僕の家はとても貧しく、テレビなどは昭和の40年代にやっと中古を買ったくらいだったが、この幼馴染の友人、仮にTちゃんとしよう、Tちゃん家にはもう30年代前半にはあったと思う。彼のお母さんがやさしくまたきれいな人で、早く母を亡くした僕をかわいそうに思ったのか、いつも親切にしてくれた。テレビを見せてもらうだけではなくずいぶんいろんなことで世話になった。Tちゃんは長男で、下に弟が2人いた。この3人が僕の幼馴染の友達だった。他にもいたとは思うが、付き合いの濃さが違っていた。Tちゃんは僕より1つ下だったので学校では会わないが、帰ると彼以外に遊ぶ友達がいなかった。僕は子供のころずっとひどい脱腸で、それでずいぶん惨めな思いをした。学校ではいじめられ、銭湯では好奇の目で見られ、喧嘩をすると必ず「だっちょ、だっちょ」と囃される。ところがTちゃんたち兄弟は一度もそんなことを僕にいったことがない。たとえ喧嘩をしてもだ。今思うとこれはTちゃんのお母さんの教育というか、「M男君(私)に絶対そんなこといってはいけません」と言い含めていたと思う。子供のころにはわからないことを大人になってから気づくことはよくある。Tちゃんのお母さんはそういう人だったと今でははっきりわかる。
彼の家はそのころは炭屋さんで、薪とか竹などを販売していたので、木片がいっぱいあってそれでよくチャンバラをした。Tちゃんは何をやっても僕より少し上で、チャンバラでも3回に2回は僕が負けた。将棋も彼のお父さんに一緒に教えてもらいよく指したが、これも3回に2回は負けたものだ。さらに大人になってから囲碁もやるようになったが、Tちゃんは囲碁でも僕よりちょっとだけ強かった。ほんとに憎らしい奴である。
今はもう見かけないが、Tちゃん家にはサイドカーの付いた自転車(確か「横付け」といった)があって、それでお父さんが炭や薪をお得意さんに配達するのだが、時々Tちゃんたちがそれをお手伝いする。そんな時には僕もお供した。お手伝いというより遊びだった。一人が「三角乗り」という乗り方で運転し、他の者が押して走る、炭を届けたら帰りは交替で荷台に乗ったりペダルをこいだりして帰る。そういえば僕は家に自転車がなかったのに、いつの間にか乗れるようになっているが、これもTちゃん家のお陰だろう。
この横付けにはもうひとつ思い出がある。Tちゃん家の2軒隣に鉄の廃品回収業をしている家があって、そこにわれわれよりいくつか年上のお兄ちゃんがいて、彼がこの横付けに僕たち3人を乗せて、アクロバティックな運転で喜ばせてくれた。近くの小川に掛っている橋の上をサイドカーの車輪が橋からはみ出して急ブレーキで止まったときなどは、町中に響くような絶叫で喜んだものだ。今では考えられない遊びだ。
Tちゃん家では、長さ20cm位の薪を10数本針金で結えてそれをひと束として売っていた。針金は最初から輪になっていて(どこかから仕入れていたようだ)、それに電気のこぎりで長さを切りそろえた丸太をまず鉈で適当に割って薪にし、それを順に丸く詰めていき、最後の一本を他の薪で叩き込んでひと束にする。Tちゃんたちもそれをやるとひと束1円のおこずかいがお母さんからもらえた。僕も手伝ったような記憶がある。この薪作りの仕事を頭の大きな障害者と思しき人がよく来てやっていた(というか生業にしていたと思う)。一日に何十束と詰めて夕方お母さんからお金をもらって帰って行くのだ。僕たちがかーぶんすと呼んで気味悪がっていた人に、Tちゃんのお母さんはやさしい言葉をかけていたのを思い出す。
この町に50年住んでいた僕は、Tちゃん家とも50年の付き合いだが、だんだんと疎遠になっていった。何故だか理由はむつかしいが、僕が大人になるにつれて僕の方で距離を置くようになったのだと思う。あんなにお世話になったTちゃんのお母さんにほとんど何のお礼も言わないまま、僕はこの町を出た。もちろん挨拶には行ったが、その時の僕の「お世話になりました」には、こういう気持ちは込めていなかった。もう一度、それが言えるときが来るだろうか。
2008年08月22日(金) 我が家にも地デジが?
今年の4月にやっと薄型テレビを買った。地デジ(地上デジタル放送)や衛星放送が観られるやつだ。ところが衛星放送はちゃんと映るが、地デジが一部しか映らない。いま住んでる市営住宅の共同アンテナが地デジに対応していないようだ。あれだけ地デジに替えろと宣伝しておきながら、自治体が対応に遅れているのだ。ここの団地で国策 に応じて地デジ対応のテレビを買った人は一部しか観られないことになる。アナログも付いているだろうというのはごまかしである。なぜならアナログを観るためにテレビを買ったわけではないからだ。しかも地デジに移行するならアナログチューナはいらないのに、それも買わされているのである。まあ2011年7月24日までには市営住宅のアンテナは何とかしてくれるのだろうけれど、たぶんこの調子では大ぜいのテレビ難民が出ることだろう。つまりアナログ放送が終わるまでにテレビを買い替えない人たちである。一方で、大量の役に立たなくなったアナログテレビが粗大ゴミとして出てくる。それこそ何千万台という膨大な数である。リサイクルの可不可も大問題だが、まだ使用できるものを千万台単位で廃品にしてしまうあたりパソコンに似ているなと思う。パソコンの場合は自分で使おうと思えば使えるものを自ら廃棄するのだが、アナログテレビの場合と比べてどっちが罪深いだろう。
そんなこんなの地デジ移行であるが、完全移行して何年もしたら「あのなつかしのアナログ映像」などといって、今まで観て来た映りの悪い画像が別の価値を持つようになるのでは? ちょうどSPレコードの雑音をなつかしむように。これなどはさしずめ今流行りの「昭和懐古趣味」風潮に通じていくと思う…。
さて、これだけ嫌味を言ったあとでやや気が引けるが、地デジや衛星・ハイビジョンの画像は本当にすばらしいと思う。この映りのいいテレビに興味を持ったのは、2年前北区の瑠璃光町にあるサウンドオンで、ハイビジョン放送中だった相撲を大画面で観た時だった。特に相撲が好きなわけでもなかったが、土俵の土のリアルさに思わず見入っしまった。それ以来いつかは買うぞと決意していた。
買った機種はSONY−BRAVIA(KDL-40V3000)で148,000円だった。現在のネットでの価格を見てもそんなに変わっていないのでお買い得だったと思う。買って16日間はWOWOWやスカパーも無料で観られ、WOWOWではちょうど「敬愛なるベートーヴェン」をやっていてラッキーだった。これらはやがて観られなくなったが、NHKはすぐ衛星契約にしたので以来ずっとハイビジョンを楽しんでいる。。今一番気にいっている番組はNHK-BShiの「世界ふれあい街歩き」(参考:http://www.nhk.or.jp/sekaimachi/)である。外国のある街を文字通り歩いて巡るだけの番組であるが、やはりハイビジョンならではの臨場感がいい。
衛星放送は地上放送に比べ、教養番組が多いせいかNHKでも民放でも質が高い感じがする。朝のワイドショーがないだけでもいい。今後もどうか今以下にならないようにお願いしたい。
2008年08月21日(木) 猛暑は自分のせい?
やっと暑さも峠を越えたらしい。朝夕が涼しくなった。半端でなく暑いときは暑いことについて考えるものだ。地球温暖化、ヒートアイランド現象、自分の体力など。地球規模のことはともかく、いわゆるヒートアイランド現象は、自分の子供のころ(約50年前)と比べても明らかだ。夏は暑かったが、これほどではなかった。その原因として、室内冷房の排気熱を考えた。もちろん原因はほかにもあるだろうが、これが一番身近だと思う。つまり、自分でも家でエアコンを使うようになったので、その分外が暑くなったのだと思う。クルマにも乗るようになり、夏にはエアコンを入れて走る。だから降りた時は異常に暑いのだ。
そう考えると、何とかしてエアコンを使わないようにしようと思うが、これが中々むつかしい。7月の中頃までは我慢してきたが、とうとう根負けして使い始めるともうダメだ。その快適さに、もう無しではいられない。毎年同じことを繰り返している。ここからの脱却が課題である。
体力は、相変わらず週末の散歩(ウォーキング)を続けていることで、かなり自信をつけてきた。もちろん熱中症に気をつけながら、日陰を拾い、水分を補給し、適度に休憩を取りながら歩く。炎天下を歩くのはもちろん良くない。見る見る体力がなくなり、めまいや脱力感がひどくなる。だから7、8月のうちはK公園のまわりか、41号線や瀬戸線の高架の下の日陰の歩道を歩き、日陰がなくなったところからバスで帰宅する。
下の写真は、瀬戸線清水駅近くの高架下で毎月10と7の日に立つ朝市(いつも立ち寄る喫茶店の人に聴いた)。
感心したのはT子(妹)だ。いつも散歩に付き合うのだが、弱音を吐かない。イヤな時は露骨に顔に出るのですぐわかるが、決して嫌がっていない。むしろ喜んで付いてくる。S子はさすがに無理で、家から41号の高架下まで行く途中でネを上げる。一度は黒川まで頑張ったが、やはりそこからバスで帰って行った。決してムリをしてはいけないので賢明な措置。
決して人には勧められない。趣味として安上がりというより、貧乏くさい。汗まみれになってユニーなどに駆け込み涼んでいる初老の兄妹の姿など、人目にも異様だ。もっとカッコよく決めたいとは思うが、まあ、おいおい考えよう。

2008年04月06日(日 ) 年年歳歳花相似・・・
半年ぶりのブログ更新。きのう、今日と五条川で花見をする。
きのうはアピタ大口店(http://www.uny.co.jp/store/apita-ooguchi/index.html)に、今日はヨシヅヤ大口店(http://www.yoshizuya.com/store/store.html#ooguchi)にクルマを停めさせてもらい、お寿司かおにぎりを買って川沿いを散策する。お酒なしの地味な花見だが、最近はこういうやり方も多くなってきたように思う。バーベキューやキャンプのように賑やかにやっている人たちもいるが、一昔前のように必死で場所取りをしたり花寒のなかを無理に夜桜見物して風邪を引くなどということは段々減ってきた。これはとてもいいことで、お花見が上品になった。今日のように一番の花盛りに来ても、スーパーマーケットには楽に駐車はできるし、歩いていても座るところはすぐ見つかる。近年にない、いい花見である。

若い時は、桜の花などそれこそ飲み会の口実くらいにしか思っていなかった。桜が毎年同じように咲くのに、自分は段々年をとっていくということが自覚されることで、初めて桜を観る目が変わってくる。「年年歳歳花相似 歳歳年年人不同」である。この劉庭芝の詩では、桃の花を表しているようだが、今の日本人はやはり桜でこの興を感じている。7世紀の唐の詩人が詠んだ興を、我々も同じように味わっているのか、それはわからないが、日本人の桜好きにはそういう諦観的心理が根底にあるように思われる。西行法師の「願はくは…」にも、落語の「長屋の花見」にも、それは見られるだろう。

2007年09月17日(月) 残暑・酷暑・惨暑!
この3連休は酷暑だった。何でこんなに暑いのだ!(聞いているのではなくて感嘆文) 今日などは33℃! しかも湿度が高い。昨夜は久しぶりに徹夜で飲んだ。同じ団地のS木さんと。8時くらいから11時まではY老の滝で、そのあとS木さん宅で4時まで。朝刊が来たのを見てヤバいと思って帰る。それから昼12時まで爆睡し、散歩へ。この残暑の中、公園では少年たちが野球してる。大丈夫かと思う。しかし、そういっている自分が大丈夫か。
結局、1.5時間くらい歩いて帰る。木陰を選って歩いているのでそれほど参らなかったけれど、帰宅途中の歩道上は炎天下! 紫外線対策で長袖シャツなのだが、いつも脱いでしまいたい衝動にかられる。人から見るとちょっとアブナイおじさんで、前から歩いてきた若い親子が避けていく。いけない。もうすこしルックスを考えないと。

2007年09月12日(水) 安倍さんの辞任
今日、安倍さん(首相)が辞任を表明した(こういう時事ネタはまめに書いていくとあとで見たとき何かと参考になる)。特に感想はないが、とにかく「テロ特措法」は打ち切って欲しい。これは切に願う。10月で期限が切れるせっかくのチャンスである。私は「ペシャワール会」(https://www.peshawar-pms.com/)の会員であるが、アフガニスタンで20年以上医療活動や灌漑・水利事業を続けている中村哲先生たちの安全のためにそれを切に願う。このまま自衛隊がアメリカ軍への給油活動を続けていけば、日本はアメリカと同列のアフガン侵略国であることがますます明らかになり、アフガニスタンの人たち、特に反政府勢力の日本に対する感情を悪化させ、ひいては現地日本人に対するテロの危険性も増える。それどころか、最新の「ペシャワール会報」(中村先生の報告)によれば、『難民強制帰還政策」が性急に進められた余波を受け、「難民診療機関」と目されるPMS(ペシャワール会医療サービス)基地病院も、閉鎖に追い込まれる可能性が出てきた。』というのである。何という非道理! 20年以上もアフガニスタンの人たちのために活動してきたPMSを、親米政府がつぶそうとしているのだ。最近の小沢さん(民主党代表)は、まるで共産党みたいだ(ジョーク)。「テロ特措法」を延長しないという、それだけで十分。ぜひそのままがんばって欲しい。絶対裏切らないでね。ただ、自民党は同法補則4項(参考:http://www.cas.go.jp/jp/hourei/houritu/tero_h.html)に基づき別法により「効力を延長」することを狙っているともいわれる。姑息ではあるが、小沢さんがしっかりしていれば大丈夫ではないか。

2007年09月09日(日 ) 何人かの天才
9月になって初めてのブログだが、ここしばらく自分のHP全般を修復・改良していたので、それが終わってから書こうと思っていたら今日になってしまった。相変わらずHTMLのタグを自分でテキストで書きながらHPを作るのだが、フレームの作り方を覚えたのが改良の動機といっていいかも。難しいものと思っていたが、案外簡単だったので、いっそのこと全ページごとフレームにしてしまおうとして時間がかかってしまった。
いつもながら思うがHTMLのタグを作った人は天才だ。HTMLと同様にタグを使ってどんな数式でも作ってしまう「TEX」を作ったクヌース先生も天才だが、世の中には本当の天才が何人もいる。僕が天才というときは、仕事が鮮やかで誰にでもわかりやすいことが条件である。ガロアも天才だが、彼の仕事は当時の一流数学者にもわからなかった。しかし、今は大学で誰でも学べる。しかも鮮やかさにおいて他の数学者の仕事の群を抜く(これは彼の「ガロア群」に掛けたダシャレ)。また、日本の高木貞治先生の「類体論」もわかりにくい。しかし、これはきっと先生のいうように「類体論の明朗化は、恐らくは、新立脚点の発見に待つ所があるのではあるまいか。」(「代数的整数論」序)だとすれば、この「予言」もまた天才的といえるかもしれない。
天才といえば、今、マーラーの「巨人」を聴きながらこれを書いているが、彼も天才の一人だ。自分のHPでいくつかのクラシック曲について批評を書こうと思っているのだが(現在のところ、1曲だけUP)、印象的なことはともかく、キチンと書こうとすると、資料を渉猟するだけでも多くの時間が必要になり、つい二の足を踏んでしまう。で、こういうところで適当なことだけ書いてお茶を濁している有様である。

2007年08月23日(木) 自棄的発言?
我慢し切れなくてクーラーを使い出したらやっと少し涼しくなった。しかしどうも夏バテらしく、元気が出ない。熱中症でなくなった人が大勢いる。中には散歩から帰って倒れ、そのまま死んでしまった30代の人もいた。ちょっと怖くなった。年寄りの冷や水ならぬ年寄りの暑さ我慢はやはりよしたほうがいいようだ。この暑さは地球温暖化の影響に間違いない。そうでない説もいろいろ取りざたされているが、あきらめた方がいい。地球温暖化のせいである。従って今年だけではなく、来年も再来年ももっと暑くなるだろう。そして我もわれもとクーラーを使い、ますます暑くなるのだ。やがて電気の使用量が供給量を超え、パンクする。クーラーがいっせいに止まる。暑さのせいでばたばた人が倒れる。社会問題、政治問題化するが、誰もどうすることもできない。…ところが、不思議にもその後急に涼しくなる。クーラーの使用をやめたおかげでヒートアイランドが収まったのだ。考えても見ると、一人ひとりのいる小さな空間をクーラーで冷やしてその中の熱を外に出せば、平均した温度は昔と変わらなくても「外」は暑くなる道理だ。もし冷やしたいのであれば全体を冷やすことを考えなくてはならない。自分のいる小さな空間だけを快適にするために、外を暑くしてもかまわないという考え方が間違っているのだ。ただ、今はもう自分を「外」の熱気から守るためにクーラーが必要である。そこまできてしまった。人間が賢くこの状況を変えられないのなら、自然が強制的に法則を貫くことで人間に思い知らせる以外にない。
北極の氷がこれまででもっとも少なくなったそうである。理論的には、もしすべての北極の氷が解けても海面は上がることはないはずだが、北極の氷が解ければグリーンランドの陸上の氷だって解けて海に流れ出すし、南極の氷も解け出すだろうから、海面は確実に上がる。海岸線が上昇し、日本は何パーセントか国土を失うかもしれない。
私たち団塊の世代はこれから数十年、年金問題だけではなく、環境的にも大変な時代を迎えることになるだろう。人によってはとても悲惨な晩年を送ることになるかもしれない。大地震か、巨大な台風か、あるいは熱波、反対に極寒の中に身を置き、それらと戦い、人類の未来に絶望しながら死んでいくのかもしれない。もちろん、私もその中の一人としてとてつもない苦痛を味わうことになるのだ…。
私がこんな自棄的なことを書いているのは、文字通り「我亡き後に洪水来たれ」の心境になっているからか。共産党だ、弁証法だ、数学だ、などと言いながら好き勝手な生き方を貫き、還暦を迎えてもう十分生きたからあとはご随意に、といっているのだ。私は人より格別恵まれて生まれたわけでもなく、より幸せな人生を送ったとも思っていない。でも自分に出来る限りの力で今の人並みの生活を築いてきた。それをよしとしているだけだ。
今の自分に出来ることは、これからの人類の未来を出来る限り見届けることだろうか。
2007年08月18日(土 ) 花火と送り火
大須へは行ったものの、それ以外はどこへも行かず、長い休みをホントにグータラで過ごした。とてもよかった。本を読んだり、数学を研究したり…のはずが、何もせず、ひたすらベッドの上で寝てばかり。ただ、ハンパでない暑さには参った。今年からクーラーを使わないことを決心していたのに、とうとう負けてスイッチを入れてしまった。8/13に関門海峡で花火大会があるというのをNTTのHPで知って、当日ネットでの生中継を楽しみにしていたのにぜんぜん繋がらなかった。他のライブ中継は見られたのでやはり関門海峡ばかりにアクセスが集中したせいだろうか。同じNTTのライブ中継で、8/16に京都の『五山の送り火:「大文字」「妙法」 』があるというので、今度は絶対見ようと、同日は朝から繋ぎっぱなしにしておいた。苦労の甲斐あって今度は無事見ることが出来た。関門の花火大会も五山の送り火もNHKが生放送でやっていたそうだが、ネット配信のほうが音がなく、よけいな人や話がないので良かったように思う(関門海峡の花火の方はテレビで見たが、明らかに人や話が邪魔だった)。この送り火を見ながらディナーという企画のツアーがあるそうだが、S子(妻)の手作りのカレーを食べながらこれを見たのですごい贅沢をした気分である。インターネットの醍醐味といっていいだろう。
これは中継画面の一部だが、実際はもっときれい。


スズキユカさんの絵は僕の想像してた「女王」の世界とかなり似ていると思った(ひとつ、ロイディだけは違った。僕の想像していたロイディはあんなにイケメンではなく、もっとマシン的で、服装もモビルスーツを曲線風にしたものを考えていた)。森先生の小説は読んでいてとても視覚的であり、地の文をそのまま想像すれば読んだ人はみなよく似た世界を描くのではないか。
あと、森博嗣原作のコミックでは「F」と「冷たい密室と博士たち」(ともに浅田寅ヲ・画)、「黒猫の三角」(皇なつき・画)を前に読んだ。繰り返し読めるほどに面白い。原作の奥深さが絵によく反映していて、現在の漫画の持つ表現力の奥深さを感じる。
2007年08月12日(日 ) 大須はどこへ行く
夏季休暇(お盆休み)の二日目。家族で大須へ(お盆は大須である!)。いつもはクルマで直接行くところを、今日は平安通にある塾(私が働かせてもらっている所)の駐車場までクルマで行き、そこから地下鉄で上前津まで行った。何といっても駐車場代がいらない。それに地下鉄はT子(妹)の福祉乗車券で二人までタダ。だから一人分の乗車券だけで済む。それもS子(妻)の買い置きのユリカを使って今日の交通費はタダ感覚(それをいうとS子は怒るが)。昼食を取らないで来たのでさっそく「あした葉」でミニ天丼定食(¥830)を。ちょっと高いけどおいしい。となり席の仲良しカップルの彼が食べていたカレーうどんがいいにおいを立てていてそれもおかずになった。食後は定番の観音様にお参り。この暑いなか、境内の入り口に托鉢のお坊さんがお経を唱えていた。思わず合掌・喜捨…。「お体を大切に」と言われた。なんとなくありがたい気分に。
そのあと、ほんとに久しぶりに第2アメ横ビル→EDM(エンターテイメントデジタルモール)本店→第1アメ横ビルをざっと廻る。1年ぶりなのに(1年ぶりだから)ずいぶん様変わりしていた。古くからの店は相変わらず客がなく、だんだん寂れていく。ゲームセンターやパチンコ・スロットのような店が増えていた。大須はこれでいいのか? 10/20、21日「大須大道町人祭」に加納真実(参考:http://www5f.biglobe.ne.jp/~kanoumami/")が来る。楽しみ。
今日はいい写真がない。大須では信秀廟(信長の父の墓所)の写真を撮っただけ。でもお墓の写真では何なので、

2007年08月10日(金) 明日から盆休み
広島・長崎の原爆祈念日が今年も過ぎた。まだ一度もこれらの地に行っていない。これは良くないことだ。せめて広島だけでも行きたい。8年前の新潟・国上山行きのときのように着いてすぐ帰ってくるような(宿泊なしで)やり方でもいいから行こうかと考えた。ただ、あの時よりかなり年月が経っているので体力が心配。人に迷惑をかけてはいけない。とするとその分お金をかけて実行するべきだろう。やはり宿泊すべきか。だったら毎年ある原水爆禁止大会に参加すればいいのだ。「広島」にはやはりこの方法で行くべきだ。何となく「日本原水協」には抵抗があるが、「広島へ行く」の一点では頼りになりそう。来年行こう。今、参考にとネットのニュースで「原水爆禁止大会」を拾って見た。日本原水協だけでなく「原水禁国民会議」もまだやってるんだなあと…(感慨)。昔、民青にいたころを思い出す。Y幡学区地域を班の仲間と署名で廻った。お金も集めて、それで代表を世界大会に送り出して、けっこうまじめにやっていた。20歳のころか、いや、22歳?。わからなくなった。…もう、そういう年齢なのだ。
ところで、題にも書いたとおり、明日から16日まで休みである。少しだけ塾の夏期講座があるが、まあ久しぶりの長期休暇となる。いろんなこと考えているけど(広島行きもそのつもりだった)、結局、ぐうたらしそうである。

2007年08月05日(日 ) だてに散歩してるのでは…
やっと夏らしい日になった。が、蒸し暑い。この湿気が早く取れて欲しい。週末の散歩も続いている。気候が良かったころには街中や郊外のいろいろな所へ行ったが、このごろは炎天下を歩くのはよくないので、近所の公園の散策路を、木陰を選んで歩いている。そこをぐるぐる廻っていると5〜6kmになる。家からの往復で2kmほどあるのでトータル7〜8kmは歩いていると思う(計測は万歩計)。公園では、炎天下で野球やテニスの練習をしている人、木陰でゲートボールをする老人会、遊びに来た親子・おじいちゃんと孫など、さまざまな人が休日を楽しんでいる。ただ、今日はゲートボールをしていた一人の女性が倒れ、救急車が来ていた。原因はわからなかったが、意識もあり、お仲間に謝りながら運ばれていったので大したことはないと思う。
あと、変わったところでは、近所(だと思う)から自転車でやってきたじいさんが、朝からカップヌードルを食べていたり、また、ホームレスと思しきおじさん(多分この公園が自宅?)が風通しのいいベンチで延々寝ていたりする。自転車のじいさんがカップを公園に捨て置いていったのにはがっかり。
いつもは野球かソフトボールの試合が行われるグラウンドで、今日は盆踊りの準備が始まっていた。今夜だろうか(そういえば昨夜わが団地内でもあったんだ…)。
毎週やってきていると、常連さんのような人がいることがわかる。年齢、服装などいろいろだが、面白いのは、コースは互いに逆周りで、散策路でも日の当たる所を避けて木陰の脇道(雑木林の中)を歩いていると、意外なところで出くわしたりして、思わず苦笑い。誰でも考えることは同じなのだ。

ついでなので、書いておくが、この考え方は、先日書いた「弁証法」の一例になる。自然数だけでは引き算が不便であることから整数が考え出され、同様に自然数での除法から分数(=有理数)が考え出されたように、整数の独特な性質(倍数・約数)をもっと抽象的にすることで(イデヤルが考えられて)「代数的な整数」における素因数の一意分解を実現したのだ(と思う)。こういう理論の発展の仕方は形式論理学や形而上的な考え方からは生まれ出ない。しかし、弁証法を知っていても、だからといってすらすらこういう風に考えが進むわけではない。理論の「飛躍」のためにはどうしても天才の努力とひらめきが必要なのだ。ここがむつかしい。
2007年08月02日(木) 幼虫が嫌いな人は要注意
8月になった。今は台風(5号が九州に上陸)が来ているから曇っていて蒸し暑い妙な天気だが、そうでなければもっとカラッとした穏やかな夏になるだろうか。そうなれば好きな季節である。小学生の頃の思い出。何ヶ月か子供向けの学習月刊雑誌を父が取ってくれたくれたことがある。たぶん学校からの紹介があって私がせがんだのだろうが、あの父がよくOKしたものだと思う。それはマンガや絵を多く使って理科や社会の学習をさせるという雑誌で、メンデルやニュートンなど偉人の生涯をマンガで読んだのを今でも覚えている。理科の実験の絵で、炭酸ガスをひらがなで「たんさんガス」と書いてあったのを「たくさんガス」と読み違え、「ああ、たくさんガスが出るんだ」と思ったりした。
この本を、夏休みに青空の見える部屋の縁で仰向けになって夢中で読んでいた。ふと空を見ると遠くの入道雲の先端がもくもく湧き上がっているのに気づいた。10分も立つともう全然違った形になっている。見る見る変化していくそのダイナミックさは今でも夏が好きな理由のひとつである。その頃の夏はどこかさっぱりとしていて、炎天下は暑いが木陰やよしずの陰に入ると涼しかった。空も安定感があり、入道雲もやや遠い感じで穏やかだった。夏の定番のスイカやカキ氷もそれなりによく食べた。こうしてみると私も人並みに幸せな子どもだったように思えてくる。

 (噴水ではなく、アカトンボを撮ったもの (○の中。右の写真は2023/09/15の復元で追加処理。拡大可))
(噴水ではなく、アカトンボを撮ったもの (○の中。右の写真は2023/09/15の復元で追加処理。拡大可))
今、思い出したが、アルキメデスの生涯もこの本のマンガで読んだ。王冠の中の混ぜ物を王冠を壊さずに調べる方法を入浴中に思いついて裸で外へ飛び出したという有名な逸話もこのとき知った。だからアルキメデスも好きな歴史上の人物である。数学の話で「アルキメデスの公理」と呼ばれているものに、「a、b 二つの正数(a>b>0)があるとき、この二つがどんなに差があっても、あるnという自然数があって a<nb とすることが出来る」というのがある。「公理」というのは証明なしに用いられる定理のようなものである。彼はこれを用いて、現在なら積分で行うような計算(曲線で囲まれた部分の面積など)を2千2百年以上も前に解いている。
この「公理」がどのくらいすごいかというと、これを現在の数学で証明しようとすると、19世紀になってから確立された「連続性の公理」を必要とするのであるが、逆にこの連続性の公理を「アルキメデスの公理」で証明することができるのである。言い換えれば、この二つの公理は同じものなのだ。かれはそういうものを紀元前に発見しているのである。
今日の話は、子どものころの学習が如何に現在の自分に直結しているかを言いたかったのである。
↑ 散歩の途中、足元で見つけた。「アオイラガ」(青刺蛾)の幼虫か。(参考:http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/youtyuu/)
2007年07月27日(金) 暑い思い出、寒い思い出
…といっていたら今日、梅雨が明けた(昨日参照)。日中は会社のクーラーの効いた部屋でPCの前に座っているだけなので外の暑さがわからない。夕方、帰るときに「ああ、今日は暑かったんだな」とわかる。これは幸せなことなのか。若いとき、夏は暑く、冬は半端なく寒かった。一番覚えているのは、ある零細企業に勤めていたとき(20代)、大阪への出張で某パンメーカーの工場のベルトコンベアを解体する仕事をしたときだった。真夏で、廃工場の屋根裏に上ってガス溶接機でコンベアを切断するのだ。すぐ上はスレートかトタン板の屋根が夏の日差しで焼けるように熱い!。そのすぐ下で、ガス溶接を使うのだから炎熱地獄である。1時間といられない。すぐ下に逃げ下りて自販機でジュースを買って飲む。500mlを12本飲んだ。丸2日その仕事だった。出張だから逃げることも出来なかった。
寒い方では、しばらく新聞配達で生活していたときの冬の早朝の寒さ。これは当然。それよりもまだクルマがなかった頃、遠い出先から帰るときにバス停で待っているときや、木枯らしの中を歩いて帰るときの寒さのほうが身にしみた。今でも真冬にバス停で待っている人を見ると何だか気の毒な気持ちになる。昔のほうが確実に寒かった。地球温暖化を肌で感じている。子どものときの手足の霜焼けや皸(アカギレ)は本当にひどかった。赤く腫れてかゆく、やがて紫色になり皮膚が破れてぐちゃぐちゃになった。母がお湯で温めてくれたのをおぼろげに覚えている。その母が死んでからは、私は学校へ行くときも靴下や足袋を履かずにいたので、登校途中、どこかのおばさんが靴下を一足くれたのも覚えている。
昭和30年代をノスタルジーを持って描くのが流行っているが、あれはいいとこ取りばかりである。確かに今から思えば懐かしいところもあるが、私には懐かしさよりは、忌まわしい思い出の方が多い。時々給食のない日の弁当で、ゴハンに醤油だけかけて持って行き、同級生に「それ、醤油だけじゃないか」といわれたのに対し、「これはうどんの汁だ」と言い返したこと。自転車が欲しくて、夜、友達の家の自転車を勝手に乗り回して見つかり、叱られたこと。土曜日の昼ごはんに、水で溶いたオリエンタルカレーを冷や飯にかけて食べたこと。友達の家でテレビを見せてもらって「さ、もう遅いから帰ってね」と言われて帰るときの寂しさ…。
日本が豊かになったことは間違いない。今の自分が大した努力もせずに今のような生活を送れるのが何よりの証拠。しかし、それであのときの自分が報われているとは思わない。今の自分を持ってあのときの自分を微笑を持って思い出すなどということはできない。それは永久に報われない。極端な貧乏は、子どもを卑屈にし、自信を失わせ、人を羨み妬むようになる。悪いことも色々考えるようになる。子どもには貧困は絶対的によくない。特に教育の場での不平等は決定的である。
話がそれるが、最近子どもの給食費を払わない親のことや、学校や先生に理不尽な要求を突きつける親のことがワイドショーなどで取り上げられているが、私は何故未だに給食費などを無償にしないのかがわからない。教育費をタダにすればこの問題は解決する。学校をタダにし、基礎的な学力を身につけ、人に迷惑をかけない人格を造ることを目的にした教育を行えばこうした問題は起きない。高校の義務教育化、教科書の無償(一部実現?)、筆記・絵画用具、体操服、そして給食等、教育の無償をなぜ名実ともに実現しないのか。教育にどんどん家計のお金を取られれば、親が自分たちの要求を出すのは当然である。カネを払っているのだからいいたいことをいうのだ。

2007年07月26日(木) 梅雨の末期にイライラ・・・
まだ梅雨が明けない。明らかに例年より遅いはずだ。冷夏の予想も出てきた。が、たぶん暑くなるだろう。なぜなら梅雨の今がとても蒸し暑いから。このごろ会社でACCESS2003を使って開発の仕事をしているのだが、ひとつ、フォームのコマンドボタンの背景色が変えられないのに苛立っている。ネットで探してもやはりないようだ。ラベルかテキストボックスで擬似的にボタンを作る以外になさそう。でも、なぜコマンドボタンは背景色が指定できないのかがわからない。何か不都合があるか? ないと思う。不都合なら変えなければいいのだから。Me!Button_Name.Backcolor=xxxxxxと打っても構文エラーにはならないのに、実行したときに初めて「サポートしていません」というエラーになる。本当に腹が立つ。別にどうしても色を付けたいわけではないが、意地になっていたのだ。気がつくと午前中が過ぎていたから、仕事にも差支える。
結局ラベルを用いて擬似ボタンを作って色を付けたのだが、今度はその擬似ボタンのイベントプロシージャのVBAが書けない。実はソーステーブルのデータによっていちいちフォームを生成し、その中にボタンをデータごとに異なる数だけ追加したいのでそのたびにVBAも書きたいのだ。例えば擬似ボタンは、追加したときは「浮き出し」にしておき、クリックしたときに「くぼみ」になり、離したらまた「浮き出し」になるようにVBAを一つひとつのボタンに持たせなくてはならないが、これをボタンの追加のときにどうやったらいのかわからない。
まさか、コマンドボタンだけ背景色のプロパティを付け忘れたのか? だから理由もいえないのではないか。あの、グレーしか使えないコマンドボタンに腸(ハラワタ)が煮えくり返っている人はゴマンといるに違いない。
2007年07月19日(木) 新潟県中越沖地震
新潟・長野でまた大きな地震があった。わずか3年の間に2度も震度6強の地震に見舞われるなど、本当に気の毒なことだ。名古屋で思いつくのは「阪神・淡路大震災」のときの震度3くらいで、私は震度4以上は経験したことがない。だから被災地の人たちが6強を経験して、どれほど驚き、恐怖を感じたかは想像を超える。これから自分が死を迎えるまでに巨大地震を経験する確率はかなり高いとみるべきだろう。一説には、次の東南海地震が2030年までに発生する確率は50%であるという(参考:http://www.jishin.go.jp/main/chousa/kaikou_pdf/nankai.pdf">「地震調査研究推進本部『南海トラフの地震の長期評価について』」)。この論文は2001年に出ているのだから、それから6年経った今、確率はもっと高くなっている。これはもう来るものと覚悟すべきだろう。では、どうすればよいか。家具の補強、防災用品の準備、いざというときの連絡方法など、人知の及ぶ範囲で為すべきことをなし、あとは運を天に任せるしかない。
阪神・淡路大震災のときもそうだったが、こんなことがあっても自分は普通に会社に行って仕事をし、帰ってからテレビを見て「気の毒になあ」といいながらご飯を食べているのだ。釈然としないとはいえ、仕事を捨ててボランティアに行くことができない。せいぜい小額の義援金を寄せる程度のことで自己満足するしかない。
人は、どうやって生きるべきかを考えるとき、自分が助けることができる力のあるうちは人を助けるべきだと思う。しかもそれを全力で行うのだ。人間はいずれは死ぬ、滅びることがわかっていてもそうするべきなのだ。それが生き物なのだと思う。人のために生きることで人は人生を全うできる。社会の仕組みを利用して、社会の歪によって生まれた我欲のために生きることは、そのことで他人の生を踏みにじってるのだから正しい生き方ではない。
2007年07月15日(日 ) 台風一過
台風4号は予想進路のもっとも南側を通って、本州直撃は逃れた。しかし、また死者が出た。しかも少年が亡くなっている。これは由々しきことだ。台風で子どもが死ぬことはあってはならない(大人ならいいという意味ではもちろんない)。今朝はまだ雨が残っていたが、やがて上がりそうなのは空模様でもわかった。とりあえず傘を持って散歩に出た。友人がこんな日に横浜へ行くと言っていたのでどうなったかメールしてみると、予定通り新幹線は出たものの静岡でもう1時間くらい止まったままだそうで参った、という返事。台風が新幹線に追いついた感じ。気の毒に。
今日は名鉄小牧線に沿って歩く。時々クルマで通っている道だが、歩くと発見が多い。高さ3メートルもあるお地蔵さんや「今上天皇御駐屯地」(大正3年)など珍しいものを見た。

天気の方は、すっかり、晴れ。台風一過。蒸す上に日が差して暑くなってきた。当初、駅を2つくらい歩いてから電車で帰るつもりでいたが、なかなか駅が現れず、疲れてきた。どうもひとつ知らずに過ぎたようだ。「西行堂小橋」という興味ある名の橋もあった。なぜこんな所に西行の名が…。


電車を降りて家路を歩いていると、さっきまで家から遠ざかるように歩いていたのと不思議な違和感が感じられた。これは普段クルマや電車で行く道を、テクテク歩いたときの違和感のちょうど逆なのだろう。大げさにいえばタイムマシンやワープ飛行の感覚に近いのでは?(どちらも経験ないけど…)
2007年07月14日(土 ) 台風接近
今日も雨。台風4号が日本を狙っている。進路予想はまさに名古屋を目指していて、現在、沖縄・九州がひどい目にあっている。このごろの雨の降り方は確かに異常だ。それにしても国民の危機感は希薄だ。マスコミも企業も言うほどには切羽つまっていない。自分でもそうだ。私はもともと人間が地上最後の「最高生物」とは思っていないので(昔、ロボットが人類の後継者になるのではという小論文を書いたことがある)、別に人類が滅びてもかまわない。ただ、人類はそれほどバカでもないとも思う。人類が登場して300万年として、その99.7パーセントの原始時代を経て0.3パーセントの文明社会を築いた人類がそれで終わりということはないだろう。これまでにも絶滅の危機はあったが、なんとか乗り越えてきたのだ。
問題は「個人」である。交通事故とか、癌とか、冤罪とか、一人ひとりがひどい目に会うことはこれからもなくならない。誰がその籤を引くかは偶然であるが、きっと誰かは引く。必然は偶然を通して実現する。だから「運命」はありえないが、自分だけは大丈夫という自信にもまったく根拠がない。こういう悲劇をなくす方法は人間の社会的活動だけに掛かっている。交通事故を「クルマが人身事故を起こすこと」と限定して考えれば、クルマを無くすことで交通事故は絶滅する。しかし、クルマを無くすことはできないから、せめて事故を減らすことを考える。「減らす」とは、逆説的に言えば、ある程度は(犠牲者が出ても)やむを得ないという考え方である。昨日の日記の「近づく」話と同じで、目標を立てそれを打ち破るのだ。これがクルマを使うという条件のもとで交通事故を無くす最も科学的な方法である。
2007年07月12日(木) 嵐と弁証法
今日はひどい雨だった。朝、会社についたとたん「バケツをひっくり返したような」土砂降り。雷も鳴っていた。瞬間的な停電もあったようで、一度だけ全館の蛍光灯が一瞬消え、すぐ戻った。パソコンにも影響が出た。私はずっと会社で大丈夫だったが、夕方仕事を終えて帰ると玄関に安物の傘が見るも無残にぶっ壊れていた。聞かなくても想像はついたが、T子(妹)が「お医者さんの帰りに雨がめちゃめちゃ降ってきて風で傘が壊れてびしょぬれになったんだよ」とそのまんまの話。S子(妻)は「今にも雨がふりそうなのに薬の出るのが遅くていらいらした。案の定、外へ出たとたんにザーッよ!」と、空にではなく気の利かない(?)薬局にお怒り。妻は以前、「まさくん」という4コマ漫画でもあまりの降りに怒っていたことがあった。見たい人はこちら。
 味美(アジヨシ)のあじさい
味美(アジヨシ)のあじさい
例えば、昨日の文で「主観はどこまでも客観に近づける」と書いたが、この「近づく」とはどういうことかを考えてみよう。「AがBに近づく」とはAB間の距離が縮まることだ。でもこれは「近づく」を「縮まる」に言い換えただけある。正解は、「BがAとの間にどんな距離を実際に作ってもAはそれを打ち破ってその中に入ることができる」ということ。例えば、A=(0.1)nとし、このnをn=1,2,3,4,…と、どんどん大きくしていくと、Aは0.1、0.01、0.001、0.0001、… というようにいくらでも0に近づくことができる。これを証明するには、0の側で任意の正の数ε(イプシロンと読む)を築いたとき、εに対してある自然数Nが決定し、Nより大きいすべての自然数nについてA=(0.1)n <εとすることができればよい。なぜなら0の側でどんなεのカベを築いても、Aはそれを破ることができるのだから、Aはどこまでも0に近づくことができる。(コーシーの収束条件)
以上は直感でも理解できることだが、計算で証明することももちろんできる。ここでも「カベを築く」とか、それを「打ち破る」など、「対立と闘争」の用語が出てくる。「対立と闘争」は弁証法の基本概念のひとつだ。
2007年07月11日(水) 主観と客観
この1ヶ月ほど、珍しく小説を書いていた。「引越しと殺人事件」というのだが、初めはこのブログの記事として書いていたものを途中から「小説」にしたもの。まあ、ブログの記事全体が虚構といえば虚構なのでたいした違いはないのだけれど、読む人の中にはそう思わない人もいるのではっきり「作り物」にしておこうと思ったのだ。新聞の記事でもテレビの映像でも、それが事実をとらえたものではあってもやはり虚構になる。記事にはそれを書いた人の主観が入る。映像では撮影の時間的前後がカットされる。いや、直接に客観的事実を「見る」こと事態、すでに「虚構」である。古代ギリシャ哲学以来の主観と客観の問題である。しかし大事なことは、主観はどこまでも客観に近づけるということである。主観の極限が客観であり、主観は客観に収束するのだ。
議論は主観と主観のぶつかり合いだが、その中から客観が見えてくる。最近の人(若い人だけではなく)は議論をしないというが、それは議論のテクニックを誰も教えないからだ。教育の現場では、学生はお互い「みんな仲良く」「平和に」「楽しく」暮らすことを教えられ、テストや受験で激しい競争を強いられる。テストは主観(学生)どうしを議論させるのではなく、それらを「管理」するのが目的だから永久に客観には近づけない。表面的な対立を避けているだけであって「ぶつかり合い」は何らかの形で現れる。それが傷害や殺人などに至るのは言語道断としても、社会的な「勝ち組・負け組」に収束することもたいした違いはない。それは対立の絶対化を目指すものである。しかし「絶対的な対立」もまたあり得ない。そこからまた新たな闘争が始まる。
「対立と闘争」とは、今日では古いとされるイデオロギー的な概念だが、一方、科学的な概念でもあることは間違いない。

2007年03月24日(土 ) 夢(続き)
「夢」という題で書き始めたのだが、子どものころの家の話ばかりになった。さてそんなうちでも来てくれるという奇特なお嫁さんがいて、私は結婚したが、家のことは相変わらず無頓着だった。S子(妻)は裏庭の流しで洗い物をし、洗濯も盥(タライ)だった。コンロはさすがに七輪ではなかったが、ガスはまだ引いていなかったので、しばらく灯油コンロを使った(「ガスに負けない火力」という宣伝文句があった)。それから10年くらいのうちに、台所らしいものもでき、水道も家の中、洗濯機も冷蔵庫も買った。これらはすべて妻がやったのだ(冷蔵庫がなくて、鴨居にひもで吊るしておいたマグロの刺身を飼い猫に盗られ、妻がべそをかいているのを横で笑って見ていたのが私である)。こうして最低限、人の家らしくなってきたのだが、長屋全体の老朽化は免れず、私もいつまでここに住めるのかは怖くて真剣には考えていなかった。
3軒長屋の真ん中の家でやもめ暮らしをしていたおばあさんが亡くなったことがきっかけで、いろいろあったが結局立ち退きが成立、私たちは市営住宅に引っ越した。始めは緊急ということで同じ区内に、それから現在の北区の市営住宅に落ち着いた。前の家の夢をよく見るようになったのはつい最近である。それがなぜか古い汲み取りのトイレの中や、壊されて屋根のない部屋でコタツに入っているところだったりするのだ。これはなぜだろう。またあるときは、家(前の)の近くの信号交差点の真ん中で空を見ていると、暗い空に不気味な得体の知れないものがいっぱい飛んでいたり、逆にきれいな星座がたくさん見えたりすることもある。今の家の夢はまだ一度も見ない。必ず前の家だ。登場人物は現在の家族(3人)のほか、死んで28年にもなる父もよく出てくる。母はさすがにでてこないが(母は今年で死後50年になる)。
生家はとっくに壊され、今は駐車場になっている。前に住んでいた所には何の未練もない。以前に比べれば今の生活は天国である。風呂はボタンひとつで沸く。ガステーブルや湯沸かし器もあるし、液晶テレビ、DVD、パソコン、クルマ等々。風呂に入りながら、「オヤジにもこの風呂にいれてやりたい」とよく思うし、母親がいたら毎日塾や会社のことを話して自慢しているだろう・・・などと考える。そのことと家の夢が関係あるのだろうか。今の生活がまた壊れて以前(の家)のような生活に戻ってしまうことへの恐怖心だろうか。
ひとことで言えば前の家は、「懐かしいが二度と戻りたくはない」ということだ。

2007年03月22日(木) 夢
今のこの団地に引っ越してからもう5年になるが、いまだに生まれた家の夢を見る。その家は県道沿いの店舗付きの3軒長屋の一軒だった。最初に建ったのはおそらく終戦直後だろう。私がものごころついた頃、その家には私より20歳くらい上の異母姉にあたる人の所帯が同居していて、そこの子どもたち(つまり私の甥だが1つ2つ下なだけだった)とよく遊んだ。私と父母は3畳一間だったと思う。そこに妹が生まれ(自宅出産だった)、4人になった。小4くらいの頃、母が死んだが、そのころには姉家族たちはもう引っ越していなかった。そのあとなぜか建て直しがあり、行くところのなかった我が家は、近所の空き地にバラックを建て、そこにしばらく住んだ。今考えると信じられないが、電気もトイレもない生活だった。ランプのほやを掃除をした記憶がある。トイレは大家さんの畑の肥溜めを使った。さていよいよ完成して引越し、のはずが、立て直した家に入るとき大家さんと家賃でもめて、深夜にこっそり入り込んだらしい。かすかな記憶で詳しい事情はよくわからないが、その後も大家さんとはずっとうまくいかなかった。新しくなったはずの家にも台所がなかった。確か水道も長屋で共同だったように思う。長屋の裏庭が通路になっていて真ん中の家の裏に蛇口とセメント製の流しがひとつあるだけだった。毎日何度もやかんで水を汲みにいった。ご飯のしたくは、七輪で火を起こし、共同の流しで米を研ぎ、鍋でご飯を炊くのだ(キャンプみたいでおもしろかったが)。いつまでもそれではというので水道だけは1軒に1つずつになったが、流しは相変わらず外にあった。雨の日の炊事は大変である。
便所はやはり外にあった。七輪でご飯を炊く真ん前に便所の戸があった。一応屋根はつながっていたが、雨のひどい日などは濡れずに済ませられない。これは引っ越すまで同じだった。年月がたって近所の家が全部水洗式になっても、うちだけはずっと汲み取り式のままで、月1〜2回は清掃局へ電話をしてバキュームカーに来て貰った。水洗になったのはかなり後のことである。(つづく)
2007年03月21日(水) 春分の日
久しぶりに一人でドライブした。といっても可児市までであるが。古い友人の住んでいるところで、会いに行くというよりもそこまでのドライブを楽しもうとしただけ。11時に出発。快晴。途中、「Timely」という名前のコンビニで昼食。「子守神社」というところが目的地。着いてから友人に電話してみると案の定お留守。いいお天気なので当たり前かも。近くのスーパーに駐車して辺りを散策。十数年まえに来た時より住宅化が進んでいると思った。行きは19号で、途中かなり渋滞(お彼岸なので潮見坂墓園のお墓参りのせいか)したが、帰りは41号ですいすいだった。今週後半からは暖かくなるそうで、今日も確かに暖かかった。東京の桜開花宣言(全国初とのこと)やテレビ番組(フジ系「ザ・ベストハウス」)で桜の名所ベスト3などを見ていると、いよいよ花見の季節だ(ちなみにベスト3は、3位・長野県高遠城、2位・京都府円山公園、1位・奈良県吉野山だった)。
さて、我が家の末っ子あてね(黒猫♀・5ヶ月)の避妊手術は昨日20日の予定だったが、日が近づくにつれあっちゃんの食欲がなくなり、当日は体重不足で先生が「今日はやめましょう」となった。前日などは声もかすれていて風邪かなと思った。手術への不安がよほど大きかったのだろうか(誰が?)、帰ってきたとたんに急に元気になった。例のサカリのついたような声も医者へ行ってからは急に出なくなっていたのだ。不思議である。今はもう静かなもので、あの1週間がウソのようである。ほっとしているのは手術ができなくなったあてねだけではない。

2007年03月19日(月) 数学のことも…(続き)
「ガロア理論」についてほぼ理解ができた今、次は何を目指すかというと「類体論」である。類体論は日本が誇る世界的数学者・高木貞治(1875-1960)先生の創設になる理論で、代数的整数論のひとつの頂点をなしている。「クロネッカーの青春の夢」を肯定的に解決したとされるこの理論の成果は、著者をして「いずれも極めて簡単明瞭であるに反して、その証明法は、上記諸家の努力にも拘わらず、今なお紆余曲折を極め、人をして倦厭の情を起こさしめるものがある.」(高木貞治著『代数的整数論』序・昭和22年6月)と言わしめている(文中、「上記諸家」とあるのはArtin,Hasse,Herbrand,Chevally等、類体論発展に寄与した「若手」数学者たちを指す)。
数学の最大の魅力は、その難解さにあると思う。しかしもちろんただ難しいだけで魅力的なのではなく、美しいものが難解なことが魅力なのである。私はまだその美しさの一端さえ見えていないのであるが、「ガロア理論」の美しさをはるかに超えるものと期待している。それはつまり難解さも並大抵でないだろうという覚悟もしている。
高木先生には数学入門書としての数々の名著がある。「代数学講義」(1930)「初等整数論講義」(1931)「解析概論」(1938)等、初版以来半世紀以上を経た現在においても広く読まれ、今日の日本の数学水準を世界的レベルに引き上げている根底的土台となっているのは間違いない。また、「近世数学史談」(1933)は、19世紀初頭のヨーロッパ数学界におけるガウス、コーシー、アーベル、ガロアたちの人間味あふれるドラマで、先生のお人柄も垣間見られるこの上ない名著である。(この著書の中で先生は、アーベル、ガロアの天才的なるがゆえの不幸を、「時代を超越するにも程合いがあって、二十年、三十年の超越は危険である。」と述べている。)
私が高木先生の本に出会ったのは、鶴舞の大学堂書店で「初等整数論」の昭和21年発行(共立出版株式会社・第8版)を手にしてからだった(1995年ごろか)。この本は本文がカタカナ!という読みにくさにもかかわらず、無類の面白さで私を惹きつけた。私は当時覚えたてのTEXの練習も兼ねて、数式はそのまま、地の文はかなに書き換えながら勉強した。やがて94年発行の第2版28刷を手に入れてから、本格的に代数的整数論の勉強を始めた。そして「二次体の整数論」に至ってついに「イデヤル」論の端緒に着いた。このブログの2002年11月16日に、「イデヤルのわかった日」とあるから、ざっと7年かかっている。大学を2回卒業できる年月である。

2007年03月18日(日 ) 数学のことも…
今日の散歩も寒かった。しかしダウンは着ずにジャケットだけで十分だった。何しろ天気がいい。ただしマスクと帽子は欠かせない。花粉症ではなく、寒さ対策。口の回りを覆っておくと自分の息で暖かく、アゴも冷えない。メガネが曇るのが困るが。帽子は紫外線避け。桜の芽も場所によって違うがかなり膨らんできた。これは庄内川の水分橋南の堤防下の桜。

学習塾は、もう30年くらい続けてきた。「数学教室」というベタな名前をつけたが、これは今でも気に入っている。4畳半の自分の書斎(?)で先生1対生徒1という原則を守って一人でやってきた。塾を大きくする気持ちはまったくなかった。経営よりも教えているほうが面白かったし、好きなことをやって食べていければいいと思っていたから満足だった。
数学とは40年くらい親しんできた。クラシック音楽にハマったのは中一だったが、数学は中三にハマった。現在でも中三の1学期に「因数分解」を習うが、これがわかったとき、数学の面白さに目覚めた(と思う)。それからは授業とは関係なく、学校の図書室で数学の本を次々読んだ。3次及び4次方程式の解法が出ていた本に「5次方程式は解けない」と書いてあったのを覚えている。その本に出ていた3次方程式は「x3−px−q=0」というもので、その解法自体はすぐ理解できたが、それ以外のことが何度読んでもさっぱりわからない。
というわけで、私の専門は方程式論になった。やがてガロアの名を知り、「ガロア理論」を理解することが目標となった。エヴァリスト・ガロアは19世紀初頭のフランスの天才的数学者で、わずか20歳で亡くなるが、その業績は実に画期的で、当時はその理論を理解できるものは誰もいなかったという。現在の大学でも専門課程に進まなければ学ばないところが多い。
天才の仕事は単純で応用範囲が広いというようなことをどこかで読んだが、まさにその通りで、この理論によってそれまでの数々の難問が「すらすら」解けるのである。例えば「一般角の三等分は定規とコンパスでは作図できない」という古代ギリシャ時代からの有名な問題は、「作図が可能であるためにはこれこれという3次方程式を解かなくてはならないが、この方程式は(ガロア理論によれば)そのガロア群の位数が2の累乗でない。よって作図は不可能である」として解決される。
2007年03月17日(土 ) クラシック音楽によせて(続)
先週の散歩で庄内川の人道橋上から見た猿投山の写真を載せたが、今日は同じ所から伊吹山と御岳もよく見えた。下の写真は伊吹山。手前の高架は名古屋高速。

昨日の日記は深夜になり眠くなったため尻切れで終わってしまった。そんなものをUPして申し訳ないが(誰に?)、このまま続きを書く。
土曜日はNHK-FM9:00a.m.の「名曲リサイタル」を録って聴く。この番組は演奏家本人の肉声も聞け、臨場感もあってよい。今日は名古屋からテノールの歌とピアノの演奏だった。昨日も書いた「トスカ」の「星はきらめき」や「トゥーランドット」の「 誰も寝てはならぬ」を聴いた。ピアノではベートーヴェンの「エロイカ変奏曲」他。「エロイカ変奏曲」は同じベートーヴェンの「プロメテウスの創造物」 のテーマを変奏曲にしたものだが、交響曲「英雄」の第4楽章も同じテーマによる変奏曲になっており、ベートーヴェンは同じテーマで数十曲の変奏曲を書いていることになる。 モーツァルトに有名な「きらきら星」変奏曲(正式には『ああ、お母さん、あなたに申しましょう』の主題による12の変奏曲』というらしい(by Wikipedia))というのがあるが、ベートーヴェンの変奏曲では「ディアベリの主題による33の変奏曲」というすごい曲がある。彼の曲のなかではあまりメジャーではないが、主題の単調さに比してなんとダイナミックであることか! 主題はまったく重きをおかれていない。いいかえればなんでもいい。彼はどこからでも、どこへでも自由にその楽想を広げていく。これに比較できるものは、バッハの「ゴールドベルク変奏曲」だけであろう。ベートーヴェンはそれを意識してこれを作ったのかも知れない。これらは装飾変奏と性格変奏といった音楽学的な分析以上のものがあり、変奏曲という音楽形式の本質を知るにはいずれも欠かせない曲である。
2007年03月16日(金) クラシック音楽によせて
クラシック音楽を聴くようになってもう50年近くになる。 小学校の音楽の時間は特に好きというわけではなかったが、それでもいくつかの歌を楽しんでいた。低学年で習った「こぎつねこんこん」や「アマリリス」、高学年になってから覚えた「冬景色」「燈台守」などは今でも歌える。中学生になってクラシック音楽に目覚めた。最初はやはりベートーヴェンだったように思う。中一の夏休み、音楽の先生が「よかったら学校へ来て好きなだけ聴いてもいいぞ」と言ってくれたのに甘えて、放送室でレコードを浴びるように聴いた。「運命」を何度も繰り返し聴いた。
当時、NHKラジオの朝8時に「音楽の泉」というクラシック番組があってこれをよく聴いた。学校に遅刻覚悟で聴いた記憶があるから毎日放送していたのだろうか。テーマ音楽がシューベルトの「樂興のとき」で解説が村田武雄さんだった。これは今でも放送されている(日曜日。解説は皆川達夫さん)。また、土曜日の午後「土曜コンサート」という番組もあってこれもよく聴いた。ベートーヴェンの「第7番」の第2楽章を聴いて言葉にならない感動を覚えた。これも形を変えていまでも日曜日の午後NHK-FMで放送されている(「FMシンフォニーコンサート」。テーマ曲は同じ)。
思い出はきりがないが、現在でも一日に大体4時間は聴いている。そんなに聴けるかと思うかもしれないが、NHK-FMの「ミュージックプラザ第1部クラシック」と夜の「ベストオブクラシック」は欠かさず録音して聴いている(本当は早朝の「バロックの森」も録りたいが録音タイマが1つしかないのだ)。今もそのうちのベートーヴェンの「英雄」を聴きながらこれを書いている。もちろん清聴ではない。何かしながら聞き流していることが多い。それでもちゃんと聴いている。
好きな作曲家は最初のうちはやはり古典派で、ベートーヴェン、モーツァルト、そしてシューベルト、ブラームスと広がり、現在はストラビンスキー、ブルックナー、マーラー、武満徹。それからベルリオーズ、フォーレ、そしてバッハ、ヘンデルも好きだ。要するにクラシックは全般に聴くのだ。演奏家はあまり選ばない。ただ、聴き比べたりはする。こっちのほうがいいという好みはある。そうそう、ドヴォルザークもいい。スメタナも、ショパンも。・・・きりがない。そうそう、ワーグナーも忘れてはいけない・・・
ドヴォルザークの「チェロ協奏曲」などはもう何曲録音しただろう。聴くたびだんだんハマっていく曲だ。ドヴォルザークはとにかくメロディがきれいで、この曲でもいたるところ美しいメロディが満ちており、彼独特の郷愁と哀愁があふれていてたまらない!
歌劇は以前はあまり好きではなかったが、このごろはアリアをよく聴くようになた。プッチーニの「トスカ」や「トゥーランドット」などいわゆる入門編で耳を養っているところか。去年ラジオでサルバトーレ・リチートラの歌うのを聴いて大泣きしたのも「トスカ」の「星はきらめき」だった。
演奏形態では管弦楽が一番好きだが、弦楽四重奏曲とかピアノ曲も好きだ。室内楽はブラームスが渋くてたまらない。
2007年03月15日(木) 春について
最近また寒くなった。三寒四温というより寒の戻りという感じ。あれだけ暖かい日があってからこうして寒くなるとやけに堪える(コタエル→常用外だけど使ってみた)。暖冬の春は寒いと誰かが言っていたと思うが、一度は仕舞い込んだダウンをまた着ている。これだと今年の桜は平年並みかな・・・。3月4日に撮った梅の写真がこれ。桜みたいである。先日の日曜(11日)にはもう散っていたから次はいよいよ桜の番。

自分のこうした性状は花見だけではなさそうだ。万事、人との付き合いは面倒だが、かといってひとり山の中で仙人のように暮らすのは嫌。親戚が多くあって節季や盆暮れの付き合いをマメにするのもいやだが、友達がいなくて酒も一人で飲むのはもっと嫌。要するにわがまま。
でも、還暦まで来たら人間好きなように暮らしていいと思う(S子(妻)に言わせるとこれまでもずっと好きなようにしてきたらしいが)。
2007年03月14日(水) 川内康範先生
けさ、いつもの「芋たこなんきん」を観たあと、他チャンネルに変えると川内康範先生のことを取り上げていたのでつい観てしまった。川内康範先生は、我々団塊の世代には懐かしい以上の感慨がある人ではないだろうか。何よりも「月光仮面」の作者であり、またその後テレビ放映された「七色仮面」や小林旭主演の映画「銀座旋風児」などの原作者・脚本家である。もちろんその後の活躍は皆さんご存知のとおり。
大人になってからの私は、もちろん無節操に先生に迎合しているわけではない。ただ子どものころに観たヒーロー物に対する切ないまでの郷愁が、今でも先生を慕う気持ちを変えないのだと思う。これは理屈ではない。
われわれが子どものときは、そのお顔を拝することはまずなかったが、昨今、某有名歌手との「事件」(これは著作権問題である)によって奇しくもマスコミの格好のネタにされ、おかげで我々ファンは先生の爾来変わらぬ硬骨漢ぶりを拝見できて嬉しい限りである。その古武士のような風貌はとても魅力的であり、現代において数少ない「思想を体現した人格者」といえる。
今回のこの「事件」が先生のお体に障るのではと心配しながらも、あるいはひょっとしたら先生のさらなる元気の源ともなるのではと密かに期待もしているこのごろである。「いつまでもお元気で頑張ってください」とは、心からの気持ちである。
2007年03月11日(日 ) 強風注意報
きのうはまあまあいい天気だったが、夜から嵐のような雨。今朝は雨はあがったが強い風。日課(週末課?)の散歩は、こういうときこそ普段と違う景色が見られるので決行。案の定、庄内川に架かっている人道橋上はすごい強風。川の上は風の通りがいいのだろう。風速20メートルは超えているかも。橋げたの鉄で造った模様が風に唸って気味の悪い音を立てている。しかし悪くはない。遠景もいつもより鮮やか。写真の中央の山が猿投山(629m)か。

橋げたにカメラを乗せて写真を撮っていたら、帽子を飛ばされた。昨日の散歩途中に買ったばかりの新調品である。こんなこともあろうかとケータイのストラップの挟みで帽子を留めておいたのだが、帽子は橋げたの向こう側にぶらりとなって肝を冷やした。
橋を半分わたって庄内川と矢田川の間の堤防を東に向かう。橋の上ほどではないが、それでも強い風で後ろから押されるように歩く。道の上で休んでいた大きなカラスが人をやり過ごすためか飛び立ったが、羽ばたいても少しも前に飛べないのが面白かった。むしろバックしている。仕方なしにUターンし、今度は風に乗ってあっというまに飛び去ってしまった。
午後から家族3人で大口町のAEONに行った。特に理由はないのだが、いい椅子があったら買おうかなと思っていた。実はお正月に大須の家具屋で「いい椅子」を買ったのだが、S子(妻))の今年の誕生日(3月3日)プレゼントにPC用デスクを買い、その椅子をあげた。決してそれが気に入らなかったからS子にやって、自分はまた別のを買おうとしたわけではない(結果的にはそうなったが・・・)。
強風にもかかわらずすごい人出。こんな田舎のショッピングモールなのに(失礼!)巨大駐車場が満員。結局屋上まで上がり、2回くらい巡ってやっと空きを見つけた。1F店舗に降りてみて混んでるわけがわかった。ホワイト・デーだ(たぶん)。今日は直近の日曜日だ。
ホワイト・デー関連の需要人口はバレンタイン・デーよりも少ないにもかかわらず、売上ではそれを凌ぐそうである(某FMラジオ番組からの受け売り)。みんな何を買っているのかはわからないが、どこのお店も人でいっぱい。でも女性が多いのはなぜだろう? ホワイト・デーは関係ないのか。それともカレ氏に付いてきているのか(どうでもいいけど)。
お昼は、2Fの「FOODPRAZA」で久しぶりに石焼ビビンバ(¥787)を2つ頼んで3人で食べた。なかなかおいしかった。
さて、日用品を買った後、ニトリで椅子を買った(¥4990)。今それにすわってこれを書いているが、すわり心地は微妙・・・。とにかく長くすわっていて腰が痛くならないことが絶対条件。また買うハメになりませんように。
2007年03月10日(土 ) あっちゃん、ついに・・・
昨年10月我が家にやってきたあっちゃん(黒猫・♀)が、ついに避妊手術を受けることになった。なぜそうなったかというと猫を飼っている人にはわかると思うが、いわゆるさかりが来たのである。普段の彼女はエサをねだるときの声でも「にゃー」などと、むしろ小さいくらいだったのに、2〜3日前から急に「アオー、アオー」というとんでもない声になった。これを一日中、夜中でもやる。あまりの大声に「うるさい!」と叱るとあら不思議、いつもの「にゃー」に戻って甘えるのである。まだ生まれて5〜6ヶ月だというのに、もう色気づいたのかと、軽くショックを受けた。ゆうべはとにかくすごかった。家の中を行ったり来たりしながら一晩中のべつ幕なし「アオー、アオー」、である。自分たちが眠れないのもさりながら、近所迷惑が気になる。ここの集合住宅では犬猫飼育禁止である。実際はたくさんの人が飼っているものの、違反は違反。苦情がきたら弁解の余地はない。深夜2時ごろ、とうとう堪忍袋の緒が切れて(おおすごい!一発で変換した)、あてねの襟首をつかんでベランダから外にたたき出した、のではなくて、抱っこしてやると鳴き止むので、そのままソファにしばらく座っていた。不思議、腕の中ですやすやし出した。とたんにこっちも眠気に襲われる。そうだ、このままソファに置いていこう。 で、そっとソファに置く。とたんに「アオー、アオー」。しかたないので布団を取ってきてソファであてねと二人でくるまる。脇の下に入り込んでおとなしく寝ている。このままこっちも寝てしまえ・・・。 ・・・明け方、S子(妻)が起きてきて、「あら、どうも静かになったと思ったら」と寝足りた顔で笑っている。あてねも起きてきて小さい「にゃー」でお母さんに甘えにいく。
そのときの話で、さっそく今日、病院へ行こうということになった。避妊手術をしてもらうのだ。いずれはと思っていたが、こんなに早いとは・・・。S子さんの話では、今いる先輩猫のすず(茶猫・12歳)はあてねよりもっと早く手術にいって、先生に「妊娠してますよ」と言われてびっくりしたそうである。
おんぼろソファで寝たものだから体のあちこちが痛い。ねじれている感じ。S子さんに後を頼んで布団を抱え、自分のベッドに潜り込む。すぐ爆睡したのでその後あてねがどうなったか記憶がない(やはりすごかったみたいだが・・・)。
で、午後S子のパートが終わってからかかりつけの病院にいき、20日の手術を予約。ついでに「三種混合ワクチン」というのを注射したせいか、病院から帰ったあてねが元気がない。寝てばかりいるし、小さい「にゃー」もない。ありがたいがちょっと心配でもある。

2007年03月09日(金) 「月光仮面」(つづき)
きのうはつたない絵をここに載せてちょっと恥ずかしい。小学生のときに一所懸命練習してここまでになったのだが、そのままで止まってその後の発展はない。「月光仮面」の第1部は「どくろ仮面」の巻であるが、この巻はテレビや漫画のほうは実はあまり覚えていないで映画を覚えている。。映画では、どくろ仮面がオートバイで追ってくる月光仮面に向かって、クルマの上から火を噴いていたのを鮮明に記憶している。どうやって火を噴くのか真剣に考えたものだ。この巻ではたしか「H・O蒸発爆弾」というのが出てきたはずだ。どくろ仮面の正体はこれを発明した科学者のライバルの科学者だったと思う。そのことが印象的だった。この爆弾は原作者の川内康範先生の”発明”だと思うが、第2部の「バラダイ王国の秘宝」編でも「メトン爆弾」というのが出てきて先生の爆弾好き(?)が面目躍如としている。
あと、「どくろ仮面」は小説でも読んだ。どうやって手に入れたかは例によって記憶にないが(たぶん友人H氏から借りた?)、石原豪人の挿絵がとても好きだった。まるで実写真のようで、ほんとうに月光仮面がいるような気がした。
さて、第2部「バラダイ王国の秘宝」編は、やはり「月光仮面」の中の白眉であろう。怪人「サタンの爪」は月光仮面の最大のライバルである。テレビでは正体が普通のオッサンだったが、桑田次郎氏の漫画では顔がお面ではなく完全に「サタン」だった。手も指がそのままとがった爪と化していた。まさに冷酷・非情な悪魔で(「スラバ・サタン」の末裔とのこと)、仲間でも警察につかまるとすぐに殺してしまう。こどもにはなかなか刺激が強かった。対する「月よりの使者・正義の味方、月光仮面」は、まことに絵にかいたようなスーパーヒーローで、いつでもどこでも現れ(このとき必ず『月の光を背に受けて・・・』というスローな「月光仮面の歌」が流れる)、覆面・サングラス・マントという格闘するにはさぞ戦いにくいだろうコスチュームにもかかわらずめっぽう強い。拳銃は百発百中。「たーっ!」という気合とともに地上から屋根の上にでも上がれる。
ところで、「月光仮面」で忘れてならないのは、名探偵・祝十郎である。月光仮面の正体は彼であるといわれている。確かにテレビでも漫画でもこの二人が同時に会ったことはないし、テレビではどうも月光仮面の声は大瀬康一(祝十郎役)のような気がする。でも決定的証拠はない。まぼろし探偵が実は富士進少年であることは、読者は常に知らされるのと好対照である。月光仮面が謎の人であることは「月光仮面」の最大のロマンである。
(このテーマ、まだまだ続けられるなあ・・・)
2007年03月08日(木) 「月光仮面」
長年の友人、H氏が昔懐かしのテレビドラマ「月光仮面」のDVDを大人買いした。といっても1枚500円のDVDが7枚だから大したことはない(「月光仮面 バラダイ王国の秘宝編 Disc1」発売元ArtStation)。しかし、我々団塊の世代としてはこれは画期的ニュースである。つい2〜3年前まではビデオテープににテレビドラマ1〜2本が入っているだけで何千円もしたものだ。これは著作権の期限切れと関係あるのか(よく知らないが)。さっそくお借りして(買えよ!)全部観た。よく、こどものころ観て感動したものを大人になってから観ると幻滅すると言われるが、そういう歳は過ぎている。もう還暦も近くなると酸いも甘いも噛み分けていて、その辺は心得て観ているから、それなりに感動できるのだ。もちろん観るに耐えない部分はあるが、そこはDVDのいいところで飛ばし観できる。そして、あの時代によくまあここまでできました、と二重丸をあげたくなる場面もちゃんとある。たとえば東京駅や有楽町などの駅での撮影や、クルマとバイク(もちろん月光仮面の!)のカーチェイスなどは今見ても面白いと思う。
月光仮面の正体を簡単に祝十郎だというものがいるが、テレビドラマや漫画、あるいは川内康範先生の原作(先生、お元気でしたね。まさかこのごろのワイドショーでお目にかかれるとは!)にもそんなことはひとことも書いてない。月光仮面の正体を知っているのはこの「バラダイ王国の秘宝編」に出てくる「ハンチングの由」だけである。彼は死の間際の頼みとして月光仮面から正体を知らされ、「ああ、やっぱりオレの思ったとおりの・・・」といって死んでいくのである。当時、そのシーンをテレビで観てどれほどうらやましかったことか。
月光仮面についてはまた続きを・・・
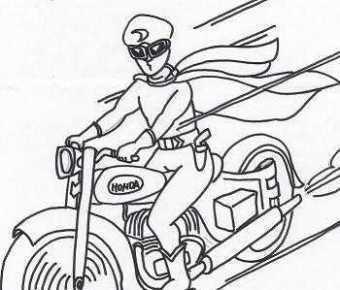
こどものころ覚えたものは今でも描けるものだ。ちなみにH氏はもっとうまい。今度描かせてみよう・・・。
2007年03月07日(水) からくり儀右衛門−田中久重
今朝起きてテレビをつけると、NHKのBShiになっていて、ハイビジョン特集「万年時計〜江戸時代の天才が生んだ驚異の機械時計」というのをやっていた。幕末の天才技師田中久重の作った時計を再現するというプロジェクトを記録したものだ(再放送)。出勤前のことで、リモコンの「すぐ録画」を押しておいた。まだずいぶん若いころ、やはりNHKのこども向けドラマで「からくり儀右衛門」というのを見た記憶があり、とっさにその人ではないかと思った。お寺の鐘突きを自動で行う機械を作ったという筋を覚えている(それも夏と冬ではちゃんと鐘を突く時間のずれを計算してのことだった)。
帰宅してからゆっくりとビデを観た。江戸時代の日本人の科学的・数学的水準は世界的にもハイレベルであったことは、当時の本(の復刻版)を見ても想像がつくが、まさかこれほどとは思わなかった。後の「東芝」の前身となる会社も作っているのだ。
太陽の年周運動や月の満ち欠け、二十四節気に合わせた時刻、それに西洋式の時計などがすべて同じ動力(真鍮によるぜんまい)によって連動し、想像を超える正確さで1年間休まず動く。
とにかく感心するばかりだった。それとともに何か心にふつふつと湧き上がるものがあるのが面白かった。何だかわからないが、やたらと「やる気」が起きてくるのだ。番組を観る人が先人の気概を学ぶとともに自分でも何かチャレンジするものを持てといわれているようで、まさに番組のねらいもここにあるのだろう。
では、自分はなにをすべきか? それを語ってしまうととても陳腐になってしまいそうなので述べないが、とてもいい刺激にはなっているのだ。おそらく明日からの自分に何か変化が現れるような気が・・・。
今日の写真はプラモのおもちゃ。左から右へ、右から左へ変身する。


2007年03月06日(火) 祝! やっと五十肩が・・・
もう1年半前になるだろうか、何がきっかけだったかもう覚えていないが、ある日突然(でもないか、段々かな。でも気づいたのは突然といってもいい)右腕が水平以上に上がらなくなった。無理に上げようとするととても痛い!。あれ?なんで? 上だけでなく、後ろにも、横にも腕を伸ばそうとすると強い鈍痛が来て、しばらく息もできないほど。左手で右の二の腕あたりをしばらくさする。やがて痛みが引いていき、何でもないようになる。で、またうっかりして、たとえば蚊がいてそれをパチン!と叩こう(これはハタクと読めるらしい。知らなかった)として、また痛い目にあう。特に治療はしなかった。時々湿布したくらい。医者は嫌いなだけでなく、なんとなく信用していないので、一度も行かなかった(そのくせ、椎間板ヘルニアでは大変お世話になっているが)。ちょっと怖かったのは頚椎の損傷か何かだったらということだった。でも痛み方がなんとなく違うように思えたので、「まあ、四十肩だろう」と思っていた。四十肩・五十腰とは昔からよく言われていたからである。ところが、「家庭の医学」(保健同人社)によると、「四十肩」ではなく「五十肩」と出ていた。成程。加齢による関節の炎症らしいのだが、半年から1年くらいで自然治癒するとのことだった。それを信じて、始めたのが、散歩、である。
週末、土日の2日だけであるが毎回5キロくらい歩くようにした。これが以外に楽しかった。幸い近くに庄内川の堤防沿いの格好の散歩道があり、ここをできるだけ手を振って歩いた。街中でやるとちょっと恥ずかしいが、ここならむしろ誇らしい気がしてくるから不思議である。この写真はその途中。

2007年03月04日(日 ) 春を迎えて
昨年12月、友人のT中君が亡くなったという知らせを受ける。58歳であった。彼とは幼馴染で、家も近かった。しかしなぜか話をするようになったのは大人になってからで、それからは急速に仲良くなった。一緒に(というか彼が言い出して)小さな同人誌を作ったり、その同人たちみんなで何度も奈良へ行ったりした。お互い古代史に興味を持っていて「古代史研究会」なども作った。古本屋を廻って「日本書紀」を一緒に探したのもいい思い出である。
お互い結婚してからは家も離れ、話すことも少なくなっていたが、年を重ねてからまた一緒に奈良へ行けたらいいなと思っていた矢先であった。

2007年01月08日(月) 還暦の年に
明けましておめでとうございます。今年は今日が仕事始め。今日は朝からすごい雪で一時はクルマで出かけるのはムリかと思ったが、午後からは晴れて何とか大丈夫だった。
正月は、初詣は2日に真澄田神社、その帰りにH井宅に寄ってすき焼きをごちそうになる。3日の大須では駐車場が見つからずその日は退却、翌日もう一度でかける。この時、自室で使う椅子を新調した(¥12,800)。今もこれに腰掛けてこれを書いてる。今までのは食卓イスで1時間も座ると腰にずいぶん負担がかかったのだが、これはなかなかいい調子。机に向かって長居ができそう。今まで主にベッドで寝そべってやっていた数学の長い計算も机でできる・・・かも。
今日は図書館へ行ってきた。年末に池宮彰一郎「平家」上中下を借りていたのだが、半分くらいしか読みきれなくて引き続き中と下を借りてきた。それと「岩波講座・現代数学の基礎」という全34冊の全集の中から1冊を借りてきた。この全集にはすべて「寄贈」のスタンプが押してある。この図書館(市立楠図書館)に数学書の全集(しかもとてもハイレベルな)を寄贈するひとがいるなんてと驚いている。本の内容上あまりたくさんの人には読まれていないだろうけれど、まさにそういう本こそ図書館に置くべきだ。寄贈されていなければたぶん置かれなかったかもしれない。自分でも読みたいからといって図書館に要求はしないだろうし。とにかく感謝。
今年は還暦になる(正確には12月なのでまだかなり先だが)。団塊の世代の露払いというか真っただ中というか、常に世の中の大きな動きにかかわってきた世代である。還暦はともかく、2007年問題が巷間でも取りざたされているが、自分にとっても一大事である。というのは、もらえる年金がとても少ないから。
昨年、社会保険庁から「年金見込額のお知らせ」というのが届いたのだが、60歳から受け取れる年金額は月1万円程度。頼みの国民年金は65歳から(早めにもらうこともできるそう)なのでまだ5年はリタイアできない。ぼくの2007年問題は2011年問題になりそう。
夢と描いていた悠々自適の年金生活は文字通り夢と消えた。あれもこれもしたいと思っていたことはしばらくお預けである。
2006年11月06日(月) あっちゃん(続報)
あっちゃん(二代目)が来てもう2週間経った。あんなに汚くて臭くて死にそうだった子猫が、こんなである。

よく食べる、走る、遊ぶし、ウンチもちゃんとネコのトイレでする、躾のいい子だ。これもひとえにS子(妻)の世話の賜物である。TVドラマ「セーラー服と機関銃」で、組長になった長澤まさみが子分を守ろうとして「子供のケツ拭くのが親のつとめじゃい!」というセリフをいっていたのをマネて、ウンチのたびに「赤ちゃんのおしりふき」(商品名)を持ってあてねを追いかけている。
そのかわり前からいる大ねこたちが大不満である。12歳のほうなどは自分も生後1〜2週間で我が家へ来て猫用の哺乳瓶で育ったくせに、新顔に対して嫌悪を隠さない。食事やトイレにも滅多にでてこなくなり、引きこもってしまった。もう一匹の10歳のほうは新顔の子猫がそばへ来るとすごい声でうなっていたが、割に早く慣れ、今ではしぶしぶだろうが一緒にご飯も食べる。
2006年10月26日(木) 國木田獨歩「武藏野」を読む
図書館の本(講談社『現代日本文学全集18」昭和55年)で國木田獨歩「武藏野」を読んだ。現代といいながらすでに古典と化している日本文学の中でも、獨歩は漱石や芥川に比すればマイナな作家である。ただこの「武藏野」はある意味作者よりも有名といってもよいくらい名が知られている。始めてこの地名を知ったのは50年前、手塚治虫の「鉄腕アトム」だった。どういう巻だったかは忘れたが、漫画の最後にこの獨歩の「武藏野」の本が出てきていたことを覚えている。その頃でもすでに昔の面影を失いつつある武蔵野を惜しんでいるようなそんな漫画だった。しかし本編(四百字原稿で四十数枚程度)を読んだのは今回が初めてである。この全集は掲載作をできるかぎりオリジナルに近いように編集されていて、いまどきの文章を読み慣れた感覚では正直とても読みにくい。この「武藏野」という字もそうである(「武蔵野」ではない)。本文を一部書き出してみると、「昔の武藏野は萱原のはてなき光景を以て絶類の美を鳴らして居たやうに言い傳へてあるが、今の武藏野は林である。林は實に今の武藏野の特色といっても宜い。則ち木は重に楢の類で冬は悉く落葉し、春は滴る計りの新隳萌え出づる其變化が秩父嶺以東十數里の野一齊に行はれて・・・」(本編三章より)云々。こうした文章はしかしわれわれ団塊の世代にはとても懐かしいものでもある。この読みにくさやとっつきにくさは、言わばタイムマシンに乗り込むための訓練のようなものであり、それを味わうこと自体が魅力であり、一気に「古典」の世界に入ることができる。
本編六章の玉川上水桜橋から堤を散歩する夏の場面はもっとも美しい。季節外れに散歩に来た獨歩たちを「東京の人は呑気だ」と笑う茶屋の「婆さん」は文学における「典型」でなくしてなんであるか。獨歩がいわゆる後の自然主義の先駆者であるかはともかく、この一編において彼が日本の「現代文学」に忘れてはならない人であることが理解できる。
2006年10月22日(日 ) あっちゃん(二代目)が来た!
2006年10月20日の金曜日の朝、愛車(軽)で会社へ行くときいつも通る小学校の校門の前になにやら黒いものが落ちている。なんだろうとスピードを落として近づくと、子猫だった。道路の真ん中にうずくまってじっとしている。これでは轢かれてしまうのは時間の問題だ。クルマを降りて拾い上げ、抱っこしたままきわどい運転でUターンをしていったん帰ることに。抱いていてガリガリにやせているのがよくわかった。だめかなとちょっと考えてしまった。奥さんは仕事でいないので留守番をしているT子(妹)にあとを頼んでまた会社に向かった。会社からS子(妻)にメールしておく。仕事中なのですぐに返事はこないが、さぞ喜ぶだろうと思う。実は今年6月にあてねという名のオスネコが急死して、とても寂しい思いをしていたのだ。他にまだ2匹、12歳と10歳のネコがいるが、あてねは1歳と8ヶ月、とても元気な、おおちゃくい、暴れん坊だったのでいなくなったあとの寂しさはなかった。叱るとき以外はあっちゃんと呼んでいたので、テレビでオリエンタルラジオの藤森クンが「あっちゃんかっこいい!」のネタをやっているのをみて泣いてしまったくらいだ。
夕方、S子(妻)が帰ってきて、子猫を見て喜ぶ舞妓とか! いや、喜ぶまいことか!かくかくしかじか経緯を説明するがろくに聞きもしない。顔もわからないくらい目ヤニや鼻汁が固まっているしアバラ骨が浮き出ている。そのうえとてもウンチくさい。なのに平気で抱っこしてうれしそうだ。
意外と元気そうでお皿からキャットフードも食べ、牛乳も飲んだ。ちょっと安心。翌日土曜日、さっそく行きつけの動物病院へ。待合室で診察を待っているあいだ、あまりに汚いので他の人たちにちょっと気がひける。お隣りのケースに入っている猫のぱっちりした眼が羨ましかった。注射と粉ミルク等で5800円。風邪を引いていて、お腹もこわしている、お腹にムシもいるが命は助かるとのこと。受付でネコの名前を聞かれ、真っ黒なので最初はクロにしようかと思ったが、死んだあてねの生まれ変わりということでやはり「あてね」になった。
 来たばっかりの二代目「あてね」
来たばっかりの二代目「あてね」
2005年02月24日(木) 放蕩息子の帰宅
・・・なんて書いていたら、なんと昨日(23日)あてねが帰ってきた。夕方、うとうとしていたら、T子(妹)が「帰ってきたよ!」といって起こすので、慌てて出て行ったら、T子が汚い猫を汚そうに持っていた。「やあ! ほんとだ、あてねじゃないか。よく帰ってきたなあ!」と私。 それにしても汚れている。臭い! この1週間、苦労したのがよくわかる。
 帰ってきたばかりのあてね。20日の写真と比べると痩せてます。
帰ってきたばかりのあてね。20日の写真と比べると痩せてます。
それにしても生後5ヶ月の子猫が外で1週間もよく一人で生きていたものだと感心した。雨の日もあったし、ずいぶん寒い日もあった。誰か親切な人が面倒を見てくれたかもしれないが、本人に聞いてもよくわからない。帰れたのがうれしいのかやたら擦り寄ってニャアニャアとうるさい。ただ、大人の猫たちには大不評で、以前はそれなりにかわいがっていたのに、そばにくると「フーッ!」と毛を逆立てて本気で怒る。すっかり忘れられている様子。慣れるまでまたしばらくかかりそうだ。
2005年02月20日(日 ) 長期脱走
一番新しく来たネコがいなくなった。去年の9月に家の前で拾ったあてねである。すっかり大きくなってたびたび脱走を計っていたが、ついに成功。そのまま今月15日以来、もう5日も帰ってこない。


もちろん、彼(あてね=オス)はこの家が大好きで、家族の誰にでも(以前からいる大人の猫も含めて)甘え、あてねの方が大人のネコをおもちゃにしていたほど、我が家になついていた。だから帰ってこないのは彼の意志ではなく、帰れないでいるのだ。みんなでずいぶん探したが、今のところ見つかっていない。毎日家中に響いていたあてねのいたずらに対する私の罵声や、おもちゃにされていた大人のネコたちの悲鳴がなくなり、ずいぶん静かな家になった。いなくなってまだ3日だから帰ってくるものと期待しているが、手や足に残っている「引っかかれ傷」を見ると、胸のあたりがきゅうとなる。
2005年02月05日(土 ) L.V.ベートーヴェン
数日前から風邪気味で、夕べはいつもの夜更かしもせず、3日深夜に録画した映画「不滅の恋 ベートーヴェン」(メ〜テレ)も観ずに早く寝てしまったので、今朝目が覚めてからずっと観ていた。ベートーヴェンは、自分にとって青春のメインテーマだった。中学一年生のとき、「運命」を聴いてからずっと彼について考えてきた。当時の自分はクラシックを自由に聴ける環境ではなかったけれど、NHK-AM放送の「音楽の泉」(いまでもやっている!)や「土曜コンサート」(これもやや形を変えていまでも放送中!)、「希望音楽会」(オープニング曲がラフマニノフで有名)などを毎週聴いていた。次々に彼の名作を聴くにつれ、憧れが強くなっていった。作曲家になろうと決心したのは16〜7才だったと思う。小説も読むようになり、小説家と作曲家のどちらになろうか迷ったものだ。
周知のようにベートーヴェンは30歳ごろから耳が聞こえにくくなり、音楽家として致命傷とも言えるハンディを持つのだが、彼の場合、そのことがその後の作曲の妨げになるどころか、明らかに数々の名曲の源泉になってさえいる。そのことがどう考えても不思議に思えてならなかった。もし神がいるとすれば、彼は、彼の曲をこの世に顕すために神が遣わした人である、そう考えたりもした。ただ、ただ、すごい!というしかなかった。
ベートーヴェンは多くの「名言」を残しているが、中でも「苦悩を通して歓喜に至れ」という有名な言葉を私は長く座右の銘と決めていた。今、若き日に持っていた情熱や感動や感受性など多くのものを失ったためか、昔ほど彼に惹きつけられる事がなくなってしまったが、今朝観た映画の中で、「第9」を指揮し終わったベートーヴェンがもう一人の指揮者によって聴衆の方に姿勢を向けられたとき、そこに熱狂するたくさんの人を見てお辞儀をするのを観て、久しぶりに感動した。この逸話をいろいろな本で読んだり見たりしていて、ほとんど自分の頭の中に長くイメージを焼き付けていたのだ。
多分、上述の「土曜コンサート」だったと思うが、「第7交響曲」の第2楽章を始めて聞いたとき、何という美しい音楽がこの世にはあるものか!と心から思ったものだ。(「第7」はテレビドラマののだめカンタービレで一躍有名になったが、第2楽章はドラマではほとんど演奏されていない)「不滅のアレグレット」などと呼ぶ人もいるとそのとき聞いたように思う。それから長い間、この曲をもう一度聴きたさに次々音楽番組を徘徊したことをよく覚えている。やがてFM放送が始まり、どこで買ったかもう忘れてしまったが、やっと手に入れたトランジスタラジオに文字通りかじりついて聞いた大晦日の「第9」に感動し、ほとんど一晩中泣いていたこともあった。いま思い出しても何と多くのわが青春の思い出が彼と結びついていることか。
音楽を「心の糧」にしてきたとつくづく思う。音楽はジャンルを問わず心の糧である。小説もそうだが、音楽は抽象的であるがゆえによけいそう思う。先ほどちょっとふれた「ラフマニノフの名曲」は「パガニーニの主題による狂詩曲」の「第18変奏」のことだが、これはきっと誰でも一度は聴いたことがあり、一度聴いたらもう一度聴きたい曲になり、何度も聴くことできっと忘れられない曲になるだろう、そして聴いていない人にはこれからその曲を聴くという幸せがあるといっていい。名曲とはすべてそういうものである。
2005年02月01日(火) 豊川稲荷
もうすぐ節分、そして立春、待ち遠しい。暖冬とか地球温暖化とか言われているが、今年はけっこう寒いなあと思っているのは私だけではないだろう。1月30日、久しぶりに三河の「豊川稲荷」へ行ってきた。昔々、もう20年も前か、友人のT中君と、誰かにタダで貰った名鉄電車初詣切符で行って以来(たしか2月だった。帰りの電車が発車までずっとドアを空けていてとても寒かったことを覚えている)。
今回はもちろんマイカー。19号を北へ春日井インターから東名へ上がり、一路豊川インターへ。T子(妹・愛護手帳保持者)のお陰で高速は半額、往路800円で済んだ。
お稲荷さんに着いてすぐ見つけた駐車場に止めて(¥700)、さっそく入り口の「総門」から中へ。もう1月も最後だったから人手はいまいち。境内で猿回しをやっていた。今の猿回しはあの反省ザル「次郎君」の影響からか、コミカルなコントや一発ネタで笑わせ、曲芸は二の次という感じがする。そのお陰でただの伝統芸に終わらず現在まで続いているのだと思うが。あまり長くただ見しては悪いのでさっそく「御本殿」へお参りする。覚えのある、せり上がり風に板が敷き詰められた参道を上がって大きな提灯をくぐって拍手を打つ。なぜか前回の印象とはずいぶん違う、寂しいような気持ちを感じる。これは最近久しぶりに訪ねたところでいつも感じる思いだ。
今日のお昼は豊川稲荷門前町の「和食処松屋」で田楽・菜飯・稲荷寿司を食べた。我が家のいつもの日曜日なら「どんどん庵」か「寿がきや」だからごちそうの方である。
寒かったのであまり長居せず、3時には帰路に着く。行きのときに気づいたのだが、我が家からなら東名阪で名古屋インターまで行き、そこから東名に入ればよかったのだな。帰りはそれを逆にたどって早く安く帰ることができた。
帰ってから「豊川稲荷」をインターネットで探してみた。なかなか充実していて楽しい。昼食を取った「和食処松屋」も紹介されていて、女将さんもなかなか美人(参考:http://www.yui.or.jp/~inami/matsuya/)ではないか!会っている(見ている)と思うが覚えてない・・・。
2005年01月10日(月) 荒木集成館と久永先生
お定まりの文句だが、1月もあっという間にもう10日である。今日は成人の日だったが、去年、団地の自治会長だった時は式にも参加して(受付だが)、「新成人」たちを間近に見てそれなりの感想を抱いたが、今年は何の感想もない。午前中塾の臨時授業があって、その帰りに街で何人かの晴れ着姿を見て、「ああ、今日は成人式だったなあ」と思った程度。人は自分の立場でものを考えるのだ。今年の正月もテレビをいっぱい観た。「阿弥陀堂だより」「ハムナプトラ 失われた砂漠の都」「国取り物語」「新春かくし芸大会2005」「ナニワ金融道・6」など。この中では「阿弥陀堂だより」が一番よかったが、ひとこと、田村高廣演じる「先生」はカッコよすぎ。人はあんなふうには死ねないだろうと思った。「国取り物語」はビデオに撮ってサーッと流すつもりだったが、3日かかって10時間じっくり観てしまった。とても面白かった。「ベルーナ」という通販会社がメインスポンサーで(CMはつまらなかったけど)、よくこのドラマのためにスポンサーになってくれたなと思ってしまったことよ。渡部篤郎の明智光秀にはすっかり感情移入して、自分が光秀でもやはり信長を討っただろうかと真剣に考えながら観ていた。「ナニワ金融道・6」はとても勉強になった。あんなのを時々テレビでやってくれればサラ金地獄も少しは減るだろうに。ドラマの途中、某サラ金会社のCMが入っていたのには笑った。
話は変わるが、昨日9日、天白区にある「荒木集成館」という所へ行ってきた。荒木実という人が個人で建てた考古学の博物館で、主に「東山古窯址群」(「荒木集成館」のHP参照)からの出土品を展示している所である。
20代の頃、「若潮」という文学の同人誌に入って小説を書いていたのだが、そこで久永春男という考古学の先生に会い、とても大きな影響を受けた。久永先生は文学にも造詣が深く、そのころもう還暦を過ぎていらっしゃったのだが、いつも若い人たちを啓発なさっていた。その後私はいつしか同人を抜け、先生にもお会いできなくなっていたところ、今から10数年前、新聞で先生がこの「荒木集成館」で考古学の講義をなさるというのを読んで矢も楯もたまらず会いに行ったことがあった。その時の講義はもちろん考古学に関するものだったが、その中で先生は「私の青春は戦争の最中でしたが、その中で私はいったい人間はどのような歴史を歩んできたのか、古代から現在までを研究しようと勉強を始めたのだが、そのまま今日に至ってしまい、今でも古代を研究し続けています。」というような意味のことをおっしゃっていた。深い言葉である。講義後、握手をお願いして、「いつまでもお元気でがんばってください」と申し上げたら、先生はくっと胸を反らせて「『いつまでも』は無理です」と笑っておられた。
——そして昨年秋、わが家の近くの本屋で「小説・荒木実集成館物語『土器は我が胸にささやく』」という本を見つけ、その中で久永先生の名を見つけた(もちろん荒木先生と久永先生はご昵懇(ジッコン)の間柄であるから不思議ではない)。で、今回の集成館再訪ということになった。大変失礼なことに、私はお二人ともご健在であるとは思っていなかったので、荒木集成館で館の人にさりげなくお二人のことを聴いてみると「え、お元気ですよ(荒木)館長は今お2階でお客様をご案内しています」。久永先生についても「もう90何歳だが、お元気です」という返事。私はもうびっくりしてしまった!!
さて、どうしたものか、今、考えているところ・・・・
2005年01月05日(水) 初詣
元旦は恒例の一宮・真清田神社へ。交通安全のお守りを買い(去年のを持参するのを忘れた)、串カツを食べて友人のH井君家へ。パソコンのわからないところを見て欲しいというので聞くと、「住所録の一覧を印刷したいんだけど『ファイル名を入力してください』という画面になってしまう」とのこと。はは〜んと思って言うとおりやってみると案の定、プリンタの設定が「プリンタ」になっていない。それだけのことなのだが、これなどはソフトが悪い。ユーザは印刷しようと思ってこの操作を行うのだから印刷だけすればいいのにファイルに保存するときもこの画面を使うのでこういうことになる。そのあとお互いの近況など話し合っておみやげをいっぱいもらって帰る。夜はテレビ三昧。 2005年01月01日(土 ) 初感染!
さて、とりあえずはあけましておめでとうございます。最近、我ながら政治的な発言が目立つが、今は言わざるを得ない。それほど危機的状況にある。イラク自衛隊派遣、首相の靖国神社参拝、憲法第9条の「改正」、この3つはどうしても阻止したい。他に消費税や日の丸や教育基本法等、いろいろあるが、要(カナメ)は憲法9条である。これを守ってくれる政府が欲しい。いや、どんな政府でもこれを守る義務があるはずだ。数十年にわたってこれほど憲法をないがしろにしている政府は世界に例をみない。「戦力を持たない」と決められた憲法に対して自衛隊の存在を子供に説明できない。「あれは憲法違反じゃないの?」といわれれば「違反している」と言わざるを得ない。「憲法を守らなくていいの?」「いや、守らなくてはいけない」「でも、守ってないね」「そうだね」「じゃ、校則くらい破っても全然平気だね」「……」。どうしてもこうなってしまう。9条をなくしたい人たちもそれはよくわかっているから、一日も早く憲法を実情(?)に合わせたいのだろう。今年は政権党がいよいよ「憲法改正要綱」を党是とする年である。我々も腹をくくってかからねばならない。
話は変わるが、我が家でのBフレッツの速度は依然8メガのままである。先日NTTのセールスマンが来て「この団地には光ファイバが引いていあるので是非インターネットいかがですか」などといささか間の抜けたお勧めがあったので、「うちはこの団地の数少ないユーザの一人だ、ついては遅いので何とかならないか」と苦情を述べておいた。案の定その後なにもリアクションがないが。
ま、遅いは遅いが、それでもこれまでと違って幾多の調べものはほとんどインターネットで簡単にわかるようになった。時間を気にしなくてよいことがこれほど快適とは予想していなかった。これはいいほうの当て外れである。
悪い方の当て外れというか、大当たりだったのがやはりウィルス。これまでは一度も(たぶん)かかったことがなかったが、とうとう嫌なのがやってきた。あるとき(正確には12月11日深夜)、ネットサーフィンの最中、突然画面の真ん中に「べー」と舌を出した大きな口を描いたポップアップウィンドゥが現れ、英語で「あなたのPCはとても住みやすい」というようなメッセージが書かれてあった。「しまった!」と思ったが、「単なるジョークかもしれない」と思い、いったんすべてを閉じ、再起動してみた。 そうしたら、I.E.(インターネット・エクスプローラ)が勝手に開き、勝手な(外国の)HPを開いてしまうようになった。別にアダルトサイトではないものの、アダルト・コーナもあるような英語の総合サイト(日本のBIGLOBEのHPのような)だった。問題は勝手にI.E.を起動し、最初のホームページを勝手に決めてしまうことだ。クッキーも全消去し、履歴を消してもだめ。何度元に戻しても再起動したりログインし直すとそこに行ってしまう。仕掛けがわからなかった。いずれにしてもさっきの「ジョークソフト」がきっかけになったのだろう。しばらく格闘してみたがついにあきらめ、気持ち悪いのでリカバリすることにした。それにしてもどういう仕掛けなのか見事なものだと一方では感心もした。
結局、データをバックアップし、4時間ほどかかってリカバリ終了。翌日にはMicrosoftのHPからWindows MeのUpdateを21箇所実行した。Updateしていないのがウィルスにかかった原因かもしれないと考えたからだ(それにしてもずいぶん修正箇所があるものだ)。あとは各アプリケーションをインストールして元に状態に戻すのだが、やはり多くのものを失った。この時本当に口惜しい思いをした。腹立たしくなった。ああいうものを作ってネットに流す奴を憎んだ。インターネットは国籍など関係なしに普及しているから、ある意味人類的規模の犯罪といえる。セキュリティについて深く考えさせられる出来事であった。
2004年12月06日(月) 若き日の妄想
最近読んだ本に、A・チェーホフの「かもめ」がある。チェーホフは若いときからよく読んだ作家で、中央公論の全集を買ったこともある。先日NHK教育テレビでロシア・マールィ劇場日本講演の「かもめ」を観たのが再読のきっかけ。若いときの印象は「よくわからない」だったが、今回観ても再読してもやっぱりよくわからない。ただ、面白いのは間違いない。だって面白くなくてはこれだけなんども読み返したりはしないだろう。その理由がわからないだけだ。「かもめ」という戯曲があるのを知ったのは、古いぞ、もう40年前で、当時私は町工場の金属労働者だったが、そこで一緒に働いていた中村さんというおばさんが「あんたは本が好きだで、これ、あげるわ」ともらった単行本が原田康子の「挽歌」だった。その中でヒロインの怜子の所属する劇団が上演する劇の演目として「かもめ」が出てきたのだ。で、それからなんとなく「かもめ」といえば「挽歌」という連想が頭の中に出来上がっている。実は先週末から近所の本屋へ行ってこの「挽歌」を探しているのだが、案の定、ない。中村さんにもらった単行本もその後どうしちゃったのかまるきり記憶がない。ちなみに同じ町工場の社長の奥さんからも「よかったらこの本あげるわ」といってもらったのが昭和三年刊行の改造社「現代日本文學全集」(いわゆる「円本」)の中の第二四巻「志賀直哉集」だったが、これを読んで最初に思ったことが「小説がこんなんでいいんだったら、自分でも書けそうだ」だった。これがきっかけで文学に傾倒していったのだ。思えばここで道を外したのかも知れない。後年、私は作家になろうとして(本気)この会社をやめている、なれなかったけれど。なれなかったものの、文学好きは生涯の性向となったようだ。恥の上塗りついでに言うと、中学1年の時、ベートーヴェンの「第九」の「ミミファソソファミレドドレミミレレ」という有名な「喜びの歌」を知ったとき、「こんな簡単な曲を作るだけで大作曲家になれるのか!」と考え、作曲家になろうと思ったものである!
2004年12月05日(日 ) 祝!光接続
先月のブログに少し書いたが、我が家の今年のトップニュースになるのが「光ファイバ」の接続である。実はこれは一大決心だった。いったん契約すればそう簡単に解除はできないから続けていけるかどうか不安もあった。ところがしばらくすると今度は不満に変わってきた。この半月、夢の常時接続を使ってみての感想は「遅い!」こと。Bフレッツサイトにある速度計測では、なんと「約8メガbps」! なんだ、これは! 絶対変! 光ファイバといえば、100メガの代名詞くらいに世間では言われているのに、8メガとは何事だ。確かにうちのPCは古いし('01年1月購入のSOTEC-IntelCeleron700MHz、Windows Me)、光ファイバといってもマンションタイプだし、BBルータは\3,560の安ものだけど、それにしても。これはきっとまだ何か他の原因があるのだろうか。
が、しかし、以前のダイヤルアップに比べればやはり早い(当たり前)。何より時間を気にしなくていい。森博嗣先生製作の「欠伸軽便鉄道・弁天ヶ丘線」の動画も初めて十分楽しめた。先生のサイトのリンクから大矢博子氏のなまもの!(参考:http://www.namamono.com/)を知り、深夜に死ぬほど笑いこけながら日記を読んだ。
2004年11月17日(水) サーフィン(ネットだけど)
実は昨日(もう0時をまわったからおととい)から我が家のインターネットはBフレッツ(光ファイバ)になった。いろいろ考えて決心したのが先月中ごろ。NTTから確認書がきたのが今月6日で、15日にはもう工事だからけっこう早い。マンションタイプ1という契約で、約2,930円/月(税込)くらい、それにVDSLという端末機器のリース料が473円/月(70メガ対応料金・税込)、そしてプロバイダとの契約改定で2,079円(税込)/月だから合計で5,482円/月である。今まではBIGLOBEの「わいわい5時間」という契約で998円/月+電話料だったから結構な出費となった(さらに別途工事費が21,000円、NTT契約料(840円(税込)がかかる!)。ある人に「今度Bフレッツにするんだよ」といったら、「そんなのにして何に使うんだ?」といわれた。確かにその通りで、今まで自分もそう考えてダイアルアップで十分だった。しかし、今はせっかくBフレッツにしたんだからおおいに利用しなくてはと思っている。
取りあえずはいろいろなサイトを見てゆっくり楽しもう。次から次へとサイトを回っていると「おおっ、これがあのネットサーフィンかっ」という新鮮な驚きは確かにある。S子(妻)の愛機「VAIO」(中古だけど)にもルータからケーブルを引いて、今日から使用可能である。しかも電話中にも利用でき、二人同時に使用できる。これだけでもすごい。
2004年11月08日(火) 紅葉の下見
昨日は大して考えもせず、愛用の道路地図(「アトラスRD東海」2001年3月発行)で岐阜県・恵那にでも行こうと決めて午後から家族で出かけた。テーマは「紅葉の下見」。いつもは41号から小牧I.C.に上がるのだが、地図を見ると19号から春日井I.C.で上がった方が中央道には近いことが(今ごろ)わかった。途中、虎渓山S.A.に立ち寄って遅い昼食にしたが、S子(妻)が「こないだも来た」と気付いた。夏に岩村町に行ったときにも寄ったS.A.だ。次回は屏風山P.A.にしよう。高速料金はT子(妹)の障碍者手帳のおかげでほぼ半額になる。おかげで最近はよく高速道路を利用する。恵那I.C.で降りて県道68号を西に。地図によるとこの県道は「恵那白川線」だから白川町まで行っているのだろうが、かえで街道という看板が何枚も立ててあった。まだ紅葉には少し早いようだったが、中々いいドライブコースである。特にクルマの少ないのがいい。自分たちの前後にまったく他のクルマがいない時もある。途中、笠置橋を渡ってからは木曽川に沿って走るようになり、一段と景観が広がる。木々の色づきも段々良くなっている。やがて 「不動の滝駅」という小さな道の駅まで来たのでちょっと休憩。

さらに同じ道をドライブは続く。この辺に「グリーンピア恵那」があるはずだが、どこにあるのかとうとうわからなかった(今ネット検索した情報では今年7月1日恵那市に売却されたらしく、現在どうなっているのかは不明)。適当にUターンして先ほど看板を見かけた「坂折棚田」という所へ行って見ることにした。県道を脇に逸れて約1.5km坂道を登る。舗装してあるので楽々。やがてこの棚田のために作ってある展望台に到着。

帰りも同じ道で景色を楽しみながら恵那I.C.入り口まできたら、ここで今日初の渋滞。まあ大したことはなく、すぐに高速へ。が、小牧Jct.でまた渋滞。前回岩村町の時もそうだったが、いつも同じところで渋滞する。何か法則がありそう。夕食は41号線沿いの「すき家」と「吉野家」に寄って牛丼を買って帰ることに決め、小牧Jct.を右(西)へ。小牧I.C.から降りる。高速料金はやはりこちらの方が少し高かった。無事帰路に着く。ちなみにすき家では牛丼を2個買い、吉野屋では先日買った時にもらった「豚丼3個で1個引換券」で豚丼を貰い、あわせて3個にするという、S子の戦略。引き換え期限が10日だったのでセーフ !
2004年10月25日(月) 新潟の地震
23日土曜日の夕方、新潟で震度6強の地震があった。「新潟県中越地震」という名前が付いた。昨日の午後にも震度5〜6級の余震があった。守山の吉根のジャスコへ買い物に行っていたとき、家電コーナーのテレビで余震の情報が流れた。あまりに頻繁にあるので、被災地からの中継中に余震が起き、緊張した生々しい映像になっていた。道路の寸断がひどい。余震が続くので家の中にいられず、道路や空き地で夜を明かす人たち、避難所で毛布にくるまっている老人や子供、少ない食料を受取るために並んでいる人たち。テレビもラジオも土曜の夜からずっと地震関連のニュースばかりである。NHK-FMと教育テレビは安否情報を延々流している。圧倒的に多いのは、全国から被災地の「○○さんへ。心配している。連絡を」で、次に被災地の人から「○○より。△△避難所にいます。無事です」。しかし、これは当然ながら少ない。それ以外の番組でも画面の上か下にテロップ情報を流しながらやっているが、CMだけはそれもなく日常性(?)を保っている。
マスコミの「今、どんな気持ですか?」というインタビューに対して、「大変ですけど、前向きに、ね」と応えていた被災者が印象的だった。そうだよなと教えられる想いであった。何よりもまず、ライフラインの整備が急務と思うが、これは数日から数週間かかる。とすればそれまで自力と近隣との協力で生き延びなければならない。外からの援助は得てしてうまくいかないことが多い。援助が手元に届けば運がいいと思わなければならない。「自助・協助・公助」というが、「自助」にはあっという間に限界がくる、また個人差がある。それを周りの「協助」がサポートし、そして国、県、自治体の「公助」につないでいかなくてはならない。全国の視聴者が、もし今自分の身に起きたらどうしたらよいかを考えながら見ている。阪神・淡路大震災の時もそうだったが、人々はこういう大惨事を教科書にして学習している。他人ごとではない、そういう時代である。
2004年10月21日(木) 妻籠
今、森博嗣先生の日記『数奇にして有限の良い週末を』(幻冬社、2004年)を(図書館から借りて)読んでいる。このブログも森先生のこれら「近況報告」の影響を受けているが、とにかく示唆を受けることが多い。森博嗣の日記はまさに『示唆の文学』である。何よりも読むことで自分も書きたくなるのがいい。彼の思想は世間的には「異端」に属するだろうが、そこから我々の「常識」がいかに脆弱な基盤に立っているかをそれとなく気付かせてくれるのだ。例えばある1節に『「何でも数字、数字」と嫌う人がいますけれど、数字を使うのは人間だけで、実に人間的な評価だと思います。」(同上、1月10日付)とある。こういう箇所が到る所に散見する。さて、8月15日には妻籠に行った。ここも「死ぬまでに一度は行っておきたい所」といえなくもない。また馬篭には行っているのに妻籠へ行っていないのは申し訳ない気持ちである。同じ理由で奈良井宿も行かなくてはならない。

2004年10月04日(月) あてね
先月のブログは2日分しか書いていないのだな。反省するが、しかたがない。最近「継続は力」という言葉を新聞でよく見るが(どうもイチローの記事のようだ)、本当に継続することは才能のひとつだと、つくづく思う。さて、家族がひとり(一匹)増えたことを報告しよう。

案の定、子猫を抱いたままS子が帰ってきて「やっぱり飼えないって。どうしよう」という。見ると人間の子供たちもぞろぞろ付いてきている。「おばさん、どうするの?」「見せてー!」と子猫よりうるさい。うちに以前からいる猫たちも突然の子供たちの襲来にパニくってT子(妹)の部屋に逃げ込んでしまった。「うちだって飼えないよ。誰か飼ってくれる人、いないか、探してきて」とまず、子供たちを追っ払い、とりあえず、相談。飼わずにすむならそれが一番であるが、もう仕方がない。それにしても団地の庭にダンボールに入れて捨てるとは。捨てた奴は、誰も通らないような堤防などに捨てるよりは罪が軽いとでも思っているのだろうか。団地で捨て猫を見かけても飼えない人は、それを「見殺しにする」という呵責を負う事になる。捨てた奴は他人のそういう気持で自分がいくらかでも楽になると思っているのではないか。怒りのやり場がない。子猫はと見ると、もうお乳をたらふく飲んで椅子の上ですやすや寝ている。薄汚れていて、お腹をみるとノミもいっぱいいる。「この子には罪がないし、しょうがないねえ」とS子はにやにやまんざらでもなさそう。これがまたハラが立つ。
そんなこんなで、やはり結局飼う事になり、名前も時節柄「あてね」に決まり、病院でノミの薬も買って来て処置する。今の薬は効果てきめんで、ほんの一滴を後頭部の下の首筋に垂らしてやると、2〜3日でもうノミの死骸がソファの上に散乱している。あてねのお腹には一匹もいない。ネコのノミの薬はすごいことになっている!
こうして1か月がたち、あてねはすっかり我が家の一員になった。先輩のしろやすずたちは、初めは見るだけですごいうなり声をあげていたが、慣れるもので今は認めているようだ。あてねの方もすっかり大きな先輩に慣れたようで、特にしろにじゃれまくっている。しろがイライラして自慢の尻尾を振り回すのが、あてねには格好のおもちゃになるのだ。しろは噛み付いたりはしないが、迷惑そうなのは見ていて気の毒なくらい。しろやすずが逃げ込むT子の部屋へも最近は自分で入るようになり、夜3匹があばれて眠れないとこぼしている。子猫の時期はほんの一瞬だから、ガマンするしかないだろう、と自分の部屋にはネコを一歩も入れない私がいう。ではもう一枚。

2004年09月16日(木) 三浦先生
旅日記?の続きを書く前に先週の土曜日に友人の出展している「G回路展」(愛知県美術館ギャラリー2004年9月7日〜12日)という美術展覧会に行ってきたので、その感想を述べたい。古い友人で人生の師匠でもある三浦英(ヒデリ)氏は、今はもうあまり見かけなくなった典型的な「闘う画家」である。権威におもねらず、信念を持って絵を描いている。画題は常に陰鬱でかつ告発的である。美しい絵ではない。政治と社会を風刺し、断罪するおどろおどろしい絵である。政治的立場を鮮明にしてときの政権を罵倒し、辛らつに批判する。ところかまわず自分の意見を述べ、敵も多い。しかし、人柄は好々爺である。囲碁が強い。風貌は違うが、私はなんとなくベートーベンをイメージする。
そういう彼が、長年自ら主幹してきた「20世紀末展」を20世紀末に終了し、新たに参加・発表の場としているのが、可児市を拠点とする「G回路展」である。今年の展覧会には彼が起稿した「G回路展の歴史」を私がワープロで清書したものが「展示」されていたが(私は長年彼の自称秘書を勤めてきた)、それによると、明治期に創設された「文展」(「日展」の前身)から分岐した「二科展」を源流とし、1969年に「カニ会研究会」として発足したのを起点とする(「二科」と「可児」を掛けたらしい...)。が、私には三浦氏はこの反骨の絵画グループさえ、超えちゃってるという気がした。彼の絵はこの展覧会においても異質である。今回は十字架をモティーフとして人類の破滅的未来を具象化している。われわれはこんな世界に向って進んでいるのだぞ!という作者の警鐘の叫びが20数枚のすべてから感じ取れる。彼の絵のライトモティーフであるエイリアン的生物(これは人類の未来の姿だ)も顕在しており、それがさらに醜怪さを増している。小さく描かれたヒトラーの顔がむしろほっとさせるほどである。こんな絵を、この時代に、この栄のど真ん中で堂々と発表していることが強い感動を呼ぶ。土曜日、無料にもかかわらず、観客は少ない。こういう絵が話題にならないことが、私にはコトの深刻さを思わせる。「ノアの箱舟」のノアも洪水の前、人々に神の怒りを説いて回ったが笑われたではないか! 私は笑わない。彼と共に箱舟に乗りたいものだ。
余談になるが、もうずいぶん昔、三浦氏の絵でやはりエイリアン的生物を描いたものがあったが、発表前本人に聞いた時「生物でもなく、物質でもないアイマイなもの」といって、なんとかいう題(忘れた)をつけていたのを、私は「モノドロミー空間」というのはどうかと提案し、受け入れてもらったことがある。モノドロミー(monodromie)とは数学の用語で、19世紀フランスの天才数学者ガロアの遺書にある有名な「曖昧の理論」について、日本の高木貞治博士が『monodromie群などに関するものでもあろうか』と著書(「近世数学史談」)に述べているのに因る。後日、名古屋駅前のあるギャラリーでこの絵が展示された時、題についてのマスコミの質問に対して三浦氏が「これはアイマイということです」と応えていたのを新聞で読んで、快哉を叫んだのが私である。
2004年09月12日(日 ) 岩村町・宇治平等院
ずいぶんのご無沙汰となってしまったが、特にいいわけはない。この半年間の近況をまとめて書いておこう。自治会長の任期を終えてずいぶん気が楽になった。新会長さんとも「引継ぎ」と称して一緒に飲みに行ったりして仲良くなった。もう自治会の方は完全に手を引いてしまった。


5月に、岐阜県の恵那市へ行っったとき、そこで見た「女城主の里・岩村町」という看板に釣られて足を伸ばした。途中、美しい田園風景を観た。写真がないのが残念だが、写真では伝えられないかもしれない。一面に広がる青々とした水田が山の傾斜に沿って少しずつせりあがっていくさまがなんとも言えない。岩村町に着いてから手に入れた宣伝パンフにも「女城主の里」の他に「日本一の農村風景」といううたい文句があった。本当にきれいだったから、山城はともかく、これを見るためもう一度来たいと思った。
6月には「生きているうちに行ってみたいところシリーズ」の1番目として宇治の「平等院」に行った(このシリーズはいま思いついた。これから続けるのだ)。宇治川が美しかった。

十円玉の模様でおなじみの「平等院鳳凰堂」。


2004年03月27日(土 ) 任期末の異変
今日は団地自治会長の活動をまとめて書いておきたい。まず1月〜2月に新年度役員の選挙があった。
選挙は棟を3つに分けたブロックごとに団地の居住者がこの人にと思う人に投票し、三役役員を選出する。それから選出された新役員のお宅に旧役員がお願いにあがって承諾を得て初めて成立する。民主的といえば民主的だが、なかば強制的でもある。まあ大体仕方ないと引き受けてくれる。一度役員をやると10年は断ることができる決まりなので、それも引き受けてもらうのに効果がある。今回もさっそく「新役員」の一人が出来ないと言ってきたが、「今年やらなければ来年も選ばれるし、いつかはやることになる。早い方がいいのでは」と説得した。
次に、団地の塗装工事があった。数十年に一度、各室の鉄扉など金属部分の塗装を住宅公社がやってくれるのだが、一軒一軒行なうので業者も大変、自治会も大変である。一番の問題は、自転車置場の塗装の時、持ち主不明の放置自転車が邪魔で塗装ができないことだった。結局放置自転車を一箇所に固め、塗装が済んだところでまた戻すことにした。今でも自転車置場の一部に山積みされたままである(ざっと50台くらいはある)。これをどうするか次期自治会役員の重点課題になるだろう。たぶん業者にお金を払って引き取って貰うことになるのではないか。なんだか環境問題の将来を見る思いである。
終わってみると中々きれいになって悪くない。「今度は団地の棟の外壁も塗装してくれるいいのに」という意見もあった。
それから次期役員への引継ぎ実務では「備品台帳」というのがあってこれに苦労した。自治会の持ち物の点検である。本当は箒一本、ごみ袋一枚まで記帳しなくてはならないが、最後はいい加減になった。正直言って捨ててもいいものがヤマほどあるが、誰もそれが出来ない。捨てても文句を言われることはないと思うが、でも自分がやるのはイヤだという気持が働く。まあ、古くからいる人がまた会長になった時に処分してくれればと期待する。
他には、いくつかの所属団体での慰労会出席。これは考えようによってはイイ事なのかもしれないが、宴席が得意でないものには苦痛である。
そしていつもの回覧活動。口にくわえて「ピーッ!」と鳴らす「呼子」という笛があるが、災害の時に役に立つということで地域の自治会連合会でこれを購入し、各戸に2つずつ配るという。で、200個あまりを持ち帰り、笛を箱から出し、これと使い方の「メモ」をホッチキスで留め、一人で全戸配布した。本当なら組長を通して各戸に降ろすのだろうが、手続きが面倒なので一人でやってしまった。案の条、何軒かから「あれ、何?」という問合せがあった。ある人などは「またどこかの悪質業者が自治会の名を利用して売りつけようとしているのか?」といってきた。連合会の作ったメモに自治会連合会の名称が入っていればと思うのだが、そこが提供する方には善意しかなく、貰う方の気持になっていないのだ。
———とにかくすべてが終わって、やっと一息入れるかと思った昨夜、一人暮らしだったお年寄り(男性)が3日も前に亡くなっていたことが判明、自治会長として責任を感じる出来事があった。
26日夕方8時ごろそのお年よりといつも連絡を取っていたという方が「最近連絡が取れない。様子が変だから一緒にきて欲しい」とうちを訪ねて来られた。一緒にいってみると明かりがついたまま、しかもドアが施錠されていない。ドアを開けるとすぐ数日分の新聞の束が玄関に溜まっているのが見えたので、もうこれは警察しかないと判断、中には入らずすぐ警察署に連絡した。この時身内の方にすぐ連絡しなければならなかったのだが、あいにく居住者名簿を時期会長さんに渡してしまい、その人も今夜は名古屋にいないとのことで連絡の取りようがなかった。痛恨の思いであった。一旦帰宅し、しばらくしてから再度訪ねてみると、警察からの連絡で身内の方が来ていた。まずは一安心し、聞いてみると23日頃に急病死らしいとのこと。早速他の役員に連絡、今後の段取りを話す。最近はあまり団地の集会所での葬儀は少なく、業者の葬儀会館で行なうことが多いので今回もおそらくお通夜と告別式への出席だけになるだろう。
亡くなられた方は「折り紙」を得意としていてマスコミにも取り上げられたことがある人だった。家の中には無数の「作品」が整然と飾ってある。一度お邪魔した時に一つ戴いたこともあった。今まで何度か会長として電話をもらったことがあって、独居老人をねらった悪質なセールスに注意するよう回覧板を回せというような内容だった。おだやかな、正義感の強い人だった。
どんな仕事もそうであるが、最後まで気を抜いてはならないと思うことしきりであった。また、この団地にも一人暮らしのお年寄りが多いが、今回のように突然発作に襲われた時に周りに誰もいないことへの不安はどれほどのものか。緊急連絡用の電話を設置するなど、自治体でなくてはできない仕事も多いが、団地の自治会にとっても課題である。しかし、役員を降りれば、もう他人事になってしまうのだろうな・・・。
2004年02月15日(日 ) 電話工事
朝、いつものように新聞を取りにいったら、何と1週間前のやつだった。何かの手違いだろうが、初め1面の記事を読んでいる時は気付かずに(なんとなく変だとは思ったが)、マンガで気付きました。それにラ・テ欄がない(2月8日は翌日が新聞休刊日だったのでいつもと違ってた)。 さっそく電話して本当のを持ってきてもらった。自分も昔新聞配達をしていて、とてもここには書けないような恥ずかしい間違いをしたこともあったので、怒る気にはならないが、いったいどういう手違いなんだろう朝食後、S子(妻)が「FAXが欲しい。今のは壊れているし」といってきた。、「ちゃんとパソコンに入ってる(まいと〜くFAX Personal Version4.52)じゃないか」というと、「あれ、調子悪い。送れない」という。例によってハイテクオンチと思って私が代わりに送ろうとすると確かに送れない。原稿をセットして送信スタートすると、FAX電話器が「FAXに切り替えます」とアナウンスしてそのあとPCがハングアップする。どうもS子のパソコンに引き込んである電話線が、その壊れているFAX機から来ているのが原因のよう。つまり、パソコンからFAXを送ると、壊れているFAX電話機につながって、そこから先へは行かないのだ。だからまず先にパソコンへ電話線を引き込み、その次にFAX機に行くようにすればいいのだが、それだと大工事になる。で、考えたのが、FAX機に入っていく電話線を二股に分け、一方をパソコンに、一方をFAX機に持っていけばいい。だから電話線用の二股を買ってくればいいのだ・・・
というわけで、41号線のわが家御用達の八千代ムセンへ出かけた。昨日は大曽根メッツのエイデンでデジカメを買ったから、休日のたびに電気屋に行っている。二股はすぐあった。540円(税抜き)。S子はやっぱり未練らしくFAX機のパンフをたくさん持って帰った。それから東片端の「正文舘」へ行ってやっと「森博嗣『四季・秋』」を手に入れた。次はホームセンターナカイと春日井市の松河戸町にあるカーマホームセンターをハシゴしてリビング兼ダイニングの床に敷く予定のカーペットを見に行った。結局買わずにカーマの近くのスーパー「SEIYU」で昼食、そこの百均コーナーで雑貨を少々。
帰ってからすぐFAXの配線をして、パソコンのFAXをテストすると、みごとに成功。これでもうFAX機は買わないくて済む?
買ったばかりのデジカメを持って出かけたが、大したものは撮れなかったので、うちの大事なネコを(このブログ最初の画像です)。

 ちょっと怖い顔したのが撮れました。
ちょっと怖い顔したのが撮れました。
2004年02月14日(土 ) デジカメを購入
やっとデジカメを買った(64MBのSDカード込みで¥47,500)。京セラのfinecam SL300Rというやつ。特徴としては、まず厚さ(薄さ) 15mm。たて・横は62.5mm×100mm。ちょうど往年のオーディオカセットテープくらい。そしてレンズの部分が前後に120度ずつ回転し、モニタを見ながら景色でも自分でも写せる。USBケーブルでPCとつなぐと、それだけでリムーバブルディスクとして認識される。あとは画像ファイルをPCに移してペイントなどで加工したりもできる。
付属のソフトを使って画像処理をしたりアルバムを作ったりもできるようだが(なぜかKODAKのソフト)、それをインストールしたらデジカメがリムーバブルディスクとして認識されなくなった。あわててアンインストールし、PCを2、3度再起動してやっと元通りになった。もうこのソフトは使わない。
2004年02月13日(金) バレンタインデー前夜
朝、早速正文舘へ注文した本(森博嗣「四季・秋」)を取りに行ったのだが、あいにく午後になるとの事。すごすご帰る。店員は皆、親切なんだが、肝心なところが・・・。さて、13日の金曜日である。実はそれらしいこともあったが、それより「バレンタイン・イヴ」(というかどうか知らないが)の方が世間的には盛り上がっているようだ。テレビやラジオやデパートなど、特集を組んだりして喧(カマビス)しい。私も塾の生徒からもらった。やっぱり嬉しい。
いつも聞くFM番組(「ミュージック・プラザ」)でいっていたが、最近は女性が好きな人のためより自分のために高価なチョコを買うらしい。初めは自分のはついでだったのが、この頃はまず自分用を買うとのこと。これはチョコ・メーカーにとってもとてもいいことだろう。女性が自分のために買うということでチョコ職人(?)も腕を振るいたくなる。これまでムリに義理チョコを買っていた人も、そんなことをしなくても買うのが楽しみになるというものだ。初めは何とか売上を伸ばすためにバレンタインデーを利用していたチョコ業界の陰謀も、これからは堂々とおいしさをアピールして真正面から一年中売ることができる。人のために買うという浮ついた需要が、おいしさを根拠にしたしっかりした需要に変わってきたといっていいのではないか。
しかし、ひとつぶ何百円などというチョコは、自分で買ってまで食べたいとは思わない。もらうなら別だが・・・。昔「森永ハイクラウンチョコレート」のブラックが好きだった。煙草のような厚紙の箱の入れ物に厚手のチョコが4本入っていた。今でもあるらしいが、イメージは変わってしまった。S子(妻)はよく「明治の板チョコ」を買ってくる。これもおいしい。
2004年02月11日(水) 今のうちに
久し振りの仕事なしの休日(祭日)。土・日曜日はいろいろヤボな用があって自分の時間にはならないことが多いが、今日は何も予定なし。午後から久し振りに本屋へ行った。初めはナディアパークの紀伊国屋へ行くつもりだったのだが、41号線を南下していたら正文舘の看板が目に入って急きょ予定変更。ちょっと行き過ぎてから最左車線に寄り、左折—左折—左折で戻った。専用のかなり広い駐車場もあるので、これからは本屋はここだなという気がした。約2時間館内を歩いて4冊買い、1冊注文してきた。買ったのは、「プチリファレンスPHP4」(秀和システム)、「天文計算入門」(恒星社)、「数学小景」「幾何への誘い」(以上2冊岩波現在文庫)で、注文は「森博嗣『四季・秋』」(講談社)。「〜PHP4」は今勉強中。あとは趣味。
「数学小景」は尊敬する高木貞治先生の著作で、中も見ずに買った。「幾何への誘い」も好きな小平邦彦氏の著作。森博嗣氏の「四季・秋」はこのシリーズが出るたび、うちの元生徒が教えてくれる(彼女も森ファン)。2週間くらい前「出たよ」の連絡。何軒か本屋を回ったが、結局今日注文して、あさってには手に入りそう。
「天文計算入門」は、出来るものなら自分で日食を予測してみたいという以前からの希望で買った。見つけた時はちょっとドキドキした。パラパラ覗いてみるとやはり難しそう。たとえこの本が読めたとしてもまだ「入門」だから無理かな・・・。
こんな時思うのが、今のうちにやりたいことやらないと死ぬ時に後悔するぞということ。そう思うと多少の困難は乗り切れそうな気がする。それにもう若くないのだからまだ頭が回転するうちにやらなければとも思う。この「頭の回転」については、現在の自分(56歳)には鈍くなったことの自覚があまりないが、さすがに60〜70歳になってもという自信はない。第一、何歳まで持つかがわからない。だから、今のうちということになる。人間いつまでたっても今のうちだが。
2004年02月08日(日 ) 日本昭和村
今日は岐阜県美濃加茂市の「平成記念公園・日本昭和村」(参考:http://www.nihon-showamura.co.jp)という道の駅へ行ってきた。道の駅といってもちょっとしたテーマパークである(名誉村長さんは女優の中村玉緒さん)。実は去年の12月にも行ったのだが、そのときはなぜかこのブログには書いていない。そのときにはまだなかった「昭和銭湯『里山の湯』」が12月20日OPENしたので、それが今日の目標。銭湯は昭和村の外にあってそこだけでも入れるのだが、せっかくだからお風呂の前に会場内を一巡りしてみると(入場料が冬季限定で半額の400円)、乗馬体験とか羊牧場など前にはなかったエリアが2つ3つ増設されていた。それにまだ何か着々と造成中のものもある。今度来る時にも何か増えているかもしれない。前回と同じ食堂で蕎麦を食べてからいったん村を出て、今日の目的である銭湯へ。一人600円。男女とも入場制限をしているほど混んでいる。「昭和銭湯」というくらいだから壁に富士山の絵でも書いてあるかと思ったが、そんなこともなく中は特にこれといって特徴はない。まだ出来て間もないので板張り廊下の板が新しい。流行の足湯は無料。明日はT子(妹)の誕生日。帰りにケーキ屋へ寄ってバースデーケーキを予約(¥1500)。我が家は12、2、3月と誕生日が集中しているのでケーキが毎月のように続く。そのかわり次の12月までケーキはまず食べない。昔は12月には結婚記念日と私の誕生日とそれにクリスマスにそれぞれ別々にケーキを買ったこともある。だから嫌いではない。
2004年01月18日(日 ) 「世界に一つだけの花」
今日から始まったTBSのドラマ「砂の器」(日曜日PM9時)を見た。スマップの中居君が主役で初回からいきなりすさまじい殺人シーンを演じていた。もう20年以上前に松本清張の原作を読んだとき、犯人の動機がわかるクライマックスの場面がちょうど深夜で恐くて鳥肌の立ったのを覚えている。ドラマはまだ1回見ただけだが、意外に面白そう。ただ、時代設定をまったくの現在(犯行日が2004年1月4日)になっているので、原作の持つ時代制約性をどう乗り切るのか、ちょっと心配。また、主人公の追想の中に、(たぶん自分であろう子供と父と思しき人との)「巡礼者の旅」のシーンが出てくるが、現在30代前半の(とすればだが)主人公の少年時代ならわずか20年前であり、80年代にこういう親子の旅があったというのは明らかに不自然。とはいえ彼の「宿命」とは一体何か、とても興味が持てる。中居君の演技は素晴らしい! 来週も見るぞ。——TBS「砂の器」の1時間前にはNHKの「新選組!」で同じくスマップの慎吾ちゃんが主役。昨年末の「紅白」でもスマップがトリで「世界に一つだけの花」を歌って、それがきっかけだと思うが、新年にまたオリコンで第1位に返り咲いたそうである(39週ぶりの新記録とのこと・「ザテレビジョン」1・23号より)。この歌は、先日のわが学区での成人式で地元の(自民党の)市会議員が挨拶の中で取り上げていたし、また今月、日本共産党第23回党大会があったが、そこでも取り上げられていた(「赤旗」1/18日付)。また、イラク戦争反対の集会ではまるで反戦歌のように若者たちが歌っているそうである。反戦歌よりもっと広い気持がそこにはあるようだ。
2004年01月17日(土 ) ラフマニノフがきっかけ
毎日少しでもここに書き込もうと思っているが中々出来ないものだ。もう前回から8日経っている・・・。10日に念願のMDコンポを買った。41号線沿いの豊場にある「八千代ムセン」という量販店で、ONKYOのFR-SX7Aという製品を買った(¥41,790)。アンプ、CD、MDが一体型になっているやつで、シンプルで場所を取らず、それでいてアンプは20W+20W。今回はカセットテープは付いていない。いよいよ我が家もMD時代の到来か。ちょうど1年前の1月10日付けのこのブログに「当分はビデオでFMを録音する」と書いている。まだDVDはいらないといっていたのだが、MDのことは書いていない。どうもMDのことは当時あまりよく知らなかったようだ。
八千代ムセンで物色していると、店員が話し掛けてきたので、希望を言うと、上記の製品を勧めてくれた。この時、サンプルCDを使って音比べをしてくれたのだが、聞くのは主にクラシックだというと、CDをクラシックのものに替えて聞かせてくれた。これが何とこの日の朝、家で(ビデオテープで)聞いていたラフマニノフの「パガニーニの主題による変奏曲」そのものだった。思わず「これ、さっき家出聴いてきたばかりですよ」というと、店員さんも「そうですか。私もこれは大好きで、こうやって持ち歩いているんです」と答えてくれた。意気投合してしばらくクラシック談義に花が咲いたが、結局それを買ったのだった。
それからずっとこの機械に取り組んでいる。取りあえず毎日のタイマー録音をセットして、あとはゆっくり説明書を読んでどんなことが出来るのかを調べる。もっと早くMDにすればよかったと思うことしきり・・・。
12日は成人の日。どこかの会場みたいな不心得者はうちの学区にはいなかったが、茶髪に白い紋付・袴という通称「白い悪魔」は一人いた。でもおとなしく「誓いの言葉」を読み上げていた。新成人は50人ほどで、彼らより多い学区役員や保護者が周りを囲んでいるような会場ではあまり目立つことも出来ないかも。全体にやはり堅苦しい時代錯誤な式であった。それでも式が済んで記念写真に移る間、新成人たちがお互いにケータイで写真を撮ったり談笑しているのを見るとこっちも和やかになった。私は受付の一人として参加したが、隣りの役員さん(私よりは若い)が「成人式は初めてでどきどきしますよ」といっていた。聞いてみると自分のときは「何だか嫌で」行かなかったそうです。なんだ、私と同じだ。式が済むと後片付けの後、別室に移って自治会連合会の1月定例会があったのだが、この時お弁当が出た。ちょっとしたご馳走。まあ、役得というのか、ありがたく戴きました。
2004年01月09日(金) 初ごみ出し
このところ、年の初めのぐうたらとそのあとの慣れない仕事で疲れたのか、昨日は夕食のあとすぐに横になって、朝まで10時間寝た。今朝は今年初の分別ごみ(資源)出しの日だったので寝ぼけ眼でゴミを持って行くと、まだ7時前なのに山積みだった。2004年01月07日(水) 「成人式」に出る!
昨年の11月にここの学区で「ウォーキング大会」というのを町内会連合で取り組んで以後、しばらく自治会長の仕事もヒマだったのだが、今月には成人式と団地のペンキ塗装工事という大事業がある。正月も過ぎてすぐ塗装工事の業者さんが会長さんにということで挨拶に見えた。1/13〜2/27という長丁場である。主に玄関鉄扉と団地共用部のペンキ塗り替えだが、一軒一軒塗っていくのでこんなにかかるのだそう。成人式の方は、1月12日に学区小学校でまったく形式ばったのをやるみたい。式次第を見ると、小学校の講堂の壇上に国旗(日の丸)を飾った会場で、「君が代」斉唱で始まり、名古屋市長の挨拶(もちろん代理)、市会議員・校長先生等の挨拶云々とある。新成人の出番は代表者の「誓いの言葉」のみ。最後に万歳三唱で終わるというもの。これじゃあ今の若者に嫌われるのも無理ない。明らかに新成人のためというより、年寄りたちの自己満足のための式である。われわれ役員も式服で出るようにとのお達しがあった。自治会からのお祝い金も出るが、慣例でひとり2千円。学区連合会からのを合わせて4千円。小学生のお年玉でももう少し出るだろうに。私が会長なんだから5千円くらいに奮発してとも思うんだが、前例になるので勝手なことは出来ない(だからいつまで経っても何にも変わらないんだといわれればその通り)。
新成人たちの気持はよくわからないが、むしろ親の方が喜びが大きいだろう。手塩にかけて育てた子供が立派に成人した姿を見るのは親として感無量だろう。私の成人式当日は、式には出ないで映画を見に行ったことを覚えている。ソビエト映画の「戦争と平和」(リュドミーラ・サヴェリーエワ主演(この名前は今でもいえる)だった。式に着ていく服がなかったこともあるが、式に出ないことが自分にとってはひとつの主張だったような気持ちもある。これは負け惜しみではない。当時親しかった友人が親のそろえた紋付・袴で出席したとあとで聞いて、「お前、なんで式に出たんだ」と論争したのも懐かしい思い出である。
2004年01月05日(月) 初洗車
今日は念願の初洗車をした。といってもGSでやってもらっただけ。千円。自分でやるには寒いし、それにキズをつけるのがコワいので。いつもなら月曜日は「不燃ごみ」回収の日だが、今年は5日は休み、12日から。でもやはり心配したとおり3人ほどごみ置き場の横に出していた人がいた。前日から注意の貼り紙をしておいてもこの状態。誰もこれを片付けなかったら、来週までずっとここに捨て置かれることになる。
久し振りにパソコンのメールチェックをしたら、年賀メールが2通ほど来ていた。返事を書きながら「今年はどんな年になるか」と考えてみた。やはり自衛隊のイラク派遣のことが気にる。いよいよ日本が戦争に巻き込まれるかと思うと、心配でならない。世論の大多数が反対していることを政府は押し通そうとしている。そういう国にしたのは他ならぬ我々だ。みんなで「イラク派兵」に反対しましょう!
2004年01月04日(日 ) スパガーラ
長いと思ったお正月休みも今日で終わり。今日は「小牧天然温泉・スパガーラ」(参考:http://www.spagala.com/)へ行ってきた。前は「ラッキー健康ランド」といっていたところ。新装開店してからは初めて。変わったところといえば、リラクゼーションというのか、マッサージやネイルアートなど、若い女性向きのコーナが増えたこと。自由にマンガが読めたり、子供をあそばせたりするところもある。お風呂もいくつか増えた。「五右衛門風呂」も出来ていた。ここでゆっくりして正月休みもおしまい。明日は私もS子(妻)も仕事始め。昨日(3日)、ある生徒から冬休みの課題についての質問(数学)が来た(FAXで)。さっそく解答を作って返信したところ、「真っ黒な紙が来た」という電話。どうも受信はいいが送信すると真っ黒になるらしい。で、面倒だがFAX用に作った解答をスキャナでパソコンに取り込み、ワープロの画面に貼り付けてパソコンからFAXしてみた。FAXソフトは「まいと〜くFAX V.4」。S子などはやはり紙のFAXのほうがいいらしく、FAX機を買い替えたいという。日本のペーパーレスはいつまでたっても実現しないとボヤいてみても仕方ないが、自分でも送りたいものを紙に鉛筆で書いてスキャナで取り込んで送っているようでは人のことは言えない。それにしてもA4・B4用紙の安いこと! 紙を使うなといってもあまり説得力はないわけだ。
2004年01月03日(土 ) 疲労参拝
2日は伊勢神宮(内宮)へ初詣に行ってきた。お伊勢さんへは10何年前にいったことがあるが、家族3人で初詣というのは初めてである。混雑は覚悟の上だったが、予想以上。内宮正宮前には何百人という人が幅20mにも並んで時速100m位の速さでゆ〜っくり進んでいく。階段の上にある鳥居をくぐりたい人はもっと遅い。階段右端(つまり鳥居の右外側)を通ってさっさとお参りし、帰ってきた。われわれの実のお目当ては「おかげ横丁」で、お参りの方がついでだからバチが当たる。こちらもすごい人でほとんど見て帰ってくるだけだった(ヒマそうな店で伊勢うどんを食べたが)。でも正月気分は満喫したかな。伊勢参拝は、クルマで来る人は今年からシャトルバス方式になっていて、伊勢道を朝熊ICで降ろされて(つまり「伊勢西」と「伊勢」の両ICは降りられなくて通過)、そのまま「三重県営サンアリーナ」というイベント会場の駐車場へ誘導され、そこで千円払って駐車し、シャトルバスで内宮へ運ばれるというわけ。「社会実験」と銘打っていたから、初の試みでうまくいけば今後もこうなるのだろうか。行きはまあよかったが、帰りのシャトルバスに乗って帰るのに1時間以上もバス停で行列して待たされた。明るいうちに並んだのに段々暗くなり寒くなり、すっかり冷え切ってしまった。もうこりごり。これでまたしばらくはお伊勢さんには出かけないだろう。
今日3日にお正月早々団地にお葬式があった。朝起きたら玄関ポストに他の三役さんからの告別式の連絡が入っていた。あわてて礼服を取り出し、葬儀社手配のバスで式に出向く。この時期にもかかわらず、多くの人が参加していた。まだ60歳という若い方で、1年間の闘病生活の果てに亡くなられたということを喪主の方の挨拶で知った。
2004年01月01日(木) 2004年あけましておめでとうございます
あけましておめでとうございます。たった今まで「紅白」を見ていた。平井堅(坂本九とのデュエット?)と森山直太郎、それにスマップが印象に残った。あと、「涙そうそう」もよかった。それにしても赤組のボロ負け振りがすごい・・・。
このブログも毎日書きたいことはあってもなかなか書けなくなった。一番の理由は気持(=時間)に余裕がなくなったというか、どうでもよくなっているということもある。ちょっと人生に対して捨て鉢になっているのか。欲がなくなった。よくないことだ・・・。
と、いいながら、昨年11月にクルマを買い換えた(3年のローン)。前のが6月に車検だったのだが、その前後から段々調子が悪くなってきて、修理などにお金がかかるようになってきた時に、以前にもこのブログに登場したH井君に相談したら「新古車でいいのがあるよ」と照会してくれたことで、決心した。今度もスズキで「WAGON-R FMエアロⅡ」という名前。格段に装備がすごい。まずエアバッグが運転席・助手席にある。そしてMD・CDが付いてる。ミラーがたためる。ABSもある。あと特徴として前席がベンチシートでチェンジレバーはコラムシフト。外装の前後左右にエアロという飾りがついている。私には贅沢この上ないクルマとなった。
相変わらず音楽はラジオのFM番組をビデオに録音して聞いているが、クルマにMDが付いた事で、MDレコーダが欲しくなってきた。S子(妻)のコンポはMD付きなのにほとんど使っていないので、これを借りて今までテープで聞いてきたものをMDに録音し直し、それをクルマで聞くようにしている。音は悪いけど、当分はこれでいい。で、知ったのだが、今のMDは表示されている録音時間の2倍、4倍で録音できるのだ。これなら今ビデオテープで聞いているFMの音楽もMDで十分録音できるから、近々MDコンポを買う予定。マーラーやブルックナーなどの大曲もMD一枚に楽々入る。これらの曲はCDでは今でも2枚組みにして売られている。昔のカセットテープでは90分テープでも片面45分だから途中でいったん切れる。もうアナログテープの時代は音楽でも映像でも終わりに近づいているらしい。別にそれでもよいが、デジタル万能というのはあまり好ましくない。時計でも仕組みとしてはぜんまいからクォーツに変わっても、表示はアナログの方がわかりやすいように、音楽・映像もデジタルで記録して操作はアナログにして欲しい。例えば、ひとつの曲を線分で表わして、カーソルをその線分の好きなところへ持っていくとそこから再生できるという具合。
2003年11月01日(土 ) 深夜の珍事
あまり自治会長のことばかり書いているのもなんだから、今日は最近読んだ藤沢周平のことを書く。藤沢周平といえば、私は「用心棒日月抄」なのだが、これはテレビドラマで最初知った。古谷一行さんが主役の浪人で、背景に赤穂事件を持ってきてなかなかアイデアだなと思った。それから「三屋清左衛門残日録」を読み、それから「NHK金曜時代劇」で「蝉しぐれ」を見てこれにしびれた(この前後に衛星放送で「清左衛門残日録」も一部だが見た(仲代達矢主演)。あと、映画になった「たそがれ清兵衛」の原作も読んだ。
で、今は「よろずや平四郎活人剣」。まだ作品はたくさんあるようだが、自分としてはこれでそろそろ終わりかも。この人の魅力はなんといっても殺陣の描写。昔、中里介山「大菩薩峠」の島田虎之助が新撰組(の前身)と戦う場面を読んですごいと思ったことがあったが、藤沢周平もすごい。剣道や殺陣のことを何も知らなくても迫力を感じる。大体主人公が勝つのだが、それがいつもきわどくて、読んでいてほっとするのだ。こっちまでなんだかまた生き延びたなあという気分になったりする。武士といわれる人々が日々いつもこんな生死の境を生きていたとは思わないが、刀を持っている日常とはそんなものかも知れない。斬りあうことの恐ろしさを感じさせてくれる。と、同時に(男には)命をかけて戦わなくてはならない時もあるかなあとも思ったりした。(ここまで実は10/30に記述)
さて、話はまったく変わるのだが、今朝、といっても3時半ごろだからまだ深夜、とつぜんけたたましいベルの音が団地中に鳴り響いた。火災報知器。あわてて起きて出てみたが(ウチのすぐ前にベルがある)、火事はどこにもなく、ひたすら大音響のベルだけがジリリリリ....。ベルとともに女性の声で『火事です。火元を確かめ、消化してください』のアナウンス。でも、どうみても誤報。それにもうみんな誤報に慣れっこなのか、誰も出てこない。まずベル音を止めなければ。耳をつんざく音の中で、まず音を止めようと・・・どれだ? なにをどうすれば止まるのだ? 火災報知器ではなくて郵便ポスト室の配電盤のような箱(あとでみると『火災受信盤』と書いてあった)で『火災』というランプが『一階東』というランプとともに点滅している。(一階東とはまさにここであるが、別に火事で騒いでいるところもないし、第一、この騒ぎでも誰も出てこない)。どうやらこれが制御装置らしい。その中の『音響停止』というボタンを押すとアナウンスが止まった。が、まだベルは鳴っている。今度はその下の『地区音響一時停止』というのを押すとやっとベルが止まった。やれやれ・・・でも、まだ『火災』と『一階東』のランプが点滅している・・・。と思っているとまたしてもジリリリ・・・。あわててまた『地区音響一時停止』を押すと止まった。なるほど「一時停止」なのだと納得するが、じゃ、どうしたら完全に止まるのだ? これがわからない。次第に冷えてくる中でじっくりと受信盤の説明書を読む。またジリリ・・・止める、読む、ジリ・・。段々止め方がうまくなる。ジ・・といっただけで止められる。が、これではいつまでもここから帰れない。説明書は何度読んでもわからない。どのボタンがどこにあるのかもまったくわからない。オレが読んでわからないものは大抵の人が読んでもわからんぞと妙な文句をいいながら、ふと、火災受信盤のフタがネジで止めてあるのに気付き、これを開けようと思い立つ。一度ジ・・と鳴ったのを止めてその隙に家に引き返し、ドライバーを持ってきて開けようとネジを左に回したが、まったく開かない。「どうも違うな」といささか泣きたい気持でまた説明書を読んでいると一人の男性(私にオジサンと呼ばれても差し支えのなさそうな人)がエレベータから降りてきて、「誤報ですか?」と聞く。どうせ冷やかしだと思っていい加減に返事をしていると一緒になって説明書を読んでくれる。で、「どうも止め方がわからなくて、すぐまた鳴っちゃうんですよ」とちょっと真剣になって相談してみる。どうもこのままずっと付き合ってくれるみたいだ。心強い味方が現れてやや元気になる。でも、ベルの音はまだ止まらない。二人で「ああだこうだ」とボタンを押したりしてみるが、止まっているのをわざわざ鳴らしてしまうだけで、うまくいかない。しかしついに火災受信盤のフタが開いた。何のことはない、ドライバーでネジをくるっと右へ回せば開いたのだ。そういえばネジの頭が大きなマイナスになっていた。ドライバーなどなくても硬貨で開けられるようになっているのだ。
とにかく中を見たが、細かい配線が詰まっているだけでスイッチとかボタンなどはない。が、また説明書があった! これはありがたい。オジサンと二人して説明書をせっせと読み始める。私が「とにかく止め方を・・・」というと「まあ待ちなさい」とオジサンは目次をゆっくり眺めている。この人は本気で付き合ってくれていると思った私はオジサンのペースに任せることにした。「あったあった。12ページだ」 そこには地区音響を完全に止めるには、『音響停止』ボタンと『地区音響一時停止』を同時に3秒間押せと書いてある。やってみると、『火災』と『一階東』の点滅ランプが消えた。止まったのだ!
やれ、ありがたい、これで帰れるかと思いきや、まだ4つばかりのボタンが点滅している。しかも数分ごとにピーッと音がする。ベルほどではないが私の家の中なら十分騒音である。これも止めようとまた説明書を読み始める。そしてついに『復旧』というボタンを見つけた(これはビデオの予約ボタンのようにもうひとつのふたの中にあった)。それを押すとさらに2つのボタンが点滅をやめた。まだピーッというのは止まらない。どうもさっきいろいろ押しまくったときによけいなものを押したようで『xxが△△しています』(xや△はもう忘れてしまった)というのだがどうしたら元に戻るのか、やっぱりわからない。でももう1時間近くこうしているのでさすがにオジサンに「ま、これなら寝られないこともないし、明日、管理事務所に連絡してみますので・・・」と話してお礼をいい、お引き取りを願った。お陰で助かったことは間違いなく、感謝の気持で一杯であった。エレベータに乗られるときお名前を伺っておいた。
しかし、私はこういうとき「まあ、明日にでも」とは思えないタチで、とてもこのままでは眠れない。しかし小康状態にはなったので、今から徹底的に説明書を読んで絶対今夜中に復旧してやるつもりでいた。部屋にかえってヒータを焚き、時々鳴るピーッという音に闘志を燃やしながら、厚着をして机でじっくり説明書を読み、ついにもう一回『音響停止』ボタンと『地区音響一時停止』ボタンを同時に押せばいいことに気付いた。そして完全に点滅ランプを消した。システムは完全に復旧した。時計を見ると5時を回っていた。約2時間の戦いであった・・・
(結局また自治会長の仕事話になった・・・)
さて今日はT子(妹)と明日の「ウォーキング大会」のコースを下見がてら散歩してきた。たった2kmの道だったが、快い疲れで久し振りにビールがおいしかった。
2003年10月21(火) 4か月ぶり
4ヶ月ぶりのブログ更新。言い訳はまあ、忙しかったことに尽きるが、そんなのは言い訳に過ぎない。10月13日にこの団地で最後となる秋祭りがあった。最後というのは来年からは学区でのイベントが中心となり、各自治会はそれに参加するという形になるから。独自に行なうお祭りとしては今年が最後。その年に自治会長とは運がいいのか悪いのか・・・。
いろいろ苦労はあったが、自治会役員をはじめ皆さんの協力で成功したといってよい結果になった(S子(妻)もがんばった)。一番の成果はやはり団地住民どうし親睦を深めたことだと思う。当日よりもそれまでの準備でいろいろお付き合いすることでだんだん気心が知れてきて、少々の口論も和気あいあいと出来るようになった。こういう催しがなくなっていくということは、そういう親睦を深める機会も減るということ。やっぱりよくない。来年からの新しいお祭りではどうなることか・・・
と、いかにも心配しているように書いたが、実はあまり考えていない。無責任だがどうでもいいと思っている。とにかく早く会長職を解かれたい。19日には学区全体でのソフトボール大会で朝6時半から夕方5時まで駆り出され、せっかくの秋の晴天日一日をつぶされた。そして今度は11月2日にはウォーキング大会だって・・・一体何の権利があってオレの大事な時間を・・・。かなりムカついている。
こういうイベントがあると必ず顔を出すのが議員さん。このたびもソフトボール大会のため1週間前にちゃんと試合の行なわれる会場(庄内川河川敷)の草取りを市に要請し、実際やってくれたとかで、開会式の挨拶の時、参加者から拍手を受けていた。
私もそうだが、自治会長の多くは区政協力委員であって、市からお金も出る。この間「区政協力委員兼災害対策委員費用弁償」という名目で27,144円いただいた。このこと、あまり知られていないのは、もらった人が黙っているせいではないか。古い自治会員さんで「会長がちゃんと任務をこなせるのは組長さんたちの協力があるからだからこういうお金は皆で分けるべきだ」という人もいたが、わたしはこれで壁掛けテレビ(といっても14インチの液晶というだけだが)を買ってしまった。もちろん足りないので持ち出しもあるが、こういう臨時収入でもないと買えない。それからついこの間は学区保健委員(これも自治会長が兼ねる場合が多い)に対しても「謝金」という名目で13,572円出たので、これは待っていたように故障した炊飯器の購入資金にした。こんなわけで自治会長も捨てたもんじゃない?
2003年06月02日(月) 多忙な日
今日は朝から忙しい。やることがいっぱいあった。まず、車検のため友人のH井君の会社へ。最近、速度センサーが調子悪いらしく、走っている途中で急にシフトダウンしたり、逆にシフトダウンしないまま赤信号で止まり、トップのまま発信することが多くなったのでそのことをお願いした。代車を用意してもらってそれで帰る。私のクルマはスズキのLoFtだが、代車はスバルのSANBER。同じ軽とはいえ、慣れなくて運転がたいへん。帰ってから自治会長職務を2つ3つ。赤十字の寄付を「社員」として登録されている人たちから集めてそれを学区連合会へ納めるために銀行で振込み。その証明書を連合会へ持っていったのに留守。午後もう一度行ったけどまた留守。まだまだ用件があったが疲れたので昼食の後寝てしまった(昨夜は2時間しか寝ていなかったのだ)。
夕方、慣れないクルマで塾へ。少し早く付いたので喫茶店へ行き、久し振りに「少年サンデー」に目を通す(創刊号から読んでいる少年週刊誌。「海の王子」が好きだった…)。今、注目しているのは「Wild LIFE」と「D-LIVE」。「Wild LIFE」は絶対音感がある獣医(のタマゴ)の話。「D-LIVE」はフリーターのような若者が実は「ACE」という組織に属する天才的運転手? どんな乗り物でも運転できるのだ。どちらも奇抜な筋立てと痛快な結末でとても面白い。その他相変わらず「名探偵コナン」は快進撃だし、「犬夜叉」もいつ果てるともない筋で延々続いている。
塾では、今日はまず、大学院生のM崎君との「公正経済学」だったが、自由主義経済の企業と消費者に政府が税金をかけるとどうなるかをグラフを使って理解するという内容だった。面白かったのは政府の課税によって社会の財の一部に誰のものでもなく失われてしまう「超過負担」というものが発生するということ。たとえ抽象的とはいえ数学を駆使して社会を分析していけばそれなりに矛盾点を暴くことが出来るのだと思った。
二時限目はちゃらんぽらんの高校生徒、M田君。かわいい(背は高い)楽しい生徒だが、いうことやること支離滅裂、破天荒、はちゃめちゃ…は言いすぎだが、とにかく授業にならないくらい質問攻めで来る。それも妙な質問が多い。今日は「『旧約聖書』には予言が載っていて2006年に人類が核戦争で滅びると書いてあるって本当ですか?」とか、「光より早い乗り物を作れば未来へいけるの?」とか。なんと答えていいかわからないのでマトモに答えているとあっという間に時間が過ぎる。どうも時間を潰すためにそういう質問をしているのかとも思えてくる。とにかく今日は「円の方程式」をやっとの思いで説明、課題に移る。一番苦労する生徒だが、憎めなくて面白い子である。
2003年06月01日(日 ) 大須!
今日は久し振りに家族で大須へ行ってきた。何日ぶりか誰も覚えていないので調べてみると去年の6月以来、1年ぶり(その時「ハリーポッター」のDVDを買っている)。実はちょっとした計画があって新しく購入するパソコンを下見に行ったのだが、気に入ったものがないのでやめた。なぜパソコンは高いか。いつまでも10何万のままである。どんどん進化してるって? そんなことはない。XPにしたってPentiumにしたって、あんなものいってみりゃ、マイナーチェンジだ。マイナーチェンジを小出しにして値段を維持しているのだ。あとはデザインの目新しさでさも納得できる値段であるかのように見せているにすぎない。
それにしても大須のパソコンショップはGOODWILLばかりになってしまった。一体何号店まであるんだろう。以前は何のお店だったか忘れてしまった所にいつのまにかGOODWILLが出来ている、という感じ。赤門通りの「グッドウィルエンターテイメントデジタルモール」なんていつ出来たんだろう。映画館かと思ってしまった。ちゃんと中を見てきた。要するにパソコン関係のお店。ちょうどこの日、お気に入りだった携帯ストラップが壊れてしまったので、ここで短いのを買ってあとで壊れたのと合体して復活させた。
ほかにもパソコンショップを数軒ひやかしてから万松寺通りの「あした葉」(讃岐うどん屋)で遅い昼食。その後観音様にお参りして帰りに東仁王門通りの「ふれあい広場」で大道芸をちょっと見て(手品)、「ボルサ」でコーヒーを飲もうとして満員なのでやめて…結局なんにも買わずに帰ってきたが、駐車料金だけ2,240円(約4時間!)も払ってちょっとムダ遣いを反省。S子(妻)にも嫌味を言われた。家の近くまで帰ってから「TARO」という喫茶店でコーヒーにした。
2003年05月19日(月) 『て』のつくもの
いや〜疲れた、昨日の棟掃除。ここの学区全体で一斉に側溝清掃というのがあってこれがコタえた。歩道沿いの側溝の100枚位の石のフタを開けて溝の中の泥やごみをあさり、またフタをする。今日は体中が痛い。よく年を取ると無理な労働のあと2〜3日してから痛み出すというが、今日から痛い。草もよく取れて可燃ごみ袋に約50袋! それでもまだ掃除は半分やり。団地に住むのも楽じゃない。夜は奮発して寿司(回るやつだけど)。先月誕生日を迎えた未来ロボットの名前のついたチェーン店。このお店が出来たばかりのころはネーミングがちょっとレトロな感じだったのが、今じゃ最先端のようだ。この間、あるテレビ番組で「今10代の若者に人気の『て』のつくもの」というのをやっていて、その中に「テツ&トモ」とともに「鉄腕アトム」が入っていた。
でも安いのに文句ばかりいってすまないけど、客あしらいがヘタで、そうするとせっかくの寿司もあまりおいしくなくなるのだ。前にも書いたけどやはりサービスにもお金を出すのが当たり前なのかも。それならそれで徹底してほしい。高くてサービスも悪いのは論外だが、どちらかが欠けても客は苦情をいう。よく地元のお店の紹介番組をテレビでやっているが、あれもそういうチェックに一役買っているかも知れない。意外にプロも見ているのでは? どうすると客が来るかの研究にああいう番組は持って来いだと思う。見ている割りには行かないが。
今日は学校が試験中なので、痛い体をおして早く出掛けなくてはならない。…T子(妹)が買い物から帰ってきて「雨が降ってきたよ」 参った・・・。
2003年05月17日(土 ) 強盗殺人事件
5月15日の夕方、知っている方も多いと思うが、北区の住宅地で、女性が殺され現金数十万円が盗まれるという強盗殺人事件があった。この日、塾の仕事を終え、41号を通って帰る時、新川中橋の上で後から緊急のパトカーが来たので右端に寄ってやり過ごしたらずっと行く先が一緒でおやと思っていたら、なんと家のすぐ近くだった。ほんの50mの所。夕食を済ませたころ、テレビで見る鑑識課のような服を着た警察の人がきて、怪しい人を見なかったか、気がついたことはないかと聞いて行った。翌日同じ団地の人に聞くと夜11時ごろまで聞き込みをしていたらしい。16日朝は、警察のほかに、新聞記者やテレビ、それに上空をヘリコプターが飛ぶなどで近辺が騒然としていた。ローカルニュースなのでテレビでもそうしょっちゅうは放映しないし、うちは一般新聞は取っていないし、で、団地の草取りなどしながら、何となく様子をうかがっていた。ラジオでは「15日が給料日と知っているなど、内部の事情に詳しいものの犯行か」と言っていたので、早くに解決するのではと思うが、先日の同じ北区の通り魔事件もまだ未解決だし、不安な日々が続いている。
不安と言えば、SARS問題が身近になってきている。昨日から今日にかけて台湾の医師が日本からお国へ帰ってからSARSを発症したとのことで、この医師の日本での立ち寄り先では消毒やら聞き取り調査などあわただしい状況になっている。一方で「日本人はSARSにはかからない」などという根拠のないデマも流れているようだが、こういう無知と誤知の流布が恐い。今のところ日本が感染をかろうじてまぬかれているのは明らかに水際で頑張っている人たちの努力のお陰である。
もうひとつ、あの「白装束集団」(「パナウェーブ研究所」)。すっかりテレビのワイドショウの常連となってしまった。オウムのこともあるせいだろうが、やや過剰反応気味だ。もちろん警察や関連自治体が対策を取るのは当然だが、連日連夜テレビを賑わすのはどうかと思う(その隙に「有事関連法案」が衆院を通過した。この方がよほど重大問題だ)。
今日からS子(妻)が横浜に行っている。何かの集まりらしいのだが、聞きそびれた。帰って来たら聞いてみよう・・・。
さて、明日は朝から月恒例の団地の掃除(晴れならだが)。出席の具合はどんなかな。先日同じ団地のある人から「今年の会長さんは中々やると評判ですよ」「なまけて掃除に参加しない人たちには会長さんからどんどん注意するようにして下さい。応援しますから」と言われて困った。私の会長就任の抱負は、とにかく任期終了後「去年の会長さんはよかったね」といわれるように、というのが本心だが、やかましいことを言って恨まれたくはない。だからせっせと草取りをして点数を稼いでいるのだ。今のところそれが功を奏しているのはいいのだが、それ以上期待されても困るなあ。
2003年04月30日(水) 公共経済学と棟掃除
あっという間に4月も終わり。G.W.まっさかりだが、ウチは今年は(今年も)ごろ寝週間(G.W.だけに・・・)。何となく体調がよくないのと(あったかくなるとよくめまいを起こす)、もちろん懐具合の関係。読む本もたくさんあるし、勉強したいことはそれこそきりがないので時間を持て余すことはないが、運動不足も気になっている。勉強といえば、今、私の塾のある生徒さん(大学院生)と一緒に「公共経済学」というのを勉強している(彼は税理士志望で国家試験にこれが出るのだそうだ)のだが、やってみるとこれが面白い。これは資本主義経済が「公共財」(道路・消防・警察などの公共物)を取り込むことによっていわゆる「市場の失敗」を起こすことを政府の経済政策で解消するための理論的根拠を与えるものだが、とても数学的。若いころマルクスなどを読んで資本主義経済の搾取の仕組みを知ると、「近代経済学」などは非科学的だと、今までバカにしていた。近代経済学が縦横無尽に数学を駆使しているのは科学的に見せるためのカムフラージュだといまでも思っている。でも、その近代経済学者たちが苦心して資本主義を守ろうとしているのを、ただ「御用学者」といって切り捨てるのは間違いだと思うようになった。マルクスが彼以前のそれまでの「古典経済学」(リカードやアダム・スミスたちのイギリス古典経済学)への批判から出発して「資本論」という巨大な成果を得たように、現代の資本主義が公認する「経済学」への批判から、来るべき新社会へ進むための新しい経済学を築きあげなくてはならないのだと思う。
…さて、高尚なお話から、現実の厳しい話。私のいる団地では月1回団地の棟の周りを住民みんなで掃除することになっているのだが、この間、ある住民の方から「高齢者や病人が多くなって棟掃除に出るのがつらい。掃除に出てこない人たちにもっと呼びかけて欲しい」という苦情が自治会長に出された。集合住宅にとっては普遍的な問題だと思うが、高齢者や独居老人、障害者が多い市営住宅では特に深刻な問題だ。他の棟での対策などを参考に今色々考えているが、完全な解決策はなさそう。団地を掃除するというのはその結果である「きれいな環境」をみんなで享受することである。しかし一部の人だけでそれを提供し、享受するのは住人全体というのは不公平だ。まして老人が病気を押してまで掃除に参加し、元気な若い人がサボっていては不公平の極みである。そのほか、掃除に出てきてもあまり熱心でなく、おしゃべりに熱中して時間になるとさっさと引き上げる人もいるなどという苦情もある。
「経済学」のお勉強は勉強だけで済むが、こうした生活上の問題はそれだけでは済まない。いわゆる政策の立案と実行が必要となる。取り合えず、苦情等をそのまま回覧する予定。深刻な問題であることをまず知って貰わなくてはならない。それから具体的な方法を考えていこうかなと…。
これで4月は終わり。これからはもう少し楽しい話を書きたい。
2003年04月22日(火) 吉野の花見
前回のHP更新から1ヶ月以上経った。イラク戦争の経過はのんきな日記など書かせないような緊迫を持って迫っていた。アメリカの非道ぶりに絶句した。とはいえ、4月12日には奈良・吉野へ花見にも行ってきた。吉野は誰もが知る桜の名所。とにかく人、人、人。以前、桜の季節でないときに行ったことがあるが、その時はすいていた(笑)。蔵王堂や吉水神社、後醍醐天皇稜などはそのとき訪れたので、この日はまあ純粋にサクラ見物。桜もきれいだったが、妙なことで感心したことがある。実は日帰り観光バスツアーで行ったのだが、駐車場でのバスたちの見事な並びぶり! ガイドさんの話でも「今日は150台は来ています」とのこと。それがきっちり収められ、ちゃんと順番に出入りしていることに驚いた。運転手さんとガイドさんと駐車場の管理者との連携プレー。我々のバスも来た時は駐車場のかなり手前で降ろされたが、帰りはスムースに出発。早かったせいか(2:30帰路出発)たいした渋滞もなく予定(7:00名古屋着)より1時間も早く帰ってきた。吉野ではまあまあの天気だったが、往復の道ではほとんど雨、名古屋に帰っても雨。ある意味最高の天気だったといえる?
去年6月、ある激安日帰りバスツアー(一人¥2900)でちょっと不満気味だったS子(妻)は、この日は大満足。一人¥3900にもかかわらず朝も軽食付きだし、昼食のお花見弁当もなかなか豪華だった。おやつの和菓子やお茶も出る。S子いわく「やっぱり2900円ではダメね。3900円は出さなきゃ」
さて、花見で浮かれてばかりはいられなかった。団地の自治会会長の任務が始まっている。《注:以下の自治会長の話はフィクションとしてお読みください》 新年度(4月1日)早々、今は使用禁止になっているゴミ置き場に多量のごみが不法投棄されるという洗礼から始まる。ゴミには強い(?)S子の活躍で何とか片付けた(結局は環境事業所に頼み込んで持っていってもらったのだが)。どうも年度末に引越した人の置き土産らしい。4月10日には「交通事故死0の日」の街頭交通安全委員も勤めた。
4月19日、初の学区自治会町内会連合会の定例会があった。行ってみると自分の座る席がすでに決められていて、立派な名札もある。しかも肩書きが「会計監査」になっている。なんとなくものものしい雰囲気。まるで市議会みたい(行ったことはないが)で、無駄口がきけない。つい1週間前(4月13日)の統一地方選で当選したばかりの某県・市会議員(連合会の顧問をしているらしい)から挨拶が始まる。町内のお歴々が勢ぞろい。司会者が一人一人、肩書きとともに名前を呼び、皆さんそれぞれ「どうぞよろしくお願いいたします」と続いていくのでどうやらこれがここでのやり方らしい。お隣の席の女性は「福祉部副部長」、聞いてみるとやはり「寝耳に水です」とのこと。
議員さんたちが帰ったあと、各団体長の報告に移り、そのあと自治会長会議になって、やっと論議らしい場に。各種ボランティア団体からの回覧は基本的にはことわっているのに仏教会の寄付や熱田神宮の初穂料などは公認で集めることに対して「素朴な疑問」が出され、幹部の人たちがとまどっているのがけっこう面白かった。もっとつっついてやりたかったけど、まあ初めからあまり目立ってもと今回は思いとどまった。 帰りに渡された袋には名古屋市長からの「区政協力委員」の委任状やバッジ、役職札、心得の記された手帳、警察からのポスター等々、たくさんの「おみやげ」が入っていた。翌日それらを整理して回覧するものは回覧し、自治会の役員さんに渡すものを渡すのに半日以上かかった。ただ働きに辟易するが、どうも年間いくらとかお金も出るらしい。もらったらまた報告しよう。
2003年03月13日(木) 着メロ
新しくなった携帯電話に着メロ用として「エリーゼのために」を入れた。機種変更のときにオマケでもらった「5曲無料であげちゃうよ」の中には(もちろん)なかったので自分で入れたのである。なんと三重和音ができるので伴奏付になった。ただ、周りがにぎやかな所だとちょっと聞き取りにくい…。で、オマケでダウンロードした「colorS](宇多田ヒカル)と交代で使う。ちょっと前、友人の携帯にリクエストで「快傑ハリマオ」を入れたことがあるが、世の中もっと自分で着メロ入れたくても出来ない人が多くいると思う。まだまだ今の携帯の音符入力はむづかしい(この友人からの着メロはもちろん「快傑ハリマオ」にする予定)。今まで出来なかった分、しばらく着メロにはまりそう…。2003年03月12日(水) 愛読書?
携帯電話を58ヶ月ぶりに換えた。これまでのはSONYのTH271というやつで、まだメールが打てなかったが、いつでもどこでも電話ができるという文明の利器を満喫していた。鉄腕アトムにさえ携帯電話は出てこない。アトムの登場人物がくるくるのコードの着いた黒電話で電話しているコマがあったし、公衆電話もよく出てきていた。あの手塚治虫さんでさえこのケータイの普及ぶりは予想しなかったのだ。ちょっと話がそれたが、今度の携帯はちゃんとメールも打てるし、インターネットも見ようと思えば見られる。流行りの二つ折りタイプではないが、フタのないキー剥き出しの機器だと機器代0円。 結局、かかった費用は、番号そのままに機種変更するための手数料2000円(+消費税)だけとのこと。さっそく取扱説明書と首っ引き。
いつも何か電気製品などを買うと、しばらくはその取説が愛読書になる。こんなものは読まないという人がいるが、私は好きである。もっとわかりやすくしろと文句をいう人も多いが、私は大体の「取説」はよく出来ていると思っている。取説の一番の目的は「わかりやすさ」ではなく、漏れのないことである。だからあんなに長いし、くどい。しかもわかりやすくしろと言われるので冗漫になり、正確でないといけないのでわかりにくくなるのだ。自分でもマニュアルみたいなものを作ったことがあるのでその苦労はわかる。「遺漏なきこと」とはとても大変なことである。
もちろん言いたいこともある。今回でもEZwebサイトへの新規接続の時、希望のメールアドレスを3つも打ったあと「OK」ボタンがどれなのかわからなくて10分くらいぶつぶつ言っていた。同じことを説明している本が2冊もあるのに、この場合の「OK」ボタンがどれかについて書いてあったのは「5曲無料であげちゃうよ」というハガキ大のオマケだけだった。それからアドレスに'_'(アンダースコア)が使えると書いてあるのに、実際は使えなかったり云々。
それでも、取説に書いてあるのは何か意味のあることであって、理解すればひとつ何かが出来るのだ。読むだけではなくて、何かについて書いてあるものを読んでその何かについて確かめることが出来るのが取説である。逆に出来るようになったあとからなんと書いてあるか取説を見て確かめるのも面白い。最近はどれでも絵を増やし、色をつけ、空白を多くして工夫してある。。
…まだ何か書けそうなので続きは後日。今日はここまで…。
2003年03月01日(土 ) 「オワラナイナツ」
あっという間に3月になってしまった。2月は全般に体調が悪く、特にパソコンに向かうのがつらくて中々更新が出来なかった。風邪のせいだと思うが、咳や熱より腹にきたようで、いろいろ辛かった。
おかげで、本はよく読めた。FMもよく聴いた。その中の出来事のひとつ。
FMで深夜に月〜金で放送している朗読の時間(たぶん「ミッドナイトポップライブラリー」45分)があって、その中でオザワセイラという人のオワラナイナツというのを1週間聴いた(実際の著者名・著書名はまだ確認していないのでカタカナにした)。小説ではなくて著者の少女時代の思い出をそのまま書いたもののようだ。家族の誕生日をみんなでこっそり準備し、当日に本人を驚かす話。ボストンに何メートルという大雪が降って、外に出た時小さなクリスマスツリーの赤ちゃんを見つけ、近寄ったらそれが大きなもみの木のてっぺんで、あっというまにその木の根元まで落ちた話。タカベエという、父の友人の話。その人が亡くなってから幽霊を見る話…。
色々な出来事を子供の感性をそのまま持ち越して描いているという感じである。主人公である少女の、ものを見る目が瑞々しく、まるで我々も同じものを同じ感覚で見ているようにさせてくれる、そういう朗読だった。
で、今度は2月23日のFMで午後から約11時間放送された「クラシックリクエスト」を全部録音してあとからちまちま聴いたのだが、その中にフォーレの「レクイエム」があって、それをDJのアサオカサトシさんが「合唱・タングルウッド音楽祭合唱団、管弦楽・ボストン交響楽団、指揮小澤征爾です」と紹介したとき、あっと気が付いた!。
あの「オワラナイナツ」の中のお父さんは小澤征爾さんだということ。そして著者のオザワセイラさんはその娘さんだということ。キーワードは「タングルウッド」でした。
朗読の中で何度も「タングルウッド」が出てきたのを覚えていて、それがアサオカさんの「タングルウッド音楽祭合唱団」で、一度につながってオザワセイラの「オザワ」は小澤征爾のオザワなんだ…。
こういう経験は確かにごくまれだが、これまで何度かある。私のカンはニブい方で、むしろそれをよしとしているのだが、そのお陰でこういうことが経験できる。
それから、これはラジオの朗読の番組だったから体験できたことだとも思う。もし、実際の本だと、こんなことは初めからわかってしまう(まず著者の名前から情報を得てしまう)。そうすると読んでいる時にお父さんが出てくれば小澤征爾さんがあの有名なヘヤースタイルで出てきてしまう等々…。 カンが鈍かったからこそ、何の先入観もなく、ただ、ある少女とその家族の話としてのみこの朗読を聴き、不思議な感動が得られたのだ。情報は多ければいいというものではない。
ちなみに、この朗読をしていたのは、「ヒロセアヤ」というとても声のきれいな人だった。
2003年02月15日(土 ) 久しぶりの名古屋駅前
…前回の記述から1週間が経ってしまった。今週はずっと風邪で悩まされた。幸いインフルエンザではなさそうだが、微熱と咳と鼻水・のどの痛み等が続いている。友人のH君との約束(購入予定のプリンタを見に行く)も実行できずすみません。9日のT子(妹)の誕生日にJRセントラルタワーズへバスで行ったのが悪かったと思う。T子のせいみたいで悪いけど、特に帰りのバスは辛かった! 約1時間立ちっぱなし。腰にもきつかった。
でも、JRセントラルタワーズは面白かった。一人700円払って53階まで上がり、名古屋を一望した。山の頂上を別にすればここはこの辺で一番高いところではないか。遠くの飛行機が目の高さに見えるぞ(これから着陸するやつだけど)。庄内川を、以前いた中川区の方から今いる北区までぐるりと目で追うことが出来、200円の望遠鏡で自分のいる団地まで見えた。御嶽山がとても綺麗でちょっと富士山のようだ。新幹線の車両がまるで白蛇のようにゆっくり上っていくのに対して、在来線か私鉄の電車がまるでおもちゃ。手にとるよう。遠くの雄大な景色に対してすぐ隣に立つ同じJRセントラルタワーズのもう一方(ホテルタワーというらしい。我々のいる方がオフィスタワーか)が異様な迫力で迫っている。巨大さがよくわかる。
子供の頃からなじんでいる中川運河はちょうど傾きかけた日の光で反射し、人工の川らしくまっすぐ、そして急に角度をつけて曲がり、そこを目印にたどって懐かしい長良橋を見つけた(昔その下に住んでいたのだ《嘘だけどそれに近い》)。今まで岐阜の金華山や御在所などの頂上から遠景を見たことはあるが、自分の住む街をこうして睥睨(ヘイゲイ)するのはなかなか快感である。初め700円は高いと思ったけど、エレベータ代と思えば安いか。山でロープウエイに乗るようなものだ。
ここへ上がる前に三省堂でT子のプレゼントを買った。何と辞書(国語辞典)。彼女の趣味のひとつは辞書を見ることで、私と妻の会話などから「再三再四」とか「徹頭徹尾」などと聞くとそれを探して「あったよ」と教えにくる。文字通り座右の書にしている。それがもう古くなったのと、ときどき載っていないものがあるというのでやや大きめのを買うことにした。それから(実はこれがこの日の目的だったのだが)、森博嗣先生の新刊「虚空の逆マトリクス」(講談社ノベルス)を買った。やはり森先生のファンである塾の生徒(高二女子)に教えてもらったもので、買ったことをその場で連絡した。彼女は私より多く森先生の本を持っているし、いろんな情報にも詳しい。森博嗣に関しては私の師匠である。
さて昼食は何かごちゃごちゃしたところで簡単に済ませ、53階に上がって先ほどの記述となる。
JRセントラルタワーズを出て、今度は隣の名鉄百貨店に入った。今日のもうひとつの用事はクレジットカードのポイントが貯まって千円分の買い物券になっていたのでそれを使うこと。名鉄という所は子供の頃からいろいろな思いがあるところだが、すっかりイメージが古くなってしまい、こんなことでもないとついでに来ることがない。名鉄さん、頑張れ! 確か昔S子と屋上でデートしたこともあるようなないような…
結局T子の春用のセータをそれ(買い物券ね)で買い、足りない分はまたクレジットカードで済ませた。名鉄はこれでおしまい。さあ、帰るぞ。
帰りは地下鉄で栄まで来、せっかくだからと評判(?)の「オアシス21」(参考:http://www.sakaepark.co.jp/)とやらを見てきた。オアシスとは言い得て妙だ。名古屋は砂漠でここはその中のオアシスというわけか…。自分たちの街を否定するものを作ってどうする。名前は公募だからというのなら、デザインした時にはどんなポリシーだったのだ…。
とはいえ地下のバスターミナルは寒いときにはありがたい。バスの道と待合室が扉で区切られ、排気ガスがこないのも良い。たまたま家に行くバスが来ていたので行列の最後尾から乗ってしまった。で、1時間の立ちっぱなしとなった。いつも自分のクルマで通る道をバスの車窓から見るのはけっこう新鮮である。最左車線を頻繁に他のクルマが駐車しているのでバスが走りにくそう。反省させられる。マイカードライバーもたまにはバスに乗るべきである。
バスが新川中橋まで来ながら渋滞で中々橋を渡れない。昔、中川区の澄池町にいた頃は、名古屋駅から6つ目のバス停で家に着いたものだった。庄内川渡ったらもう名古屋じゃないなんていう人もいたけれど、確かに市中から家に帰るとき必ずこの橋を渡らなきゃ帰れない。昔の渡しのようなものだ…ぶつぶつ。
さあやっと家に着いた。すぐ横になる。疲れた。どうも体の調子が変だ。今日はT子の誕生日なのでお寿司。ちょっと気が重い。それにしても二人は元気がいい。今日は疲れていないはずがないのにこれから買い物にも行くし、風呂も掃除して沸かしてくれる。負ける。
翌朝、案の定、発熱。8度2分ある。インフルエンザかと緊張する。お腹の具合も変だ。張っているだけでなく痛い。置き薬の風邪薬を飲んで出来るだけ安静にする。
…こんな具合に始まってもう1週間になる。ただ、熱は3日目には下がり、頭痛も治まったので、起きているが。今日はT子と団地の広場でバドミントンもやった。けっこういい汗かいて久し振りに気分爽快になった。
2003年02月08日(土 ) ネタバレあり、注意!
1月30日付けの「最後の弁護士」のオチを書いておこう。今ごろどうでもいいと言われそうだけど一応。酒井美紀扮する被告人は空き巣の疑いで逮捕され、起訴されるが、国選弁護士(阿部寛)に無実を訴える。しかしプロ並の進入手口を不思議に思った阿部は元大泥棒(大滝秀治)の協力でホームレスをしている男を訪ね、そこでその男の死体を発見する。彼は空き巣の真犯人だったのだが、なぜか殺されていた。一方、資産家の一人暮らしの婦人が強盗に殺され、大金を盗まれるという事件も並行して捜査が進む。そして弁護士はついに空き巣事件の被告人(酒井)が実は強盗殺人の犯人であることを公判で明らかにすることになる。酒井が阿部に弁護を頼んだのは、国選なら裁判に負けて空き巣の犯人にされ、強盗事件のアリバイが成立することを狙ったものだった…というもの。真実悔悟した被告人は改めて阿部に弁護を頼み、ドラマ冒頭の無期懲役宣告シーンは実は強盗殺人罪の死刑求刑に対する勝利のシーンだったことになるのだ。酒井美紀には珍しい悪女役でちょっとびっくりした。
…こうしてミステリィもののネタバレを書いていると、やはり作者(脚本家)に悪い気がするものだ。たとえ放映済みのテレビドラマでも良くない(再放送で見る人もいる)。もうしません _m(._.)m_
さて、今日、団地の自治会の現会長さんから「三役を決めたいので集まって欲しい」とTELがあった。それでわかったのだが、実はわたしはまだ自治会長ではなかった(笑)。選挙ではただ3人が選出されるだけで、その3人で会長、副会長、会計の三役を互選して始めて決定するのだ。すっかり次期会長気分でいたのでこの場で他の二人から会長をやってもらえないかという要請を受けて2つ返事で引き受けてしまった。だから結局会長である。
今週は嬉しいことがひとつ。塾の生徒の一人が高校受験に合格。K塚君、おめでとう!。よくがんばったね。この調子で車校もがんばって(春休みを利用してクルマの免許取得中)。
この土日(2/8〜9)には他の生徒の受験がある。受験前ぎりぎりの5日(水)にその生徒から聞かれた質問が難しくて即答できなかったのが2つあった(どんな問題かはここ)。帰宅してからやってみてもなかなか大変だった。
明日(9日)はT子(妹)の誕生日。まだ何も考えていない、何かしなきゃ…。
2003年02月02日(日 ) 投票と天才と回転すし
昨夜はこれを書きかけのまま眠ってしまった。今朝はゆっくり10時に起きて朝食の後すぐ家族みんなで愛知県知事選の投票に行った。投票所は三三五五という感じで今回も投票率悪そう。出かける時のニュースでは9.何%。まあ最終で30%前後かな。戦前戦後の民主主義に対する弾圧の歴史を思うと本当にこれでいいのかと思う。これも政治不信なのだろうけど、行かない有権者にも責任はあると思う。投票後図書館へ行って例によってミステリィを何冊か借りてきた。もう何年も前から推理小説を書きたいと思いながら果たしていない。小説を書くことと数学の勉強を続けることはどちらもやりたいことのトップだといっていいのだが、やはり創作の方は遅々として進まない(数学も遅いけど)。
このことと関係あるというとおこがましいが、昨年のノーベル物理学賞受賞者の一人である小柴昌俊先生が「モーツァルトとアインシュタインをくらべたとき、モーツァルトの方がもっと天才だろう。なぜか。科学は認識する主体と客体にはっきり分離している。アインシュタインがたとえ一般性相対性理論を発表しなかったとしても、ほかの人が論理的に同じ理論を提案することがありうる。ところが、モーツァルトがつくったすばらしい曲は、彼以外につくれないだろうから」という内容の講演をされている。反論もあろうが、大事なことは、こういいながら小柴先生は物理学を専攻しているのだ。これを単なる謙遜と受け取るにはテーマが重過ぎる。
芸術はともかく、科学は人間の認識の「形態」であるから、これが実存するのは本や数式としてではなく、あくまで人間の頭脳の中である。ある理論が確立されても次の人がそれを自分の頭の中に再生産しなくてはその理論は存在するとはいえない。よく出される例だが、19世紀前半フランスの数学者E.ガロアは1832年に死去して以後、その理論は忘れ去られ、1870年に「再発見」されるまではこの世に存在しなかったのだ。(注)
同じようなことが音楽にもある。ガロアとほぼ同時期、ドイツの作曲家メンデルスゾーンによるJ.S.バッハの「マタイ受難曲」の「再発見」は、天才の仕事を引き継ぐのはやはり天才であるとの感を強くする。
教育の目標の一つに「人類の認識の継承」があるのは明らかだが、それを自覚した人が次に自らの仕事を行なう時には、継承に続く創造と発展が求められる。小柴先生の言われることにはそういうことへの強い自覚が感じられる。小柴先生は今現在の人類の歴史の中でのご自分の役割を強く意識しておられるのだと思う。これをわれわれは学ばなくてはならない…。
…話が少々カタくなったが、こんなことを考えつつ(嘘)、午後は爆睡してしまった。その間にS子は一人で「喜多の湯」(参考:http://www.super-sentou.com/index.html)へ行ってしまった。昼寝から起きるとT子(妹)が一人ですず(猫)を抱っこして食卓のイスに座っていた。
今日の夕食は月初めということで、久し振りに「回転寿司」にした。最近あまり行かなくなっていたのだが、先日黒川の「365日全品100円」という看板のある「元気寿司」というのを見つけていた。
10組くらいの待ちがあったのだが、すぐ順番がきたので「回転寿司だけあって回転が速い」などと思ったことよ(口に出してはいない)。ちょっと驚いたのは、ぐるりと回っているベルトの内側で明らかにバイトの女子高生と思しき若い女性がせっせと寿司を握ってベルトに乗せていた。握るのではなく、寿司ロボットの握った飯に具を乗せているだけ。あっという間に10皿くらいをさばく。いろんな意味でさすが100円だなと微妙に感心。おなか一杯食べて3人で2550円。なぜか一皿150円が混じっていた。S子の食べた白身か。牛丼なら3人で840円だけど寿司がほんとに安いのかは微妙・・・。
回転寿司といえば、先日友人のH君と最近CMで有名な「かっぱ寿司」(水主町店)に行った。ここも一皿100円。ここでは回転ベルトの内側には人がいなくて、注文したいときは自分の顔の前にあるインタフォンを押してそこで寿司の名を言って注文する。すると「34番さまご注文」と書かれた台皿に乗って注文したものが流れてくる(女の人が注文を聞きに来る時もあるみたい)。どこでも安さと引き換えに何かを犠牲にしている感じがするが、それが本当に必要なものかどうかはわからない(例えば屋台のこっちと向こうでの会話とか?…)。
<注:高木貞治先生は(参考:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%9C%A8%E8%B2%9E%E6%B2%BB)「近世数学史談」の中で「時代を超越するにも程合いがあって、二十年、三十年の超越は危険である」といっている。
2003年02月01日(土 ) 会長誕生!
2月、寒い。毎年「この月を凌げば春になるんだ!」と思っていたような気がするが、今年はそんな希望も持てないほど寒い。このままどんどん寒くなって8月ごろには南極のようになるのではないかと・・・。寒風の中で仕事をしている人を見ると、尊敬より寒さが感染って来る気がする。寒いとまず体がおかしくなる。震えるだけでなく、めまいがする。ひたすら暖を求めて彷徨うようになる。新聞配達10年の経験があるが、あのころの自分が信じられない。昨日、仕事から帰るとS子(妻)が、「あ、会長さん、お帰りなさい」と挨拶した。そう、なんと団地の棟自治会の会長に選出されていた! そういえば先日居住者名簿と選挙用紙が配られていたのを思い出した。まだこの団地に来て1年半の自分が4月から会長である。というわけで、これからできるだけこの会長職を中継してやろうと思っている。
2003年01月30日(木) 支配者のアイデンティティ
雪である。仕事に出かける時もうチラついていたので「ヤバいなあ」と思っていたが、こんなに降るとは! で、帰りにいつもの道(三階橋〜水分橋)を通ろうとするとすごい渋滞! 信号が何回青になっても動かない。どうも三階橋のあたりで何かトラブルがあったよう。これではラチが開かぬと、Uターン、平安通りから19号線へ、さらに302号に出て、ようやく帰ってきた。いつもなら10分の道のりが今日は1時間! 19号は渋滞はなかったけど、みんなノロノロ運転なので遅い遅い。ほとんどLレンジで走り、ブレーキはほとんど使わない。こんな日に限って携帯電話を忘れたので、さぞS子(妻)は心配していると思いきや、家に着くと長電話の最中。たぶんこっちから掛けてもお話中だったのでは…。明日の道路が思いやられる。
昨夜、久し振りの友人からメール&TELあり。この「HPが見られない」というクレームから始まって2時間くらい話し込んでしまった(自分の長電話は気にならないのだ )。HPの問題はどうもURLの中の ~ (通称「にょろ」)が問題のようだ。〜でなくて ~ という話。URLの中ではよく使われている文字。
この友人とのイラク情勢の話の中で、「なぜ小泉首相は『靖国神社』へ参拝するのか」ということで議論した。興味深かったのは「靖国」は彼のアイデンティティではないかという彼の意見。小泉首相だけでなく、現在の日本の支配層にとって「靖国」へ参拝せずにはアメリカに奉仕することは出来ないのではないか。これは多分にメンタルな問題なので証明はできないが、妙に納得が行った。
さて、帰ってきて観たテレビのお話。「最後の弁護人」が面白かった。冒頭にいきなり「被告人を無期懲役に処する」という裁判長の通告。被告はゲスト女優の酒井美紀。まさか彼女が無期懲役なんて! ははあ、これを阿部寛扮する国選弁護人がひっくり返すんだなと思っていたら、なんと…。
テレビのミステリィドラマは好きだ。よく毎日の夕方「火サス」や「土ワイ」等の再放送をやっているのをエア・チェックしてあとでCMを飛ばしながらザーッと観るのがいい。2時間ドラマを大体20〜25分で観られる。もちろん面白いところはじっくり観るが。たとえ途中からでも「これはどういうドラマか」と前半を推理するなどけっこう楽しめる(^^;。犯人は大体当ってしまうので、あまりそこには興味はない。S子(妻)などは新聞か「ザテレビジョン」(番組週刊雑誌)の記事だけで当ててしまう。登場する俳優を知っていて、それでわかるらしい。インチキといえばインチキだ。
テレビのミステリィに一つ二つ注文したい。犯人と被害者しかいないはずの場面をわれわれに見せるのはインチキである。事故か故意かなどという微妙な場面を視聴者に見せて「あれじゃ事故だな」と納得させようというのだろうけど、まさにそこが裁判では論点になるのではないか。また、犯人の動機をいかにも納得させるために、被害者を殺されても仕方ないかのように描いたりするのも安易過ぎるのではないか。
そもそもあらゆる事件が2時間(CM入れて)でカタが着くのも考えてみればおかしなことだ。小説なら長編・短編など中味に合わせて描けるけど、テレビドラマは1時間か2時間と決まっている。仕方ないのかな、と納得してはイケナイ…。
ああ、すっきりした。
2003年01月26日(日 ) 「タイタンの戦い」
大体1週間に1度これを書いてるペース。ま、比べるのもなんだが、森博嗣先生は、大学の仕事、小説の仕事をしながら「近況報告」を6年(1996年〜)毎日続けている。この2週間数学三昧で過していたが、やっと一区切りつけてみた。例の相加平均と相乗平均の方は終わったが、あまり出来が良くないので没。もう一つは「平成15年度大学入試センター」の数学ⅠA・ⅡBを解いていた。特にⅡBが難しかった。こんなのをわずか60分で解く学生たちをすごいなと思った(ただ、センター発表の平均点は49.82(数ⅡB)とやや低い)。…というわけで数学論文のUPは今回は挫折。ちょっと気が楽になってる(^^;。
昨日は辻町のアピタで「タイタンの戦い」(CLASH OF THE TITANS) というDVDを買って来て(¥2,500)すぐ観た。面白い。「ストップ・モーション・アニメの巨匠レイ・ハリーハウゼン」製作の「SFX神話スペクタル」(DVDパッケージ)で、ギリシャ神話の英雄ペルセウスが王女アンドロメダとの愛を成就させるまでの冒険を描いたものだが、次々出てくる怪物や天馬ペガサスなどを実写と人形のコマ取りを組み合わせて作っている。特に魔女メドゥーサがすごい!。メドゥーサは「ギリシア神話のゴルゴン三姉妹の一人。蛇の頭髪をもち、これを見るものを石に化した」(広辞苑)という化物。なぜか昔から人気があるようだ。実はずっと以前深夜のテレビ映画でこれを何気なしに観たとき、すごいと思って以来彼女のファンである。
2003年01月18日(土 ) 500円の「刀根真理子」
前回から1週間経ってしまった。この間、ずっと相加平均と相乗平均。そろそろケリをつけなければ・・・。12日の日曜日は小牧のイトーヨーカドーへ行ってきた。近場なのでカーナビは必要なかったのに、近くに行ってから探すよりはと思って目的地を指定したのはいいのだが、国道41号線の上には名古屋高速が走っていてそれがカーナビの電波を遮断して画面が更新しなかったのでずいぶん行き過ぎてしまった(笑)。メカを過信するとこういうこともあるという例の一つ。
イトーヨーカドーというS.C.(大型ショッピングセンター)は初めてである。行ってみると「ITO YOKADO RAPIO」という名になっていたので、「ああ、2軒のS.C.が続いているんだな」と思ったら、そういう名のイトーヨーカドーだった。
駐車場は地下2Fで、駐車券を取る。これを持ってエレベータで店まで上がり、何を買うともなく散策していると、4Fに古レコード店があって面白半分に刀根真理子を探していたら何とあるではないか、「JUST MY TONE」(1987年)! 新譜の店にはもうCDもないことが多いので出会うととても嬉しい。CDとしては持っているアルバムだが、レコード盤でも出ていたのだ(そういえばCDの出始め当時は歌手はみんなCDとレコード盤の両方を出していたな)。値段を見ると500円!。買ってしまった。
そのあと百円均一の店でなんやかや(特にS子が)買いこんでから「若鯱屋」で遅い昼食にした。そこであらためて刀根真理子のレコードジャケットを見てみたが、やはり大きいジャケットはいい。CDのジャケットは小さい。面積で約6分の1。レコードを聴きながらジャケットを見る楽しみは昔より少なくなったと思う。何でも小さくなればいいものではないという例の一つ(今日は例えが多い)。
刀根真理子は、オトナになってからハマった唯一の歌手。一般には「キャッツ・アイ」のテーマ曲を歌っていたことで有名だが、現在では知る人も少ないかも。
「百円均一の店」で思い出したが、先日AMラジオで(たぶん17日。番組名は忘れた)、電車の中で女子高生の付け爪に見とれていた隣のオジサンが「ねえちゃん、それきれいやな」と聞いたら「きれいやろ、百均で買うたんや」「そうかあ、やっぱり借金せんと買えんわなあ」という会話を聞いた人の投書を放送しているのを聞いた。ここで始めて「百均」というのを聞いて、これはいわゆるコギャルことばのひとつかなと思った(それとももう普遍化してるのか?)
イトーヨーカドーの向かい側にコジマ電気があったので覗いてきた。まあどうってことはなかったけれど、ビデオテープを買おうとレジへ行ったらレジが一つしか稼動していなくて、しかも先客がずいぶん長くかかっていたのでやめてしまった。こういうことには本当に気が短い。国道41号線豊場にできた「横綱ラーメン」も気にしていながら、いつも車が並んでいるのを見て行きそびれているのも同じ理由。何も並んでまでと思ってしまうのだ。
話がバラバラだが、レコードの後日談。翌日から2日間、せっかく手に入れた刀根真理子を聴こうと押入れの奥にしまってあったレコードプレーヤーを引っ張り出して試してみた。今月10日付けに書いた「25年も前に買ったシステムコンポとは名ばかりの、今はチューナとアンプしかないステレオ」に付いていたやつだ。もう動かなくなっても捨てるに偲びずとっておいたのだが、やはりダメだった。これでまた惜しいものがひとつ減って、欲しいものがひとつ増えた。
2003年01月11日(土 ) バカ親子!?
今日は、E美(友人)宅へパソコンの調子を見に行った。このHPが見られないというので。その時こんなネタを提供してくれた。去年の夏、E美の長男K君(大学生)からの熱い(暑い)要望で彼の部屋にクーラーをつけたのだが、昨日!になって「母さん、このリモコン(クーラーの)、暖房っていうボタンがあるよ」 「えっ? うそ!」 やってみると何と暖かい風が…。「へえ〜、これ、エアコンだったんだね…」「うん、そうみたい」 …というバカ親子のお話。
その話を聴いて大笑いし、「説明書くらい見たら?」というと、「そんなもん見なくても動くし。大体安かったんで、エアコンって思わなかった」とのこと。
HPが見られないといってたくせに、URL(http://www5e.biglobe.ne.jp/~tennin/)を入れたらすぐ開いた。ま、深くは問うまいということで、ついで森博嗣先生の浮遊工作室(参考:https://www.ne.jp/asahi/beat/non/mori/)のURLも「お気に入り」に登録してしまおうと、URLを入れると…。なんと、トップページがリニューアルされているではないか! 実は去年の8月「森ぱふぇ」(参考:https://www.ne.jp/asahi/mori/fan/101_intro/aboutpramm.html)に入会(ファンクラブです)してすぐ「近況報告」等をDownLoadし、それをじっくり読むばかりの日々でずっと「浮遊工作室」には直接アクセスしなかったのだ。家に帰ってからじっくり見るとリニューアルの日付は2002年12月ということで1ヶ月も知らなかったことになる。それにしても美しいHPで、センスの良さに汗が出た。
E美宅での続き。
K君が学校の授業で、VBで行なう数値解析のことで聴きたい、なんて質問をしてきた。K君を小さい時から知っているが、こんなことを質問するようになったんだなあと、つくづく時の流れを痛感!
帰りのクルマの中で、FM-Aichiの「AVANTI」(参考:https://ja.wikipedia.org/wiki/サントリー・サタデー・ウェイティング・バー)を聴いた。これは、毎週あるテーマでその道のプロが「AVANTI」という Waiting Bar でカタるという、ある意味マニアックな、毎週楽しみにしている番組。今日は録音の予約をしてこなかったのでちょうどよかった!。今日のテーマは「業界用語」。「ケツカッチン」などの語源の話が楽しかった。
帰ると、S子(妻)たちが辻町のAPITAへ行って松浦亜弥の大きなカレンダを買ってきてくれていた。2000円だったのが半額だったそうで。早速自室の壁に掛けてみた。くるくるに巻いてあったので、まだ表紙の亜弥ちゃんの顔が半分くらいしか出ていない。これから何日かして全貌を表わすのが楽しみ。そういえば書き忘れていたが、お正月2日の「忠臣蔵・決断の時」(テレビ東京)に亜弥ちゃんが出ていた。ファンにとってはいいお年玉であることよ。
2003年01月10日(金) FMをビデオに録音
この7日付けに書いたように相加平均と相乗平均のことを調べていて段々深みにはまっている。解答をHPにアップしようと思っていたが、この分じゃ、相当先になりそう(別に締切があるわけじゃないのであわてないが)。今年になってイラク情勢が急展開である。政治には色々な立場があるが、それはお互い尊重しあわなくてはいけない。しかし他国への戦争は別だろう。これは絶対許してはいけない。始めれば必ず人が死ぬ。人が必ず死ぬとわかっている戦争を起こす権利は誰にもない。しかも世界世論は「イラク攻撃反対」が圧倒的だ。イギリスもフランスも中国もロシアも、アメリカ国内さえも反対の声をあげてる。
われわれ「団塊の世代」は、ともかくも戦争の終わった日本に生れ、貧しいながらも平和な中で育った。途中、朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争などが起こったが、日本は残念ながらそれらの戦争に反対の姿勢を貫けなかった。個人としては反対していても、その声を自分たちの政府に実行させることが出来なかった。とても残念だが、日本はまだ戦争を厭う平和を志向する勢力が政権を担っていない。このことに対するわれわれの責任はまだ果たされていない。この責任を果たすこととイラク攻撃反対の声をあげることとは同じことだ。イラク攻撃を阻止できれば、とにかく数百万の人々がミサイルの脅威にさらされることはなくなる。すべての問題はその後でもいい。その大きな世論の力をテロに対しても向けていくことでこれを防ぐことも可能になる。手立ては見えている。その人に出来る方法でこれを実行しよう!。
昨日は、かねてからの願いだった「自分の部屋でFM番組をビデオに録音する」ことを実現した、なんて書いても大したことではないが。25年も前に買ったシステムコンポとは名ばかりの、今はチューナとアンプしかないステレオ(まだCDはなかった時代のもの)を、去年の夏に買ったビデオ(¥9,980)につないだだけ。スピーカもなかったが、これは友人が引越の時にいらないからとくれたミニコンポをつないでみた(CDは使用不能だった(*_*))。
初の録音テストは午後2時からのNHK-FM「ミュージックプラザ第1部」。これで今までS子の部屋で録音していたことから開放される。この日のブラームスの交響曲第2番は格別。
クラシックは大好きだが、生演奏を聴いたことは殆んどない。無料のリサイタルが何回かと、N大のオーケストラの「第九」を一度聴いたことがあるだけ。CDもあまり買わない。ラジオやテレビの放送が主なソースである。ビデオテープに録音するメリットは長時間録音が可能なこと。日曜日のNHKFM2時〜6時はずっとクラシックだが普通のカセットテープではムリ。VHSビデオテープなら3倍モードで6時間可能だからむしろ音楽向きかも。年末にFMでやっていた「バイロイト音楽祭」なども録ろうと思ったらこれでないと無理。このごろはDVDプレーヤも普及してきたからやがてそちらに移るのだろうが、まだ当分はこれでいいかな。
2003年01月07日(火) 七草粥
昨日は初仕事。6日からの雪が残っていて運転下手の自分は緊張しまくり。アイスバーンというのか、昼間でも陽の当らない道路が凍っていて恐くてブレーキが踏めない(本当に踏まないわけではない)。余談だが、今「アイスバーン」と書こうとして「アウトバーン」と書いてしまった。どちらもよく滑りそう? 辞書をみるとどちらもドイツ語(EisbahnとAutobahn)だった。知らなかった!平均気温以下の日らしく久し振りの教室は寒かった! いつまでたってもエアコンが効かない。家に帰ってからの山本屋の味噌煮込みうどんで温まった。(うどんが硬すぎ! それが自慢らしいが。)
今日は「七草粥」。朝、S子が「ななくさなずな、とうどのとりが…」と歌いながらまな板で七草の具をとんとんたたく音で目が覚める(歌で起こそうとしているのだ)。Nフコ(誤植ではない。S子と同じ略称のつもり)勤務なのでこういうイベントは欠かさない。T子(妹)が横でけたけた笑っていた。わが家は朝いつもお粥だが、具を入れるのは珍しい。さっぱりしておいしい。
(以下、数学のことを書きます。興味ない人は飛ばしてください)
夕べは遅くまで数学の問題を解いていた。「異なる二つの数a,bから相加平均a1と相乗平均b1を作り、またa1とb1から相加平均a2と相乗平均b2を作り…というふうに限りなく続けていくと最後には(極限値が)一致する」というもの《高木貞治著「解析概論」練習問題(1)》。
初めは実際に計算して確かめてみたが、なるほどこの両者はだんだん近くなる。だから最後には一致するだろうことも想像できる。でもなぜそうなるのだろう。これら自身が半端じゃない不思議さを持つ。
いつも思っているが、数学の問題を解くことはミステリィ小説を読んでいるのと同じだ。答えがないものは自分で「犯人」を見つけなくてはならないが・・・
まず、問題を見て、知って(あるいは発見して)、それを不思議に思う。つまり「事件」に遭遇するのだ。そしてそれを解決していくのは、まさにミステリィ小説である。犯人がわかってしまえば「そうだったのか!」でめでたし々々になる。しかし犯人がわかっても、今度は、ではなぜそうなっているのかと不思議に思う。さらにこれを追求していくことが始まる・・・。それを書き下すことができれば、つまり解答論文ができれば、それはそのまま「ミステリィ小説」になるのではないか。この小説の「犯人」は常にわれわれの生きている自然界である。自然はちゃんと理由があって不思議なことをする。動機がある。それを人間が解明していく、そうして物理や化学や数学が出来た、と思う。自分もそれをしたい。そういう仕事がこのHPでできたらどんなにいいかと考えている。
2003年01月05日(日 ) 祝HP開設!
今日はこのHPへのリアクションがあった。まず、塾の生徒さんからの「祝口H・P・開設!」という年賀状(「祝」の字の隣の口はたぶん日の丸?)が来た。彼女は自分のパソコンがないにもかかわらず、弟さんの携帯電話で見てくれたとのこと。それから、友人が二人、TELとメールをくれた。皆さん、ありがとうございました。
この友人のうちの一人はこのブログの2002年11月11日で「ぷりずむ」主宰者として登場したT中君の奥様だが、お二人は「うば姫(美)笑品」(この(美)のところは美という字を○で囲んである)という通信を発行していて、その創刊号を年賀状として戴いていた。 2003年01月04日(土 ) 寝正月
早くも4日。実は2日、3日は背中を痛めて寝ていた。クッチャネクッチャネの日々がもう1週間続いているので、たぶん筋肉痛(運動不足が原因の)と思うのだが、恐くて動けない。おかげでテレビは嫌というほど観た。2日はテレビ東京の「忠臣蔵・決断の時」。10時間通して観た。3日はNHKの「信長」(昔の大河ドラマの再編集もの)とフジテレビの「平成教育委員会」。「忠臣蔵」はわかりやすくて面白かった。このドラマの吉良上野介(橋爪功)はこれまでのドラマの中でも最低の男に描かれてると思う。愛知県吉良町の人たちはさぞ不満だろう。テレビ局に苦情が行っているのではないか。それに比べて大石内蔵助(中村吉右衛門)は、欠点のない間違いも犯さない長谷川平蔵そのままで、やや類型的とも思えるが、内蔵助はこうでなくては忠臣蔵にならないのだろう。
「信長」は、4日の「秀吉」、5日の「徳川家康」と共に「テレビ放送50年特別企画」として放送されたものなので、作品として特に言うことはない。「テレビ放送50年」についてはまたの機会に。
「平成教育委員会」は小中学校の入試問題等から出題するクイズ番組で、仕事柄(塾講師)興味がある。「緊緊」や「予予」「寸寸」などの読み方などは知らなかった。皆さん、わかりますか?(正解はこの漢字をクリックしてみてください) 今ここで正解の読み方をタイプしてみても出てこないので、ワープロの辞書にも載せていないものがあるようだ。
…とまあ、文字通りの寝正月となったわけだが、このままお正月終わりではあんまり寂しいので、今日は知多の野間大坊(参考:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E9%96%93%E5%A4%A7%E5%9D%8A)(鶴林山大御堂寺)というところへ家族3人で行ってきた。実は昔(1980年)、日も同じ1月4日に友人のT中君と一度行ったことがあって、その時の印象が良かったので再度訪ねてみたいと思っていた。ここは1160年、平治の乱に敗れた源義朝が謀殺された所として有名だが、昔とはずいぶん印象が変わった。風格のある堂々とした大社と思っていたのに、今日は俗っぽく品のないお社に見えてしまった。たぶんこれは見ている自分のほうが変わってしまったのだろう。神社や仏閣を畏怖していた昔の自分を失い、替わりにこういうものを「客観的」に見てしまうようになった自分がいる。こういう時、来たことをちょっと後悔するものだ。
子供の頃、父に連れられて行った大須観音の仁王さんが恐くて山門を通れなかったことを覚えている。今の仁王さんがその時と同じかどうかわからないが、大人になってここを通るたびに我ながら笑ってしまう。それと同じかもしれない。でも、なんだか寂しくもあり、懐かしくもある。
つまりこれはもう一度行ってみる必要があるということかも。「何でも3回は見なくてはならない」、これが今回の野間大坊訪問の教訓。
さて、この日はこれで終わらない。目ざとく「えびせんべいの里」(参考:http://www.ebisato.co.jp/)という看板を見つけたS子は、立ち寄りを命ずる。行きはドライブを楽しもうと247号を走ってきたのだが、背中も痛いし、帰りは高速道路で帰ろうと美浜インターに来ると、まさに眼前に「えびせんべいの里」が! もうここはHPを見てもらったほうが一目瞭然なのだが、見たくない人のためにちょっと説明すると、えびせんべいをまるでスーパーマーケットのようにして買うところ!。野間大坊より混んでいた(笑)。試食自由だし、作っている所を見学できたり、コーヒーが無料で飲めたり出来る。S子はとてもお気に入り。
結局ここでえびせんべいの他にいわしとじゃこを買って帰った。
2003年01月01日(水) 明けましておめでとうございます
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。これを書いているのがまだ新年の午前1時ごろなので、特にネタはないのだが、さっきまで見ていた「紅白」の感想をちょっと。例年に比べ格別の感動はなかったが、普段聞かない歌もつい聞いてしまうことから「あ、けっこういい歌なんだ」と思ったのが、Gacktの「12月のLove song」。サビの「大切な人だからずっと変わらないで…」のところで声がきれいだと思った。「紅白」のあと、民放のあるライブ番組でも彼の別の歌(曲名を忘れた)を聞いたが、同じことを思った。Gacktはあのキャラも好きだが、歌もうまいんだ。その他印象に残った歌手をあげると、華原朋美、ジョン健ヌッツォ(オペラ歌手)、中島みゆき、石川さゆりなど。
ところで、「レコード大賞」は誰だったのか? 「紅白」でいつも紹介するけれど、聞いてなかった。明日になればわかるけど、面白いから予想しておこう。本命・浜崎あゆみだが、自分では森山良子にあげたい(ただ、金賞十曲のうち、知らない曲が六曲もある! これでは、予想ができない)。
明日(じゃない、もう今日)は、一宮の真清田神社へ初詣の予定。
…というわけで、もう一日が過ぎてしまった。夕べは4時ごろ寝たのだが、もう8時には目を覚ましてしまった。S子がお雑煮を作り出したので起きていき、さっそくテレビをつけると例によって紋付袴のお笑いタレントと晴れ着の女性たちのオン・パレード。この雰囲気がいい。
さて、「レコ大」が気になるので、新聞を見ると、予想的中! 浜崎あゆみ(「Voyage」)。しかも森山良子は最優秀歌唱賞!
午後、真清田神社へ初詣。去年行ったので今回はカーナビを使わないで行ったらやはり迷った。神社まで1kmもない所から結局カーナビを始動。無事一宮市街地に入ると案の定というか、すごい渋滞。で、神社のかなり手前に車を止めて歩く。人混みを分け入って参拝を済ませ、いつものように車のお守りを買って串カツを食べて、S子が猫の置物を2つ買って、帰りは22号線で帰る。こちらは渋滞なし。
猫の置物はこのごろどこへ行っても売っているやつで、たぶん作っている所が同じだと思う。恒例により買ったところの地名から命名。今、車に乗っているのは一昨年湖東三山の百済寺で買ったので「くだらちゃん」、去年犬山城で買ったのが「いぬやまじょうちゃん」。で、今回は親子二匹の方が、「まーちゃん」と「すみちゃん」、もう一つが「たーちゃん」です。べたに付けるのがコツ。何でもそうだが、名前を付けると大事にするものだ。わが家の備品にはかなり恥ずかしい名前がいくつか付いているが発表は差し控える。
というわけで今年もつつがない元旦となった。
年頭に当って、抱負を書いておく(これは自分に対する公約)。今年こそ、高木貞治の「4部作」を読破すること(4部作とは「解析概論」「初等整数論講義」「代数学講義」と「代数的整数論」のことだが自分で勝手にそう呼んでいるだけです)。これが実現すれば、自分にとって大きな未来が開ける(と思う)。さあ、がんばるぞ!
2002年12月31日(火) よいお年を!
いよいよ大晦日。でも掃除はほとんど前日終わって今日はちょっと暇。が、S子(妻)はきょうも6時まで仕事。そのかわり、従業員価格で正月用品が買える特典付きだそうで、まんざらでもなさそう。午後になってからT子(妹)が「時計が止まった」と言ってきたので、見ると腕時計が朝10時半で止まっている。電池切れと思うが、近くに時計屋さんがないので、辻町のアピタまで散歩がてら行くことにする。
風がやや強かったが、なぜか南風(庄内川の河川敷に凧が上がっていた)で、さほど寒くはない。アピタはすごい人! 不景気などどこ吹く風。食品売場はごったがえすという言葉を久し振りに思い出したくらいだ。でも我々は1000円の腕時計だけ買い、年越しそばに入れるえび天を3個買ってついでに昼めしにラーメン食べてすぐ帰った。ぐずぐずしているとどんどんお金を使いそうでコワい。
帰ってからお正月準備の仕上げに鏡餅と注連縄をセット。鏡餅はいまどきのプラ容器でパックした、紙の組立三方付きです。注連縄も団地のドアに貼り付けるタイプで、ちょっと見クリスマスのリースの様。でも中にまねき猫なんかいたりしてしっかり日本。
S子も帰宅して、年越しそばを作り、紅白も始まった。この続きを書く頃はたぶんもう新年だろう。では皆さん、よいお年を!
2002年12月29日(日 ) 豊浜でマグロと海草を
一週間これを書かなかったら、世はなべて年末バージョン一色。クリスマスの「ク」の字もない。見事なものである。今日は友人のH井夫妻の誘いで知多豊浜の魚いちばへ正月の買出しに同行させてもらった。S子(妻)は仕事で来られなかったので、 独断でマグロの切身と海草を買う。帰りに昼食をごちそうになってしまった。
H井さんのご主人は車のプロで、クルマもマニュアルである。運転がうまいせいもあるが、助手席にいてもアクセルの動きを車がきちんと反映しているのがよくわかる。小気味がいい。自分はオートマ(チック)しか乗れないけれど、今日はちょっとだけ気が大きくなった。今度はマニュアルかなと。(そのときになればまたオートマになることはわかっているが…)
さて、明日あさってのわが家は(どこでもそうだろうけど)大掃除。自分の受持ちはガラス磨きと網戸の掃除、それにガステーブル、花壇の花活け、最後に注連飾り。これが終われば年越しそば(天ぷら付き)が食べられる。
2002年12月22日(日 ) アップロード初体験
昨夜から今朝にかけては自分のサイトのアップロード前最後の仕上げで徹夜した。今日は念願のアップロード初体験。まず、FFFTPをダウンロードしてマニュアルを読む。簡単。すばらしいソフトだ! FFFTPの名前は以前から聞いていたが、人気抜群のわけが理解できる。これからずっとお世話になりそう。Lhaとか、Ishとか、フリーソフトでDOS時代から使い続けているものがあるが(IshなどDOSからWindowsへの移行期に、どのくらい重宝したことか!)、これらの作者の方たちを私は神のようにあがめている。さて、アップロード実行。紆余曲折あったもののなんとか成功! 一部、表示されないものがあったのだが、ファイル名の拡張子に大文字があったのが原因とわかって解決! なにはともあれめでたしめでたし。これで年賀状にもURLが書き込める。だから宣伝のために今年はいつもより多めに(年賀状を)書いた。これからどういうリアクションがあるか楽しみでもあり、怖くもある。皆さんよろしくお願いいたします。
2002年12月21日(土 ) 「体制順応型気質」へ
いよいよクリスマスの雰囲気になってきた、テレビの番組も、街の様子も。どうも日本にもすっかりクリスマスが定着したのは認めざるを得ない(今頃?)。日本が豊かになったことがクリスマスを定着させたことは間違いないだろう。貧しかった子供の頃に、父親が生まれて初めてケーキを買ってきて、「景気が良いのでケーキを買ってきた」とダジャレを言ったのを今でも覚えている。お盆には坊さんを呼んでもキリスト教のキの字も知らない、職人気質で冗談ひとつ言わない父がである。私は近所にそのことを言いふらしに行ったくらいだった。
なぜ父はケーキを買ってきたのか。それは人並みにしたいということだろうと思う。現在でも私は(どっちでもいいとはいいながら)ケーキを買う。人並みにクリスマスをしたいのだろう。、単に人並みの暮らしをしていることを自分に確認したいという気持ちだと思う。よくいわれる日本人の「体制順応型気質」かも知れない。
今日はいよいよ年賀状の準備も始めた。今プリンタが壊れているので、どうしようかと思ったが、S子のワープロが印刷可能だったのでこれで作ることにした。カラーじゃないけど、羊もいるし。
年賀状はずっと年内には出さない主義だったが、これもクリスマスと同じ年末の行事として認めることにした。いろんなことに妥協し始めて、これもトシのせいなのかなあ。
2002年12月15日(日 ) 名古屋駅へ
今日は自分の誕生日。55歳。S子(妻)が「昔なら定年だね」といっていたが、自分でも信じられない年齢になった。朝からどうも様子がおかしいと思っていたが、どうもささやかながらお祝いをしてくれるらしい。というわけで辻町のアピタに行くことにした。
そのアピタで、ズボンを買った。ウエストに合わせて買うと、裾をずいぶん切らなくてはならないし、太もものところはダブダブ。つくづく年齢を感じた。
あと、ついでにCD屋さんでリコーダを500円!で買った。説明書が英語で、しかも「German System」なんて書いてあるので「まさかドイツ製じゃないよな」と思ってよく見るとケースに「made in taiwan」という小さなシールが貼ってあって何となくホッとする… 楽器は何でも好きで中学時代はクラリネットを吹いていた。本当に欲しいのはピアノだが、さて、生きている間に買えるか。
夕方、家族3人で名古屋駅へイルミネーションを見に行った。遠くから見た名古屋駅のツインビル(JRセントラルタワーズ)のライトアップもずいぶんきれいだが、10日の日に友人のH君と駅前を通りかかったときあまりの見事さに、S子とT子(妹)に見せようと思ったのだ。あのツインビルの正面に凱旋門を描いた巨大なイルミネーションと、その下に何百万個もの電球で作ったSLのイルミネーション、そして回りのビルのあっちにもこっちにもにも無数の電球が…。。感動的だが、一方でとてつもない浪費ではないかという自責の念が起こる(なぜ自責なのか、自分でもよくわからないが、これも先日書いた「責任の一端」かも)。クルマでぐるっと回るだけのささやかな見物だったが、渋滞のお陰で結構ゆっくりと見られた。何年ぶりかに駅前のロータリーも一周した。歩道にもたくさんの人で、「立ち止まらないで下さ〜い」というスピーカーの声も聞こえてきた。帰りもわざと渋滞の広小路通りを通って、最後は家の近くの「角千うどん店」で天ぷらうどんを食べ、家に帰った。「利家とまつ」の最終回を見ながらアピタで買ってきたショートケーキを食べて生誕記念日を終えた。
2002年12月08日(日 ) クルマに頼っている自分
愛車のロフトで仕事へ行く途中、ガソリンを入れた。環状線の平六通りで、従業員に言われるまでセルフスタンドだと気がつかなかった。でも初めから終わりまで親切に教えてくれて「セルフなのに変なの」と思ったことよ。これじゃセルフにしたメリット(人件費)がないのでは? しかもカード会員募集キャンペーン中らしく、大きなトイレットペーパーがサービスになっていた。つまりカード会員を増やせば会員が自分で入れてくれるようになり、そのうち従業員も必要なくなるだろうという戦略か。カードはガソリン代を銀行引き落としにするというものだったので作らなかった(カードは一種類しか持たない)。もうひとつ不思議なのは、すぐ近所の普通の(つまり従業員が給油し窓も拭いてくれる)スタンドとガソリン単価が同じことだ。セルフなら安いかと思ったがそうでもないらしい。最近のスタンドはフロントガラスも拭かない所が増えてきたし、ゴミも吸殻以外は引き取らないようだ。それでいいと思う。いずれにしてもガソリンスタンドはものすごく多い。過当競争の見本のようだ。市内では リッター当り92〜3円が多く、これでは採算が取れないかも。現在の自分からクルマを取り上げられると生活に支障が出るので困るが、昔は(免許を取る前は)、飼い猫が轢かれたり、自分も事故ったり、排気ガスや騒音に悩まされたりしていたのでクルマを憎憎しく思っていた。今でもそれらは解決していないのに、クルマに頼っている自分を矛盾していると思うが、そういうことはたくさんある。クルマ以外に、原子力発電、家庭排水、ゴミ。このパソコンもそうだ。新しい機種が出ると欲しいなと思ってしまう、等々。自分にすべての解決の責任があるとは思わないが、その一端があるのは間違いない。
2002年11月23日(土 ) 格安電話機
今日は友人のE美(塾の昔の教え子。もう大学生の子がいる)が遊びに来たので、うちの家族もいっしょに大曽根の栄電社へ行った。前から自分の部屋専用の電話機を買おうと思っていた(パソコンまでは電話線を引いてある)が、ちょうどあつらえ向き(¥1,980!)のがチラシに出ていたので買ってきた。E美が「どうしてそんなの簡単に買って付けられるの?うちにも付けて欲しいな。」というので、今はどこのうちにもモジュラージャックがあってそれに繋ぐだけだと説明したが、いまひとつ理解していないようだった。あと、ニトリでS子(妻)がベランダ下の花壇に置くねずみの人形(「人形」は変か)を買い、ユニクロをちょっとのぞいて、次に上飯田のダイエーに行ッった。ここも古い店で、大昔(25年は前だ)この近くに住んでいた友だちと来たことがある。ここのすがきやでラーメンを食べ、その後向かい側の「80円均一」でなんやかやと雑貨を買ったが、80円の電卓があったのには驚いた。ちゃんとルートもあるし、M+やM−、MRも、小さくたたんだ説明書もついている。帰宅して、さて電話機を取り付けた。といっても付属のモジュラーケーブルでパソコンと電話機をつなぐだけ。試しに携帯から自宅へ掛けて見る。呼出音が大きくてびっくりした。スピーカーに透明のガムテなど貼ってみたがまだ大きい。せめて呼出音の「切」くらい付けて欲しかったが値段が値段だからしかたないか。
2002年11月18日(月) 免許更新
今日、免許の更新に行ってきた。三年ぶり、ということはゴールド(優良運転者)ではない。実は平成10年4月の速度超過違反がまだ影響していて、前回に続き今回もゴールドではなかった。しかし「一般運転者」ということで1時間の講習後、5年の免許がもらえた。「規制緩和」の一環なのか、有効期間が延びている。今度の更新は平成20年の1月。それにしても平針試験場は車の量と人の多さがすごい! 平日の、それも8時に出かけたのに(月曜日だったのがいけない?)。試験場に入って駐車するだけでも20分くらいかかった。
帰りも試験場を出るのはすぐだったが、行きと同じく302号線で帰るつもりが植田あたりですごい渋滞。ずっと先のほうの信号が青になるたび5m位ずつ進むのだが、けっきょく痺れを切らし、Uターンして153号に戻り、41号へ出たのだが、ここがまたすごい渋滞。事故か何かあったのかと思ったが、自然渋滞らしい。毎日仕事でクルマに乗っている人は本当に大変だ。一つ違えば(自分と他人の)命にかかわる仕事だ。しかも会社や得意先から早く運べというプレッシャーが掛けられる……。
帰ったのは2時。疲れた。おかげで昼寝はぐっすり。
2002年11月16日(土 ) イデヤル
本当にわかったのかどうかあやしいが、もし、わかったのであればあとで思い出すためにこれを書いておく。ここでいう「イデヤル」とは、高木貞治(参考:http://ja.wikipedia.org/wiki/高木貞治)の「初等整数論講義」に出てくる数学概念。最近の本では「イデアル」と記述される方が多いようだ。「イデヤル」が「倍数」の概念の拡張であることはもう何年も前に別の本で読んでいたが、その意味が今ひとつわからなかった。例えば2の倍数の集合に「イデヤル」と名づけてもそこに何か新しい意味が生まれるのだろうか、と思っていた。
現在の理解度は次の通り。
「ある整数の倍数の集合をAとする。Aには次のような性質がある。
①Aの要素の和、差はAに属する。
②Aの任意の倍数はAに属する。
ここで発想を転換し、この①②の性質を持つ整数の集合を『イデヤル』と名づける。」
つまり、倍数の持つ性質から①②を抽出し、今度は逆にその性質を持つ集合を新たに定義する。こうすると(数学ではよく起こることだが)、新たな概念は元の「倍数」の概念以上のものになる。そこで、それを「イデヤル」と名づけたのである。
普通の整数の世界では素因数分解は一意性を持つが、整数の世界を広げると、それは成り立たなくなる。「それはむしろ例外である」(「初等整数論講義」)という。そこで、「イデヤル」を導入することで、素因数分解の一意性を再構築する。そしてそれが『「イデヤル」論の基本定理』となるのだ…。
こんなふうに理解しているが、その真骨頂にはまだ及んでいない。しかし、「イデヤル」がわからなかったことが「代数的整数論」(高木貞治著)に至る上での大きな壁であったから、今度は期待が大きくなる。もちろん目標は「類体論」である。
2002年11月11日(月) 「ぷりずむ」
今日は「おしどり」という自作をHPにアップするため、昔、自分も参加していた、「ぷりずむ」という同人誌を探し出してきた。「ぷりずむ」は、7〜80年代当時そろそろ流行の兆しがあったタウン誌のひとつ、もう少し正確に言うと「地域密着型総合小冊子」である。幼なじみのT中君が主宰し、近所の友人、家族を「ばんちゃ倶楽部」同人と称し、原稿を集め、初めの頃は月1回発行しながらも、やがて、季刊?となり、ついには年刊!、そしてやがて自然休刊となってしまったが、冊子の発行だけでなく、旅行や季節の催し、麻雀など、幅広く活動した。現在手元にある「ぷりずむ」の「最新号」は26号で、日付は1989年2月26日発行となっているので、のべ12年は続いたことになる。記念すべき第1号は、1977年1月、湿式のコピーで印刷されたB5版たった2枚。まだ「ぷりずむ」の名もなく、その後の大きな特色となった表紙の版画もなかった(「ぷりずむ」の名と、表紙の版画は第2号から)。が、裏にはその後も押捺されることになった「ばんちゃくらぶ」の板判がある。以下に主宰者の第1号への巻頭言全文を載せる。
「ばんちゃ倶楽部は今、その活動の世界を拡大せんと、1977年に対して大いなる野望を持ってその第一歩をこの紙面上 諸君に示るす。
20世紀が残り4半世紀を切った現在、我々は破壊と再生の20世紀を基盤として、21世紀への過渡期に未来を望む。我々は自らの存在をこの歴史に位置ずけるべく、日常に埋没することから、はい上がる努力をおしむべきではない ここに記載したものは新しい年に対面する各自の一つの軌跡である。」(原文のまま!)
このあとに9人の「同人」がおもに新年への抱負を述べている。近所の幼なじみ、お世話になった人ばかりで、今読むと懐かしいことこの上ない。この仕事をした主宰者のT中君の発想と情熱はいくら高く評価してもいいと思っている(わたしは彼の結婚式でもこのことを強調したものだ)。
当時けっこう評判だった(もちろん同人・友人の間でであるが)「ぷりずむ」の表紙をいくつか載せたので興味のある人は覗いてみてください。
2002年11月7日(木) ブログ開始!
今日からいよいよ「ブログ(公開日記)」を書こうと思う。お手本は森博嗣先生の「近況報告」。<漢字の読みの答え:「緊緊」は「ひしひし」(bishibishi、pishipishiでも可《広辞苑》)、「予予」は「かねがね」、「寸寸」は「ずたずた」です。(戻る)>