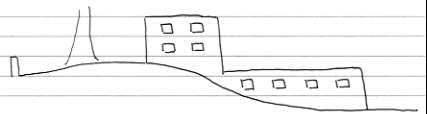
② 郊外のシュタイナー学校
「さあ次です、次!しかし弱ったな…。こんなに時間をさいてくれるとは思わなかった……。電車じゃ間に合わない。」
何のことを言っているのかわからなかったが、どうやらもう1つのシュタイナー学校にもアポイントを取ってくれていたようだ。
目の前にいたタクシーに乗って行き先を言うと、生粋のミュンヘンっ子と言う若いあんちゃんは
「そんなとこ、何しに行くの?あそこはそもそも、人なんかいないしな~。」
いったい、どんなとこだい。30分ほどで着いた。
ほんとに何もなかった。畑と野原の中に、ひっそりとしている。外の原っぱには、教師のものなのか5~6台の車が止めてある。
校門を入ると大きな木のまわりが輪になって、木のベンチになっており、右が2階の古びた校舎、左はビニールハウスの畑になっており、生徒の姿は見えず、ただの農家へ来た感じがした。
私たちはベンチで案内人のヘール先生を待ったが、実は私は、その時にはもう放心状態にあった。シュタイナー学校訪問にとどめを刺すこの旅の様々の体験を、無意識に体の中で消化する作業に入っていたようだ……。
静かにヘール先生が現れた。少し
「話を先にしましょうか?それとも校内見学から始めましょうか?」
話を先にしたが、放心している私は何を訊いて良いかわからず、ロイヒテンベルガー先生にしたのと同じ質問しかできなかった。答えも同じだった。
「手に負えない生徒などいくらでも出てくる。カウンセリングの方が必要な子は、そのような施設へ、点取りばかりが気になる子は、進学校へ、それぞれ転校させてやる方が良い。ここは、普通の子が来る普通の学校なのだ。」
とっくにシュタイナー学校では結論が出てしまっていることなのだろう。
次の質問の出せない私は、見学させてもらうことにした。
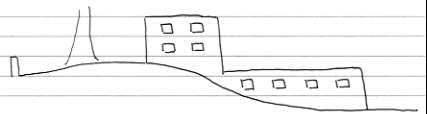
小さな校舎だなと思っていたが、後ろに半地下になった教室がいくつもあった。しかし、やはり市街地のものより小さめだ。生徒も少ないのだろう。
工作教室、オイリュトミー教室などおきまりのものを見せてくれるが、もう私にはおもしろくない。
「何か、生徒の作品が見たい……。」
この願いに、ヘール先生もまた、少し意外そうにする。いったい今までに来たという日本人は、何を見て帰ったのだろう。まさか建物だけ見て帰ったとも思えないが。
「いいですとも」
と、まず入ったのが体育館…と言うより講堂に近いものだった。いたいた、やっと生徒が見れた。
10人ほどの生徒が、忙しそうに舞台の大道具を作っている。
「今夜、生徒達の劇があるんだ。それはすばらしいものだ。ぜひ見に来るがいい。」
「見たい……。でも私は、明日朝一番に日本へ帰らなくてはならない。……時間がない……。」
地上へ出ると、小屋のような教室へ入った。中はきれいで、絵がいっぱい置いてあった。水彩画もあれば、クレヨン画もある。どの絵も本人の心がにじみ出ているようで、とても美しい。
「シュタイナー学校以外の生徒に、この絵の本当の良さがわかるでしょうか?
「わかるとも!みんなすばらしいって言うよ。」
ヘール先生は得意気だ。
ついでに畑も見せてもらった。生徒はここで農作業をするが、収穫が終わったばかりらしい。
「シュタイナー学校の生徒は両手に土を持って、どちらがやせた土か豊かな土かわかるそうだが、今でもそうですか?」
おまえ、よく知ってるなと言う顔をしたヘール先生は 「できるとも。うちの生徒にはわかる。今でもだ!」
さらに得意気であった……。
「私も帰るから、一緒に駅まで行こう。」
と言うヘール先生と、田舎道を歩いた。
「先生!最後のチャンスですよ。何か訊いておかなくていいのですか!」」
感無量となって口をきけなくなった私を気づかい、辻君があと押しをしてくれた。
「ヘール先生も、シュタイナー学校の教員養成所を出られたのですか。」
「いいや、私は普通の大学しか出ていない。赴任前の、3週間の講習会という制度もあるが、私はそれにも参加していない。」
「では、なぜ安定した公立学校へ行かなかったのですか。」
「私は……国家の為には…働きたくなかった。人と……生徒と、より密に接する為には、公立よりシュタイナー学校の方が良いと思った…。」
私はいっぺんに、ヘール先生が大好きになってしまった。この人こそ、シュタイナーが最も望んだ教師だろう……。
中学生くらいの女の子が4~5人、向こうからやって来て、ヘール先生に気づき、
「ヘール先生だ、ヘール先生だ!」
と、キャッキャと走って来て、口をとがらせ
「ボンジュール!アハハハ………。」
その笑い声は歌のように、田園風景に広がって行った……。もう、日本にはないシーンかも知れない。
私達は駅に立って列車を待っており、ヘール先生が口を開いた。
「君は何をしに、ドイツまで来たのかね?」
「シュタイナー学校を見に……それだけ……。」
「日本にもあるじゃないか。え~と、確か……。」
「東京のシュタイナーハウスですか?」
「オオ!それそれ!」
「あれは学校ではありません。アジアには、まだ一つもシュタイナーシューレはありません……。」
「君が作ればいいじゃないか。」
「……どうやって作るのですか?私の考えではシュタイナーシューレは、作るものではなく、発生するものです……。歴史も宗教観もまるで違う日本では、日本のシュタイナー教育が発生しなくてはならない。今のあなたの学校を、そのまま日本へ持って帰っても、何の意味もないし、機能もしないでしょう……。」
こわかったヘール先生の顔に、みるみる笑いが広がりやさしい顔になっていった。“受け入れてくれた”とわかった。頭を振りながら、
「そう!君の言うとおりだ。実は、私は明日アフリカのある国へ行くんだ。シュタイナーシュ-レを作りたいらしい。ここだけの話、私は、“なぜそこにシュタイナーシューレなんだ!”と思っているんだよ……。」
遠くに列車が見えた。ヘール先生は私の手をとった。
「君がやるならできる!ぜひ日本にシュタイナー学校を」
「力も人材も、私にはありませんよ……。」
「そうだ、人材を集めるんだ!そして、困ったら私を呼べばいい!いつでも日本へ行ってやろう……私の力を貸そう!さようなら、気をつけて……私は反対方向へ帰るんだ。」
「え……え?……あ……あ……。」
もう列車は来ており、ヘール先生は反対側のプラットホームへ向けて歩いて行った……。