神武天皇から崇神天皇に至る皇統譜の世代
序文
前稿「意富比垝と大毘古そして卑弥呼」では、雄略天皇から遡って崇神天皇に至るまでの歴代とその続柄を信頼できるものと仮定したうえで、邪馬台国問題についての私見を述べてみた。
その際、崇神天皇以前の歴代については、父子継承の連続となっており、その続柄に疑義があることも、併せて述べておいた。
単純に、父方の血統を辿るだけであれば、直線的な父子の連鎖となるが、統治者の地位継承次第となると、兄弟などの傍系親族も含むのが一般的である。
4〜5代程度の連続であれば、ともかく、それ以上の父子継承については、やはり、不自然であると見做さざるを得ないであろう。
そのような父子直系の皇統譜が出現した背景については、以前、「皇祖等之騰極次第の注釈的研究」や「意富多多泥古の系譜の系譜」などの小稿においても考えてみたことがある。
その詳細は、ここで再論しないが、要するに、初期天皇の続柄には、いくつかの異伝が発生していたものと想定されたのである。
おそらく、その混乱を収拾するために選択されたのが、広義の「子」によって歴代を繋ぐ簡易な系譜=「皇祖等之騰極次第」であったのではないだろうか。
本稿においては、記紀に残された異伝の痕跡と思われるものを繋ぎ合わせて、系譜の原形を推理してみたいと思う。
ただ、現状では、個々の続柄にまで踏み込んで推測をすることが難しい。
各天皇と婚姻関係で繋がる人々の系譜を対照することによって、おおよその世代を推定するのが精一杯のところであろう。
第一図
初代、神武天皇の皇后については、情報が錯綜した状態になっている。
本人の名前も、父母兄弟等の名前も、記紀によって、バラバラである。
その中にあって、外祖父の名前(ミシマノミゾクヒ)は、比較的よく一致していると言うべきであろうか。
ここで、古事記と日本書紀(本文)の系譜を対比しておくと、次のとおりとなる。
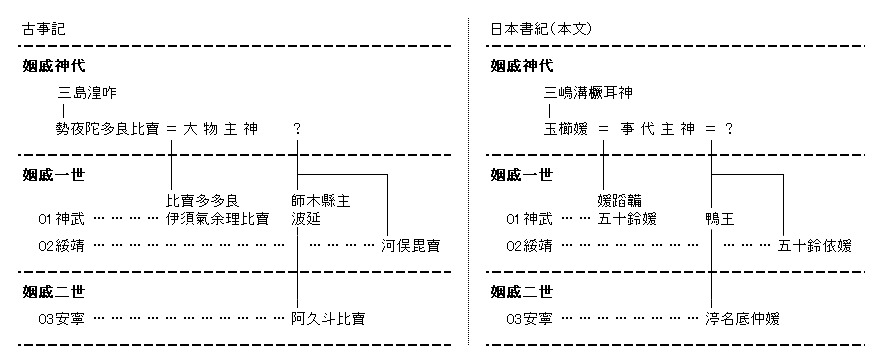
※ 古事記の「比賣多多良伊須氣余理比賣」については、別の箇所で「富登多多良伊須須岐比賣」とも、「伊須氣余理比賣」とも記されている。この図では、日本書紀(本文)との一致点が多い「比賣多多良伊須氣余理比賣」を掲出しておいた。
こうして見ると、不思議なことに、名前以外の系線(親縁関係)は、ほぼ同型となっている。
唯一の相違点は、古事記で言うと、「師木縣主波延・河俣毘賣」兄妹の父が明記されていないところであるが、日本書紀の系線と全くの同型であったとすれば、こちらは大物主神であったということになろう。(この点については、第二図でも触れる。)
「師木縣主」も大物主神を奉斎していたのであろうか。
それはともかく、神武天皇の皇后と綏靖天皇の皇后は、姉妹ということになり、この姻戚の血縁を基準として分類すると、神武天皇と綏靖天皇は、同一世代に包摂されることとなる。
この場合、両者の皇后を年の離れた姉妹と仮定すれば、神武天皇・綏靖天皇を父子としても、さほど無理のない説明となる。
※ 類例としては、持統天皇・元明天皇の姉妹に対する、天武天皇・草壁皇子の父子などがあげられよう。
ここで、当該世代を姻戚第一世代とすると、安寧天皇の皇后は、「波延」(鴨王)の娘であり、第二世代ということになる。
※ なお、「鴨王」が「鴨玉」か「鴨主」の誤写であろうことは、「意富多多泥古の系譜の系譜」の補注でも触れておいた。
第二図
前図で設定した姻戚第二世代を、さらに検討してみることにしたい。
この際、参考となるのは、日本書紀の細注(一書云)に見える「磯城縣主葉江」の系譜である。
各天皇紀(綏靖・安寧・懿徳・孝昭・孝安)に分散している「一書」の記述をまとめて図示すると、次のとおりとなる。
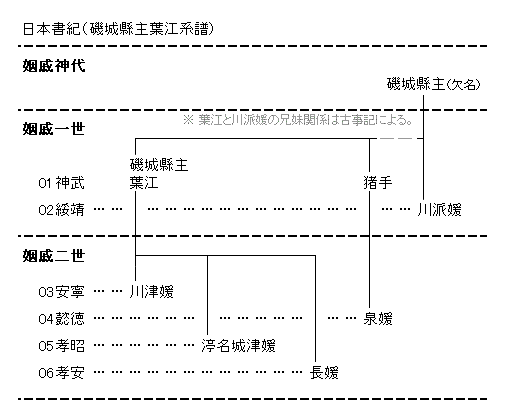
言うまでもなく、「葉江」は、古事記に見える「波延」と同じ音であり、同一人物と考えて間違いあるまい。
「川派媛」と「河俣毘賣」の音も一致している。
ただし、日本書紀においては、「葉江」と「川派媛」の関係が明示されておらず、かろうじて、古事記によって、それと分かるようになっている。
その「川派媛」の続柄については、綏靖紀の細注に、
一書に云はく、磯城縣主の女(むすめ)川派媛なりといふ。
とあって、名前不詳の「磯城縣主」の「女」ということになっている。
この情報と前図の推理を重ね合わせると、大物主神と「磯城縣主(欠名)」が同一人物?ということにもなるのだが、細注の「女」は「妹」の間違いであるかも知れず、何とも判断のつきかねるところではある。
さて、この「葉江」の系図によると、孝安天皇の皇后までもが「葉江」の「女」となっており、安寧・懿徳・孝昭・孝安の4代が姻戚第二世代に位置付けられる。
仮に、姉妹の年齢差が相当なものであったとしても、現実に、父子直系4代が同一世代の中に納まってしまうとは考え難い。
おそらく、「磯城縣主」が伝えていた系譜においては、天皇4代のうちの何代かが父子以外の傍系親族となっていたのであろう。
第三図
上記「葉江」の系譜と親和性の高い系譜が、古事記(崇神記)に見える意富多多泥古の系譜である。
意富多多泥古を崇神天皇と同一世代の人物と考えて対比させると、次のとおりとなる。
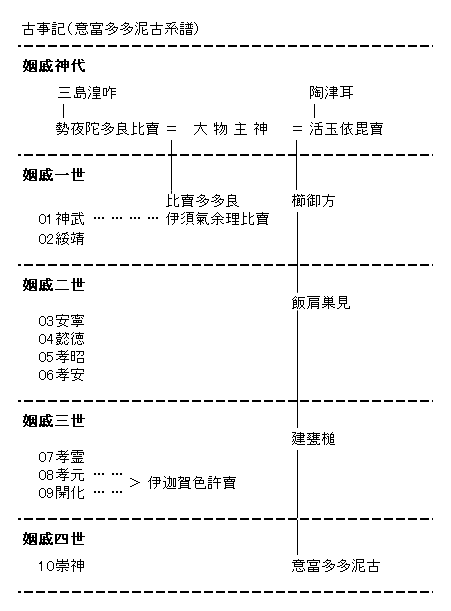
この時、意富多多泥古の系譜だけでは、神武天皇と崇神天皇以外の世代を設定できないのであるが、既述の姻戚第一世代と第二世代を仮定すると、消去法で、孝霊・孝元・開化の3代が第三世代に落ち着くこととなる。
※ このうち、孝元天皇と開化天皇とは、同じく「伊迦賀色許賣」を后妃としており、明示的に“同一世代”となっている。
この第三世代においても、現実に、父子直系3代が同一世代の中に納まることは困難であろうと思われ、傍系相続のあった蓋然性が大きいように思われる。
もちろん、こうして得られた姻戚4世代は、あくまでも姻戚側の世代であって、皇室側の世代は、もう少し多くなっていた可能性がある。
年の離れた姉妹と父子の組み合わせなど、1世代=2世代の対応は、姻戚第一世代から第三世代まで、いずれの世代においても起こりうることであろう。
第四図
上記のような4世代の系譜を設定した場合に、何かと都合が良くなるのが、古事記に見える意富夜麻登玖邇阿禮比賣の系譜である。
当人の名前は、安寧記と孝霊記に見られるが、それに連なる系譜も合わせて図にすると次のとおりである。
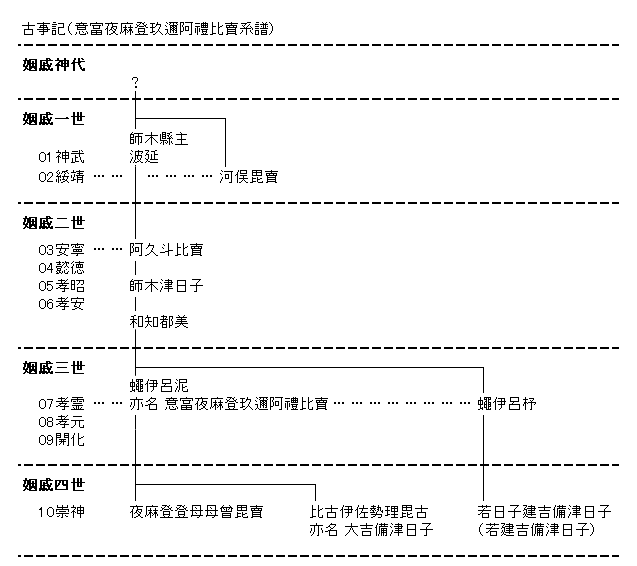
※ 「蠅伊呂泥」の「亦名」が「意富夜麻登玖邇阿禮比賣」とされているのは、安寧記においてである。ちなみに、日本書紀(孝霊紀)の場合は、「倭國香媛」の「亦名」が「絚某姉」とされており、父母を辿ることも出来ない。
こうしてまとめてみると、姻戚第一世代から第四世代に至る連続した系譜が現れる。
その中でも、特に注目されるのは、第三世代から第四世代にかけての系譜である。
これによると、「夜麻登登母母曾毘賣」が崇神天皇と同一世代となり、日本書紀の伝承とも平仄が合ってくる。
あらためて説明するまでもなく、崇神紀(十年七月是後条)には、「倭迹々日百襲姫」が大物主神の妻となり、薨後、「箸墓」に葬られたとする有名な説話が収録されている。
また、四道将軍の一人「吉備津彦(彦五十狭芹彦)」も、同じく崇神朝の人物となる。
※ さらに付け加えておけば、孝元天皇の皇子である「大毘古」も、また、崇神天皇と同じ世代となる。
ただし、一方では、「阿久斗比賣・師木津日子・和知都美」の母子直系3代が姻戚第二世代に位置付けられることとなり、かなり“窮屈”となる。
この部分については、直系3代を許容する別の異伝を想定した方が良いのかも知れない。
なお、余談ながら、安寧天皇(師木津日子玉手見)と「師木津日子」の父子については、その名前の共通性から、本来、同一人であったものが、いずれかの時点で分化したのだという“誤伝の発生”を導入することも不可能ではあるまい。
そうすると、原形と思しき母子として、「阿久斗比賣」と「和知都美」が残り、姻戚第二世代の中に納めても、さほど“窮屈”ではなくなる。
もちろん、これは、完全なる臆説であり、強く主張するつもりはない。
跋文
以上、四つの図を通して見てきたところからすれば、初期天皇の続柄には、異伝が発生していたものと想定されるのである。
現実に生起したであろうことを考えてみても、5〜7世代ほどの間に、10人の天皇が即位したと仮定するのが、最も無理の少ない説明となるように思われる。
履中天皇以降の系譜を参照すると、兄弟や従兄弟の相続が増え、1世代あたり3人程度の天皇が即位しているのであるが、それ以前は、そこまで頻繁に傍系相続が行われることはなかったようである。(履中天皇以降の世系については、前稿や「皇祖等之騰極次第の注釈的研究」など参照。)
なぜ、履中天皇の世代になって、そのような変化が現れたのか。
ここで、あらためて確認しておくと、相続は、基本的に、親から子へと受け継がれて行くものであるように考えられる。
それは、現代の遺産相続に至るまで、一貫して変わることのない基本線であろう。
ただ、それが、特定の地位や職掌と結び付くと、さまざまな制約を受けることとなる。
例えば、邪馬台国の卑弥呼の地位が「宗女」の台与へと受け継がれた背景には、「鬼道」に関する能力が大きく影響していたように想像されるのである。
兄弟相続の盛行も、多分に、そのような一定の能力が求められた結果ではないだろうか。
仮に、履中天皇の頃から、朝廷内部で有力な氏族が台頭し始めたのだとすれば、彼らを統率するだけの政治力が求められたはずである。
そのような状況の中では、重臣達よりも年上の老成した天皇が理想とされるようになったのではないだろうか。
※ この年齢的な条件については、天皇の即位年齢という観点から、すでに論じられているところである。→補注
一方、それ以前の朝廷は、皇族将軍の物語に象徴されるように、天皇の“身内”による運営(皇親政治)という側面が強かったと推測されるのである。
時によって、親征が行われることもあったのだとすれば、むしろ、ある程度の若さが必要とされていたかも知れない。
おそらく、その頃は、世代交代も順調に行われていたのであろう。
つまるところ、若々しい行動力が期待されていた頃には、比較的父子相続が多くなり、老練な政治力が要請されていた頃には、兄弟などの傍系相続が優勢になったと想像されるのである。
補注 即位の年齢
天皇の即位年齢について論じたものとしては、村井康彦「王権の継受:不改常典をめぐって」などがある。
そこでは、日本書紀に依拠して、文武天皇以前の状況を調べ、
・・・武烈が十歳、安寧が二十九歳で即位しているのを除いて、すべて三十歳以上である(平均年齢四十七歳)。これらのうち問題のある応神以前を除いても、即位年齢が三十歳以上であったというのは、これが不文律として存在していたことを思わせるに十分である。天皇の年齢は即位の要件であったとみなければならない。これは大王・天皇が諸豪族を統括して執政する以上、一定の年齢に達していることが不可欠の条件だったからである。
という推論を展開している。
引用文中「問題のある応神以前」というのは、紀年延長のことを言っているのか否か、定かではないが、とにかく、日本書紀においては、ほとんどの天皇について、三十歳を越えてからの即位が語られて(設定されて)いる。
おそらく、上記論者が想定しているのは、応神天皇以降の、少なくとも日本書紀が編纂されていた頃には、即位年齢に係る不文律が存在していたということであろうか。
※ 論点が「不改常典」にあるため、古い時代のことについては、焦点が当っていないように感じられる。
ちなみに、日本書紀に見える崩年干支と古事記の崩年干支が一致し始めるのは、安閑天皇の頃からである。
年齢に関する記事に信頼感が出始めるのも、その頃からとなろうか。
それ以前の即位年齢については何とも言い難く、不文律の有無も容易に推測できない。
この点、兄弟相続の盛行を指標として見た場合には、履中天皇以降という目安が、はっきりと現われてくる。
もちろん、最初から三十歳という年齢が出てきたわけでもなかろう。
年配の天皇を求める気運が、徐々に醸成されていったのだと思われる。
参考文献
日本古典文学大系『古事記・祝詞』(岩波書店、1958年)
日本古典文学大系『日本書紀 上・下』(岩波書店、1965〜67年)
村井康彦「王権の継受:不改常典をめぐって」(『日本研究:国際日本文化研究センター紀要』1、1989年、Web版)