意富比垝と大毘古そして卑弥呼
序文
いわゆる邪馬台国問題を考えるうえで、基点となるのは、西暦3世紀前半の頃という年代であろう。
魏志倭人伝等の中国正史に見える紀年は、おおむね信頼できるものとして検討を加えて行くことにしたい。
この点、日本側の史料、日本書紀の場合は、大幅な紀年の延長が認められ、古事記の場合は、紀年そのものが記されていない。
※ ただし、古事記では、例外として、33代中、15代ほどの天皇記に崩年干支が記載されている。この崩年干支の信頼性については、諸説が入り乱れており、筆者も判断のつきかねるところである。→補注1
おそらく、紀年のない古事記の方が原伝承に近い形をしているのであろう。
記紀の記述から、正確な紀年を求めることは出来ないが、完全に時間軸が失われているというわけでもない。
例えば、「此の天皇の御世」などとあるのが、時代指定の役割を果たしている。
このことは、不完全ながらも、皇統譜の“世代”を手がかりとして、ざっくりとした年代の推定が可能となることを示唆していよう。
本稿では、上記のような見通しのもとに、いくつかの推論を積み重ねて、邪馬台国問題に対する私見を述べてみたいと思う。
※ なお、本稿における記紀の引用は、日本古典文学大系本の訓読によった。ただし、振り仮名は、括弧書きとし、適宜、省略してある。その他、引用した書籍は、最後に参考文献としてまとめておいた。
第一段
埼玉県行田市稲荷山古墳出土の鉄剣に銘文が発見されたのは、昭和54年のことであった。
この鉄剣銘と記紀とを比較した時に、二つの名前が一致していることは、誰もが認めるところであろう。
その一件目は、ワカタケルという名前の一致である。
繁を厭わずに、それぞれの表記を掲示しておくと、次のとおりとなる。
・鉄 剣 銘:「獲加多支鹵大王」
・古 事 記:「大長谷若建命」
・日本書紀:「大泊瀬幼武天皇」
また、これに関連して、熊本県江田船山古墳出土の太刀銘に見える「獲□□□鹵大王」がワカタケルであろうことも大方の認めるところとなった。
それまでも、雄略天皇は、宋書倭国伝等に見える倭王武に比定されていたが、鉄剣銘に見える辛亥年(西暦471年)が倭王武に係る記事と矛盾することもなかった。
このようなことから、雄略天皇の実在が、広く一般に認められるに至っている。
第二段
さて、もう一つの一致は、オホヒコという名前の一致である。
・鉄 剣 銘:「意富比垝」
・古 事 記:「大毘古命」
・日本書紀:「大彦命」
こちらについては、名辞だけでなく、世代も、おおむね一致している。
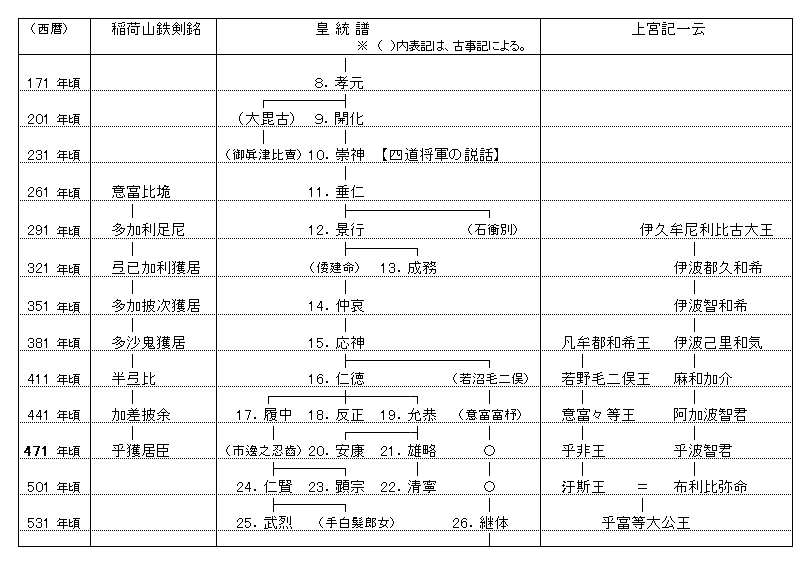
ただし、厳密に言うと、若干のズレがある。
上記系譜対照図のとおり、記紀の皇統譜(孝元天皇の皇子とする。)によると2世代。
四道将軍の説話に依拠して、崇神朝の人物だとすれば1世代。
本稿では、このように、微妙にズレながらも、ほぼ一致している状態を指して、“近接”と呼んでおくことにしたい。
もっとも、同一世代ではあっても、親子ほど年の離れた兄弟の存在などは考慮に入れておく必要があり、時として、ほぼ1世代程度のズレが生じることもある。→補注2
特に、一夫多妻が珍しくなかった時代においては、むしろ頻繁に発生していたと考えた方が良いのかも知れない。
7世代ほど遡った時点で、1~2世代のズレが生じているというのは、ごく自然のことと言えよう。
してみると、以上のような“近接”は、単なる偶然ではなく、系譜の正確さ、さらには、オホヒコの実在を示唆しているのではないだろうか。
このことは、決して筆者だけの発想ではなく、すでに田中卓「稲荷山古墳出土の刀銘について」や原秀三郎「古代地域研究の文明史的方法」も同様の指摘をしている。
第三段
しかし、これに対しては、7世代前の祖先の名前が、どこまで正確に伝わっていたのかという疑問を抱く人も少なくないであろう。
確かに、系譜偽造の可能性なども排除できない。
雄略朝における系譜の存在は認めるにしても、その中の人物(特に、祖父の代よりも以前の人物)の実在は、別途、考えてみなければならないとする議論が多数を占めているように見える。
ただ、系譜偽造の確実な証拠が明示されたこともなく、あくまでも、一般的な可能性の指摘にとどまっている。
今のところ、オホヒコの実在を否定しなければならない積極的な理由は、存在しないように思われる。
この点、名前の一致、世代の近接という具体的な事象が見られるからには、事実を伝えている“蓋然性”を認めても良いのではないだろうか。
何と言っても、当時は、世襲制の行われていた時代である。
ある人の地位や身分を決めるのは、その人の親(祖先)が誰なのかという点に懸かっていた。
例えば、崇神記(三輪山伝説)では、意富多多泥古が、
汝は誰が子ぞ。
と問われて、
僕は大物主大神、陶津耳命の女、活玉依毘賣を娶して生める子、名は櫛御方命の子、飯肩巣見命の子、建甕槌命の子、僕意富多多泥古ぞ。
と答えている。
実際に、慣行として、そのような系譜の披露が行われていた可能性は、十分に考えられよう。
一定の身分・地位にある人物が7世代ほどの系譜を記憶していたとしても、さほど不思議なことではあるまい。
鉄剣銘の系譜が独自に作成されたものであろうことは、先ほどの世代のズレからも窺われるところであって、もし、偽作されていたのだとすれば、むしろ記紀と完全に一致していて然るべきところではないだろうか。
第三段補足
なお、この際、一言付け加えておきたいのは、鉄剣銘と上宮記一云の系譜を比較した場合にも、次のような一致と近接が認められるということである。
・「ワケ」という名辞が使われている世代の一致。
・「臣」および「君」という、姓(カバネ)と解される名辞の出現する世代の近接。
※ 詳細は、上記系譜対照図参照。
この二点についても、田中卓前掲論文に言及があり、
・・・そして私は、『紀・記』によって察せられるやうに、允恭天皇の時代にカバネ制度の整備がおこなはれたと認めるので、この「ワケ」を、もともと允恭天皇以前の自然的・一般的な発生で特定の身分のものにつけられた尊称とみなし、「君」や「臣」は、允恭天皇以後に人為的・制度的に制定せられたカバネと考へたい。
という見解が述べられている。
※ このうち、「ワケ」については、単なる美称と考えた方が良いように思われ、その採否は、名前の流行として説明することが可能であると思われる。(先稿「鉄剣銘についての覚え書き」など参照。)
記紀において、允恭朝の盟神探湯は、氏姓の乱れを正したことになっているが、実際には、姓(カバネ)の賜与が始まったということであったのかも知れない。
とにかく、8~9代の名前が連なる各系譜において、ほぼ同じ頃になって、「臣」と「君」(具体的には、乎獲居臣と阿加波智君)が出現しているのは、単なる偶然ではあるまい。
双方の系譜が史実を反映している蓋然性を考えるのが通常の感覚であろう。
もちろん、そのことから、直ちに7~8代前の祖先の実在を推断するまでには至らないが、両系譜に対する信頼感が、より一層高まったと言うことは出来そうである。
第四段
本稿では、“蓋然性”を根拠に、オホヒコの実在を仮定して推論を進めていくことにしたい。
もし、この時、“蓋然性”だけでは不十分だと考える読者は、卑弥呼の場合を思い出してほしい。
卑弥呼の実在性は、何によって担保されているのか。
魏志倭人伝(および少帝紀)以外に何かしらの証拠はあるのか。
この点、中国正史については、文字による記録が古くから広範に行われていたことを理由に、信頼できるとする考え方もあるかも知れない。
しかし、「東夷」の中でも辺境に位置する「倭人」の情報がどこまで正確に記録されているのか。
あるいは、テキストの生成や転写の過程で、誤字・脱字等が放置されているのではないか。
疑問は尽きない。
※ 魏志倭人伝の情報に錯誤が含まれているであろうことは、邪馬台国の位置が、いまだに決定できない一事からしても、容易に察知されよう。また、史料による文字の異同も、例えば「邪馬臺」と「邪馬壹」など、枚挙に暇がない。
つまるところ、卑弥呼は、“蓋然性”だけで実在の人物とされているのではないだろうか。
筆者には、卑弥呼(中国正史)にだけ、緩い判断基準が適用されているように思えてならない。
※ この二重基準(ダブルスタンダード)の問題は、前稿「日本古代史学界の現状と問題点」でも触れておいた。
もし、読者が卑弥呼の実在を認めることが出来るのであれば、筆者がオホヒコの実在を仮定したとしても、何ら問題はあるまい。
第五段
さて、オホヒコを実在の人物とした場合、その活躍年代についても、おおよその見通しをつけることができる。
鉄剣銘に見える辛亥年(西暦471年)を基準にして、1世代を30年として遡れば、上記系譜対照図のような振り当てをすることができる。
この30年という概算は、古くから行われてきたものであり、そもそも、「世」という漢字自体に三十年という意味があった。(大漢和辞典など参照。)
ただし、先ほども触れたとおり、同一世代の兄弟であっても、長子と末子の間では、親子ほどの年齢差が生じる場合がある。
長子による相続が続いたり、末子による相続が続いた場合には、かなりの誤差が見込まれることとなろう。
それでも、長い目で見れば、特定の相続関係が延々と続くことは稀であり、長短が打ち消しあって、おおむね1世代=30年ほどに落ち着くものと思われる。
※ 年代の推定にあたっては、安本美典『新版卑弥呼の謎』などのように、天皇1代を約10年ほどで計算する方法もある。当然ながら、この算定法は、1世代あたり3人程度の天皇が即位している場合に限り、1世代=30年の計算と、ほぼ同じ結果をもたらす。どちらの算定法を採用すべきかは、ひとえに記紀皇統譜(続柄)の正確性に懸かっていると言って良かろう。本稿では、当該部分を信頼できるものとして話を進めているので、1世代=30年の計算を採用することとなる。
推定されるオホヒコの活躍年代(西暦)は、上記系譜対照図のとおり、鉄剣銘=261年頃、四道将軍の説話=231年頃、皇統譜=201年頃となる。
微妙にズレている3世代の中で、中間の崇神天皇の世代を目安とすれば、おおよそ3世紀前半の頃の人物と言うことになろうか。
※ 補注2でも触れたとおり、仲哀天皇の母方を辿ると、1世代短縮されることにもなる。3世紀前半というよりは、3世紀中頃とした方が良いのかも知れない。
この時代は、邪馬台国の女王卑弥呼の時代とも重なり合ってくる。
奇しくも、オホヒコは、卑弥呼と、ほぼ同じ時代を生きた人物ということになろう。
また、あらためて確認しておくと、オホヒコのみならず、崇神天皇以降の歴代とその続柄についても、信頼できるものとして話を進めて行きたいと思う。
※ 後ほど、跋文でも触れるが、崇神天皇以前の歴代については、その続柄(父子継承のみ)に疑問が残る。
第六段
崇神天皇と卑弥呼が、ほぼ同じ時代の人物であるということになると、大和朝廷と邪馬台国の関係は、どのように考えれば良いのであろうか。
ここで「邪馬臺」という文字がヤマトという音を写しているのだとすれば、邪馬台国畿内説が浮かび上がってくるところではある。
事実、隋書倭国伝・北史倭伝には、
・隋書:「都於邪靡堆,則魏志所謂邪馬臺者也。」
・北史:「居於邪摩堆,則魏志所謂邪馬臺者也。」
とあって、隋代に至るまで、一貫してヤマトに都が置かれていたように解釈している。(諸書の指摘するように、隋書の「靡」は「摩」の誤りであろう。)
しかし、邪馬台国について、記紀と倭人伝が一致するのは、ヤマトという国名の音のみであり、その他、卑弥呼という人物、あるいは、女王共立の政治的状況など、全く、一致するところがない。
九州説が即座に否定されることもなさそうである。
しからば、邪馬台国については、どのように考えるべきか。
筆者の現時点での見通しを述べておくと、以下のとおりとなる。
第七段
魏志倭人伝の中で、比較的信頼できる記述は、対馬海峡から九州北岸にかけての地理であろう。
そこに、対馬・一支・末廬・伊都・奴という国々のあったことは、ほぼ間違いがないことのように見受けられる。
また、それらの国々に対して、
自女王國以北、特置一大率、検察諸國、諸國畏憚之、常治伊都國、於國中有如刺史、
とあることからすると、諸国が卑弥呼の支配下にあった蓋然性も大きいと思われる。
一方で、崇神朝の四道将軍の派遣範囲は、北陸・東海・吉備・丹波であり、九州に及んでいない。
〇崇神紀(十年七月条)
・「 大 彦 命 」=「北陸」
・「 武渟川別 」=「東海」
・「 吉備津彦 」=「西道」
・「丹波道主命」=「丹波」
ただし、古事記では、孝霊記に、
大吉備津日子命と若建吉備津日子命とは、二柱相副ひて、針間の氷河の前に、忌瓮を居ゑて、針間を道の口と爲て吉備國を言向け和したまひき。
という記事があり、その分、崇神記では、
・「 大毘古命 」=「 高 志 道 」
・「建沼河別命」=「東方十二道」
・「 日子坐王 」=「 旦 波 國 」
という三方面への派遣にとどまっている。→補注3
記紀においては、その後、景行天皇から神功皇后の時代にかけて、九州に係る遠征記事などが、多数見受けられるようになる。
〇景行記
・倭建命を派遣して「熊曾建兄弟二人」を征伐。
〇景行紀
・12年7月:「熊襲」反乱。
・同年8月:天皇「筑紫」へ出発。
・同年9月~18年8月:天皇「豐前國長峽縣(京)」から「的(浮羽)邑」まで、九州各地を巡幸・平定。
・19年9月:天皇「日向」より帰還。
・27年8月:「熊襲」反乱。
・同年10月:日本武尊を「熊襲」征伐に派遣。
・同年12月:日本武尊「熊襲國」に到り「川上梟帥」を討伐。
・28年2月:日本武尊、帰還して「熊襲」平定を報告。
〇仲哀記
・天皇「熊曾國」を討伐しようとするも「筑紫之訶志比宮」にて崩御。
・皇后、朝鮮出兵、「宇美」にて応神天皇を出産。「末羅縣」にて釣魚。
〇仲哀紀
・2年3月:「熊襲」反乱。
・8年正月:天皇「筑紫」に行幸。「岡縣主祖熊鰐」や「伊覩縣主祖五十迹手」が帰服。
・同年9月:天皇「熊襲」討伐に失敗。
・9年2月:崩御。(一説に「熊襲」と交戦して戦死。)
〇神功摂政前紀
・仲哀9年3月:「熊襲國」帰服。皇后「羽白熊鷲」や「田油津媛」を討伐。
・同年4月:皇后「松浦縣」にて釣魚、「裂田溝」を開削、「橿日浦」で卜占。
・同年9月~10月:朝鮮出兵。
・同年12月:皇后「宇瀰」にて応神天皇を出産。
これらの記事から推察すれば、大和朝廷の支配が九州に及ぶのは、景行朝以降のこととなる。
もっとも、神武東征伝承においても、その途上、筑紫に滞在したことが語られており、その時、すでに服属していたとする解釈もできないことはない。
〇神武記
・「日向」を立って「筑紫」へ向かう。
・「豐國宇沙」で「宇沙都比古・宇沙都比賣」の饗応を受ける。
・「竺紫之岡田宮」に至り一年滞在。
〇神武紀(即位前紀)
・甲寅年10月:「筑紫國菟狹」に至る。
・同年11月:「筑紫國岡水門」に至る。
記紀の記述は、今ひとつ、はっきりとしないのである。
この点、ある程度、信頼出来る情報は、高句麗好太王碑銘に見える、
百殘・新羅、舊是屬民、由來朝貢、而倭以辛卯年來渡海、破百殘□□新羅、以爲臣民。
という有名な一節であろう。
辛卯年(西暦391年)の頃には、「倭」が朝鮮半島へ本格的に出兵していたことは、事実であるように解される。
歴史の大きな流れとして、大和に本拠を定めた勢力が、次第に周辺の諸国を従属させ、やがて九州北岸に至り、さらに朝鮮半島にまで進出するという図式は、非常に理解し易い。
後世、豊臣秀吉が天下統一の余勢を駆って朝鮮出兵に至った事実とも重ね合わせて、「歴史は繰り返す」という言葉を思い起こさせるところである。
秀吉の時は、九州平定(1587)、小田原攻め(1590)、朝鮮出兵(1592)という具合に、矢継ぎ早に兵を動かしていることからすると、古代においても、九州北岸の制圧から朝鮮半島への進出までは、比較的短期間のうちに行われたのではないだろうか。
もし、そうだとすれば、景行朝以降の九州進出を考えた方が、より整合的ではある。
はなはだ、心もとない推理ではあるのだが、崇神朝における大和朝廷の版図は、九州北岸にまで及んでいなかったと想定しておきたい。
※ さらに、推測を重ねておくと、卑弥呼→台与と続いた女王国は、その後、「相攻伐」する状態に戻ったところを大和朝廷に個別撃破(あるいは調略)されてしまったのではないだろうか。
以上、心証としては、邪馬台国九州説に傾いているのだが、ヤマトという国名の一致も捨てがたく、畿内説にも、若干の未練があるというのが偽らざるところである。
なお、九州説に立った場合、邪馬台国の所在地を九州内のどこに求めるのか、あるいは、神武東征伝承との関係をどう捉えるのかといった点については、考えがまとまらず、腹案を得るまでにも至っていない。
跋文
古墳時代とは、文字どおり、全国各地に古墳が築造されていた時代である。
それぞれの古墳は、単に築造されただけではなく、その後も、長く祭祀が続けられていたと考えて間違いあるまい。
例えば、大伴家持(万葉集 十八 4096)は、
大伴の 遠つ神祖(かむおや)の 奥つ城は 著(しる)く標(しめ)立て 人の知るべく
という歌を残しているし、壬申紀(七月条)には、
是より先に、金綱井に軍(いくさだち)せし時に、高市郡大領高市縣主許梅、儵忽(にはか)に口閉(つく)びて、言ふこと能はず。三日の後に、方(みざかり)に神に着(かか)りて言はく、・・・「神日本磐余彦天皇の陵に、馬及種種の兵器を奉れ」といふ。・・・故是を以て、便(たちまち)に許梅を遣して、御陵を祭り拜ましめて、因りて馬及び兵器を奉る。・・・
という著名な記事がある。
このような祭祀が行われていた頃、人々は古墳の被葬者を認識していたのであり、時には、被葬者に係る系譜の口誦も行われていたようである。
推古紀(二十年二月条)には、
皇太夫人堅鹽媛を檜隈大陵に改め葬る。・・・便(すなは)ち境部臣摩理勢を以て、氏姓の本を誄(しのびことまう)さしむ。
という記事も見られる。
古墳時代、祖先の名前は、個別・具体的な古墳とも結び付き、定期的な祭祀を通じて、絶えず、思い返されていたらしい。
そのような環境の中で、乎獲居臣が7代に渉る祖先の名前を記憶していたとしても、何ら不思議なことではあるまい。
ましてや、系譜の“総本山”たる皇統譜においては、なお更のことである。
ただ、上記系譜対照図のとおり、崇神天皇から仁徳天皇にかけての時期は、父子継承が連続しており、その後の兄弟相続が頻発する系譜とは対照的である。
続柄の伝承に錯誤が生じているのではないかという疑いも捨て切れない。
※ 考えてみると、続柄の記憶は、古墳などの具体的な事物とは直接に結び付かず、薄れがちであったのかも知れない。
とはいえ、系譜の該当部分を見てみると、成務天皇の次は、甥の仲哀天皇であり、神功皇后が事実上の天皇となるなど、単純な父子継承だけではないことも伝えられている。
4~5代程度の父子継承は、蘇我氏本宗(大臣・紫冠)の、
稲目 ― 馬子 ― 蝦夷 ― 入鹿
という相続などにも見られるところである。
そうしてみると、皇統譜の当該期間は、たまたま父子継承が優越した時期であったと考えても、ぎりぎり許される範囲内に収まるのではなかろうか。
本稿では、そう考えておくことにしたい。
それにしても、さらに神武天皇にまで遡ってみると、さすがに父子継承が連続し過ぎているように見える。
この点については、稿を改めて考えてみたいと思っている。
補注1 天皇の長寿
古事記の崩年干支、あるいは日本書紀の紀年延長を考える場合に避けて通れないのは、歴代天皇の異常な長寿であろう。
百歳を超える長寿が記紀ともに、多数見られる。
ここで、百歳以上と明記されている天皇・皇后を一瞥しておくと、次のとおりである。
〇古事記
・神武=137歳・孝安=123歳・孝霊=106歳・崇神=168歳・垂仁=153歳・景行=137歳・神功=100歳・応神=130歳・雄略=124歳
〇日本書紀
・神武=127歳・開化=115歳・崇神=120歳・垂仁=140歳・景行=106歳・成務=107歳・神功=100歳・応神=110歳
また、元興寺伽藍縁起には、
楷井等由羅宮治天下等與弥気賀斯岐夜比売命乃生年一百歳次癸酉正月元日尓・・・
とあって、推古天皇が癸酉年(西暦613年)の時点で百歳であったと記されている。
さらに付け加えれば、魏志倭人伝においても、
其人壽考、或百年、或八九十年。
という記事があり、「倭人」の“長寿”は、早くから国外にも知られるところとなっていたらしい。
これらのことを考え合わせると、記紀の長寿も、簡単に“後世の作為”として片付けるわけには行かないようである。
しかも、二百歳を超える長寿は、存在しないのであり、何かしらの算出基準があったと考えた方が良さそうにも思えてくる。
※ ただし、天皇以外に目を向けると、武内宿禰は、景行朝から仁徳朝まで仕えたこととなっており、公卿補任では、「春秋二百九十五年」とされている。
この点、諸書に論及のある「二倍暦」などの存在も、即座に否定することは出来ないであろう。
もし、そのような、特殊な暦法が行われていたのだとすれば、崩年干支は、通常の太陽年に係るものなのか、あるいは、特殊な暦年に配当されたものなのか。
筆者には、何とも判断のつきかねる問題である。
補注2 世代のズレ
世代のズレについては、父方・母方による微妙なズレもある。
例えば、景行記に記された倭建命の系譜には、
此の倭建命、伊玖米天皇の女、布多遲能伊理毘賣命(注略)を娶して生みませる御子、帶中津日子命。一柱。
とある。
この場合、仲哀天皇の父方と母方を辿ると、それぞれ次のような系譜となる。
・父方:(1)垂仁 ― (2)景行 ― (3)倭建命 ― (4)仲哀
・母方:(1)垂仁 ― (2)布多遲能伊理毘賣命 ― (3)仲哀
父方では、4世代の系譜が、母方では、3世代となってしまう。
おそらく、景行天皇と布多遲能伊理毘賣命は、年の離れた兄妹であったのだろう。
ここで、鉄剣銘の系譜と比較してみると、仲哀天皇母方の系譜を採用した方が世代のズレが緩和されることとなる。
記紀皇統譜の世代にも修正を加えたくなるようなところではある。
ただ、“異世代婚”は、決して珍しいことではない。
例えば、天武天皇の皇后は、兄(天智天皇)の娘(持統天皇)である。
世代には、そのような“重なり”が、しばしば発生しているというのが実態であろう。
紀年のごとき明確さは期待できないのであり、あくまでも、おおよその目安として取り扱うことが肝要となる。
補注3 四道将軍の系譜
崇神紀に見える四道将軍は、いずれも皇族であり、その系譜を示すと次のとおりである。
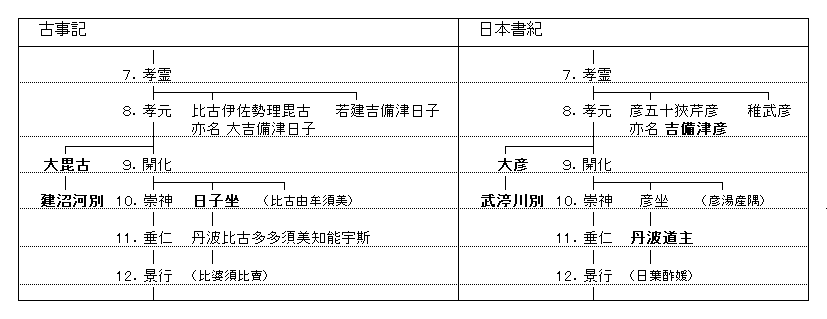
こうしてみると、吉備津彦(彦五十狭芹彦)の世代が、やや上の世代に振れていることが分かる。
この世代のズレをそのまま受け取って良いものかどうかは、微妙なところであろう。(崇神天皇以前の続柄に疑義のあることは、跋文でも触れておいた。)
1世代でも下降すれば、やや遠いという感覚からは、抜け出すことができる。
この点、孝霊記の文章では、大吉備津日子命(比古伊佐勢理毘古命)と若建吉備津日子命の派遣時期が明示されていない。
暗々裡に、孝霊朝の派遣を物語っているのであろうか。
可能性としては、孝元朝・開化朝の派遣も考えられる。
いずれにせよ、崇神記の記事は、“三道”への派遣にとどまっており、“四道”には、なっていないのである。
なお、記紀による相違点で、もう一箇所、目に付くのは、丹波に派遣された将軍の名前が異なっているというところであろう。
さりながら、全くの他人というわけでもなく、系譜によると、彦坐王と丹波道主命は父子とされている。
もしかすると、大彦命と武渟川別の場合と同様に、父子による征討伝承があったのかも知れない。
ただし、垂仁紀(五年十月条)の細注では、
道主王は、稚日本根子太日日天皇の子孫、彦坐王の子なり。一に云はく、彦湯産隅王の子なりといふ。
という異伝も紹介されている。
原伝承の解明は、一筋縄では行かないのである。
参考文献
埼玉県教育委員会編『稲荷山古墳出土鉄剣金象嵌銘概報』(県政情報資料室、昭和54年)
日本古典文学大系『古事記・祝詞』(岩波書店、1958年)
日本古典文学大系『日本書紀 上・下』(岩波書店、1965~67年)
東京国立博物館編『江田船山古墳出土国宝銀象嵌銘大刀』(吉川弘文館、平成5年)
黛弘道「継体天皇の系譜についての再考」(同著『律令国家成立史の研究』、吉川弘文館、昭和57年、所収。)
田中卓「稲荷山古墳出土の刀銘について」(同著『邪馬台国と稲荷山刀銘』、国書刊行会、昭和60年、所収。)
原秀三郎「古代地域研究の文明史的方法」(同著『地域と王権の古代史学』、塙書房、2002年、所収。)
安本美典『新版卑弥呼の謎』(講談社現代新書、昭和63年)
和田清石原道博編訳『魏志倭人伝・後漢書倭伝・宋書倭国伝・隋書倭国伝』(岩波文庫、1951年)
『隋書』(“漢籍電子文献資料庫”、台湾中央研究院公開電子テキスト)
『北史』(“漢籍電子文献資料庫”、台湾中央研究院公開電子テキスト)
佐竹昭広 木下正俊 小島憲之『萬葉集 訳文編』(塙書房、昭和47年)
田中卓「元興寺伽藍縁起并流記資材帳の校訂と和訓」(同著『古典籍と史料』、国書刊行会、平成5年、所収。)
新訂増補國史大系『公卿補任 第一篇』(吉川弘文館、昭和51年)