皇祖等之騰極次第の注釈的研究
序文
ここで、注釈的研究というのは、史料から史実を取り出そうとする研究の前段階として、本文の意味を明確にしようとする試みである。
文献の製作者は、その文章によって、どのような事象を語ろうとしたのか、あるいは、その語句を使って、何を指示しようとしたのか。
本人に直接聞くことができない以上、我々が解釈するほかあるまい。
解釈とは、推理である。
作業としては、対象とする本文を他の文章や用例と比較しながら、語られた文脈の中で、最も自然に意味が通じるものを常識的に判断するという流れになろ
う。
その推理が正鵠を射ているか否か、確証を得ることは困難であるが、意味が通じて、無理なく理解できれば、それを正解として話を進めるのが現実的な態度で
あろう。
(つまるところ、我々の実生活自体がそのような態度で成り立っている。)
なお、言葉として意味が通じた後に問題となるのが、その意味内容と史実との対応関係である。
意味を明確にする作業と、それが史実か否かを検討する作業は、よく似た作業ではあるが、決して同じものではない。
混同を避けるためにも、段階を分けて研究する必要がある。
本稿の目的は、あくまでも意味の解明にある。
第1章 皇祖等之騰極次第
第1節
皇祖等之騰極次第とは、一体いかなるものであったのだろうか。
持統紀二年十一月十一日条を見ると次のような一文がある。
[原文]
直廣肆當摩眞人智德、奉誄皇祖等之騰極次第。禮也。古云日嗣也。
[訳文]
直廣肆當摩眞人智德、皇祖等の騰極の次第を誄奉る。禮なり。古には日嗣と云す。
(日本古典文学大系『日本書紀』による。ただし、漢字の旧字体等については、文字セットの制約により、新字体に置き換えたも
のもある。以下、記紀の引用は、日本古典文学大系本を使用し、訳文のみの引用とする。)
この文章からすると、皇祖等之騰極次第は、誄(しのびごと)されるものであることが分かる。
誄とは、故人の死を悼んで述べられる詞であり、この場合は、天武天皇の殯(もがり)の場で奉ら
れたものである。
殯とは、遺体を陵墓に埋葬するまでの間、別の場所に仮安置して祭る行為である。
天武天皇の場合は、次のような経過を辿った。
1.朱鳥元年九月九日、天武天皇崩御。
2.同月十一日、殯宮を南庭に設置。
3.その後、2年2ヶ月の間、断続的に慟哭や誄などの儀礼が繰り返される。
4.持統二年十一月十一日に至り、皇祖等之騰極次第が誄される。
5.その終了後、大内陵に埋葬。
一言でまとめると、皇祖等之騰極次第は、先帝の殯の場で奉呈される詞であったことになる。
第2節
しからば、その詞の内容は、いかなるものであったのか。
まず、使用されている語句の意味を見てみると、「皇祖等」とは、皇室の祖先のことであり、「騰極」とは、即位するということであり、「次第」とは、順序
のことである。
これらの語義を総合すると、皇祖等之騰極次第とは、歴代天皇が即位した順序ということになる。
おそらく、歴代天皇の名前を即位の順番に並べたものをそのように呼称したのであろう。
なお、「次第」については、ようす・わけ・事情といった意味もあり、ここからすると、天皇名の他にも、即位の経緯を記した物語などが含まれていた可能性
も考えられないわけではない。
しかし、漢和辞典によると、「次第」の漢語としての意味は、順序というところにあり、ようす・わけ・事情といった意味は、国語のみに用いられるものとさ
れている。(角川漢和中辞典など。)
この国語の語義がいつ頃発生したのか、筆者には調べきれないが(小学館日本国語大辞典には、次第の「はじめから終わりまで」
という意味での用例として大和物語が引かれている。)、そもそも、一語を構成する「皇祖」・「騰極」が漢語である以上、「次
第」も、また漢語と考えるのが普通であろう。
日本書紀があくまでも漢文として書かれていることからしても、そう思われる。
こうしてみると、即位の物語などは、含まれていなかった公算が大きい。
第3節
この点を別の角度からも検討してみる。
まず、殯の儀式が行われた時間帯を考えてみると、それは、夜間であったと思われる。
例えば、仲哀紀九年二月の記事に、仲哀天皇の喪を秘匿して、「无火殯斂」(ほなしあがり)をし
たことが記されている。
喪を隠すための特別な殯が「无火」であったとすると、平常の殯は、“有火”であったことになる。
なぜ火なのかといえば、それは、火が儀式に不可欠な要素であったからに違いない。
照明のため、あるいは、迎え火・送り火のような意味合いで使用されたのであろうが、その時間帯は、夜が相応しい。
即位の大嘗祭が夜通し行われたように、崩御の殯もまた夜中に執り行われたのであろう。
このことは、行為としての誄を考える手掛かりとなる。
およそ、誄は、文面を読み上げたか、暗誦したかのいずれかであるが、夜の仄暗い中で行われたとすれば、暗誦の可能性が大きくなる。
また、推古紀二十年二月二十日条を見ると、皇太夫人堅塩媛を檜隈大陵に改葬した記事がある。
そこでは、阿倍内臣鳥、中臣宮地連烏摩侶、境部臣摩理勢等が誄をしたことが述べられており、これに続けて、
・時の人云はく、「摩理勢・烏摩侶、二の人、能く誄す。唯鳥臣のみは誄すこと能はず」といふ。
と記されている。
この記事からすると、誄の上手、下手は、「時の人」の話題となったことが窺える。
聴衆から良い評価を得るためには、澱みなく朗々と発声することが求められたであろう。
してみると、誄は、事前の準備なしに語れるようなものではなかったと想像され、この点からも、暗誦の可能性が高まるのである。
(誄
の詞は、おそらく文字化されていたのであろうが、儀式の場では暗誦されたと考えて置きたい。また、仮に文書を読み上げたのだとしても、仄暗い中で、漢文、
もしくは、万葉仮名を目で追い、大和言葉で朗詠し、良い評価を得るためには、相当の習熟が必要であったと思われる。)
このように、誄が暗誦を求められるような種類のものであったとすれば、その内容が、長大で複雑なものには、なり得なかったと思われる。
ここからしても、皇祖等之騰極次第は、歴代天皇の名前から構成される単純で簡潔な内容のものであったことが推測されるのである。
第4節
上記のような皇祖等之騰極次第のイメージに、最も近いのは、稲荷山鉄剣の系譜であろう。
銘文を埼玉県教育委員会編『稲荷山古墳出土鉄剣金象嵌銘概報』から引用すると次のようになる。
(表)
辛亥年七月中記乎獲居臣上祖名意富比垝其児多加利足尼其児名弖已加利獲居其児名多加披次獲居其児名多沙鬼
獲居其児名半弖比
(裏)
其児名加差披余其児名乎獲居臣世々為杖刀人首奉事来至今獲加多支鹵大王寺在斯鬼宮時吾左治天下令作此百練
利刀記吾奉事根原也
この系譜は、上祖から続く人名を「其児」という同じ言葉で繋ぐことによって成り立っているが、皇祖等之騰極次第も類似の構成になっていた可能性がある。
皇位が世襲である以上、その正統性を示すためにも、続柄は必要な要素であったと思われる。
ただし、それは暗誦が容易な形で語られていたに違いない。
この点、代毎に異なる続柄を語るよりも、同じ言葉を繰り返した方が遥かに容易である。
多様な続柄を一言で表現できる言葉があるとすれば、それを繰り返した可能性が大きい。
そう考えたときに注目されるのが“子”である。
第5節
記紀の中から“子”の用例を探してみると、親から生まれたものという意味の他に、次のような用例を見出すことができる。
1.子孫を意味する“子”
崇神記三輪山伝説の段に次のような記述がある。
・爾に天皇、「汝は誰が子ぞ。」と問ひ賜へば、答へて曰ししく、「僕は大物主大神、陶津耳命の女、活玉依
毘賣を娶して生める子、名は櫛御方命の子、飯肩巣見命の子、建甕槌命の子、僕意富多多泥古ぞ。」と白しき。
この記事では、「汝は誰が子ぞ。」という問いかけに対して、「子」で続く5代の系譜で答えている。
系譜中の「子」が親子の子であるとした場合、「誰が子ぞ」の“子”の意味は、親から生まれた子というよりも子孫と解釈した方が自然である。
“オヤ”が「親」とも「祖」とも書かれるように、“コ”にも、「子孫」の意味があったと考えられるのである。
※ 本居宣長『古事記伝』を見ると、「天神之御子」に注釈をした中で、「天神とは、上にも云る如く、凡て高天原なる神を申す
中に、此はも
はら天照大御神を指奉るなり、さて、天忍穗耳命は、其御子に坐々ば、もとよりのことにて、此次々には、御孫なる邇々藝命をも、又鵜葺草葺不合命をも、神武
天皇をも、みな天神御子と申せり、子とは、子孫末々までにわたる名なるが故なり、」と述べて、“子”に子孫の意味があることを指摘している。
2.一族を意味する“子”
推古紀二十年正月七日条に次のような歌がある。
・眞蘇我よ 蘇我の子らは 馬ならば 日向の駒 太刀ならば 呉の眞刀 諾しかも 蘇我の子らを 大君の
使はすらしき
この場合の「蘇我の子ら」は、「大君」に出仕する人々であり、蘇我の一族の者と解釈するのが自然である。
3.配下の者を意味する“子”
神武記東征の段に次のような歌がある。
・忍坂の 大室屋に 人多に 來入り居り 人多に 入り居りとも みつみつし 久米の子が 頭椎 石椎も
ち 撃ちてし止まむ みつみつし 久米の子等が 頭椎 石椎もち 今撃たば良らし
この場合の「久米の子」は、先ほどの「蘇我の子」と同様、久米の一族と解することも可能であるが、文脈からすると、それは兵士であり、大久米命の配下の
者とした方が、より自然であるように感じられる。
兵士の中には、当然、一族の者も含まれたであろうが、非血縁者も含めて“子”と呼ばれているように思われる。
4.“人”と同じ意味の“子”
景行記倭健命の薨去の段に次のような歌がある。
・命の 全けむ人は 疊薦 平群の山の 熊白檮が葉を 髻華に插せ その子
この場合の「その子」は、冒頭の「命の全けむ人」を受けており、“人”と“子”が同じ意味で使用されていることが分かる。
5.人間以外の“子”
武烈即位前紀に次のような歌がある。
・あをによし 乃樂の谷に 鹿じもの 水漬く邊隠り 水灌く 鮪の若子を 漁り出な猪の子
この場合の「猪の子」とは、猪そのものである。
また、仁徳記八田若郎女の段に次のような歌がある。
・八田の 一本菅は 子持たず 立ち荒れなむ あたら菅原 言をこそ 菅原と言はめ あたら淸し女
この「子」は、根から生える“ひこばえ”のことである。
〔追記〕
上記以外の意味合いで使用されている用例を追加しておくと、顕宗即位前紀に見える「室壽」の中の「吾が子等。」に対して、「子は、男子の通稱なり。」とい
う分注が付されている。
以上のように見てくると、“子”は、多様な意味で使用されている。
中でも、親子の子と同様に血縁関係を前提としながら、より広い意味を持った子孫や一族という用例は注目される。
この意味であれば、兄弟やオジ甥など広範な続柄を“子”の一言で表現することが可能である。
第6節
もう一つ、別の視点から考えられるのは、擬制的な親子の可能性である。
続日本紀の宣命を見ると、親子以外の続柄であっても、“我が子”という言葉が使用されている場合がある。
具体例としては、次のとおりである。
1.神亀元年二月四日の聖武天皇即位詔では、元明天皇が氷高内親王(元正)に譲位する時の言葉
が引用されており、その中で、元明天皇が皇太子(聖武)を「我子」と呼んでいる。
2.同じ聖武天皇即位詔の別の個所では、元正天皇が皇太子(聖武)を「吾子美麻斯王」と呼んで
いる。
3.天平十五年五月五日の元正太上天皇の詔では、元正太上天皇が聖武天皇を「現神御大八洲我子天皇」と呼んでいる。
4.天平宝字三年六月十六日の淳仁天皇の詔では、太皇太后(光明皇后)が淳仁天皇を「吾子」と
呼んでいる。
5.神護景雲三年十月朔の称徳天皇の詔では、元正太上天皇の遺詔が引用されており、その中で、元正太上天皇が聖武天皇を「朕子天皇」と呼んでいる。
(な
お、天平元年八月二十四日の光明立后の詔でも、「我王祖母天皇」が聖武天皇を「我児我王」呼んでいる。この「我王祖母天皇」が誰なのか、新日本古典文学大
系『続日本紀』の脚注では、元明太上天皇としているが、田中卓「中天皇をめぐる諸問題」などでは、元正天皇としている。どちらの説をとるべきか、俄かに決
定し難いのであるが、いずれにしても、本当の親子ではない“我が子”の一例には、なるであろう。)
これらの用例からすると、天皇が皇太子に対して、または、太上天皇や太皇太后が天皇に対して、実際の続柄に拘らず“我が子”という言葉を使用していたこ
とが窺える。
この宣命に見える“我が子”は、上記の子孫や一族という広い意味での“子”と考えても良いのだが、それよりも、太上天皇、天皇、皇太子という地位に付随
した擬制的親子と考えた方が、しっくり来るように思われる。
特に、光明皇后の場合は、藤原氏の出で、皇族出身ではないので、血縁よりも擬制的な関係を想定した方が、より自然に感じられるのである。
第7節
いずれにしても、皇祖等之騰極次第の中で続柄が語られていたとすれば、それは、“子”であった可能性が大きいと思われる。
具体的な文言については、稲荷山鉄剣と同様に「其児」であったのか、あるいは、もう少し別の表現であったのか、定かでないが、何らかの形で“子”を含む
表現が繰り返されたであろうことが想定される。(なお、鉄剣銘の「其児」については、後でも触れる。)
そして、その名残りではないかと考えられるのが、古代天皇系譜の十数代に渉る父子継承である。
記紀の神武天皇から成務天皇に至るまでの系譜は、下記の図のように父子継承ばかりである。
これは、履中天皇以降、兄弟相続等が盛行していることと比較して“不自然さ”を感じさせるものであった。
古代天皇系図
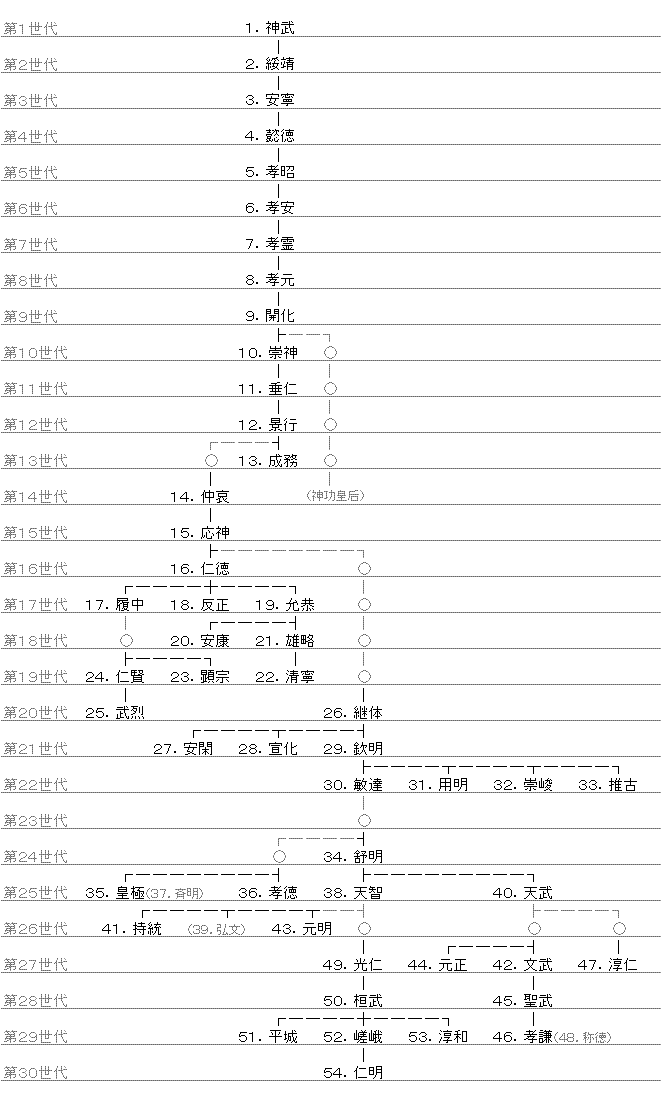
(初代神武天皇を第1世代として数え、切れのいいところで第30世代までを掲示した。また、男系で世代を数えたため、母子が
同一世代になっている場合もある。)
安本美典『新版卑弥呼の謎』を見ると、古い時代の父子継承の連続が信用できない理由として、次
の四点を挙げている。
1.用明天皇以降、昭和天皇に至るまでの皇位継承を調べると、時代を遡るにつれて、父子継承率が低下するという傾向が認められること。
2.上記期間の父子継承の発生頻度を基準にして考えると、仁徳天皇以前の父子継承の連続は、確率的に極めて起きにくい事象であること。
3.仁徳天皇以前の父子継承率が高い時期は、皇子(男子)の出生率が異常に高い時期でもあるこ
と。
4.景行天皇が四世孫にあたる訶具漏比売を娶って大江王を生むという不自然な例が見られること。
確かに、十数代にも渉る父子継承は、現実の世界では、起こり難い現象のように思える。
(しからば、何代続けば不自然となるのか。明確な一線を引けるわけではないが、おおよそ五~六代というのが一つの目安であろ
うか。例えば、蘇我氏本宗家が、稲目―馬子―蝦夷―入鹿、という四代の父子継承であったことからすれば、その程度の連続はあり得るものと思われる。)
このように、一見、不可解な十数代の父子継承も、その原因が皇祖等之騰極次第にあったとすれば納得できる。
皇祖等之騰極次第は、記紀の原材料の一つになったと考えられるからである。
第8節
記紀を見ると、歴代天皇について、后妃子女等のことが記載されており、皇祖等之騰極次第以外にも続柄に係わる原材料のあったことが推定される。
その原材料として、一般に考えられているのは、古事記の序文などに見える帝紀・旧辞であるが、いずれも現存していないため、詳細な内容を知ることはでき
ない。(この点については、後でも触れる。)
ただし、帝紀・旧辞については、古事記序第二段に、
・諸家の賷る帝紀及び本辭、既に正實に違い、多く虚僞を加ふ
とされていたり、欽明紀二年三月条の后妃子女の注で、
・帝王本紀に多に古き字ども有りて、撰集むる人、屢遷り易はることを經たり。後人習い讀むとき、意を以て
刊り改む。傳へ寫すこと既に多にして、遂に舛雜を致す。前後次を失ひて、兄弟參差なり。
とされていることからすると、異伝が多く、錯綜した状態になっていたらしい。
誤字、脱字、衍字等も、当然考えられる。
してみれば、そこに記された神武天皇から成務天皇に至る歴代の続柄にも、混乱があったに違いない。
後世の例ではあるが、先代旧事本紀巻第七天皇本紀「孝照天皇」段を見ると、
・諱觀松彦香殖稻尊者。磯城津彦玉手見天皇太子也。
(鎌田純一『先代舊事本紀の研究 挍本の部』による。)
とあり、孝昭天皇が安寧天皇の「太子」とされている。
これも、上記のような混乱を髣髴とさせるものである。
このような中で、記紀の編者は、何を基準として系譜をまとめたのか。
その基準こそが皇祖等之騰極次第であったと思われるのである。
そこに記されていた“子”を文字通りに生かして、系譜を繋いだとすれば、十数代に渉る父子継承の原因を説明することができる。
記紀の間で、后妃子女の記述に少なからぬズレがあっても、歴代の続柄に齟齬が生じなかったのは、このためであろう。
なお、仲哀天皇以降の続柄については、帝紀・旧辞の異伝もなくなり、そちらの記述を生かすことができたのだろうと思われる。(た
だし、仲哀天皇の場合を例外として考えると、履中天皇に至るまでの歴代に皇祖等騰極次第の続柄を適用した可能性が残る。)
第9節
また、これとは別に、皇祖等之騰極次第が、すべて“子”で繋がっていたことを窺わせる史料として、懐風藻の葛野王伝を挙げることができる。
そこには、皇太后(この場合は、持統天皇)が皇太子の人選を群臣に諮問したときの様子が記され
ており、王子(葛野王)の一言によって、天武天皇の嫡孫、軽皇子(文
武天皇)の立太子が実現したことになっている。
その該当する部分を抜き出すと、次のようになる。
・高
市皇子薨りて後に、皇太后王公卿士を禁中に引きて、日嗣を立てむことを謀らす。時に群臣私好を挾みて、衆議紛紜なり。王子進みて奏して曰はく、「我が國家
の法と爲る、神代より以來、子孫相承けて、天位を襲げり。若し兄弟相及ぼさば則ち亂此より興らむ。仰ぎて天心を論らふに、誰か能く敢へて測らむ。然すがに
人事を以ちて推さば、聖嗣自然に定まれり。此の外に誰か敢へて間然せむや」という。弓削皇子座に在り、言ふこと有らまく欲りす。王子叱び、乃ち止みぬ。皇
太后其の一言の國を定めしことを嘉みしたまふ。
(日本古典文学大系『懐風藻』による。)
この発言の中にある「我が國家の法と爲る、神代より以來、子孫相承けて、天位を襲げり。」という部分は、履中天皇以降の皇位継承の実態と、かけ離れてお
り、事実ではないとするのが通説となっている。
例えば、早川庄八『日本の歴史 4
律令国家』では、当時を、嫡出子と庶子を厳格に区別する中国流の思想が流入し、嫡々相承が重視されはじめた時期であるとした上で、
・葛野王の発言の中にある「子孫相承」は新しい思想であって、王が主張したような神代以来のものではな
い。
と説明している。
しかし、いくら持統天皇の意を汲んで強弁したのだとしても、中国流の新しい思想を神代以来の伝統だと言い張るのは、さすがに強引に過ぎるのではないだろ
うか。
この点、皇祖等之騰極次第が“子”で繋がれていたということが周知の事実としてあり、その意味をわざと曲解してこのような主張に至ったのだと考えれば、
それほどの無理もないように思われる。
古くからの慣習を前提とした発言であれば、「神代より以来」という言葉も生きてくる。
もし、そう考えて良ければ、葛野王の発言は、皇祖等之騰極次第が“子”で繋がれていたことの傍証となるであろう。
以上、皇祖等之騰極次第については、歴代天皇名から構成される単純で簡潔な内容のものであったと想定され、続柄として“子”を含む表現が繰り返されてい
た可能性が考えられたのである。
これを一言でいえば、簡略版天皇系譜とでもいうべきものであろうか。
第2章 日嗣
第1節
ここで、もう一度、持統紀二年十一月十一日条の記事に戻ってみると、「皇祖等の騰極の次第を誄奉る。」という文言に対して、「禮なり。古には日嗣と云
す。」という説明が加えられている。
このうち、「礼なり。」とあるのは、皇祖等之騰極次第を誄するという行為について、それが殯の儀式として定着していたことを説明したのであろう。
続けて、「古には」と述べていることからしても、文章の作者は、古くから行われてきた儀式と認識していたようである。
次に、「日嗣と云す。」であるが、率直に読めば、先に「礼なり。」と説明されたものが、過去には日嗣と云われていたのだと主張しているように思える。
そうだとすると、皇祖等之騰極次第を誄するという“儀式”が過去に日嗣と呼ばれていたことになる。
ところが、皇極紀元年十二月十四日条を見ると、舒明天皇の殯の記事があり、
・息長山田公、日嗣を誄び奉る。
と記されている。
この文章を「“儀式”を誄び奉る。」と解しては、わけが分からなくなる。
持統紀と皇極紀の文章を両立させるためには、武田祐吉『古事記研究 一
帝紀攷』などの言うとおり、皇祖等之騰極次第そのものが日嗣と呼ばれていたのだと解釈しなければなるまい。
この点については、倉野憲司『古事記全注釈 第一巻
序文編』のように、日嗣を「騰極」の訓注と考える説もあるが、文章の流れからすると、「皇祖等之騰極次第」全体を説明していると考えた方が自然である。
ここでは、日嗣を皇祖等之騰極次第の古風な名称であると考えて置きたい。
なお、「古には日嗣と云す。」という説明は、皇祖等之騰極次第の訓を説明したものではなく、漢字で“日嗣”と表記されていたことを説明したものであろう
と思われる。
もし、訓の説明であれば、一字一音の漢字が当てられて然るべきところである。
また、「古には」と限定しているところからすると、新しい時代(持統二年、または、日本書紀成立の頃)に
は、それを日嗣と表記する習慣が廃れていたことになる。
日嗣には、皇位や皇太子など、別の意味も存在しており、そちらの方が一般的な使用例となっていたため、このような言い方になったのであろうか。
第2節
さて、日嗣が皇祖等之騰極次第と同じものだとすると、次に問題になるのは、古事記の序文に記された帝皇日継との関係である。
といっても、結論は、すでに見えており、日嗣と日継が同じく“ヒツギ”であることからして、帝皇日継も、また同じものと考えるのが順当な推理であろう。
そして、その場合に問題となるのが、帝紀・旧辞との関係である。
古事記の序文には、
・諸家の賷る帝紀及び本辭、既に正實に違い、多く虚僞を加ふ
・阿禮に勅語して帝皇日繼及び先代舊辭を誦み習はしめたまひき。
・舊辭の誤り忤へるを惜しみ、先紀の謬り錯れるを正さむとして、
・稗田阿禮の誦む所の勅語の舊辭を撰録して獻上せしむといへれば、謹みて詔旨の隨に子細に採り摭ひぬ。
とあって、古事記撰録の様子を知ることができる。
また、天武紀十年三月十七日条には、これとは別に、
・帝紀及び上古の諸事を記し定めしめたまふ。
という記事もある。
これらの記事に見える帝紀・旧辞等の内容が、それぞれ如何なるものであったのか。
一般的な考え方を数式風にまとめると、
帝紀=先紀=帝皇日継=皇祖等之騰極次第=日嗣=皇室の系譜
旧辞=本辞=先代旧辞=上古諸事=種々の物語
古事記=帝紀+旧辞
となるであろう。(津田左右吉『日本古典の研究 上』などによる。)
さらに、武田祐吉『古事記研究 一
帝紀攷』によると、帝紀は、「先皇との御續柄、御名、皇居、御統治年數、后妃皇子皇女、御代の事件、寳算、崩御の年月日、山陵等の記事を含むもの」と考え
られている。
しかし、帝皇日継を簡略版天皇系譜と考える本稿にあっては、このような考え方を全面的に採用するわけにはいかない。
帝紀が皇居や后妃子女のことなどを含むとすれば、
帝紀≠帝皇日継
となる。
ところで、古事記序文によると、古事記は、「稗田阿礼の誦む所の勅語の旧辞」を子細に採り摭ったものとされている。
そして、その「勅語の旧辞」は、前の文にある「勅語阿礼令誦習帝皇日継及先代旧辞」
を縮約したものとされている。(例えば、倉野憲司『古事記全注釈 第一巻 序文編』などによる。)
この考え方に従うと、
古事記=帝皇日継+先代旧辞
となる。
ここで、帝皇日継が簡略版天皇系譜であったとすると、古事記の内容の、ほぼ全てが先代旧辞であったことになる。
しかも、先代旧辞に天皇名が欠けていたとは考えられない(ただし、続柄には異同があったのかも知れない。)の
で、実質的に、
古事記=先代旧辞
これに、「旧辞=先代旧辞」という式を正しいものとして代入すると、
古事記=旧辞
従って、先ほどの「古事記=帝紀+旧辞」という式を生かそうとすると、
帝紀=空集合
となって、「帝紀=皇室の系譜」という一般的な考え方と矛盾するに至る。
この点、太田善麿『古代日本文学思潮論 第二編 古事記の考察』では、
・帝紀に伝えているところは、本辞では欠かねばならず、本辞の物語るところは、帝紀では洩らさねばならぬ
ということが、何によってきめられていたか
という疑問を発して、
・自然に考えれば、これらの内容は本来「これ」か「あれ」かというように峻別し得ない性格を有したものが
多かったはずである。
という考察を展開し、
・「勅語の旧辞」とは畢竟素材内容的には帝紀以外の何ものでもなかったと言ってよいものであったと考えら
れる。
という意見の表明に至っている。
帝紀と旧辞の内容が重なり合っていても不思議ではないというのは、そのとおりであろうが、両者が全く同じというのも気が引けるところである。
そこで、一つの可能性として、
帝紀=歴代天皇についての記事全般
旧辞=広く神代も含めた記事全般
という等式を提示してみたいと思う。
西郷信綱『古事記注釈 第一巻』の場合は、
帝紀=神武天皇以下の記事
旧辞=神代の物語
という具合に両者を截然と分離していたのであるが、そうではなく、帝紀は旧辞の部分集合であると考えるのである。
つまり、
帝紀=歴代天皇の(系譜+物語)
旧辞=神代の物語+帝紀
と考えるのである。(この図式の中において、帝皇日継は、帝紀の部分集合ということになる。)
なお、神野志隆光『古事記の達成』を見ると、“紀”とは、紀年をたてた編年体のことであるとい
う想定のもとに、
帝紀=編年体
旧辞=非編年体
という体裁による区分を提示している。
しかし、日本書紀も“紀”であるとすれば、その神代巻は、非編年体の“紀”となり、上記の想定に反する事例を簡単に見出すことができる。
当時の人々に、体裁を書名で表そうとする意識があったかどうかは、甚だ疑問である。
第3節
日嗣の用例が数ある中で、注意を惹かれるのが、平安時代初期の“誄諡”の文中に見える「天ツ日嗣ノ御名」である。
“誄諡”とは、先帝に諡号を奉る旨を述べた誄で、次の三例が知られている。(引用は、いずれも新訂増補国史大系本による。)
1.日本後紀大同元年四月朔条に見える桓武天皇の“誄諡”
畏哉平安宮爾御坐志天
皇乃。天都日嗣乃御
名事袁。恐牟恐母誄
白。臣未。畏哉日本根子天皇乃天地乃共
長久。日月乃共遠久。
所白將去御謚止稱白久。日本根子皇統彌
照尊止稱白久止。恐牟恐母誄
白。臣未。
2.類聚国史帝王部十五諒闇に見える平城天皇の“誄諡”
畏哉讓國而平城宮尓御坐志天
皇乃。天都日嗣乃御
名事遠。恐牟恐母誄
曰。臣末。畏哉日本根子天皇乃天地乃共
長久。日月乃共遠久。
所白將去御謚止稱白久。日本根子天推國
高彦尊止稱白久止。恐牟恐母誄
白。臣末。
3.続日本後紀承和七年五月九日条に見える淳和天皇の“誄諡”
畏哉。讓國而御坐志天皇乃天
津日嗣乃御名乃事乎。
恐牟恐母誄白。臣末。畏哉日本根子天皇乃天
地乃共長久。日月乃共
遠久。所白將往御謚止稱白久。
日本根子天高讓弥遠尊止稱白久止恐牟恐母誄
白。臣末。
いずれも同形式の文章で、大きな違いはない。そこで、本居宣長「續紀歴朝詔詞解」第四十詔の注
釈を参考にしながら、桓武天皇の“誄諡”を漢字仮名交じり文に書き直すと次のようになると思われる。
畏きかや平安の宮ニ御坐しましシ天皇ノ。天ツ日嗣ノ御名の事ヲ。恐ム恐むモ誄白す。臣らま。畏きかや日本根子天皇ノ天地ノむた長ク。日月ノむた遠ク。白
され去かむ御謚ト称へ白さク。日本根子皇統弥照の尊ト称へ白さクト。恐ム恐むモ誄白す。臣らま。
(「臣
未」、または「臣末」の読みについては、本居宣長が「詳ならず」としながらも「ヤツコラマにて末はまの假字歟」と推測しているのに従ってみた。なお、倉野
憲司「帝皇日繼と先代舊辭」では、引用した「未」の傍らに「ナニガシ」というルビを振っている。おそらく、“臣某”を想定しているのであろう。)
この文中に見える「天ツ日嗣ノ御名の事」について、倉野憲司『古事記全注釈 第一巻
序文編』では、「御名が御業・御仕事の意であることは言ふまでもない。」と述べて、「天ツ日嗣ノ御名の事」を「天皇の御位にましました事」と解釈してい
る。
これに従うと、“誄諡”には、在位の確認と、諡を奉るという二つの目的があったことになる。
しかし、「御名」の意味については、わざわざ、「御業・御仕事」という特殊な意味を持ち出さなくても、普通に“名前”の意と解して、充分に意味は通じる
のである。
この場合、
天ツ日嗣ノ御名=御謚=日本根子皇統弥照の尊
という等式が成り立つであろう。
そう考えてこそ、“誄諡”は、諡号を奉ることを述べた一貫した文章となり、その名に相応しい内容となるのである。
そもそも、先帝が天皇として在位したことは、当時の人々にとっては、自明のことであり、殊更に確認するまでもないことのように思われる。
第4節
上記のように考えた場合に、「天ツ日嗣ノ御名」という言葉の意味は、いかなるものとなるのか、今少し触れて置きたい。
例えば、続日本紀天平宝字八年十月十四日条の宣命に見える、
・此の天つ日継の位を朕一り貪りて後の継を定めじとには在らず。
(新日本古典文学大系『続日本紀』による。以下続日本紀の引用は、新日本古典文学大系本による。)
という用例にならって、
天ツ日嗣=天皇
と解すれば、
天ツ日嗣ノ御名=天皇名
ということになるのであるが、これまで述べてきたように、
日嗣=皇祖等之騰極次第
と考えれば、
天ツ日嗣ノ御名=日嗣(皇祖等之騰極次第)に記載された天皇名
となるように思われる。
天皇名には、実名や通称、あるいは某宮治天下天皇といった呼称など、幾つかの種類があったと思われるのだが、その中の一つとして、日嗣に記載された名
称、すなわち、「天ツ日嗣ノ御名」もあったと想像するのである。
記紀の標目に掲げられている天皇名も、この「天ツ日嗣ノ御名」を採用したものであろう。(採録にあたっては、若干の手直しが
行われる場合もあったようで、例えば、清寧天皇の場合、古事記では「白髪大倭根子」、日本書紀では、「白髪武
廣國押稚日本根子」と表記されており、両者の間で美称部分に“ゆれ”が生じている。)
なお、平安時代初期においては、
天ツ日嗣ノ御名=御謚
となっていたわけであるが、それは、諡の風習が取り入れられて以降の話であろうと思われる。
本来は、生前に贈られたのか、崩後に贈られたのかの別を問わず、日嗣に記載された名称が「天ツ日嗣ノ御名」であったと思うのである。
記紀の天皇名を見てみると、おそらく生前からのものであろう名前を指摘することができる。
例えば、崇峻天皇の「泊瀬部」(表記は日本書紀による。以下同じ。)は、穴穂部皇子や額田部皇
女などと同様のものであり、諡というよりは、皇子の頃からの通称であるように思われる。
また、雄略天皇の「大泊瀬幼武」の場合、「幼武」(ワカタケル)が生前のものであろうことは、
稲荷山鉄剣の銘文によっても、裏打ちされるところである。
一方、諡であることが確実なのは、持統天皇の「大倭根子天之広野日女」以降の名称である。(次節で引用したとおり、続日本紀
に「諡たてまつりて」と明記されている。)
しからば、それ以外の天皇名は、どうかというと、はっきりしたことを言うことができない。
和田萃「殯の基礎的考察」を見ると、和風諡号の献呈は、安閑天皇の頃から始まり、それ以降の天
皇名は、「明らかに和風諡号である。」と述べられている。
しかし、これに対しては、
・安閑以降の「和風諡号」は諡ではなく、在世中の尊号と見なされる
(長久保恭子「「和風諡号」の基礎的考察」)
という意見も提出されている。
この点については、どちらに与するべきか、あるいは、第三の可能性を想定すべきか、人によって判断の別れるところであろう。
いずれにしても、「天ツ日嗣ノ御名」と「諡」とは、元来、別々の概念であったと思われるのである。
第5節
ところで、平安時代初期に「天ツ日嗣ノ御名」が奉呈されていたことは、すでに触れたとおりであるが、その「天ツ日嗣ノ御名」を累積したであろう日嗣本体
が誄されたという記録は残っていない。
その後も、この点に関しては、何の痕跡も見出すことができないことからして、その頃までに、日嗣を誄する慣習は途絶していたように思われる。
時代を遡ると、元明天皇は、遺詔で薄葬を指示し、聖武・称徳の二帝は、出家していたため、仏式の葬礼が行われたようであるが、おそらく、この頃を境にし
て、日嗣を誄する慣習は断絶したのであろう。
さらに、持統・文武の二代についても、日嗣を誄した確証はない。
しかし、この二代については、殯の記事があり、そこには、次のように記されている。
1.続日本紀大宝三年十二月十七日条(持統天皇の殯)
従四位上当摩真人智徳、諸王・諸臣を率ゐて、太上天皇に誄奉る。謚たてまつりて大倭根子天之広野日女尊と
曰す。
2.続日本紀慶雲四年十一月十二日条(文武天皇の殯)
従四位上当摩真人智徳、誄人を率ゐて誄奉る。謚したてまつりて倭根子豊祖父天皇と曰す。
これらの記事を見ると、天武天皇の殯の時と同じく当摩真人智徳が誄を奉っており、前代に引き続いて日嗣が口誦された可能性が考えられる。
そうしてみると、断絶の嚆矢は、やはり、元明天皇の薄葬指示にあった可能性が大きいように思われる。
ただ、この遺詔が原因とすると、その後、日嗣の誄は復活してもよさそうなものであるが、なぜ、復活しなかったのか。
そこで思い当たるのが、元明崩御の前年(養老四年)に完成した日本書紀三十巻と系図一巻の存在
である。
すなわち、簡略であるとはいえ、権威ある系譜であった日嗣に代わって、日本書紀が、新たな権威として重視されるようになったと考えるわけである。
そうなれば、当然、日嗣を誄するという行為の重要性は低下したことであろう。
養老五年以降、日嗣の誄に代わるものとして、日本書紀の講書が行われるようになったというのは、考え過ぎであろうか。
(日本書紀の講書は、葬礼に関係なく、おおよそ三十年に一度の割合で行われたようである。坂本太郎『六国史』など参照。)
第3章 稲荷山鉄剣の其児
第1節
先に第1章では、皇祖等之騰極次第の中で続柄が語られていたとすれば、“子”であった可能性が大きいと考え、“子”は、子孫や一族という広い意味での
子、もしくは、擬制的な親子であろうと推理してみた。
その際、皇祖等之騰極次第のイメージに、最も近いものとして、稲荷山鉄剣の系譜を取り上げたものの、銘文中の「其児」の意味については言及していなかっ
た。
ここでは、その点について、若干の考察を加えてみることにしたい。
義江明子『日本古代系譜様式論』を見ると、稲荷山鉄剣の系譜は、族長位の継承者を親子関係の有
無に関係なく「コ」でつないだ地位継承次第であるという考えが述べられている。
その地位継承次第を見分けるための特徴としては、「コ」でつなぐ一本筋の系譜であることと、族長位の継承を示す大王への奉仕文言を持つという二点があげ
られており、竪系図として有名な海部氏系図なども、上記の特徴を持った地位継承次第であると述べられている。
しかし、稲荷山鉄剣の系譜や海部氏系図が、言うとおりの地位継承次第であるかどうかは、疑問が残るように思われる。
例えば、稲荷山鉄剣の場合、乎獲居臣(オワケの臣)に至る八代が同じ族長位を継承したのかどう
かが問題となる。
多くの人が言うように、上祖の意富比垝(オホヒコ)が四道将軍の大彦命であったとすると、その
地位は、後世の中央豪族阿倍氏に繋がる血統に受け継がれていったと考えられる。
もしも、三代目の弖已加利獲居(テヨカリワケ)が本朝皇胤紹運録に見える豊韓別(大
彦命の孫で、阿倍氏の祖とある。)であったとすれば、少なくともそこまでは、阿倍氏直系の祖先と考えても良さそうである。
そして、阿倍氏の祖先とあれば、代々、上級官人として奉仕していたことが想定されるであろう。
(宋書倭国伝を見ると、倭王珍が倭隋等十三人のために平西・征虜などの将軍号を求めて聴されているが、阿倍氏の祖先は、この
ような将軍号を授けられる上級官人であったと思われる。)
しかるに、乎獲居臣は、杖刀人首であった。
銘文に、世々奉仕した旨が記されていることからすると、少なくとも数代前からは、杖刀人首の地位を継承していたように見える。
おそらく、杖刀人とは、後に百八十部(モモアマリヤソトモノヲ)と呼ばれるような下級官人の一
職種であったと思われ、杖刀人首も、せいぜい、後の伴造(トモノミヤツコ)に
相当する程度の中級官人に過ぎなかったと考えられる。
(蛇
足ながら、官人の序列を窺わせる記事としては、推古紀二十八年是歳条の「皇太子・嶋大臣、共に議りて、天皇記及び國記、臣連伴造國造百八十部幷て公民等の
本記を録す。」や、孝徳即位前紀の「百官の、臣・連・國造・伴造・百八十部、羅列りて匝りて拜みたてまつる。」などを挙げることができる。)
そうすると、八代の系譜は、同一の地位を継承したものではなく、途中で地位の下降があったことになる。
乎獲居臣は、阿倍氏本宗家の族長ではなく、いずれかの代で分岐した傍系の子孫であろう。
このように考えてみると、稲荷山鉄剣の系譜は、杖刀人首の地位継承次第というよりも、乎獲居臣が意富比垝の子孫であることを主張した血縁証明と考えた方
が説得力があるように思われる。
第2節
次に海部氏系図であるが、この場合も、継承した地位が、途中で変わっているように思える。
海部氏系図に記載された名前と注記を抜き出すと次のようになる。
丹後國與謝郡従四位下籠名神従元于今所齋奉祝部奉仕海部直等之氏
│
始祖彦火明命 正哉吾勝〃
也速日天押穂耳尊
│ 第三子
│
三世孫倭宿祢命
│
孫健振熊宿祢 此若狭木津
高向宮尓海部直姓定賜弖
│ 楯桙賜國造仕奉支品田天皇御宇
│
兒海部直都比
│
兒海部直縣
│
兒海部直阿知
│
兒海部直力
│
兒海部直[勲]尼
│
兒海部直伍佰道祝 従乙巳
養老元年合卅五年奉仕
│
兒海部直愛志祝 従養老三
年至于天平勝寳元年合卅一年奉仕
│
兒海部直千嶋祝 従養老五
年至于養老十五年仕奉
│弟海部直千足
│弟海部直千成
│
兒海部直綿麿祝 従天平勝
宝二年至于天平寳字八年合[十]四年奉仕
│
兒海部直望麿祝 従天平神
護元年至于[延曆]十年合十五年奉仕
│
兒海部直雄豊祝 従延曆十
一[年至于]弘仁十年合廿五年奉仕
│
兒海部直田継祝 従弘仁
[十一年]至于承和十四年合廿八[年]
│
兒海部直田雄祝 従嘉(以
下原本破損)
(田中卓「『海部氏系図』の校訂」を参照。ただし、横組に変更したため、系線等は、そのままではない。)
このうち、「児」以外の続柄が記されている部分を異質なものとして除外してみても、なお、名前のみの五代と、名前の後に「祝」とあって奉仕年数を注記し
た八代とに分かれることは一目瞭然である。
「祝」と記された八代は、籠神社の祝(はふり)として奉仕したことが考えられる。
しかし、その記載がない五代については、祝であったとは断定できない。
むしろ、「健振熊宿祢」の注記に「國造仕奉支」とあることからすれば、国造の地位にあったとも
考えられる。
そうすると、先の稲荷山鉄剣の系譜と同様のことが考えられる。
また、もう一つ気になるのは、奉仕年数の注記である。
これらの注記には、「千嶋祝」のように明らかに誤記と思われるものや、「望麿祝」のように計算違い(天平神護元年から延暦十
年までは26年。)と思われるものも含まれているが、おおよそ、30年前後の奉仕が多数を占めているように見て取れる。
このような奉仕年数の長さは、古代天皇の平均在位年数が約10年と言われていること(安本美典『新版卑弥呼の謎』などによ
る。)と比較して、かなり長いと言うことが可能であろう。
古代天皇の場合は、兄弟などの同世代相続が多く、そのような結果になっていると思われる。
そこで、世代と在位年数の関係について、第1章に掲げた古代天皇系図を見ながら簡単な計算をしてみると、
(紀年が確実で、世代の切れが良い舒明天皇以降を対象として数値を得た。)
舒明即位(629)~仁明退位(850)=7世代、21代、221年
221年÷7世代=31.6年
1世代平均≒30年
となる。
この結果を受けて、海部氏系図の注記を見てみると、代々の祝は、1世代から1人づつ出ていることが推測できる。
このことは、その続柄の「児」が親子の子であることを支持しているように思われる。
少なくとも、同世代相続が頻繁に行われたようには見えない。
祝のような神職の場合、国造や郡司ほどの実権が伴わなかったため、年齢や能力による制約、あるいは同族による競争が起こらず、父子相続が難なく続けられ
たのではないだろうか。
海部氏系図の親子関係を否定することに対しては、慎重にならざるを得ないのである。
第3節
こうしてみると、稲荷山鉄剣の系譜などが地位継承次第であるという想定には、俄かに賛同できない。
その続柄については、なお、広い意味での子や擬制的親子の可能性も残されているのだが、実際に親子であった可能性も捨てきれないのである。
ここで、改めて稲荷山鉄剣の銘文を刻んだ目的を考えてみると、それは、あくまでも乎獲居臣という個人の出自と業績の顕彰にあったように思われるのであ
る。
この場合、歴代の族長を誇るよりも、自分の血統を明確にしようとする意識の方が強く働いたのではないだろうか。
そう考えて良ければ、その系譜の目的は、第1章で引用した意富多多泥古の系譜と同じく、「汝は誰が子ぞ。」という問いに答えるためのものであったと想定
できるのである。
この点、皇祖等之騰極次第は、歴代天皇名の顕彰が目的となっていたように思われる。
古系譜に地位継承次第という類型を設定した場合、最も良く適合するのは、皇祖等之騰極次第であろう。
ただし、天皇は奉仕される側の立場にあるので、当然、「奉仕の文言を持つ」という特徴を見出すことはできなくなる。
系譜が地位継承次第であるか否かを判別するためには、系譜作成の目的を見極める必要があるように思われるのである。
跋文
本稿では、皇祖等之騰極次第という言葉の意味について考えてみた。
それは、時に日嗣とも呼ばれ、口誦を前提として製作された簡潔な天皇系譜であったと推測されたのである。
また、それが系譜であるという点に関連して、いくつかの問題に触れてみたが、具体的な要素である個々の天皇名については、ほとんど触れることができな
かった。
それらは、一般に、和風諡号と呼ばれている場合が多いように思われるが、本当に諡号であったかどうかも定かではなく、古代天皇の実在性とも関連して多く
の研究が積み重ねられている。
注釈的な観点からも、名前の組成や命名法など、気になるところではある。
今のところ成案を得るまでには至っていないが、別の機会に、改めて考えてみたいと思う。
参考文献
日本古典文学大系『日本書紀 上・下』(岩波書店、1965~67年)
埼玉県教育委員会編『稲荷山古墳出土鉄剣金象嵌銘概報』(県政情報資料室、昭和54年)
日本古典文学大系『古事記・祝詞』(岩波書店、1958年)
新日本古典文学大系『続日本紀 一~五』(岩波書店、1989~98年)
田中卓「中天皇をめぐる諸問題」(『田中卓著作集 5 壬申の乱とその前後』、昭和60年、国書刊行会、所収。)
安本美典『新版卑弥呼の謎』(講談社現代新書、昭和63年)
鎌田純一『先代舊事本紀の研究 挍本の部』(吉川弘文館、昭和35年)
日本古典文学大系『懐風藻・文華秀麗集・本朝文粹』(岩波書店、昭和39年)
早川庄八『日本の歴史 4 律令国家』(小学館、1974年)
武田祐吉『古事記研究 一 帝紀攷』(青磁社、昭和19年)
倉野憲司『古事記全注釈 第一巻 序文編』(三省堂、昭和48年)
津田左右吉『日本古典の研究 上』(岩波書店、1972年、改版)
太田善麿『古代日本文学思潮論 第二編 古事記の考察』(桜楓社、昭和37年)
西郷信綱『古事記注釈 第一巻』(平凡社、1975年)
神野志隆光『古事記の達成』(東京大学出版会、1983年)
新訂増補国史大系『日本後紀』(吉川弘文館、昭和57年、普及版)
新訂増補国史大系『類聚国史 前篇』(吉川弘文館、昭和8年)
新訂増補国史大系『続日本後紀』(吉川弘文館、昭和58年、普及版)
本居宣長「續紀歴朝詔詞解」(『本居宣長全集 第七巻』、筑摩書房、昭和46年、所収。)
倉野憲司「帝皇日繼と先代舊辭」(同著『古事記論攷』、立命館出版部、昭和19年、所収。)
和田萃「殯の基礎的考察」(森浩一編『論集終末期古墳』、塙書房、昭和48年、所収。)
長久保恭子「「和風諡号」の基礎的考察」(竹内理三編『古代天皇制と社会構造』、校倉書房、1980年、所収。)
坂本太郎『六国史』(吉川弘文館、昭和45年)
義江明子『日本古代系譜様式論』(吉川弘文館、2000年)
「本朝皇胤紹運録」(『群書類従・第5輯 系譜・伝・官職部』、続群書類従完成会、昭和57年、訂正3版5刷、所収。)
和田清石原道博編訳『魏志倭人伝・後漢書倭伝・宋書倭国伝・隋書倭国伝』(岩波文庫、1951年)
田中卓「『海部氏系図』の校訂」(『田中卓著作集 2 日本国家の成立と諸氏族』、国書刊行会、昭和61年、所収。)
小林敏男「王朝交替説とその方法論をめぐって」(同著『日本古代国家形成史考』、校倉書房、2006年、所収。)
本居宣長「古事記傳十四之巻」(『本居宣長全集 第十巻、古事記傳 二』、筑摩書房、昭和43年、所収。)
* 平成28年8月28日 第1章第5節に※印で始まる細注追加。
* 平成29年3月18日 第1章第5節に〔追記〕を追加。