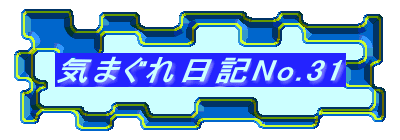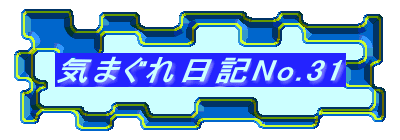「
●気まぐれ日記No.32」へ移りました。
●(467) 2013年6月24日
「バイト嬢」
もう40年も店をしていると延べ何人の人が働いてくれたことでしょう。今は男性スタッフはいないのですが、かつて男性は京大の学生と院生でしたので今では弁護士、企業の研究員、大学の先生などと立派な活躍をしています。
女性スタッフはそれこそ男性の何倍もいます。このところそんな彼女たちが突然店に尋ねて来て驚きます。
先週も学生時代にバイトしていてその後、九州で教師をしていた女性がこのたび結婚をするということで彼氏と一緒に来店。また別の日には家内が闘病している頃にバイトをしていた女性が訪問。沖縄で仕事をしていてこの度京都に帰ってきたのだとか。私の「気まぐれ日記」を見てママの亡くなったのを知っていたとか。こんなページを見てくれていることも嬉しいですが923を懐かしく思って来てくれことが嬉しいです。
先週は店のお嬢が一人退店です。親の面倒を見なくてはいけないということで九州へ帰ることになりましたが彼女はもともと舞妓をしていた女性です。舞妓時代の写真を無断で載せてみましたが若くて一番綺麗な頃の写真、まして横顔ですので許してくれるでしょう。

舞妓の頃
●(466) 2013年6月17日
「実山椒」
毎日の買い物へ行っていると旬のものがよく分かりますが今は新生姜と山椒の実が目立ちます。
そういえば家内が元気な頃には年中「ちりめん山椒」を作っていましたので、この時期には山椒のヘタ取りを手伝わされました。結構面倒くさい作業で手間がかかりますので店の従業員もヒマなときにはやらされていました。実をとって集めたら、一度湯がいてアク取りをしてから冷凍します。いつでも「ちりめん山椒」が作れるようにするためにと最低一年分は冷凍保存します。家内が亡くなってからはこの冷凍したものを何とかしなければと思いながらもそのままになっていました。今年こそはと思ってはみたものの、おじゃこや昆布などと一緒に焚くほどの気力もなく、先週とりあえず山椒だけの佃煮を作ってみることにしました。失敗してももともとという気持ちで作りましたがこれがなかなかの出来栄えで美味しいです。でも山椒なんてそんなに沢山あっても困るしネットで使い道を調べても大量には使えない。タッパに一杯もあるのでどうしようかと思案しましたが、とりあえず何にでも入れてみることにしました。蕎麦やそうめんの薬味、焼き魚や冷奴にかけたり、サラダに入れてみたりすると、これがなかなか何にでもよく合います。このところ我が家の料理は何でも山椒味。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
藤森神社は6月中は「紫陽花まつり」で土日毎に藤森太鼓、蹴鞠(けまり)、雅楽、舞楽などの奉納イベントが行なわれています。16日に行ってきましたが紫陽花満開までにはまだちょっと早い。次週にはもっとたくさん咲きそうです。

藤森神社の紫陽花
●(465) 2013年6月10日
「みすゞライブ」
先週は大谷学園で「金子みすゞ」ライブをしました。生徒対象ではなく大人の方のためのイベントです。呼んで頂くのはありがたいのですが今回は早朝のライブで夜型人間の私としてはなかなか厳しいです。
前日は店を早閉まいして深夜1時半には帰宅。5時半に目覚ましをセットしてすぐ就寝。裕香嬢は東京から夜行バスで6時過ぎに京都駅に到着ですので、私は6時に家を出発して京都駅へ迎えに行ってそのまま学校へ直行。7時前から荷物を搬入してPAセッティングと音合わせ。8時から9時まで会場(講堂)は生徒の行事で使用するのでPAを一旦ステージ下へ片づける。裕香嬢とは僅かの時間で簡単な打ち合わせ、9時から再セッティングして9時半から本番という段取りです。たった25分ほどの短い「みすゞライブ」でしたが時間厳守でピッタリ終了。
学校の中もいろいろ案内してもらいましたが市内が一望できるすばらしい屋上があります。五山の送り火も右の大文字以外は全部見えるようです。芝が植えてあってベンチもあって屋上公園です。
帰りがけには皆さんに喜んで頂けたとの報告を受けて「ホッ!」と一息。 PAを片付けてゆっくり昼食をしてから私は帰宅して昼寝。寝ておかないと夜がもたない。彼女はまたその日の夜に東京へ。0泊3日か?お疲れさん。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
今日は忙しいなか毎年恒例の「新生姜の酢味噌漬け」1キロほど作りました。
レシピは
「気まぐれ日記No.24」(364)「料理」に掲載。
●(464) 2013年6月3日
「打ち合わせ」
40周年パーティをすることになってから発起人さんとの「打ち合わせ」と連絡で俄かに忙しくなりました。今週は学校での「金子みすゞ」ライブもありますので先方との「打ち合わせ」、東京にいる裕香嬢とメールでの「打ち合わせ」も頻繁です。
ところでこの「打ち合わせ」という言葉、もともと日本の雅楽からきた言葉なのだそうです。雅楽の管弦楽(オーケストラ)は笙などの管楽器(吹きもの)、琵琶などの弦楽器(弾きもの)、太鼓などの打楽器(打ちもの)で構成されていますが、リズムを合わせるのには鞨鼓(かっこ)という鼓のルーツのような打楽器が指揮者の役割をしています。この鞨鼓を打って全員の息を合わせていくということが「打ち合わせ」の語源だそうです。
また「銀行の頭取」などの「頭取」は雅楽の全管弦奏者中の一番偉い人、云わばコンサートマスター。「音頭取り」の「音頭」は各管弦奏者の長、パートリーダーだそうだ。
また芝居、相撲など興行の終わりに「本日の打ち止め」と言いますが、舞楽の終わりなどで曲を止める時に打楽器が出す合図が「打ち止め」ということです。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
先週の続きですが、茄子の花が咲いていました。茄子にはこんな花が咲きます。みんな下を向いていて咲いていますので写真は非常に撮りにくいです。

茄子の花
●(463) 2013年5月27日
「野菜の花」
毎日のウォーキングコースは花盛りで道路脇には名前も知らないきれいな花がたくさん咲いています。周りの田んぼにも水が入ってどこも先週あたりに田植えが終わりました。毎日見ていると農家の仕事もつくづく大変だなと思います。
今の時期は畑の中にもいろんな花が咲きます。トマトの花、茄子の花、ジャガイモの花なんてご存知ですか?私も最近になっ初めてて知りましたが可愛い花が咲くものです。
今回は茄子の花を撮るつもりでしたが茄子の花だと思って撮ったものは、どうもジャガイモの花だったようです。そもそもジャガイモもピーマンもナス科らしく、その花は茄子の花とよく似ているらしい。トマトもナス科で小さな黄色い花をつけます。実は私はまだ茄子の花を知りません。




トマトの花 ジャガイモの花
●(462) 2013年5月20日
「40周年記念パーティー」
923が今年で40年を迎えます。周りの皆さんの後押しもあって「40周年パーティー」をすることになりました。 かつては20周年の大パーティー、30周年の「金子みすゞ」コンサートと、10年毎のイベントですがいつもたくさんの方に来て頂くきました。ママ(家内)が亡くなってもう4年が過ぎ、私だけで何とかやっている923で果たして何人来て頂けるかのかと思うと少々不安です。またパーテイー内容をどうするかということも大きな問題です。ただでさえ時間に追われる毎日で走り回っていますが、またまた忙しくなりそうです。
概略は次のとおりです。
〜〜〜〜923、40周年記念パーテイー〜〜〜〜
●日 時 9月23日(祝) 18時
●場 所 京都ホテルオークラ
●会 費 13000円(予定)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
20周年パーテイーの最後の集合写真を載せてみました。店の写真ではしっかりピントが合っているので拡大して見ると奥の人まで判別できます。もう20年も経ちます。時の流れは恐ろしい。


左の写真の前には星由里子さんも
写真拡大⇒
●(461) 2013年5月13日
「木津の流れ橋」
久御山町と八幡市を結ぶ木津川に架けられた「流れ橋」があります。初めて行ってみました。橋脚は固定してあるのですが橋桁は載せてあるだけで川が増水すると橋桁が流れてしまう構造になっています。橋桁は流れてもロープで結ばれているので、水が引けばまた戻して使います。正式には上津屋橋(こうづやばし)といって府道281号線の一部です。幅は3mしかなく車は通れないのですが、長さは356.5mもあって木橋としては日本最長級で周辺住民の生活道路としても重要な役割を果たしています。恒久的な橋を建設するのには数十億円もかかり、1キロ下流には幹線道路もあるのでこのような構造の橋にしているそうです。
橋の周辺は茶畑ばかりで民家や電柱がないので時代劇のロケにはたくさん使われています。故人ですがこの橋を愛した俳優の藤田まことさんは「木津の流れ橋」という歌も出しておられ、橋のたもとには藤田まことさん寄贈の石柱も建っています。


木津の流れ橋
●(460) 2013年5月6日
「続OB会、慶應大学」
少子化で学生の数が減るなかどこの大学も志望者、受験者を増やすためのPR活動をしていますが、OB会も大きな力になるようで、関東の大学のOB会京都支部の懇親会などにもわざわざ学長などが京都へ来られてOBとの親睦を図っておられるわけで学長、総長なども何かと大変な仕事です。
よく慶應のOB会(三田会)は結束が固く、また卒業生の愛校心は他大学と比べて格別であるといわれます。慶應大学の卒業生には卒業から25年目にその年の卒業式への招待状が届くのだそうです。出席した人の話しによると久々の母校での卒業式という雰囲気のなか深く感動するそうで、自分の子供たちも我が母校に入れたいと思うそうです。卒業から25年というとちょうど子供が大学へ行く頃です。また卒業から50年目の年にはその年の入学式への招待状が届くということです。ちょうど孫が大学を目指す頃で我が孫にも母校に行かせたいと思うらしい。ということで慶應の卒業生は人生で二度の入学式、卒業式に出席することができるわけです。このようなことも卒業生の結束力と愛校心の力になっているのかもしれません。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
あっという間にGWも終りました。休みの間に店を改装、少しきれいになりました。店は暦どおりに休みでしたが親戚が来宅で毎日京都観光です。

少し新緑の清水寺です。
●(459) 2013年4月29日
「OB会、同窓会いろいろ」
同志社グリークラブのOB会のやり方で面白い話を聞きました。もちろんOB全体の会はあるのですが全体では世代差があって知らない人も多く、みんなで一緒に歌える曲も違っています。そこで全体でのOB会とは別に卒業後40年目の学年が幹事になって開催するOB会をしているということです。その幹事をする学年が前後3年ずつの7学年でのOB会をするというものです。
最初の案内は自分が1回生の時の4回生の学年からきます。最後は自分が4回生の時の1回生メンバーが幹事をする年まで計7年間続けて参加できるOB会というか同窓会です。当然そのあいだに自分たちの学年がお世話をする卒業40年目の年があってその年は、自分たちが1回生の時の2,3,4回生と自分たちが4回生の時の1,2,3回生という全員知っているメンバーに案内をすることになります。また卒業して40年というとちょうど会社を退職する頃で時間的にも余裕がある頃です。これはOB会の中のオフィシャルな会なのですが、そのあと卒業して50年目のOB会もやっているのだとか。
我々のような歳になるとみんなよく同窓会をしていますが、店のお客さんで毎月4日に同窓会をしているグループがあります。卒業期が4期ということで毎月決まった洋食屋さんに集まります。当然のことながら毎月、曜日が変わりますので月毎に曜日の都合も解消されます。毎回の案内状も出欠の申し出も無しで当日に現地集合ですが、いつも10人以上、多いときは数十名も集まっておられます。
私も仕事がら各種同窓会の万年幹事で先週も高校の同窓会をしました。高校の同窓会といっても正式なものは数年に一度なので、今回の会は京都在住者主体で2,3ヶ月毎にやっている気楽な食事会と飲み会です。毎回10数名の集まりですが今回は金沢からの参加や福井県から先生にも来て頂いて全部で17名。毎度のことながら賑やかなことです。

高校同窓会
同窓生はこちら⇒
●(458) 2013年4月22日
「続、銭湯」
そういえば学生時代は頻繁に銭湯へ行きました。所属の合唱団の先輩などが下宿生で風呂好きであったこともあるのでしょうけれど、暇があれば大学前の銭湯へ行っていました。信州の山へ行っても温泉を探し、旅の帰りは駅前の銭湯でひと浴び。誘い合って銭湯へ行くことは我々にとってはまったくの日常でした。
私にはまったく覚えがないのですが、私が4回生のときに大学に入りたての新入生が初めてクラブのボックスをのぞいた時に初対面の私が銭湯に誘って一緒に行ったらしい。その彼は何と変な怪しいクラブと思ったと未だに笑い種になっています。確かに今思うとちょっと変だという気はしますが、当時銭湯に行くことはそれくらい自然なことだったわけですが。
ところでまたまた余計な話しですが銭湯の経営者の9割近くが北陸出身者で、特に石川県出身の人が非常に多いということです。京都府下では70パーセント、大阪府下でも50パーセント以上が石川県出身者で占められている。石川県出身者は東京では新潟、富山県人に負けて3位ですが神奈川では約50パーセント、千葉でも35パーセントということで、関東にも多く進出されています。ほとんど日本の銭湯は石川県人をはじめとする北陸県人が支えているということです。
また銭湯の名前でいうと、東京では「松の湯」「梅の湯」など、めでたい名前に「湯」と付けたものが多いのに対し、大阪では半数以上が出身地や地名に「温泉」と付けた「○○温泉」が多いようです。京都を調べてみると「○○湯」の方が多いようですが。
また風呂場の造りでいうとカラン(水や湯が出る蛇口)の数が東京のほうがかなり多いらしい。東京では浴槽の湯を汲んで身体にかけるということをまったくしないのでカランの数が必要なのだとか。それに関西の風呂では浴槽の周りに一段段差があって年寄りなどがそこに腰掛けてしゃべっているいる光景が見られますが、東京の銭湯にはそのような段差は造ってないらしい。また驚くことに東京の「女湯」にはイスが無いらしい。女性がイスに座って足を広げて体を洗うのは、はしたないということで東京ではイス無しでしゃがんで片ひざを立てて洗うらしい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
先週、松尾大社へ行ってきました。もともと住んでいた桂からすぐで当時はわざわざ行くこともなかったのですが、今では関西一のヤマブキの名所になっているようで驚きです。3000株ものヤマブキが境内を横切る一ノ井川沿いの水面に黄金の花を咲かせます。昨日21日はちょうど千年以上も続いている松尾大社の神幸祭でヤマブキ満開の中を神輿が出て行ったことでしょう。神社から出る6基の神輿と唐櫃が桂離宮前から船に乗って桂川を渡るというお祭りでしたが、生憎の悪天候のためこの「船渡御」は12年ぶりに中止になったそうです。
写真は一週間前の写真です。多分今は満開です。



松尾大社のヤマブキ
●(457) 2013年4月15日
「銭湯」
車で5分くらいのところにちょっと小奇麗な銭湯を見つけました。和風で番台があってというような昔ながらの銭湯ではなく料金を払う受付もサウナ風です。中にはもちろんサウナもあるし露天風呂もあります。露天風呂は鳥の鳴き声も流れていて雰囲気充分、入湯料は410円で一般の銭湯です。
毎日のウォーキングも時間のあるときは稲荷山や清水山など東山を歩いていますが、先日もお天気の良い日曜日に将軍塚から知恩院まで行くことにしました。山頂の駐車場に車を停めてのんびり15分ほどもあれば知恩院の鐘楼のところまで下ります。この鐘は年末の除夜の鐘の時に、仰向けに倒れながら突いているのをご覧になったことがあると思いますが日本三大名鐘のひとつ、さすがに大きい。私も鐘のところへ来るのはもう何十年ぶりかのことです。知恩院の御影堂は現在修理中で全体が工事用フェンスで覆われています。少し降りて円山公園をまわってまた上まで戻ろうとすると、私と同じ歳くらいの男性から将軍塚への道を訊かれる。このところ我々世代の年寄りがよく歩いていますが、その人は西加茂から歩いてきているとか。すごい!時間はたっぷりある。ひま人、元気です。その人を将軍塚まで案内してまた車で帰宅。
そのあとその銭湯の露天風呂でのんびり汗を流すとちょっとした温泉旅行気分。安い日帰り温泉の一日でしたが夜にはまた飲み会で痛飲。折角の健康ウォークも台無し。

知恩院の大釣鐘
●(456) 2013年4月8日
「923号引退」
以前の「気まぐれ日記No.21」(312)=2010年5月31日にも書きましたが、私には30年以上も毎日送り迎えしてもらっているタクシーがあります。車のナンバーもわざわざ「9235」(923号)というナンバーを付けられたくらい私の店とともにあったタクシーでした。お父さんと呼んでいた運転手さんは私の一回り上の戌年ですからもう80歳手前です。以前から奥様や子供さんからの引退勧告に抵抗してこられたのですが、とうとう抗しきれず先月一杯で引退ということになってしまいました。3月末で車も営業免許も返却してちょっと小さめの乗用車を購入されました。昔から新車になる時にはいつも最初のお客として新しい車に乗せて頂いていたので、今回も4月1日に新車で店まで送ってもらうことになりました。店の前に着いても永年の習慣でドアの開くのを待っている自分には思わず笑ってしまいましたが、そんなDoor to dooの習慣が身についてしまっています。その車のナンバーを見るとまたまた「9235」。運転手のお父さん一生こだわって923号のようです。
今年は京都も長い間桜が楽しめましたがそろそろ終わりです。毎年桜の時期には店の帰りにお父さんのタクシーで必ず円山の夜桜を見に行きました。今年も先月に行きましたが来年からはどうしましょう。
丸太町橋からの桜の春と紅葉の秋の写真です。


丸太町橋から鴨川の春と秋
●(455) 2013年4月1日
「春爛漫」
すっかり暖かくなって京都も一斉に桜が咲き街中が桜で化粧されます。桜が咲くだけで何故か心ウキウキ、楽しい気分になって忙しい合い間にもあちこちウロウロして写真してしまいます。
久しぶりに我が母校に隣接する植物園にも行ってきました。昔は塀越しに無料で入れましたが、今は60歳以上の老人ということでまた無料です。今は代わりましたが前園長が大学同窓生で革新的な改革で来場者数を飛躍的に伸ばしたということですが、この日もたくさんの人が来ています。
このところこのページもズボラして写真ばかりでごまかしています。つまらないことばかり書いているよりいいかもしれませんが。



冷泉通東大路疎水 祇園白川 円山夜の枝垂れ



山科大石神社の枝垂れ 植物園のチューリップと奥の桜林
●(454) 2013年3月25日
「連鶴」
妹がいくつもの鶴をつなげて折る「連鶴」という折り紙をしています。最初に折り紙に切り目を入れておくことが大事ですが一枚の紙から何羽もつながった鶴を折ります。妹はもともと編み物の資格はほとんど持っていたくらい器用でしたが今は折り紙でリハビリと楽しみです。それでも元気な私よりは相当手早くきれいに作ります。





連鶴いろいろ
●(453) 2013年3月18日
「スマホ」
未だに携帯を使っていると周りの若い者からバカにされて先週とうとうスマートフォンに変えました。慣れるまでは大変ですよとは聞かされてはいたのですが、もう永年パソコンをしているので何とかなるだろうと思っていたのが大間違いでした。電話とメールするだけでも一苦労。電話とメールだけなら今までの携帯の方がずっと便利。携帯でもネットにはつながるしパソコンは家でしているわけで、こんなことなら携帯のままでよかったかなと思っています。もう高い物を買ってしまったわけですから少しづつ慣れるしかしょうがないです。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
温かくなりましたが京都の花は、あともう少し。
渉成園(枳殻邸、きこくてい)へ行きました。当然桜はまだですが梅もまだ少し早いです。
今年の「都をどり」では小野小町と深草の少将の百夜通いがテーマになっていて、よく知っている芸妓さんが演じるとか。見にいかなくてはなりません。その小野小町の邸宅跡といわている隨心院へ行きましたが梅の満開まではあと一週間くらいでしょうか。




枳殻邸の傍花閣の梅 隨心院の梅林など
●気まぐれ日記No.30 ●気まぐれ日記No.32へ
●トップページへ ●掲示板へ