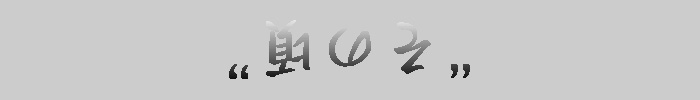結城昌治の引き出し
私が結城昌治の小説と出会ったのは、中学生の終わりごろだから1970年代末期。高校生の頃には、図書館で借りてきては読み漁ったものだ。そして、社会人になってしばらく経った1990年代、書店で売られている結城作品のあまりの少なさに驚き、古本屋を回り始めたのである。しかし、そのときは集めるだけで、読むということはしなかった。手元に置いたことで安心感を得たかったのだ。
そこで今回、集め続けた結城昌治の作品を、30年以上経ってから、もう一度読み直すことにした。しかし、怠け者の私は、脳の退化も激しいようで、活字を読み続ける忍耐力がほとんど失われてしまっている。いつになれば完成するのか分からないし、完成する前に自分の生命が終わってしまうのかもしれない。ならば、それはそれでライフワークとして気長にやっていこう。
そんな気持ちで、1冊ずつゆっくりと読みながら、読み終えたものから記していくことにした。
★の数は、飽くまでも私の個人的な好み。最大が★5個。
(可能な限り、著者の執筆順に上から並べます。私が読む順番は、完全にランダムです。読みたいものから読んでいきます)
結城昌治(1958-60)温情判事

★★★
結城昌治初期の短編6篇を集めたシリーズ第1弾。事実上のデビュー作である「寒中水泳」がそのトップを飾る。
結城昌治と言えば、後のスパイ小説やハードボイルドで、情景描写をことごとく廃したスピーディな会話による進行が文体の特徴になっていったが、この時期にはまだその片鱗は見えない。ふくよかというか、ゆったりとした文章で物語が進む。ただし、「オチ」を大事にする姿勢は最初から変わらない。これらは、もしかすると落語の影響なのかもしれない。また、憧れの女性というような存在が描かれるのも、まだ著者に若さがあったんだということを気付かされる。
「長すぎたお預け」はセクションごとに語り部を変えるという結城昌治得意の手法が既に現れた作品。最初の方で話者だった人物がその後に殺されたり、その時に疑われた人物がその後に話者になったりという計算し尽くされた構成の中で、事件の真相と犯人はやっぱり意外。ただし、その終わり方の捻りの真意はよく分からない。
そしてその続きであるかのように始まる「幽霊はまだ眠れない」は、自分を殺した犯人を捜すという男の話。自分が死んだ理由などを報告書にしないと死者として「事務所」に認められないので、幽霊の状態のまま捜査を続ける。ふざけた設定だが、ストーリー設定は真面目な推理小説。事件の真相にも奥深いものがある。
それから「危険な果実」には「ひげのある男たち」に出てくるのと同じ香月という名前のひげのある探偵が出てくる。作者の気に入っているキャラクターなのだろうか。いずれにせよ、初期の遊び心が見え隠れする作品集だ。
(角川文庫 1981)
結城昌治(1959)ひげのある男たち

★★★★
郷原部長刑事のシリーズ第1弾。
冒頭から「人間のひげはえるものなのか、はやすものなのか」という議論から始まる。この小説は推理小説なので、かなり早い段階で殺人事件が起こるのだが、その現場に駆けつける郷原部長刑事は、鼻と上唇の間に太い真一文字のひげを蓄えている。「ひげは部長のために生えたのではなく、ひげのために部長の顔が要求されたようでもある」などとわけのわからない説明がつく郷原部長刑事が、この物語の主人公だと言っていい。
推理小説なので、犯人の候補者は最初の章で一通り顔をそろえる。その後、郷原部長刑事を取り巻く刑事たちや、私立探偵だと名乗る香月栗介というひげの男によって、さまざまな推理が繰り広げられる。ときどき、その推理の内容が箇条書きで示されたりして、最後は意外な結末となるのだが、そんなことはどうでもいいくらい、話の展開が面白い。
ひげのある男がたくさん関与する中、捜査会議にマスクをかけた謎の男が侵入するなどというのはこっけいな話だが、セキュリティなんて言葉もない時代、そんなことも起きえたのだと思う。
事件がだんだんと解決に近づいてゆく第5章の冒頭で、各容疑者たちを尾行していた刑事たちは、ことごとく尾行を巻かれるのだが、そのスピーディな描写が映像的で面白い。
そして、郷原刑事が浮浪者を取り調べるシーン(P.185)
「その男はどっちへ行った」
「前のほうです」
「当たり前だ。犬だって歩くときは前へ歩く」(中略)
「その男は急いでいたかい」
「それは分かりません。本人によく聞いてみないと」
人を食った会話である。
(講談社文庫 1975)
結城昌治(1960)長い長い眠り

★★★
結城昌治の長編推理小説かつ郷原部長刑事シリーズの第2弾。
明治神宮外苑の絵画館裏の雑木林に、黒縁のロイド眼鏡で鼻下に口ひげをたくわえた紳士の死体が横たわっていた。巡査がそれを見つけた時、下半身はパンツ1枚、さらに交番から同僚を連れてくる間に、革靴もなくなっていた。
死因は薬物で、傍らに薬包紙が落ちていたことから、自殺にも見えるが、わざわざズボンを脱いで自殺するわけはない。自殺に見せかけた他殺だとしたら、ズボンを脱がせた理由が分からない。
そんな滑稽な始まりで、かつ「ひげ」が話のポイントになるのは、ひげの郷原部長刑事シリーズならでは。
推理小説なので、事件の関係者は冒頭で出揃う。野平電気の社長である野平研造の娘のカオル、野平の情婦で小料理屋の榎本胡蝶(こちょう)、野平の4人目の妻である三輪子、野平電気の嘱託眼科医である宮坂朱月(しゅげつ)、家畜病院長の藪下計介、その2階に間借りする新海静子は実は野平電気の電話交換手、そして現場近くで寝泊まりしているバタ屋の神奈川。
これら容疑者の可能性のある人物の間で、郷原ら警察は右往左往する。その警察の面々も相変わらず滑稽な輩ばかり。
鬼頭刑事「悲鳴をあげさせぬためには、猿ぐつわをはめてから、無理に毒薬を飲ませてもいいでしょう」
郷原部長「なるほど。しかし、猿ぐつわのはまった口に、どうやって毒薬を飲ませるのかね」
そして、酒取係長は三輪子を犯人と考え「それでは賭けるか」「いいか、太平軒のカツ丼だぞ」と警察官なのに掛けをする。しかも、そのカツ丼はまずいらしい。
結局、最後はみんなでカツ丼を食べて終るのだが、「そそっかしいために殺された被害者、そそっかしいために捜査を誤った刑事たち、生きている者のそそっかしさは直りそうもない。」という言葉で物語は結ばれる。
(中公文庫 1975)
結城昌治(1961)隠花植物
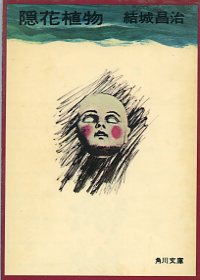
★★★★
ハードボイルド的推理小説。
主人公はスリの小森安吉。山手線の車内で男から財布をすり取った後、その財布を黒い服の女にすりとられ、そのあとを追いかけてゆくが、女と交わした翌日の約束の現場で死体に出くわす。
スリだったはずの主人公は、まるで刑事か探偵のようにその事件の犯人探しに奔走するが、そうしないと自分が犯人扱いされてしまうからだというのがその理由。
そんなあらすじ的な話はともかく、この小説の最大のハイライトは主人公が「アドニス」というゲイバーに足を踏み入れてからだろう。男色という不慣れな場に飛び込んだ主人公の心細さは想像に難くない。そして、そのあとで男色の教授から長々と聞かされる「日本における男色の歴史」のうんちく話は、「ひげのある男たち」の冒頭で作者が披露した「ひげ」のうんちく話にも共通する。それは同時に、この物語の説明をする上で欠くことのできない要素を含んでいる。
教授は続ける。「男性的な型の同性愛者は女性的な美少年を好む(第一の型)。女性的な型の同性愛者は髭の濃い逞しい大人を好む(第二の型)。そして第三の型として、男性を男性として愛するという型がある。第一の型と第二の型が同性愛として結ばれるが、彼らは女性をも愛することができる両刀使いだ。しかし、第三の型は男性しか愛することができない」
ゲイの世界も奥深いものがあるんだ、と思いながらこの小説を読んだ青春時代。
(角川文庫 1977)
結城昌治(1961)仲のいい死体

★★★★★
郷原部長刑事のシリーズ第3弾。
この話の舞台は、山梨県東八代郡にあるという腰掛町。人口は約1万人で、甲州街道の宿場町として発展したものの、今はブドウやモモの果樹園以外見るべき産業はない。そんな腰掛町で、突如温泉が湧き、それをめぐる町民の欲望や駆引きが物語の始まりである。
もちろん、地図をめくっても腰掛町は存在しない。実在する石和町が最も近いのだが、石和町は物語の中でも別に存在し、腰掛町から10kmほど離れた存在になっている。そもそも、物語の最後では、石和町に新温泉が湧き「山梨交通」が保養施設を作るためにボーリングを始めたりする。
そんな腰掛町の名前は、昔町に現れた平宗盛の怨霊を日蓮上人が近くの岩に腰掛けて経文を唱えて追い払ったことに由来する。他にも腰抜け地蔵とか馬恋橋とか、名前にそれらしき由来のあるおかしな地名が出てきて退屈しない。
そんな腰掛町の円命寺で発見された二人の死体から事件は始まる。郷原部長刑事がその殺人事件の真相を解明するのがこの長編推理小説の主題だが、一癖も二癖もある住民たちの人間関係の間を行きつ戻りつする郷原部長刑事は、なかなか真相に辿りつけない。一応、物語の冒頭にきちんと伏線は打ってあり、主題とはほとんど関係ないと思われた保健所長が事件解決のキーマンでもあるのだが、胡散臭い住職や医者などが次々登場するうちに、そんな小さなことは忘れてしまう。
ちなみに私はこの小説を、高校時代にこの舞台のすぐ近くの西八代郡のある町で読んだ。円命寺ではないが、山の斜面にあるお寺の近くで読んだ。この町には温泉は涌いていないようだったが、腰掛町とは逆に町の北側に笛吹川が流れ、いくつもの寺や神社が点在するのどかな町だった。自分自身がこの物語に入り込むには絶好の場所で読ませてもらったことは、偶然ではあるが感謝したい。
(角川文庫 1978 第7版)
結城昌治(1961)死者におくる花束はない

★★★
巻末の解説によると「わが国には珍しいコメディ仕立てのハードボイルド推理小説」。
主人公の佐久は私立探偵で、「わたし」と言う一人称で話が進む。頭は切れるし喧嘩も強いが「フライ級」と紹介されることから、小柄なようだ。私立探偵とはいっても、事務所に所属しているわけではなく、久里十八の探偵事務所で気に入った事件だけを選んでいる。
その久里十八は、背が低くてカボチャのように太っていて若いころから髪の毛が薄い。
久里十八の事務所と机を並べるタイプ会社の経営者であるタイピストの加山春江は「化粧をするとかなり美人」で「足がきれい」なのだが独身主義を通している32〜33歳の女。久里十八はこの加山春江に惚れている。
そしてもう一人、郷原部長刑事も登場する。私立探偵ものには、味方なのか敵なのかよく分からないが刑事は付き物。しかしそれが他の作品では主役を張っている郷原部長刑事なのは驚き。やはり歯ブラシのような口髭をたくわえるが、この時点では四谷署勤務。
そんな面々に囲まれて、依頼された事件だけにとどまらず、危険な世界に足を踏み入れてしまう佐久。でも、最後は納得できず、「今度の事件で殺された奴らに花束なんかおくる必要はない」と腹を立てたまま終わる。
そんな結城昌治らしい終わり方が、なんだか嬉しい。
(講談社文庫 1976)
結城昌治(1962-63)死体置場は空の下

★★★
私立探偵佐久と久里十八のコンビによるユーモア・ハードボイルドの第2弾は、短編が8つ入って1冊になっていた。
話のパターンはシリーズ第1作の「死者におくる花束はない」と同様、佐久が仕事を探して久里十八の探偵事務所に顔を出し、久里十八は自分一人では事件を解決できないので、佐久の助けを借りてしまうというパターン。
第6話「死体置場は空の下」では、夜の神宮外苑で殺されていた若い女に、久里十八は馬乗りになって人工呼吸をしているところを逮捕されてしまう。第7話「オメカケだって楽じゃない」では、依頼主にオメカケを監視するよう頼まれた久里十八が、別の部屋で全裸で体操をする女を見ているうちに、監視すべきだった女が殺されてしまうという大失態をやらかす。
その久里十八が第8話「川を越えた死体」では張り切って自ら調査に出かけ、チンピラを外に連れ出して叩きのめしてしまうのだから、びっくりしてしまう。作者もダメ人間として書いてきた久里十八が好きになってきてしまい、活躍させたくなったのかもしれない。
(講談社文庫 1980)
結城昌治(1961-62)犯行以後
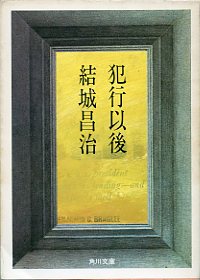
★★★
結城昌治初期の短編6篇を集めたシリーズ第2弾。捻りの効いた短編小説が詰まっているという面では、初期の結城昌治の脂の乗った時期なのだということがよく分かる。
「犯行以後」は浮気の相手を殺した後、見覚えがある男とすれ違ったことから始まる不安を描いた作品。その男はいったい何者で、何を知っているのかという不安は、最期に読者だけが知ることができる。
「死んでから笑え」は言い方は悪いが三流のテレビドラマにありそうなシチュエーション。3人の誘拐犯人が被害者を別荘に監禁し、運悪くそこに飛び込んでしまった人々とのやり取りが描かれる。あとがきに「サスペンス・コメディを目指した」と書かれているので、その感想は間違っていなかったようだ。間抜けな人たちが、間抜けに演じている風景が目に浮かぶようだ。
(角川文庫 1981)
結城昌治(1962)ゴメスの名はゴメス

★★★★★
日本で初めての国際的スパイ小説というのが、この作品の解説としては定番となっている。
第二次大戦後のベトナムが舞台。フランスなどの資本主義国側の支持する政権(後の南ベトナム)とベトミンと呼ばれるベトナム独立同盟(後の北ベトナム)との内戦が繰り広げられる中、そこで行われていた複雑なスパイ活動に巻き込まれた日本人の行動と心理を描く。
物語は、首都サイゴンに就いた主人公・坂本が、同僚で友人の香取を探そうとすることから始まる。題名の「ゴメス」が最初に出てくるのは第1章の終り。自分を尾行している男がいると気付いた坂本が、それを交わそうとした直後、その男が射殺される。死ぬ間際に男が「ゴメスの名は・・・」と言った。
ギア刑事は、狙われたのは坂本ではないかと言う。それから、両隣に住む謎の男、トウとズック、記者クラブの森垣、ラシェルと言う女、など何か裏を持っていそうな人物たちとのかかわりの中、話は段々とサスペンスの度合いを高めてゆく。
作者が得意とするハードボイルド小説の王道でもある、会話だけで綴られる進行により、無駄な修飾語を抜きにしてスピーディに読み進められるのも特徴。主人公の坂本が、敢えて自分自身で謎を解明しようと危険なところに踏み込んでいく感じは、単なる商社マンの行動とは思えないが、ここで坂本がひるんでいては物語は進まないのだからしょうがない。
しかし、こういった非現実を嘘に感じないのは、坂本が常に抱いている心の闇。実は日本で香取の妻と関係を持っていた。そしてそれは、香取の存在があってこその背任行為であって、香取が死んでしまっては成立しないものであった。
(角川文庫 1974 改版初版)
結城昌治(1962)葬式紳士
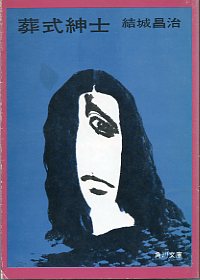
★★★★
落ちのある短編集。ショートショート3篇を含む。
表題作「葬式紳士」は、その題名のインパクトから表題作となったのだろうか。ちょうどモータリゼーションの発達により、交通事故が増加し始めた時代、その風刺を込めたという意味も持つのかもしれない。
「妻よ永遠に」は、結婚した妻の求める愛の強さに辟易している主人公の起こした犯罪。しかし、その後に待っていたはずの幸せは・・・。
「通り魔」は、この短編集の中で最もよくできた作品だと思う。通り魔として逮捕された馬場は、容疑を否認し続け、懲役2年の実刑となるが、これにも不満で不良囚だった。そのため仮出獄にもならず、刑を満期まで勤めて釈放される。ところがその9日後、真犯人だという男が名乗り出てくる。法律に詳しい作者ならではの落ちが、8ヵ月の懲役を勤めた後に待っている。
「替玉計画」は、自分とそっくりな男をアリバイ作りに利用するが、その緻密な計画に対しての過剰な自信から引き起こされる結末に苦笑する。
(角川文庫 1978 第6版)
結城昌治(1963)夜の終る時

★★★
悪徳警官物というジャンルを築いた、と評される長編作品。
2部構成になっており、第一部は聞き込みに出た徳持刑事が死体となって発見され、同僚刑事たちを中心にしてその真相を捜査してゆく推理小説、第二部は悪徳警官の立場から事件を振り返る倒叙形式を用いている。
最初のうち、殺された徳持刑事が情報を流していた悪徳警官であるとの噂が先行するが、安田刑事はそれに疑問を持ち、同僚の刑事たちに徳持刑事を殺した悪徳警官がいるのではないかとの推理をする。
第二部では冒頭から悪徳警官本人による倒叙が始まり、本作の真犯人は当然そこで明かされる。第一部で書かれていた一つ一つの事象がそこでつながることになる。
ちょっと本格的な長編推理には息切れする私は、いわゆるネタばらしである第二部を読むことで、この作品の全体像を再確認することが出来、最後は休憩を入れずに読み切ってしまった。
(中公文庫 1990)
結城昌治(1963)あるフィルムの背景

★★★★
短編集。
表題作「あるフィルムの背景」は、主人公の笹田検事が証拠品閲覧と称して映写されたブルーフィルムの中に、自分の妻とそっくりな女を発見する。笹田は、その中の紙焼き写真を家に持ち帰り、何気なく妻に見せるのだが、その行為は裏目に出る。更に、救いにもならない結末があるのが、結城昌治作品たるゆえん。時代は変わっても、裏ビデオやWeb上の裏画像など同じようなことは、どこかで起きている気がする。
「惨事」はこの文庫(1982年)発行時に2時間ドラマ化されており、帯にその記載がある。夏の花火大会での暴行事件の被害に遭った主人公夏江は、仕事も定時制高校もやめ、東京へ出るが、仕事も恋愛もうまくは行かない。最後に福島県でバスの車掌になるというのは、ちょっと唐突な感じがしたが、この話の結末には、それが必要不可欠。
「蝮の家」は、夫と妻に交互に1人称で語らせるという手法を用いた習作的な作品。ただし、夫の項は途中で放り出された感があり、もう少し丁寧に両者の心理描写を見せてほしかった気がする。
ほかに「孤独なカラス」「老後」「私に触らないで」「みにくいアヒル」「女の檻」の合計8編を収録。
(角川文庫 1982 第18版)
結城昌治(1963-64)影の殺意

★★★★★
巻末の解説によると、1963〜64年に書かれた短編から6編を選りすぐったもの。比較的癖のない作品群で、まず結城昌治に親しんでもらうための入門としても使える、読みやすい短編が多く収められている。
「最後の分別」は「事件はおかしな具合に発生した」という一文から始まる通り、郷原部長刑事シリーズを思い起こされるユーモア推理小説。人物の描写も凝っていて、マッチ箱のレッテルを集める地味な刑事とかキャベツを机の引き出しに入れて絶えずちぎって食べている刑事とかが、関係する人物を当たって捜査を進める。「最後の分別」を欠いたために失敗してしまった犯人の真実とは。
「ある恋の形見」もそのオチからなるほどと思わせる犯罪小説。
「あとは野となれ」は、この時代から流行りはじめた、何の変哲もない一般人がある日犯罪を起こしてしまうというタイプの小説。ただし意味深な題名が必ずしもこのストーリーを的確に表現しているわけではなかった。
表題作の「影の殺意」は「すべての犯罪は、かならず何らかの動機にもとづいて行われる」という一文から始まる。それが何の説明なのかよく分からないまま、浩子という女性が何者かに狙われているという不安を描き続ける。後半の二つ目のセクションでその種明かしとともに、結末になだれ込む。
「あるスパイとの訣別」は結城氏得意のスパイ小説の一つ。他の作品と同様、消えた人物をめぐる物悲しいストーリーが展開され、結末の後味も決してよくはない。小粒だが印象に残る作品。
(角川文庫 1981)
結城昌治(1964)夜は死の匂い

★★★
昭和30年代というのは、民放テレビがスタートした時代で、ラジオや映画から新しいテレビの時代に消費者が移行し始めた初期の頃。さらに1964年の東京オリンピックを境に、カラー放送も始まる。テレビ番組の作り手にとっては、最も華やかだった時代だった。
そんな時代に、女優を志して上京した姉の圭子が妊娠3か月で自殺を図る。妹の裕子は、その真相を知るために自らも女優を志す。
TVプロダクション社長の小久保、ディレクターの有原、ADの矢代、そういったTV現場に関わる男性たちの間で、姉が命を絶った真相に近づいて行く裕子。そして、やりきれない結末が待っている。
もしかすると、TV制作の社会では、今もそんなことがあるのではないかとふと思ってしまう、リアル感のある推理小説。
(集英社文庫 1982)
結城昌治(1965)白昼堂々

★★★★★
実在する万引き集団をヒントにした犯罪小説。執筆連載中に本物の万引き集団が検挙されたというエピソードが作者本人の「あとがき」により明かされている。
北九州の炭鉱を根城にし、炭鉱不況からスリに手を染めたかつての仲間に、デパートでの万引きを勧めるというところから話は始まる。そして、様々な手口で万引きを繰り広げる彼らと、それを捕えようとする刑事たちとの、息詰まる・・・というよりユーモラスな駆け引きが展開される。最初、万引き集団の立場から読んでいるので、捕まらないで逃げおおせることを無意識に望んでしまう。しかし、後半で刑事たちのほうから描かれると、上手に捕まえられないことに失望したりする。それだけ、登場人物たちが活き活きと描かれているのだ。
それは作者も同じ思いのようで、「あとがき」で登場人物たちのその後を親身になって心配している。妙に賢かったり、間抜けだったり、艶っぽかったり、呑気だったり、そんな登場人物たちが、その後も白昼堂々とデパートで万引き稼業を繰り返していたりしてほしい。そんな気持ちになってしまう快作だ。
(角川文庫 1971)
結城昌治(1965)暗い落日

★★★★
元警察官で私立探偵の真木が依頼人の求めに応じて失踪者を探すうち、殺人事件に巻き込まれ、意外で暗い結末に向かってゆくというハードボイルド的ミステリー小説。
巻末の解説によると、結城昌治はロス・マクドナルドの「ウイチャリー家の女」に対する不満からこの小説を書いたとのことだが、外国のみならず日本の推理小説にも馴染みのない私としては、何に対するどういうアンチテーゼなのかはよく分からない。
ただし、田園調布の資産家の社長の豪邸に呼ばれ、失踪した孫娘の捜索を依頼されるという幕開けからして、現実離れした外国風推理小説の始まりを予感した。
失踪した乃里子は19歳。吉井克也という男性と交際していたらしい。その吉井克也も行方が分からない。真木は、克也の父親の情婦が住んでいたアパートに向かうが、そこで後ろから襲われ、意識を失う。何か事件に巻き込まれる予感の始まりだ。そして、この部屋に住む女の死体が発見されることで第1章が終わる。
その後も真木は乃里子の行方を探すが、そうしている間に、今度は吉井の父親も殺される。乃里子が犯人なのか、それとも乃里子はすでに殺されているのか。
乃里子の乗っていた水色のブルーバードは房総半島の崖の下で発見される。「暗い落日」の題名は、真木がその海をみつめながら思う第三章での記述から来たようだ。「海はぐんぐん暮れていく。水平線はもう見えない。雲にさえぎられた落日に、鈍い金色の余映を残していた黒いうねりも、やがて夜の闇に包まれようとしている。(中略)揺れているのは波ではなく、わたしの心だ。暗い。」
事件の真相は、終戦後からの家族の悲劇を背景にしていた。
(角川文庫 1975)
結城昌治(1965-1966)風の報酬
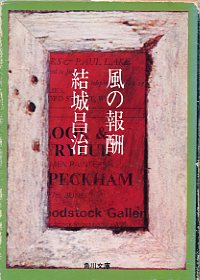
★★★★★
巻末の解説によると、1965〜66年に書かれた短編から6編を選りすぐった文庫とのこと。そこでも書かれている通り、氏が最も脂が乗っていた時の短編作品と言っていい。
表題作の「風の報酬」は氏の得意とするスパイ小説の短編版。題名そのものもそうだが、見知らぬ国での孤独を感じる書き出しに胸が締め付けられる。記者である主人公が殺人の容疑で警察に連行されることから始まるこの話は、内戦が続いているラオスで、政府側と反政府側との複雑な関係の中で、スパイになってしまった人間の悲しみが描かれる。主人公とそれを取り巻く共演者の孤独感が最後まで付きまとう。
そのほかの5篇も、オチやエスプリの効いた秀作で、「六年目の真実」は自分の子供の父親が別人ではないかと疑いを持つユーモア短編、「殺人のためのソナタ」は男女関係の中で周到な殺人を計画実行したにもかかわらず、そこには意外な落とし穴があったという話。「十年の後に」は過去の忌まわしい事実を葬り去るための犯罪を終えた後の危機は救われたが、それを救ったのがその人であって良かったのかという話。「虚ろな眼」は妻に浮気を知られないためのアリバイ証言をいつも頼んでいた友人が殺されたが、その殺人の理由が・・・というオチを持つ犯罪短編。読み飽きることのない組み合わせの短編集。
(角川文庫 1981)
結城昌治(1966)死の報酬

★
私立探偵の佐久と久里十八のコンビの第3作。前作から少し時間を置いているが、内容もコメディタッチが影を潜め、同じ時期に書かれた真木シリーズや五郎高根などを連想させるシリアスなハードボイルドの雰囲気をたたえる。
文庫で370ページ近いという長編なのだが、申し訳ないが、ワンパターンに陥っているような気がして、途中で飽きてしまった。行方不明の女を探してほしいという依頼を受け、その女かも知れない死体が見つかり、佐久は複雑な人間模様の事件に巻き込まれてゆく。
加山春江をクラブに潜入させたり、それを久里十八が心配するというようなシチュエーションも挟まれるが、基本的に佐久が一人で事件を解決し、一人で危険に立ち向かう。せっかくのコンビ物の面白さがなぜか発揮されていないように思えてしまうのだ。
(講談社文庫 1977)
結城昌治(1966-1969)童話の時代
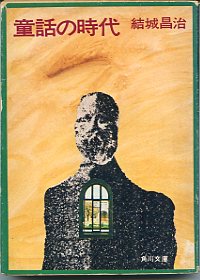
★★★★
短編5編を集めたものだが、「童話の時代」という題名からはあまり想像できない、虚しさを感じるというか、空虚な空間が流れる作品が並ぶ。
「小指のサリー」の舞台はフランス。かつての恋人洋子を訪ねて行った結末は、彼女が「小指のようにかわいい」という理由で「小指のサリー」と呼ばれる娼婦になっていた。そして、再会を果たした時には、精神を病んでおり、記憶さえも失っていた。
「沈む夕日に」も「紺の彼方」も、悲しい運命にもてあそばれた女の結末を描く。秘かな過去の企みが成功裏に終わったという意味では、「紺の彼方」は救いのある結末かも知れない。
そして表題作「童話の時代」は、対中国の諜報活動に誘われた男の結末。そしてその中でブローカーであったスティグラーという男のその後を描く続編として「凍った時間」が続く。
「ゴメスの名はゴメス」で書ききれなかった結城昌治の世界観が展開されているようだ。
(角川文庫 1975)
結城昌治(1967)公園には誰もいない

★★★
私立探偵の真木を主人公にしたシリーズ第2弾。やはり外国の本格推理小説を意識したらしい雰囲気が漂う推理小説。
のっけから有栖川宮記念公園とか南部坂とかいう麻布の地名が出てきて、依頼主は元子爵の外交官と結婚した元映画女優。シャンソン歌手の娘が失踪したので探してほしいという相談だ。なんだか現実離れした設定に見えてしまう。そして真木は娘が軽井沢の別荘にいるのではないかと思い、母親から鍵を借りて軽井沢へ向かう。
ここで娘の死体に出会ったところから、私立探偵として依頼された仕事は終わりになるが、殺人犯人を捜すという新たな局面に移る。ここからハードボイルド小説の面白さが出てくることになる。
真木は推理しながら行動する。怪しい奴らは何人もいるが、真犯人にはなかなか辿りつかない。推理小説としては、当然のことながら、真犯人は唐突に出てくるのではなく、最初からどこかにいる。
「公園には誰もいない」というかっこいい題名は、そのシャンソン歌手が歌った新曲の題名でもある。歌詞の最後にもそのフレーズが歌われる。この歌そのものも、実は事件の本質に関係しているし、またこの物語の最後の場面にも共通するものがある。もしもこの小説を映像化するなら、物悲しげで気怠いシャンソンが常に背景に流れているような気がする。
(講談社文庫 1974)
結城昌治(1967)夜の追跡者

★★★★★
五郎高根という姓と名が逆転したような名前の弁護士を主人公にした長編ハードボイルド。
弁護士であるが、民事訴訟の法廷で相手側の弁護士を罵倒し、弁護士会の懲戒委員会にかけられ1か月間の業務停止を命じられている。ちょうど昨日その停職期間が終わった。
そんな五郎高根は、朝にも夜にも、気付け剤のようにジンを飲む。そして利奈子という肌の白い美しい女の部屋に転がり込んでいる。おまけに強い。そんなかっこいい男が主人公となって、事件を解決してゆく。
事件・・・バーのホステスからツケの取り立てを依頼されたにもかかわらず、その金をホステスに渡さない悪徳取り立て屋。その取り立て屋から金を回収することを頼まれた五郎高根。彼はさっそくその悪徳取り立て屋の死体に出くわすことになる。
内気なジミー、猫背のハリー、みなし児ジョーなど、外国の小説に登場しそうな名前の男たちが次々と現れる。それらと五郎高根との会話は、スピーディーなテンポで進み、場面がどんどんと先に進んでゆく。
最後に事件は解決するが、そこにはそこはかとない虚しさが残される。五郎高根は今度はどんな事件に巻き込まれるんだろうか。そんな期待感を持たせながらも、このキャラクターはこの作品でしか会うことができないのだ。
(角川文庫 1978)
結城昌治(1968-69)炎の終り

★★★
私立探偵の真木を主人公にした「暗い落日」「公園には誰もいない」に続くシリーズ第3弾で最終作。
20年前に映画俳優だった青柳峰子という女性から、娘の由利を探すよう依頼される。由利とは間もなく会うことができるが、峰子から呼び出されて向かったマンションで会った霜川という男が殺される。こういった流れから、依頼者峰子の意思と関係なく、真木はここに何らかの事件性を感じて探偵活動を続けてしまう。
このあたりの流れは前作とよく似ていて、あるアパートの部屋で死体を見つけた直後に、何者かに後頭部を殴られるあたりも既視感がある。
物語の最後で、登場人物の人間関係のキーマンでもある木村順一郎と対峙して、事件の謎が明かされる。真木の一人称「わたし」の目線で語られてきたこの物語の最後に、真木はそんなことに既に気づいて動いていたのかという意外な事実なども明かされる。
男にとってはちょっとやるせない結末。とりあえず今の一読時点では、由利がどういう心情でこの結末を迎えたのかはきちんと理解できていない。
(角川文庫 1975)
結城昌治(1969)春の悲歌

★★★★
これは青春小説とでもいうのだろうか。結城昌治作品に多い事件物、つまりサスペンスでもハードボイルドではないが、そのテイストはある。
この時代、学生運動の最も激しい時期で、デモ隊と機動隊が衝突し、負傷者が出るような事件が東京の各地で起きていた。しかし、この小説の登場人物は、そういうことにはあまり関心がなく、自分の求める芸術を論じることに生きがいを見つけている若者。当時ノンポリとか呼ばれていたのだろうか。
彼らが集まる新宿のサロンである名曲喫茶「風月堂」。ここに現われる美しい女性、冴子(さえこ)をめぐる男たちの様々な感情を、フリーカメラマンの矢代の目から語らせる。
冴子は、美しいがなぜか影のある女性で、被写体としての再会を望む矢代の前には姿を現してくれない謎の女である。しかし、章立ての中で「間奏曲(過去)」と題した真ん中あたりのセクションで、矢代の目を通さない真実が明かされる。
お互いに惹かれ合いながらも、運命に翻弄される(という表現も陳腐だが)男女が、結局は本当の気持ちも確かめ合えないまま散ってゆく。そのラストは、やっぱり何も救われるものはない。
(集英社文庫 1985)
結城昌治(1970)不良少年

★★★
ナイトクラブのボーイの仕事を辞め、盗んだ拳銃を持っている17歳の少年と、家庭裁判所の調査官とを、交互に描きつつ、ストーリーが進む。人を殺すつもりはないけれど、結果的に人を殺してしまう少年。その少年に助けられた少女・栄子。40歳を超えたストリッパーのマギーなどという、心に影をもった人々が、虚ろな言葉を交わしてゆく。
少年なりの正義なのか、栄子の父親に金を貸した悪徳不動産屋に向かい、結局また人を殺してしまう。最後に、調査官との間で電話を通じて言葉を交わすが、もう手遅れだった。栄子も少年と運命を共にする。
結城昌治の書く飾り気のない会話と、救いようのないストーリー進行で、口を挟む隙もなく、物語は終わってしまう。あとがきを見て、これは少年時代の結城昌治とリアルタイムでの結城昌治との心の交流が描かれているのではないかと気づいたりした。
(中公文庫 1974)
結城昌治(1971-72)殺意の軌跡

★★★
1971〜72年に月刊誌に掲載された短編小説を集めた1冊。当時「不倫」という言葉があったのかどうかは分からないが、間違った男女関係から殺意を描き、それを実行するまでの駆け引きを描くような作品が多い。
表題作の「殺意の軌跡」は、ある女の死を関係者からの供述という形で解き明かすという結城昌治の得意そうな手法をとる。続く2作ともに共通することだが、起こる殺人の真相には、想像していたこととは逆の、意外な真実が隠れている。
「七人目」は幼いころから予知能力を持つという女性の話。題名から察して、7人目に何か強烈なオチがあるのだろうということは想像できる。結果その通りなのだが、そのオチは想像とは異なっていた。ちょっとショートショートのようなにおいのする小作品。
(中公文庫 1980)
結城昌治(1971-73)死者たちの夜

★★★★
紺野弁護士を主役にしたシリーズ。紺野弁護士は、7人の弁護士仲間とビルの1室を借りて事務所にしている。独立した事務所を構えられない弁護士たちの集まりで、紺野弁護士も例外ではない。そして乗り古したポンコツ車が移動手段というのも、決してヒーローではない主人公像が現実的。
7つの短編が収められているが、いずれも弁護士の仕事の本筋ではないところから事件が転がり込んでくる。何が起きたのか分からない事件当事者と行動を共にするうちに、事件の輪郭が見えてきて、最後はあまり爽やかでない結末が待っている。
「暗い海辺で」「汚れた月」「風の嗚咽」などの題名は、そんな短編ハードボイルドの最後の場面を言い表している。
そして7つの短編の中で、一番ひねりが聞いているのが「白い猫と男がいた」。話の展開も分かりやすいが、実際の犯人とこの題名には、なるほどと頷いてしまった。
(角川文庫 1977)
結城昌治(1969-79)犯罪者たちの夜

★★★
紺野弁護士を主役にしたシリーズの第2集だが、巻末の解説を読んだら、掲載順は必ずしも発表順ではないという。紺野シリーズの第1作である「夜に追われて」はこちらの第2集に入っている。いずれの作品も、紺野弁護士が7人の仲間と共同でビルの1室を借りていることや、事件を追いかけることは本来の弁護士の仕事ではないことなど、説明が繰り返されているから、どの作品を最初に呼んでも構わない作りにはなっている。
そして最後に作者自身の「あとがき」で、マンネリ化するからこのシリーズは打ち止めと宣言される。
確かにマンネリ傾向のあるシリーズだが、事件を紐解くにつれて、意外な人間関係が明らかになるところなどは、個々の作品での魅力になっている。
私が気に入った作品は「行きずりの女」。紺野弁護士が珍しく女性に好意を抱く描写がある。その相手は出会った夜に殺されてしまうのだが、その真実はちょっと意外な結末だった。
(角川文庫 1980)
結城昌治(1972-85)偽名

★★★★
人生なんて思い通りに事は進まない・・・というようなことが、ここに収められている短編の数々を読むとよく分かる。
表題作の「偽名」は過去に人を殺したため、中学の同級生の名前を使って秘かに暮らしている。実在する人物の偽名を使っていれば安心というわけではないという、この物語のオチは、結城昌治作品らしさを感じる。
「夏の記憶」は護送される男と、その男が戦地から空襲で焼きつくされた東京に帰ってきたときの話とが交互に語られる。「みんなが誰かを探している時代があった」の文章が、結城昌治の経験した戦後の時代を今に伝えてくれる。
「寒い夜明け」と「雪の降る夜」は、それぞれ刑事とやくざの話だが、思い通りにならない、と言うか、思いとは裏腹な人生に向かわざるを得なくなり、最後に命を捨てることになる点では共通している。表題作「偽名」以外の作品は、結城昌治の短編によく見られるあからさまなオチではなく、自身の責任で選ばざるを得なくなった残念な人生のオチ・・・というものを感じてしまう。
(新潮文庫 1989)
結城昌治(1973-82)振られた刑事

★★★
短編集。
昭和40年代後半から昭和50年代にかけてのこの時期、非現実的なトリックを駆使した推理小説ではなく、日常の中ですぐ近くにいる人が、或いは自分が起こすかもしれない犯罪を描くという手法が一般化し、それにも飽きてしまった読者からは、より高度な意外性が求められていた。
しょっぱなの「喪服の仲」は、そんなニーズに応えてくれる作品。不倫(という言葉は当時なかったかもしれないが)をしている男女に訪れた殺人事件。真実が判明するきっかけになった自分の行動は、誰にでもあり得る気持ちから・・・。
「影の侵入者」「諦めない男」など、その他の作品にも、結城昌治らしい結末が用意されている。
(文春文庫 1983)
結城昌治(1975-82)魔性の香り

★★
昭和50年代に書かれた作品を集めた短編集。どれも、それなりの落ちのある小作品。
「草葉の蔭で」は、社長と関係を持つ秘書が、社長の遺産のすべてを相続できるとの遺言状を見せられた後、余計なひと言が結末を変えてしまうという話。
「最後の客」は元刑事、「偽りの構図」は元やくざが巻き込まれる犯罪をめぐるハードボイルド的小説。結城昌治の文体が活きる。
表題作の「魔性の香り」は天地真理主演で映画化されたとのこと。文庫の表紙写真はその一場面だと思う。
(集英社文庫 1985)
結城昌治(1976)汚れた刑事

★★★
自選傑作集。つまり、結城昌治が自分で選んだ作品が入っていて、あとがきも自身で「私の推理小説作法」という文章を書いている。その中で、「ゴメスの名はゴメス」について、推理小説の限界を感じていた時に、スパイ小説なら主人公を勝手に行動させることができるので、書き下ろし作品だからこそできた作品だと述べている。
「視線」(1961)はその題名の理由も含めて最後の2行でネタを明かすという手法。「老後」(1961)はまだ女性の地位が低かった終戦後を描写した作品で、これも最後にオチがあり、意外な結末ではあるのだが、蛇という必然性が理解できなかった。
「死んだ夜明けに」(1967)は、3人の男女が殺されるのだが、その真実が最後に明かされる。短編集の表題作にもなった作品。
そのほかに「葬式紳士」「孤独なカラス」「風の報酬」など、他の短編集でも存在感を主張する作品が詰まった分厚い文庫本だ。
(ゲイブンシャ文庫 1985)
結城昌治(1978)刑事

★★★
書名の通り「刑事」を主人公にした短編集。巻末で解説者が書いているように「連作小説」と言った方が言い得ているのかもしれない。どの作品も、平凡な刑事が主人公だが、その刑事がふとしたきっかけで知り合いのやくざを殺してしまい、犯罪者になってしまうというような経過を描く。そして、隠していた犯罪は、結果的には隠し通すことができずに、自滅の運命をたどることになる。
「夜が崩れた」はそうとは知らずにやくざの妹と付き合っていた刑事が、強盗殺人を犯したその兄を探すというストーリー。結城作品ならではの後味の悪い結末が待っている。
「熱い死角」は妻が知り合いのやくざと歩いている姿を目撃したことから始まる疑惑を描く。この短編集の定石として、刑事はそのやくざを殺してしまうのだが、そのことが発覚した原因はやはり後味がよくない。
「殺意の背景」は結婚するつもりだったバーのホステスが殺され、その疑いをかけられた刑事の話。真犯人は意外な人物でその動機も想定外。
「残酷な夕日」はバーで会った女と関係を持った刑事が、実は罠にはめられ、それが二重三重に罠に発展する。
最期の「乾いた女」は以前に関係を持ったことのある女が先輩刑事の妻になっていたということから始まる。浮気を重ねた末、犯罪者になるのは主役の刑事ではないというのが、この短編集の中ではちょっぴり異色。
これらを含め、収録されている作品は11篇。
(集英社文庫 1978)
結城昌治(1978)遠い旋律

★★★★
結城昌治の作品の中では末期のものと思われる長編推理小説。時期が時期だけに、2時間ドラマのような雰囲気が漂う。
物語の始まりは、比呂子が中絶手術のあとの病院で目を覚ますところ。近くのラジオから覚えのあるギターの音楽が流れており、婚約者の利根はなぜか姿を消している。姿を消した理由は分からない。
比呂子はそれから、利根を探し始める。利根の元同僚の出身地である高知県へ向かう。それには利根の友人の野上という男がなぜか同行するのだが、旅先では利根に会うことはできない。それどころか、比呂子と野上が滞在している最中に、高知県出身の元同僚が殺される。
利根に会えないまま二人は東京に戻るが、そこで第二の殺人が起こる。このあたりで、読者には明らかに誰が怪しいのかが伝わってくる。それが簡単な謎解きなのか、作者がわざと示した罠なのか、それはよく分からない。
ところで、病み上がりの比呂子は、食欲はないようだが、よくコーヒーを飲む。また比呂子自身は食べないが「ハンバーグサンド」がよく出てくる。これは「ハンバーガー」のことだろうか。数多い結城作品の中で、時代がかなり進んだ後なのが、その辺の時代背景で読み取ることができる。
比呂子は常に手の届くところにいそうな利根に、いつまでたっても追いつけない。
殺人犯人はだれなのか。利根はなぜ姿を消したのか。野上は何を思っているのか。後味の悪いエンディングが待っているのは、結城昌治作品の醍醐味であるが、そのストーリー運びにもこの話に限っては2時間ドラマ的な香りを感じるのは、私だけだろうか。
(中公文庫 1982)
結城昌治(1960-1979)泥棒
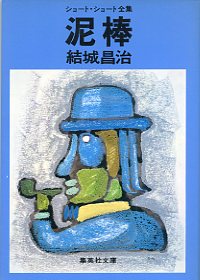
★★★
この題名なので、どうしても短編集「刑事」の次に読みたくなる。ただし、この文庫はショートショート作品を集めたもので、「泥棒」をテーマにしている連作は8篇だけで、残りの30篇のテーマは異なる。
高齢者ネタの「極楽往生」から始まり、しばらく高齢者ネタが続くことに不安を覚えるが、どうやら近いテーマごとにまとめたという編集方法のよう。ショートショートと言えば、SFネタがよく知られるが、結城昌治作品には少なく、唯一「彼の中の他人」がそれ。ふとした日常の変化を題材にした「別の男」も面白い。
そして中盤の前の方で精神疾患を題材にした作品が現われる。「親のかたき」「殺人の方法」などなるほどと思わせるオチではあるが、現在の目から見ると、露骨にこういうテーマ設定をしていいのかという後ろめたさも感じてしまう。
推理作家ならではの「絶対反対」、この文庫の中で最も強烈なオチが待っている「遺産」などはお勧め作品。メインの連作「泥棒」の中では「専門家」が面白い。後半では男女関係ネタの作品が並ぶが、その中では「厄介な病気」のエスプリが利いている。
結城昌治本人による文庫版あとがきによると、1960年から1979年の間に書かれた作品とのこと。
(集英社文庫 1980)
結城昌治(1979)真夜中の男

★★★★
結城昌治のお得意なハードボイルドで、2部構成になっている。第一部は主人公の久保が佳代子を殺した罪で逮捕され、有罪になるまでの経緯。第二部は久保が7年後に釈放され、佳代子を殺した真犯人を探すための行動を描く。ストーリーの主流は第二部なので、2部構成といえども第一部はあっという間に30ページほどで終わってしまう。
第二部は、同じ日に出所した三村との再会を約束した別れから始まり、かつて勤めた探偵社の佐々木、弁護士の東堂、佳代子の弟の小沢隆夫、久保を逮捕した元刑事の鳥山など次々と関係者を訪ねてゆく。佳代子には男の影がつきまとう。矢代という男、病院の院長をしている大熊、元大学教授の鳴海。その最中に、事件の目撃者だった林田という男が殺され、小沢隆夫がその容疑で逮捕される。
物事の進みは速い。そうしているうちに、久保は佳代子を殺した真犯人というより、佳代子という女性そのものの真の姿を、一つ一つ知ってゆくことになる。
真犯人は久保の手で明らかになるし、途中で起きた林田殺人の真犯人も明らかになる。真犯人を突き止める伏線は最初のほうできちんと張ってある。ちょうどこのくらいの時代に、花粉症というようなものが知られ始めたのかもしれない。
物語の最後で、ハードボイルド的真骨頂が現れた描写が続く。久保が小沢隆夫と別れる時に言う言葉。「とにかく生きていれば、また会うこともあるだろう。そしたら、またサヨナラを言うだけさ。たぶんな」 そしてラストで久保の脇を痩せこけた犬が通り過ぎてゆくが、真っ暗な夜の闇の向こうへ消えていく。
(講談社文庫 1981)
結城昌治(1981)逆流

★★★★
ほとんど忘れていた過去の浮気相手から、堕胎したはずの子供が生きていることを告げられ、突然過去が逆流してきたと衝撃を受けることから、この「逆流」という題名が付けられた。これを読んだ高校生のとき、人生の過去が「逆流」してくるという題名に感銘を受けたものだ。
しかし、その後に発刊された文庫には「オフィス・ラブ殺人」という副題が付けられてしまった。確かに副題を見ればこの小説の内容は一目瞭然だ。でも残念なのは、物語の半分まで殺人は起きないのに、この副題のせいで主人公が相手の女性を殺すことは最初から想像できてしまう。
この小説は、小野寺昭と市毛良枝の主演で2時間ドラマになっている。話の展開は、いかにも2時間ドラマ向きな内容かもしれない。ただ、ラストで結城昌治が得意な「落ち」が待っている。これがいいから4点。
(角川文庫 1987)
結城昌治(1983)花ことばは沈黙

★★★
結城昌治にしては(と言うのもどうかとは思うが)読みやすい長編小説。雨宿りのために寄った喫茶店で出会った祐子というスレンダーで冷たい視線の女とわたし(風間)との関係が徐々に深まっていく経過が描かれる。
物語の最後にならないと、事件らしい事件は起こらない。ただし、祐子という女が、何らかの意図をもって接近しているのであろうことは、読者として早いうちに気づいてしまう。その辺が、この時期のよくある推理小説の常道をなぞってしまっている残念な部分かも知れない。だから、80年代に流行していたサスペンスドラマの原作として書かれたかのようにさえ思えてしまうのだ。
ただ、祐子の抱えていた過去は、読者が想像していたようなものとはちょっと違う。そのあたりの伏線があったとすれば、わたし(風間)が二人もの女を囲えるほどのお金持ちで、娘や息子も自分に対して従順だと信じ込んでいる自分本位の中年男だという点だろうか。
(集英社文庫 1987)
結城昌治(1984)終着駅

★★★★
結城昌治がときどき用いる、語り手が章ごとに入れ替わる手法の中では完成版と言ったところか。
「序章 ウニ三のこと」では、終戦後にバラックで暮らすウニ三がどぶにはまって死んだことについて、供述書の形式で書かれる。この物語の登場人物が一通り出てくるが、ウニ三の位牌を誰が引き取るかということがテーマとなっている。
一章は落語のマクラの語りで始まり、サゲで終わる。どうやらウニ三の位牌を引き取ったのは渡辺という男。しかし彼はメチールを飲んで死んでしまう。
二章は女のひとり語りの形を借りて、最後に死んでしまう黒いデメキンと横田という男とを掛け合わせた表現になっている。
三章は結核で入院中の野村という男から妻の千代子への一方的な手紙という形をとる。野村の強い想いとは裏腹に、千代子は見舞いにも来ないし手紙の返事も来ない。この物語に出てくる女は、みんな同じように男に冷たい。章の最後は野村の死を告げる電報で終わる。
四章は熊切という男の独り言。終戦後から5年経っており、朝鮮戦争が始まる頃。これまで死んできた4人の男の位牌は熊切が預かっている。そして彼らの死について語りながら、最後には女(民子)が自ら命を絶つ。
「終章 風景」はいきなり終戦から37年後、つまりこの小説が書かれた昭和58年まで時が飛ぶ。序章で出てきた山尾という男はまだ生きている。ウニ三の女房だったイナ子は画家になって生きていた。しかし、その帰り道、山尾は終着駅で電車を降りた後、不思議な世界に迷い込む。いきなり宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」のような世界観が展開する。ウニ三はなぜか犬になっている。
この作品はもしかすると、結城昌治自身の人生が描かれているのではないかと感じる。終戦後に肺結核にかかったり、落語を愛したり、多分知り合いにも死なれたり、もしかすると多くの女につれなくされたり、そうして最後に自分が死んでゆく様を描きたかったのではないか、そんな気がする。
(中公文庫 1987)
結城昌治(1988)エリ子、十六歳の夏

★★
題名からして、結城昌治の作品にしてはちょっと新しい印象を抱く。
夏休みに突然家出した高校生の孫娘エリ子を探す60代後半の田代を主人公に、そのエリ子を取り巻く同世代の女の子たちとの掛け合いで話は進む。
“おじいちゃん”と“若い娘”というコンビのハードボイルドという不思議な雰囲気の作品だが、実際にそういう世代差がしっかり描かれているのかというと、ちょっと物足りない気がする。
同棲する暴走族のチンピラが交通事故で死んで以来、自分を「未亡人」と名乗る15歳の少女とか、自分のことを「オレ」と呼ぶラッキーと名乗る少女とか、それぞれに個性はあるようだが。
考えてみれば、1927年生まれの結城昌治は、この作品を書いていた頃、ちょうど60歳くらい。主人公の田代は、著者自身の生き写しなのかもしれない。
しかし、そんなおじいちゃんと、ハードボイルド的な言葉のキャッチボールを、10代の少女たちがよどみなく応えてくれるかどうかは疑問も残る。
(新潮文庫 1992)
結城昌治(1990)修羅の匂い

★★★★
東京都内の場末のビルに調査事務所を持つ流木(ながれぎ)を主人公にした5編の連作小説。同じビルの3階の大横弁護士事務所や隣りの結婚相談所などから回ってくる仕事を受けながら、報酬の何割かは彼らに持ってかれてしまう立ち位置にある。その依頼内容は浮気の調査であったり離婚の相談であったりする。
流木がいいのは、スーパーマンではなく、ちょっと動きが鈍いところ。もっと違う動きをしていれば、関係者が死んだりしなかったかも知れない。そんな後味の悪さも残しつつ、また次の事件が起こる。30分くらいのテレビドラマで、ちょっと冴えないコメディアン出身の俳優が演じたりすれば、面白いんじゃないかと思ったりする。
ただ、下請けの探偵業は佐久を連想するし、ジンが好きな所は五郎高根を連想するし、後味が悪い終わり方は真木を連想する。どのシリーズの続編にしたとしても、成り立つような気がするけれど、なぜか身近に感じる流木という男は流木という男以外誰でもないのかもしれない。
(文春文庫 1993)
結城昌治(1991)指揮者
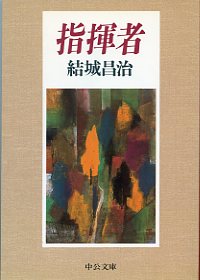
★★
結城昌治末期の短編集。「葬式紳士」と似て、落ちのある作品が多く、また最後のほうにはショートショート3篇が含まれる。
表題作「指揮者」(1989)は、オーケストラの演奏家たちは果たして指揮者を見ているんだろうかという誰しもが思うことを指揮者の立場から描いた短編。エンディングは確かに予想した通りになる。続く「エンドレス」(1989)「ミステーク」(1991)もオーケストラを題材にしているので、連作かと思いきや、特に関係はないらしい。ただしこの時期の作品は、落ちがちょっと分かりにくい。
「喪中につき」(1975)はこの短編の中では古い作品だが、やはりこの頃の結城昌治のほうが冴えている気がする。謎解きの雰囲気を漂わせつつ、なるほどと思わせつつ、最後の落ちに至る。葛原の娘が誰に似ているのかという軽いジョークのようなネタが笑わせる。
ショートショートのうちの一つ「電話魔泥棒」(1983)もユーモアのある作品の一つだろう。
ほかに「切符」「血統」「約束」「1時間後」「某月某日 晴」。
(中公文庫 1994)