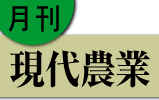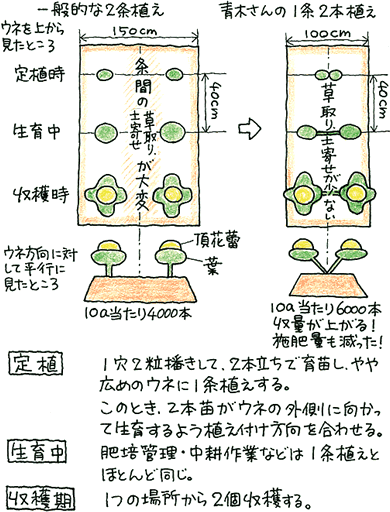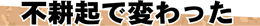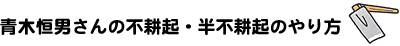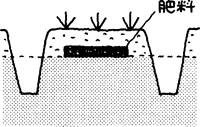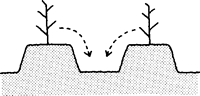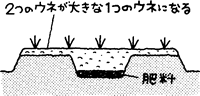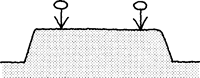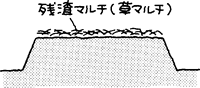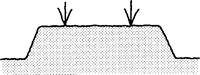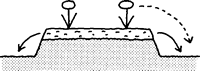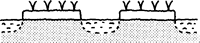密植する作物は半不耕起で定植をラクに
では、私が行なっている栽培法を、ハウス中心に紹介したいと思います(上図参照)。私のハウス利用のサイクルは、冬の切り花ストックと、春夏のシシトウ・スイートコーン・ナスなどの半促成・雨よけ栽培の組み合わせが基本となり、一部に水稲の育苗が加わります。
夏作から冬作(ストック)に切り替え時のおもな作業パターンに、平地(水稲育苗の跡地や夏にスイカ・カボチャなどを作った圃場)にウネを立てる場合(図A)と、前作物やウネがある場合(図B)があります。ストックや葉物野菜など密植する作物は、まったくの不耕起では定植の穴掘りが大変なので、このA・Bのような半不耕起の方法なのです。
 |
| パターンCの畑。ウネは不耕起のまま次作を植えるので、採花中のストックと冬草、次作のシシトウが同居することもある |
 |
| パターンD。水稲育苗の作業場として使用したハウスの、運動場のように硬く締まった場所にトマトを定植。手作業は無理なので、シャベルでポットと同じ形の穴を掘り、苗を穴に差し込んでかん水しておいた |
 |
| 定植後15日目。敷きワラ代わりと追肥を兼ねて、全面に牛糞堆肥マルチして乾燥防止。地温の上昇を防ぐ |
 |
ウネは不耕起層をなるべく損なわないよう注意しながら、最終的にウネ表面の耕起層が5〜10cmの深さになるように仕上げます。元肥はゼロ、追肥は尿素・硝酸カリを水に溶いて液肥をつくり、手かん水で与えます(詳しい施肥の仕方は206ページ参照)。
なお、A・Bパターンともに、ウネづくりの作業を定植10日以上前に終わらせ、十分なかん水をしておくと、一週間後には雑草が生え揃います。この雑草を除草剤で枯らすか、三角ガマで削り落としてすぐに播種・定植すれば、その後冬の間の雑草はほとんど生えません。冬作物は極端に密植するので、邪魔になる草マルチはできないし、作物定植後の除草もほとんど不可能なので、定植までの間に生えきらせて完全に除草しておくのです。
密植しない果菜類は完全不耕起で
▼ウネを踏み固めてさらに水はけをよく
図C、Dは冬作から夏作への切り替え時のおもな作業パターンです。夏作は基本的に植栽本数の少ない果菜類が主力で、定植に手間がかからないので、完全不耕起でスタートします。
やり方は図のとおりですが、Cの場合は夏に向けてウネを固めるため、作業時には通路を避けてウネの上を歩き回るようにします。踏み固めたウネのほうが地下水が地表面まで上がってきやすくなり、水分が安定して、夏場、頻繁に水やりしなくてよくなるからです。いっぽう、歩かない通路は排水用の溝として使います。
▼元肥ゼロ、追肥は液肥を手かん水で
施肥は冬作と同様、元肥ゼロスタート。追肥は尿素・硫酸カリを水で溶いて液肥をつくり、手かん水で与えます。作の切り替えに伴う作業がとくにないので、前作物の収穫が終了しだい、徐々に後作に切り替えることができ、省力的で効率的です。
▼雑草マルチで地温低下、乾燥防止
雑草は、株回りに生えてきたものだけを手取り除草し、残りは邪魔になると草刈り機で刈り倒してマルチの追加にします。多少の雑草は、ウネ上面の地温を下げ、乾燥防止に役立つので放置してOKです。
露地畑も、もちろん不耕起
5年間ほど耕作を放棄していた畑を、ウメ・カキ・ミカン等の家庭用果樹園にしました。まだ樹が小さく空間が大きく空いていて、草だけを生やしておくのはもったいないので、カボチャとスイカも植えました。不耕起のスイカは、耕した畑のスイカが枯れてしまった後も元気に成り続けました。この後、ツルや葉は果樹のためのマルチとなり、土に還っていきます。
私のところのような重粘土地帯では、ダイコンやゴボウなどの根菜類・イモ類のように地中で作られる野菜だけは不耕起に向きませんが、その他の野菜はほとんどが不耕起を嫌わないと思います。皆さんの土地ではどうでしょう? 皆さんも自分の畑と自分のやり方に合わせた「不耕起栽培」に挑戦してみてください。
(三重県松阪市)
*私のイネ・花・野菜の作付け記録は、わが家のホームページで紹介しています。この記事の詳細や質問などについてもお答えできると思いますのでぜひお越しください。