親のしごと 教師のしごと――賢治の学校の挑戦、鳥山敏子、法蔵館、2000
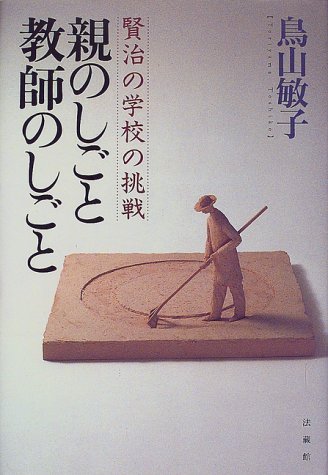
いつも読んでいる書評で見つけた引用文に惹かれた。
(人生におけるつらい体験は)どんなにその人にとって受け入れがたく、つらく、苦しいものであっても、その人の魂はそれに取り組む力を内包している。それに取り組むことこそが、その人の人生の道の仕事。その仕事あってのその人なのだ。それに取り組んでいく過程すべてが道であり、それによって自分を表現し、生活し、文化をつくり天と地とつながり、自分の精神、魂を自由にしていくことを可能にしていく。
手にとってみると、はじめは読み進めるのが辛かった。その原因は私のなかにある異常なほどの教員アレルギーにある。その職業に師をつけて呼べないほど、嫌悪しているため。加えて職業的な読書法を中途半端に身につけたため、読みながら著者に議論をしかける奇妙な癖がある。そのため、冷静な論文調のほうが、本書のような体験的で実践的な文章より、なじみやすく好む傾向がある。
余談。そのため私の文章は中途半端な論文調になっていて、なかなか自分では好きになれない。
人との付き合い方も相手によって変えたほうがいいこともあるように、本との付き合い方も、相手によって変えたほうがいいときもある。理論に合わせてではなく、現実に合わせて行動を変えていく鳥山のような実践家の本は、議論をしながら読まないほうがいいのかもしれない。そう気づいて読み進めると、引用したような文章もすんなり流れ込んでくる。著者には失礼かもしれないが、私には「世話好きの人の話」として読むくらいがちょうどよかった。
家庭での教育、つまり親子関係を鳥山は重視する。親の教育だけが親を越える存在へ子どもを導いていくことができるから。そのためにまず親子の関係を絶対化させる。絶対化を推し進めることによって、最終的にその関係を相対化させることができると考えている。
絶対的な関係がそこで終わらないのは、親は自己の存在を子に対し絶対化するのではなく、親自身が個として成長し、子を相対化していくことを学べるから。鳥山の戦略は単純にすると、このように理解できる。要するに教えるとは、一方的に育てることではなく、共に育つこと。
そのような教育ができる場は家庭であるというとき、実は積極的な理由とともに消極的な理由もあることを認めないわけにはいかない。核家族、壁に仕切られた狭小住宅、産業社会の進展による地域社会の没落、教員のサラリーマン化、偏差値などに象徴される学校教育の世俗化、技術化。
こうした問題に囲まれたとき、家庭は子どもにとって最後の砦あると同時に、最初の、つまりもっとも身近な抑圧装置として働くことは想像に難くない。家庭に重圧と期待がかかり過ぎている。
かつて親たちは全体が高度成長するために家庭の外へと働きにでた。そこで、しつけと言われる基本動作までを含め、て教育の多くの部分を学校に依存した。その結果、子どもはおかしくなっている。
では、子どもが帰るべき家庭はどうか。親たちは会社で疲れ、家庭は団欒ではなく閉塞した場となり、やはりおかしくなっている。鳥山がいくつもの事例から説き明かすように、今では家庭の問題が社会の問題を生み出し、親の問題が子の問題を作り出し、社会の問題が家庭へ、子の問題が親へ逆流するという悪循環に陥っている。
このような悪循環を、家庭の復権でもなく学校の改革でもなく、家庭と学校をつなぐ新たな場を設けることによって断ち切ろうという試みは画期的。その意味で学校週休二日制に私は賛成する。教員も休日が増えれば体力も熱意も再生できるかもしれない。何より子どもたちにとって土曜日は学校や家庭を相対的に視る力を養ういい機会になるだろう。
その場合、鳥山が主宰する場のように親や教員が一緒に参加する必要はない。むしろ親も教員もいない新しい場こそ、子どもたちには有益ではないだろうか。親という権威もいなければ、教員という権力もいない場で大人や子どもと接することで、学校とは異なる人間関係を自力で作り出すことが可能になる。
こうした機会は、自治体、なかでも学校に対して補助的な地位しか与えられていなかった児童館や図書館、保健・介護などの施設も積極的な学びの場に変えていくかもしれない。
ただし、楽観的にばかりはなれない。土曜日の活用には経済的な格差が大きな影響を及ぼすと考えられる。余裕のある家庭ならば、学校とは違う体験や新たな人間関係を創る場にもより積極的に参加できるだろう。
推測するに、これから裕福な階層を狙った子ども向けのカルチャースクールのような業種が現れるのではないか。専門家と博物館や遺跡を見る文字通りの修学旅行や、たとえば陶芸や登山といった特殊な趣味や、運動の本格的な体験などを提供する業者。海外体験の有無はすでに大きな格差となっている。
貧富の差はいつの時代にもあった。また経済的に裕福なことが即、幸福を意味するわけではない。しかし、革命や暴動は我慢できない貧富の格差が社会に充満したときに暴発してきたことも歴史をみれば明らか。とくに富裕層は富裕である身を守るためにもっと有効な策は、貧しい者をなくすことだと知らなければならない。
ところで、本書を私の関心にひきつけると、全文を通して親を国民国家に子を国民として読み替えると非常に含意豊かなナショナリズム論になる。私の理解では、国民国家の原初的な理念を創りだした、いわゆる啓蒙思想家、なかでもジャン=ジャック・ルソーの政治思想は国家を学校として、ナショナリズムを教育理念としてとらえている。
ルソーにおいて、国民は国家において自由であること、民主的であることを強制される。つまり国民にとって国家は親のように絶対的な存在。ただし、国民は学校としての共和制国家を通じて、自分を育てた国家を相対化する力を身につけることができる。このような私のルソー理解は、鳥山の親子関係の理解に共通するところがある。
ところが思想上はともかく、国家は現実には絶対的な存在のまま国民をしばりつけ、抑圧、差別、戦争など多くの問題を引き起こしてきたことは歴史が語っている通り。こうした状況において、鳥山が親子関係について提案しているように、学校でも家庭でもない新たな場を設けることは、国家の相対化にも寄与するところがあるに違いない。国際社会におけるNGOや、地域社会におけるNPOの活動など、すでに実例は少なくない。
親子の関係と国家と国民の関係では共通しない点もある。一方は人間どうしの関係で、他方は制度と人間との関係であるという点。
鳥山は親が変わる、親が育つことによって、子どもも変わる、子どもも育つと考えている。この考え方は国家と国民の関係にはあてはまらない。制度は人間がつくるものだから、まず人間、すなわち国民が国家を相対化させる努力をしなければ、国家は変わらない。
読み替えが過ぎたかもしれない。本書へ話題を戻す。本書はキャンプ場で食べるカレーライスのよう。大味ではあるけれど、確かに美味い。
鍋の中をよく見てみると、宮沢賢治、シュタイナー、過剰なほどの親仏教と反キリスト教、やや性急な身体論、出産や血縁に対する過度の意味づけなど、言ってみれば下味の濃い具や骨付きの肉もころがっていて、すぐには呑み込めそうにないところもある。
それでも気持ちよく終わりまで読み進めることができるのは、悩みながらもつねに努力し、実践していることが率直に表現されているからだろう。例えば次のような一文にも実践者らしい前向きな姿勢が感じられる。
一人ひとりが、どうすれば自分が生きていることをリアルに感じる感覚をもつことができるか、それぞれのからだで探らずには生きられなくなっている社会が出現してきたとすれば、それはまた大きな希望であります。
あれだけ多くの悲惨な事例を目の当たりにしながらも、なお、絶望的な状況を直視し、にもかかわらず希望を見出す姿勢には、学ぶところが少なくない。
uto_midoriXyahoo.co.jp