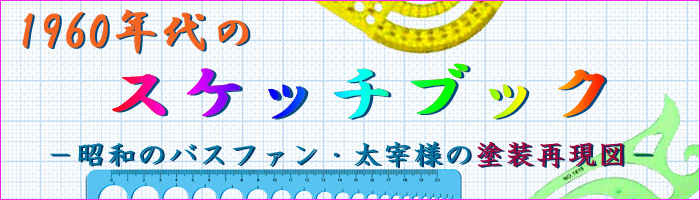
東北地方(南東北)
昭和のバスファン・太宰様が東北の地に足を踏み入れ、新たな生活を始めたのは大学時代。バスが発達していた西日本と比較して、東北地方のバスの実態には大きなショックを受けたそうです。そして、猛烈な勢いでバス描画に対峙したのがこの地であったそうです。
福島県
福島交通
三菱 MAR471(呉羽自工)

作画:昭和のバスファン・太宰様
1961年に福島電気鉄道と福島県南交通が合併して福島交通が誕生しました。太宰様が「磐梯吾妻スカイラインをイメージさせる空と流れ雲模様」と表現するこのカラーは、福島電気鉄道のカラーで、合併後もしばらく使われていました。
会津乗合自動車
日野 RB10(富士重工)

作画:昭和のバスファン・太宰様
常磐交通自動車
日野 RB10P(金沢産業)

作画:昭和のバスファン・太宰様
福島県では「浜通り」と呼ばれる太平洋岸の地域をエリアとするのが常磐交通。これは路線バスの旧塗装で、ワンマンカーになると窓下帯の白い部分が黄色く塗られてしまいますが、この時点ではシックなデザインに見えます。
日野 RB10P(金沢産業)

作画:昭和のバスファン・太宰様
かっての常磐炭鉱の閉山後、新エネルギー原子力発電シフトに対応した町にスパハワイアンセンターを開設し、町あげて地域振興実施。これに同調したバス運行会社もデザイン改革への強い意思で最新のデザインを採用し、東京まで運行させ都民の目を見張らせている。一番先端的なデザインである。(太宰様談)
山形県
山形交通
日野 RB10P(金沢産業)

作画:昭和のバスファン・太宰様
蔵王を主に観光路線運用と仙台までの急行路線有し、塗装はサクランボを連想する赤と桃色主体で視認性が高く、見映えも良好である。(太宰様談)
庄内交通
日産デ 4RFA92(富士重工)

作画:昭和のバスファン・太宰様
山交とは真逆に黄色の濃淡組合せで注意を引くには充分であるが、好みが分かれる塗装か。(太宰様談)
宮城県
陸前乗合自動車
いすゞ BR20(川崎航空機)

作画:昭和のバスファン・太宰様
陸前バスは戦時統合により古川地区のバス事業者が合併して成立した会社です。栗原電鉄とは同じ地域でバス事業のやりとりもあり、結果的に1964年に合併して宮城中央交通となります。
宮城中央交通
いすゞ BR20(富士重工)

作画:昭和のバスファン・太宰様
栗原電鉄のカラーで、側面にはウサギのマークがあります。1964年に合併して宮城中央交通となった後の姿。
太宰様が仙台在住中に、このような合併という変化があったのです。
いすゞ BR20(富士重工)

作画:昭和のバスファン・太宰様
宮城中央交通の新カラー。色使いや前面は陸前乗合を引き継いでいますが、側面は近鉄風の流雲形塗り分けに変わりました。このような経緯でカラーリングが変わってゆくという実例です。
宮城中央交通は1968年には鉄道を分社して宮城中央バスとなり、1970年には宮城交通に統合されます。
宮城バス
日野 RB10P(帝国自工)

作画:昭和のバスファン・太宰様
宮城バスは、栗原地区で軽便鉄道を運行していた仙北鉄道の傘下となっていたバス会社3社(仙台鉄道、古川交通、塩竈交通)が1962年に合併して成立した会社で、1964年にはさらに親会社の仙北鉄道に合併し、宮城バス(新)となっています。
1970年に成立した宮城交通の前身3社のうちの一つです。
仙南交通
民生 RFA91(富士重工)

作画:昭和のバスファン・太宰様
仙南地区の仙南交通自動車と秋保電気鉄道が1959年に合併して成立したのが仙南交通で、他社の例に漏れず、間もなく鉄道を廃止してバス専業となっています。
クリーム色と水色と白というのは、薄色同士の組み合わせで、太宰様によると「視認性は低かった」とのこと。
やはり宮城交通の前身3社のうちの一つ。
仙台市交通局
三菱 MAR475(呉羽自工)

作画:昭和のバスファン・太宰様
初めて仙台に行った時のバスのイメージは広島に比べ旧式でキャブオーバー車も多く短い車体が主であった。観光運用は塩釜・松島と仙台城址主体で、車両数も少なかった。
在仙中の近代化は著しく長尺車導入やワンマン化が一気に実施され近代化された。(太宰様談)
三菱 MR475(呉羽自工)

作画:昭和のバスファン・太宰様
仙台市営バスの貸切バス。車体裾が茶色です。
いすゞ BR10(富士重工)

作画:昭和のバスファン・太宰様
仙台市営バスのワンマンカー。窓下帯がオレンジ色です。
前後ドアの初期ワンマンカー。後ドア前に車掌台があるので、ツーマン・ワンマン共用車です。
