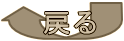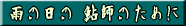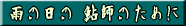鱒二、鮎釣りを佐藤垢石に教わる
井伏鱒二の『釣師と釣場』の一編「水郷通いの釣師」のなかで、千葉県佐原付近の水郷の寒鮒釣りの名人真野源一さんとの対談に、源一さんが昭和3年、鱒二が昭和6、7年頃に垢石から鮎釣りを教わったときの様子が書かれている。
水郷通いの釣師
・・・・・・・・・・(中略)・・・・・・・・
「佐藤垢石を御存知ですか。最初、私は鮎釣りを垢石老に教わりました。」
と源一さんが云った。
鮎釣りは私も初め垢石に教わった。源一さんが教わったのは三十年前だそうだから、私の方が三年か四年か後輩の弟子ということになる。
私は垢石に教わるとき、囮を粗末にして、ひどく叱られた話をした。源一さんも囮を茶化して垢石に叱られた話をした。越後の魚野川で教わったときのことだそうだ。
鮎の囮を激流に沈めるには道糸を相当に長くする。ところが道糸を長くすると、竿を立てても糸が張らないので囮が沖に出て行かない。私も最初のうちはそれに頭を悩ませた。ふと思いついたのは、囮を浅瀬に入れておいて、自分が三歩か四歩か川上に行ってから竿を立てたらどうかということであった。これなら足場さえ悪くなければ通用する方法である。
源一さんも初め魚野川では囮の操作に手こずった。釣宿に帰ってからいろいろ考えた末、その翌日は風呂場の焚口にあった渋団扇を持って川へ行き、沖へ出て行かない鮎をその団扇で煽ぎたてた。囮はみるみる沖に出て行った。すると垢石が遠くのほうからそれを見て、わざわざ叱りにやって来た。
「お前、さっき妙な真似をしていたな。その腰に差しているのは、いったい何だ。」
「団扇だ。暑いからね。」
垢石はたいへん怒ったそうである。
そのときの垢石の激昂ぶりには私にもほぼ想像がつく。たいていの釣師がそうであるように垢石も濁声だが、人を叱るときには特に異色ある濁声を張りあげていた。囮を粗末にすることを何よりも禁忌として、川底に引っかかった囮を一かばちかぐっと引抜くことを厳禁した。私が富士川の十島で初めて垢石に教わったとき、囮を川底に引っかけると、垢石が私に厳命した。
「俺が竿を持っててやるから、川のなかにもぐって囮を外して来い。これは友釣の原則だ。」
当時、まだ十島にはその上流にダムが出来ていなかったので、川の流れが相当に激しかった。富士川や木曽川なども、遠くから汽車で見ると何でもない川のように見えている。ところが、川っぷちに立って見ると案外そうではない。向岸に渡るために浅瀬を辿って行くときでも、足もとの砂が水で激されて掘れるので、リュクサックに大きな石を入れて重しにしなくては足を掬われて流される。
垢石は私が尻込をすると、
「お前は、水というものを知らなくっちゃいけねえ。抱けるだけの大きな石を抱いてもぐるんだ。」
と睨みをきかせた。
私は止むなくパンツ一つになって、抱けるだけの大きな石を抱いて流れのなかにもぐった。囮を外して川から出ると、私の腕時計は硝子が毀れダイヤルが毀れて用をなさないことになっていた。当時、腕時計は紐を外に、時計を内側にする風習が一部にあったので、私もそれに従っていた。
「しかし垢石翁は、鮎を釣るときには、姿も技術も心境も見事でしたね。」
私がそう云うと、
「ほんと、きたない釣服を着てましたが、川へ行くと実に立派でしたね。」
と源一さんが云った。
鮎を釣って囮をつけかえるときの垢石は、いつも釣竿をまっすぐに立てていた。軽妙に囮を扱っていた。五間の竿を片手で軽々とあげていた。囮箱を持って身軽に山裾の小道を歩いていた。
垢石は東京にいるときには飲んだくれていたが、川へ行くとがらりと人が変ったように謹直になっていた。宿に着くと節酒して早く寝た。朝は、私のまだ寝ている間に、川のコンディションを調べて来て、それから私と一緒に朝飯を食べた。初めての土地へ行くと、その土地の釣師に宿へ来てもらって、川の様子や特徴を根ほり葉ほり聞いていた。どういうものか私は、世間の釣師の云うような垢石のデカダンぶりは、旅先では一度も見たことがない。今でも私は垢石のことを立派な釣師であったと思っている。
自分が友釣を始めた昭和四十年代でも、手尻は一尋ほどとるのが普通で、はじめのうちは囮鮎を送り出すのに難渋した。掛かった鮎は竿でタメ、道糸を手繰ってタモに落とし込んだ。友竿の長さは四間前後がほとんどだった。
昭和初めの五間の竿といえば7~800グラム位の重さがあったと想像され、それを垢石は片手で軽々と扱っていたというのだから尋常の釣師ではない。友釣中興の祖といわれたのもうなずける。
さて、初めての友釣で、鱒二が石を抱いて流れにもぐり根ガカリを外した時の様子を、彼に友釣を教えたほうの垢石は「つり姿」(昭和17年発行)のなかの一編、「釣姿漫筆」のなかで次のように書いている。
釣姿漫筆
・・・・・・・・・・(中略)・・・・・・・・
私の釣友の一人である小説家の井伏鱒二の釣姿は、まことに悠々迫らぬ趣を持ってゐる。静かにそしてゆるやかに、釣趣を耽味するといふ風だ。
鱒二の文章には、鱒二の人柄がよくでてゐる。誰の文章でも、個性は失はぬものだが、鱒二の文章を讀むと、鱒二が飄々と野路を歩いてゐるのに、逢うような想ひがする。釣りも同じで、その人々によって姿とか振舞とかに異なったところのあるものであるけれども、鱒二の釣場に在る持味といふのは、寒山拾得の匂ひがある。全く、枯れきってゐる。
だからと言って、鱒二は不満に思ふかも知れないが、鱒二の釣は永年の經驗を持つものではない。しかしながら、鱒二に竿を持たせて水邉に立てると、その釣姿が板についてゐる。まことに、妙なことであると思ふ。
實をいふと、鱒二は私の釣弟子なのである。四五年前、甲州の富士川の十島河原へ伴って行って、鮎の友釣の手ほどきをしたことがある。そのときは、八月の末か九月のはじめで、鮎は肥育の絶頂に達して、七八寸の長さで四五十匁。まれには、六七十匁の大ものが掛かってくる季節であった。
鈎の結び具合から、囮鮎の鼻の穴へ鼻鐶を通す次第。竿捌きのあんばい、囮鮎を水底へ巧に泳がせる方法など、私が細やかに實演してみせると、鱒二は直ぐ會得してしまったらしい。やがて、鱒二は自ら竿をとって、私が敎へた通りにやりはじめた。見ると、からだのこなしや、竿の持ち方まで、はじめて友釣を試みる釣人とは思へぬほどである。静かに竿を上流へ引きあげて行くうちに掛かった。彼は、苦心に苦心を重ねて掛かった鮎を、汀へ引寄せそれを手網で掬ひとった。
それがなんと五十匁もある大鮎ではないか。沈着の彼でも、さすがに胸の動悸を抑へきれぬといふ態である。囮鮎をとりかへてから、さらにそれを急流のなかへ泳がせて行ったところが、少し錘が重過ぎたためか、綸が水底の岩に噛まれて、上がってこない。このまま綸を切ってしまへば、囮鮎を失ってしまふことになる。
そこで、私が言った。鮎の友釣には、囮鮎を大切にすることが、作法である。だから、ここで綸を切ってはならぬのだ。この激流のなかへ飛び込み、潜り込んで綸を岩からはずし、囮鮎を取ってくるのがよい。しかし、この奔湍の底へ潜ぐり込むのは、大抵の業ではない。それには、一貫目程度の石を左の腕に抱へ、頭を下にして潜り込めば、容易に水底に達する。これは、なかなか恐ろしいことだが、貴公にやれるかと問ふたところ、師匠の敎へとあらば、敢然としてやると言ふのだ。
つひに、彼は決心したらしい。裸になり石を抱へ、ざんぶと流水のなかへ飛込み、水底へ潜り込んで、囮鮎を取ってきた。それで、安心した。が、水へ入るとき腕から時計をはづして置くのを忘れたため、彼が大枚を投じて求めた腕時計は、水底の石に當ってめちゃめちゃに壊れてゐた。向かふ脛からも肉が破れて、鮮血が流れてゐた。
途方もないことを敎へたものだ。と、私は悔いた。けれども、鱒二の勇気と、釣りの作法に忠實なるには驚いた。貴公は、將來一かどの釣人になれるであらう。と、言って大いに劬つたものだ。
それから、また釣りはじめた。彼は自分の釣場を守り、釣場の個性を味ふやうに、一二町の間を上下して、決して私等の釣場の方へ色目など使ふ風は無かったのである。釣には、嫉妬心を最も禁物とする。他の釣人が、いかに數多く釣らうと、それをねたむ心が起こってはならぬ。自分は自分で、自分の釣場を研究し、親しんでそこで釣らねばならない。と、いふ道理があるのである。鱒二は、いつの間にか、この道理を心に解してゐたと見える。
脇目もふらず虚心の姿で釣ってゐたが、たうたう夕方河から引きあげるまでに、大ものを七八尾釣りあげた。初心者としては、素晴しい手柄であった。
これは、鱒二が虚心の姿で、わが釣場を物してゐたためであったらう。
釣の道は、人生の道と相通ふところがある。釣に嫉妬は禁物であるやうに、人生にも嫉妬心は魔物である。その心に打克つことは、一つの修養である。やきもちは、人間の弱點だ。これを抑える一つの修養でも、並大抵のことではない。
他人が發見した釣場へ割り込んで、そして數多く魚を釣つたところで、それは自ら顧みて愉快ではないのである。人間が世に處する道も、これを撰ばない。吾等は、先輩の訓へをよく守り、そして人生のわが釣場に、謙虚な心を持つて、親しまう。
(*注;古くは、釣り糸を緡糸(ビンシ)といい綸(リン)ともいった。緡と綸は同じ意味である。)
この二人は大人だ。 言いも言ったり! やりもやったり!
「釣には、嫉妬心を最も禁物とする。」とここに書いてある。 確かにそうだ。
しかし、他の者が多く釣るのをねたんだり羨やんだりせずに悠々と釣りをするというのは凡人には為し難いことだ。