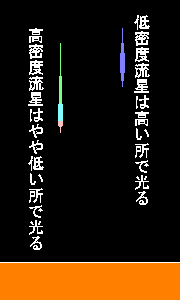![]()
流星物理のページに戻る
1.力学的質量と測光質量との関係から
直接手にとって測定したくても、大気との衝突で蒸発して採取できない流星物質です。
いろいろな状況証拠を積み上げて密度を推定するしかありません。
流星物質の密度は、古くより力学的に求めた質量と、測光により求めた質量が等しくなければならない、
という条件から計算をされてきました。
この考え方に基づいて計算すると、ほとんどの流星物質の密度が1g/cm3以下になり、
水に浮くほど密度の小さいスカスカした組成であるとされてきました。
このように計算した密度から、主にヨーロッパの研究者によって、密度による種類分けも行われてきました。
この分類によって、高速度で大気に突入する物質、すなわち、その日心軌道が彗星に近いものほど、
密度が小さいことがわかりました。
2.隕石や宇宙起源のダストの密度
ほとんどの場合手に取って測定ができない流星物質ですが、少しの例外があります。
それは、その物質があまりにも大きく低速度で落下し、隕石となって地上まで到達する場合と、
逆に、あまりにも小さすぎて、地球大気に軟着陸できる場合です。
まず、大きな隕石の場合、最も普通の隕石種である「普通球粒隕石」であれば、
3.4-3.7g/cm3前後で、我々が普通に目にする地表の石と比べてやや重い石です。
隕鉄であれば、鉄-ニッケルを主成分とするため、8g/cm3に近くなり、たいへん重くなります。
いずれにしても、地球の石より重く、上記流星密度とかなり相違します。
その解釈として、流星物質と隕石とでは、その起源、成因が違う、と考えられてきました。
つまり、流星物質は、彗星が放出した塵で、元々揮発成分が内部に多く含まれていたため、
それが抜けるとスカスカになってしまう。
一方、隕石は、小惑星由来で元々しっかりした岩石質である。という解釈です。
さて、一方の小さすぎて軟着陸できてしまう微小な塵は、
高い高度の成層圏を飛行する航空機や気球によって回収されます。
余りにも小さい物質ですが、これぞまさに想定していた流星物質の形を示しています。
すなわち、極微の物質が適当にひっついたような形で、まさにスカスカでありました。
流星物質は、まさにこのような形と密度なんだ、と思われていたのです(・・過去形・・)。
3.破砕理論の衝撃
1991年10月、京都で行われたババジャノフ博士の講演会の衝撃は、今でもよく覚えています。
博士の研究はもっと前から行われていたもので、本当はもっと早くから知っておくべきだったのでしょうが。
さて、その中で、飛行中に分裂する流星の映像と共に、流星物質の分裂、破砕を考慮して求めた密度が示されました。
幾つかの流星群に対して求められた密度は、多少ばらつきはあっても、隕石−隕鉄の間にあることを示していました。
決して水に浮くようなスカスカの物質ではないのです。
実は、力学質量と測光質量から求める密度計算には、重要な弱点が隠されていました。
すなわち、密度の小さい単一の物質と、密度は大きいけれど多数に分裂した物質を見分けることができないということです。
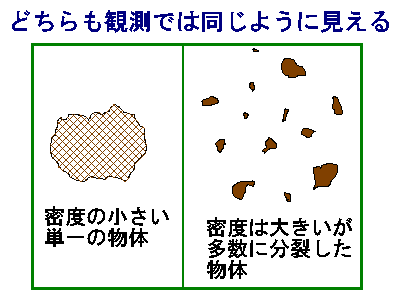
分裂を考慮することで、流星の複雑な光度変化も説明が可能になりました。
すなわち、分裂によって表面積が増えた流星物質は、大気とよりよく衝突し、より明るく光ると理解できます。
また、従来使われていた密度分類によって、突入速度と密度との相関は、
突入速度が速いほど大気との衝突によって流星物質が破砕しやすい、と置き換えが可能になります。
結果として、分裂を考慮せずに測光質量と力学的質量とから求めた密度より、
分裂を考慮して求められた密度のほうがより信頼度が高いと考えられます。
4.流星の密度と力学的な強さの区別
破砕理論は、幾つかの明るい火球ではかなり良い結果を示しています。
ただ、その多くは、"隕石的な"低速、大質量の流星物質です。
元々、密度が大きくても何の不思議のない流星物質と言えるかもしれません。
全ての流星物質にう対して、破砕理論が成功したと良いと言い切るにはためらいを感じます。
更に、破砕の形態によっては、光度変化に破砕の影響があまり現れない場合もあるはずです。
このとき、密度の低い物質と、破砕しやすい結合強度の弱い物質との区別ができないことになります。
さて、10月8日頃に時折大出現する10月りゅう座流星群(ジャコビニ流星群)は、
その速度の割に高い高度で発光することが知られています。
これは、この流星群を形作る流星物質の密度が小さいか、容易に破砕する結合強度の弱い物質であると解釈できます。
幾つかの流星群で、このような特徴が知られており、流星群ごとに流星物質の力学的強度に個性があると思われます。