第二章 LED回路の作成 |
「第一章 経緯と準備」へ戻る |
◎LEDの選定と電流制御を考察しよう!
前回の「第一章」で希少なパーツが揃いましたので、今回は「LED回路」の作成に入りたいと思います。その前に、回路作成後に電流消費量を比較するために、FD純正のバルブワット数を挙げておきます。尚、ポジションとブレーキは ダブル球です。
ウインカーランプ 21W × 2個
ポジションランプ 5W × 4個
ブレーキランプ 21W × 4個
ハイマウントストップランプ 8W × 3個
ホゥ、意外とポジションランプは小さいですね!
それでは、多岐にわたる「LED」の中からどれを選択するか決めなければなりません。
同時に「LED」の特性上、電源をバッテリーからそのまま取ると電流が高すぎるため、30mAを超えると一瞬で焼けて破損してしま います。
そのため、何らかの方法で電流制限を行う必要があるのでそちらも検討します。
・ LEDの選定条件
1.LEDの性質上、集光性が高いため、ある程度の個数を束ねる必要がある。さらにクリアレンズに収まる個数にする。(内径37 mm)
2.本人のこだわりから無灯時にはクリアであること。
3.輝度を得るために、「超高輝度」タイプにする。
4.おそらく数十個使用することから、単価あたりあまり金額が高くならないものにする。
・ 電流制限の選定条件
1.愛車のバッテリー電圧を計測したところ、充電直後は14.4V位出ているが、夜雨天時に渋滞にはまり、エアコン使用時には 12.9V(ほとんどバッテリー上がりの寸前ですね!)まで下がることを踏まえる。
2.クリアレンズ内に収めることを考慮する。
3.電流制限とは、基本的には熱に変換することなので、レンズの曇り防止を考慮する。
以上を踏まえて、「LED」を決めました。特性は以下の通りです。値段は一個80円位で無色透明タイプです。
黄色(超高輝度)
TLYH180P 8000mcd 波長590nm
直径5mm 2.1V 20mA 指向特性8度
赤色(超高輝度)
TLRH180P 5000mcd 波長644nm
直径5mm 1.9V 20mA 指向特性8度
電流制限に関しては、当初は低価格の固定抵抗を検討していました。
オームの法則に当てはめて抵抗値を計算してみると
抵抗(R) = 電圧(V) ÷ 電流(I)
最大値 14.4V ⇒ 720Ω
最小値 12.9V ⇒ 645Ω
となり、実際には最大値の2割り増しが安全なことから、かなり格差があり性能を出しきれそうにありません。
そこで、この変動する電圧特性を考えて、「定電流ダイオード」を使用することとしました。
これは電源電圧に関係なく電流を一定にするもので、自動車のようにオルタネーターによる発電している状態や、停止で変動する 電圧を制御するのに都合が良いダイオードです。
上記の「LED」の規格に合わせて、明るさを求めて10mAの2本を並列につなぎ、20mAで使用するか悩みましたが、クリアレンズ 内に収めることを考えて、少し暗くなりそうですが、定格電流が15mAのタイプに決めました。
(何事にも追求する私は、このダイオードの特性グラフを検証したんですが、グラフ上では15mAまで上がっていないので、ちょっと 心配ですが・・・)
定電流ダイオード
E−153 最大印可電圧25V 定格15mA
電流12〜18mA
◎LED回路の考察と作成しよう!
それでは、回路の考察に入りたいと思います。「LED」は単純に直列につないだだけでは、正常に光らないどころか、破損してしまうので「定電流ダイオード」につき、最高いくつ 直列につなげられるか考える必要があります。
「定電流ダイオード」が安定した性能を出すには、4〜5V必要とするので、電源電圧からそれを引いた電圧を「LED」にまわせる ことになります。
平均して4.5Vで計算してみると
最大値 14.4V − 4.5V = 9.9V ⇒ 黄色: 9.9 ÷ 2.1 ≠ 4本 赤:9.9 ÷ 1.9 ≠ 5本
最小値 12.9V − 4.5V = 8.4V ⇒ 黄色: 8.4 ÷ 2.1 ≠ 4本 赤:8.4 ÷ 1.9 ≠ 4本
となり、各々5本でも大丈夫と思いますが、バッテリー能力の下限に合わせると黄・赤ともに4本が妥当に思われますので、これを前提に 回路を考えていきます。
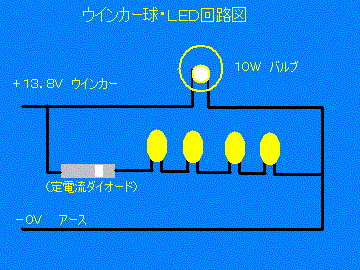
・ ウインカーバルブ+LED回路の作成
第一章で述べたように、ハイフラッシャー対策の「隠し玉」を使用しないで、小さいバルブを点灯させようと考えています。
このバルブは希少な10Wで、残念ながら(というか当然ながら)色付きになっています。
果たして、このバルブ追加で、どれだけ負荷がかけられるでしょうか?
これは実際に車体につながないと判らないので、今から楽しみです!
これを左の回路図のように並列につなぎます。
※後述しますが、実際にはこれ以外にもブレーキレンズ側で2個点灯させることになってます。
これならば、たとえどちらかが破損したとしても、他方は点灯出来るので少し安心です。

右画像が実際の状態です。
それでは実際に純正に比べてどれだけ省エネになっているか計算して見ます。
机上計算なので目安でしかありませんが ・ ・ ・
ちなみにこれはハザード点灯時です。
電源電圧を平均の13.8Vとした場合、オームの法則に従って計算すると
ワット(W) = 電圧(V) × 電流(I)
純正 : 21W × 2 = 42W
LED :((13.8V × 0.015A)×3 + 10W) × 2 =約21.2W
約1/2の消費量となりました。
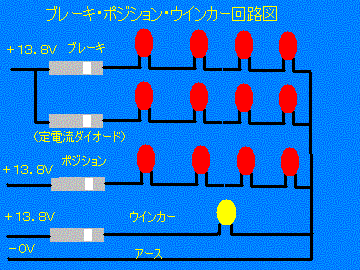
・ ブレーキ+ポジション+ウインカーLED回路の作成
純正ではこの位置にはブレーキとポジションしかありませんが、洒落っ気と少しでも負荷を増やすために、ウインカーを一個加えること にしました。
まあ、一個だけではそれほど輝度が期待出来ませんが、点灯しているくらいは判るかもしれません。
あと気をつけなければいけないのは、直列上にLEDが一個ということは、残った電圧は全て「定電流ダイオード」が受け持つこととなり 、かなり熱を持つと予想されますので、放熱させる必要があることです。
それ以外では、4個をポジションに、ブレーキに踏めばポジションと合わせて12個点灯させることにしました。
明るさの方ですが、純正の21W相当まで照らすには、指向性が強いLEDでは30個位必要になりそうですが、ドライバーの視線に 当たれば問題ないと思っています。
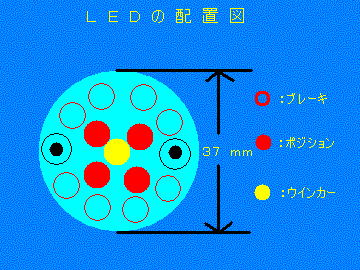
右図が各LEDの配置です。ユニバーサル基盤をクリアレンズの内径に合わせてカットして、ハンダ付けすることにしました。
黒丸は台座に取り付けるためのビス穴と、クリアレンズの肉厚ですが、かなり密集します。場所によっては1mmありません。
そこでLEDをノギスで実測したら、カタログ上では5mmだったのに、楕円形で6mm以上ありました。これでは密集するのも 無理はありません。
しかもこれ以外に「定電流ダイオード」を付けなければなりません。
う〜ん、果たしてこんな緻密なものを、私に出来るのでしょうか?ハンダ付けなんて高校の時にラジコンの燃料タンク作成以来です。
しかも、ダダ漏れだったような ・ ・ ・
さらにLEDはそんなに熱に強くないので、コテを当てる時間は5秒以内にしないと、破損する可能性があるので素早さも必要です。
もしも点灯しなかった場合は、熱破損によるものなのか、ハンダがあまいのか判断が難しそうです。
ハンダの吸引機は持っていないので、失敗は許されません。
一発勝負です!!
これがカットしたユニバーサル基盤の裏側で、LEDの足がこれだけ生えています。まるでハリネズミみたい!
LEDや定電流ダイオードには極性があり、長いのがアノード(+)、短い方がカソード(−)で間違えて電流を流すと破損してしま います。(定電流ダイオードの足の長さは同じです)
おそらくこのままハンダを始めると、絶対に間違える自信があったので、考えました。
どうせ短くカットしてしまう、足の片方(アノード側)にホワイトマーカーを塗っておけば、裏から見ても間違いにくくなります。どうです? Good アイディアでしょう!
後は地道に1つずつ付けていくだけです。
下の画像は「試作2号機」で、回路図に従ってハンダ付け後、裏側から見たところです。
「初号機」は明るさを実験するために全てのプラスマイナスにコードを付けてタコ状態になりました。
2号機で判ったんですが、位置決めはアース側から決めた方が間違いないみたいです。
画像で判るように、ブレーキの並列化でアノードが両端にきてしまい、ジャンパー線を引かないと、つなげられなくなってしまいました。
ここで気がついたんですが、純正のコードは「0.75sq」だったのに、「1.25sq」を使用したので、かなり窮屈に なっていました。まあ、抵抗が減るから良しとしましょう!
それでは実際に純正に比べてどれだけ省エネになっているか計算してみます。
ポジションランプの省エネ度
純正 : 21W × 4 = 84W
LED : 13.8V × 0.015A × 4 =約0.9W
なんと約1/93の消費量となりました。(本当ですか?)
ブレーキ(ハイマウントストップランプを含む)の省エネ度
ワット(W) = 電圧(V) × 電流(I)
純正 : (21W × 4) + (8W × 3) = 108W
LED : (13.8V × 0.015A × 2) × 4 =約1.7W
約1/63の消費量となりました。
さて、総消費量はどれ位差が出たでしょうか?
純正: 42 + 84 + 108 = 234W
LED:21.2 + 0.9 + 1.7 = 23.8W
ウオォー、凄いです!!約1/10の節電になりました。自分でも信じられません。
尚、図に載せていませんが、保険のため「定電流ダイオード」の直前に「1A」のヒューズをかますことで、「LED」側でショート等 の問題が起きても、車体側にその影響を伝えないように配慮しました。
上の画像は、試験的に予備バッテリーで点灯してみました。
このLEDは照射角が8度と狭角で集光性の高いので、少し拡散させる「ウラ技」として瞬間接着剤をLEDの頂点に塗っておきます。
ヤスリを掛ける手もありますが、これならその名の通り「瞬間」で完了します。
しかし「露出」が足りないのでしょうか? うまく撮れません。実際にはもっと赤くて、眩しくて、輪郭がぼやけているんですが ・ ・ ・
皆さんは、こんな時どうやって写しているのでしょうか?
でも思ってたより、明るくないなぁ〜!バッテリーを充電してないからかな〜
これが4個付けば、問題無い明るさになるのだろうか?ちょっと不安です。
次回はたぶん最終章となる「第三章 愛車への装着」に入りますので楽しみにお待ち下さい。
※それまで待ちきれない人は、予告編をどうぞ!! ⇒ 「第三章 予告編」