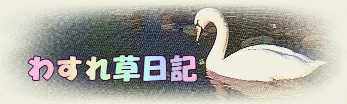
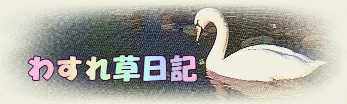
|
◆「美味しい!」という言葉◆ 胃がんの末期だった父を自宅で看ていたときに感じた「ものを食べられない苦しみ」は言葉で表現できません。「食べ物の匂い」をさせない為、自宅での煮炊きをやめました。病床に流れてくる食べ物の匂いは、幸せな食事の団欒から見放された人にとっては残酷に思えるでしょう。ご飯の炊ける匂い、味噌汁や葱の匂い、魚の焼ける匂い、酢の物の匂い、様々な食べ物の匂いは健康だった過ぎし日々を思い起こさせます。同時に「人のために料理をする幸せ」があることを知らされました。「お前の料理は美味しい」と父がいってくれていた事を。自分が作った料理を人と一緒に食べ、お互いに「美味しいね!」というときは、「私は幸せ!」といっているのだと思います。  20日に上京。歳末の東京の街はいまだに不景気のせいか、クリスマス商戦の狂騒はなく、いたって地味な印象です。見上げると赤坂プリンスホテルの部屋の窓が電飾で色分けされ、
巨大なクリスマスツリーが静かに夜空に浮かび上がっていました。 20日に上京。歳末の東京の街はいまだに不景気のせいか、クリスマス商戦の狂騒はなく、いたって地味な印象です。見上げると赤坂プリンスホテルの部屋の窓が電飾で色分けされ、
巨大なクリスマスツリーが静かに夜空に浮かび上がっていました。帰ってきたら大急ぎで年賀状を作り投函してきました。PCトラブルでごっそりデータを無くしたので、すべて初めから作り直しです。オリジナルのイラストも今年が初めて。試し刷りをした後、念のため1枚だけを来年の年賀ハガキに印刷したら ヤヤッ!宛名書きの面にイラストが印刷されて出てきました(T_T) 1年に1回しかハガキに印刷することがないので毎年何か失敗します。でも今年は上々のうちです。 04. 12. 25 ◆長崎の街路樹「南京はぜ」◆ 昨日午前、自動車道の気温掲示板は18℃を示していたといいます。桜並木は、葉こそすっかり落したものの、無数の細い枝を空に広げて白く光り輝き、凛々と春の到来を待ちかねるように力が漲っています。小春日和が続き、例年の冬景色と比べ、今年はどこか違って見えます。
身のまわりの自然を、強く深く感じるようになったのは年齢のせいでしょうか。子育てに追われている若いころは毎日が闘いだったので、自分自身に向き合う時間や自然の移り変わりに心を動かされても、深く感じるゆとりがなかったように思います。今しみじみそう思うのも、自然の成り行きなのでしょう。 私の好きな風景があります。晩秋の長崎は街路樹「南京はぜ」が紅葉して緑黄紅と3色の色が一度に見られ、それはそれは錦のようにきれいです。市内を走る路面電車の中からも楽しませてくれます。爆心地付近の並木も見事に色付いて、スペード型の真っ赤に染まった一枚を拾って、友達へ出すハガキに貼り付けたこともありました。師走になると白いはぜの実だけが梢に残り、下から見上げると冬の青空に真珠をちりばめたようです。父が元気だった頃、南京はぜが好きだと言ったら、その後、長崎に帰ったとき白い実を拾っておいてくれました。貰って帰って庭に蒔いたのに、芽が出なかったのでしょう、いつの間にか忘れてしまいました。芽が出ていたら大木になって、今頃は困っていたことでしょう。 04. 12. 17 ◆♪幸せになりたいけど頑張りたくない〜♪◆ このテレビの C M が一体何を宣伝しているのか、 歌(?)のインパクトが強すぎて記憶に残りません。こういう気持ちが堂々とCMにのるということは、それだけ若者の共感を呼ぶからでしょう。職につかない若者達が、「どんなことをやりたいの?」というレポーターの
以前、NHKで「死の国の音楽家達」という番組が放映されました。「大量殺戮に荷担した」と苦しみ続けたアウシュビッツ女囚の、戦後60年間の心の軌跡です。ナチス・ドイツによって、アウシュビッツ強制収容所に各地から列車で送られてくる人達を、囚人音楽家達で結成されたオーケストラで迎え、毎日、行進曲で囚人を労働に追いやったのです。音楽家達はその役割を拒否すれば自分達がガス室送りになる事を知っていました。今もトラウマから抜け出せないでいる仲間もいる中、彼女は自分自身との苦しい闘いの末ようやく音楽を鑑賞できるようになったのです。戦後、音楽から逃げるのをやめようと決意して初めてコンサートに行った時、そこで彼女は意識を失ってしまいました。オペラ「蝶々夫人」のアリア、『ある晴れた日に』はアウシュビッツで演奏していた曲の一つでした。高齢の女性の驚くべき記憶力と共に、命について、人が生きる意味について、体験を通して心の底から湧きでる真摯な言葉に圧倒されました。「白い雲と風に揺れる麦畑を畦に寝転がって見るのが好き。」と話す時だけ、彼女の笑顔は少女のように輝いていました。これほど悲しい音楽家達の人生をかつて聞いたことがありません。 04 .12. 11 |