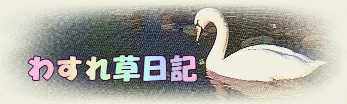
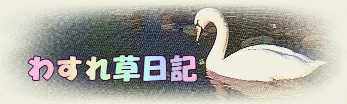
|
◆「絶対音感」連想◆
子供の才能はちょっとしたきっかけで、元々あるものが大きく伸びたり摘み取られたりします。小学館ノンフィクション大賞を受賞した「絶対音感」を読んでいて、自分の子供の時のイヤ〜な思い出が甦ってきました。絶対音感の能力を海軍が聴音訓練に応用し、軍に押されて文部省は昭和16年国民学校発足と同時に学校教育に採用したとあります。ある人の体験が語られています。「私たち少国民はピアノの音を聞いてB29の爆音や敵船のスクリュー音を同定し、それに反応できるような訓練を受けたものであった。その結果が昭和一ケタ音痴時代の誕生である」。 私の場合はその時の音楽の授業がその一環だったかどうかは不明ですが、2学年迄は、「今日はお天気が良いから屋上で授業をしましょう」とアコーディオンを胸に抱えた母に似たH先生と楽しく歌ったり遊んだりしたのが、3学年になると眼鏡をかけた若い女教師に替わり、音楽教室に移動しての授業が始まりました。不運にも、私が麻疹(ハシカ)にかかってしばらく学校を休んだ後の音楽の時間でした。 先生が鍵盤を叩くと、みんなは声を揃えてハーとかホーとか言 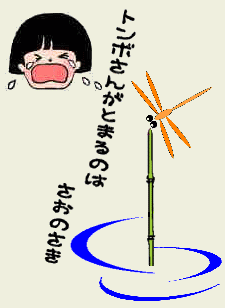 うのです。突然のことで何が何だかさっぱり判らずボ〜っとしていました。すると今度は左の掌を開いてその指先をさしたり指の間をさしたりして「トンボさんがとまった」、とか「ヘイタイさんがトテチテタ」とかいうのです。隣の子に小さな声で何のこと?と聞くと、「そこの2人!」と先生から注意されました。3度目の注意ではとうとう先生は激怒され、音楽とは全く関係ない恐ろしい言葉を私に投げつけると荒々しく教室を出ていったきり戻って来られませんでした。それから後のことは何も覚えていません。 うのです。突然のことで何が何だかさっぱり判らずボ〜っとしていました。すると今度は左の掌を開いてその指先をさしたり指の間をさしたりして「トンボさんがとまった」、とか「ヘイタイさんがトテチテタ」とかいうのです。隣の子に小さな声で何のこと?と聞くと、「そこの2人!」と先生から注意されました。3度目の注意ではとうとう先生は激怒され、音楽とは全く関係ない恐ろしい言葉を私に投げつけると荒々しく教室を出ていったきり戻って来られませんでした。それから後のことは何も覚えていません。これは左の5本の指を五線譜にみたてて、それぞれの音階にある音を覚えさせるものでした。「トンボさんが止まった」はドレミファソラシドをハニホヘトイロハで呼ぶようになったのでトンボさんのトの音は、ドレミでいうソの音、ヘイタイさんのヘの音はファなのです。 この事は思い出したくもなかったので自分の記憶がどこまで正確か判りません。その後長崎に引越して恐怖の時間はなくなりましたが、【後遺症】はドレミファになった戦後も尾を曳いて、他の生徒が苦もなく和音の音を答えるのに、複数の鍵盤を同時にガ〜〜ンと叩かれたとたん、私の頭の中はトンボさんや兵隊さんがとびだして火事場の騒ぎになってしまうのです。 (参考 「絶対音感」 最相葉月著 小学館文庫) 04. 4. 28 ◆春は凧(ハタ)揚げの季節◆ 私が女学生の春休みに、近くの諏訪の杜(もり)の頂上に行った時、沢 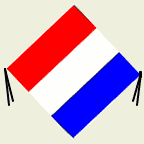 山の家族が親子で凧(ハタ)を揚げていました。なだらかな斜面に腰を下ろし、春風に吹かれてお喋りをしていると周りで小さな歓声が上がりました。ハタが切られてふわふわ落ちて行くところでした。別のハタは急降下して今にも墜落しそうで、見ている人達から悲鳴が上がりましたがちゃんと持ち直して、ぐんぐん大空高く昇っていくのです。勇壮であり、のどかでもありました。 山の家族が親子で凧(ハタ)を揚げていました。なだらかな斜面に腰を下ろし、春風に吹かれてお喋りをしていると周りで小さな歓声が上がりました。ハタが切られてふわふわ落ちて行くところでした。別のハタは急降下して今にも墜落しそうで、見ている人達から悲鳴が上がりましたがちゃんと持ち直して、ぐんぐん大空高く昇っていくのです。勇壮であり、のどかでもありました。 私が知っていた奴凧や武者絵のそれではなく、長崎のは本当は菱形を縦に少し伸ばしたような形です。お店に売っている小さなハタはインテリアに使いたい程ステキです。沢山の柄はどれもシンプルで、古典的な柄を見慣れた目には新鮮に見えます。 凧の形も変わっている上に、どうして長崎では凧をハタと呼ぶのか不思 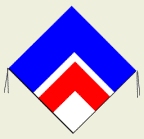 議でしたが、オランダの国旗(ハタ)が起源らしいというのです。そう聞いてハタと思い当りました。(^o^) 議でしたが、オランダの国旗(ハタ)が起源らしいというのです。そう聞いてハタと思い当りました。(^o^)赤白青の3色で染め分けた柄は成る程、オランダの国旗そのものではありませんか! 長崎に住むまで凧揚げは子供の遊びだと思っていましたが、長崎の凧(ハタ)揚げは伝統があり大人の遊びでもあるようです。ヨマと呼んでいる麻糸にビードロの粉を練りつけた糸で相手の糸に絡ませて切り落と 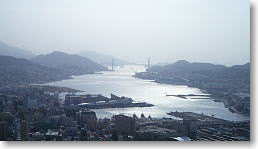 すハタ合戦というのがあるくらいですから。 すハタ合戦というのがあるくらいですから。今年の2月、その立山から長崎港を臨むと遠くに巨大なクレーンが両側にそびえているのが見えます。 2年後の2006年春、橋が完成するのだそうです。名付けて「女神大橋」とか。 04. 4. 22 ◆揚雲雀 なのりいで・・・◆ 月曜の朝、テレビをつけたら『 もう雲雀(ひばり)が鳴いていました 』 という弾んだ若い女性アナの笑顔の次に、イラクでの日本人3人の人質事件のニュースが続きました。24時間以内に解放すると言う声明にほっとする間もなく、更に厳しい解放のための交換条件が提示されたというのでした。  時は春 日は朝(あした) 朝は七時 片岡に露みちて 揚雲雀 なのりいで 蝸牛 枝に這ひ 神、そらに知ろしめす すべて世は 事も無し (上田敏訳) ブラウニングのこの詩を学校の教科書で習ったとき、平和であることの幸せを実感したのでした。10代の私達はこれからの日本を、2度とあのような恐怖と悲しみを味わうことのない平和な国にしようと心に誓いました。将来、国際社会が複雑になり、日本だけが紛争や戦争と無関係ではいられないこのような状況になるとは、想像できませんでした。 新憲法施行の年、新制中学一年生になった私達は毎日社会科の時間に民主主義について学びました。民主主義で大切なことは、「自由の裏に責任あり」と言うことだと教わっても理解できなかったのが、時々事が起こると、「ああ、こういう意味だったのか」と思い当るのです。自由の意味も責任の取り方も、信じられない程大きく変わってきました。人の気持ちで昔から変わらないものがあるとしたら、無償の愛、母が子を想う気持ちではないでしょうか。
◆桜を見て足元を見る◆ 昨日は歩くと汗ばむ程で、日よけ帽子を被って絶好の  お花見日和となりました。 お花見日和となりました。山口市の一の坂川は満開で、10日程前にローカルテレビで七分咲きという花便りがでた上、雨も降ったのでもう遅いと思ったのか、殆ど人影が無く、珍しくのんびりと満開の花を楽しむことができました。  この桜並木の両岸の道路の消火栓やマンホールの蓋は【一の坂川に桜と蛍】というカラフルなデザインで、今年初めて気が付きました。デジカメに撮ってしばらく歩くと、「ほら!ここにも綺麗な蓋が」と友達が教えてくれました。 花ばかり見てうっかり通り過ぎるところでした。足元を注意していると沢山ありました。画像が台形になっ  たのは真上から撮ると自分の影がもろに写ってしまうので少し斜めから撮ったせいです。 たのは真上から撮ると自分の影がもろに写ってしまうので少し斜めから撮ったせいです。両並木の桜は狭い道を隔てて民家が立ち並んでいるので、出店もなく、ただ静かに語らいながらぶらぶら歩くだけですが、いい雰囲気です。どの樹も宿り木をつけて、古木なのに立派な花を咲かせています。苔むした
 幹から直接花が咲いているのもあります。枯れた樹の跡は添え木をした若木が植えられていて、手入れが行き届いています。昔、大内氏が小京都にしたいと町造りのとき鴨川にみたてて造ったといわれています。 幹から直接花が咲いているのもあります。枯れた樹の跡は添え木をした若木が植えられていて、手入れが行き届いています。昔、大内氏が小京都にしたいと町造りのとき鴨川にみたてて造ったといわれています。橋の上では新しい赤いランドセルの女の子と黒いランドセルの男の子が並んで桜をバックに、若いお母さんに写真を撮られています。ちょっ  と照れながらも顔中が嬉しそうな笑顔が可愛い。♪ピッカピカの一年生・・・小さく口ずさみながら、つい足を止めて幸せな光景に見とれてしまった私達でした。(^o^) このまま橋の上で、花びらが水面を流れて行くのをぼ〜っといつまでも時が過ぎるのを忘れて眺めていたい1日でした。 と照れながらも顔中が嬉しそうな笑顔が可愛い。♪ピッカピカの一年生・・・小さく口ずさみながら、つい足を止めて幸せな光景に見とれてしまった私達でした。(^o^) このまま橋の上で、花びらが水面を流れて行くのをぼ〜っといつまでも時が過ぎるのを忘れて眺めていたい1日でした。
04. 4. 7
|
||||