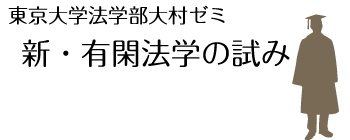近代と読書ーゼミの周辺(3)
近代になってから、読書のあり方は大きく変わった。日本に限って言えば、それ以前の読書は、たとえば四書五経に代表される古典の素読・会読が中心であった。これはいわば「社会に接続された読書」であったと言えよう。これに対して、近代以降においては「個人に集約された読書」が登場する。「小説」の登場、「黙読」の誕生、「個室」の成立などがこれを支えた。
ここでいう日本の近代とは、明治に入ってしばらくしてから、すなわち「政治青年」が減って「煩悶青年」が増えた時期以降であるもしれない。人々が「内面」というものを持つ、その内面を涵養するのが読書である。こうした傾向は、たとえば漱石において顕著になる。同じ1868年生まれの小説家であるが、紅葉の『金色夜叉』と漱石の『三四郎』の間には、大きな断層があるように思われる。そのことを象徴するのが、美禰子である。彼女は「本を読む女」として描かれている。
その漱石の弟子ともいうべき人々、たとえば阿部次郎(『三太郎の日記』)、和辻哲郎(『風土』『古寺巡礼』)、安倍能成、その他に、倉田百三(『愛と認識の出発』)、西田幾多郎(『善の研究』)などが旧制高校生の必読書となった。大正期以降の教養ブーム、それと呼応した出版ブームの原因については、慎重な検討が必要ではあるが、「近代と読書」の密接な関係は確かに存在していた。
この傾向は戦後も、ある時期までは続いていた。文学全集の終焉、文庫本の変質が、読書の性質を変えたように思う。もっとも、最近のピケティ『21世紀資本論』の大ヒットを見ると、大正教養主義とは異なる平成教養主義が実は存在するのではないか。それは一種のビジネス教養主義なのではないかとも思えてくる。このヒットと終戦直後におけるサルトルの『存在と無』のヒットとの間には、どのような異同があるのか。この問題は、「現代と読書」について考える一つのヒントとなりうるだろう。
最後に、「近代と読書」と「教養主義」に関する参考文献をいくつかあげておく。北村三子『青年と近代』(世織書房、1998)、永嶺重敏『モダン都市の読書空間』(日本エディタースクール出版部、2001)、同『東大生はどんな本を読んできたか』(平凡社新書、2007)、竹内洋『教養主義の没落』(中公新書、2003)、高田理恵子『グロテスクな教養』(ちくま新書、2005)。