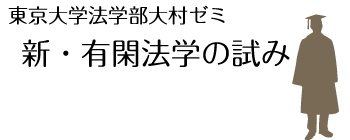補講—P・ウィリスから何を読み取るか
P・ウィリス(1950-)は、バーミンガム大学の現代文化研究センター(CCCS - Centre for Contemporary Cultural Studies)で学んだ研究者である。スチュアート・ホール(1932-2014)らによって1964年に設立されたこのセンターは、その後、「カルチュラル・スタディーズ」(日本では「カルスタ」などと略称されることもある)と呼ばれることになる研究動向の拠点となった。カルチュラル・スタディーズの代表的研究としては、トムソン『イングランド労働者階級の形成』やウィリアムズ『文化と社会』が挙げられるが、トムソンの本にも窺われるように、それは労働者階級の「文化」に強い関心を寄せるものであった。ウィリスの研究もこの流れの中に位置づけることができるが、その特色は、エスノグラフィーの方法によることのほか、サブ・カルチャー研究に繋がること、構造と主体の間に「文化」を置こうとしていることなどに見出される。サブカル研究はウィリス自身によっても続けられるとともに、カルチュラル・スタディーズの中心的なテーマになった観がある。また、構造と主体の関係はギデンズやブルデューによって、理論的に展開されることになる。以上のような意味で、ウィリスはある意味では、カルチュラル・スタディーズの第2世代と呼ぶことができるかもしれない。ウィリスの研究には、「文化資本」の「遺産相続」に着目するとともに「ディスタンクション」の指標を剔出したブルデューの研究と共通する面も多いが、マルクス主義・左翼的な関心から研究がスタートしている点においても、カルチュラル・スタディーズとブルデュー派社会学の間には共通点が見出される。
以下、補講の参加者による要約・評価である。
A 1 個人の決定を促す規定要因は、文化のレベルに媒介されてはじめて、規制力として働く。また規定要因そのものの再生産も、文化を媒介せねばなされない。
文化が再生産される過程には、二つの基本的なモメントが存在する。外部構造が文化の位相で集団に把握される、洞察を基本とするモメントと、その取り込まれた外部構造が今度は個々人の意思決定に一定の枠をはめるというモメントだ。この枠の下で行われた選択の積み重なりの結果が、社会の基本構造の現実的な再生産である。制約因は、社会集団が社会変革に取り組む可能性を中断するが、洞察に含まれる理知が生きながらえることは重要だ。
社会と文化が再生産される過程には、深刻な不和と予断を許さない緊張状態が存在し、現代資本主義社会は、絶え間ない闘争の社会である。様々なモメントが多面的に抗争しながら再生産される文化の領域が、他のどの社会体制にも増して資本生社会にとっての死活問題だ。
2 文化と社会の再生産に国家諸制度が果たす役割について論ずる。再生産の任務を託された国家諸制度が現実にどのように機能するかは、それらと土着のインフォーマルな諸文化との予断を許さない交渉過程によって決定する。また、制度の重要な組織改革について十全な評価を加えるには、制度の三つの層の区別と絡まりを押さえなければならない。
ある制度の中で上から下へとつながるイデオロギーの鎖の切れ目やもつれの部分こそが、社会の再生産に果たす制度の客観的な機能を見極める上で重要な意味を持つ。
インフォーマルな文化を媒介した、制度についての洞察の中にこそ、社会の再生産の秘密が封印され、保存される、ということが重要である。
B 社会の構造や階級の再生産について、外部構造により必然的・強制的にそうなるという見方を変える文章である。
社会の構造や階級といったものは再生産されることが多いが、それには文化の媒介が大きな役割を持っている。しかし、単純に文化現象のレベルがそのまま下部構造に還元されるのではなく、あくまでも労働者は自前の文化により自立的に選択してその労働に就く。そのため、社会諸関係が再生産される過程には、従来とは異なる結果が現れる可能性が常にある。それにもかかわらず基本的なレベルでは階級文化の本質的な特徴まで左右されることがないのは、外部世界の構造や階級関係が文化の位相で象徴的・概念的な関係群として集団に把握され、それがアイデンティティの裏付けとして内部に取りこまれることで、個々人の意思決定や進路決定に一定の枠をはめるからである。この理論からは、取り込まれた外部構造によって文化がみずから枠にはめる悲観的な見方と、しかし、この結果は不可避ではないという楽観的な見方がでる。筆者は楽観的な立場であり、階級文化の営みに対するあまりに機能主義的な捉え方は排されねばならないという考えである。
この文化と社会の再生産に対抗しようとするのが福祉や教育といった国家諸制度である。しかし、本来は階級差をなくすことを目的とする制度だが、建前の目的に対する対抗文化の高まりによって、逆説的に再生産が促進されうる。この理論で捉えると、ハマータウンの野郎どもについても、学校によって落ちこぼれされるという捉え方ではなく、自立性が認められる中、反学校文化によって自ら落ちこぼれるという捉え方ができよう。
C 文化は、社会構造と個人の主観や行為との間を媒介する役割を果たす。資本主義社会において、個人は自由主義・民主主義の建前のもと、自由意思で行動しているように思われがちだが、実は自律的な文化を介して、社会構造の影響を間接的に受けている。つまり個人レベルで社会の再生産が行われているのである。文化の内部には2つの相反するモメントがある。1つは集団レベルで社会構造を批判的に洞察するというモメント、もう1つはその洞察を妨げ、個人の意思を無意識のうちに社会構造に沿うように制限するというモメントである。前者を重視すれば、文化は社会の変革可能性を秘めたものとして、楽観的に捉えられる。しかし筆者は、社会と文化の緊張状態をより重視し、文化による支配イデオロギーの超克も可能とする。資本主義社会における自由は、資本主義社会に有利に働くとは限らず、不利に働く場合もあることを強調するのである。教育・福祉の制度は、自由競争の過程で国家がやむなく生み出したものであるが、かえって資本主義の問題を表面化させ得る領域となる。国家の諸制度は、たてまえとしては国家のイデオロギーを反映させたものであるが、その制度の枠内でイデオロギーを現実に実践しようとすると、現実と理念の齟齬からイデオロギーが変化を迫られる。さらに制度の文化としての領域のなかでは、対抗文化も生まれるのである。しかし、イデオロギーへの反骨心が対抗文化のレベルにとどまることによって、逆説的に、社会構造の根本的な改革を抑止しているという面もある。反骨心を持とうとしても、それが反制度的な態度にとどまってしまうと、社会構造への洞察を鈍らせ、変革を困難にし、社会の再生産に寄与してしまうのだ。
D 社会構造と文化は、相互に独立しているとか、あるいは一方が他方を完全に従属させるといった関係にはない。両者は各々、一方が他方を媒介することで初めて再生産されうるという相互的な不断の干渉のプロセスの中で維持・更新されており、この視角にこそ、文化が社会に対して果たす積極的な役割を見ることができる。たとえば、本著で述べた学校への反抗文化と資本主義的社会構造は相互に関連している。もっとも、このような社会構造と文化の再生産の循環は絶対不可避の運命ではなく、そのプロセスは当然に幾つもの亀裂をはらむ。再生産のプロセスがこのような不確実性を伴う以上、構造が人々の主体的な行為を支配するという言説は説得力を失うし、国家的諸制度は常に社会構造の維持という目的に沿って運用されるという議論も当を得ない。制度は社会の再生産に資する形で厳格に運用されるわけではないし、制度にはその建前と乖離した側面がある。寧ろ、建前としてのイデオロギーが首尾一貫しないという自己欺瞞を制度が抱えるからこそ、逆説的にインフォーマルな対抗文化が再生産され、社会構造全体が再生産される契機を形作るのである。もっとも、この対抗文化は制度と無関係には現実生活を営みえないという限界を自ずから有しており、それゆえに対抗文化はそれ自体主流となる力を構造的に持ちえず、従って既存の社会構造の維持・更新という帰結を生む。その点では、国家的諸制度が社会の再生産に果たす機能には注目すべきものがある。
E 社会の再生産は文化というフィルターに媒介されて行われる。ここでの文化は階級的、地域的な出自や教育環境という規定因を機械的に反映したものではなく、独自の論理で運動する自律的なものである。社会を存続させる文化レベルの事象の特徴として①様々な象徴記号とその分節的な体系から成り立つこと、②産出の過程には物質的なものの生産と同じく現実的な過程が含まれること、③集団の成員はその集団の文化を拠り所として自らの主観を培い、アイデンティティを確立させること、の三つが挙げられ、再生産の過程においては文化を通じて集団が外部世界の構造や階級関係といった外部構造を把握し直す洞察が行われる。しかしこの第一のモメントに対して、社会の制約因によりその洞察は外部構造の拒絶ではなく再生産への合流を導くような意思決定が行われるという第二のモメントが干渉することで、基本構造の現実的な再生産につながることとなる。このように文化はさしあたり資本主義の求める社会の再生産に寄与する方向に機能しているといえるが、対抗文化の挑戦的・破壊的側面は社会を脅かす力をもっており、文化の領域における亀裂や闘争によって変革が起こりうる不確かな状態を作り出しているのも事実であり、社会の再生産における文化の本質的な働きは緊張関係を再生産の過程にもたらすことであるといえる。また国家の制度についても制度が直接的に再生産を規定していると考えるべきではなく、制度の建前の側面・実務の側面・文化の側面という三つの側面それぞれに着目し、制度の建前は階級関係をはじめとする基本構造と文化の織りなすテクストとのかかわりにおいて理解されるべきである。
F この章では、前半で社会の再生産における文化の役割を、後半で国家との関係を論じている。前半では作者は社会の再生産は唯物論的には説明しきれないことを強調し、再生産をもたらす個人の自律的な決定の根拠を文化に求める。文化と構造は必然的な円環をなしており、実在の社会構造と概念上の構造の双方向の転換は文化を媒介してなされる。その見通しには悲観・楽観の二側面があり、創造的な洞察の側面において文化が自らの可能性を断つという考えと、様々な阻害要因にも拘らず、洞察を打ちかためて外部構造に働きかける余地が生まれるという考えがある。楽観的に考えれば、文化と社会の再生産には不確かさがあり、絶え間ない闘争の社会である資本制社会においては自由が再生産に繋がるとは限らない。そして、国家制度の中で変動可能性は教育・福祉の領域において顕著である。
後半では、再生産の任務を委託された国家諸制度が現実にどのように機能するかは、制度と土着のインフォーマルな諸文化との予断を許さない交渉過程によって決まるとした上で、一つの制度をたてまえの層、実務の層、文化の層に分けて論じる。たてまえの層で定められた公式のイデオロギーは制度の最末端まで届かないが、それは実務の層で制度の秩序を維持し機能させるという課題を抱える実務担当者によって意図しないうちに見直され、文化の層においてイデオロギーが本来目的としていない社会全般の再生産をインフォーマルな対抗文化が引き起こすためである。これを筆者は進歩主義の教育制度において論じ、その他の諸制度に容易には一般化できないものの、多くの制度においてインフォーマルな文化がもたらす洞察が社会の再生産をもたらす選択へ人々を動機付けているとした。
G 社会の再生産に、文化はどのような役割を果たすだろう。再生産を微分する。すると、強制力なく再生産が繰り返される以上、文化固有の領域を認めなければならない。再生産の過程を見る。そこでは、再生産から離脱するモメントと、それへと合流するモメント、二つのモメントを文化の位相に認めることになる。文化なしに再生産は存在し得ない。文化と再生産は、メビウスの帯の関係である。
では、文化と社会の再生産に、制度はどのような役割を果たすだろう。なるほど、制度は文化を駆逐する。しかし、制度は常に顕教と密教の二つの顔を持つ。顕教で殴った文化と、制度は密教で以って結合する。文化と制度の対立が膠着し、反転した文化は、翻って保守化する。文化は制度の代行者として、再生産のイデオロギーとなるのである。
H 『ハマータウンの野郎ども』は、マルクスの議論を一歩進めようとしたものである。マルクスは資本家の利益を反映したものとして国家を捉え、労働者はもっぱら従属的な位置に置かれるとしたが、ウィリスは労働者側も再生産に能動的に寄与しているとする。であるがゆえに、資本主義社会における資本家の支配は決して安定的・決定的なものではないとする。
ウィリスは教育制度改革によってこのような自律的文化を媒介とした再生産を完全になくすことはできないとしたが、それは決して進歩主義教育を全面的に否定するものではないとするが、はたしてそのように考えてよいものだろうか。ある「公的イデオロギー」に染まらない「インフォーマルな文化」に属する個人が、積極的に、「一部的な洞察」によって反発する道を選んだというのなら、少なくとも「自由意志」は尊重されているといえる。しかし、努力してもどうしようもないというような無力感から、消極的にそのような選択がなされた場合にもそういえるのか。近年では後者のケースのほうが問題にされることが多いのではないか。また、そもそも自己決定によるものはすべて是とされうる価値観にも疑いをさしはさむ余地がないわけではない。
マルクスは国家を資本家の道具であるとしたが、ウィリスはそうではなく、教育・福祉行政は「市民社会のおのずからなる活動が集約されて積み重ねられたもの」であるとする。であるからこそ、「野郎ども」の反発を「個々人がみずからを見限る自由として費消」されたものであると言ってしまうことができたのであろうが、では、ウィリスのいう「市民」に最底辺の労働者たちは本当に含まれているのだろうか。もう一度現在の状況に引きつけて考えるべき問題であると思う。
I 「野郎ども」が、ある種の誇りすら抱いて自ら底辺の労働に参入していくのはなぜか。そこでは「文化的なもの」が作用して資本制生産様式の再生産が行われている。文化現象の分析は下部構造への還元で済ませることはできない。生産のあり方が直接に「規制力」として働くのではなく、自律的な文化のレベルでの「媒介」について考える必要があり、そこにはそれ独自の運動の論理がある。
「野郎ども」の反抗的な「対抗文化」は、制度の表向きの政策にとってはつねに否定か矯正の対象であるが、現実にはむしろそれこそが、「自由意志において」自ら進んで労働の最底辺層を埋めてくれる「野郎ども」の存在こそが、資本制社会全般の再生産に寄与している。
社会が文化に媒介されながら再生産される過程には「創造性をはらんだ緊張状態」が生じ、現状とは異なる結果がたぐり出される可能性が恒常的にひそんでいる。このプロセスの推進力となるのは、インフォーマルな社会集団であり、集合体に固有のエネルギーである。全体社会における自集団の位置について意味の了解が可能な図式が構築され、それによってうっぷんを晴らす可能性が探られる一方、そのプロセスの中で「創造的な加工」が生じて、現実と切り結ぶ予想外の結果がもたらされることがある。
しかし、このプロセスが現状の打破よりも現状の再生産の方へ傾くのは、文化の内部に「制約因」があるためである。内に相対的に自律的な意味体系を背負い込み、外からイデオロギーの強力な作用を受けることで、現状への批判的な洞察はねじ曲げられ、現状の受容に傾く。とはいえ、従属的な境遇への自縄自縛は絶対的な運命ではなく、現代資本制社会がはらむ絶え間ない闘争のうちに「社会を変える」希望はある。
J まず、資本制生産様式を支える諸条件の維持・更新の局面において、文化的なものが果たす役割についていくつかの考察がなし得る。第一に、文化現象のレベルは直ちに下部構造に還元し得ない。すなわち、文化のレベルの諸現象を、階級的・地域的出自・教育環境といった大局的な規定要因の機械的反映と直ちに断定することはできない。とはいえ、大局的な規定要因そのものが再生産されるためには、ひとまず文化のレベルに媒介されねばならない。そして、この社会を存続させる文化のレベル(位相)の事象については、①文化を形成する素材は多様な象徴記号とその分節的な体系から成っており、②文化の産出過程には、物質的なものの生産と全く同様の現実的な過程が包含されており、③集団の成員は、集団により形成される文化を拠り所としつつ、個々の主観内容を培いアイデンティティを確認する、といった特徴を指摘できる。構造と文化は相互に一方を切り離して個別に考えることのできない必然的な円環をなしており、実在の社会構造は文化の位相を通路としてはじめて概念上の構造へと転換され、逆の転換もまた同じ通路を通るといえるのだ。もっとも、かかる理論は、文化における洞察が世界の真相に届き外部構造に働きかける余地(ラディカルな展望)をあらかじめ排除しないとして、著者は悲観的な見通しに懐疑的であり、資本主義体制に固有の「不確かさ」が教育・福祉の体系に突発的な変動を生ぜしめることを予感する。
次に、文化と社会の再生産に国家諸制度が果たす役割についてある仮説を定立し得る。制度が「たてまえの層」「実務の層」「文化の層」の諸層から複合的に構成されることを議論の出発点とした場合、諸制度の実際の機能は「たてまえ」の存在理由とは異なる働きをしており、自己欺瞞を犯しているといえる。
K なぜ社会は再生産されるのか。簡単に言うと、自由競争の社会の中で、なぜエリートの子供はエリートで、バカの子供はバカになるのか。彼らは決して、生まれや育ちによってその階級にとどまるように社会に強制されているわけではない。そうではなく、社会構造が文化として立ち現れ、その文化が個々人の意思決定を導くことによって、自発的にその集団・階級を選び取るのである。両者は似ているようで大きく異なる。
もっとも、このような階級支配の方法は一見完成されたもののように思えるが、決してそうではない。現在は前述のように、与えられた自由によって人々は自らの階級を選択していると考えているから、自由は秩序維持の方向に機能している。しかし、いつその自由が階級闘争のために行使されるかはわからないのである。そして、実は支配のために構築された機構ではなく、市民社会の活動のボトムアップ的な結果にすぎない国家制度、とりわけ教育・福祉行政には、こうした事態をコントロールする力がない。
以上を踏まえて社会の再生産の仕組みを考えると、社会の再生産は、たてまえを実践するときに対抗文化が生まれることで実現されるという仮説が立てられる。本書の教育の例によると、「たてまえ」とは労働によって社会に貢献し自己実現を図ることが素晴らしいという金科玉条の概念であり、「実践」とはその準備としての学校教育であり、「対抗文化」とはそうした学校教育をクソくらえと考える少年たちのことである。そうした少年たちは「自由意志において」労働階級を選ぶことになる。
「たてまえ」は本書では公式イデオロギーとも呼ばれるのだが、公式イデオロギーは全体に浸透することはなく、必ず対抗文化が生まれる。したがって、公式イデオロギーを推し進めるだけで、勝手に社会の再生産は進むことになる。これこそが社会の再生産の秘密であるのだ。
L 本文献においてウィリスは社会の再生産において教育段階に着目するという非常にわかりやすい、ともすればよくある形をとっている。しかし、彼は資本主義社会における階級の固定化に対する既存の推察を批判する。その中にはマルクスの史的唯物論や主流であった社会的文化的な再生産理論が含まれる。彼が社会の再生産において注目したのは外的変数ではなく文化であり、文化によって若者たちは自らの“なじみ”の世界を選び取っていくと主張している。
では文化とはなにか。彼は文化を実践との関わりの中で考える。それは構造と文化は切り離せない必然的な連環を成し、洞察と制約因の間で絶え間ない闘争を繰り返すという不安定な状態の中にあるからであり、この不確実性に資本制社会自体の延命と衰退をみる。労働者は基本的に旧状を墨守する傾向があるとしても、洞察を行うことができ、その意味で抗する足場も持っていると言えるからだ。
そして彼は再生産と制度との間に仮説を見出した。その中心にあるのは制度の絶対視に対する懐疑である。第一に制度の趣旨と実際の機能の齟齬、第二に制度の複雑さを挙げている。制度にはたてまえ、実務、文化の3つの層があり、最下層である文化の層で生まれる対抗文化の盛り上がりを防ぐのは難しいと考えた。そしてこの対抗文化が制度改革の意図と異なる諸結果を招き寄せてしまう。この結果人々は自らを既存の世界に引き入れてしまうのだ。ある制度をみるためには最末端に至るまでどのような抵抗を受けたかをみていかなければならず、抵抗の生じた切れ目に再生産の秘密が封印されているとした。