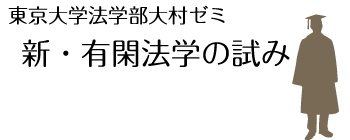国技としてのスポーツ
報告者:長岡・籾井
課題図書
①山口和幸『ツール・ド・フランス』
②佐山和夫『ベースボールと日本野球』
③小川光生『サッカーとイタリア人』
④33代木村庄之助『力士の世界』
⑤松井良明『近代スポーツの誕生』
課題図書の紹介
①山口和幸『ツール・ド・フランス』序:★★★破:★★急:★
①本書は世界的には高名なものの、我が国ではいまいち注目度の高くない自転車レースの大会「ツール・ド・フランス」について、その歴史と魅力を紐解こうとするものである。第1「ステージ」から第2ステージではベルナール・イノーをはじめとするツール・ド・フランスを彩った歴代の名選手の活躍の足跡を追うなかで、大会の概要や競技の面白さ・奥深さを浮き彫りにしようとしている。そこにはフランスの「国技」であるがゆえの特殊性も垣間見える。第3ステージでは黎明期、第4ステージでは比較的近年の歴史を概観しつつ、さらにツール・ド・フランスの魅力を掘り下げ、第5ステージで日本人選手の活躍をピックアップする。エピローグではツール・ド・フランスの近年の国際化にも触れる。
全体として選手個人の視点から競技の魅力を伝えようとするスタンスなので非常に臨場感があり、競技を知らない読者にも親しみやすい構成となっている。そのなかで、大会の国技としての側面と、国際化した競技としての側面とが一種の緊張感をもって内在している様子がみてとれる。反面、ツール・ド・フランスの魅力を紹介するという本のコンセプトからか、筆者の意見や問題意識についてはあまり明確に描写されていない。
①著者はツール・ド・フランスを20年以上にわたって取材しているジャーナリストである。ツール・ド・フランスは経済・社交・娯楽が一体となって進行するものであるとしながら、その本質ともいえる自転車競技としての魅力を、選手たちの織りなす人間ドラマを通じて描き出すことに重点が置かれている。
本書では歴代チャンピオンがこの権威ある大会をいかに戦ってきたかが語られる。そこでは、選手本人の事情に加えて、最高権威であるレースディレクターの思惑やフランス国民の心情、そしてチーム競技であるが故のしがらみが大きく関わってくる。特に山岳コースではこのことがはっきり示される。大会の競技形式によって確立した近代ツール・ド・フランスの勝ち方では、山岳コースでの勝利は比較的軽視されるようではあるが、それでもなお著者が山岳スペシャリストに注目するのは、困難に立ち向かう選手の姿がスポーツの魅力として重要な部分を占めていることを確認させてくれる。
今日では世界規模に拡大したツール・ド・フランスだが、21世紀になってもフランス的、あるいは欧州的な伝統がしっかり残っているようである。国技としてその国の価値観に多大な影響を受けたスポーツが、どのようにして文化の垣根を越えていくのかを示唆してくれる一冊である。
②佐山和夫『ベースボールと日本野球』序:★★★破:★★急:★
日米の野球をめぐる精神的文化の違いを、それぞれの歴史的背景の対比から説明しようとする著作。第一・二章ではアメリカにおいて、子供の遊びであった「タウン・ボール」から派生した野球が、次第に社交場としての役割を担わされるようになり、一大ショー・ビジネスとして成立するまでの、いわば「下から上」への過程を説明する。第三章ではそれとは対照的に、旧制一高でお雇い外国人から日本に伝わった野球が、中学・小学校へと「上から下」に伝播した歴史を振り返る。それを踏まえて第四章以降、日米の野球に対する考え方の違いをより深く考察してゆく。
確かに「ベースボール=遊び=打のスポーツ」とするアメリカと、「野球=列強との真剣勝負の場=守りのスポーツ」とする日本を対比させる筆者の主張には一定程度の合理性が認められ、傾聴に値するものがある。ただ時代背景もあってか、やや「ベースボール贔屓」な感は否めず、因果関係の説明や分析が不正確だという批判の余地はなお残されよう。
③小川光生『サッカーとイタリア人』序:★★★破:★★★急:★★
イタリアの各地方のサッカーファンのカンパニリズモ(郷土への帰属意識)を、インタビューを通じて描き出そうとする一冊。彼らの多くは、故郷のチームを贔屓にしつつ、同時にユヴェントス、ミラン、インテルの3強を応援している。しかし、例外的に自分の故郷のチームに固執する人々も存在し、特に近隣のチームが対戦するダービーが行われる時には、過激なまでに熱狂する。
著者はイタリア人の3強信仰・二元主義に驚き、イタリア人の勝ちにこだわる姿勢からくるものであると説明するが、本書の記述からは、それがイタリア人に特異なものであるとは感じられない。強いチームが人気を博するのはある種当然のことではないのだろうか。また、クラブの会長の資金力が強さに直結するため、レッチェのように、経済力に劣る南部のチームが若手育成に力を入れるようになったというが、それによりさらに南部のカンパニリズモが高まり、南北のサッカーがより異なる方向へ発展していくことを予感させる。
④33代木村庄之助『力士の世界』序:★★破:★★急:★
著者が相撲の世界に身を置いた経験から、日本の国技である相撲の伝統がいかに変容してきたかが語られる。相撲界が昔から勝てばお金が入る実力の世界であるとしつつ、弟子制度による助け合いや、神事としての一面に由来する伝統様式美といった価値観がかつては今よりも強かったとする。
外国人横綱は著者の現役時代にすでに登場していたが、その頃から横綱の品格が問われることが多くなった。著者はかつての価値観は外国人力士のみならず若い世代の日本人力士にも受け継がれていないようであると指摘するが、たしかに相撲は神事というよりはスポーツとして捉えられることのほうが多いのではないだろうか。そうであるならば、相撲の存続を望むにせよ、それにとどまらず文化の垣根を越えて競技人口を拡大させ、より相撲を発展させようとするにせよ、神事としての一面はこれからも薄まっていくのではないだろうか。
⑤ 松井良明『近代スポーツの誕生』(担当:長岡)序:★★★破:★★急:★★★
筆者は、従来のスポーツ史研究が近代的な「競技スポーツ」の成立にのみ焦点を当てることを批判し、近代化の過程で排除された「ブラッディ・スポーツ(流血を不可避の要素とするスポーツ)」に着目する。そのなかで一種目の「競技史」にとどまらないスポーツの「全体史」を探り、いわば逆説的に近代スポーツの成立過程を明らかにしようと試みる。「名誉」や「勇気」を重んじる前近代的・騎士道的な価値観の下、ジェントルマンから労働者まで熱狂した闘鶏や拳闘が、19世紀以降の社会変容を経て、一方では非合法化されて歴史から姿を消し、あるいは「健全な(アスレチズムの精神に適った)」スポーツとして大きな変化を遂げる様を追う。
著者の問題意識が明確で、また挿絵も多いため、慎重に議論を展開する割に読みやすい著作である。正史ではなく、「裏」の歴史を探りながら近代スポーツの成立を考察しようとする姿勢も面白い。
コメントⅠ
①ではフランス、②では日本・アメリカ、③ではイタリア、④では日本、⑤ではイギリスを例に、各国のメンタリティがスポーツに反映される様を概観した。一方で、特に20世紀以降、国際化の波はスポーツ界にも急速に押しよせ、国技としてのスポーツに新たな解釈が加えられ、変容を迫られるという事実も厳然と存在している。国技とされるようなスポーツが国際化することについて、単純な是非を超えて、メリットとデメリットを天秤にかけながら論考したいと思う。2020年に控える東京オリンピックのことをも念頭におかれたい。
また、ナショナリズムをスポーツに動員することについても同様に議論したい。ナショナリズムは人々のスポーツへの熱狂を高めることができるが、同時に痛ましい事件を起こし、あるいは政治利用されるという危険をも含む諸刃の剣であるようにも思える。いかにしてそのバランシングを図るのが適切なのだろうか。なるべく多くのゼミ生の忌憚のない意見を求めたい。(長岡)
スポーツは、「気散じ」を原義とし、時代・社会の要請により様々にその形態を変化させる。①③④⑤では時代の流れ、②では国による文化的背景の違いからどのようにスポーツが変化していったかが、人気のあるスポーツに注目して述べられる。前者の中でも、特に⑤は18、19世紀におこった変化について、何が失われたのかという観点からアプローチするものである。
現代という時代の特色の一つとして、情報技術の発達があげられるだろう。それにより、かつてアマチュアリズムを重要な要素としていたスポーツは、プロにより行われるものとなった。特に人気のあるスポーツのビッグゲームともなれば、放映料など巨額のお金が動くビジネスになっている。そんな中で、スポーツのルールというものは、コミッショナーの収益を求めた結果としてスポーツが観客にとって面白くなるように作られている。しかし、競技人口のすべてがプロ選手であるというわけではもちろんなく、そのようにして決められたルールが多くのアマチュアにとって競技の魅力を損なうようなものであるならば、長期的には競技人気が下がり収益を損なうことにはなるが、より直接的に選手自身を縛るルールの作成に関与する仕組みが必要であるとはいえないだろうか。(籾井)
コメントⅡ
スポーツの世界はハード・ロー(国会により立法される法)よりもむしろソフト・ロー(私的な取り決め、裁判所による強制力をもたない法)が支配する領域が大きいと言われる。スポーツを巡る紛争のなかには、例えば代表選手選考のように、そもそも「法律上の争訟」(裁判所法3条1項)にあたらないものも多いのである。2011年制定のスポーツ基本法も、「スポーツ事故の防止」や「スポーツに関する紛争の迅速かつ適切な解決」を国の努力義務として規定しているにすぎない。
もっとも、スポーツが公共財としての役割を果たしていることに鑑みれば、ある程度国内裁判所が関与すべき場面も少なくないのではないか。プロ・スポーツ選手を巡る契約問題、ドーピング問題、八百長問題、スポーツにおける人種差別、代表選考、スポーツ事故などスポーツを巡る紛争は多岐にわたる。どのような仕組みで法律・法曹はスポーツの発展・振興に寄与できるであろうか。議論が進んでいない分野なので、率直な意見を求めたいと思う。
また、国際スポーツ法を管轄するCAS(Court of Arbitration for Sport, IOCにより1984年設立)との関係で、どの程度国内裁判所の関与が許されるかという点についても問題が残っている。その点も頭の片隅に置いていただけたらと思う。(長岡)
日本では2011年にスポーツ基本法が制定された。1961年のスポーツ振興法との大きな違いは、「スポーツをする権利」が明文化された事である。
一方、情報革命の影響で、アマチュアとプロの間に、セミプロとしてビジネスの対象になる層が生まれてきている。アメリカでは、大学スポーツがプロよりも収益を上げている状況で、2014年にはノースウエスタン大学のフットボール選手が「労働者」と認められた。日本でも、甲子園を盛り上げるため、選手が過剰な負担を強いられ、ビジネスの犠牲になっているという指摘もされている。
スポーツ基本法では、「スポーツを行う者の心身の健康の保持増進及び安全の確保」が理念として掲げられ、そのために、国や公共団体に施策の作成・実施の責務を課し、スポーツ団体に努力を求めている。そんな中で、心理的圧迫により無理をしてしまう青少年スポーツ選手の保護と、彼らの自発性や日本のガンバリズムの精神の尊重はどのように調和させていくべきなのだろうか。(籾井)
ディスカッションの概要
まず、スポーツが国際化するとはどういうことかから議論を始めた。国際化の条件として、競技としての客観性要求されるのではとの指摘がなされた。これはスポーツ文化の発展が賭博文化と深くかかわっており、それとの決別のための明確な基準が求められたという言説に相通ずるものである。国民性がスポーツにおいて示されるかどうかという点に関しては、そのスポーツに内包された価値観が同時に伝わっていく場合と、外来のスポーツに受容した側の独自の価値観が織り交ぜられる場合の区別が必要であるとの指摘もなされた。現在国際的に人気のあるスポーツの多くが、近代以降支配的な価値観を生み出してきた西欧諸国発祥である事を併せ考えれば、今後のスポーツの変化について、より深い考察を要すると思われる。
また、スポーツの国際化に関わる問題として、スポーツとナショナリズムの関係についても議論した。郷土愛がスポーツをより熱狂的なものにする側面を有することは間違いなく、そもそも戦争を引き起こすようなナショナリズムと同質のものとして捉える事が適切かは議論の余地がある。この点、ラグビーでは代表チームを組織するにあたり所属協会主義がとられていることは興味深い。日本国籍を持たない選手で構成された代表チームを、日本国籍を要件として構成された代表チームの場合と同じように応援することができるならば、スポーツにおいて現れるのは、20世紀のナショナリズム、つまり民族主義とは異なるものであるといえるのではないだろうか。ナショナルチームの国籍要件自体がいわば過渡期を迎えており、今後のあり方になお注視を要するといえよう。
スポーツと法という観点からは、スポーツの公共性が問題となった。主体的にスポーツを嗜むという場合のほかに、スポーツが社会的貢献をもたらすのかについては議論の余地が残された。
憲法との関係でいえば、ドラフト制度と職業選択の自由との対立も論議の的となった。球団ではなく球界に参入すること自体を一つの職業選択として捉えてよいのか、それが職業選択の自由の制限にあたるとすれば、それはリーグの均衡維持、ひいてはスポーツの価値を維持するためのやむを得ない制約として許容されるのかという問題意識を各人の間で共有していただけたのではないかと思う。
商業主義とスポーツの関わりについても触れた。その際、商業主義が必ずしもスポーツの発展を阻害するものとは限らず、商業主義によるバランシングが図れる面も無視すべきではないという指摘もなされた。
スポーツ基本法については、具体的な法規範としての意味が想定しにくい点において、古典的な法律のあり方とは異なることも指摘された。法学において研鑽を積んでいく我々にとって、いま一度立ち止まって「法とは何か」について再考する機会となった。