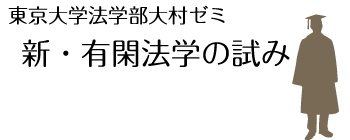冠婚葬祭
報告者:大村・樫村
課題図書
①斎藤美奈子『冠婚葬祭のひみつ』(2006)
②北村文、阿部真大『合コンの社会学』(2007)
③高木侃『三くだり半と縁切寺』(1992)
④碑文谷創『新・お葬式の作法』(2006)
⑤高橋純『「黒」は日本の常識、世界の非常識』(2011)
課題図書の紹介
①斎藤美奈子『冠婚葬祭のひみつ』(2006)序:★★★破;★★急:★★
①冠婚葬祭の内の「婚」と「葬」について、明治以来100年の歴史をひもといた上で、少婚多死社会である現在を捉えなおしているのが本書である。
冠婚葬祭はしきたりや作法に縛られた独特の文化でありながら、その「型」自体は時代の要請に合わせて変幻自在に変容してきた。神前結婚式やチェペルウェディングにしろ、祭壇や霊柩車にしろ、社会の変化に合わせて業者がうまいことしつらえ、またたく間に普及したものである。もっとも、「家」観念が崩壊した現代においては、既存のマニュアルでは対応できないような冠婚葬祭の多様化が観測され始めた。ゲストハウス婚やレストラン婚、家族葬や無縁墓の増加はその最たる例だ。冠婚葬祭の分野は、もはやマニュアルに頼る時代ではなく、自分で自分の行動規範を決定する時代へと移り変わっていると言えよう。
全編を通してシニシズムを交えた軽妙な語り口で書かれており、岩波新書にしては画期的とも言える読みやすさが印象的である。第2章では別姓婚の話題など多分に感覚的な議論が為されている一方、葬送についての第3章は激しく現実的であり、本章自体一つのマニュアルとして通りうるほどだ。フェミニストとしての著者の顔が垣間見える。
①著者は冠婚葬祭(結婚式・葬儀)をめぐる三度の転機(明治30年代・高度経済成長期・バブル経済崩壊後)に着目することにより、“冠婚葬祭のひみつ”〈現在人口に膾炙している冠婚葬祭の「伝統」「しきたり・作法」は戦後出版され好評を博した“冠婚葬祭マニュアル”(塩月弥栄子著『冠婚葬祭入門』)によって創作されたものにすぎず、冠婚葬祭は「ファッション(流行)」「ビジネス(商機)」としての側面を多分に有するということ〉を鋭く抉り出す。
結婚と葬儀の最大の相違点は、結婚は婚姻する当事者二人が名実共に主役・主体(でありそれで完結する)のに対して、葬儀は死去した本人が主役でありながら通夜・告別式を執り行う主体は喪主をはじめとした遺族であり、葬儀の場面においては両者の意思の乖離が問題となり得ることである。とりわけ今日においては、葬儀の種別(樹木葬から散骨まで)も多様化しており、「本人の望む葬儀」と「遺族の望む葬儀」の不一致は少なくないだろう。原則として死者の意思が尊重されるべきであるのは論を俟たないが、筆者は第三章において、葬式費用のみならず死後の始末(遺品の処理)や臓器提供に際しての家族の同意が遺族に相応の負担を強いる事実を指摘し、「あなたの死は~(中略)~あなただけの死ではない」旨を我々に忠告する。
本書の後半部分では「事実婚・別姓婚」や「代々墓」についても紙幅が割かれているが、著者のフェミニズム的価値観が先行しているきらいがあり、実態に即した議論とは言い難いように思う。
②北村文、阿部真大『合コンの社会学』(2007)序:★★★破:★★急:★★
本書は、「合コン」をキーワードに、現代を生きる若者たちの恋愛と結婚を社会学的に分析した一冊である。
著者は、「運命的な出会い」を希求する若者が、「合コン」というこれ以上ないくらい恣意的なイベントに惹かれる構造的な矛盾を指摘した上で、その矛盾を隠そうと若者が洗練させた種々の技巧や協働関係について分析する。そして、出会いという本来の目的を潜在化して純粋に合コンを楽しむことの功罪を説いた上で、合コンという制度と私たち自身との関わり方――主体性の重要さ――に触れて本書の結びとしている。
本書が拠るデータは(わずか)31名の(しかも同階層の)男女へのインタビュー調査であり、量的アプローチは捨てて専ら質的アプローチに特化している。それゆえ説得力に限界を感じるのも事実だが、本書の役割は合コンに通う男女のリアリティの一部を切り取ることに過ぎないと豪語するその思い切りの良さには、ある種すがすがしさすら覚える。若者の俗っぽい所作からいちいち社会学的な示唆を得ようとするのは無理があるようにも感じるが、その胡散臭さは本書の問題というよりは社会学という学問そのものの宿痾か。
③高木侃『三くだり半と縁切寺』(1992)序:★破:★急:★★
本書は、「三くだり半」と「縁切寺」という江戸時代に存在した離婚システムを分析しつつ、それを取り巻く家族のエピソードを豊富な史料を基に考察することで、「女性は男性に全面的に服従していた」という江戸時代の男女に対する固定観念を掘り崩すことを目的としている。
従来の通説であった「夫専権離婚」を批判し、江戸時代の離婚の諸相を明らかにすることで浮かび上がったのは、活き活きとした力強い女性の姿であった。むろん、父権優位という建前はありながらも、夫婦の内実は我々が想像するほど夫の思うがままではなかったことが窺える。
有力説をひっくり返すことで発見した新たな女性像は極めて新鮮であるが、著者自身認めているように、やや結論ありきの議論になっている点は否めない。しかし、それを差し引いてもなお、多彩なエピソードを盛り込んだ本書の説得力の強さは揺るがないように感じる。
④碑文谷創『新・お葬式の作法』(2006)序:★★破;★★急:★★
本書では表題の通り、死亡から葬儀を経て法事に至るまでの手順・手続について詳説されているが、本書の醍醐味は礼儀・作法の表層的・形式的な解説ではなく葬儀儀礼の存在意義についての深遠な考察にある。
前述の齋藤(『冠婚葬祭のひみつ』)が商業的側面に主眼を置いて冠婚葬祭を論じたのとは対照的に、本書の筆者・碑文谷は宗教的側面から葬儀を位置付けることを試みている。
まず筆者は、「グリーフ(死別に伴う悲嘆)」という感情をキーワードに遺族の側から死を捉え、グリーフに対する内的な働きかけ(「グリーフワーク」=悲嘆を抑制せずに十分に悲しみ現実を受け容れること)の必要性を説く。そして、“グリーフワークの実践の場”、すなわち、“大切な人の死が現実のものであるという過酷な現実認識を遺族が自らに強いる場”として葬儀を位置付ける。
かかる見解を敷衍すると、厳粛性を喪失した葬儀は「遺族自身に対し、死の事実を突きつけることを弱くする」ことにより遺族からグリーフワークの機会を剥奪しかねないものとして否定的に解することとなる。
したがって、家族葬ブームなど葬儀を「ファッション」化する近時の風潮について、葬儀儀礼の存在意義を没却せしめるものとして筆者は総じて批判的である。
従来の葬式の過度の簡略化・略式化に対する警鐘は他の類書には皆無であり、この点については筆者の慧眼に感服せざるを得ない。葬儀の本質に迫る名著と評価できる。
⑤高橋純『「黒」は日本の常識、世界の非常識』(2011)序:★★破:★★急:★★
一見意味不明な表題であるが、「黒」とは日本の結婚式等フォーマルな場面において“礼服”として用いられることが多いブラック・スーツのことを指している。ブラック・スーツは日本ではフォーマル・ウェアとして通用するが、グローバル・スタンダードに照らせば略礼装にすぎず、さらに「黒」は喪の色であることからブラック・スーツで結婚式等祝いの席に参加することはヨーロッパのドレスコードを基準とすればルール違反になる。
日本人に対してヨーロッパ発祥の服装文化を錦の御旗のごとく振りかざす筆者の姿勢に違和感を覚える向きも見受けられるが、「洋装は日本のものでないのだから、日本人が勝手にアレンジしたり日本風に解釈したりすることは許されない」というのが筆者の一貫した哲学である。それゆえ、筆者は日本での洋装のカジュアル化についても極めて否定的な態度をとっており、洋装での礼装文化が未成熟な日本で洋装ルールを簡略化することは、ルールに対する「掟破り」ですらなくルールの「無知」にすぎない、と舌鋒鋭く批判する。
洋装文化に疎いと本書を十分に楽しむことは難しいが、礼服は自分のためだけでなく周囲の人間を不快にさせないために存在するという筆者の主張は、服装文化ひいては冠婚葬祭という「儀式」の文化について語る上で不可欠の前提といえるだろう。
コメントⅠ
冠婚葬祭とは古来より伝わる伝統儀礼であり、人生の節目そのものである。今でこそ「冠」と「祭」の重要性は薄れてきているものの、「婚」一つとってみても、その儀式的側面(①)、そこに至る過程(②)、そしてその終焉(③)、と社会学的考察の余地は大きい。
しかし、個々人が行うミクロな行為にマクロな社会学的意味を付与するという営為は、一定の限界を呈し始めたことも事実ではないか。確かに、明治民法下の家制度にがんじがらめにされたお見合い結婚はそれ自体高度に社会的な制度であった(①)。しかし、恋愛結婚が主流となった現代においては、結婚する当事者の目的はただ好きな人と恋愛を成就させて一緒に暮らしたいということに尽きる。新婚アツアツのカップルに対し、「君たちは家族集団を形成して将来の社会成員を再生産し、社会構造の維持に寄与しようとしているんだね!」などと囃し立てれば、グーで殴られること請け負いである。
他方、個々人の思惑を離れて、個人の行為の総和が全く異なる形で社会全体に影響を与えるということもまた、現実に起こっている。社会学の対象となる出来事や行為に対し、当事者の内面的な意味を把握すること、そして社会全体に対する意味を見出すこと――この2つのレベルの意味の相互関連は相当に注意深く吟味する必要があるように思う。結婚や葬儀の様式が多様化し、当事者の主体的意思決定の幅が広がりつつある現在、冠婚葬祭というテーマを通じて社会学の意義を再考してみたい。(大村)
冠婚葬祭の文化はその時代を生きる人々の価値観(①では家制度を中心とした家族観・③では江戸時代の男女観にそれぞれ着目している)によって形成・変容してきたといえる
そして近年、日本人の死生観(死に対する意識)も変化の兆しがみられる、という指摘がある(④)。かつては「長寿=幸せ」という単純な図式が成り立っていたが、医療技術の発達により延命治療が容易になった現在では「尊厳死」「安楽死」を望む人も少なくない。この背景には、“インフォームド・コンセント”の理念の浸透や少子高齢化社会の到来に伴う近親者の介護負担・医療費負担の増加といった問題があると考えられる。このような死生観の変化は我が国の葬儀文化にどのような影響を与えるだろうか。
また、冠婚葬祭と宗教の関係も興味深いテーマである。結婚式と宗教の関係性については希薄といえるだろう(①)。一方で、日本の仏教界は“葬式仏教”と揶揄されるように葬儀・法事といった葬送儀礼に大きく依存している。我が国の仏教が“葬式仏教”化した原因の一つは檀家制度にあると考えられる(私見)が、このような現在の仏教のあり方の是非についても考えてみたい。(樫村)
コメントⅡ
家制度が法定されていた明治時代に比べれば、現代の冠婚葬祭は多分に個人主義の色彩が強い。個人の自由意思が広く尊重される時代の中で、冠婚葬祭の形も変容しつつある。その一例が事実婚の増加だ。どうも、事実婚というスタイル自体は明治大正期からあったらしい(①)。しかし、「事実婚」というワードが大衆に膾炙したのは現代のことだ。まさに今、改めて結婚に対する法律の関与のありかたを問い直してみることには価値があろう。
もとより実定法は、人々がよりよく生きられるように設定した行動規範の総体である。こと婚姻においては、男女の結婚に法的扶助を施すことにより、将来の社会成員の再生産を促し、社会システムを維持するという純公益的な側面が強い。この理屈を通せば同性婚や近親婚は(法的には)禁止されるべきであろう。しかし、それでよいのか。
法的扶助さえ諦めればよいのだから問題はない、という議論はやや乱暴に過ぎる。問題は法的扶助の有無に留まらず、「世間並み」から外れることが生む周囲との軋轢にもある(①)。
法定された社会規範がパブリックスタンダードとして流通し、事実婚者や(事実上の)同性婚者をマイノリティーとして排斥する。こうした現実を見つめ直した上で、それでもなお現行法を維持すべきか。考えてみたい。(大村)
冠婚葬祭と密接な関係を持つ法制度として戸籍制度が挙げられる。結婚の際には婚姻届を、離婚の際には離婚届を、死亡の際には死亡届を提出する。
戸籍は東アジア圏(日本・中国・かつては朝鮮などにも)にしか存在しない世界的にも稀有な制度であり、戸籍により身分関係の明確性が保たれ相続手続や婚姻届・離婚届の提出手続を容易に行える等の利点がある。
他方で、戸籍が個人単位ではなく家族単位で編製されているため戸籍筆頭者がその集団の統率者であるかのような家族観を社会に定着させている点、戸籍はプライバシー性の極めて高い情報であるにも関わらず第三者による不正取得のおそれが否定できず結婚差別等の原因となりうる点などが批判されており、戸籍制度の改革・廃止を求める声も一部では有力である。現行の戸籍制度の是非について、夫婦別姓と併せて、考えてみる必要があるだろう。
また、コメントⅠで触れた“死生観”に関連する問題として「尊厳死・安楽死」のほか「脳死」が挙げられる。尊厳死・安楽死法制化の是非、(臓器提供時以外にも)脳死を一律に人の死として扱う法律案の是非についても議論の余地がある。(樫村)
ディスカッションの概要
コメントⅠについて
●社会学のありかた
「社会学はこじつけではないか」というファシリテーターからの問題提起について意見を募った。豊富なデータに基づいてはいても、そのデータからどのような結論を導出するかは純粋に解釈の問題であり、やはり社会学者の恣意を免れないとの意見が大勢を占めた。また、この現象は社会学のみならず人文科学全体に通底する問題であり、ひいてはあらゆる学問は解釈学に通ずるのでは?との疑問も浮かび上がった。
(先生のコメント)
社会学の役割は、いうなれば一意見の提示に過ぎない。そこにはこじつけの要素を含むことも当然ある。ただ、自説の胡散臭さに対する自己反省の意識があるかどうかが、社会学という学問と単なるエッセーの分水嶺になるのであろう。
●法学はscienceかartか
人文科学は果たして科学なのかという論点に関連して、我々が現在学んでいる法学すら、科学としての性質を有するか怪しいという意見が出された。一見緻密な論理で構成されているように見える法学もまた、ありうべき価値規範をいかに論理的説明で正当化するかという側面を有することは否めない。
(先生のコメント)
科学としての法律学(ex.法社会学)は50年代に流行ったが、これは敗戦によって実定法学に対する空しさが広がったことによる。その一方で、現実的な要請に押される形で法解釈学も活力を取り戻していく。
●死生観の変化が葬儀文化にどのような影響を与えるか
尊厳死・安楽死(が認められた場合にはそ)の際に家族へのグリーフケアが要請されるという意見が出された。また、死生観の変化の現実的なあらわれとして「生前葬」の普及・浸透が挙げられた。従来のように“生”と“死”をそれぞれ「点」として分断的にとらえるのではなく、“生”と“死”を自己の人生・価値観の実現のプロセスとして連続的に把握する視点が不可欠だといえるのではないか。
(先生のコメント)
死生観の変遷の背景には妊娠中絶技術・生殖補助医療の進歩・発達など“生”に対する価値観の変化が存在することが指摘できる。
●日本の仏教のありかた
葬式仏教、すなわち、宗教的世界観を喪失しているように思われる現在の我が国における仏教のあり方についても議論が交わされた。ここでは、仏教と権力の関係性についてきわめて興味深い考察が参加者から示された。民衆・武士の生活全般に関わりをもつことで彼らの救済を図ろうとした鎌倉新仏教が鎌倉時代に生まれ、その後、江戸幕府により仏教勢力が権力側に組み込まれ檀家制度等の既得権益に安住することとなり、その結果として従来の鎌倉新仏教が有していた民衆の宗教的救済という色彩を喪失したという見解である。
(先生のコメント)
葬儀等の冠婚葬祭儀礼に大きく依存している宗教は仏教に限られないものの、かかる宗教のあり方の是非については議論の必要性があろう。
コメントⅡについて
●異性婚は法律上認められるべきか
そもそも異性婚を国家が認めない理由が不明瞭であるとの指摘があった。結婚のような個人的な領域に法律が踏み込むのは不適切であり、異性婚もひいては近親婚も、法的に認めて差し支えないのではないかという意見が多くを占めた。
(先生のコメント)
同性愛については、現行日本法では刑罰を課されていない以上論じる余地はない。他方、同性婚については議論の余地がある。現実には、特別養子制度のように利用者が僅少な制度も存在するが、人々の要求には限りがなく、それを全て保護すべきなのか、という視点が欠かせない。
●戸籍制度の是非
戸籍と住民基本台帳の関係性・代替性について参加者から質問がなされた。下記③については、一定の限度で身分関係を公示することの必要性(たとえば、婚姻年齢を確認する場合など)は否定し得ないことから、戸籍を完全に非公開として一切の開示を認めないとする扱いは非現実的ということになるであろう。もっとも、戸籍の有する高度のプライバシー性に鑑みれば、公開範囲の限定は戸籍制度を存続させるうえで不可欠といえるだろう。
(先生のコメント)
将来的に住民基本台帳に記載される情報量が増加すれば戸籍の重要性は相対的に低下し得る。その上で、①身分を登録することの必要性、②(身分を)集団単位で登録することの必要性、③公開範囲をどの程度限定すべきか、の三段階に分けて議論すべきであろう。