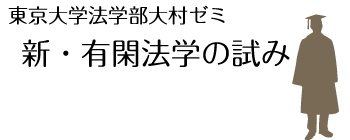都と鄙
報告者:青木・南
課題図書
①河西英通『東北―つくられた異郷』
②入江敦彦『やっぱり京都人だけが知っている』
③林家辰三郎『町衆―京都における「市民」形成史』
④隈研吾・清野由美『新・ムラ論TOKYO』
⑤王維『素顔の中華街』
課題図書の紹介
①河西英通『東北―つくられた異郷』序:★★破:★★★急:★★
①どのように自己を認識し、いかに他者から認識されてきたかという視点で、明治期に東北がいかに後進的な単一空間領域と成立させられてきたかを検討している。提示される史料からは実に多様な東北認識のあり方が描き出されていく。あるときには未開、あるときにはフロンティア、またあるときは一体的に、さらにあるときには非同質的に捉えられる。これらの多様なイメージが東北=後進地として社会に定着するのは20世紀に入ってからとしている。これらを踏まえて、結びとして著者は<東北>論の基本的視座を整理している。まず、一体的に捉えるのでなく、実地のレベルで考えること。さらに、種々の枠組みを超えたつながりに注目すること。加えて、固有の論理からの歴史の構成、またこれを過たない術を身に着けること。
多様性に注目すべしという主張にあまり目新しさはないが、このような認識の下で東北各地が今後どうなっていくのか楽しみである。「行くぜ、東北」どこに向かおうか。
①本書は「遅れた東北」「異境」などというイメージに着目し、東北の人々自身を含む様々な立場から東北がどう捉えられてきたのか、「東北」はどのように形成されてきたのかを紹介し、結論として東北をどう語っていくべきかいくつかの視座を提示しつつ、「想像の政治的共同体」としての国民イメージにも批判を加えている。東北の歴史を追う中で多くの人物や著作・記事が紹介されていくが、一つの時代を切り取っても捉え方は様々で、「野蛮な異境」と「豊かさを秘めたフロンティア」や「第一維新の敗北」と「第二維新の待望」など、対立・共存する観点が多々挙げられていることで、東北論として豊かな視点を提供してくれると共に、東北を一体のものとして捉える難しさを痛感させる。
本文中に、「大飢饉という異常時のイメージが東北固有の姿や歴史段階として伝えられた」、「凶作の報道が魅力あるイメージを消し去り、貧しくて遅れたイメージを植え付けた」というような記述があったが、未だ記憶に新しい震災についても同様の理論が凡そあてはまることからも、本書を今一度読み返してみる意義が認められるように思われる。しかし一方で、結論としては提示した視座を意識することで新たな歴史が始まる「気がする」と、曖昧に締めくくっており、当の視座も概して過去の論をまとめているに過ぎず、あくまで現状確認の段階に留まっている。またアイヌや東アジアに対する差別が東北差別と重なっていたという記述があったが、それらの比較対象にはあまり言及がない、そのような考察の余地も残している。したがって、本書を現状の改善に一役買わせるためには、紹介された歴史・視座の意味を咀嚼しつつ、もう一段階の議論を要すると思われる。なお、本書では主に1910年代までを中心に語られているが、続編の『続・東北―異境と原境のあいだ』ではさらに1945年までが対象とされ、筆者によると本書とは若干違った方向性も含まれているようなので、本書で提供された視座の実際を確認する過程では参考になるであろう。
②入江敦彦『やっぱり京都人だけが知っている』序:★★★破:★急:★
本書では京都・西陣出身の筆者が、「『一見さんお断り』に憧れる馬鹿が後を絶たない。だったら、京都自体を一見さんお断りにしてしまえ」と、京都に対するイメージが錯綜し、京都「風」で甘い汁を吸う「京都人モドキ」がはびこる現状への憂いを露わにし、前作『京都人だけが知っている』に続いて、我々「よそさん」に真実の京都を知らしめんと奮起している。章ごとに「言葉」や「京おんな」、「魔」や「ラーメン」など親しみやすいテーマに着目し、筆者自身の体験を多分に含めつつ、京都あるいは京都人の本質を暴こうと試みている。仄めかされる「隠れた京都」はテーマにより様々だが、全体を通して、表面上は柔らかい様子(いわゆる「はんなり」)でも、実は人を値踏みしていて試すようなところがあり、かといって想像されるほど保守的ではない、ちょっと「意地悪」な京都人の姿が浮かび上がっていた。
京都の新たな一面に多角的に触れることができる面白い本だが、筆者自身京都に関するステレオタイプを否定しようとするあまり、「京都」らしいテーマばかり取り上げることになり、結果的にステレオタイプの再生産に繋がっている節もある。また本書の性質上仕方のないことだが、筆者の体験談に基づいた、趣味のお話とも言える視点が多分に見受けられるので、いまいち示唆には欠けているし、主張の強い本書のみによって京都像を形成しすぎないよう注意が必要である。しかし、筆者の軽快で歯に衣着せぬ物言いや京都体験談は大変読むに易しく、むしろ一風変わったガイドブックとして十分楽しめるものである。章ごとにテーマも様々なので、ご旅行の際には関心に沿ったものだけでもご一読いただければ、新しい京都の楽しみ方を発見できるかもしれない。
③林家辰三郎『町衆―京都における「市民」形成史』序:★★破:★★急:★★★
本書も②と同様京都の文化に関わりが深いものだが、その時代背景も語り口も大分異なっている。本書は京都の独特の町名にその痕跡を残す「町衆」という存在に注目し、副題にあるように、主に京都における人と人との歴史を「ムラ」の誕生期から「町人」階級が成立する江戸時代に至るまで概観している。四章までで平安時代の隷属的な「京戸」→律令体制解体期の自立的・批判的な「京童」→南北朝時代からの集団的地域生活のなかに組織された「町衆」という大まかな流れを追いつつ、政治や見世物、宗教など人々の生活との相互的影響の中で共同体の意義を語り、五章から七章で歌や踊、宗教などの文化の変遷に特に着目した後、八章で江戸時代の特権的な門閥商人を中心とした「町人」へとつなげ、市民意識のあり方を語って結んでいる。
上のような一本の流れの中で京都やその文化の発展、宗教や一揆、政治の動きなどを生き生きとしたものとして捉えている点で、興味深い部分は多い。しかし一方で、冒頭で現代(本書は昭和39年著)において京都の歴史性や芸術性を蔑ろにする開発、文化破壊が行われていることの原因を、「行事や芸能を育ててきた地域的共同体が、急速に解体しつつある」ことに求めつつも、現代との関連性や共同体の解体に関する記述は少なく、さらに結論としても市民社会の前提条件としての民主・自由・平等へ繋がるものとしての町衆を示す、棘の無い主張に留まっている。これらの点で些か物足りなさを感じるが、地域における人間関係の希薄化が進んでいる現在において、近代にかけて人々の社会的関係性が何を動かし、何に動かされてきたのかを考えることは、有意義なことであるように思われる。
④隈研吾・清野由美『新・ムラ論TOKYO』序:★★★破:★★急:★★
空間の商品化やグローバリズム、経済至上主義など、現代の社会システムの限界が指摘されることは少なくない。本書は、それらの問題に対して「ムラ」の可能性を論じている。「ムラ」とは、「固有の場所であり、多様な生き方と選択肢のよりどころであり、人が存在する価値を『エコノミー』ではなく『ライフ』に振り戻す地域」、あるいは端的に「その場所と密着した暮らしがある場所」であるとしている。構成は建築家の隈研吾とジャーナリストの清野由美が「ムラ」を実際に歩きながらの対談が大半で、実際に生活する人々と土地との結びつきが二人の街歩きの中で描かれていく。
対談という形式の問題もあり、必ずしも精緻な議論ばかりでなく飛躍した論理も多いが、それでも、土地の歴史と現代社会システムとの摩擦、その中で生活する人々を見る目には興味深い発想がある。
⑤王維『素顔の中華街』序:★★破:★★急:★★
長崎、神戸、横浜の三つの中華街の成立からその変遷を追いつつ中華街とは何かを明らかにしようとしている。さらに、現在につながる活動として各地の町おこしの事例を紹介している。町おこしの直接のきっかけは合理的経済利益の追求であったが、意図的に選択されたエスニック・アイデンティティの創出がエスニシティの再編につながったという見方は興味深い。さらに、三つの中華街の比較の上で、横浜では華僑居住者の多さやその密集性から結束力が強く、華僑のみが主体となっているのに対し、神戸、長崎では華僑と日本人の割合は半々ほどで「町おこし」という利益が共有されているという。この状況の是非はまた問題ではあると思うが、町おこしや異文化理解に一つの指針となるのではないか。
コメントⅠ
都と鄙といった時に対比されているものは、時代や場所により、一様でないということを一連の課題本を通して感じた。特に現代の都市の問題をとらえるのであれば、④が現代の都市が抱える問題とその中にあるムラの可能性を示している。一方で、過去の都を扱った③を見ると、生き生きとした町衆の文化が花開いた都には現代のような問題は見られないようである。しかしながら、農村と都市商工業者の対立や商工業者間の格差の問題が生まれることになる。また、①では、東北が多様なイメージから離れ、異境として位置付けられていく。しかし、⑤では、中華街が町おこしの取り組みの中で観光地としての地位を得ることになる。
都市に埋没してしまう個人や、ロードサイド型店舗の立ち並ぶ均質化した街並み、過疎に陥る村など、現在指摘されている問題は多々あるが、都鄙の関係性をどのように捉えていくと良いのか考えてみたい。(青木)
今回のテーマは都と鄙、すなわち都会と田舎の二項対立だ。しかし地域や時代によって、これら二つの言葉がそれぞれ有する意味合いや、その相克が生み出すものは様々である。①では、主に「先進的な西南」に対するものとして「後進的な東北」の自己認識や他者認識の対立や変遷が紹介された。②では、長きにわたって「ミヤコ」であった京都が内包する「イナカ」的な空間・人付き合いの魅力が語られた。③では、これも都たる京都について、その歴史の形成に深くかかわってきた共同体「町衆」の変遷を追った。④では、現代では「鄙」の特徴として意識されがちな「ムラ」性に焦点をあて、主に都市計画の観点から、それぞれの町に内在する、所謂お役所的な開発と「ムラ」的な開発(あるいは現状維持)の痕跡や展望を検証している。⑤では、ある意味中国と日本という二つの背景をもちつつも、居住地として、また観光地として一定の成功を収めている中華街を舞台に、華僑たちの活動のダイナミズムに迫っている。
以上のように、五冊の中で都と鄙は対立するものとして必ずしも登場していないが、一つの共通するキーワードとして「共同体」というものが浮かび上がってくる。今日では、特に都市部において血縁的・地縁的な共同体は縮小・消滅する傾向にあると言われる。一方で、田舎への旅行・移住を志向する人々には、人同士の密な繋がりへの憧憬も内在するのではないだろうか。我々の周りにはどのような共同体が存在するのか、その性質には地域性があるのか、共同体は今後どのような道を辿り、何をもたらすのか。こういった問題も都鄙との関係性の中で論じてみたい。(南)
コメントⅡ
地方創生が議論されている。東京一極集中と地方の衰退は問題とされて久しい。バブル期のリゾート法による開発の失敗など、試みがなされてはいるがうまくいかないものが多いのが現状だろう。その中で、地方自治体の権限の強化も議論されている。地方の固有の事情に配慮するという点ではもちろん自治を広く認めていく必要があるだろう。しかし、リゾートなど都市とのつながりが必須であるようなものを志向していく地域であれば関連都市との連携は欠くことができない。どのような単位で自治の権限を強化し、どの範囲の権限を持たせるべきなのか考える必要があるだろう。
また、迷惑施設の問題などは都市の利益と地方の利益の調整の必要から法が整備されている。地方の利益と都市の利益、全体の利益のバランスをどのようにとっていけばよいのだろうか。(青木)
人口減少と東京一極集中による国力低下が危惧される中、先日地方創生関連2法が成立した。現時点ではまだ理念的な内容に留まっているが、少なくとも国全体の意識が地方の活性化に向けられつつある。だが国があくまで調整機関であることもあり、その手法は地域性を無視した画一的な開発や、補助金のばら撒きによるハコモノの乱立に終始する傾向にあるのは、④でも論じられているし、竹下内閣の「ふるさと創生1億円事業」の迷走も例に挙がる。一方で、地方を野放しにすることによる財政の不健全、生活インフラの欠損等は看過できない。笹子トンネルの崩落は記憶に新しいが、あのような公共施設の老朽化対策等にも国の財政的支援や計画的管理が必要となってくる。
このように、地方の機能維持には国の関与を除くことはできない場合がある一方で、地方の振興を考える上では、少なくとも土着の文化に価値を見出す観点からは、画一的になりがちな国の関与は望ましくないと主張される。国が法律という政策ツールを用いて、地域の望ましい形での振興に寄与しうるのか、望ましい振興とは一体どのようなものか、そしてそもそも地域振興に向けて国が旗を振る必要性はあるのか。「地方創生」が共通語となりつつある現在、一度立ち止まって考えてみる意義はあるだろう。(南)
ディスカッションの概要
前半では、主に現代において都会(都)と田舎(鄙)という構造を想定しつつ、それぞれにおける共同体のあり方について議論した。まず田舎における密な地縁的・血縁的な共同体、都会における希薄な人間関係というステレオタイプを提起したが、これについては各自の具体的な経験に基づき、実情はそう単純に二極化しているわけではないことが分かった。次に我々が地域的共同体に求めるものは何かという話題になり、心のふるさとが欲しい、いざというときに助けてくれる、ドロップアウトした人間の受け皿になる、社会的立場同士の関係性ではないところに繋がりが欲しい、などといった意見が挙げられた。ここでは、一般的に田舎にイメージされがちなセーフティーネットとしての密な繋がりは、束縛されているということでもあり、一方都会に多く見られる個人の機能的側面以外の個性の捨象は、コンテクストに縛られず自由であることをも意味しているのだから、一概にどちらが良い悪いとは言えないという議論もなされた。
前半の最後では、都会に田舎的な共同体を形成することは可能かという議論になった。都会では、田舎における共同体の代替として、24時間営業の店や運転手などの職業、多くの託児所などがセーフティーネットとして設けられているのではないかというところから、大学における交流の場としての寮やビリヤード場、地域における交流のきっかけの場としての公園が例として挙げられ、それぞれが共同体形成にどの程度寄与し得るのか、という点については意見が分かれた。また、流動性の高さという都会の良さを確保しつつ拠点としての交流の場を設けることの可能性や、あるいは自然発生的な共同体には限界があることを前提とした、生活保護などの社会保障の観点からの救済措置の必要性も提起された。この中で、都会のように流動性が高まり競争が激しくなることで、あぶれる人々が発生するという点は、いずれの意見にも共通していた。
以上のように、共同体というキーワードに若干焦点を当てすぎた議論ではあったが、各地の社会の性質を都会と田舎といった区別に結び付けて一般化することは困難であることや、流動性の高まる社会において、(共同体という形ではないとしても)何処かに繋がりを保っておくことが求められている事実とその理由がはっきりしたように思われる。
後半では、近年話題にのぼることも増えた地域振興などにつき法制度を議論した。国の役割と地域の役割、地域の意思形成やその調整が主に議論の的となっている。
街づくりにおける国と地域の関係について、「合理的」な発展のために中央が主導的な役割を果たしていくという考え方がまず示され、それとの対比の中で、さまざまな意見が述べられた。「合理的」な発展については、特に集約的な大型店舗と地域の商店街を比較しつつ、経済合理性、地域の雇用、地縁的結合の外の住民などさまざまな問題が提示された。前半の共同体の議論を前提にしつつ、商店街や共同体に参加しており、その利益を受けられる人と、共同体に参加せず、単純に便利さを求めている人の違いがあるという指摘があった。
さらに、何を重要とすべきかがそもそもわからないという指摘もあった。この考えからは、地域にノウハウを伝えていく国の働きかけの必要なども指摘された。
大規模小売店舗法の例から、地域の利益に対して海外との関係による限界も指摘された。経済的な規制の根拠に共同体の保護を据えることができるか、他の根拠はどんなものがあり得るかということも話題に上っていた。
どの利益を重視するか、どの機能に注目するか、一般的に捉えるのではなく、各地域の特質から何が重要かを問題にしていく必要があるという方向の議論であったように感じる。今回の議論では、一般的に街として議論してしまったが、住民の構成や産業の構造、さまざまの要素を検討して街づくりをすべきで、それぞれのイメージする都市像の違いで議論が食い違ってしまった部分もあったかもしれず、より具体的に街の例を示して議論しても深みが出たかと反省した。
先生からは、まず、共同性については人の流動性の有無との関わりという点を話していただいた。さらに、都市について、人の側からだと共同性として捉えられるが、場所の側から見ると集積性があり、それゆえに生まれる変化があるのではないかという指摘もいただいた。法との関わりでは、合意の形成について、マンションの区分所有と再開発を例にしながら、多数決と少数派の離脱といった技術をどう用いるかということを話していただいた。規制については、規制を強化する論理として、フランスのアンチアマゾン法では、文化というラベルで経済に規制を加えているという例を挙げていただいた。