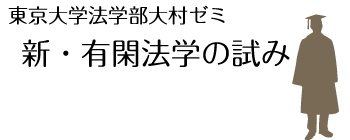皇国としての日本
報告者:飯田・木下
課題図書
①米窪明美『明治天皇の一日』(2006)
②古川隆久『皇紀・万博・オリンピック』(1998)
③原武史『皇居前広場』(2007)
④栗原俊雄『勲章』(2011)
⑤溝口睦子『アマテラスの誕生』(2009)
課題図書の紹介
①米窪明美『明治天皇の一日』(2006)序:★★★破:★★急:★★
①明治天皇の日常生活を平易な言葉と親しみやすい文体で描いた著作。他の課題本と比べると非常に読みやすい。明治天皇は日本の近代化の象徴のように捉えられがちだろう。しかし、本書から浮かび上がるのは古色蒼然たる公家社会の伝統と近代日本の間で揺れ動く明治天皇像である。当初は「奥」すなわち「御内儀」と「表」すなわち「御学問所」とが対比されているように読める。しかし、読み進めていくうちに御学問所にも前近代的な伝統が残存していることが明らかになっていく点が面白い。
ただし、副題を「皇室システムの伝統と現在」としておきながら明治天皇崩御後の状況を第七章に押し込めてしまったのは少し残念ではある。明治宮廷が固守してきた伝統が次第に消失していったのは分かるのだが、そこから現代の皇室問題に対していったいどのような示唆が得られるのだろうか。その点に付き著者の意見を明確にして欲しかったと思う。
①著者は本書において明治天皇の何気ない一日を追いながら、伝統と改革のはざまに揺れる天皇家の苦悩に迫る。明治天皇の側近であった者たちの回想や手記からは、豪華で何一つ不自由のないというイメージからはかけ離れた、質素で規則にがんじがらめにされた天皇の生活ぶりが明らかになってくる。また宮中は厳しい身分制度が徹底された社会であったが、それは決してその頂点に君臨する天皇にとって有利なものではなく、むしろ不自由を強いるものであったことが分かる。近代化する明治の世において電気を使うこともなく、ひたすら旧来の伝統を守り続ける姿や、厳しい身分制度の中で臣下に迷惑をかけまいと、自らの自由を犠牲にする姿からは伝統と合理化の間で揺れる天皇の苦悩が読み取れる。
結果的に大正・昭和を通して宮中の伝統の多くは消えていくこととなるが、現代の皇室も皇太子妃雅子殿下の健康問題や皇室典範の改正問題を抱えており、本書はこうした問題における天皇家の苦悩の本質を示唆するものとなっている。
②古川隆久『皇紀・万博・オリンピック』(1998)序:★★破:★急:★★★
本書は「皇紀」等の皇室ブランドが経済発展のための象徴あるいは「正当化事由」として利用されてきたさまを描く。とりわけ、「紀元二六〇〇年=西暦一九四〇年」を名目にして計画された東京オリンピックと万国博覧会が話題の中心となる。また、神武天皇を祀る橿原神宮を中心に据えて観光立県を目論む奈良県の興味深い動きにも触れている。もっとも、戦時色が強まる中で政府は皇室ブランドを国民精神動員の手段として位置付けていく。それでも国民の本音は皇室ブランドを利用した経済発展にこそあったと本書は指摘する。
戦前の日本は軍国主義へひた走るものとして捉えられがちだが、むしろ本書から浮かび上がるのは各省庁から商工業者にわたる大小様々なアクターが生々しい自己の利益を追求してうごめく、現代とさほど変わらない社会の姿である。当時の日本を天皇盲信の全体主義と単純に捉えたり、あるいは戦後日本との断絶を強調し過ぎたりすることは、皇国日本を見誤る原因となってしまうといえるだろう。
③原武史『皇居前広場』(2007)序:★★破:★急:★★
筆者によれば、「本書は、(中略)特定の政治空間を主人公として描く近現代日本思想史の試みである。本書は宮城前広場あるいは皇居前広場で繰り広げられてきた種々の営みをその背景と共に物語る。
昭和前期に広場は「無駄な空間」から天皇の神性を演出する「聖なる空間」へと変貌する。しかし敗戦後は一転して進駐軍と左翼(、そして「アベック」たち)がそれぞれの方法で使用する自由な空間になった。当初は進駐軍と左派勢力は互いに承認し合う関係にあったが、所謂「逆コース」の時期になるとGHQ及び政府は皇居前広場をメーデーに使用させない方針を採るようになった。そして1952年5月1日の「血のメーデー事件」を迎えることになる(関連して、集会の自由に関する判例として著名な皇居外苑使用不許可事件(最大判昭28・12・23民集7巻13号1561頁)を参照してほしい)。同年4月28日に日本は独立を回復していたから、広場からは進駐軍も左翼も姿を消すことになった。その後広場は「空白期」を迎える。
さて、本書によれば深沢七郎の『風流夢譚』が終戦から皇太子成婚記念パレードまでの皇居前広場の記憶を踏まえており、ロラン・バルトが『表徴の帝国』で「空虚な中心」として皇居を捉えた時期はまさに皇居前広場の「空白期」に当たるという。ある空間の歴史をその誕生まで遡って通観することにより、その空間を巡る事件や表現をその背景を踏まえて理解できるようになることが本書の醍醐味といえるだろう。
④栗原俊雄『勲章』(2011)序:★破:★★急:★★
毎日新聞の記者であり、「国家とはなにか」というテーマで執筆活動を行う著者の三冊目の新書であり、勲章をはじめとする栄典制度の変遷を紹介する。第1章から第4章では、外交上の必要と「天皇の藩屏の創設」という目的のためにつくられた日本における勲章の歴史的変遷を、その時々の制度への批判も紹介しつつまとめ、5章では現在の栄典制度の選考の仕組みを、7章では勲章が売買されている様子を伝えている。興味深いのは6章の「国家との向き合い方」であり、勲章を受け取った人・受け取らなかった人の勲章に対する考え方を国家との向き合い方という尺度から考察しており、著者のテーマに沿った部分である。勲章に対する必要性の主張や批判は随所に登場するが、栄典制度に対する著者の主張ははっきりと示されておらず、議論の紹介に留まっている。法との関係からは栄典制度が、現在でも明治時代に出された太政官令や勅令で運営されている点が重要であるだろう。
⑤溝口睦子『アマテラスの誕生』(2009)序:★★破:★★急:★
本書は、アマテラスはいつ国家神となったのかをテーマとしており、著者は長い間日本の皇祖神・国家神であるとされている天照大神は当初、その地位にはいなかったという主張を行う。前半では記紀の天孫降臨神話と北方ユーラシアや朝鮮半島の支配思想に共通点を見出し、外来神であるタケミムスヒが皇祖神の座についていたと説明する。そして後半において、土着神であり地方神であったアマテラスが天武天皇の時代に政治的な背景や理由から皇祖神・国家神の立場に据えられたと考察している。記述においては他の学者の研究や主張が多く登場し、複雑で分かりやすいとは言えないが、アマテラスが国家神へと変貌する過程には一定の説得力があるように思える。
コメントⅠ
そもそも「皇国」とはなんだろうか。広辞苑によれば「皇国」とは「天皇の統治する国の意」であるという。とすれば、「皇国としての日本」は少なくとも昭和天皇が統治権の総攬者から単なる象徴へと移行した時点で終わったといえる。
しかし、我々は「皇国としての日本」と「皇国でない日本」との間に断絶を見出す傾向があるのではないだろうか。あるいは「皇国としての日本」を誤解していやしないだろうか。今回の課題図書はそんな疑問を抱かせてくれるものが多かったように思う。
例えば、明治天皇というと口髭をはやした軍服の厳めしい姿をイメージする人が多いと思うが、米窪の著作はそんな近代的君主像を揺さぶるものであっただろう。また、原や古川の著作から見える「皇国としての日本」の内実は、現在とさほど変わらないいきいきとした社会だ。ともすれば我々が戦前の日本に対して抱きがちな全体主義的イメージが日中戦争激化から敗戦に至るまでのごく短い時期にしか当てはまらないことがよくわかるのではないか。(飯田)
今回の課題本である5冊はいずれも天皇(皇室)と国家というものをテーマとしていたが、中でも天皇(皇室)と臣民/国民との関係という視点で書かれているものが多かったように感じる。「皇国としての日本」という国の捉え方は戦前に国民統合と戦争動員のために用いられたが、敗戦後には天皇は国家元首ではなくなり、そのような捉え方はあまりなされなくなっているというイメージがある。
しかし②では万博を巡って地域の利益誘導のために皇室ブランドを利用する市民の姿が描かれ、④では天皇から授与された勲章が売買される様子が描かれているように、「皇国」というのは建前のようにも感じる。その一方で③では皇居前広場や地方行幸で天皇の登場に熱狂し、万歳三唱を行う国民の姿も描かれている。また現在でもニュースや新聞では連日、皇室の動向が取り沙汰されている。果たして戦前の日本は本当に「皇国」であったのだろうか。現在の日本はどうなのか。考えたい問題である。(木下)
コメントⅡ
「皇国としての日本」と法を関連付けようとして、とりあえず明治憲法を持ち出すのは味気ない気がするので、課題図書の中に登場した法令をいくつか拾い上げてみたい。
まずは刑法第187条(富くじ発売等)である。古川の著作によれば皇国としての日本は戦後日本に負けず劣らず博覧会好きだったようだ。しかし財源には余裕が無いので入場券に富くじを付す案が幾度も検討されたという。もっとも刑法で富籤行為を厳重に処罰していた手前そう簡単に政府が富くじを発売するわけにもいかず、結局「割増金付回数入場券」は皇紀二六〇〇年を名目にした万博に至ってようやく発売された。なお、もっぱら地方財政と戦災復興を正当化事由として戦後には「当せん金付証票」が発売されるようになった。
次に、国立公園法である。国立公園構想自体は地方経済の振興を目的に一九一〇年代には既に存在していた。そして、国民の保健休養・教化とともに外人観光客を増やし外貨獲得を促進することを目指した国立公園法は一九三一年に公布された(なお、柳条湖事件は同年9月の出来事である)。
「皇国としての日本」で形成された法や制度の中には現在に至るまで受け継がれているものがある。法制度の面では憲法などを例外として「皇国としての日本」と「皇国でない日本」の連続性を看取しやすいのではないか。(飯田)
皇室と関係の深い法といえば皇室典範であるが、平成に入り皇室典範の改正が盛んに議論されるようになっている。最大の論点は女性天皇・女系天皇を認めるかどうかであり、皇位継承資格者を確保するために皇位継承順位も含めて問題となっている。男女平等が叫ばれて久しい現代の社会の状況を考えれば、女性天皇・女系天皇が認められてもおかしくないと思われるが、①でみたように皇室には伝統というものが重くのしかかる。「伝統」と「革新」の間に揺れ動く天皇家の苦悩を理解したうえで、この問題を考えなければならないと思う。
また勲章制度の根拠法が存在しないという現状に対して、栄典法を制定すべきなのかということも議論の余地があるだろう。(木下)
ディスカッションの概要
前半部分では「皇国」とは何かという点について議論を行った。広辞苑の定義によれば「皇国」とは「天皇の統治する国の意」であり、明治期から戦中までは日本が皇国であったということについては共通認識があったように思えるが、江戸時代以前や現代を皇国と捉えるのかどうかについては意見が分かれた。天皇が統治権をもつ国を皇国とすると江戸時代や現在の日本は皇国ではないということになるが、統治権力にこだわる必要はなく、天皇のもつ権威や影響力を考えれば江戸時代以前や現代も皇国といえるのではないかという意見も見られた。また時代によって天皇の権威や影響力に差があることから、皇国性に濃淡があるだけであって、どのように歴史を切り取り評価するかによって皇国であるか否かは変化するのではないかという議論も行われた。
結論としてはまとまらなかったが、天皇の権威と影響力は時代によって濃淡があるものの、時代を超えて存在するものであり、「皇国」をどう定義して歴史をどう評価するかが問題になるように感じた。
後半部分は皇室典範の改正問題に関して、皇位継承者の問題、女性天皇・女系天皇の問題について議論した。まず継承者が不足していることに関しては皇位継承範囲が狭すぎるという意見がなされ、女性・女系天皇の問題とは切り離して議論が行われた。議論においては、天皇家とヨーロッパの王室の比較を行いながら、皇位継承範囲を拡大も考えられるという意見と、それに対して天皇は万世一系であることに正統性を負っているので、王室と異なり血筋が重要なのではないかという意見が見られた。また女性・女系天皇を認めるかについては、女性天皇は歴史上存在することから認めてもいいという意見が多かった一方、女系天皇については、万世一系であるという伝統が天皇家の存在価値であることを考えると認められないという意見と、伝統があることは認めるが、伝統は変遷するものであり、現代社会における皇室の在り方を考えると認められるべきという意見に分かれた。
この議論に関しても結論は出なかったが、「伝統と現代社会への適応」という共通本のテーマとなっていた問題が、ここでも重要になっていることが感じられた。
最後に大村先生よりコメントをいただき、問題の整理や他国との比較の仕方についての意見をいただくとともに、天皇家の文化の担い手としての立場や、天皇と国家の関係・天皇家と一般家庭との関係、皇位継承と民法上の相続の比較といった新たな視点を提供していただいて、議論は終了となった。普段何となくタブーとされているようなところにまで踏み込んで、天皇と国家の関係について考える良い機会になったと思う。