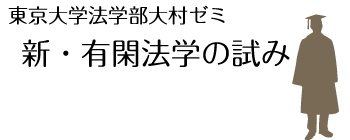イスラーム
報告者:名取徹・森本大貴
課題図書
①内藤正典『イスラムの怒り』
②大川玲子『イスラーム化する世界』
③藤村信『中東現代史』
④小岸昭『離散するユダヤ人』
⑤川田順造『マグレブ紀行』
課題図書の紹介
①内藤正典『イスラムの怒り』序:★★破:★★急:★★★
ムスリムは何に怒るのか、ということを非ムスリムの立場から冷静に見極める必要性から書かれた。著者の現職は同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授、現在の関心はトルコ及びトルコ系移民の暮らすヨーロッパで、フィールドワークを重視して研究を行っている内藤正典である。
本書は序章でジダンの頭突き事件を例に取り上げ、なにがいったい彼をそこまで怒らせたのか、という問題を扱う。ここで問題提起されているのは私たち日本人を含む西欧的な価値観を持つ者からは捉え難い、イスラムの世界観である。
まず第一章では「テロとの戦い」の失敗というテーマが扱われているが、その原因として著者は西欧側のイスラムに対する間違った理解や単純化をあげている。具体的には「原理主義者」というイスラム側からは理解できない類型化や、戦闘員?市民という西欧的なものの捉え方の押しつけが結果としてイスラムの怒りを大いに買ったのだとする。そして後章ではなぜこのような偏見が西欧で生まれたのかを、キリスト教徒の歴史的な対立、近代的合理主義的見地、植民地支配、移民問題の4つの観点から考察を加え、イスラムへの軽蔑の出発点を不合理な嫌悪感だと主張する。これらを踏まえた上で、第四章で筆者はイスラム教へのステレオタイプの典型として男尊女卑を話題に、イスラムの世界観に基づいた「反論」を行って読者に理解を求め、十分な相互理解が行われていない現状を指摘し、終章でムスリムに何をしてはいけないのかを提示している。
本書はイスラムの視点からムスリムが見ている世界の理解を読者に理解してもらうように務めている点が評価できる。その一方で、本書そのものが前提として「偏見を持った西欧vs十分に理解されないムスリム」という不公平な図式の中で描かれており、中立性を装いながらも終始イスラムを擁護する立場にあることには注意が必要である。さらに結論としてあげられている点は、結局は相互尊重、異文化理解といった点で平凡であり、それに気づいてか、最後は小咄で上手にごまかそうとしている点が気になる。
①「イスラム教徒はなぜ怒るのか」というシンプルなフレーズの下、筆者はイスラムに対する様々な「誤解や偏見」を解いてゆく。まず、序章において筆者はジダンの頭突き事件を取り上げ、イスラムの価値観と「われわれ」の価値観が大きく異なっていることを示す。そして、この不理解こそが「ムスリムは好戦的で怒りっぽい」というイメージの原因、延いてはイスラムが関係する現在の諸紛争の根源である、との主張を展開する。第一二章は序章で提示したテーマの肉付けといえ、「イスラムにおける戦闘員、非戦闘員の区別は成年男子か否かである」など、イスラムの価値観や伝統が紹介される。次いで三章では、かかる価値観や伝統に対して「われわれ」が不理解や嫌悪を抱くようになった(歴史的)経緯を、様々な観点から明らかにしようとしている。そして、続く4章では、イスラムの文化・伝統が「人権を抑圧している」との批判は、実はイスラムの価値観に従えば失当であり、「われわれ」の価値観の押し付けにすぎない、との主張を展開する。(あるいは一部の極端なムスリムの行為であり、イスラム教・イスラム教徒自体の問題ではない。)このように、イスラムに対する「誤解」を解いた上で、最終章において、筆者はそれらに対する理解と尊重を求める。
芸人全裸事件に関して「確かに芸人に落ち度はあったとは言え、相手が共有していない教義で以って『これは神の教えだ』と言ってリンチを加えるのは、少なくとも異文化理解という観点からは問題があるのではないか」とか、「総じてイスラム側の立場を擁護しすぎではないか」とか、「ジダンの一件はこの本とあまり関係がないのではないか」とか、本書を批判しうるポイントは少なくないように思われる。ただ、この本が出版された時代(時代というほど古くはありませんが)におけるイスラムに対する理解の程度を考えれば、このような立場でわかりやすい本を出すこと自体が、アンチテーゼとして画期的だった(と思う)ことは差し引いて考えるべきではないか。もっと言えば、本書が「一昔前の本」と評されることは、この本が使命を果たしたことの、一つの証左と言えるかも知れない。
②大川玲子『イスラーム化する世界』序:★★破:★★★急:★★
クルアーン解釈の方法論をベースに書かれた本。伝統的な伝承解釈と対比する形で、本書では4人の現代の解釈者を紹介している。サブテーマであるグローバリゼーションとの厳密な関連性は不透明だが、グローバリゼーションの中で個人に依拠した多様な解釈が生まれる土壌ができたという理解でいいだろうか。それぞれの解釈者の解釈の議論をクルアーンの中の具体例を用いながら紹介する点は面白い。しかし注目するべきはそれぞれの解釈者が女性、ムスリム・マイノリティ、政治状況、地理的環境などの個人的な文脈を出版点に、それぞれ困難を乗り越えるためにクルアーンの解釈を行ったという点である。結果としてある者はよりラディカルに、ある者はよりコンサバティブになっていったが、単純に善きムスリムとしてクルアーンの教えを受け入れたいという段階から、グローバリゼーション時代の中で直面する諸問題に対して、その解決策をクルアーンから得たいという動きがでてきているという指摘は興味深く、日本人の持つイスラームへのイメージをより活き活きとしたものへと変える。
③藤村信『中東現代史』序:★破:★急:★★
丁寧に20世紀のこの地域の歴史を概観しており、知識不足の人にとっては役立つ。特筆するべきことはないが、97年段階で、2001年の同時多発テロとその後の西欧とイスラムの対立について予言するかのようなことが終章に書いてある点は興味深い。
④小岸昭『離散するユダヤ人』序:★破:★急:★
本書も紀行文。マラケシュ、カイロ、エルサレムと、エクシールによって散った、ユダヤ人の足跡を辿っている。「イスラームなのに、なぜユダヤ人?」と疑問に思われた方がいらっしゃるかもしれないが、本書をお読みになれば、イスラームとユダヤの極めて緊密な関係が明らかになり、ご納得いただけるのではなかろうか。ただし、本書の文体が極めて淡々粛々であるところ、少なからぬ人に冗長との印象を与えることは間違いない。そこで、本書を紹介するにあたり、イスラームに関連する部分を中心にしたいなぁとの願望を抱きつつ、興味深かった(少なくとも私には相対的にそのように思われた)記述をいくつか抜粋する形を取りたいと思う。ⅰ1993年(!)に進展したモロッコ・イスラエルの関係改善の裏には、モロッコにおいて隠然たる力を有する、ユダヤ・パワーの影響があった。 ⅱカバラ思想というユダヤ神秘主義の一種が、ベンヤミンやシェリングなどに影響を与え、ハーバーマスによって「驚くべき事態」として指摘された。(ただ個人的見解を申しますと、そもそも西洋思想自体がヘブライズムの大きな影響を受けているわけですから、カバラ思想とかいう、ヘブライズムの小さな支流の影響をわざわざ指摘する必要があるのかな、とは思いました。)ⅲ徳富蘆花がイェルサレムに訪れたことがあり、漢文訓読調のコメントを残した。さぞ立派なコメントを残しているのだろうと思いきや、事実は「イェルサレム、汚いから焼きたい」程度のことしか言っていない。(ちなみに、彼が旧制一高(現在の前期教養学部に相当)の弁論大会に寄せた「謀叛論」は非常に名文(正確には名講演)です。岩波から出ていて、短いので一読下さることをおすすめします。)
⑤川田順造『マグレブ紀行』序:★破:★急:★
本書は、文化人類学者である著者が、アルジェリア、チュニジア、モロッコ、イベリア半島南部と巡った際の紀行文である。ご存じのように、マグレブとはジブラルタル海峡を挟んで、イベリア半島と向かい合ったアフリカ北西部のエリアのこと。また、当該地域がイスラーム史において、極めて重要な地位を占めてきたことは、レコンキスタなどの名を挙げるまでもなく、ご案内の通り。
本書は、紀行文だけあってマグレブの人々のライフスタイルや旅中のできことについて叙述的に(あるいはダラダラと)記しているが、ここではできる限り「イスラーム」と関連する部分を摘要したい。まず筆者は2章で当該地域がイスラーム・キリストの攻防として描かれやすい現状に対し、ユダヤ人が果たした役割や、それらを囲む多神教の世界の影響を指摘している。そして、続く3章において筆者は、近代国民国家の枠組みに縛られない遊牧民族ベルベル人に注目する。国民国家という概念が、dominantな個人あるいは民族にとって都合の良いものとして機能していることを抉出し、そこに潜む矛盾を暴きだしているといえよう。また、そのようなシステムの中で、国王が近代国民国家という概念を利用する一方でイスラム・カリフという前近代的な権威を利用していることも注目に値する。最後の4章では、このようなマグレブエリアがあらゆる文化・文明(あるいは人文!)の結節点であることを、歴史的経緯を紹介しながら示している。
コメントⅠ
『イスラムの怒り』はどのような書き方であるにせよ、異文化理解を求める本である。その中でヨーロッパの「寛容」に関する批判がある。そもそもリベラリズムの上にあったヨーロッパの多文化への寛容というのは、むしろ自らに危害を加えない、という暗黙の前提があり、すなわち「無関心」に近いものであるとのことである。その一方で『イスラーム化する世界』では、同じ文化的背景(クルアーン)を持ちながらも、よりリベラルな考えが生まれていることが紹介されている。そこで、一つの共同体が他文化に対して臨むべき態度の在り方、自文化から派生した異なる文化との接し方について考えたい。(名取)
「彼ら」と「われわれ」
「異」文化理解というものが(「われわれ」とは)異なるところの「彼ら」について語るものである以上、異文化理解論は「彼ら」と「われわれ」の(二項)対立を前提とし、その上での批判や相互理解を論ずることが多い。(例えば、『ジャパン・アズ・ナンバーワン』における欧米先進国とJapan、『菊と刀』における西欧とJapanなど)。このような構図は、状況整理には極めて有効であり、『イスラムの怒り』においても「われわれ(非ムスリム、とりわけ先進国)」と「彼ら(ムスリム)」の二項対立がベースとなって議論が進んでいる。しかし、このような二項対立によって、多様でありうる「彼ら」を一枚岩として語ってもよいのだろうか? 例えば、同書においては女性のヒジャブ着用は「彼ら」の文化であり、「われわれ」の目には人権制約に映っても、「彼ら」にとっては制約に当たらないとの主張がなされている。しかし、ヒジャブ着用は単なる伝統であるという意見に対し、「彼ら」の構成員たるムスリム女性も同意するとは言いきれないのではないか。というのも、ヒジャブ着用に関する社会的圧力が弱いトルコと圧力が強いイランでは着用率に違いがあるわけだが、これを単なる文化の違いと片付けるのは単純にすぎると思われるからである。また、ヒジャブによる身体的・精神的負担の重さを考えれば、これが社会的圧力によるものではなく、進んで受け入れられた文化だと無邪気に認めることは安易ではないか。
筆者は「彼ら」を擁護したつもりでも、実はその「彼ら」の中には、反対の立場の人もいるのではなかろうか。延いては、筆者による「彼ら」擁護は、「彼ら」の改革にとっては邪魔であり、「彼ら」の“進歩”を阻害する可能性もあるのではないか。(森本)
コメントⅡ
イスラームという宗教は、法(シャリーア)でありながらも善きムスリムとしての在り方等、生活にまで入り込んでいる。『イスラーム化する世界』にあるとおり、イスラームはただの善悪の判断の基準ではなく、それ以上のものとしてムスリムが依拠するものである。しかしこの生活までの介入がフランスのブルカ禁止にみられるように、ムスリムとの軋轢を生み出しているものである。また人としての在り方が(男性は?、女性は?、といったように)クルアーンよって規定されている点も、欧米のカルチャーの中では理解しづらい。そしてこれらはシャリーアを用いて実行されるため、イスラームの教えは生活様式の規範以上に強制力を伴うものとなる。このような私空間への法の進出について考えたい。(名取)
法と道徳・宗教
「イスラムは厳しい宗教である」という認識のお持ちの方は少なくないと思う。しかし、イスラムが厳しいと言ったとき、そこには様々な事実の混同があるのではなかろうか。
①五行六信など、そもそもイスラムの教義自体が生活に対して大きな制約を課す(というイメージ)
Ex.一日数回の礼拝
②そのような宗教的道徳体系が、具体的罰則・執行力を伴った法であることが、法典において規定されている
Ex. 物を盗んだ場合は断手、姦通は石うち
③そのような宗教法が、現在イスラム諸国においてしばしば国法となっている
Ex. サウジアラビアにおいて改宗した場合、近代的な刑法によって裁かれるのではなく、宗教法によって裁かれ、死刑となる(また、そのような宗教法によって裁かれること自体が国家によって承認されている。)
③´そのような宗教法が、現在信者に浸透し、それに反するものに制裁が課されるような、具体的現実的社会規範となっている
このような分類に則って考えれば、確かに①②はイスラムの教義に関係するものであるが(いわば「イスラム自体」)、③③´はイスラム国家・信者の現状に過ぎないといえるのではないか。「イスラムは厳しい」と言った場合、それは本来「イスラム自体」の厳しさを批判するべきであるから、③の厳しさを差し引いて考えるべきではないか。(もちろん、「教義と担い手・担う国家を分けて宗教について論ずることに意味があるのか、可能なのか」「そもそもイスラム自体とは何か」という意見は尤もである。) 例えば、中世ヨーロッパにおいては「教会法」というものが刑罰権に裏打ちされた法として機能していたわけだが、これと現在のサウジアラビアの状況がそこまで異なるか。あまり異ならないとすれば、上述に言ったような意味に関する限り、その厳しさはイスラムにuniqueではないことになる。(ただ、私は教会法について勉強したことは全くないので、これが正しいかは分かりません。)
加えて、①も相当怪しいのではないか。もちろん、クルアーンやシャリーアにおける生活に対する制約は他の宗教のそれに比して圧倒的に具体的ではあるが、だからといって①のような厳しさがイスラムにuniqueと言えるだろうか。(キリスト教などと比較して) 単に、現在も③や③´に裏打ちされているために、①が顕在化しているにすぎないのではないか。
このように、法と道徳の関係性という点で、イスラムは非常に興味深い性質を有している。「イスラムは厳しい」と言ったとき、そのuniquenessはイスラムの宗教道徳を世俗的な法に高めることを最初に宣言した点につきるように思われる。(森本)
ディスカッションの概要
今回の議論で重要と思われる論点はコメント1に集中していたので、それに則って議論をまとめてみました。
第3回の共通本の主張を集約すると以下の通りであると思われる。
――「彼らを理解し、尊重しよう」――
Q01 「彼ら」の存在は所与か?そもそも存在するか?
①北海油田発見後に「スコットランド民族」意識が高揚した②ティトーの死後にユーゴスラヴィア内の諸民族の民族主義が高揚した③中東諸国や旧ソヴィエトのイスラーム諸国は宗主国・ソヴィエトの統治によって(時にはその思惑に従って)新たなナショナリズムを有するに至った。ここからわかるように、集団概念は政治的・経済的影響な影響によって新たに出現することがあり、また恣意によって創出されることもあるから、その存在を所与として受け入れてはならない。「彼ら」の場合も、中東における諸紛争とテロリズムが「彼ら」を立ち現われさせた側面は否定できない。
他方、イスラーム文化を共有し、またその自覚を有するイスラームという集団が社会的に認識されていることも事実なので、「彼ら」は存在しないというのは言いすぎである。
Q02「彼ら」は一つか?
シーア派・スンニ派などの分裂もあるし、「彼ら」の文化として紹介された文化を批判する「彼ら」も多く存在するから、一枚岩とは言えない。しかし前述のように「彼ら」が、文化的共同性・その自覚・その社会的認識を有した一つの集団であることも事実である。また、先生がコメントして下さったとおり、共通本の意図に鑑みれば、「彼ら」が多様であることと、理解・尊重が必要であるという同書の趣旨とは、矛盾しないので、そもそも論点ですらないかもしれない。
Q03「理解」することはできるか?
どうせ異質なものであるから無理に理解しようとする必要はない、との考え方がありえる。しかし、現在の国際的交流の深化や移民の増加を考えると、単なる無関心だけでは不十分ではないか。異質なものを「理解」するとは、「受け入れられないものであることを了解し、承認する」ことであり、tolerate=寛容・忍耐の精神を一定程度持つことも必要と思われる。求められるのは「まあ、しょうがないか」という、「おとなの無関心」ということであろう。
Q04「尊重」しないといけないのか?
文化というものは変容を前提とするものだから、尊重する必要などないとの考え方がありえる。しかし、多様性は尊重すべきである(と思われる)し、文化の消滅は(基本的に)不可逆な変化であるから、必ずしもそうとは言えないのではないか。また大村先生がコメントして下さったように、文化は希少動物のような外的存在ではなく、我々が結び付けられ属しているようなものであるから、それらを同列に語るのには注意を要する、との指摘が考えられる。
それに対し、文化とは(消滅や“衰退”を伴う)変容によって生まれるものであるという反論や、一方に対する文化の尊重は他方に対しては抑圧となりうるのではないか、との反論が考えられる。
Q05「尊重」していいのか?
「彼ら」が残虐な行為を働いていたとしても、それは「彼ら」の文化であり、また「彼ら」(ここではその中の国家)の主権の範囲内のことであるから、介入すべきでない、との考え方がありえる。
しかし前者に対しては①他文化尊重と普遍的正義論は両立しうる(少なくともその企ては無意味ではない)②確かに「人権」という概念の記号表現は普遍的ではないにしても、その記号内容は一定の普遍性を持つのではないか(「人権」という言い方では表現されなくとも、「これは人間として守られるべきものだよね」ぐらいの合意はありうる) ③Q02でも言及されたように、「彼ら」の中にも「彼ら」の現状を批判するものが多く存在する、等の反論が考えられる。また、後者に対しては、タリバン政権やフセイン政権は米ソなど外野の影響で誕生した側面があるので、「彼ら」内部の問題にすぎないと片付けるのは歴史的経緯に反するし、また無責任である、との反論が考えられる。
他方、大村先生がご指摘下さったように、(記号内容レベルでも)「人権」という概念が重視されるようになったのは冷戦崩壊以後というコンテクストの下であり、絶対的な普遍性を有しているわけではない、という事実には留意が必要である。また、そもそも押し付けはよくないという反論が考えられる。