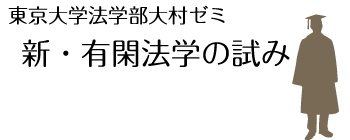文化をめぐる議論
報告者:大村敦志
課題図書
①青木保『多文化世界』(2003)
②祖父江孝男『県民性―文化人類学的考察』(1971)
③加藤秀俊『暮らしの世相史―かわるもの、かわらないもの』(2002)
④鶴見太郎『民俗学の熱き日々―柳田国男とその後継者』(2004)
⑤上野俊哉=毛利嘉孝『カルチュラル・スタディーズ入門』(2000)
課題図書の紹介
①青木保『多文化世界』(2003) 序:★★ 破:★★ 急:★★
著者は東南アジアなどをフィールドとする文化人類学者。日本人論を総括する著書『「日本文化論」の変容』などを書いているほか、文化庁長官も務めた。本書は、前著『異文化理解』に続くものだが、前著と対比すると、9.11以後の状況を織り込むとともに、よりマクロの観点から議論を展開しようとするものになっている。
本書は序章で、9.11以後の状況を「グローバル化する文明の世界」と「その外にあって固有の価値を守ろうとする文化の世界」の対立としてとらえた上で、人類全体への視野と文化の多様性を承認する「本来の文明」(多文化世界)が求められるとする。その上で第1部では、「文化は対立するものなのか」(1)という問いを設定し、対立の要因としての「宗教・民族の課題」(2)を示し、相対主義とは異なる多元主義を掲げて「理想の追求」(3)をはかることを提唱する。第2部では、国際政治について言われる「ソフト・パワーの時代」(1)を非政治化して、文化の魅力という観点から「現代都市と文化の力」(2)について論じ、「魅力の追求」(3)のための指標を提示する。
本書は全体として、「文化」を世界を分断する否定的な要因とするのではなく、多様性の開花に繋がる肯定的な要因としてとらえようとするものである。著者は、極端な相対主義に立つことなく、共通の価値を前提にした上での多様性を求める立場に立っている。その議論のインパクトは強くはないものの、広い共感が得られる穏健さには安定感がある。また、文化の力の指標として、外部への開放性、人間的なスケール、伝統の保存などが挙げられているが、あわせて大学の意義に注目しているのが興味深い。
もっとも、公共性や正義に関する思想につき、文化的な楽しみがなければ意味がないとする主張は、いささか挑戦的である。この点は十分な展開がなされておらず、今後に委ねられているが、法律家にとっては最も気になるところである。
②祖父江孝男『県民性―文化人類学的考察』(1971) 序:★★ 破:★★ 急:★★★
文化はどの程度の固定性・規定力を持つのだろうか。著者は、「県民性」に文化人類学的なアプローチを試みる。一口に県民性といっても、特定の職業・階層だけに見られるものと全員が平均的に備えているものとがあるという指摘や、風土・歴史・生産様式などの諸要因の指摘は、印象論のレベルにとどまる議論と一線を画する。やや横道にそれるが、旧日本軍の師団ごとの特色に関する言及や北海道・旧植民地に関する言及も面白い。やや古い本なので、住民の流動性が高まった今日でも同様のことが言えるかが問題になる。世界における人の移動速度が増せば、「国民性」は「県民性」に近づくのだろうか。この観点から、宮崎正弘『出身地でわかる中国人』(PHP新書)も参照。
③加藤秀俊『暮らしの世相史―かわるもの、かわらないもの』(2002) 序:★★★ 破:★★ 急:★★
著者も言うように、柳田国男『明治大正史・世相編』(講談社学術文庫)を意識しており、その昭和編とも言うべきもの。大別すると、「買い物」「服装」「家財」など日常生活に関する話題、「家」「宗教」など内面にかかわる話題、「日本語」「アメリカ」「外国人」など国民をめぐる話題が取り上げられているが、それぞれが「文化」と呼びうるものである。かつて「家」からの自立をはかる女性の武器であった「洋裁」がいまでは「英語」になっていると考えると、全体が一つに繋がる。平成日本に先行する「もうひとつの日本」は本演習の各論テーマの一つでもあるが、その序論をなすものと位置づけられよう。
④鶴見太郎『民俗学の熱き日々―柳田国男とその後継者』(2004) 序:★ 破:★★ 急:★
本書の帯には「柳田国男を受け継ぐ者は誰か」という問いが掲げられている。与えられている答えは、柳田民俗学は隣接諸学において自由な形で受け継がれているというもので、今西錦司・貝塚茂樹・梅棹忠夫・桑原武夫ら新京都学派の人々や花田清輝、永瀬清子の名が挙げられている。今日であれば、柄谷行人などを加えることもできるだろう。近代日本の学問史としては興味深いが、常民の文化を民俗学がいかに発見してきたかというオーソドックスな観点からはやや物足らない。他方、新渡戸稲造や石黒忠篤など農政官僚との関係を探究すれば、文化と政治の関係への展望が開けるだろうが、それは無い物ねだりということになろう。
⑤上野俊哉=毛利嘉孝『カルチュラル・スタディーズ入門』(2000) 序:★ 破:★★ 急:★★
カルチュラル・スタディーズに関する標準的な入門書。ハイカルチャーとは別の大衆文化に注目するとともに、階級のほか人種・性別などの観点に立った批判的・実践的な研究潮流の全体像を概観している。国・地域ではなく階級・人種・性別によって文化が分断されているという指摘は重要。フランクフルト学派や構造主義との対比が行われているが、同じくマルクス主義を出発点として文化を取り上げて批判的・実践的なスタンスを示すピエール・ブルデュー(とその学派)への言及があってもよかろう。最後の第3章では、日本の先駆者として中井正一や花田清輝が挙げられていること、空間論との関係が論じられているが、この部分には入門書の域を超えた独自性が現れている。
コメントⅠ
文化人類学(①②)、民俗学(③④)、カルチュラル・スタディーズ(⑤)と、文化を扱う学問には複数のものがあることがわかる。文化人類学と民俗学、文化人類学とカルチュラル・スタディーズの間にはある種の緊張関係があるが、民俗学とカルチュラル・スタディーズがどのように切り結びうるかは、検討を要する。
他方、①は世界レベルでの多文化状況を対象にするが、②④⑤は一国内での文化の相違に、③時間の流れの中での文化の変化に注目している。全体として、文化が多層的なものであることが理解される。また、②が研究の体裁をとるのに対して、①③は評論的な性格を帯びている。④⑤は学問史であると言えよう。
取り上げられている素材に即して言うと、①③では都市や宗教が、②③では家が、①②ではブランドないしステレオタイプが、とりあげられている。④にはこうした具体的な素材は現れないが、そこには学派の違い(柳田・石田・岡)に文化の違いに類するものがあることが現れているとも言える。また、①は大学と文化の関係について説いているが、⑤はイギリスの地方大学がカルチュラル・スタディーズという「文化」によって、その存在をアピールする様子が現れているとも言える。さらに、①は「帝国」に言及するが、③にも帝国日本が登場する。文化への意識は多文化を包摂して存在する帝国と親和的であり、単一民族神話の根強い戦後日本とは非親和的なのかもしれない。もっとも、徳川日本が300諸侯の小国に分かれていたことを考えるならば(②)、話は少し違ってくる。
コメントⅡ
普遍と特殊(グローバルとナショナル、ナショナルとローカル)の関係をどのように考えるかは、法の世界でも大きな問題である。たとえば、アメリカン・スタンダードの取引法の統一にどのように対処するか。これは多くの国々が直面する問題である。また、一国の中での文化の違いも、法の統一の阻害要因となる。たとえば、フランスの北部と南部では、もともとは異なる夫婦財産法を持っていた。ナポレオン法典の制定時には、北部の慣習が法定財産制(主)とされ南部の慣習は契約財産制(従)とされた。
こうした地域差だけが法の多様化をもたらすわけではない。同一地域においても、たとえば宗教が違えば、離婚に対する考え方は異なってくる。そこで1970年代のフランスでは、「各家族にそれぞれの法を」「ア・ラ・カルト離婚」をスローガンに複数の離婚制度が設定された。カトリックは有責主義により、プロテスタントは破綻主義によって離婚をすればよいというのである。これを立法的多元主義と呼んでいる。
親族集団(家族構造)のあり方は社会のあり方を性格づける。川島の『日本社会の家族的構成』は日本一国について、この点を強調したものであったが、より一般化した形で類型化を試みるものとして、E・トッドのような論者も登場している。私は日本の家族制度の根幹をなすのは本家分家の制度だと考えているが、その背景にあるのが生産様式(②)であるのか、より精神的なものであるのか(③)については、考え方が分かれるだろう。この観点からは、いまはマージナルな存在となっている祭祀承継は意外な重要性を持っている。神棚・仏壇はなくなってもお盆に帰省はしなくなっても、墓はなお存続しているのではなかろうか。それが「家」とどの程度の結びつきをもっているのかは、また別の話ではあるけれども。
ディスカッションの概要
前半では、共通本の「文化」の定義が明確でないため、「文化」という言葉で想起するイメージをすりあわせるように努めた。そのための素材として、参照本のテーマの一つである「県民性」を取り上げて、参加者の意見を聞いた。「県民性」と「国民性」との対比を通じて、「普遍と特殊」という対比は時間的・空間的に見て相対的なものであること、より普遍的・一般的であると思われるものとの関係で自らを位置づける際に「文化」が意識されること、などが指摘された。他方、グローバリゼーション(文明化)に関しては、同一の地域に居住していても社会階層によって移動のスピードが違うので、感じ方も違うという意見が出された。持てる者か持たざる者かではなく、身軽な者か動きが重い者かが重要になっているという指摘もあるが、「階級」とは異なるものが国民を分断するようになっているのかもしれない。
その他に、言語(たとえば日本語)がわれわれの思考様式を規定するかという問題についても意見交換がなされたが、この点は後半で問題になった法概念や法的思考様式による各国法の異同にも結びつく。
後半では、脳死や人工生殖など生命倫理にかかわる問題につき、文化(特に宗教や死生観)が影響を及ぼすか、ということが議論にされた。そのほかに、日本法は大陸法に属するので、フランス法・ドイツ法との比較は相対的に容易だが、英米法との対比は難しいこと、日本法学の特色と言われるものも絶対的なものではなく、30年ぐらいの間にトレンドが変化していることなども話題になった。その中で、日本法は最近では英米法の影響を強く受けるようになっているものの、法学的な思考様式について見ると、アメリカに見られるようなリアリズムが後退しており、影響関係を語ることはそう簡単ではないことも示唆された。