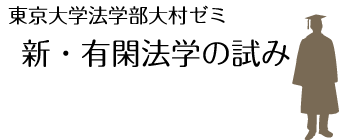補講——J・デューイ から何を読み取るか
J・デューイ(1859-1952)は「アメリカの哲学者・教育学者。パース以来のプラグマティズムを集大成し、また道具主義を唱えた」(岩波哲学・思想事典)とされている。ゼミデ取り上げた『民主主義と教育』(1916年)はその主著の一つで57歳の時の作品であるが、長命であったこの著者はその後も多くの重要な著作を刊行している。教育学者・佐藤学によれば、1980年代以降、アメリカを中心にデューイに対して新たな関心が寄せられるようになり、「デューイ・ルネサンス」と呼ばれる状況が生じているという。日本でも、1990年代から2000年代にかけて、『学校と社会』や『経験と教育』の新訳が試みられたり、『デューイ=ミード著作集(全15巻)』が編まれているのは、その影響かもしれない。『民主主義と教育』に関しても、1975年に岩波文庫版で松野安男訳の上下2冊が刊行されたほか、上記の『デューイ=ミード著作集』の第9巻(2000年)に河村望氏の新訳が収められているが、できれば文庫本を使用する、という原則に則り、ゼミでは岩波文庫版を読んでもらった。教材選択にあたっては、同じ著者の『学校と社会』やコンドルセの公教育論(コンドルセ他=坂上孝編訳『フランス革命期の公教育論』岩波文庫、2002)も候補にしてみたが、テクストの一部を切り取って取り上げることから、相対的にまとまりがあり、より成熟した内容を持つ『民主主義と教育』を選び、その中から終章に当たる第26章「道徳の理論」を採った。なお、デューイの「指導(direction)」「統制(controle)」観を示す第3章「指導としての教育」を参考教材とした。
以下、補講の参加者による要約・評価である。
A デューイは本テキストの中で、歴史的に繰り返されてきた二項対立を説明し、一方がもう一方より優れているかどうかを考える姿勢を批判する。彼からすれば、その二つを分離させることは無意味である。むしろ、二つが有機的に結びつき重なりあっているという人間の性質に注目し、その状態に沿った刺激をつくりだすことが教育の本質だと考えている。
その二項対立とは、何か。いくつかに分けて説明される。
たとえば、自己の内で完結する理想的な思想の正義と、外界に生み出す影響を基準に善悪が判断される行動の正義の対立である。実際には、単一のあらわな行動に未だ現れない内的な逡巡は、その悩んだ結果の「単に外的であるにすぎない行為や結果」と有機的に結びついている。
義務と興味は、前者が良く、後者が悪いということはできない。仕事の進展に興味をもてれば、一見苦痛で短期的に非合理なことであっても、その先に期待して行動することができる。また、「道徳的」と呼ばれる徳性は、実は社会的に選ばれた骨格のようなもので、他の血肉の部分を削ぎ落としている点で恣意的である。
これらから導き出されることとして、教育とは一方的に性善説や性悪説に立って考えるべきものではなく、生徒が外界と関わる中で自己に働きかけるという営みの質をどうやって上げていくかが重要なのだとわかる。生活を通した経験がより高いレベルの知識を構成していくという彼のこうした指摘は、ある目的に向けた政策としてより本質的な、人間という種のありかたを持続・変化させるという意味での教育の考え方に強く影響を与えるものである。
B 学校での道徳の授業に意味はあるのだろうか。これは誰しも考えたことがあると思う。デューイは教室道徳が実際の生活や我々の性格形成に役立たない原因を次の4つに求める。まず教室道徳は道徳を内的な動機によるものと外的な結果を求めるものに分離し、両者を無理やり折衷してしまっていること、次に自己を固定したものと考えることで原理と興味の間にジレンマを発生させてしまうこと、そして道徳を一方では理性的なもの、他方では日常的な知識と異なるものと考えることで教室道徳をただの説教にしていること、最後に学校が社会的環境の欠如により孤立してしまっていることである。
では本来の道徳、そして教育とは何か。キーワードとなるのは「全体」「他者・社会との関わり」「相互作用」「ダイナミズム」であろう。学ぶという言葉の由来は「まねぶ」にあると言われるが、誰かの作った型をそのまま受容するだけの模倣は学習とは呼ばない。自分から進んで興味を持ち、社会・他者を知る手段としての模倣を試行錯誤しつつ繰り返すことで、柔軟性がある応用の効く学びが行われる。こうした行動の形成を通じて、不断の形成過程にある自己は再調整され、拡大・深化されていく。この生活そのものが教育であり、社会の一員として生活する能力を保持することが道徳に他ならない。また学校での教育の価値は、真に社会生活を反映し、学校の外との連続性を持つことで社会精神による活気づけが行われているかどうかで決まっていく。
社会や他者との相互作用から切り離され孤立した学校、自己は道徳とはむしろ反対の方向に暴走してしまう、それが現在起きているのではないか。本テクストはそうした危機感をふと抱かせるものだった。
C 人間はたえず自分を取り巻く環境と相互作用を持ちながら成長していく。そのような動的な人間像をもとに、デューイは学習・知識と道徳・行為とを分離できないものとする。人間の活動は内面における思慮と外にあらわれた行動との連続的な営みであり、また、真に行動を正当化するのは原理でなく興味だからである。そして、興味を基にした直接的な自分自身の体験的認識としての知識が行為に影響を与えるが、ここで行為の道徳的性質と社会的性質は合致するため、学校における教育でも社会精神を活気づけることが目指されるのである。
この議論は法や教育あるいはその二つの関係について示唆に富む。デューイは内的なものと外的なものとの区別を否定しており、カントの道徳観も斥けているが、このことは法の規律対象への問いを喚起する。カントによれば、法は外面を規律し、道徳は内面を規律するものとして峻別されるが、内面と外面とが不可分であれば一体法は何を規律するのか・規律してよいのかが問題となるからである。また、デューイが考える教育は今日採用されている制度的・段階的・集団的な教育とは異質であり、その是非や実現のための方途が考えられねばならない。教育が社会精神の発達を目指すものだとするなら、法と教育の関係を考えるには法の社会性を踏まえる必要があることにもなろう。
他方、議論として物足りなさを感じさせるところもある。例えば、行為の道徳的性質と社会的性質とを同視している以上、社会生活に有効に参加する能力が道徳的だと説明したとき、デューイは循環論法に陥っているのであり、道徳性ないし社会性それ自体の説明をしなければならないはずである。多くを議論しているためであるが、もうひと押し、議論を敷衍してもらいたかった。
D 本章で、デューイは積極的な社会参加のできる人格を育て確立するための、学校における道徳的教育の必要性を説く。知性と性格の関係についての誤った考えが目的実現の弊害となっているとして、それらの考えへの批判を交えつつ議論を進めている。本章における主張の柱は主に以下の三つである。
第一の柱は、人間の成長するプロセスについての分析である。有機体である人間は、観察や思考を発端として行動に至るまで「組織的再適応」という一連のプロセスを絶え間なくたどっている。自我と興味は密接不可分の関係にあり、自己の興味に基づく行動を選択することを通じて人格は不断に形成されるものである、との立論がなされている。
第二の柱は、道徳的教育の必要性についてである。単なる知識の伝授ではなく、実社会とのつながりを有する、生きた知を授ける教育が生徒の道徳的関心を育て、道徳的な見識を発達させると主張する。社会との接点を持つことで生徒は「組織的再適応」のプロセスを繰り返し、社会に有効に参加する能力を発達させていくというのである。
第三の柱は、学校で、社会精神に根ざした教育を行う条件についてである。学校生活が社会生活の縮図の性質を持っていること、そして学校での学習が学外の世界と連続し、自由な相互作用があることが、学校が社会精神によって活気づけられ、道徳的教育が実現される条件であるとの主張がなされている。
E 望ましい生の在り方、「道徳的」として志向されるのは関連性や連続性としてあらわされるところの<つながり>であり、忌避されるのはもろもろの分離や分裂である。さまざまに取り上げられる好ましくない分裂の仕方は、一身における「精神的なもの」と「肉体的なもの」ないし「思考」と「行為」との分裂と、「自己」と外界との分裂とに大別できようが、これらはけだし同じことの両面であろう。すなわち、「自己」を「行動の選択を通じて不断の形成過程にある何ものか」としてではなく、「行動に先立って存在する固定した何か」、それ自体で切り離され完結した何かとしてとらえようとする態度である。
「道徳の本質」とは、結局、「教育を受け容れる能力を保持すること」であると結論されるが、これを、自己を<開かれた>ものにし続けることと言い換えられようか。それは、「自己」のあり方と、周りの情況とが相容れなくなった場合に、これまでの「自己」のあり方に閉じこもるのではなく、自らの態度を再編成し、置かれている状況に適応させようとすること、「自己」と相容れないものを否定するのではなく、それらを包含するように「自己」を拡大させていくことである。
社会生活の標準的諸要素となる諸学科を、それらの社会的意義が実感されるような状況、社会生活そのものの中で修得させることが、社会的関心を確立し、その関心を実効あるものとするのに必要な知性を授ける「道徳教育」となる。「教育」は、社会生活を準備するものとして、生活から切り離されて施されるというようなものではない。社会的な環境、共通な経験を築き上げるように対等な立場でのやりとりが行われる環境において、生活していくことそれ自体が「教育」となるのである。
F 「民主主義と教育 第26章 道徳の理論」において、教育において望ましいすべての目標や価値そのものが道徳的である、というのがデューイによる「道徳」という言葉の見方である。そして、ある特定の社会の中で立派な人間であるとされるためには、人はある諸特徴を身に着けることが必要になるところ、これらの諸特徴(=道徳的特性)を助長することが教育の任務であるというのが本章における基本的な視点であると考えられる。訓練、自然な発達、教養、社会的に有為な能力が、抽象的ではあるが道徳的特性の例としてあげられている(最終段落)。この観点から、デューイは、まず、道徳性の本質を内心の状態と外的な行動・結果のどちらかのみに見出すことを妥当でないとして、道徳性を内心と行為の動的な連続体として捉えている。次にデューイは、行動が従うところの「原理」(一般的な法)と「興味」(私心やその時々の都合)の対立を取り上げ、自己とは所与の存在ではなくて、行動の選択を通じて不断の形成過程にある何ものかであると捉え、興味を自己と一定の対象との活動的同一性であるとすれば、人が気移りや障害にもかかわらず自らの役目を果たすことができるのは、義務への忠誠ゆえではなく、その仕事対する興味ゆえであるとする。そして、知識については、それが利用される文脈によって、さまざまな用い方がありうることを指摘する。続いて、行為の道徳的性質と社会的性質の同一性や、学校と社会の連続性を確保することの重要性が強調される。ここでの主眼は、教育の環境においても、知識それ自体に関しても、社会との関連性を軽視してはならないという主張にあると思われる。
G デューイは、道徳の本質は、社会の一員としての共同生活を受け容れられることにあると考える。よって、道徳は誠実・正直・貞節といった特性だけを指すのではなく、全ての行動を包含すると解し、性格全体に関わるものであるとしている。
我々は他人とともに日常生活を営むなかで様々な行為の意味を理解し、自分の行為を他人と関連づけて考えることができるようになる。また、そうした積み重ねを経て人々の間で事物に関する共通の観念が成立することにより、自分自身を社会に適応させ、共同生活を送れるようになる。
つまり、道徳を身につける、すなわち他人と共同生活を受容するためには、日常生活のなかから経験を通して多くを学び取っていくことが必要だといえる。
学校は書物や談話に頼りすぎる傾向にあるが、子どもにより大きな影響を与えるのは経験を通して獲得した知識である。そこで、子どもに道徳を身につけさせるために、学校は目標を持って他人と仕事や遊びを共にできるような、縮図的な社会となる必要がある。
デューイは机上の知識よりも経験を通して学ぶとことを重視している。一方、現代の日本では、学力低下が叫ばれて学習指導要領が改定され教科書が分厚くなったり、道徳の教科化が議論されたりしている。学習すべき内容を増やしたり固定したりすることで本当に子どもたちの生きる力を育めるのか、そもそも「生きる力」とは何なのか。子どもたちに何をどう教えるべきか、目先の点数にとらわれすぎず、広い視野を持って考えていかなければならないと思う。
H 教育について道徳の観点から論じている。デューイは、学校教育の包括的な目標を「性格を確立すること」だとして、その目標の実現のために、知性と性格についてのある種の考えを警戒すること、目標が作用する条件を見つけることが重要であると述べる。
この目標を妨げる障害の一つは、動機や性格を内的なもの、結果や行為を外的なもの、というように二分し、道徳性をどちらかに分類して、もう片方とは分離させてしまう道徳観である。道徳教育の場では、この両極端な見解を折衷する形になってしまう。
もう一つの障害は、行為を原理によるものか、興味によるものかで対立させる考え方である。私心なく一般法に則って行動することが「原理」による行為であり、逆に、私心に従って利己的に行うのが「興味」による行為だとされているが、これは自己が固定された一定量のものだという誤った認識によって導かれるジレンマだ。自己は行動の選択を続けて常に形成過程にあるものであり、興味は現在の自己の性質を表す、つまり動く同一性であるとする。
これらの分離は、道徳を狭く解釈することから生じる。本来、道徳はその人そのものである性格全体に関わるものであって、行為の道徳的性質は社会的性質と同視できる。つまり、教育において、社会精神を常に意識することが必要不可欠となる。そのためには、①学校が縮図的な社会的集団であること、②学校における学習が、学校の外での学習と相互に作用することが条件だとする。
読むのに一苦労したが、特に、一つの学科としての学習は専門的価値があるにすぎず、それが社会的意義を実感できる環境の下で学習することによって道徳的知識となるという意見は、自分の体験的にも納得できる部分があり、興味深かった。もう少し具体的に場面をイメージできたらもっと深い理解が可能だと思う。
I デューイの道徳の理論は二元論批判から出発する。第一に、「内的」なもの(動機・性格)と「外的」なもの(結果・行為)を一つの連続的な行動としてとらえるべきであるとする。第二に、「原理」に従った行動と「興味」に従った行動とを対立させることに疑問を呈する。原理は活動の連続性を示すにすぎないが、興味は自己と一体をなし、困難を乗り越えて仕事を続けさせるものは義務ではなく興味であると強調する。以上のことから、学校では興味を引き熟慮を伴う連続的な活動を行うことが大切であることが見えてくる。
また、彼は道徳と知識の分離を問題視する。もし道徳と知識とが分離されるのであれば、学校での学習は性格には影響を及ぼさず、学校が性格の確立を目標としていることと整合性がない。しかしながら、経験を通して直接に得られた知識は行為に影響を与える。知識と活動の関連を維持することが重要であり、目標を持って他人との協働を伴う作業の中で得られるものは、認識されようとされまいと道徳的知識なのである。
したがって、彼によれば、道徳はわれわれの行為すべてを包含し、性格全体に関わるものである。道徳性即ち社会性ということになる。教育には社会精神が必要不可欠であり、(①)学校そのものが社会生活であること、(②)学校における学習と学校の外での学習との相互性、この二つが学校にとって必要な条件となる。社会生活に参加する能力を成長させることにこそ道徳の本質がある。
以上のように、デューイは道徳を現実の社会状況や人間性に密着した広範かつ可変的なものと捉え、教育と現実社会との結びつきを重視する。彼からすれば、我が国で現在一般に行われている座学と説教形式の道徳の授業は批判の対象となるに違いない。彼の考え方を突き詰めれば実用的でないものが教育から除外されるといった危惧が生まれる可能性もあるとはいえ、学校教育が受験ありきで実生活には役立たず、仕事に直接結びつかない、という意見も聞かれる現代社会においてデューイの主張は十分に意義のあるものであり、決して古びたものとは思えない。また、二元論に依らず事物の結びつきを柔軟にとらえていく姿勢には個人的に魅力を感じた。
J 子供の参加する連帯的活動の量を多くすることが肝要だとデューイは述べている。しかしこれを社会で合意形成することは難しいのではないかともいます。政府は有限な税収を子供の教育に対して有利配分できるのかが問題となる。資本主義経済において資本は収益を生み出すだろう分野に投下されるが教育の分野に資本が投下されるかは難しい。なぜなら学校での教育の成果は短期的にも、長期的にも見えにくいからだ。「充実した生活を送る」ために学校教育があるとしてどこまでデューイの理想通りの教育が実現できるかは疑問が残るところである。
人間は社会的集団的全体的生き物である。との記述が最後の解説の章にある。また「人間は社会環境に対して積極的適応講堂によって社会化される可能性が大きい。」ある環境に「うまれ、育った個人の生活、行動、思考探求の過程が、それを担い、発展させるのである。」との記述もあった。
あらゆる個体は遺伝子を次世代へと残すための道具にすぎない。これはドーキンスによって書かれた「利己的な遺伝子」の一内容である。生物は種を後世に残すための道具であって個の生存を目的には作られてはいない。自己犠牲、利他行動もこれで説明がつくが、ここから導かれることは個が生きる目的は「後世への遺伝子を残すこと」である。
デューイによれば、ある環境に生まれ育った人間の生活、行動、探求の過程が制度、慣習、言語、文化、知識を担い、そして発展させていくこととなっている。また「人間の行動の目的は歴史的に変化し、発展するもので、あり、生活は単に知的なものでも、また単に情的なものでもなく、すべてを含む過程である。そしてそれは認識の過程であるだけではなく道徳的意味をもち、鑑賞的意味をもつ過程でもあるのである。」ともデューイは述べている。
人間以外の生物の行動の目的は究極的には遺伝子を後世に残し種を保存することである。人間以外の生物には制度、文化、言語、慣習もなく、思考を含んだ行動も見られない。すべての行動は遺伝子の保存でありそれ以外に意味はない。ここに人間と人間以外の生物に決定的な違いが見られる。人間も生物の一種である以上後世への遺伝子を残すための行動をとることは間違いない。しかし人間は必ずしもそれだけで行動しているわけではない。種の保存以外にもさまざまな目的に基づいて行動をしており、生殖活動が後回しにされることも多く見受けられる。この意味においては人間はほかの生物とは相いれない存在となるだろう。
しかし人間は個人勝手に生きているのではなく全体的社会的生物であるとデューイは考えている。人間が充実した生活を送ることは「人類の経験を共有し、その意味を自分の生活によって確かめながら生きるということ」としている。人間以外の生物は種の保存という全体的な目的を共有している。その一方で人間の「充実した生活」を上記のようにデューイは定義しており、その意味で人間もそれ以外の生物も社会的全体的生き物であり、両者の間に類似性を見た気がしました。
デューイは、「道徳の理論」の末尾の「要約」で、「社会生活に有効に参加する能力」を発達させ、「成長に欠くことのできない連続的な再適応に興味を持つ性格」を形成する教育を「道徳的」と呼ぶ。彼にとって、社会的であることと道徳的であることは同義であり、教育の目的は本質的に道徳的であるということになる。彼が批判する「偏狭な道学者的な見解」は、動機を行為に、義務を利益(興味)に優越させる考え方に立つが、彼はこれを退ける。初めに確固とした(孤立・限定された)自己があり、それが世界と対峙しているという発想に与することなく、自己は活動を通じて形成(再調整・拡張)されていくという見方が採られている。デューイは「興味」「知識」を具体化し社会化することを通じて、これらを救いだす。デューイの議論の特徴は、社会と個人とを対峙させない点にある。個人は社会(Society)に従属するのではなく、そもそも社会的(sociable)な存在である。個人は自ずから社会性を身に付けるように行動するが、同時に、その行動を通じて自己と社会の意味を拡張していく。このように、個人は社会的であり道徳的な存在なのである。彼は、社会を個人に立脚させる民主主義社会には、このような個人=社会=道徳観が適合的であると考えているのだろう。もっとも彼は、個人は常に社会的・道徳的でありうると考えているわけではない。デューイの「教育」は二義的であり、理論上の(あるべき)教育と実際上の(行うべき)教育とが区別されている。人間は本来、仕事を通じて学習するはずである。しかし、デューイは仕事に伴って学習が生じるような学校が必要であると説く。そこには、現代において人間は仕事から、すなわち学習から疎外されているという認識が潜んでいる。社会が十分に教育的でなくなっているのであれば、学校を中核として教育的な社会を創りだしていこうというわけである。