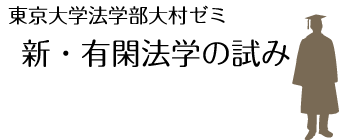9 芸能
報告者:長谷川、小倉
課題図書
①山川静夫『歌舞伎の愉しみ方』(岩波新書、2008)
②田中優子『芸者と遊び―日本的サロン文化の盛衰』(学研新書、2007)
③岡田暁生『音楽の聴き方 聴く型と趣味を語る言葉』(中公新書、2009)
④藤沢秀行『勝負と芸―わが囲碁の道』(岩波新書、1990)
⑤熊谷早智子『踊りませんか?―社交ダンスの世界』(集英社新書、2004)
課題図書の紹介
①山川静夫『歌舞伎の愉しみ方』(岩波新書、2008) 序:★★ 破:★★ 急:★★
フリーアナウンサー・歌舞伎評論家である山川静夫さんが、歌舞伎鑑賞の入門者に向けて、自己の体験を交えながら歌舞伎の基礎知識や魅力を語った本。第一章では、歌舞伎の見方は人それぞれであり、サラリーマンの人生やBLの文脈、映画との類推でも楽しめると述べている。第二章ではリアリズムに欠ける歌舞伎の約束事に進んで参加することが歌舞伎を楽しむために大切であると述べる。第三章では、歌舞伎の演目にはいくつかのパターンがある中で、それぞれの魅力について説明している。第四章では、様々な舞台について着目すると面白いポイントを例示している。第五章では、役者の「ひいき」の愉しみについて述べた上で、役者も観客も変化・成長すること、それも歌舞伎の愉しみの一つであり、双方が響きあう関係が大切であると述べている。歌舞伎を主題にして何かを論じ主張するというよりは、歌舞伎の面白みがあるところを例示して解説していく形の本である。(長谷川)
本書は、アナウンサー、エッセイストであり、歌舞伎愛好家を自負する著者が、題の通り歌舞伎の約束事・ジャンルなどを紹介しながら、歌舞伎の愉しみ方を教えてくれる作品。
第1章では、一流のものを観劇し、気軽に自分なりの感性の尺度で愉しむことが大切だと説く。第2章では歌舞伎の約束事について、花道や女形といった一度は聞いたことのあるものから、「ツケ」「廻り舞台」といったかなりマニアックな仕掛けや、演出効果まで解説されている。第3章では、「時代物」、「白浪物」といった歌舞伎のジャンルについて詳細な解説がなされている。第4章では、第2、第3章のような一般化された知識とは別に、著者なりの感性での愉しみ方を紹介している。第5章では、観劇に慣れてきたら、ひいきの役者をつくることを勧めている。
全体を通して、歌舞伎は庶民の娯楽であって、役者と観客が響きあう関係があるべきだ、という主張がうかがえる。「判官びいき」「見得」といった歌舞伎由来の言葉の紹介も散りばめられており、おもしろい一方で、個々の内容がマニアックすぎて、ついていくのが難しく感じるかもしれない。しかし、歌舞伎への興味を湧かせてくれる作品である。しかし、歌舞伎に対する堅苦しい印象を捨て、まず劇場へ足を運んでみて自由に楽しんで欲しい!という著者の歌舞伎愛がひしひしと伝わってくる、エネルギッシュな作品である。(小倉)
②田中優子『芸者と遊び―日本的サロン文化の盛衰』(学研新書、2007) 序:★★ 破:★ 急:★
「音曲」と「踊り」の専門家としての芸者について、社交文化という観点から考察した本。前半は江戸時代の芸者について、明治時代における芸者文化の形成につながる歴史を丁寧に追っている。幕府による女歌舞伎の取り締まりが色と芸の分離につながったという点に①との連続性がある。後半では、具体的なエピソードや回想に依拠しながら、明治時代の芸者遊び・日本的サロン文化について考察している。社交界における「暗黙のルール」、言い換えればマナーと言われるものを体現した所作の洗練が求められる空間として花柳界が存在していたと述べられている。「人間関係の洗練」や「のんびり」「いき」といった美意識が近代社会において失われていってしまったことへの嫌悪感が時折うかがえる。(長谷川)
③岡田暁生『音楽の聴き方 聴く型と趣味を語る言葉』(中公新書、2009) 序:★★★ 破:★★ 急:★
音楽を「聴く」、「語る」、「する」の三面から分析的に語った本。音楽の言語的な性質や、特定の音楽が発生した文脈にも注目して、我々に音楽がどのように感じられ、語られるのかを浮かび上がらせている。音楽を語る語彙や表現によって、音楽体験の豊かさも変わってくることを述べた第二章の内容が個人的には興味深かった。
音楽論の語り方に慣れていないためか読みづらいと感じられる箇所もいくつかあったが、全体的には簡潔で読みやすい文章である。さらに、「おわりに」において音楽の聴き方としての筆者の意見のポイントが短くまとめられているので、中核的な主張はわかりやすい。(長谷川)
④藤沢秀行『勝負と芸―わが囲碁の道』(岩波新書、1990) 序:★★ 破:★★ 急:★
著者は名誉棋聖の称号を手にした有名な囲碁棋士。酒、ギャンブル、借金、女性関係など破天荒な生活でも有名であった。本書の前半では名誉棋聖となるまでの自伝的な内容、後半は人生観や囲碁界グローバル化、将来像が述べられている。当時の囲碁界の勢力図が詳細に語られているが興味を引くとは言い難い。また、「勝負と芸」という題は、「目の前の勝ちにこだわるのではなく、人間を含めて腕を磨け」というようなことを言っているのだが、深い論究には乏しく残念なところである。(小倉)
⑤熊谷早智子『踊りませんか?―社交ダンスの世界』(集英社新書、2004) 序:★★★ 破:★★ 急:★
著者はパリ在住のフリージャーナリスト、エッセイストであり、30歳から社交ダンスを始めたアマチュアである。なかなか言葉では表現しにくいダンスの世界を、ダンスをする人ともしない人とも分かち合ってみたいというのは本書の趣旨である。競技ダンス公式10種目の各種目について、生まれや伝播、標準化といった歴史的文化的背景を述べる一方で、「ダンスは人生そのもの」と述べ、ダンスに秘められた男女の恋模様や体験談がエッセイ風に語られており、読者を飽きさせない。ダンスに全く興味がないと読みにくい点は否めないが、そんな人も一読してみればダンスに興味が湧く一冊であると思われる。(小倉)
コメントⅠ
③は、音楽生活に関して、「する」「聴く」「語る」の三つの視点からなる公的空間であるという観点を提供している(P203)。本欄では、これを1段階抽象化して、ある芸術分野について「実践者」「鑑賞者」「批評者」の3つの観点があるという見方から、5つの本の特徴や位置関係を整理したい。(それぞれは連続性を持つものの、「鑑賞者」と「批評者」の視点は特に重なる部分が大きいと思う。)①は歌舞伎を楽しむために知っておくと良いことについて述べている、「鑑賞者」または「批評者」の視点である。②は芸者文化の歴史について詳述しているので、「批評者」の視点である。③は実践の効用にも頁を割いているが、主に「鑑賞者」と「批評者」の視点である。④は棋士の手による本であり、「実践者」視点である。⑤は「実践者」と「批評者」の視点を持っていると言えるだろう。それぞれ全く別の分野について書かれた本であるので内容面での連続性や意見の相違として取り出せるものはあまり無いが、ある芸能(に限らず、学問、芸術、スポーツ)にかかわり楽しもうとする際には、当該分野での決まり事をある程度理解する必要があるというポイントが、5冊を通じて浮かび上がってくる。詳しくはコメントⅡに譲る。(長谷川)
共通テーマである「芸能/芸」に対しては3つの視点が考えられる。すなわち、「やる人」、「見る/聴く人、(お客さん)」「批評する人」の3つである。
④及び⑤の筆者の視点は「やる人」である。その中でも④はプロであるのに対し、⑤はアマチュアである、という違いはある。また、①と③の筆者は「見る/聴く人」及び「批評する人」である。①は愛好家としての視点が強い一方、③は学者としての視点が強い。②の筆者は「批評する人」である。実際に芸者遊びをこなしているというよりは、学者として歴史、文化面からの分析が光る。
内容面については、①及び⑤は、それぞれのテーマを筆者独自の分析や考えに基づいて解説し、魅力を語っている。自分の知っている魅力的な世界に、知らない人を誘い込もうとする意図が見える。④は、自伝的で具体的な内容が大半を占め、①及び⑤に見られるような読者(顧客)志向性には乏しい。②及び③は、学者としての冷静な分析と抽象化がなされていて、評論文として読みやすい。
5冊はまったく違ったテーマについて述べられているが、どのテーマにも「型」や「約束事」、「マナー」といったものの存在が示唆されていた。ある程度の事前知識や共通認識は不可欠であるというのである。例えば、音楽では尺八の音色に、ベートーヴェンの<第九>と同じように感動を覚えようとしても難しいのである。「型」を知ってこそ、批評することができるようになり、魅力を語り合うことができる。一方で、その「型」を共有することは難しいということも示唆された。現にまったくダンス経験が無い人が⑤を読んでも退屈に感じる可能性が高い。②でも、芸者と客の男性が考える「芸と売色のバランス」感覚の崩壊が、芸者文化衰退の原因であるとしている。
芸能/芸という客観的な価値判断ができないものへの関わり方を考えさせてくれる5冊であった。(小倉)
コメントⅡ
ある分野に関わろうとする場合にはその分野の決まりごとを理解する必要がある。ルールを知らなければサッカーも囲碁もプレイできないし、劇の進行上はいないものとして考えるべきである黒子にいちいち突っ込んでいては歌舞伎を楽しんでいるとは言い難い。芸者文化ではどのような振る舞いが粋であるか、音楽ではそのジャンルの形式、囲碁では攻めの型や手の美しさに対する勘、ダンスではステップについてある程度知らなければ、鑑賞・批評・実践をするにあたって重要なポイントを落としてしまう。法律学習の場面で、専門用語特有のニュアンスに慣れるまで文章の意味がつかみにくかったりするのも、似たようなことだと言えないだろうか。「決まり事を理解する」ことが、何かを理解し、身に着けようとする場合に必要になるのである。
では、ある決まり事が、当該分野の参入障壁になるということも考えられないだろうか。あまりにも複雑なルールを持ったゲームは敷居が高いであろう。一方で、決まり事を緩くすることで失われるものも多くあるだろう。決まりごと自体が当該分野を形作っているのが常だからである。ローカルルールだけでは世界とつながれないが、逆に世界に開かれることで失われるものがある時に、ある種のバランス感覚が必要になる場面は多いのではないだろうか。(長谷川)
はじめに、伝統芸能を守る、世界に広めるという場合の法の関わり方がある。端的には、国が文化振興にどれくらい資金を投入するかという問題が生じる。芸能/芸が客観的な価値判断基準も持たない点、経済に及ぼす影響が不明な点などが、他の産業や科学技術とは別次元のものとして立ち現れる。また、当該芸能の中での法という観点もある。芸能を広めると、亜流は生じるし、標準化、ルールの策定なども必要になる。
次に、法規制と文化について考えたい。とくに風俗などについて、法が規制を加えることがある。しかし、それによって新たな脱法的な文化が生まれたり、逆効果を生むこともある。人間関係を規律するのが法である一方で、その枠組みの中で、人間関係を洗練させるのが文化であるということもでき、法規制と文化については考えさせられるべきことが多い。(小倉)
ディスカッションの概要
第一に、議論の導入として、「今までどのような習い事をしていたか」という事と、その理由と意義について思うところを質問した。ピアノ、オーケストラ、合唱、けんだま、サッカー、剣道と、人それぞれ多様な経験をしていることがわかった。習い事を始めた理由としては、自然と耳に入ってきた音楽に魅かれた(ピアノ)、高尚な感じがした(書道)といったことが挙がった。意義については、他人への指導を通じてコミュニケーションを取ることが可能になるということ、文化を海外の人に伝えるきっかけになる、といったことが挙げられた。中でも、スポーツの中にルールを使いこなす面白さを見出したという発言が興味深かった。
第二に、今現在、やっておけばよかったと思う習い事について質問したところ、ダンスなどは自分が出来ないから純粋に楽しめる面があるという意見が出された。さらに、始める前は簡単だと思っていたことについて、手を付けてみることでその困難さに気づき、面白みがわかるという議論も現れた。鑑賞・批評に際して「かじってみること」の意義・効用が大きいということを指摘したものであったと思う。また、どのような習い事でも、共通して、先輩から技能を習いつつ、同輩と切磋琢磨するというコミュニケーションの場となっているということが指摘された。第一と第二の質問は裏表の関係にあるようなものだったので、ここで議論がつながったことはよかったと思う。
第三に、習い事がステータスとして機能する場面があるのではないか、という議論に移った。例えば、字がうまくかけることが「ちゃんとした人である」という評価につながったりするという声が上がった。また、これは「かじってみること」の意義とも重なるが、文化を理解し批評するにあたっての教養を身に着けることになり、それが文化的なステータスとなるという点で、習い事には価値があるという指摘があった。さらに、所属するコミュニティによって評価されるステータスが変わってくるという発言があった。座学と芸能という言葉の違いが、実用的な価値の有無にあるのではないかという問題提起がなされたが、実用的な価値それ自体が所属コミュニティによって外から規定されることが多いように思う。ここで、評価基準の多様性についての議論が展開された。固定的な尺度に基づいた記録や数字に結果が表れる分野がある一方で、他方に純粋に客観的評価ができないようなものもあるというのである。その差はスポーツと芸術の差というのではなく、プロセスを含めた評価や、基準の多様性の程度の違いによるのだという指摘がなされた。
第四に、文化をどう広めていくかというテーマについて議論した。メディアを利用した接点の創造や、入門的な楽しみを伝える重要さが強調された。
以上の議論が終わった後、大村先生から4つの点についてコメントを頂いた。第一に、先生がピアノを習われた体験から、技能を身につけるときに、学習者は指導者からの指示を常にそのまま実行できるというわけではないということ、それゆえ指導方法として効果的であるのが「褒めること」であるとの指摘があった。第二に、「型とアクター」の役割についてのコメントがあった。例えば、法学の論文を書くときでも型は重要であり、また、民法上に用意された契約類型というものも、歴史の中の淘汰をくぐってきた「型」であるということだった。アクターに批評者がいることによってプレイヤーのレベルがあがるということであり、例として最高裁判所にたいする判例評釈が挙げられた。第三に、ある技能のレベルの評価基準についてのコメントがあった。法学が技能なのかという問題はあるが、論文の良し悪しを判断する際には、分野を異にする学者の間で判断が一致しないことがあって、その原因はローカルな知識が異なるためであるということだった。その一方で論理展開に関するユニバーサルな判断基準もある程度あるということだった。緩やかな基準が存在して、人によってそれは違うものの、当該分野に専門性を持つ人の間ならばある程度それは収斂するものだという。第四に、文化を伝えることに関連して、入りやすさと同時に奥の深さも大事であるとの指摘があった。ある程度の複雑さが当該分野の魅力になっているので、それも重要なポイントであるということだった。法学に関連した例として、天皇機関説(国家法人説)は、一定の複雑さを持ちつつも色々なことが説明できる理論であったために注目されたのだという指摘があった。