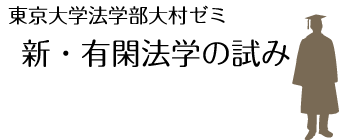1 大学
報告者:大村敦志
課題図書
①橘木俊詔・早稲田と慶応―名門私大の光と影(講談社現新書1958)2008
②潮木守一・世界の大学危機―新しい大学像を求めて(中公新書1764)2004
③中山茂・帝国大学の誕生―国際比較の中での東大(中公新書491)1978
④水月昭道・高学歴ワーキングプア―「フリーター生産工場」としての大学院(光文社新書322)2007
⑤大塚英志・大学論―いかに教え、いかに学ぶか(講談社現代新書2043)2010
課題図書の紹介
①橘木俊詔・早稲田と慶応―名門私大の光と影(2008) 序:★★ 破:★★ 急:★★
本書の帯には、「大学格差社会を生き残る戦略とは?」と記されている。このことからもわかるように本書は、「なぜ早慶の両校がこれほどまでに地位を高めたか」を「幅広い視点から」論ずることを目的としている。著者の橘木氏は格差社会論の提唱者の一人として知られているが、当然ながら学歴格差にも関心を持っており、本書のほかにも複数の大学論(『東京大学 エリート養成機関の盛衰』2009、『京都三大学 京大・同志社・立命館 東大・早慶への対抗』2011)が公表されている。
本書の概略は、第1章「早稲田と慶応はなぜ伸びたか」に示されている。第2章では、二人の創設者の特徴=二つの大学の学風が示され、第3章・第4章で、慶応と階層固定化、早稲田とマスプロ化が結びつけられている。結論にあたる第5章においては、「大学の生きる道」が語られている。本書は、基本的には大学の側に立って、その生き残り戦略を論ずる書物であるが、より広く、企業の生き残り戦略という観点から本書を読む読者も少なくないだろう。やや重複感があるものの、読み物としては読みやすい。
著者が指摘する諸事情のうち、興味深いのは近年の変化であろう。国公立と私立の間での学費差の縮小、共通一次制度の導入による旧帝大・二期校の威信低下、東京への一極集中などは読者が漠然と感じていることの言語化に成功しており、説得力がある。これに対して、著者が推奨する「就職に役立つ技能の徹底的な授与」が、私立大学の生き残る道であるか否かについては、意見が分かれるところであろう。「公共性の論理」が論点として指摘されつつ、十分に展開されていないのを、物足らないと感じる向きもあろう。
大学の側ではなく、学生(あるいは社会)の側に立つならば、早慶の教育の特徴(あるいは目標)がどのような点にあるのかが関心の対象となろう。(慶応に比べて早稲田の分析がやや弱いが)慶応=コミュニケーション能力、早稲田=指導力という指摘が興味深い。
②潮木守一・世界の大学危機―新しい大学像を求めて(2004) 序:★★★ 破:★★ 急:★★
本書は、大学アドミニストレーターの養成のために書かれた教材を基礎にしている。著者の潮木氏は、日本の大学研究の第一人者の一人である。英・独・仏・米の大学の由来や特徴が簡潔にまとめられており、1冊で世界の大学の様子を鳥瞰することができる。①との違いは、「人々は高等教育の拡大にいかなる夢をかけたのであろうか。納税者は大学に何を託したのであろうか」という問いを立てる点、「大衆化」と「卓越性」の双方を追究する点、そして、大学を青年層の居場所としてとらえる点などに求められる。もっとも、処方箋として示される「知識・技能のディズニーランド化」=「成人のための学習センター」化は、①の主張と奇妙に重なり合う。
③中山茂・帝国大学の誕生―国際比較の中での東大(1978) 序:★★★ 破:★★ 急:★★★
本書は、東大百周年を契機に書かれたものであり、他の4冊とは出版時期を大きく異にする。東大が一強であること、ドイツの大学とは異なること、官の優位など、興味深い指摘がなされており、ある意味では①②を先取りしている面も多い。唯一の違いは、東大の一強支配がなお続くということを前提としている点であろうか。①が述べるように、大学制度の大きな転換点が1979年にあるとするならば、本書はそれ以前の東大のあり方を説明するだということになろう。他方、本書は法学のあり方につき、いくつかの興味深い洞察を含んでおり、その部分は古びていない。
④水月昭道・高学歴ワーキングプア―「フリーター生産工場」としての大学院(2007) 序:★★ 破:★ 急:★★
本書は、大学院生の視点に立って書かれた異色の書である。著者には、博士号の価値に対する過大な期待もみられるが、著者に言わせれば、それは大学側の説明義務違反の結果であるということになろう。また、博士課程修了者の就職浪人をロースクール卒業生の将来と対比していたり、あるいは、文部省の大学院重点化構想を省庁の権益確保と結びつけているのは、刺激的な視点ではある。こうした議論には賛否両論がありうるであろうが、大学の教員ポストが非正規化しているという指摘は、重要な指摘であると言えよう。その意味で、ここにあるのは「ワーキングプアー」の問題であると言える。また、「ノラ博士」の活用も真面目に考えるべき問題であることも確かである。
⑤大塚英志・大学論―いかに教え、いかに学ぶか(2010) 序:★★ 破:★★★ 急:★★★
まんが原作者・批評家として知られる大塚英志が、私立大学の「まんが表現学科」教授となった。その教育経験に基づいて「いかに教え、いかに学ぶか」を論じた1冊。自身が実作者であるとともに批評家でもあるという二重性、さらに、教える体験と自らが教えられた体験を重ね合わせるという二重性が、本書を奥深いものにしている。「技術」ではなく「方法」を教えるという意識、「軋轢」や「無茶振り」こそが教育的であるという確信、「技術」の土台となる「教養」に着目する見識、プロ養成機関に特化しないという姿勢。いずれも卓見だろう。「書く」ことの市民性・公共性、「翻訳」の重要性の指摘も重要だが、欲を言えば、さらなる展開が望まれる。
参考文献
大村敦志「現代日本の法学教育」同『法典・教育・民法学』(有斐閣、1999)
同「共和国の民法学」同『20世紀フランス民法学から』(東京大学出版会、2009)
同『〈法と教育〉序説』(商事法務、2010)
同「架橋する法学・開放する法学―星野英一『法学入門』」書斎の窓2011年4月号
同「グローバリゼーションの中の法学教育」法の支配xxx号(2013)
コメントⅠ
①②③は、研究者の立場からの大学論である点で共通している。①が現在の「早慶」に焦点をあてて日本の大学を論ずるのに対して、②は比較に、③は歴史に、それぞれ視野を広げる。これに対して、④⑤はそれぞれ、大学院生、大学教員の立場から書かれている。もっとも、④がルサンチマンに満ちているのに対して、⑤は自信に支えられているのが、対象的である。
内容に即して言えば、①②③⑤は大学教育のあり方について論ずるが、①は経営サイドから(どんな人材がほしいか)、②は教育サイドから(何を大学は提供できるか)、大学の存在意義を見直しているようにみえる。ただ前述したように、いずれも職業性・大衆性を重視しており、公共性・卓越性については触れられはするものの、十分な展開がなされていない。視点が大学の中に置かれているためであろうか。これに対して③⑤は、方向は異なるものの、国家や社会が大学に求めるものは何かという視点を含んでいる。
比喩を用いるならば、①②は「市場」の中で大学を見ているが(①は需要サイドから、②は供給サイドから。なお、④もまた供給サイドに立っているもと言える)、③⑤は「市場」の外で大学を見ているということになろうか。
他方、①⑤は程度の差はあるものの、大学教育が学生に及ぼす影響に注目している。①は、カリキュラム上どのような知識や技能が提供されているかではなく、どのような資質が重要だとされているかに着目する。その意味では「隠れたカリキュラム」の教育機能が摘出し、早慶にキャッチ・アップしたいならば、意識的にこの機能を強化し職業教育に特化せよと説く。⑤は、「スキル」教育を出発点としつつ、「方法」と「教養」によってこれを支えようとする。そこにあるのは、大塚流の「公民」を生み出そうという強い意志、教育によってそれは実現しうるという強い信念である。
コメントⅡ
大学という機関は、規律されるとともに規律する存在である。大学は法令によって規律されるだけでなく、市場の論理や人々の集合心性の影響を受けるし、時代や地域によって変化する国家・社会の要請にも反応する。他方、大学院大学化や専門職大学院の導入は、学生の行動に大きな影響を与えた。
また、学生は、ひとたび大学に入学して教育を受けるようになると、望ましい人間像がいかなるものであるかを、有形無形の手段を通じて教え込まれることになる。かつては、外来の知識を有することが統治のために有用であるとされてきたが、いまでは、有能な人材となるにはコミュニケーション力や指導力が重要であるとされるようになりつつある。
大学に何が求められたのか、そして、大学が何を与えてきたのか。この点を法学に即して見てみると、③が、明治期のエリートの変遷を、工学系→経世学(官房学・行政学)→法学系、と整理している点が興味深い。これに対して、①は、法学系エリートの時代は終わったことを含意しているようにみえる。制度の管理や規範による規律は時代遅れだというわけである。
法学エリートの命脈は尽きたのか。これについては、③がいくつかの興味ある指摘をしている。一つは、明治期の私立法律学校が持っていたリベラル・エデュケーション機能(105頁)、もう一つは、帝国大学の教育の虚学性―「法律学的なものの考え方」の訓練によって基礎を養う(114頁)―である。⑤の「公民」性はこれらといかに切り結ぶのだろうか。
ディスカッションの概要
共通書に関しては、まず、その主張する早稲田・慶応の魅力が受験生にどのように受け止められているか、参加者の個人経験に基づく意見が示された。あわせて、東大との比較を念頭に置きつつ、大学選択の要因について意見交換がなされた。経済的要因はなお重要であること、地域社会における各大学のステータスが影響を及ぼすことなどが指摘された。
次に、早稲田・慶応の戦略が他の私立大学にとって本当に有益か否か、また、早稲田・慶応自体にとって、今後さらなる成長を目指すとしたら、どのような選択がありうるかが議論された。最後の点に関しては、経済界(慶応)・政界(早稲田)との関係をより積極的に活かすとともに、弱点であるとされる研究分野の強化をするべきだとの意見が述べられた。
最後の点は、東京大学法学部の将来をどう考えるかという問題に連なることになった。かつての東京大学においては、「研究」と「就職」とが両立していたが、今はそうではなくなっているのではないかという意見に対して、そこでいう「研究」とは何か、また「就職」に必要な能力とは何かが議論された。現代の法学が統治の術としての有効性を失っているのではないかという疑問が提示されるとともに、研究によって養われる能力とは別に就職力が存在するわけではないという見方も示された。議論においては、意見の相違にもかかわらず、「社会」との積極的な関わりを持つことに肯定的な態度がほぼ共有されていたが、大学、特に法学部のあり方は、「社会」との関係をどうとらえるかによって、大きく異なる。共通書が私立大学に推奨する生き残り戦略は、「社会」の現状を前提に、これによりよく対応するためのスキルを提供するというものであるが、そもそも大学、特に法学部が前提とする「社会」像はそのようなものであってよいのか。
初回であることもあり、文献を読むことよりも、意見交換をすることに重点を置いたが、活発な発言がなされたこともあり、次回以降、「教育」について議論をしていくための構えはできたと思う。