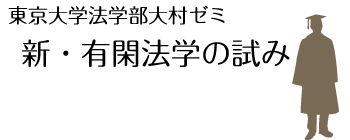ゼミの周辺(1)―新書を読むということ
新書という言葉を創ったのは、岩波新書である。同新書は「現代人の現代的教養」を標榜して、1938年に創刊された。この時代は大学にとっては難しい時代であった。そのことは、未刊本のリストにも窺える。たとえば、佐々木惣一『法治国日本』、恒藤恭『法と経済』、末川博『法律に於ける正義とは何か』、美濃部達吉『議会の話』などが、予定されながら刊行されるには至らなかった。
戦後になると多くの新書シリーズが創刊されたが、そのうち、今日でも残るものの代表格は、中公新書(1962年創刊)、講談社現代新書(1964年創刊)である。その後、1990年代後半から、光文社新書、集英社新書、新潮新書、文春新書、平凡社新書、ちくま新書などが相次いで創刊された。いまでは新書のレーベルは、いったいいくつあるのかもよくわからないほどになっている。
岩波新書創刊から三新書鼎立時代に至るまでは、新書の機能はアカデミズムの普及に求められていたと言えるだろう。外国でいえば、フランスのQue sais-je ? などが同旨のものであると言えるだろう。
しかし、近年の創刊ブームを経て、新書の性格は変化しつつある。一言で言えば、ジャーナリズムへの接近が進んでいるように思われる。かつての新書には「古典」となったものも少なくなかったが、今日の新書の多くは読み捨てられる対象となりつつある。より早く、より広く、より易しくが、求められているかのごとくである。
少し前までは、この手の「情報」「記事」「評論」は、総合雑誌に掲載されていた。ところが、今日では総合雑誌は退潮し、「知」のパッケージは崩壊、硬軟とりまぜた新書が様々な分野で刊行され、個別の需要に応じるようになっている。見方を変えるならば、マスとしての新書群(年間2000冊前後)が、総合雑誌に取って替わっているのである。
新書の発展によって、部分的には知の深化も見られるほか、知の普及が進み、越境も促進されている。そのこと自体は望ましいことではあるが、知の見通しが悪くなったこともまた確かである。私たちには、新書を媒介として本格的な専門知に向かうとともに、分断されがちな知に対して、統合への意思を持ち続けることが求められている。