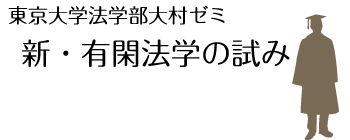補講(合評会)―バルトのテクストから何を読み取るか
『エクリチュールの零度』(ちくま学芸文庫、1999)はR・バルトの初期の作品である。1953年に刊行されたこの作品が日本で翻訳されたのは1965年のことであった。その後、別の訳も刊行されているが、ちくま学芸文庫版は、森本和夫による初訳を底本としている。今回(ゼミ補講で)検討するのは、この本の巻頭論文「エクリチュールとは何か」である。
この論文に限らず、一つの論文を読む際の読み方はいろいろである。同じ本に収録された他の論文とあわせ読むところから始めて、発表当時の文脈を考慮に入れて(いわば共時的に)読む、その後のバルトの作品の中に位置づけて(いわば通時的に)読む、さらにより広く、第二次大戦後から今日までのいわゆる「フランス現代思想」の文脈の中で読む。どれも可能であり、現にあちこちで行われている読み方であろう。しかし、ここではそのような読み方はしない。様々な文脈は捨象し、10頁ほどのテクストそのもの(ただし、文庫版の巻末に収録されているブランショの「零地点の探求」のみを補助テクストとする)から読み取れるだけのものを読み取り、その上で、このテクストが私たちが専門とする法学に何をもたらしうるのかを考えてみたい。
ただ、次の点のみ補足しておく。バルトは、レヴィ=ストロース、アルチュセール、ラカンとともに構造主義を代表する思想家であるとされる。しかし、レヴィ=ストロースが『野生の思考』でサルトル批判を展開したのは、1962年のことである。本書刊行当時、フランスで支配的なのは、依然としてサルトルの実存主義であった。以下のA〜Iは参加者による要約・評価である。
A.言語体とは、ある時代のすべての著作家たちに共通の規則や慣習の集合体である。それは言語活動における行動の領域であると同時に限界であり、その言語体を用いる人々が共有する歴史的な財産といえるものである。
文体とは、著作家自身の過去の記憶であり、彼の身体に根差している孤立性ともいえるものである。それは必然的に著作家の気質を言語に結びつけるものとして働く。
言語体も文体も、著作家は選択する余地がない。それらは(ある人々に共通する特定の言語が用いられたという意味での)時代や、生物学的な個人の自然的な所産であり、言語のあらゆる問題性に先行する、言語の〈自然〉である。
著作家の形式上の独自性は、言語的自然の限界のうちに閉じ込められて書かれた後の連続体が、人間的な行動の選択となるところでしか発揮されない。
上記のような文学の問題性の核心に存在するのがエクリチュールであり、著作家が自分の言語の〈自然〉を、そのただなかに位置づけようと決心するところの社会的な領域の選択である。それは、文学的な言語として、著作家の志向性となって現れる。しかし、選択できる社会的領域とは、実際の社会に有効性をもつものではなく、彼自身の意識上のものである。著作家は、文学的な消費の客観的な所与を全く改変できないために、自由に生産される言語の要請をその源泉の中心へ向かわせるのである。
エクリチュールの選択とそれに伴う責任は自由をしめすものであるが、それに対しても、歴史や伝統という圧力が働き、かつ選択されたエクリチュールはその時点における慣用の記憶を持ち続ける。エクリチュールは、選択の所作においてしか自由でなく、その持続のなかにおいてはすでにもはやそうではない。
しかし、著作家が表意しようとする所作から出る、一点の自由としてのエクリチュールは、だからこそ、文学の他の何らかの断片よりも顕著に〈歴史〉に姿を現すのだ。近代フランス文学史における著作家間のエクリチュールを対置すると、本質的な分裂が見られる。
B.ロラン・バルトはこの議論において、エクリチュールとは何であるかを明らかにし、それを踏まえてエクリチュールの選択の意味を論じている。以下議論を要約する。
文学の形式は言語体、文体、エクリチュールに区別される。言語体とは、ある時代ある場所の言語に関する共通の規則や慣習のことであり、文体とは個人個人の過去の経験に基づく、語の選択のことである。そしてそれらのあいだに位置するのがエクリチュールだ。
エクリチュールとは社会的な機能を有する、文学における共通の表現形式のことだ。前述した2つと異なり、著作家はエクリチュールを選択することができるが、その選択は全般的な歴史と、伝統の2つの圧力がかかった状態でしなければならない。ゆえにエクリチュールの歴史は、総体的な歴史と対応している。
この議論について3点指摘したい。
1.エクリチュールの選択は歴史と伝統によって制限されるとあるが、それはエリクチュールの選択が意識の選択であって、有効性の選択ではないという主張に矛盾するのではないだろうか。
2.エクリチュールと歴史との対応関係を実証するためには、文学に属する作品を知る必要があるが、その基準が示されていないため、実証できない。したがってエクリチュールと歴史との関係についてのこの仮説はこの議論だけでは正当化できない。
3.エクリチュールと歴史の具体的関係について述べられていない。もちろん、文学の内容ではなく形式に注目し、その1つのエクリチュールと歴史の関係を指摘したのは興味深い。
文章は比喩が多く、重要な点もつかみづらく、非常に読みにくかった。この文章自体が文学なのであろうか。個人的には何らかの主張を述べ、それを正当化するための文章はもっと単純なほうがよいと感じた。
C.ロラン・バルトは、書くことについて、言語体(ラング)・文体(スティル)・エクリチュールという概念を用いて論じている。
まず、ラングについて、それは著作家だけでなく人々が共有している財産であり、著作家に選択の自由なく与えられているものであると述べている。続いて、スティルは生物学的な起源を持つ、個人の閉ざされた振る舞いであり、ラングと同様に著作家が自由に選ぶものではないとしている。これら二つに対して、バルトは、著作家に選択の余地があるエクリチュールが存在することを指摘する。そして、エクリチュールによって著作家は、明瞭に自分の個性をあらわすと述べている。ただし、エクリチュールが自由として存在するのは、選択の所作の中だけである。
「エクリチュールとは何か」と題されたこの文章は、バルトによる『エクリチュールの零度』の一部分である。難解な文章ではあるが、ものを書くという営みについて深く考えるきっかけを与えてくれる。
モーリス・ブランショによって書かれた「零地点の探究」は、バルトの『エクリチュールの零度』を出発点として、書くことについて著者の考えを述べている。
前半は、『エクリチュールの零度』の要点をわかりやすく説明している。後半では、バルトのような見方は、「われわれが自分たちに提起されている問題の重大性の拡がりをよりよく把握する助けになる」として、バルトがエクリチュールの零と呼んだものについての考察をさらに進めている。
短い文章の中に表現されている、文学をめぐるブランショの思考は非常に興味深い。しかし、彼の文章に馴染んでいない読者にとっては、読み進めるのが難しい。
D.芸術というものを卒然と観念するとき、我々は《型》からの逸脱にこそ、芸術家の個性、芸術の真髄が表れると考えがちである。芸術家を作家と言い換えれば、作家の個性はスティル(文体)において顕著に見られる、というパラフレイズが可能となるだろう。だがしかし、ロラン・バルトはスティルを《孤独》、芸術を《安堵》と評した。つい先程卒然と観念した《個性》なるものは、独りよがりな生物学的所与であるとして切り捨てられてしまったのである。バルトは執拗に、作家が被投的存在を脱して《社会参画》することを訴え、その場としてエクリテュールという形式的現実を想定した。バルトは、エクリテュールは形式の作法であり、歴史的連帯の行為であると言うが、ここで看過できないのは、形式と連帯に強調が置かれているということであろう。第二次世界大戦の悲劇的かつ非人間的な結末を乗り越え、第四共和政の瓦解を目前とした1953年、バルトは何を思って『エクリテュールの零度』を執筆したのだろうか。ウケを狙って奇抜な内容に走るのではなく、明確な志向性と形式を備えることこそが、文学においては本質的であるというバルトの主張からは、文学論にはとどまらない迫力のエコウが確かに響いてくるように思われてならない。社会への強いまなざしは、1968年の学生闘争を予期させるものがある。Vive la solidarité! 今後到来する連帯の時代の一翼を作家にも担わせようというのだろうか。いずれにせよ、実存主義的な姿勢を維持しつつも、自我の過剰な肥大に対しては厳しい態度をとるバルトが、ソシュウルとサルトルを継ぎつつも一步も二歩も自立を図った点で、現代思想の息吹を感じさせてくれることは確かであろう。最後に一つ附言すると、文学の本質を《悪》だとした点でバルトと対立したサルトルが、件の学生闘争で学生の援護に回ったというのは、なかなかに興味深いねじれではないかと思われる。
E.「エクリチュールとは何か」というこの章で、バルトは言語活動に纏わる概念としての「エクリチュール」の説明を試みる。そして「エクリチュール」概念を引き出すために平面的な構造を持つ「ラング(言語体)」と、垂直的な構造を持つ「ステイル(文体)」を対置させる。前者は本来的に社会の客体として、同時に原初的な限界として存在するものであり、われわれが普段共同体で使用する言語のひろがり全体をイメージすればよいだろう。後者はあるひとの過去と身体的な次元で結びつき、そのひとの言葉を規定するものとして定義される。ゆえにバルトに言わせれば、シューベルト風のプーランクには「ステイル」が不在なのである。
続いてバルトは「ラング」と「ステイル」に彩られた無垢な言語学的自然の中から創造されたものを、社会的な用途に結びつける機能を「エクリチュール」とする。また、ひとは社会と対決しながら自由に「エクリチュール」を建てられる反面、その選択の自由は歴史や伝統といったものに制限されるのであるので、「エクリチュール」には限界を伴うある一時点の自由しか存在しない、と看破する。
バルトはこの章の末尾で同質性の保たれていた「エクリチュール」の多様化が近代に進み、その現象を<歴史>の危機と評する。この文章が書かれた時代を勘案するに「エクリチュール」の多様化はフランス革命以降進んだということであろうから、革命によるナショナリズムの萌芽や近代の象徴たる「大きな物語」の揺らぎと再強化を社会背景として、それが進展したと見ることができるだろう。
また蛇足ではあるが、このバルトの文章は、文学的で揺らぎが多く、難解だという印象を抱いた。「エクリチュール」を定義する文章においてバルトが敢えて「文学的なエクリチュール」を選び取ったのは、メタ的な視点に立てばやや皮肉なことのように思う。
F.ソシュールは「langage(言語)」をその社会的な側面である「langue(言語体)」と個人的な側面である「parole(語り)」とに分け、言語学の対象を前者に置くべきであると主張したが、本書においてバルトは、それらの概念を前提として、新たに「style(文体)」とそれに続く「écriture(エクリチュール)」という概念を導入している。
バルトによれば、「langue(言語体)」が「ある時代のすべての著作家たちに共通の規則や慣習の集合体」と定義され、社会的な言語環境とでも表現されるものであるのに対し、「style(文体)」は著作家の個人的な身体や過去の経験から生じる言語感覚のようなものとして理解することができる。
両者はともに所与のものとして本来的な客体なのであって、それだけでは〈文学〉足りえず、もうひとつの形式上の現実である「écriture」に目を向ける必要があるとされる。その語の明確な意味は把握しづらいが、いうなれば物を書く際の言葉の選択であって、己の生き様を体現するものであり、「style(文体)」との関係でいえば、「個性のある各々の身体」と「その身に纏う衣服」と譬えることはできないだろうか。
バルトはその選択における〈自由〉(それは一時的であり制約を伴うものではあるが)を強調している。また、かつて単一性を持ちえた「écriture」がいまや多様になっていることにも注目している。
ここにおける〈文学〉の意義や「style」及び「écriture」の導入により果たして何が生まれるのかは、この時点(p.19~p.30)においてはまだ漠然としたイメージを抱くことしかできないが、文学の未来を考える上で、バルトの考察は非常に価値のあるものを残したと言えるのだろう。
G.言語体は基本的に普遍で、誰しもが同じ意味を込めて用いることを強制する。文体は、言語体のはめようとする枠の外で繰り広げられるあくまで個人的な営みであるが、言語体の普遍性の拘束は免れ得ない。この両者の間の微妙な関係をとりもつ行為として存在するのがエクリチュールという行為なのである。いわばその社会、その時代に通底する文脈のようなものとしてエクリチュールが語られる中で、バルトはそのありようが近代に於いて無限に拡散し、既存の文学という枠そのものを変えうるものとなるほど深刻な分裂がある、と述べる。―こうして、今まさに私が施したようにして、乱暴さの中には私個人の経験、それを拘束する文化や言語体が存在し、その檻の中ではじめて発生している独自の文体というものがあり、そんなものを全て歴史的なつながりの中に位置づけていく行為こそエクリチュールなのだ。
指定されたバルトの短文には、当然彼のエクリチュールが反映されている。そしてこれまた当然にバルトの主張は彼の文章そのものにも妥当するはずである。ではバルト自身が使用したエクリチュールとは何なのか、という問いがまず立てられるであろう。
次に、一人の人間が生まれてから、いかにエクリチュールを手に入れ、実践していくのか、という発達心理学的な問いも可能であろう。バルトが述べるような時代の変遷にともなうエクリチュールのドラマは当然個人の人生の変遷の中にも見て取れるはずであろう
から。
そしてこの二つの前提を踏まえてはじめて、バルトの論に対峙することができる。バルトが体感したフランスのエクリチュールの破裂は、価値観も言語も異なる現代の日本でどこまで妥当するのか。私は自らの体験を踏まえれば、エクリチュールの拡散を抑えるように働くことが多かったように思うが、これが国あるいはコミュニティ内の歴史にどの程度妥当するのか、はよく分からない。
H.バルトは言語活動を三層から理解する。ある時代のすべての著作家に共通の規則や慣習の集合体である言語体ラング。気質の変貌である文体ステイル。歴史的な連帯性の行為であるエクリチュール。著作家は、言語体や文体が自然として与えられている中で、エクリチュールの選択においてのみ自由であるが、一度選択をすればそのエクリチュールの歴史や伝統に縛られることになる。エクリチュールの選択は、著作家が自分の言語の自然を位置づける社会的な領域の選択なのである。したがって、エクリチュールにより著作家は社会に立ち現われる、すなわちアンガージュマンする。
三層の構造は、コミュニケーション一般を考える際にも有用であろう。コミュニケーションの主体の孤立性、コミュニケーションそれ自体を可能ならしめる間主観的条件、コミュニケーションの形式、という三層である。ここでエクリチュールはコミュニケーションの形式に対応するが、コミュニケーションがそれとして成り立ちうるためには定型性が必要であり、エクリチュールが記憶を伴う選択肢として社会的な定型性を有することと一致しよう。コミュニケーションそれ自体を可能ならしめる間主観的条件も言語体と同様に否定性であるし、主体の孤立性は気質とコミュニケーションとを必然的に結びつける。このように、バルトの議論は一つの視角として思考を豊かにするのである。
しかし、彼はエクリチュールが選択肢であることを想定しながら、その選択肢がいかに生成されるのかは明らかにしていないし、零度と形容するにふさわしいエクリチュールが果たして言語体と異なり得るのかについて十分な検討を示していない。その点で、エクリチュールを中心の主題とするには物足りなさが残る。
I.「エクリチュールとは何か」と題された文章である。が、まず「言語体」と「文体」とは何か、が初めに示される。言語体
これに対して、著作家が自由に己の個性を発揮できるのが「エクリチュールの選択」であって、それは歴史的・社会的に形成された「文学」に対していかなる態度をとるか、ということである。つまり著作家は既存のエクリチュール(=「書き方」=形式
しかし、この自由にも限界がある。それは選択という身振り
J.本文においてはまず、言語体と文体という2つの概念が提示される。言語体とはある時代において共有されている規則や慣習の集合体であり、抽象的に平面的に広がっているものである。一方で、文体とはその著作家の<気質>の変貌であり、その個人の中で閉ざされつつ、月日を経て育まれてきた垂直的な広がりを有するものである。しかし、どちらも意識的に選択できるものではないため、著作家たちはこの2つを用いて、自己を明瞭に個別化することは出来ない。そこで、提示されるのがエクリチュールである。エクリチュールとは、自己の書く言語の調子・志向性・語り口などの選択であり、またその選択の結果のことである。この選択を行うことによって、著作家たちは、自らの著作を社会のどこに位置づけるかを決定するとともに、その位置づけの中で著作を深めていくのである。エクリチュールが異なる者の差異は先の2つの概念において異なる者の差異よりも大きい。だが、その選択したエクリチュールもずっと独立して保てるものではなく、他者の語や過去の慣用といった平面・垂直の両方の影響を受ける。このように本文では述べられていた。
文章自体は難解であるが、この議論を読者の側に引き込んでみると面白い。我々がある書き手を好むのはなぜなのであろうか。以前とは、全く趣の異なる作品であるにもかかわらず、この書き手の作品であれば読んでみようと思う。そこには、その書き手のエクリチュールへの信頼があるのではないか。ある書き手が選択したエクリチュールは、その作品の内容などを離れ、我々読者にとっての一貫した書き手自身として存在している。だからこそ小説・エッセイなどのジャンルの枠を超えてまで、ある書き手を好むのかもしれない。
また、翻訳作品を読む際、我々は一体誰のエクリチュールの影響を色濃く受けているのだろうか。やはり原著の書き手であろうか、それとも翻訳家であろうか。